数学 において、ニュートン多角形は、 局所体 上、またはより一般的には超計量体 上の多項式 の挙動を理解するためのツールです。元の場合、対象の超計量体は本質的に 不定値Xの 形式ローラン級数 の体、つまり 上の形式冪級数 環の分数の体 で、は実数体 または複素数 体でした。これは、ピュイズー展開 に関しても依然としてかなり有用です。ニュートン多角形は、 が の係数を持つ多項式である方程式 の冪級数展開解の主要項、つまり多項式環 、つまり暗黙的に定義された代数関数 を理解するための効果的な手段です。ここでの指数は、選択した分岐に依存する特定の有理数 で あり、 解 自体は、 に対応する 分母 についての冪 級数です 。 ニュートン多角形は を計算するための効果的なアルゴリズム的アプローチを提供します。 K [ [ X ] ] {\displaystyle K[[X]]} K {\displaystyle K} K {\displaystyle K} 1つの X r {\displaystyle aX^{r}} P ( F ( X ) ) = 0 {\displaystyle P(F(X))=0} P {\displaystyle P} K [ X ] {\displaystyle K[X]} r {\displaystyle r} K [ [ はい ] ] {\displaystyle K[[Y]]} はい = X 1 d {\displaystyle Y=X^{\frac {1}{d}}} d {\displaystyle d} d {\displaystyle d}
p進数 の導入後、ニュートン多角形は局所体の分岐 問題、ひいては代数的整数論においても同様に有用であることが示されました。ニュートン多角形は 楕円曲線 の研究にも有用です。
意味 5 進評価に関する多項式 1 + 5 X + 1/5 X 2 + 35 X 3 + 25 X 5 + 625 X 6のニュートン多角形の構築。 体上の多項式が与えられた場合、その根の振る舞い(根を持つと仮定した場合)は、事前には不明です。ニュートン多角形は、根の振る舞いを研究するための一つの手法を提供します。
を非アルキメデス的評価値 を持つ体 とし、 K {\displaystyle K} v K : K → R ∪ { ∞ } {\displaystyle v_{K}:K\to \mathbb {R} \cup \{\infty \}}
f ( × ) = 1つの n × n + ⋯ + 1つの 1 × + 1つの 0 ∈ K [ × ] 、 {\displaystyle f(x)=a_{n}x^{n}+\cdots +a_{1}x+a_{0}\in K[x],} となる。すると、 のニュートン多角形は、 となる点を無視した点の集合の凸 包の下界として定義される。 1つの 0 1つの n ≠ 0 {\displaystyle a_{0}a_{n}\neq 0} f {\displaystyle f} P 私 = ( 私 、 v K ( 1つの 私 ) ) 、 {\displaystyle P_{i}=\left(i,v_{K}(a_{i})\right),} 1つの 私 = 0 {\displaystyle a_{i}=0}
幾何学的に言い換えると、これらすべての点P i を xy 平面にプロットします。点のインデックスは左から右に向かって増加するものと仮定します(P 0 P n P 0 から始めて、y 軸と平行にまっすぐ下に放射線 を描き、この放射線を反時計回りに回転させて点P k 1 P 1 である必要はありません)に当てます。ここで放射線を切断します。次に、P k 1 からy 軸と平行にまっすぐ下に2番目の放射線を描き、この放射線を反時計回りに回転させて点P k 2 P n P 0 、P k 1 P k 2 P k m P n
このプロセスをより直感的に捉える別の方法は、 P 0 , ..., P n の すべての点を囲む輪ゴムを考えてみましょう。輪ゴムを上方に伸ばし、輪ゴムの下側をいくつかの点に引っ掛けます(これらの点は、xy平面に部分的に打ち込まれた釘のような働きをします)。ニュートン多角形の頂点は、まさにこれらの点です。
このわかりやすい図については、JWS Cassels 著「Local Fields」(LMS Student Texts 3、CUP 1986) の第 6 章 § 3 を参照してください。これは、1986 年のペーパーバック版の 99 ページにあります。
主定理 前のセクションの表記を用いると、ニュートン多角形に関する主な結果は次の定理である。[ 1 ] f {\displaystyle f}
を(上で定義したように)ニュートン多角形の線分の傾きを昇順に並べたものとし、を x 軸上に投影された線分 の対応する長さとします(つまり、点間に伸びる線分があり、その長さが である場合)。 μ 1 、 μ 2 、 … 、 μ r {\displaystyle \mu _{1},\mu _{2},\ldots ,\mu _{r}} f ( × ) {\displaystyle f(x)} λ 1 、 λ 2 、 … 、 λ r {\displaystyle \lambda_{1},\lambda_{2},\ldots,\lambda_{r}} P 私 {\displaystyle P_{i}} P j {\displaystyle P_{j}} j − 私 {\displaystyle ji}
これらは異なります。μ 私 {\displaystyle \mu_{i}} ∑ 私 λ 私 = n {\displaystyle \sum _{i}\lambda _{i}=n} がの根である場合、;α {\displaystyle \alpha} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K} v ( α ) ∈ { − μ 1 、 … 、 − μ r } {\displaystyle v(\alpha )\in \{-\mu _{1},\ldots ,-\mu _{r}\}} 任意の に対して、の根の値(重複度を数えると)が に等しいものの数は最大で 個であり、が 上の線型因子の積に分解される場合は と等しくなります。私 {\displaystyle i} f {\displaystyle f} − μ 私 {\displaystyle -\mu_{i}} λ 私 {\displaystyle \lambda_{i}} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K}
帰結と応用 前のセクションの表記法を用いて、以下では上の の分解体を で表し、を に拡張したものを で表す。 L {\displaystyle L} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K} v L {\displaystyle v_{L}} v K {\displaystyle v_{K}} L {\displaystyle L}
ニュートン多角形定理は、次の系の例のように、多項式の既約性を示すためによく使用されます。
評価値が離散的かつ正規化されており、ニュートン多項式には傾きが でx軸への射影が であるような線分が1つだけ含まれていると仮定します。が と互いに素である場合、は上で既約です。特に、アイゼンシュタイン多項式のニュートン多角形はと を結ぶ傾きの単一の線分で構成されるため、アイゼンシュタインの条件 が成り立ちます。v {\displaystyle v} f {\displaystyle f} μ {\displaystyle \mu} λ {\displaystyle \lambda} μ = 1つの / n {\displaystyle \mu =a/n} 1つの {\displaystyle a} n {\displaystyle n} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K} − 1 n {\displaystyle -{\frac {1}{n}}} ( 0 、 1 ) {\displaystyle (0,1)} ( n 、 0 ) {\displaystyle (n,0)} 確かに、主定理によれば、が の根である 場合、が 上で既約でなければ、の次数はとなり、 が成り立ちます。しかし、は と互いに素である ため、これは不可能です。 α {\displaystyle \alpha} f {\displaystyle f} v L ( α ) = − 1つの / n 。 {\displaystyle v_{L}(\alpha )=-a/n.} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K} d {\displaystyle d} α {\displaystyle \alpha} < n {\displaystyle <n} v L ( α ) ∈ 1 d Z {\displaystyle v_{L}(\alpha )\in {1 \over d}\mathbb {Z} } v L ( α ) = − 1つの / n {\displaystyle v_{L}(\alpha )=-a/n} 1つの {\displaystyle a} n {\displaystyle n}
もう一つの単純な帰結は次のようになります。
がヘンゼル多様体 であると仮定する。 のニュートン多角形が何らかの に対してを満たす場合、 はに根を持つ。( K 、 v K ) {\displaystyle (K,v_{K})} f {\displaystyle f} λ 私 = 1 {\displaystyle \lambda _{i}=1} 私 {\displaystyle i} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K} 証明: 主定理より、は の付値となる単一の根を持つ必要がある。特に、は 上で分離可能である。が に属さないなら、は上で別個のガロア共役を持ち、 となる。 [ 2 ] f {\displaystyle f} α {\displaystyle \alpha} v L ( α ) = − μ 私 。 {\displaystyle v_{L}(\alpha )=-\mu _{i}.} α {\displaystyle \alpha} K {\displaystyle K} α {\displaystyle \alpha} K {\displaystyle K} α {\displaystyle \alpha} α ′ {\displaystyle \alpha '} K {\displaystyle K} v L ( α ′ ) = v L ( α ) {\displaystyle v_{L}(\alpha ')=v_{L}(\alpha )} α ′ {\displaystyle \alpha '} f {\displaystyle f}
より一般的には、次の因数分解定理が成り立ちます。
がヘンゼル的 であると仮定する。すると、は任意の に対して単項であり、の根は付値、 となる。( K 、 v K ) {\displaystyle (K,v_{K})} f = あ f 1 f 2 ⋯ f r 、 {\displaystyle f=A\,f_{1}\,f_{2}\cdots f_{r},} あ ∈ K {\displaystyle A\in K} f 私 ∈ K [ X ] {\displaystyle f_{i}\in K[X]} 私 {\displaystyle i} f 私 {\displaystyle f_{i}} − μ 私 {\displaystyle -\mu_{i}} 度 ( f 私 ) = λ 私 {\displaystyle \deg(f_{i})=\lambda _{i}} [ 3 ] さらに、 であり、 が と互いに素である場合、は 上で既約です。μ 私 = v K ( f 私 ( 0 ) ) / λ 私 {\displaystyle \mu_{i}=v_{K}(f_{i}(0))/\lambda_{i}} v K ( f 私 ( 0 ) ) {\displaystyle v_{K}(f_{i}(0))} λ 私 {\displaystyle \lambda_{i}} f 私 {\displaystyle f_{i}} K {\displaystyle K} 証明: 任意の に対して、がおよびの根となるような単項式の積を で表します。また、 における の素一価因数への因数分解を と表します。をの根とします 。は上の の最小多項式であると仮定できます。が の根である場合、を に送るのK-自己同型が存在し、 はヘンゼルであるので が成り立ちます。したがっても の根です。さらに、重複根は明らかに同じ値を共有するので、重複 の のすべての根は明らかに重複の の根です。これは、 がを割り切ることを示します。 とします。の根を 1 つ選びます。 の根は の根とは異なることに注目してください。上の の最小多項式で前の議論を繰り返し、wlg を と仮定して、 が を割り切ることを示します。 のすべての根が尽きるまでこのプロセスを続けると、最終的に に到達します 。これは、が一価であることを示します。しかし、 は互いに素です。なぜなら、それらの根は異なる値を持つからです。したがって、明らかに となり、主な論点が示されています。 は主定理から導かれ、 も主定理から導かれます。これは、 のニュートン多角形はに接続する線分を1つしか持たないことを指摘することによって示されます。 の既約性の条件は、上記の系から導かれます。(qed) 私 {\displaystyle i} f 私 {\displaystyle f_{i}} ( X − α ) {\displaystyle (X-\alpha )} α {\displaystyle \alpha} f {\displaystyle f} v L ( α ) = − μ 私 {\displaystyle v_{L}(\alpha )=-\mu _{i}} f = あ P 1 け 1 P 2 け 2 ⋯ P s け s {\displaystyle f=AP_{1}^{k_{1}}P_{2}^{k_{2}}\cdots P_{s}^{k_{s}}} f {\displaystyle f} K [ X ] {\displaystyle K[X]} ( あ ∈ K ) 。 {\displaystyle (A\in K).} α {\displaystyle \alpha} f 私 {\displaystyle f_{i}} P 1 {\displaystyle P_{1}} α {\displaystyle \alpha} K {\displaystyle K} α ′ {\displaystyle \alpha '} P 1 {\displaystyle P_{1}} σ {\displaystyle \sigma } L {\displaystyle L} α {\displaystyle \alpha } α ′ {\displaystyle \alpha '} v L ( σ α ) = v L ( α ) {\displaystyle v_{L}(\sigma \alpha )=v_{L}(\alpha )} K {\displaystyle K} α ′ {\displaystyle \alpha '} f i {\displaystyle f_{i}} P 1 {\displaystyle P_{1}} ν {\displaystyle \nu } f i {\displaystyle f_{i}} k 1 ν {\displaystyle k_{1}\nu } P 1 k 1 {\displaystyle P_{1}^{k_{1}}} f i . {\displaystyle f_{i}.} g i = f i / P 1 k 1 {\displaystyle g_{i}=f_{i}/P_{1}^{k_{1}}} β {\displaystyle \beta } g i {\displaystyle g_{i}} g i {\displaystyle g_{i}} P 1 {\displaystyle P_{1}} β {\displaystyle \beta } K {\displaystyle K} P 2 {\displaystyle P_{2}} P 2 k 2 {\displaystyle P_{2}^{k_{2}}} g i {\displaystyle g_{i}} f i {\displaystyle f_{i}} f i = P 1 k 1 ⋯ P m k m {\displaystyle f_{i}=P_{1}^{k_{1}}\cdots P_{m}^{k_{m}}} m ≤ s {\displaystyle m\leq s} f i ∈ K [ X ] {\displaystyle f_{i}\in K[X]} f i {\displaystyle f_{i}} f i {\displaystyle f_{i}} f = A f 1 ⋅ f 2 ⋯ f r {\displaystyle f=Af_{1}\cdot f_{2}\cdots f_{r}} λ i = deg ( f i ) {\displaystyle \lambda _{i}=\deg(f_{i})} μ i = v K ( f i ( 0 ) ) / λ i {\displaystyle \mu _{i}=v_{K}(f_{i}(0))/\lambda _{i}} f i {\displaystyle f_{i}} ( 0 , v K ( f i ( 0 ) ) {\displaystyle (0,v_{K}(f_{i}(0))} ( λ i , 0 = v K ( 1 ) ) {\displaystyle (\lambda _{i},0=v_{K}(1))} f i {\displaystyle f_{i}}
以下は上記の因数分解の直接の系であり、ヘンゼル体上の多項式の約分可能性のテストになります。
がヘンゼル多角形 であると仮定する。ニュートン多角形が単一の線分に簡約されない場合、 は上で簡約可能である。( K , v K ) {\displaystyle (K,v_{K})} ( μ , λ ) , {\displaystyle (\mu ,\lambda ),} f {\displaystyle f} K {\displaystyle K}
3 x 2 y 3 − xy 2 + 2 x 2 y 2 − x 3 y のニュートン多角形。正の単項式は赤、負の単項式は水色で示されている。面には極限項がラベル付けされている。ニュートン多角形の他の応用は、ニュートン多角形がニュートン多面体 の特別な場合であることもあり、次のような2変数多項式方程式の漸近解を構成するために使用できるという 事実から来ています。3 x 2 y 3 − x y 2 + 2 x 2 y 2 − x 3 y = 0. {\displaystyle 3x^{2}y^{3}-xy^{2}+2x^{2}y^{2}-x^{3}y=0.}
対称関数の説明 付値化の文脈において、多項式の根の基本対称関数の付値化という形で特定の情報が与えられ、 代数的閉包における実際の根の付値化に関する情報が求められる。これは 分岐理論 と特異点理論 の両方の側面を持つ。有効な推論は、ニュートンの恒等式 を用いて、べき乗和 の付値化へと導くことができる。
歴史 ニュートン多角形はアイザック・ニュートン にちなんで名付けられました。彼は1676年にヘンリー・オルデンバーグ に宛てた書簡の中で、ニュートン多角形とその用途のいくつかを初めて説明しました。[ 4 ]
参照
参考文献 ^ 超体に基づく興味深いデモンストレーションについては、Matthew Baker, Oliver Lorscheid (2021). Descartes' rule of signs, Newton polygons, and polynomials over hyperfields . Journal of Algebra, Volume 569, p. 416-441 を参照。 ^ ヘンゼル環においては、任意の付値は基底体の任意の代数拡大に一意に拡張されることを思い出そう。したがって、 はに一意に拡張される。しかし、の自己同型に対して はの拡張であるため、v K {\displaystyle v_{K}} v L {\displaystyle v_{L}} v L ∘ σ {\displaystyle v_{L}\circ \sigma } v K {\displaystyle v_{K}} σ {\displaystyle \sigma } L {\displaystyle L} v L ( α ′ ) = v L ∘ σ ( α ) = v L ( α ) . {\displaystyle v_{L}(\alpha ')=v_{L}\circ \sigma (\alpha )=v_{L}(\alpha ).} ^ JWS Cassels、Local Fields、第6章、thm. 3.1。 ^ Egbert Brieskorn , Horst Knörrer (1986).平面代数曲線 , pp. 370–383.
外部リンク 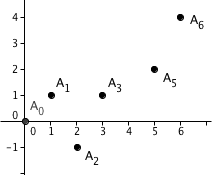

![{\displaystyle K[[X]]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/829385e112c1f43b691f221a8c47437b3ec65e68)




![{\displaystyle K[X]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5bb4d802ca5718a14dc961af8692f35cdfad169b)

![{\displaystyle K[[Y]]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2340f020be9eb59d273ca164e1d3148699198659)



![{\displaystyle f(x)=a_{n}x^{n}+\cdots +a_{1}x+a_{0}\in K[x],}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/801ccad008b0caab1fbc25ab654fab0fe6748ab3)








































![{\displaystyle f_{i}\in K[X]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e227d6ac60efe70b46e0284d5c53e97f98a97565)






























