H定理
古典統計力学において、1872年にルートヴィヒ・ボルツマンによって導入されたH定理は、分子のほぼ理想気体におけるH(以下に定義)の減少傾向を記述するものです。[ 1 ]このHは熱力学のエントロピーを表すことを意図していたため、H定理は統計力学の威力を示す初期の例となりました。H定理は、熱力学第二法則(根本的に不可逆な過程に関する記述)を可逆な微視的力学から導出すると主張したからです。H定理は、低エントロピー初期条件を仮定しているものの、熱力学第二法則を証明するものと考えられています。 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
H定理は、ボルツマンによって導かれた運動方程式(ボルツマン方程式として知られる)から自然に導かれる。H定理は、その実際の意味合いについて多くの議論を引き起こしてきた[ 6 ] 。主なテーマは以下の通りである 。
- エントロピーとは何ですか?ボルツマンの量Hはどのような意味で熱力学的エントロピーに対応しているのでしょうか?
- ボルツマン方程式の背後にある仮定(特に分子カオスの仮定)は強すぎるのでしょうか?これらの仮定が破られるのはどのような場合でしょうか?
名前と発音
ボルツマンは最初の出版物で、その統計関数を記号E (エントロピーの) で表記しています。[ 1 ]数年後、この定理の批判者の一人であるサミュエル・ホークスリー・バーバリーは[ 7 ]この関数を記号H で表記し、[ 8 ]この表記法は後にボルツマンが「H定理」について言及する際に採用しました。[ 9 ]この表記法は、定理の名称に関して混乱を招きました。この命題は通常「エイチの定理」と呼ばれますが、ギリシャ文字の大文字のエータ( Η ) がラテン文字の大文字のh ( H )と区別がつかないため、 「エータ定理」と呼ばれることもあります。[ 10 ]この記号をどのように理解すべきかについて議論が行われてきましたが、定理が発表された当時の文献が不足しているため、依然として不明確です。[ 10 ] [ 11 ]タイポグラフィの研究とJWギブスの研究 [ 12 ]は、 Hをイータと解釈する傾向があるように思われる。[ 13 ]
ボルツマンのHの定義と意味
H値は、時刻tにおける分子のエネルギー分布関数である関数f ( E , t ) dEから決定される。f ( E , t ) dEの値は、 EとE + dEの間の運動エネルギーを持つ分子の数である。H自体は次のように定義される 。
孤立した理想気体(総エネルギーと粒子総数が一定)の場合、関数Hは粒子がマクスウェル・ボルツマン分布に従うときに最小値となる。理想気体の分子が他の分布に従う場合(例えば、すべての分子の運動エネルギーが同じ場合)、Hの値はより高くなる。次のセクションで説明するボルツマンのH定理は、分子間の衝突が許容される場合、そのような分布は不安定であり、 Hの最小値(マクスウェル・ボルツマン分布)に向かって不可逆的に移動する傾向があることを示している。
(表記に関する注記: ボルツマンはもともと量Hを表すために文字Eを使用していました。ボルツマン以降の文献のほとんどはここでのように文字Hを使用しています。ボルツマンは粒子の運動エネルギーを表すために 記号xも使用しました。)
ボルツマンのH定理
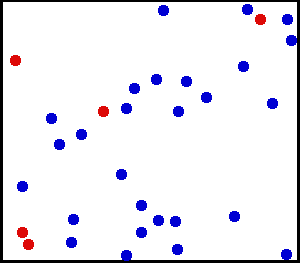
ボルツマンは、2つの粒子の衝突時に何が起こるかを考察しました。2つの粒子(剛体球など)の弾性衝突において、粒子間で伝達されるエネルギーが初期条件(衝突角度など)に応じて変化することは、力学の基本事実です。
ボルツマンは、分子カオス仮定(Stosszahlansatz )として知られる重要な仮定を立てました。それは、気体中のあらゆる衝突事象において、衝突に関与する2つの粒子は、1) 分布から独立して選択された運動エネルギー、2) 独立した速度方向、3) 独立した開始点を持つというものです。これらの仮定とエネルギー移動のメカニズムに基づき、衝突後の粒子のエネルギーは、計算可能な特定の新しいランダム分布に従うことになります。
ボルツマンは、気体中のあらゆる分子間の無相関の衝突を繰り返し考慮し、運動方程式(ボルツマン方程式)を構築しました。この運動方程式から、衝突の継続過程によってHの量は減少し、最終的に最小値に達する という自然な帰結が得られます。
インパクト
ボルツマンのH定理は、当初主張されたように熱力学第二法則の絶対的な証明とはならなかった(以下の批判を参照)が、H定理は19世紀末のボルツマンを熱力学の性質に関するより確率的な議論へと導いた。熱力学の確率的見解は、1902年にジョサイア・ウィラード・ギブスによる(気体だけでなく)完全に一般的な系に対する統計力学と、一般化統計アンサンブルの導入によって頂点に達した。
運動方程式、特にボルツマンの分子カオス仮定は、半導体中の電子などの粒子の運動をモデル化するために今日でも使用されている一連のボルツマン方程式の基盤となりました。多くの場合、分子カオス仮定は非常に正確であり、粒子間の複雑な相関関係を無視できるため、計算ははるかに単純化されます。
熱化の過程はH定理や緩和定理を用いて記述することができる。[ 14 ]
批判と例外
H定理が、少なくとも1871年の原型においては、完全に厳密ではない理由はいくつかある。以下に述べるように、ボルツマンが後に認めるように、 H定理における時間の矢印は、実際には純粋に力学的なものではなく、初期条件に関する仮定の結果である。[ 15 ]
ロシュミットのパラドックス
ボルツマンがH定理を発表した直後、ヨハン・ヨーゼフ・ロシュミットは、時間対称力学と時間対称形式論から不可逆過程を推論することは不可能であると反論した。ある状態においてHが時間とともに減少する場合、Hが時間とともに増加する対応する反転状態が存在するはずである(ロシュミットのパラドックス)。その説明は、ボルツマン方程式が「分子カオス」の仮定に基づいている、つまり、粒子は独立かつ無相関であるとみなすという基礎となる運動モデルから導かれる、あるいは少なくともそれと整合しているというものである。しかし、この仮定は時間反転対称性を微妙な意味で破ることが判明し、したがって論点回避となる。粒子が衝突すると、それらの速度方向と位置は実際には相関する(ただし、これらの相関は非常に複雑な方法で符号化されている)。これは、(継続的な)独立性の仮定が、基礎となる粒子モデルと整合していないことを示している。
ボルツマンはロシュミットに対して、これらの状態の可能性は認めつつも、そのような状態は非常に稀で異常であるため、実際には不可能であると反論した。ボルツマンはその後、状態の「稀少性」という概念をさらに明確にし、 1877年にエントロピーの式を導き出した。
スピンエコー
ロシュミットのパラドックスの実証として、現代の反例(ボルツマンの元々の気体関連のH定理ではなく、密接に関連する類似物)はスピンエコー現象です。[ 16 ]スピンエコー効果では、相互作用するスピン系において時間反転を誘発することが物理的に可能です
スピン系におけるボルツマンのHの類似物は、系内のスピン状態の分布によって定義できる。実験では、スピン系はまず非平衡状態(高H)に摂動され、H定理によって予測されるように、 Hの量はすぐに平衡値まで減少する。ある時点で、慎重に構築された電磁パルスが印加され、すべてのスピンの運動が反転する。すると、スピンはパルス印加前の時間発展を元に戻し、しばらくするとHは平衡状態から実際に増加する(発展が完全に元に戻ると、Hは再び最小値まで減少する)。ある意味では、ロシュミットが指摘した時間反転状態は、完全に非現実的ではないことが判明した。
ポアンカレ回帰
1896年、エルンスト・ツェルメロはH定理の更なる問題点を指摘した。それは、系のHがいかなる時点でも最小値でない場合、ポアンカレ再帰則により、非最小Hは必ず再帰する(ただし、非常に長い時間の後に)という問題である。ボルツマンは、 Hのこのような再帰的な上昇は技術的には起こり得ると認めたが、長い時間にわたっては、系がこれらの再帰状態のいずれかに費やす時間はごくわずかであることを指摘した。
熱力学第二法則は、孤立系のエントロピーは常に最大平衡値まで増加すると述べています。これは厳密には、粒子数が無限の熱力学的極限においてのみ当てはまります。粒子数が有限の場合、エントロピーは常に変動します。例えば、孤立系の一定体積において、粒子の半分が体積の半分の一方に、もう半分がもう一方の半分にあるときに最大エントロピーが得られます。しかし、一時的に片側に粒子がもう片側よりも少し多く存在する場合があり、これはエントロピーのごくわずかな減少となります。これらのエントロピー変動は、待つ時間が長くなるほど、その間に見られるエントロピー変動が大きくなる可能性があり、与えられたエントロピー変動が最小値まで変動するまでの待ち時間は常に有限です。例えば、すべての粒子が容器の片側に収まっているという極めて低いエントロピー状態が考えられます。気体はすぐにエントロピーの平衡値に達しますが、十分な時間があれば、同じ状況が再び発生します。実用的なシステム、たとえば室温および大気圧の 1 リットルの容器内のガスの場合、この時間は非常に大きく、宇宙の年齢の何倍にもなり、実際にはその可能性を無視できます。
小さなシステムにおけるHの変動
Hは保存されない機械的に定義された変数であるため、他の同様の変数(圧力など)と同様に、熱変動を示します。これは、Hが最小値から定期的に自発的に増加することを意味します。技術的には、これはH定理の例外ではありません。なぜなら、H定理は非常に多数の粒子を含む気体にのみ適用されることを意図していたからです。これらの変動は、系が小さく、観測される時間間隔がそれほど長くない場合にのみ知覚できます。
H をボルツマンの意図どおりエントロピーとして解釈すると、これは変動定理の現れとして見ることができます。
情報理論との関連
Hはシャノンの情報エントロピーの前身です。クロード・シャノンは、 H定理にちなんで情報エントロピー の尺度Hと表記しました。 [ 17 ]シャノンの情報エントロピーに関する記事には、量Hの離散的な対応物である情報エントロピーまたは情報不確実性(マイナス記号付き)の説明が含まれています 。離散情報エントロピーを連続情報エントロピー(微分エントロピーとも呼ばれる)に拡張すると、上記の「ボルツマンのHの定義と意味」のセクションの式で表される表現が得られ、 Hの意味をよりよく理解できるようになります。
H定理による情報とエントロピーの関係は、ブラックホール情報パラドックスと呼ばれる最近の論争において中心的な役割を果たしています。
トールマンのH定理
リチャード・C・トールマンの1938年の著書『統計力学の原理』では、ボルツマンのH定理と、ギブスの一般化古典統計力学におけるその拡張について、丸々1章を割いている。さらに1章が、 H定理の量子力学的バージョンに当てられている。
古典力学
粒子集合の一般化正準座標をq iとp iとします。次に、位相空間の状態における粒子の確率密度を返す関数を考えます。この関数に位相空間の小さな領域( と表記)を掛け合わせると、その領域内の粒子の(平均)期待数が算出されることに 注意してください
トールマンは、ボルツマンの元のH定理における量Hの定義として次の式を提示しています。
ここで、位相空間を で分割した領域全体にわたって和を求めます。この領域は で添え字付けされています。また、無限小の位相空間体積 の極限では、和を積分として表すことができます。
H は、各セル内に存在する分子の数で表すこともできます。
量Hを計算する別の方法は次のとおりです。
ここで、Pは指定されたミクロカノニカル集団からランダムに選ばれたシステムを見つける確率です。これは最終的に次のように表すことができます。
ここで、Gは古典状態の数です。
量Hは速度空間上の積分として定義することもできます。
(1)
ここでP ( v )は確率分布である
ボルツマン方程式を使用すると、H は減少することしかできないことが証明できます。
N個の統計的に独立した粒子のシステムでは、Hは熱力学的エントロピーSと以下の関係がある: [ 23 ]
したがって、H定理によれば、S は増加するだけです。
量子力学
量子統計力学(古典統計力学の量子版)において、H関数は次の関数である。[ 24 ]
ここで、合計はシステムのすべての可能な異なる状態にわたって実行され、p i はシステムがi番目の状態にある確率です。
これはギブスのエントロピー公式と密接に関係している。
そして我々は(例えばWaldram(1985)、p.39に従って)HではなくSを使用して進めていく。
まず、時間に関して微分すると
(Σ dp i / dt = 0 という事実を利用します 。Σ p i = 1 なので、第 2 項は消えます。後で、これを 2 つの合計に分割すると便利であることがわかります。)
フェルミの黄金律は、状態αからβ、そして状態βからαへの量子ジャンプの平均速度に関するマスター方程式を与える。(もちろん、フェルミの黄金律自体には一定の近似値があり、この規則の導入によって不可逆性がもたらされる。これは本質的に、ボルツマンの「ストスザランザッツ」の量子版である。)孤立系の場合、ジャンプは次のような寄与をする 。
ここで、ダイナミクスの可逆性により、両方の式で同じ遷移定数ν αβが現れるようになります。
つまり
和の2つの差項は常に同じ符号を持ちます。例えば:
すると
全体として、2つの負の符号は打ち消されます。
したがって、
孤立したシステムの場合。
同じ数学は、相対エントロピーが詳細なバランスやその他の化学の文脈 におけるマルコフ過程のリアプノフ関数であることを示すために使用されることがあります。
ギブスのH定理
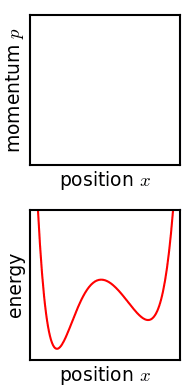
ジョサイア・ウィラード・ギブスは、ミクロなシステムのエントロピーが時間とともに増加する傾向を示す別の方法を説明した。[ 25 ]後世の研究者たちは、その結論がボルツマンの結論に似ていることから、これを「ギブスのH定理」と呼んだ。 [ 26 ]ギブス自身はこれをH定理と呼んだことはなく、実際、彼のエントロピーの定義、そして増加のメカニズムはボルツマンのものと大きく異なっている。このセクションは歴史的完全性のために収録されている。
ギブスのエントロピー生成定理はアンサンブル統計力学において設定されており、エントロピー量は、系全体の状態に対する確率分布で定義されるギブスのエントロピー(情報エントロピー)である。これは、系の特定の状態における個々の分子の状態分布で定義される ボルツマンのHとは対照的である。
ギブスは、最初は位相空間の小さな領域に限定された集団の運動を考察した。つまり、系の状態は、完全に正確ではないものの、かなりの精度で分かっている(ギブスエントロピーが低い)ことを意味する。この集団の時間的発展は、リウヴィル方程式に従って進行する。ほとんどすべての現実的な系において、リウヴィル発展は、非圧縮性流体中で染料を混合するのと類似した過程として、位相空間上で集団を「攪拌」する傾向がある。[ 25 ]しばらくすると、集団は位相空間上に広がっているように見えるが、実際には細かい縞模様であり、集団全体の体積(およびギブスエントロピー)は保存される。リウヴィル方程式は、系に作用するランダムプロセスが存在しないため、ギブスエントロピーを保存することが保証されている。原理的には、運動を反転させることで、いつでも元の集団を復元することができる。
したがって、この定理の重要な点は、攪拌された集団の微細構造が何らかの理由でわずかにぼやけると、ギブスエントロピーが増加し、集団は平衡集団になるという点である。現実になぜこのようなぼやけが生じるのかについては、様々なメカニズムが提案されている。例えば、位相空間が何らかの理由で粗視化されているというメカニズム(図に示す位相空間のシミュレーションにおけるピクセル化に類似)が提案されている。必要な有限の細かさであれば、集団は有限時間後に「実質的に均一」になる。あるいは、系が環境と制御されていない微小な相互作用を経験すると、集団の明確なコヒーレンスは失われる。エドウィン・トンプソン・ジェインズは、このぼやけは本質的に主観的なものであり、系の状態に関する知識の喪失に過ぎないと主張した。[ 27 ]いずれにせよ、それがどのように起こったとしても、ぼやけが元に戻らない限り、ギブスのエントロピーの増加は不可逆的である。
増加しない、正確に進化するエントロピーは、細粒度エントロピーと呼ばれます。ぼやけたエントロピーは、粗粒度エントロピーと呼ばれます。 レオナルド・サスキンドは、この区別を綿糸の体積の概念に例えています。[ 28 ]一方で、繊維自体の体積は一定ですが、別の意味では、綿糸の輪郭に対応する、より大きな粗粒度体積が存在します。
ギブスのエントロピー増加機構は、ボルツマンのH定理に見られる技術的な難点のいくつかを解決する。ギブスのエントロピーは変動せず、ポアンカレ回帰も示さないため、ギブスのエントロピー増加は、発生した場合、熱力学から予想されるように不可逆的である。ギブスの機構は、図に示す単粒子系のような自由度が非常に少ない系にも同様に当てはまる。したがって、集団がぼやけることを受け入れる限りにおいて、ギブスのアプローチは熱力学第二法則のより明確な証明となる。[ 27 ]
残念ながら、量子統計力学の発展の初期にジョン・フォン・ノイマンらによって指摘されたように、この種の議論は量子力学には適用できない。[ 29 ]量子力学では、ヒルベルト空間の関連部分の次元が有限であるため、集団はより微細な混合過程をサポートすることができない。古典的ケースのように平衡集団(時間平均集団)に収束していくのではなく、量子系の密度行列は常に変化し、時には再帰性を示す。したがって、シュトスツァーランザッツに依拠することなくH定理の量子版を構築することは、はるかに複雑である。[ 29 ]
参照
注記
- ^ a b L. Boltzmann, " Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen ." Archived 2019-10-17 at the Wayback Machine . Sitzungsberichte Akademie der Wissenschaften 66 (1872): 275-370. English translation: Boltzmann, L. (2003). "Further Studies on the Thermal Equilibrium of Gases". The Kinetic Theory of Modern Physical Sciences. Vol. 1. pp. 262– 349. Bibcode : 2003HMPS....1..262B . doi : 10.1142/9781848161337_0015 . ISBN 978-1-86094-347-8.
- ^ Lesovik, GB; Lebedev, AV; Sadovskyy, IA; Suslov, MV; Vinokur, VM (2016-09-12). 「量子物理学におけるH定理」. Scientific Reports . 6 32815. arXiv : 1407.4437 . Bibcode : 2016NatSR...632815L . doi : 10.1038/srep32815 . ISSN 2045-2322 . PMC 5018848. PMID 27616571
- ^ 「熱力学第二法則を破る方法が発見されたかもしれない」『ポピュラーメカニクス』2016年10月31日。 2016年11月2日閲覧。
- ^ Jha, Alok (2013年12月1日). 「熱力学第二法則とは何か?」 . The Guardian . ISSN 0261-3077 . 2016年11月2日閲覧。
- ^ Zeh, HD, & Page, DN (1990). 時間の方向の物理的基礎. Springer-Verlag, New York
- ^ポール・エーレンフェスト、タチアナ・エーレンフェスト(1959年)『力学における統計的アプローチの概念的基礎』ニューヨーク:ドーバー。
- ^ 「S.H.バーバリー」『情報哲学者』 2018年12月10日閲覧。
- ^バーバリー、サミュエル・ホークスリー (1890). 「気体の運動論におけるいくつかの問題について」 .ロンドン、エディンバラ、ダブリン哲学雑誌・科学ジャーナル. 30 (185): 298– 317. doi : 10.1080/14786449008620029 .
- ^ボルツマン、ルートヴィヒ (1896)。フォルレスンゲン ウーバー ガス理論。ライプツィヒ:アイ・タイル。
- ^ a b Chapman, Sydney (1937年5月). 「ボルツマンのH定理」 . Nature . 139 (3526): 931. Bibcode : 1937Natur.139..931C . doi : 10.1038/139931a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4100667 .
- ^ Brush, Stephen G. (1967). 「ボルツマンの「イータ定理」:証拠はどこにあるのか?」American Journal of Physics . 35 (9): 892. Bibcode : 1967AmJPh..35..892B . doi : 10.1119/1.1974281 .
- ^ギブス、J.ウィラード(1902年)『統計力学の基本原理』ニューヨーク:シュリブナー社。
- ^ Hjalmars, Stig (1976). 「ボルツマンHが大文字のイータである証拠」. American Journal of Physics . 45 (2): 214– 215. doi : 10.1119/1.10664 .
- ^ Reid, James C.; Evans, Denis J.; Searles, Debra J. (2012-01-11). 「コミュニケーション:ボルツマンのH定理を超えて:平衡への非単調アプローチにおける緩和定理の実証」(PDF) . The Journal of Chemical Physics . 136 (2): 021101. Bibcode : 2012JChPh.136b1101R . doi : 10.1063/1.3675847 . hdl : 1885/16927 . ISSN 0021-9606 . PMID 22260556 .
- ^ J. Uffink、「古典統計物理学の基礎大要」(2006年)
- ^ Rothstein, J. (1957). 「核スピンエコー実験と統計力学の基礎」. American Journal of Physics . 25 (8): 510– 511. Bibcode : 1957AmJPh..25..510R . doi : 10.1119/1.1934539 .
- ^グレイック 2011
- ^トルマン 1938年 135ページ 式47.5
- ^トルマン 1938年 135ページ 式47.6
- ^トルマン 1938年 135ページ 式47.7
- ^トルマン 1938年 135ページ 式47.8
- ^トルマン 1939年 136ページ 式47.9
- ^ Huang 1987 pg 79 式4.33
- ^トルマン 1938年 460ページ 式104.7
- ^ a b第12章、ギブス、ジョサイア・ウィラード(1902年)『統計力学の基本原理』ニューヨーク:チャールズ・スクリブナー・サンズ社より。
- ^トールマン, RC (1938). 『統計力学の原理』ドーバー出版. ISBN 978-0-486-63896-6.
{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ^ a b E.T. Jaynes; ギブス対ボルツマンエントロピー; American Journal of Physics,391,1965
- ^ Leonard Susskind , 統計力学講義7 (2013). YouTubeの動画.
- ^ a b Goldstein, S.; Lebowitz, JL; Tumulka, R.; Zanghì, N. (2010). 「マクロ量子系の長期挙動」. The European Physical Journal H. 35 ( 2): 173– 200. arXiv : 1003.2129 . doi : 10.1140/epjh/e2010-00007-7 . ISSN 2102-6459 . S2CID 5953844 .
参考文献
- リフシッツ, EM; ピタエフスキー, LP (1981).物理運動学.理論物理学講座. 第10巻(第3版).ペルガモン. ISBN 978-0-08-026480-6.
- ウォルドラム, JR (1985).熱力学の理論.ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-28796-8.
- トールマン、RC(1938)『統計力学の原理』オックスフォード大学出版局
- ガル, SF (1989). 「エントロピーに関するいくつかの誤解」 . バック, B.、マコーレー, V. A. (編著). 『最大エントロピーの実践』 .オックスフォード大学出版局(1991年出版). ISBN 978-0-19-853963-62012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ
- ライフ, F. (1965).統計および熱物理学の基礎.マグロウヒル. ISBN 978-0-07-051800-1.
- グレイック、J. (2011). 『情報:歴史、理論、洪水』 .ランダムハウスデジタル. ISBN 978-0-375-42372-7.
- 黄、カーソン (1987).統計力学、第2版.ランダムハウスデジタル. ISBN 978-0-471-81518-1.
- バディーノ、M. (2011). 「機械論的眠り vs. 統計的不眠症:ボルツマンのH定理の初期の歴史(1868–1877)」.ヨーロッパ物理学ジャーナル H. 36 ( 3 ): 353– 378.書誌コード: 2011EPJH...36..353B . doi : 10.1140/epjh/e2011-10048-5 . S2CID 120302680























