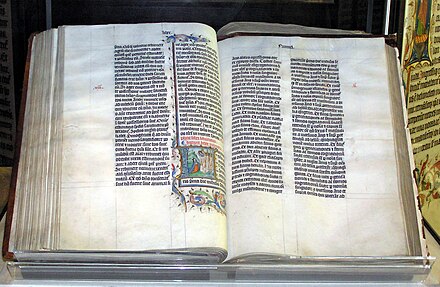聖書の地理学では、インドはアハシュエロス(クセルクセス1世)率いるアケメネス朝ペルシア帝国と国境を接していたと記されており、エステル記(エステル記1:1および8:9)にも記されている。[1]外典(デウテロカノノン)に所蔵されているマカバイ記第一には、「アンティコスの戦象を倒したインドの象使いたち(紀元前2世紀)」(マカバイ記第一6:37)が言及されている。[1]キシュ、ラガシュ、ウルを含むシュメールの都市で考古学的発見があり、インドとメソポタミアの交易が行われたことが確認されている。[1]例えば、インドで作られた象牙製品がメソポタミアで発見されている。[1]
列王記上9:26-27には、ソロモン王の海軍がオフィル(七十人訳聖書では「ソフェイル」および「ソファラ」)へ航海したことが記されている。 「ソフェイル」という言葉はコプト語でインドを意味する。インドでは金が豊富だったため、「オフィルはインドの港であったと一般に考えられている」。[1 ]列王記上10:22には、ソロモン王とヒラム王の海軍がイスラエルにもたらした「金、銀、象牙、猿、孔雀」について言及されている。[1]旧約聖書では、孔雀のtuki、象牙のshen habbim、猿のkofは、それぞれインドのtokei、ab、kapiに由来すると考えられる。[1]箴言 7:17、詩篇 45:8、雅歌 4:14には、インドの香木である沈香について言及されています。これはヘブライ語で「アハリム」と呼ばれ、サンスクリット語の「アガル」に由来しています。[1]同時代のバビロニア文献では、亜麻布を「シンドゥ」(「インドの」という意味)と呼んでおり、ギリシャ語文献でも「シンドン」が使われています。[1]エステル記 1:1に登場する「ホドゥ」は、インドの聖書名で、インド・ガンジス平野のシンドゥ川の住民を指す「ヒンドゥー」という言葉に由来しています。[2]
聖書、神学、教会文学百科事典は、インドのユダヤ人がペンテコステに現れることに関して次のように述べています。[3]
ペンテコステに出席した外国人ユダヤ人のリスト(使徒行伝 2:9)において、Ι᾿νδίαν(インド)と読むべきであり、Ι᾿ουδαίαν(ユダヤ)と読むべきではないという説も、ある程度の根拠に基づいていると考えられる。しかし、もし一般的な読み方を変更する必要があるならば、より可能性の高い読み方はΙ᾿δουμαίαν(イドマイア)である(クイノル『コンメンテーション』参照)。ヘブライ語の「ホッドゥ」は「ホナドゥ」の略称であり、これはインダス川の現地名「ヒンドゥ」または「シンドゥ」と同一であり、また「ヴェンディダッド」に登場する国の古代名「ハプタ・ヘンドゥ」とも一致する。現地語の「シンドゥス」はプリニウスによって言及されている(vi, 23)。[3]
ジェラルド・フラリーによると、エゼキエル書38章5節の文脈から、クシュとプトの子孫はインドと現在のパキスタンに居住していることがわかる。[4]このため、「シリア語、カルデア語、アラビア語訳では、その語(クシュ)をインド人またはインド人と呼ぶことが多い。例えば、歴代誌下21章16節、イザヤ書11章11節、イザヤ書18章1節、エレミヤ書13章23節、ゼパニヤ書3章10節などである。」[3]
参照
- 聖書に登場する場所のリスト
- 初期の教父の著作に言及されているギュムノソフィスト
- インド(ヘロドトス)
- インドの名前
参考文献
- ^ abcdefghi ザカリアス・P・サンディ (1993). 『古代におけるインドと西洋』ブリル・アカデミック・パブリッシャーズ212–267頁.
- ^ デュリン、レイチェル・ゾハール(2015年10月26日)「ターネゴル・ホドゥ、七面鳥と呼ばれる鳥」。デイトン・ジューイッシュ・オブザーバー。 2024年3月7日閲覧。
ホドゥは聖書に登場するインドの名称(エステル記1:1)で、ペルシャ語のヒンドゥー(インダス川流域の地域名)に由来しています。ちなみに、ロシア語、ポーランド語、イディッシュ語でも七面鳥はインドの鳥と呼ばれています。トルコ語でもヒンディー(インド)と呼ばれています。
- ^ abc マクリントック、ジョン (1872). 『聖書・神学・教会文学百科事典』ハーパー社 551ページ.
- ^ ジャック、ジェレミア(2019年5月28日)「聖書にインドは記されているか?」フィラデルフィア・トランペット紙。 2023年8月9日閲覧。