この記事は更新が必要です。理由は、「この記事は20世紀初頭のカトリック百科事典からコピー&ペーストされたものです。 (2023年6月) |
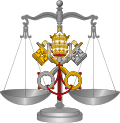 |
| シリーズの一部 |
| カトリック教会の教会法 |
|---|
 Catholicism portal Catholicism portal |
カトリック教会の教会法における譴責(けんしょう)とは、洗礼を受けた者、非行者、反抗的な者に対して教会が課す、医学的かつ精神的な罰である。この罰は、当該者が反抗を克服するまで、特定の霊的利益を全部または部分的に剥奪する。これらの霊的利益には、秘跡へのアクセス、特定の典礼活動への参加、教会行事への参加などが含まれる。
カトリック教会における譴責は、古代の教会慣習に起源を持ち、何世紀にもわたって進化してきました。譴責は、初期の教会が信徒間の秩序と規律を維持しようと努めたことに端を発しています。歴史を通して、譴責は教会の教えと価値観を守り、悔い改めを促し、精神的な成長を促すために用いられてきました。
歴史と発展
This section relies largely or entirely on a single source. (April 2024) |
「検閲」という用語とその概念は、ローマ共和国にまで遡ります。ローマ共和政紀元311年、公的検閲官(censores)の職が設立されました。彼らの職務には、すべてのローマ市民の登録簿(census)と、元老院議員や騎士などの階級の維持が含まれていました。彼らはまた、風俗や道徳に関する懲罰権を持ち、国家の道徳的または物質的福祉に影響を与える理由で市民を社会階級から降格させるなど、罰則を科す権限も持っていました。この形態の処罰は検閲(censura)として知られていました。ローマ人が市民の尊厳の維持を重視したことは、教会が信徒の清浄性と神聖性を重視していたことと似ています。初期の教会では、良好な会員は公の集会で読み上げられる登録簿に記載され、破門された者はこのリストから除外されました。これらの登録簿はディプティク(二重写本)またはカノン(聖名帳)と呼ばれ、存命の会員と故人の会員の両方の名前が含まれていました。ミサ典礼書はこの古代の慣習の要素を残しています。[1]
当初、破門は、教会の非行に走った信徒に対して用いられたあらゆる懲戒処分の総称であり、キリスト教社会における様々な聖体拝領の段階に応じて様々な形態があった。例えば、信徒の位階には、 expiatores(エクスピアトーレス) 、pænitentes (ペニテンテス)があり、さらにconsistes(コンシステンス)、substrati(サブストラティ)、audientes(アウディエンテス) 、flentes (フレンテス)、lugentes (ルゲンテス)といった下位区分もあった。祈り、聖餐、聖体拝領への参加、キリスト教の埋葬といった教会の権利は全信徒に共通であったが、その他は聖職者の様々な位階に特有のものであった。これらの権利を剥奪されると破門となり、それは教会の位階に相応する聖体拝領から、全部または一部排除されることを意味した。[注 1]初期の教会文書では、破門などの用語は必ずしも譴責や特定の種類の譴責と同義ではなく、より広い意味での懺悔や処罰を指すこともあった。[1]
後期ローマ法用語(Codex Theod. I tit. I, 7 de off. rector. provinc.)において、「譴責(censure)」という用語は一般的な意味で刑罰を指すようになった。教会は初期にこの用語を採用し、公開懺悔、破門、そして聖職者にとっては停職や降格など、様々な形態の刑罰を描写した。ローマ国家と同様に、教会は刑罰を単に苦痛を与えることだけでなく、特定の善、権利、特権の剥奪とみなしていた。教会の文脈において、これらは祈りへの参加、聖なる犠牲、秘跡、教会の一般的な交わりといった霊的な善と恩恵、あるいは聖職者にとってはその職務に付随する権利と名誉であった。[1]
法的な発展ジュス・ノヴム
数世紀後、教令の時代に法学は大きく進歩した。内部法廷(罪と良心に関するもの)と外部法廷(教会の統治と規律に関するもの)の区別が確立された。刑罰の様々な種類と性質は、注釈者、裁判官、法学者によってより明確に定義された。13世紀初頭までには、教令には明示的には述べられていなかったものの、「譴責」という用語は、禁錮、停職、破門といった教会刑罰の特定のカテゴリーを指すようになった。1200年に刑罰一般を指して「譴責」という用語を用いた教皇インノケンティウス3世[注 2]は、その後、1214年に教皇文書における教会の譴責に関する回答の中でその意味を明確にした。彼は譴責を他の教会刑罰と明確に区別し、譴責とは具体的には禁錮、停職、破門を指すと宣言した。[注 3]
この明確化を受けて、教会法学者たちは、治療的または矯正的な刑罰(譴責)と報復刑という2種類の刑罰を区別し始めた。譴責は主に犯罪者の矯正または更生を目的とし、この目的が達成されれば終了する。報復刑(poenæ vindicativæ)は、非行者を更生させる可能性を排除しないものの、積極的な苦しみを課すことで正義または社会秩序を回復することを主な目的としていた。報復刑の例としては、肉体的または金銭的な罰、懲役、修道院での終身隠遁、キリスト教の埋葬の剥奪、聖職者の解任、品位の低下、一時的な職務停止(例えば、聖アルフォンソ・リグオリが特定のケースにおける譴責とみなした、一定期間の職務停止latæ sententiæ)などがある。告解による償いも、その主な目的が個人を更生させることではなく罪の償いをすることであるため、報復刑と見なされる。重要なのは、犯罪から生じる不規則性は非難でも報復的な処罰でもなく、個人が聖職を全うするのを妨げる教会法上の障害であり、それによって聖職の受任や行使が禁じられるということである。[1]
譴責の問題は、1418年に教皇マルティヌス5世が発布した憲法「アド・ヴィタンダ」によって大きく変化した。この憲法以前は、譴責対象者で公に知られている人物はすべて避けるべき存在(ヴィタンディ)であり、宗教的交流や市民的交流(イン・ディヴィニスまたはイン・ヒューマニス)に参加することはできなかった。譴責は、キリスト教共同体の特定の精神的利益に参加する権利に対する刑罰的制限であるため、譴責を受けた個人だけでなく、こうした精神的事柄で彼らと交流した人々にも影響を及ぼした。たとえば、聖職停止処分を受けた聖職者は、秘跡やその他の宗教的儀式に参加することを許されなかった。しかし、マルティヌス5世の憲法では、司法判決によって明示的に個人的にヴィタンディと宣言された個人のみが、今後はそのように扱われると規定されていた。 1884年、ローマ異端審問所は、聖職者に対する冒涜的な暴力による悪名高い破門ヴィタンディの場合にはこの手続きは不要であることを明確にした。マルティヌス5世の宣言は、社会情勢の変化により、寛容な破門者(トレラティ)と非難されていないかのように交流できるようにすることで、信者のより広いコミュニティに利益をもたらすことを意図していました。
1869年、教皇ピウス10世は、その憲章『使徒的戒律の穏健化』(Apostolicae Sedis moderationi)を通して、譴責に関する教会規律に大幅な改正を加えた。この文書は、多くの判例法に基づく譴責を廃止し、他の譴責を改正し、新たな判例法に基づく譴責のリストを作成した。これらの変更により、譴責の件数は大幅に減少し、教会の規律措置は変化する状況に応じて調整された。[1]
罰則の内容
This section relies largely or entirely on a single source. (April 2024) |
カトリック教会は、これらの条件を強制する権限をイエス・キリストから直接授かったと信じている。また、教会員を規律する規律法を制定する権利も主張しているが、教会法の遵守を強制する権限がなければ、この権利は無意味となる。教会は創立当初から、この権限を行使して規律を強制してきた。これは、近親相姦を犯したコリント人[注4]やヒュメネオとアレクサンダー[注5 ]に対する聖パウロの行動に見られる通りである。 [1]
教会の究極の目標は、信者の永遠の救済(salus animarum lex suprema、「魂の救済は至高の法である」[注 6])です。したがって、教会は非行に走る信者に対して、まず第一に彼らの矯正と改革を求め、罪人が神のもとに立ち返り、魂が救済されることを目指します。これが教会の刑罰の主目的ですが、他の結果も伴うことが多く、例えば他の信者への模範となることや、キリスト教社会の維持などが挙げられます。神の原則によれば、神は罪人の死ではなく、彼らがその道から立ち返って生きることを望んでおられます(エゼキエル書18章23節)。したがって、教会は、罪人の改心の望みがほとんど、あるいは全く残っていない場合に限って用いられる報復的な刑罰よりも、治療的あるいは矯正的な性質を持つ譴責を優先します。[1]
譴責の第一かつ当面の目的は、反抗心や故意の強情を克服し、犯罪者が自らの精神状態をより深く理解できるようにすることです。第二の、より遠大な目的は、他の犯罪者に対する抑止力となることです。反抗心とは、法に対する頑固で反抗的な不服従であり、権威への軽蔑を反映しています。なぜなら、反抗心は法を犯すだけでなく、一般的には法に付随する罰や譴責に対する軽蔑を表明するものだからです(レームクール、判例集、フライブルク、1903年、第984号)。脅迫される罰を知らない場合や、強い恐怖を感じている場合には、通常、譴責を受けることはありません。なぜなら、そのような状況下では、真の反抗心は存在し得ないからです。反抗心は執拗な悪行を意味するため、犯罪を犯すだけでなく、しかるべき警告と訓戒を受けた後も悪行を続ける必要があるからです。この警告(monitio canonica)は、法律そのもの、あるいは教会の長老や裁判官から発せられる。従順は二つの形で起こり得る。第一に、教会の長老や裁判官から直接発せられた警告を無視した場合。第二に、教会法とそれに付随する譴責を故意に破り、法律自体が永続的な警告(Lex interpellat pro homine)となる場合である。[1]
譴責は、重大な霊的利益の剥奪であり、キリスト教徒が犯す罪が、内外ともに重大で、罪自体が「イン・ジェネレ・スオ」(その種類において)であるか、あるいは譴責によって完全かつ完全であるとみなされる罪である場合にのみ課せられます。罪と刑罰の間には相応の関係がなければなりません。譴責は治療薬として、個人から霊的財産を剥奪するのではなく、その使用を一時的に、つまり本人が悔い改め、霊的病から回復するまでの期間のみ剥奪するものです。最も重大な譴責である破門は、特定の期間を定めて課せられることはありません。一方、活動停止や禁令は、一定の条件下で、一定期間適用される場合があります。教会による譴責の実際の処罰は、教会の管理下にある特定の霊的財産や利益、例えば秘跡、公の祈り、免罪符、聖なる儀式、管轄権、教会の聖職、職務へのアクセスを剥奪することです。しかし、洗礼の消えることのない性質により聖徒たちの永遠の交わりはそのまま残るので、譴責によって個人の恩寵や信者の個人的な祈りや善行が奪われることはありません。
三つの譴責の効果を区別するために、破門は聖職者と信徒の両方に科せられ、信徒を信徒の交わりから排除し、ローマ教皇を目に見える長とする目に見える教会の信徒が共有するすべての霊的財産の使用を禁じる。聖職者にのみ適用される停職は、信徒を信徒の交わりの中にとどめるが、聖職者(qua ministri)としての聖なる職務の遂行を直接的に禁じ、裁判権、告解の聴取、役職の保持など、聖職者の権利の一部またはすべてを剥奪する。禁令は、聖職者または信徒が聖なる事柄(res sacræ)に関連する特定の教会財産や、特定の秘跡の受領やキリスト教の埋葬などの共同体への参加に受動的にアクセスすることを禁止する。[1]
分割
非難法律そしてアブ・ホミネ
譴責を破門、停職、禁錮に具体的に区分することに加えて、譴責にはいくつかの一般的な分類がある。まず、a jure (法律による)譴責とab homine (人身に対する非難)がある。a jure(法律による)譴責は、立法者の恒久的な布告によって課されるものであり、つまり、法律自体によって犯罪に付随するものである。ここで、恒久的かつ永続的な拘束力を持つ制定法と、通常は義務が一時的であり、それを発布した上位者の死とともに失効する単なる命令または戒律とを区別することが重要である。したがって、 a jure (法律による)譴責は、教皇の布告や総会の布告など、教会の慣習法に付随するか、または、通常は管区または教区会議において、たとえば特定の教区または領土の司教によって一般法によって課される。
一方、人による譴責( ab homine)は、前述の法律とは対照的に、司教などの裁判官による判決、命令、または特定の戒律によって課されるものである。これらの譴責は一般的に、特定の一時的な状況に起因するものであり、その状況が続く間のみ有効である。人による譴責は、すべての対象者に適用される一般的な命令、命令、または戒律( per sententiam generalum )の形をとる場合もあれば、犯罪者が有罪判決を受け譴責される裁判中など、個別の事件に対する特定の命令または戒律として発せられる場合や、特定の犯罪を防止するための特定の指令として発せられる場合もある。[1]
非難latæ sententiæそしてferendæ sententiæ
教会の刑罰法におけるもう一つの重要かつ独特な譴責区分は、a jure(法律に基づく)譴責とab homine (人身に関する)譴責の区別であり、これらは(1) latæ sententiæ (判決に基づく)または(2) ferendæ sententiæ(懲役刑に基づく)に分類される。[1]
(1) 宣告された刑罰( latæ sententiæ )は、犯罪を犯すだけでipso facto(事実上)に課せられる。言い換えれば、犯罪者は法律を破った時点で自動的に刑罰を受け、その譴責は裁判や司法判決を必要とせず、直ちに良心を拘束する。法律自体が、違反が完了した瞬間に刑罰を執行する。この種の刑罰は、信者が道徳的に教会法に従う義務を負う教会において特に効果的である。犯罪が秘密裏に行われた場合、譴責は秘密のままであるが、神と良心において拘束力を持つ。犯罪が公に行われた場合、譴責も公にされる。しかし、秘密裏に行われた譴責を公にするためには、犯罪に関する司法調査が行われ、その後、犯罪者が譴責を受けたことを確認する正式な宣言(確認判決)がなされなければならない。[1]
(2) 宣告を待つ譴責ferendæ sententiæ は、法や戒律に結びついており、刑事手続きを経て正式に判決または断罪判決が下されるまでは、違反者に刑罰が科されないものである。譴責がlatæ sententiæであるかferendæ sententiæであるかは、法律の文言から判断できる。latæ sententiæの譴責に使用される最も一般的な用語には、ipso facto、ipso jure、 eo ipso sit excommunicatusなどがある。一方、文言が将来の司法措置を示唆している場合、譴責はferendæ sententiæ(例:excommunicetur 、 suspenditur)である。疑義がある場合、譴責はferendæ sententiæであると推定される。刑事問題では寛大な解釈が好まれるからである。さらに、懲戒処分を科す前に、3回の警告(monitiones)、または1回の厳重警告が必要である。ただし、犯罪と非行者の不服従がともに悪名高く、十分に証明されている場合は除く。[1]
譴責は留保と非留保に分けられます。罪が留保されるように、譴責も留保されます。この場合の留保とは、下位の者が譴責を免除する権限を制限または否定し、免除する権限は上位の者が保持することを意味します。[1]
譴責の要件
譴責を課すには、それが陪審によるものであろうと人身に対するものであろうと、以下の要件を満たす必要がある。[1]
- 立法府または裁判官の管轄権。
- 十分な理由;
- 正しい手順。
管轄権については、譴責は教会の外部の法廷または外部統治に属するものであるため、当然のことながら、法律または裁判官による譴責には、管轄権、すなわちこの法廷において行動する権限が必要である。さらに、譴責を科すには十分な理由が必要である。譴責は、法の制裁として、法の付属物である。したがって、法に不正義や不合理など、法に修正をもたらす重大な瑕疵は、それに付随する譴責も無効にする。この譴責の十分な理由は、法の制定過程において法秩序が遵守されなかったため、または法が対象とする犯罪が教会の譴責を正当化するほど重大ではなかったために、法に欠ける場合がある。刑罰は犯罪に比例するものでなければならない。立法行為において法秩序が遵守されていたものの、刑罰が犯罪に見合っていない場合、すなわち、犯罪行為が法律に定められた極端な刑罰を正当化していない場合、法律は二つの部分から成り立っているため、戒律は維持されるが、刑罰または譴責は維持されない。[注 7]疑義がある場合には、法律と刑罰の両方が有効であると推定される。
適切な手続きに関して言えば、譴責判決は、人身に対する譴責に必要な警告など、実質的な手続き上の規則が遵守されていない場合、無効となる可能性がある。しかし、刑罰の重さと犯罪の重さの間に客観的な比例性がある場合、たとえ判決に偶発的な瑕疵(例えば、有罪者に対する個人的な敵意から譴責が科された場合や、その他の付随的な手続き上の規則が遵守されていない場合)があったとしても、譴責判決は有効である。
内部法廷(「内部法廷」)では無効、つまり真実に照らして無効であるが、外部法廷では有効、つまり法の推定に照らして有効な譴責について疑問が生じる。例えば、ある人物が外部法廷において譴責の対象となる犯罪で有罪判決を受けた場合、良心においては自らが無実であると認識しているならば、その譴責の効果はどうなるだろうか。外部法廷で有罪と認定された以上、その譴責はその法廷において有効な効果を有し、スキャンダルを避け、規律を維持するために外部的に遵守されなければならない。このような譴責を受けた人物による外部法廷における管轄権行使はすべて無効と宣言することができる。しかし、内部法廷においては、その人物は管轄権を保持し、スキャンダルがなければ、譴責違反に対する罰則(例えば不正行為)を負うことなく、譴責を受けていないかのように行動することができる。譴責には条件が付されることもあり、条件が満たされれば、その譴責は有効となる。[1]
譴責は復讐的な罰として、すなわち、主として救済措置としてではなく、むしろ犯罪への復讐として課すことはできるだろうか。これはより深刻な問いであり、教会法学者たちは、特定の法文、とりわけグラティアヌス教令の解釈を通じて、この問いに答えようと努めてきた。[注 8]しかし、これらの法は、譴責という用語が特定の意味を持たずに一般的な罰則を指して使われていた、より初期の規律に関係するものである。したがって、今やその解決策は実定法の中に見出されなければならない。教令法は、異なる種類の罰則がより明確に区別されているものの、この問題に明確に答えてはいない。後の法では、トレント公会議(第 25 会期、第 3 章、De ref.)が賢明にも司教たちに、譴責の剣は控えめに、かつ細心の注意を払って用いるべきであると助言している。譴責は本質的には霊的な財産や利益の使用を剥奪するものであり、治療的に課されるべきものであり、違反者が反抗的な態度を改めれば直ちに解除されるべきである。
前述のように、聖アルフォンソとその後の著述家たちは、譴責は副次的に懲罰的、抑止的目的を持つ場合があり、この観点から、特定の期間を定めて科されることもあると主張している。これは一般的には正しいが、破門が報復的な罰として科されることは決してないことは確かである。しかし、停職や禁令は、たとえ稀で短期間であっても、実定法に基づく報復的な罰として科されることがある。その理由は、停職や禁令は破門のように、違反者を信徒の交わりから追放したり、あらゆる霊的財産を完全に剥奪したりするものではないからである。したがって、重大な理由がある場合、これらの譴責は報復的な罰の性質を帯びることがある。これは特に、聖職者が職務や聖職資格を停止される場合のように、何らかの現世的権利の剥奪を伴う場合に当てはまる。このような場合、譴責は、霊的財産の使用を剥奪することを主たる目的とする譴責というよりは、厳密に言えば罰に近いと言えるでしょう。[注 9] [1]
非難の対象、能動的および受動的
譴責の主体、すなわち誰が譴責を課すことができるかについて言えば、譴責は教会の外部統治に属する。したがって、教会の外部フォーラムにおいて正当な管轄権を持つ者によってのみ、譴責を課すことができる。陪審による譴責、すなわち、全体的または部分的にキリスト教社会を拘束する法律に組み込まれた譴責は、立法権を持つ者によって課すことができる。たとえば、教皇または総会は、全世界、それぞれの管轄区域内のローマ諸教会、その教区内の司教、司教座聖堂空位時の参事会または司教代理、外部管轄権を持つ常任高位聖職者、聖座の使節、および各自の臣民に対する常任司祭参事会に対して、そのような譴責を課すことができる。しかし、教区司祭、女子修道院長、世俗の裁判官には、そのような権限はない。教会裁判官による譴責( ab homine)は、その裁判官の管轄権が通常のものか委任されたものかを問わず、特定の法律を執行するため、または特定の悪事を防止するために科される。立法権を持たない総司祭長や委任裁判官は、司法命令の執行を強制するなど、自らの権威を維持し保護するために、 ab homine 譴責(ab homine)のみを科すことができ、a jure 譴責(ab homine )は科すことができない。[1]
譴責は霊的な罰であるため、キリスト教徒、すなわち洗礼を受けた者にのみ課せられる。さらに、罰であるがゆえに、譴責を課す上位者の臣民にのみ課せられる。このような臣民は、居住地、準居住地、あるいは犯した犯罪行為(ratione delicti)を理由として生じる。特定の法に違反した巡礼者は譴責の対象とならないが、譴責(ferendæ sententiæ )が付された慣習法に違反した場合、地元の司教は彼らに譴責を課すことができる。枢機卿と司教は、法に明示的に規定されていない限り、(破門を除き)法的譴責を免除される。 [1]国家元首を裁く権限は教皇のみにある。[ 2]
国王や君主は司教によって譴責を受けることはできず、共同体や教会会議を破門することもできない。しかし、共同体は禁令や停職処分を受ける可能性がある。このような場合、これは本来の意味での譴責ではなく、むしろ刑罰的剥奪となる。つまり、ある人が共同体の一員でなくなった時点で、もはや刑罰の対象にはならないのである。[1]
非難からの赦免
すべての教会法学者は、一度受けた譴責は赦免によってのみ解除できることに同意する。譴責は強情を克服するための治療的罰ではあるが、悔い改めによって直ちに解除されるわけではない。譴責の賦課は司法行為であるため、司法上の赦免が必要であり、真の改心がみられる場合に合法的に認められなければならない。譴責を受けた者が破門または禁令を受けた場合、たとえ死亡しても譴責は解除されない。キリスト教の埋葬を拒否されるなど、何らかの影響が依然として残る可能性があるからである。正式な赦免は、特定の行為の完了を条件とする執行猶予など、譴責が解消条件付きで課される場合に限っては不要である。執行猶予または禁令が報復的罰として課される場合、それらは赦免によってではなく、課せられた期間の経過によって消滅することがある。譴責自体は、それがまだ課されていない場合、それが付された法律の廃止、取消、または(典型的には)特定の戒律として人身に対する罰として課された場合には上位者の死によって終了することがある。[1]
赦免は権限のある当局による刑罰の免除または緩和を伴う正義の行為であり、譴責におけるres favorabilisである。したがって、悔い改めた譴責対象者に対して拒否することはできない。赦免は 2 つの方法で与えられる。(1)内部のフォーラム、すなわち罪および隠れた譴責に対して。これは、告解または告解以外の良心のフォーラム ( forum conscientiæ )において、必要な管轄権を持つ司祭によって与えられる。いずれの場合も、譴責に関する秘跡の式文が用いられる。(2)外部のフォーラムでは、譴責を課した人物、その後継者、代理人、上位者 (教皇など) など、必要な司法権を持つ者によってのみ赦免が与えられる。使用される式文は、状況に応じて厳粛なバージョンまたは短縮版のいずれかであり、両方ともローマ儀式書に見られる。赦免は、その有効性のための条件が満たされるかどうかによって、無条件または条件付きで与えられる。また、すべての勅令、勅書、使徒特権において、赦免の効果が隠れた譴責によって妨げられないように、安全のためにad cautelam (安全のために)が与えられる。さらに、即時に効力を発揮するabsolution ad reincidentiamという赦免もある。これは、一定期間内に定められたことを行わなかった場合、 ipso facto、赦免されたのと同じ譴責を受けることになる。譴責を解除した者はreincidentiaを課すことができる。今日、reincidentia はab homineのみであり、つまり、赦免する者によって適用されなければならない(Lega, lib II, vol. III, nos. 130–31)。[1]
赦免の司祭、すなわち譴責を免除できる者に関して、一般原則は「縛ることができる者のみが解くことができる」(illius est solvere cujus est ligare)であり、必要な権限を有する者のみが譴責を与えることができることを意味します。この権限は、通常の権限または委任された権限のいずれかです。特定の判決または命令によって課された人身譴責(ab homine)や、法律上の留保譴責(reserved censure a jure)の場合、譴責を課した本人、またはその後継者、上位者、もしくは委任された者のみが譴責を与えることができます。したがって、司教代理(vicar capitular)は、故高位聖職者の権限を継承し、故司教の通常の権限によって課された譴責を免除することができます。上位者の権限に関して言えば、教皇は普遍的上位者として、司教などの下位者によって課された譴責をいつでも取り消すことができます。しかしながら、大司教は属司教の絶対的な上位者ではなく、参事官が課した譴責を、参事官が面会または上訴した際にのみ解除することができます。上位者が下位司教が課した譴責を免除する場合は、必ず下位司教に通知し、違反者に十分な弁解を求めなければなりません。委任判事の免責許可権の範囲は、委任状において明確に示されなければなりません。[1]
一般判決によって公益訴訟または人身訴訟として譴責が課せられた場合、譴責が留保されていない場合、罪を赦免する権限を持つ承認された聴罪司祭は、外部および内部の両方の法廷で譴責を免れることができます。一方の法廷で与えられた免罪は、譴責が法廷係争中である場合を除き、他方の法廷でも有効です。この場合、内部法廷での免罪は外部法廷では有効になりません。承認されていない司祭、または告解を聴く権限を持たない司祭は、たとえ譴責が留保されていない場合でも、死の危険がある場合を除き、譴責を免れることはできません。譴責が公益訴訟として留保されている場合、譴責が留保されている本人、またはその上司、後継者、または代理人のみが免罪を与えることができます。教皇に留保されている譴責は留保されているか、特別な方法で留保されています。前者については、トレント公会議(第 24 会期、第 6 章、「De ref.」)で、犯罪が隠蔽され、知られていない場合、または司法裁判所に持ち込まれていない場合、司教または司教から委任された者は、良心の場(foro conscientiæ)で、またその司教の教区内で、臣民をこれらの譴責から赦免することができると定められています。ここでいう司教には、教会領を持つ修道院長、司教座聖職者、および司教の管轄権を持つその他の者も含まれ、総長の委任に基づく総司教座聖職者や常任高位聖職者は含まれません。これらの権限を受けることができる臣民は、司教の教区内に住む者、またはそこで告解に来る外部の者であり、彼らは赦免の対象となる臣民とみなされます。ただし、このような赦免は良心の場(foro conscientiæ)または良心の領域に限定されるため、外部で付与することはできません。譴責がローマ教皇に特別に留保されている場合、司教は必要不可欠な場合を除き、通常の権限で赦免を与えることはできない。これらの場合、聖座は司教に対し、一定期間、司教の生涯、または指定された件数について、特別な許可を与える。教皇法によって司教または裁治権者に留保されている譴責は、すべての司教、修道院長、司教代理、司祭代理によって、たとえ悪名高い事件であっても、いかなる法廷においても赦免される。死(死因死)の時点では、承認されていない司祭であっても、すべての譴責を免除することができ、すべての譴責の免除は教皇憲章『使徒的中庸の使徒的中庸』(ピウス9世、1869年)の規定に従う。[注 10] [1]
赦免の条件
これらの条件は、赦免を与える司祭と赦免を受ける者の両方に適用されます。司祭による赦免は、強制によって得られた場合、または重大かつ不当な恐怖によって強要された場合は無効です。さらに、虚偽の主たる理由に基づいて赦免が与えられた場合も無効です。例えば、実際には償いがなされていないのに、償いがなされたと虚偽の主張をして裁判官が赦免を与えた場合などです。赦免の条件は一般的に、法の定めることを命じるという意味の「 injunctis de more injungendis(インジュンクティス・デ・モア・インジュンゲンディス)」という文言で概説されています。これには以下のものが含まれます。
- 被害者の満足
- 非行者は司教または告解師の賢明な判断に従ってスキャンダルを修復し、罪を犯す機会をすべて取り除かなければなりません。
- 特別に留保された譴責に対して赦免が認められる場合、その人は(外部で、宣誓のもとで)その件に関する教会のさらなる指示に従うことを約束しなければならない(stare mandatis ecclesiæ)。
- より重大な犯罪の場合、再犯を防ぐために宣誓が必要となる場合があります。
- 告解で課せられた償いとは別に、赦免された者は過ちに対する償いとしてもう一つの有益な償いを行い、それを完了しなければならない。[1]
注記
- ^ (Bernardi, Com. in Jus Eccl., II, pt. II, diss. 3, cap. 5.)
- ^ (cap. 13 X De judicious、II、1)
- ^ (cap. 20、X De 動詞、signif. V、40)
- ^ (I コリント 5 章、i 章以降)
- ^ (Iテモテ120)
- ^ 参照:教会法典1752条、1983年教会法典。
- ^ (スアレス Disp. IV、セクション VI、no. 10)
- ^ ( Eos qui rapiunt、Raptores。 — Caus. XXXVI、Q. 2、c. 1、2、Si quisepiscopus、Caus. XXVII、Q. 1、c. 6、など)
- ^ (スアレス、前掲書、第IV部、第V節、29-30)
- ^ 聖コング・インクイジスの法令(1886年6月23日)およびその後の解釈による、教皇の譴責に対する赦免方法(必要な場合)の重大な変更については、Tanquery, Synop. Th. Mor., III (II), 1907, pp. 321-24およびGury-Ferrères, Th. Mor., II, nn. 575-76を参照。
参考文献
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxy ガンズ、レオ(1908年)カトリック百科事典第3巻。
- ^ 教会法典1405条1項1号、1983年(イントラテキスト)、2016年4月16日にアクセス。


