
ロシア帝国の軍事史は、ロシア帝国が関与した武力紛争の歴史を網羅する。この歴史は、1721年のピョートル大帝による建国から、ソビエト連邦の成立につながったロシア革命(1917年)まで遡る。関連する出来事の多くは、ロシア帝国陸軍、ロシア帝国海軍、そして20世紀初頭以降はロシア帝国航空隊に関係している。
帝政ロシア

歴史家たちは、ピョートル大帝の治世がロシア史においていかに重要であったかを長らく指摘してきた。ピョートルは、広大ながらも技術的にも社会的にも後進的な国で成人した。1682年にロシアを掌握すると、皇帝は西側諸国に近づくべく、ロシアの政府、社会、そして軍隊のあらゆる側面を精力的に改革した。彼は近隣諸国との大規模な戦争を繰り広げ、あらゆる資源を駆使して軍事力を強化し、多くの若者を西側諸国に送り込み、将来のロシアが必要とするであろう職業や技能を習得させた。ピョートルは、旧体制を打ち砕くことで新たなロシアを築いた。
ピョートルが築いたロシア史の時代は、統治者と領土の間に新たな繋がりが生まれたことから帝政時代、彼の治世中に新たに建設されたサンクトペテルブルクに首都が遷都されたことからサンクトペテルブルク時代、そしてかつては排外主義的であった国に築かれたより大きな覇権を強調する全ロシア時代など、様々な呼び名で呼ばれてきた。彼の統治時代から1917年の十月革命(そしてロシア帝国の崩壊)までの期間は、彼の重要性に敬意を表してピョートル時代と呼ばれることもある。しかし、ロシア帝国が正式に成立したのは、大北方戦争の終結後、ピョートルがインペラトル(皇帝)の称号を授かってからである。[1] [2]
ピョートル大帝
幼少期と王位継承

ピョートル大帝は1672年6月9日、皇帝アレクセイ1世と2番目の妻ナタリア・ナルイシキナの間に生まれた。皇帝は2度の結婚で14人以上の子をもうけたが、成人まで生き残ったのは最初の結婚で生まれたフョードルとイヴァン、2度目の結婚で生まれたピョートルの3人だけだった。ピョートルは異母兄弟たちに比べてかなり健康だったが、異母兄弟たちは2人とも重度の身体障害を抱えていた。ピョートルの父は1676年に亡くなり、前皇帝の長男フョードルが皇帝に即位した。そのフョードルも1682年に亡くなったが、彼には皇位継承者がいなかった。継承の道筋が明確でなかったため、最も有力な2つの大貴族の家系であるナルイシキン家とミロスラフスキー家は、皇位をめぐる競争でそれぞれ異なる継承者を支持した。ピョートルを支持するナルイシュキン家は早々に勝利を収め、1682年4月、ピョートルは母を摂政としてツァーリに即位した。しかし、5月、ピョートルの健常な異母妹ソフィアが、ミロスラフスキーの支援を受けたストレリツィの反乱を率いて帝位を奪取し、ナルイシュキン家の有力者を多数殺害した。ピョートルはこれらの殺害を目撃した。その後、イヴァンが上級ツァーリ、ピョートルが下級ツァーリ、ソフィアが摂政に就任した。実際には、ソフィアは独裁者として絶対的な権力を握り、異母兄弟たちを権力の座から引きずり下ろした。[3] [4]
ピョートルは子供の頃、頭は良かったものの(曖昧)、知識人でもなければ特に洗練された人物でもなかった。身体能力は高く、躁病的なエネルギーに溢れていた彼は、手仕事に情熱を傾けた。特に、航海術と軍儀礼に興味を持ち、貴族や召使の息子である友人たちと模擬部隊を編成し、模擬戦を繰り広げた。成長するにつれ、これらの戦闘は組織化された部隊や隊形、実弾使用など、より複雑なものになっていった。ピョートルが模擬戦を繰り広げた少年たちは、成人すると彼の指揮官や側近の軍事顧問となり、やがてロシア初の精鋭親衛隊であるプレオブラジェンスキー連隊とセミョーノフスキー 連隊の中核を担うことになる。これらの連隊はロシア貴族の中核を担い、若い貴族たちの訓練の場となった。彼らは一般兵として軍隊生活を学び、その後、将校へと昇進していった。[5] [6]
ピョートルが成長するにつれ、ゾフィーは、成長しつつある男子後継者を前に、自身の玉座の不安定さを痛感した。1689年、彼女はストレリツィの支持者たちを扇動して再び反乱を起こし、再び権力を掌握した。陰謀の噂に怯えたピョートルはモスクワから逃亡した。その後の危機的な状況において、総主教と多くの貴族や貴族階級がピョートルを支持した。ストレリツィの大半は動揺し、何の行動も起こさなかったため、ゾフィーは平和的に玉座から退位させられた。こうして、1689年8月、彼はロシアの実質的な統治者として認められた。しかし、17歳という若さで軍儀にはほとんど関心がなく、母ナタリア・ナルイシキナに統治権を譲った。ピョートルが国家の実権を握ったのは、1694年にナタリア・ナルイシキナが死去した後のことである。[ 3] [7]
初期の統治と軍事改革

ピョートルは兵士や水兵を基礎から学び、下士官として勤務した後、士官団に昇進しました。そのため、ピョートルが正式な将軍になったのは1709年のポルタヴァの戦いでの勝利後、そして提督になったのはそれから10年以上後の大北方戦争終結後でした。早くも1694年には、アルハンゲルに造船所を設立し、自ら船一隻を建造しました。ロシアは深刻な専門知識不足に悩まされていましたが、ピョートルはモスクワの駐在官区に赴くことでこの問題を緩和しました。そこでは、帝位から遠く離れた落ち着いた環境で、造船、航海術、軍の編成、要塞の建設といった事柄を詳細に学びました。ピョートルはあらゆる場所に同時に存在し、すべてを自分の目で見たいと考えていました。皇帝としての役割をあまり真剣に受け止めていなかったため、彼と貴族の友人たちはしばしば手の込んだ酒宴やその他のおふざけを繰り広げました。こうした個人的な贅沢を誇示することで、会話や酒を通して友人たちの絆を深めていたのです。しかし同時に、彼は残酷な一面もあり、反乱を鎮圧するために武力を行使することを躊躇せず、必要と判断すれば時には友人を殴ることもあった。[5] [8]
ピョートルは政府機構を掌握すると、政権運営を担う熟練した専門家が明らかに不足していることに気づいた。身分や出身を重視せず、農奴、外国人、聖職者、外国人専門家に加え、通常のボヤール(貴族)など、ロシア帝国の隅々から熟練した専門家を招聘し始めた。こうして彼の政権は、社会階層のあらゆる人々から構成されることになった。その中でも特に目立った人物は、アレクサンドル・ダニロヴィチ・メンシコフだった。彼はピョートルが模擬部隊にいた頃からの幼馴染である。メンシコフはかつて最下級の厩務員だったが、後に昇進し、ピョートルの最も有能な行政官となる。精力的に活動する一方で腐敗も蔓延していたメンシコフは、ロシア政府機構のあらゆる場所に潜伏し、ロシア宮廷の監視下に置かれ、しばしばピョートルの攻撃にさらされながらも、何とか重要な地位を維持していた。[9] [10]
ロシア統治の最高責任者が確固たる地位に就いたピョートルは、軍の抜本的な近代化に着手した。ピョートルは部分的に西洋化された軍隊を引き継ぎ、前任者たちの改革を確固たるものにしようと努めた。軍は毎年収穫期に解散し、ロシア軍の正規兵力はストレリツィのみとなった。ストレリツィは正式にはエリート部隊であったが、ピョートルの時代には世襲制となり、訓練不足で装備も不十分な部隊となっていた。ストレリツィはモスクワに駐屯し、実戦よりも政治に重きを置くようになっていた。[11]
ピョートルはまず、貴族を将校団にしっかりと組み込むことから始めた。自身の経験に基づき、若い貴族は将校団に昇格する前に平兵として勤務させ、功績を挙げた平民も将校に昇格できた。ピョートルは、農作物の栽培であれ戦争であれ、国家への終身の奉仕を信条としていた。そのため、農奴には農場での終身の奉仕から解放される代わりに、軍隊での終身の奉仕を認めた。高齢の退役軍人や障害を持つ退役軍人は、行政機関や予備役に転属させられた。こうして、ピョートルの軍隊は一度入隊すれば、生涯にわたって軍隊に所属することになった。[12]

ピョートルはロシア軍を率いるエリート将校のために新たな学校と訓練場を設立し、多くの兵士を海外に派遣して外国人教師の下で学ばせた。農奴解放の約束だけでは不十分だと考えたピョートルは、50世帯につき1人の兵士を徴兵することから兵士の徴兵を開始した。この徴兵は実に53回も繰り返され、30万人もの新兵が軍隊に加わった。彼は聖職者や敵の脱走兵など、あらゆる利用可能な資源から兵力を引き出すことに長けていた。こうして誕生したロシア軍は、ロシア人色が強く、傭兵に大きく依存していたヨーロッパの軍隊よりもはるかに国家主義的な軍隊であった。 [12]
ピョートルは、高貴な貴族階級の騎兵隊からの脱却を重視したが、それを完全に放棄したわけではなかった。彼は、膝丈ズボン、三角帽子、ロングコートといったヨーロッパ風の服装規定を導入した。また、軍にフリントロック銃を導入し、本来は防御用に設計された銃剣を攻撃に使用した最初の部隊となった。また、攻城砲を大幅に改良・拡張し、後に軽砲も導入した。彼の2つの精鋭親衛隊は、臨時の警察部隊としても機能し、違反行為をした貴族や役人を鎖に繋いで連行するなど、即決権限を持っていた。ピョートルに最も欠けていたのは専門化であった。偵察、小競り合い、襲撃といった軽騎兵の役割を、コサックや遊牧民などの非正規の戦力に頼っていた。彼の本来の騎兵隊はもっぱら竜騎兵であり、竜騎兵は馬に乗るが戦闘時には下馬して徒歩で戦ったからである。[11] [12]
アゾフ包囲戦、大使館、ストレリツィの反乱

1695年、ピョートルは新進気鋭の軍隊を率いて初の大規模作戦を遂行した。1694年に実権を掌握したピョートルは、神聖同盟のトルコとの戦争を引き継いだ。オスマン帝国の支配下で、トルコはアゾフ海河口のクリミア・タタール人の地域を支配していた。トルコとロシアは1568年以来、黒海周辺の地域の支配権を争い、断続的に戦争を続けていた。クリミアを直接奪取しようとする以前の試みは失敗していたため、ピョートルはドン川河口にあるトルコが支配するアゾフ要塞を包囲することを選択した。彼は2部構成の計画を構想していた。まず、陽動作戦として大規模な騎兵隊をドニエプル川下流のトルコの要塞に向けて進軍させる。一方、小規模な歩兵部隊がドン川を下り、1695年の夏にアゾフを包囲した。ピョートル大帝は、彼特有の勇ましさを見せつけ、砲兵として到着した。[13] [14]
ロシア軍はまず、水上でのロシア軍の動きを制限していた重鎖を守る2つの監視塔を占領しなければならなかった。その間にトルコ軍は出撃に成功し、ロシア軍の攻城兵器の多くを鹵獲した。ロシア軍は損失を受け入れ、砦への継続的な砲撃を開始した。しかし、砦は絶えず水路から補給を受けており、消耗戦はトルコ軍よりもピョートル大帝の軍隊に打撃を与えていた。3ヶ月後、ピョートル大帝は撤退を余儀なくされた。[13]
アゾフへの最初の攻撃は茶番劇に終わったものの、ピョートルは粘り強さを見せた。最初の戦いで敗北した原因はトルコの制海権にあると理解し、ドン川上流のヴォロネジに大艦隊の建造を命じた。彼自身も、若い頃に習得した造船技術を駆使して、油断なく作業に取り組んだ。こうして1696年4月、アゾフ北方で30隻の航洋艦と1,000隻以上の輸送船からなる艦隊を進水させた。この艦隊は、ピョートルが最初の包囲戦で率いた兵力の2倍にあたる7万人の歩兵を伴い、トルコからの物資供給を断つことに成功した。1ヶ月の消耗戦の後、2,000人のコサック部隊が砦を襲撃し、撃退されたものの、砦の外部施設の一部を占領した。トルコ人は敗北を認め、1696年7月18日に砦をロシアに明け渡した。[13] [14]
アゾフでの出来事は、ピョートルに海上艦隊の価値を証明した。彼の前任者たちは必要に応じて原始的な艦隊を建造していたが、第二次アゾフ包囲戦がそれらの最初の成功した応用であった。こうして、造船の知識を必要とし、トルコに対抗する強力な連合を発展させたいという願望を抱いたピョートルは、1697年3月に250人のヨーロッパ遠征隊を組織した。ピョートルはピョートル・ミハイロフとして変装して旅をしたが、誰も騙せなかった。身長6フィート8インチの皇帝は文字通り他の人より頭一つ抜きん出ていたが、変装のおかげで宮廷の儀式に参加する必要はなかった。彼はスウェーデン、オーストリア、オランダ、プロイセン、イギリス、ハプスブルク帝国を旅し、大陸中のさまざまな港や工場で労働者として働いた。18か月間、ピョートルはヨーロッパの職人技、特に航海術、そしてヨーロッパ社会全般についてできる限りのことを吸収した。ピョートル大帝の旅は、イタリア通過の予定を前に国内でストレリツィ反乱が発生したという知らせによって中止となり、1698年にロシア産業のために召集した750人の外国人とともにロシアに急送された。使節団の政治的な成果は期待薄だったものの、軍事的な成果は莫大なものであった。[15] [16] [17]

ピョートルはモスクワに戻ると、反乱は既に鎮圧されていた。彼はストレリツィを尋問し、多くの者を拷問にかけ、異母妹であり元皇后であったゾフィーに同情していることを明かさせた。数千人のストレリツィが処刑され、公開処刑された。モスクワ近郊の修道院に流刑されていたゾフィーは、修道女になることを強要された。ピョートルは、ソフィーに対峙することの重大さを思い知らせるため、数百人のストレリツィの遺体を窓の外に吊るした。また、ストレリツィに同情していたエヴドキア・ロプヒナとの結婚生活も終わらせ、彼女も修道女になることを強要した。[13] [15] [17]
大北方戦争
ピョートル大帝のトルコに対する「大同盟」は発展に至らなかったものの、新たな政治情勢の展開により、彼の軍事的関心は急速に北方へと向かった。1697年、スウェーデン王カール11世が崩御した。彼は15歳の息子カール12世に王位を譲った。国王の若さと経験不足に加え、バルト海沿岸の主要港湾を複数保有していたことから、スウェーデン帝国は近隣諸国による分割の格好の標的となった。アゾフ海戦役の成功後も、ピョートル大帝はトルコとの和平交渉を続けていたが、同時にポーランド王アウグスト2世およびデンマーク王フリードリヒ4世との同盟交渉も進めていた。ピョートルは1699年後半に兵力補充のための徴兵を開始し、1700年初頭に開戦が合意された。計画では、ポーランドがリヴォニア南部に進軍し、デンマーク軍がシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のスウェーデン同盟国を攻撃することになっていた。しかし、ピョートルとトルコの交渉は予想以上に長引いたため、1700年1月にアウグスト2世はスウェーデンに宣戦布告し、数ヶ月後にはデンマーク軍もこれに続き、ロシアは傍観者となった。同年7月、ようやくコンスタンティノープル条約が締結され、ピョートルはトルコにおける獲得領土を保全され、スウェーデンとの開戦が可能となった。[18] [19] [20]
初期の損失とナルヴァの戦い
ピョートルが参戦した頃には、同盟はすでに崩壊しつつあった。カール12世は類まれな軍事的才能と、敵が予想していたよりもはるかに優れた指揮官であることを証明した。1700年7月、カール12世はこの上ない勇気で1万5千人の兵士と共に海峡を渡ってデンマークに向かい、戦闘をデンマーク領土の中心部にまで持ち込んだ。デンマーク軍は完全に敗北し、1ヶ月以内に降伏した。これを知らないピョートルは、1700年8月にスウェーデンに宣戦布告した。ピョートルは3万5千人の軍を率いて、フィンランド湾のすぐ南、ナルヴァ川の岸にあるナルヴァ市を素早く包囲した。ピョートルは包囲網を組織したが、すぐにカール12世の救援活動のための援軍を組織するために出発した(そして結果的に、自らは危険から逃れた)。ポーランドとロシアのどちらかを選んだカール12世は、ロシアの方がより危険な脅威だと考え、11月に約11,000人の小さな軍隊を率いて包囲された都市に侵入した。[18] [19] [20]
_-_Nationalmuseum_-_18638.tif/lossy-page1-440px-Narva_(Gustaf_Cederström)_-_Nationalmuseum_-_18638.tif.jpg)
ロシア軍は3対1の数的優位に立っていたため、カール12世が援軍を待って攻撃してくると予想した。しかし、これまた大胆な行動として、吹雪に紛れたスウェーデン軍はロシア軍戦線への奇襲攻撃を選択した。油断していたスウェーデン軍は手薄になり、突破されやすく、熟練のスウェーデン軍に包囲されたため、戦闘はたちまち敗走に転じ、パニックに陥ったロシア軍は極寒のナルヴァ川を泳いで渡ろうとしたが、多くが凍える水の中で溺死した。残りのロシア軍は容易に掃討された。ピョートルの精鋭部隊と1個軽歩兵旅団の3個グループのみが、補給車を間に合わせの防御として使い、まともな戦闘撤退を行った。後にナルヴァの戦いと呼ばれるようになったこの戦いは、ピョートルの若い軍にとって大敗となり、ロシア軍の大半が壊滅し、攻城兵器のほぼすべてが鹵獲された。スウェーデン軍の死傷者はわずか700人であったが、ロシア軍は6,000人以上が死亡し、さらに20,000人が捕虜となった。[18] [19] [21]
軍の再建、リヴォニア遠征、そしてポーランドの敗北
戦闘後、ロシア軍が壊滅したことで、カール12世はロシアはもはや脅威ではなくなったと判断し、ロシアを追撃する代わりに南下してポーランドと対峙した。歴史家たちは、カール12世が壊滅したロシアの敵国への追撃を続行すべきだったかどうかについて、いまだに議論を続けている。もしカール12世がピョートル1世の追撃を選んでいたら、早期の勝利を収め、戦争の帰趨を変えていた可能性も否定できない。いずれにせよ、1701年夏、ザクセン軍によるリガ包囲を突破したカール12世は、ポーランド・リトアニア共和国へと侵入した。ポーランド軍は6年間抵抗したが、フラウシュタットの戦いでスウェーデン軍が再び圧倒的な戦力差で勝利したことで、ついに戦争から撤退を余儀なくされた。アウグスト2世は退位させられ、より攻撃的でないスタニスワフ・レシュチニスキが後を継ぎ、ポーランドはロシアとの同盟を解消した。[18] [19] [22]
6年間の猶予はピョートル大帝にとって決定的な決定打となった。持ち前の活力で、彼は速やかに軍を立て直した。ロシアの貴族階級から新たな将校を引き抜き、海外から雇用した。ナルヴァの戦いで失われた兵士の補充は、強引な徴兵によって行われた。ピョートルは新たな戦役の資金を捻出するため、あらゆる手段を講じた。増税、新設、塩貿易の独占、通貨の切り下げなど、あらゆる手段を講じて資金を調達した。最も悪名高いのは、髭税の導入と、教会に鐘を溶かして大砲を作らせたことである。新兵が新たな武器を必要とするにつれ、資金の多くはロシアの金属加工産業に投入され、金属加工産業の量と質が大幅に向上し、ひいてはロシアの武器の質も向上した。北方戦争は長距離戦であったため、ピョートルは騎兵隊も大規模に編成した。[18] [19] [20]
ピョートルは、この新生軍を鍛え直し、バルト海沿岸のスウェーデン領リヴォニアとイングリアを攻撃した。カール12世が南下したことを確信すると、元帥ボリス・シェレメーテフに防御の手薄な植民地への攻撃を命じ、同時に南にも師団を派遣してカール12世の進軍を遅らせ、ピョートルが軍の修復を終える時間を与えた。1701年末、シェレメーテフはリヴォニアのエラストフェルで、数で圧倒的に劣るスウェーデン軍と遭遇し、完勝した。そして1702年7月、フンメルスホフでもこの偉業を再現した。ロシア遠征における最初の意義深い勝利となったこの2度の勝利は、ナルヴァでの大惨事の後、ロシアの士気を高めるのに役立った。ピョートルはその後シェレメーテフをイングリアに派遣し、ラドガ湖地峡のスウェーデン軍を掃討させた。 1702年10月、スウェーデン軍はノーテボリ要塞を陥落させた。1703年5月、ピョートル1世はニーンシャンツ要塞を占領した。彼はネヴァ川河口の湿地帯に囲まれた一帯を要塞サンクトペテルブルクの建設地とした。当初はスウェーデン軍に対する前哨基地であり、ピョートル1世の「西への窓」であったこの要塞は、後にロシア最大かつ最も重要な人口密集地の一つへと発展し、ピョートル1世の治世下、ロシアの首都となった。[18] [19] [23]
シェレメーチェフの成功は1704年まで続いた。内陸の主要都市ドルパトは1704年7月に陥落し、その城壁はピョートル1世の新型砲兵隊によって突破された。この砲兵隊はその後、第二次ナルヴァの戦いで極めて重要な役割を果たすことになる。この時は兵力が多く、カール12世がポーランドに遠く離れていたため、ピョートル1世は多くの死傷者を出したにもかかわらず、ナルヴァを占領することができた。ナルヴァの指揮官は名誉ある降伏の理想を破って降伏を拒否し、ロシア軍がナルヴァを突破すると、残っていたスウェーデン軍は虐殺された。全体として、国内でのスウェーデン軍の多くの損失は、すでに戦争の影響でひっ迫していたスウェーデン経済にさらに大きな打撃を与えた。ピョートル1世はまた、南方の艦隊に似た新しい艦隊をバルト海に急いで編成し[18] [19]、その頃1705年にはロシア初の海軍部隊を正式に編成した。
カール12世は1704年に自らの候補者をポーランド王位継承者に選出し、その後3年間を、故郷ザクセンに向けて西へ逃亡するアウグスト2世の追撃に費やした。カール12世は1706年初頭、グロドノに陣取るピョートルの主力軍と遭遇した。外国の領土で精鋭部隊と遭遇することを望まなかったピョートルは、軍に撤退を命じたが、可能な限りスウェーデン軍を妨害するため、小規模な部隊をその地域に残した。メンシコフ率いる撤退隊列の一部は、カリシュで小規模なスウェーデン軍分遣隊と遭遇し、続く戦闘でこれを完敗した。しかし、1707年までにカール12世はついにアウグスト2世を追跡して廃位させ、ポーランド遠征を終わらせ、ロシアへの注意を再び集中させた。[18] [19]
国内の反乱とウクライナへの迂回
わずか5万人の兵士を擁するカール12世は、ロシア全土を征服することなど夢にも思っていませんでした。彼はむしろ、ピョートル大帝が祖国にかけた戦時中の強大な圧力と、大貴族階級の不満が相まって、望んでいた勝利を得られると考えたのです。カール12世にとってこの決断には確固たる根拠がありました。ピョートル大帝の強圧的な課税が国王に対する不満を高めていたからです。1705年の夏、無名の修道士とストレリツィの一員が、貴族階級の破壊的な影響力と外国の影響に反発し、アストラハンで反乱を起こしました。この反乱は1707年3月に血なまぐさい鎮圧を受けました。同様に、1705年にはトルコ系バシキール人の反乱も起こりましたが、これも同様の理由で鎮圧されました。この反乱は1711年まで鎮圧されませんでした。[18] [19]
より深刻だったのは1707年のブラヴィン反乱である。逃亡者に関する政府の立場に反対し、排外主義の影響を受けたドン・コサックの指導者コンラト・ブラヴィンが反乱を起こした。これはロシアとコサックの緊張関係の中で起きた最初の反乱ではなかったが、同様の傾向を辿った。反乱は南部に広く広がり、最高潮時には10万人もの兵士が参加したとされるが、組織化されておらず、指揮も不十分だった。反乱は前線から撤退したロシア軍によって組織的に鎮圧されたが、ブラヴィンの部下の間で不和が広がり、彼は1708年7月に自殺した。反乱の残りの部分は1709年までに鎮圧された。[18] [19] [24]

いずれにせよ、1708年の夏までにカール大帝はリトアニアに陣取り、モスクワへ直結する街道に面していた。しかし、彼の目の前にはロシア軍によって意図的に荒廃させられ、スモレンスク要塞という強固な要塞に守られた荒涼としたツンドラが広がっていた。彼の軍隊はロシアの軽装歩兵の攻撃に絶えず晒され、増援部隊もまだ到着中だった。外交的には、ピョートル大帝はサンクトペテルブルクとネヴァ川を除く占領地の全てを返還するという条件を提示したものの、カール大帝はスウェーデンの勝利以外は受け入れなかった。肥沃でまだ戦争の影響を受けていないウクライナは南に位置していた。またカール大帝は、ピョートル大帝の下でウクライナの大部分を支配していたコサックの ヘトマン、 イヴァン・マゼパが、密かにツァーリに対する陰謀を企てていることも知っていた。こうしてスウェーデン軍は南に進軍し、ウクライナに侵攻した。[18] [19] [25]
歴史家たちは今でも直接攻撃が成功したかどうかについて議論しているが、ウクライナの陽動作戦はカール大帝にとって悲惨な結果となった。 1708年秋、リガを出たカール大帝の長い荷物列車は1万2000人の増援部隊とともに、機敏に動きまわるロシア騎兵隊に捕まった。ロシア騎兵隊は増援部隊と補給品を妨害し、続くレスナヤの戦いではピョートル大帝の竜騎兵がスウェーデン軍と戦い、膠着状態に陥った。ロシア軍の兵力増加に直面して、スウェーデン軍は補給品を燃やし、大砲を地中に埋め、カール大帝の主力軍に襲撃せざるを得なかった。1万2000人の兵士のうち、実際にカール大帝のもとにたどり着いたのはわずか6000人で、補給品はほとんどなかった。兵士は増える一方補給品はなくなり、カール大帝の食糧問題はさらに悪化した。コサックの援軍の構想も幻に終わった。マゼパはスウェーデンに亡命したものの、3,000人の兵力しか引き連れてこなかった。報復として、メンシコフはバトゥリンを略奪・破壊し、6,000人以上の男女子供を虐殺し、マゼパの首都を完全に破壊した。他の者は誰も亡命を敢えてせず、ウクライナはピョートル大帝の支配下に置かれ続けた。[18] [19] [25]
ポルタヴァの戦い
カールには時間と選択肢が尽きつつあった。1708年から1709年の冬は、ウクライナに駐屯していたスウェーデン軍にとって悲惨な冬となり、翌春、カールはロシアの小さな要塞ポルタヴァの包囲戦で泥沼にはまった。ピョートルはスウェーデン軍との会戦に依然として警戒を抱き、この小さな要塞を救出するため、要塞化された陣地を通ってゆっくりと軍を進めた。カールはロシア軍を避けてポルタヴァを占領するのは間に合わないと予見していたが、兵力の減少、補給不足、疲労にもかかわらず、2万5千の熟練兵が4万人のロシア軍を戦闘で破り、最終的にスウェーデンの勝利で戦争を終わらせることができると確信していた。一方、ピョートルには忍耐する余裕があった。スウェーデン軍は支援や増援から遠く離れた場所に孤立しており、日に日に兵力を失っていたからである。ロシア軍の北方陣地とポルタヴァを結ぶ最短経路は、危険な森と沼地を通るものだった。そのため、ピョートルはスウェーデン軍の攻撃が左翼を迂回し、西へ向かった後、北へ開けた土地を通ってロシア軍に向かってくることを予見した。ピョートルは、このスウェーデン軍の突撃に面して一列に6つの土塁を築き、後にさらに4つの堡塁を南にT字型に拡張した。[26] [27]

6月下旬、攻撃の準備中にカール12世は足を撃たれた。そのため、1709年7月8日の朝 ( NS ) に突撃が開始されると、彼は担架で戦いを率いた。スウェーデン軍はピョートル大帝の満足のいくように、まさに彼の予想通りに動いた。カール大帝はピョートル大帝が掘った堡塁をよく知っており、泥沼にはまって奇襲のチャンスを失うのを避けるため、できるだけ早くそこを通り過ぎて、その結果生じる損失を受け入れ、移動を速めるために大砲の大半を残してでも行こうと考えた。しかし、カール大帝はピョートル大帝が戦闘前夜に掘った追加の4つの土塁については知らなかった。この新たな問題を克服するため、カール大帝は貴重な時間を費やして、一斉射撃に最適な射撃線から、移動は速いが射撃準備の整っていない縦隊へと部隊を再配置したが、これは時間のかかる動きであり、当初期待していた奇襲のチャンスは失われてしまった。ピョートルがカール大帝の動きに気づいたことで、計画はたちまち頓挫した。スウェーデン軍の多くは堡塁との戦闘に巻き込まれ、両軍の砲火による煙と、主力部隊の前方でロシアとスウェーデンの騎兵隊が交戦する騒音によって、ピョートルは軍を効果的に組織化することができなかった。カール大帝は軍を西へ撤退させ、ロシア軍主力陣地脇の低木地帯で再び戦線を組むよう再編した。[26] [27]
一方、ピョートルも準備を進め、騎兵隊を北へ移動させてスウェーデン軍左翼に進攻させ、部隊を縦隊配置した。カール大帝は攻撃の重責を担い、ロシア軍の戦列を崩すため、再び部隊の堅実さと経験に頼ることとした。続く攻撃はスウェーデン軍右翼が指揮し、以前の戦闘と同様に、熟練兵はロシア軍を圧倒し、後退させ、支援砲も奪取した。しかし、ロシア軍の集中砲火はスウェーデン軍戦列の中央に穴を開け、この隙を突くことができたロシア軍はそこから突撃し、スウェーデン軍の縦隊を分断した。スウェーデン軍の戦列は崩壊し、散り散りになり、1万人のスウェーデン兵が戦死または捕虜となった。残りの大部分はドニエプル川岸でメンシコフに捕らえられた。カール大帝自身を含む数百人だけが南へ逃れ、トルコに亡命した。[26] [28]
ポルタヴァの戦いは、ロシア史上最も決定的な勝利の一つであった。ポルタヴァの戦いとそれに続く降伏の結果、スウェーデン軍の大半は壊滅し、スウェーデンは攻撃に対して無防備な状態となった。国内においては、この勝利はピョートルに政治的資本と戦争の小康状態をもたらし、彼は国内問題の処理に必要な時間を確保した。実際、もしピョートルが戦いに敗れていたならば、ツァーリの改革への反対勢力が新ツァーリへの積極的な支持へと転じていた可能性もあった。ポルタヴァの戦いは、ロシア軍がどれほどの進歩を遂げたかを示している。実に、わずか9年前、ロシア軍はスウェーデン軍との戦闘で、数的優位に立つスウェーデン軍にほぼ壊滅させられていたのである。ピョートル大帝はこの戦いの結末の重要性を十分に認識し、捕虜となったスウェーデン軍に「教訓」を与えたことに感謝の意を表した。しかし、この戦いは戦争の勝利にはつながらなかった。戦争はまだ半分も終わっていなかったのである。[18] [26] [27]
オスマン帝国の迂回路

オスマン帝国はピョートルの軍事的利益を懸念していたものの、戦争には介入しなかった。しかし、フランスとカール12世の圧力を受け、当時亡命中のカール12世をかくまっていたオスマン帝国は、1710年にピョートルに宣戦布告した。ポルタヴァの戦いで大北方戦争が一時的に小康状態にあったピョートルは、南下を急いだ。彼は多くの兵と、最も頼りになる将軍シェレメーチェフを率いて、ロシア全土を南下させ、この新たな戦争に臨んだ。ロシアがオスマン帝国と戦ったのはこれが初めてではなく、またこれが最後でもなかった。しかし、以前の戦争と同様に、ピョートルは距離と二つの戦争を同時に戦わなければならないという重圧を過小評価していた。ピョートルは、トルコの支配下にあったキリスト教地域であるワラキアとモルダヴィアに対し、オスマン帝国の支配者に対する反乱を積極的に促した最初の人物であった。 [29]
1711年の春までにピョートルは準備を整えた。彼はキエフから軍を進め、黒海を大きく迂回してポーランドを南下し、ドニエストル川を渡ってモルダビアに入り、トルコの支配から切り離すことを目指した。しかし実際には、この作戦は惨敗に終わった。4万のロシア軍は長距離の移動に阻まれ、代わりに13万のトルコ軍によってプルト川で包囲されたのである。唯一の大きな戦闘で、ロシア軍は集中したロシアの火力に慣れていないオスマン帝国をうまく食い止めたが、ピョートルは包囲され、優勢なトルコ軍に直面していたため、戦いは本当に絶望的だった。結果として得られた条約は、ロシア軍が壊滅の危機に瀕していたことを考えると驚くほど寛大なものであった。ピョートルはアゾフを失い、南方艦隊を放棄せざるを得なくなり、ポーランドの問題に干渉しないと約束し、カール12世のスウェーデンへの安全な航路を保証した。その代わりに、ピョートルは状況から抜け出すことができ、大北方戦争で優位な立場を維持し続けました。[29]
スウェーデンの最終的な敗北とその後
オスマン帝国との問題が解決したので、ピョートルは再び北方に目を向け、バルト海沿岸のスウェーデン帝国の解体に取り組んだ。 1710年にはヴィボー、リガ、レヴァルを占領した。カール12世が廃位されると、再びスウェーデンに対する同盟軍が結成された。ピョートルは軍を分割し、南バルト海の同盟軍の支援と東部の攻撃に振り分けた。現在のエストニアとリヴォニアは守りが弱く、すぐに陥落した。次にピョートルは北上し、 1713年にフィンランドに侵攻した。一方、カール12世は匿名で旅を続け、1714年にスウェーデンに戻った。帝国が崩壊し、失うものがなくなったスウェーデンは戦いを続けた。海上では、勝利がまだ不確定だった頃には役に立たなかった既成のロシア艦隊が、ロシアの勝利を固める上でその真価を発揮していた。 1714年のガングート、 1719年のオーゼル、 1720年のグレンガムでの勝利により、ピョートルは制海権を獲得した。[18] [29] [30]
ピョートルはスウェーデン帝国を解体しつつも、軍の改革と強化を続けた。当時のロシアの行政制度であるプリカーズィは、管轄権が重複し権力分立が欠如した、時代遅れで混乱した統治形態であった。1717年、ピョートルはこれをスウェーデン式に倣ったコレッギア(「カレッジ」)に置き換え始めた。ピョートルは原則として、ロシア人兵士と外国人従者を同数ずつ雇用した。プリカーズィとは異なり、カレッジは構成員の合意なしには決定を下すことができなかった。いわゆる「委員会による統治」は、恣意的な決定や腐敗を抑制するのに役立った。最初に設立された二つのカレッジには、陸軍を統括しメンシコフが率いた陸軍大学と、海軍を統括しフョードル・アプラクシン提督が率いた海軍本部があった。[31] [32]
ロシアの急速な台頭と戦争における長期にわたる勝利は、ヨーロッパ全土に不安の波を引き起こした。こうした不安を鎮めるため、ピョートルは1717年にパリを訪れた。この旅は決定的な成果には至らなかったものの(フランスは介入を避けると約束したのみ)、ピョートルに西ヨーロッパを視察する機会を与えた。1718年後半、カール12世自身も小規模な戦闘で頭部を撃ち抜かれたが、これは恐らく自軍の兵士によるものだった。疲弊したスウェーデンはロシアの巨大勢力に対抗する同盟国を探したが、その努力は実を結ばなかった。ロシア軍は定期的にバルト海を渡り、スウェーデン本土を襲撃し、ストックホルム郊外にまで達したため、スウェーデンはついに敗北を認めた。[29]
結果として締結されたニスタット条約において、ピョートルはスウェーデンに対して極めて寛大な態度を示しました(誰がそう呼んだのでしょうか?) 。エストニア、リヴォニア、イングリア、そしてフィンランド南部の一部(特にサンクトペテルブルク)をスウェーデンに返還し、フィンランドの大部分をスウェーデンに返還し、銀200万リクスダラーを支払うという条件で返還しました。この戦争はヨーロッパの勢力均衡を決定的に変化させるものであったため、ピョートルには寛大な態度を取る余裕がありました。スウェーデン帝国は分割され、大国としての地位はロシアに奪われました。これらの勝利を祝してピョートルは皇帝の称号を授かり、こうしてロシア帝国が建国されました。北方戦争によってロシアは北欧における支配的な勢力となり、バルト海を強固に支配し、「西への窓」となりました。この戦争は、ポーランドに対するロシアの立場をも有利にしました。この状況は、ずっと後になってエカチェリーナ2世の治世下、第一次ポーランド分割によって頂点に達しました。最終的に、ロシアはヨーロッパのもう一つの列強であるドイツと直接接触することになった。ピョートル自身も国民的英雄となり、当時の文献ではヘラクレス、サムソン、ダビデに比喩された。[18]
ペルシャ遠征と最終的な軍事改革

ピョートル大帝の治世下における最後の戦争は、長期にわたる大北方戦争ではなかった。ピョートル大帝は南部で最後の短い戦争を経験した。1722年、ピョートル大帝はジョージアおよびアルメニアと同盟を結び、衰退しつつあったサファヴィー朝ペルシアの領土を奪取し、オスマン帝国の侵攻を阻止しようとした。宣戦布告後、ピョートル大帝はカスピ海艦隊の建造を命じ、ヴォルガ川を下り、陸海合同作戦を指揮してデルベントを占領したが、補給のためアストラハンへ戻ることを余儀なくされた。ロシア軍はピョートル大帝の介入なく、ほとんど抵抗を受けずに戦い続け、同年末にレシュトを、翌年にはバクーを占領したが、ペルシアは最終的に和平を申し出た。[32]
1719年11月、スウェーデンとハノーファーの間でストックホルム条約が締結された。スウェーデンは財政支援と海軍支援と引き換えに、ブレーメンとフェルデンをホルシュタインに譲渡した。ハノーファー選帝侯はゲオルク1世であった。その後、1720年1月から2月にかけて、スウェーデンとブランデンブルクの間で別のストックホルム条約が締結された。スウェーデンは金銭と引き換えに、シュテッティン、南ポメラニア、ウーゼドム島、ヴォリン島を割譲した。大北方戦争終結前に、スウェーデンとデンマークの間でフレドリクスボー条約が締結され、スウェーデンは軍事利用のための納税免除を放棄した。また、ホルシュタイン=ゴットルプも放棄した。そして戦争が進む中、1721年8月から9月にかけて、スウェーデンとロシアの間でニャスタッド条約が締結された。スウェーデンはリヴォニア、エストニア、イングリアを割譲し、ロシアはケクスホルムとカレリアの一部を除くフィンランドを返還した。[33]
ピョートルは1725年に死去する前に、国内に最後の重要な要素をもたらした。それが階級表である。1722年に導入されたこの表は、陸軍、海軍、官僚、宮廷の4大政府部門を14の主要階級に体系化した。これにより政府職が標準化され、士官は自分たちの相対的な重要性を正確に判断できるようになった。一般人用の表はなかった。この表はピョートルが貴族の任命を行うとともにロシア軍の職を編成する方法であった。ピョートルは新たな大貴族を任命せず、実際の技能よりも世襲を重視する古い名誉規範であるメスニチェストヴォは1682年に当然ながら廃止されていた。ピョートルは以前にも臨時の任命に頼っていたが、大北方戦争の頃にはこれがすぐに煩雑になることが判明し、変更が必要となった。この表で一定の地位に達した者には個人貴族の称号が与えられ、また、功績に応じて12位または8位に達した者には世襲貴族の称号が与えられました。これは功績への報奨であると同時に、ピョートル大帝の貴族としての地位を満足させるものでした。この表は、若干の修正を加えられながらも、1917年に廃止されるまで使用され続けました。[32] [34] [35]
エカチェリーナ1世とピョートル2世

ピョートルの死後、帝位継承者の明確な候補者は残されなかった。息子のアレクセイは内気で書物好きの人物で、帝位にはほとんど関心がなく、ピョートルの統治を覆そうとする反乱の標的として常に目立っていた。アレクセイは1714年に帝位継承権を放棄したが、これはピョートルを激怒させた。アレクセイは捕らえられ、拷問を受け、1718年に負傷により死亡した。ピョートルの他の男子は成人まで生き延びなかった。さらに1722年には、後継者の指名は皇帝の判断であり、系図の問題ではないと宣言した。[36] [37]
ピョートルは1724年に2番目の妻エカテリーナをロシア皇后に即位させ、彼女の帝位継承権を強め、ピョートルの孫ピョートル・アレクセーエヴィチと並んで彼女を有力候補とした。当時子供だったピョートルは旧貴族の支持を受け、一方エカテリーナは新階級、特にメンシコフの支持を得た。エカテリーナが夫の後の軍事作戦に同行した際に行動を共にしたプレオブラジェンスキー近衛連隊とセミョーノフスキー近衛連隊は、エカテリーナへの支持を示すことでこの問題を解決した。反対派は崩壊し、エカテリーナ1世が新ツァーリに指名された。この2つの近衛連隊は、この点でかつてのストレリツィに似ており、今後こうした政治問題の多くを決定することになる。エカテリーナは統治の業務のほとんどを側近のメンシコフに任せていた。彼女の最も重要な貢献は、皇帝の顧問団(メンシコフもその一員であった)である枢密院の設立と、2つの近衛連隊の育成であった。[36] [37]
エカチェリーナ2世は長くは統治せず、1727年に崩御した。2人の娘が生き残ったものの、メンシコフはピョートルの孫であるピョートル2世を新皇帝に即位させようと画策した。ピョートル2世はまだ12歳にもなっていなかったため、メンシコフは積極的に自身の地位を強化しようと画策した。彼はピョートルを自分の娘と結婚させて自分の家に迎え入れ、枢密院における反対派を着実に弱体化させ始めた。しかし、メンシコフは結局、権力を掌握しすぎた。彼の大胆な権力掌握はロシア貴族を警戒させ、メンシコフへの嫌悪感を募らせていたピョートルは、代わりにイヴァン・ドルゴルーコフ公と同盟を結んだ。メンシコフはシベリアに流刑され、1729年にそこで亡くなった。ピョートル2世自身も1730年に天然痘で亡くなり、再び後継者はいなかった。[36] [37]
エカチェリーナ2世とピョートル2世の短い治世は、ロシア陸軍と海軍の緩やかな衰退を特徴としていた。ピョートルの過酷な税制は軽減され、軍隊は解散させられ、海軍は停泊したまま衰退した。1730年代と1740年代には、陸軍は様々な小規模な作戦のために再び増強されたが、ロシア海軍の衰退傾向は何世紀にもわたって覆されることはなかった。[36] [37]
アンナ1世
.jpg/440px-Louis_Caravaque,_Portrait_of_Empress_Anna_Ioannovna_(1730).jpg)
枢密院によって次期帝位継承者として選ばれたのは、ピョートル大帝の亡き弟イヴァン5世の娘、アンナ・イワノヴナであった。枢密院が彼女を選んだ主な理由は、彼女が女性であり未亡人であることから政治的に脆弱であったことであり、枢密院はこれを積極的に利用しようとした。枢密院は、彼女が税の制定・改正、宣戦布告、軍の統制、領地の付与・剥奪、政府高官への任命権を放棄する場合にのみ、彼女の戴冠を承認すると宣言した。要するに、枢密院は皇帝の権力を骨抜きにし、ロシア帝国を事実上の寡頭制にすることを目指していたのである。しかし、この計画は実現しなかった。ロシア貴族は、宮廷衛兵連隊と同様に、権力の移行の可能性に恐怖し、アンナは結束した力で自身に課せられた制約を破り、枢密院を完全に解散させたのである。[36] [37]
アンナはクールラント時代からロシア政府内に友人がほとんどおらず、また一度は彼女を無視しようとしたロシア貴族への強い不信感も抱いていた。そのため、彼女は支配者のほとんどを外国人、特にバルト系ドイツ人で固め、寵臣エルンスト・ヨハン・フォン・ビロンが率いた。彼女はしばしば、実際の経験の有無に関わらず寵臣を重要な地位に選出したため、多くの人が私財と影響力を蓄積しようとし、腐敗が蔓延した。とはいえ、アンドレイ・オステルマン率いる外務省とブルクハルト・クリストフ・フォン・ミュンニヒ率いる陸軍は外国の影響から大きな利益を得た。この2人はかつてピョートル大帝の支配下にあったことは注目に値する。宮殿衛兵は彼女の帝位継承を助けたが、それでもアンナは彼らの力に対抗するため、第三のイズマイロフスキー連隊を創設した。 [36] [37]
ミュンニヒの改革

精力的に権力を貪欲に求めるミュンニヒは、ロシアに渡りピョートル大帝の遠征に技術者として従軍する前に、スペイン継承戦争で経験を積んでいた。ロシア貴族から独立したドイツ代表として、彼はアンナに訴え、その訴えを糧にミュンニヒは1732年に陸軍大学総長に就任した。ミュンニヒはより小規模で強力な軍隊の育成に尽力した。彼は不要な部隊を解散させ、財政管理において数々の改善策を導入した一方で、海軍は停泊したまま腐らせるという現状を維持した。彼は若い貴族を兵役に就かせるための士官候補生団を設立し、ピョートル大帝が定めた下級兵役義務を事実上廃止した。また、兵役義務を25年に短縮した。これは依然として過酷な要求ではあったが、ピョートル大帝が理論上は終身在職としていたモデルよりははるかに良いものであった。[37]
ミュニヒはまた、ロシア軍の柔軟性と効率性を高めることにも努めた。歩兵部隊あたりの砲兵の数を増やし、擲弾兵を再配分して効率を高めた。ミュニヒはロシア騎兵にも重要な変更をもたらした。ミュニヒ以前のロシア騎兵のほとんどは竜騎兵であり、騎兵隊に沿って移動しながらも徒歩で戦っていた。ピョートルはコサックも所有し、敵軍の襲撃、妨害、監視、偵察という伝統的な軽騎兵の役割を果たした。ミュニヒは、非正規のコサックを正規軍で補完するため、軽騎兵連隊(主に東欧の外国人で構成された軽騎兵)を導入した。さらに深刻だったのは、突撃を行う重騎兵連隊が明らかに不足していたことである。ミュンニヒは、この役割を担うため、精鋭近衛騎兵連隊3個(近衛歩兵連隊3個に相当)と重装甲騎兵連隊数個(彼らが着用していた重い胸当て、または胸甲にちなんで名付けられた)を導入した。これらの新連隊は、当時ロシアで最も重い馬に乗っていた。[37]
ポーランド継承戦争
ピョートル大帝の死後、ロシアの軍事力の最初の試練となったのは、それほど困難な戦争ではなかったものの、 1733年から1734年にかけてのポーランド継承戦争であった。ピョートル大帝の旧盟友であったポーランド国王アウグスト2世の死後、新国王を選出する選挙が行われた。ロシアはアウグスト3世の息子であるアウグスト3世が父の跡を継ぐと予想していたが、1733年秋、選挙の結果はフランスの支援を受けたスタニスワフ・レシュチニスキに決まった。レシュチニスキは大北方戦争でカール12世の傀儡国王を務めていた人物である。ロシアとオーストリア帝国は共に、フランスの支援を受けたポーランド国王は受け入れられないという点で一致し、スタニスワフに代えて幼いアウグストを即位させるべく介入した。[38] [39]
こうして1733年、亡命中のアイルランド将軍ピーター・レイシー率いるロシア軍がスタニスワフを廃位すべくポーランドに侵攻した。レイシーはアウグスト3世を国王とする第二次選挙を綿密に計画し、逃亡中のスタニスワフを1734年初頭にダンツィヒまで追撃した後、ミュンニヒに政権を委ねた。フランスは遠く離れた同盟国(戦争中最大のフランス軍はバルト海沖に展開し、わずか2,000人で構成されていた)を支援することができず、代わりにオーストリアを攻撃することで自国を慰め、ラインラントおよびイタリア全土で大規模な戦闘を引き起こした。一方ポーランドでは、ダンツィヒの包囲を破ることができなかったスタニスワフがフランスに逃亡し、ロシアはアウグスト3世を国王として再確認することとなった。ポーランドはロシアの緩衝国として確認され、その後数十年にわたりロシア軍は意のままにポーランドに介入することになる。レイシーはオーストリアとフランスの間で続いていた戦争に向けて西へ軍隊を率いたが、ウィーン条約が批准され短期間の戦争が終結するまで実戦には参加しなかった。[38] [39]
1735年から1739年の露土戦争
ミュンニヒは部隊がポーランドから帰還すると、すぐにロシアの宿敵トルコとそのクリミア・タタール人領土に対する拡張主義的な軍事行動の計画を開始した。クリミアによるロシア領への絶え間ない襲撃とオスマン帝国がペルシャとの戦争に巻き込まれていたことが、ミュンニヒを刺激した。ミュンニヒはますます精鋭化するロシア軍がオスマン帝国のどんな軍をも打ち破れると確信し、オスマン帝国の首都イスタンブールを最終的に占領するという野心的な軍事行動を計画した。この計画において、彼は多くの戦略的障害に直面した。アゾフの主要要塞は東に位置しアゾフ海へのアクセスを遮断しており、クリミア・タタール人は黒海の北岸全体を支配していた。長距離であるため、ロシア軍は長い補給線を必要とするだろうが、どの軍事行動もこの補給線に対する行動によって遮断される危険にさらされていた。さらに、この地域は黒海に流れ込むいくつかの主要な河川によって守られており、それぞれの河川沿いにトルコの要塞が築かれていた。[40] [41]

戦争は1735年にロシア軍がクリミア半島を襲撃して失敗したことで始まったが、最初の本格的な作戦は1736年まで行われなかった。ミュンニヒはロシア軍を2つのグループに分け、彼の指揮下にある主力軍はクリミア河口のペレコープ攻撃を目指し、ラシー率いる小規模な分遣隊はアゾフ海へ進軍した。ミュンニヒは1736年5月にペレコープのタタール軍の防衛線を難なく突破したが、敵を戦闘に引きずり込むことはできなかった。ほとんどの兵士が山岳地帯へ逃げ込んだためである。ミュンニヒは地方の略奪で満足したが、部隊は渇きと病気に苦しんだため、秋に撤退した。ラシーの攻撃ははるかに成功した。要塞を包囲して間もなく火薬庫が爆発し、守備隊は壊滅した。アゾフ海は6月に降伏した。[40] [41]
ロシアの突然の勢力拡大に勇気づけられ、またいくぶんか警戒もしたオーストリアは、1736年にトルコ領バルカン半島の一部を自国で掌握しようと参戦した。アゾフがロシアの支配下に入ったことで、作戦は黒海に沿って東へ移動した。1737年、ラシーは4万人の兵を率いて再びクリミアに侵入し(ペレコープを通らずに狭い西部の砂州を越えて)、再びこの地域を破壊し略奪したが、前年のミュンニヒの攻撃と同様に病気と渇きに苦しみ撤退を余儀なくされた。一方、ミュンニヒと8万人の兵は南ブグ川を渡り、トルコの主要要塞オチャキフの上流に至り、引き返してオチャキフを包囲した。砲撃中に偶然当たった弾が要塞の火薬庫を再び破裂させ、オチャキフは間もなくロシア軍に降伏した。[40] [41]

1738年はロシアにとって決着のつかない年となった。ラシーは再びクリミアに侵攻したが、またしても永続的な成果はあげられなかった。ミュニヒは10万人の兵士を率いて黒海西岸を南下しドニエストル川を渡ったが、またしても病気(今回はペスト)や補給不足、トルコ軍の掩蔽部隊による嫌がらせにより、すぐに北へ撤退を余儀なくされた。この問題を回避するため、1739年、ミュニヒは黒海西岸のさらに西側を切り開き、ポーランドを迂回してプルート川に到着した。しかし、状況は1711年のピョートル大帝の軍事作戦の再現となった。またしてもロシア軍の補給線はトルコ軍の包囲によって遮断された。必要ならこの罠を突破できると確信したミュニヒは、1737年8月28日(新共同訳)、スタヴチャニのトルコ軍主力野営地を攻撃した。ミュニヒはトルコ軍右翼に陽動攻撃を仕掛け、続いて右翼に軍隊を集結させてトルコ軍を突破し、トルコ軍の野営地、砲兵隊、補給物資、そしてドニエストル川上流のホティン要塞を占領した。 [40] [41]
それでも、この戦いは空虚な勝利に終わった。オーストリアはその年にオスマン帝国と和平を結び、同盟国を失い更なる利益も不確かなロシアは、ニシュ条約に署名して戦争を終結させることを決意した。ロシア軍は疫病に甚大な被害を受け、戦争に費やした兵力と資金の全てに対し、ロシアが獲得したのは黒海北部の人口のまばらな草原と、かつての戦利品であるアゾフ海だけであり、しかも要塞化はしないという条件付きだった。それでも、この戦争は二つのことを明らかにした。第一に、ロシア軍がいかに前進したかを示したこと。戦争中、ロシア軍はより大軍のオスマン帝国軍を容易く撃退したのだ。ミュンニヒは野心的すぎたが、自軍の優勢性に関する彼の推測は間違っていなかった。第二に、この戦争は、将来のトルコとロシアの戦争で展開されることになるパターンを確立し、維持した。すなわち、ロシア軍が河川の要塞で早期に獲得したものの、疫病の影響でその成果は打ち消され、より深い攻撃はトルコとタタールの騎兵隊の機敏な動きによって補給線から遮断されたのである。[40] [41]
エリザベス
![[アイコン]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | このセクションは拡張が必要です。追加していただけると助かります。 (2024年1月) |
.jpg/440px-Carle_Vanloo,_Portrait_de_l’impératrice_Élisabeth_Petrovna_(1760).jpg)
アンナ1世は1740年秋に崩御した。死の直前、彼女は姪にあたるメクレンブルク公女イヴァン6世の息子で幼い甥の息子をツァーリに任命し、かつての寵臣ビロンを摂政に指名していた。しかし、この仕打ちもビロンをアンナの治世中に作った多くの敵から救うことにはならず、彼女の死後3週間以内にシベリアに流刑となった。摂政はイヴァンの母アンナ・レオポルドヴナが引き継いだ。しかし、この取り決めも役に立たなかった。[説明が必要]従妹の嫌悪感に気づき、衛兵に対する統制を強化したピョートル大帝の娘エリザベートは、無血クーデターを起こして帝位に就いた。アンナと幼いイヴァンは連れ去られて投獄され、エリザベートはその道中で、彼女の反対者と疑われる者全員を逮捕した。[36] [42] [43]
エリザヴェータは比較的静かな環境で育ち、幼少期からその美しさを称賛されていた。服、ショッピング、ダンス、そして男性に興味を持ち、治世中は公然と、そして非常に長い[説明が必要]求婚者リストを抱えていた。しかし、彼女はピョートル大帝の治世を復活させるのに大きく貢献した。帝位に就くと、直ちに元老院を復活させ、アンナのドイツ統治を解散させ、ミュンニヒとオステルマンの両名に死刑を宣告した(刑期は絞首台流刑に減刑された)。憎まれていたドイツ人を解散させ、美と愛情のイメージを植え付けることで、エリザヴェータは当時のロシア民衆の間で最も人気のあるイメージの一つを維持した。彼女は政務の多くをアレクセイ・ベストゥージェフ=リューミンに委ねた。彼女は彼を個人的には嫌っていたが、彼の能力が国家に必要であることを鋭く理解していた。[36] [43]
1741年から1743年の露綛戦争
1741年の政治的混乱は、スウェーデンに大北方戦争での敗北への報復への期待を与えていた。さらに、オーストリア継承戦争へのロシアの介入を阻止しようと目論むフランス外交官の扇動もスウェーデンを煽っていた。スウェーデンはロシアに宣戦布告し、サンクトペテルブルクに向けて軍を進軍させた。エリザベスの即位を支持することでこの戦争を薄っぺらな正当化にし、エリザベスは見返りにロシアの領土の一部を割譲することを約束した。しかし、即位したエリザベスは条件を拒否し、準備不足のスウェーデン軍に軍を率いさせた。[42]
1741年秋、ピョートル・レイシーは、わずかな兵力で守るフィンランド侵攻を開始した。彼はコサックの襲撃能力を巧みに利用し、可能な限り多くの地方を破壊しようとした。同盟国が壊滅すると見たフランスは和平仲介を試みたが、成果はなかった。レイシーは1742年に二度目の進軍を指揮し、フィンランド沿岸部を進軍して1万7000人のスウェーデン軍を足止めしようとした。ヘルシンキ(ヘルシンキ)でこの目的は達成された。スウェーデン軍は降伏し、レイシーはヘルシンキとフィンランドの行政中心地であるオーボ(トゥルク)を占領した。1743年までにスウェーデンの敗北は完全に終わり、スウェーデン防衛のための連合軍結成への懸念が高まる中、エリザベス1世はついにスウェーデンを交渉のテーブルに引きつけた。オーボ条約でエリザベスは驚くほど寛大で、東フィンランドのいくつかの州を譲り受けたが、スウェーデンにはその支配の大部分を残すことを認めた。[36] [42]
七年戦争
プレリュード
1740年代と1750年代は、ヨーロッパ全土で緊張が高まった時期でした。この不安定さの鍵となった出来事は、プロイセンの突如として華々しい台頭でした。幾世代にもわたる慎重かつ強力な王たちの統治の下、プロイセンは北部ドイツにおける権力を統合し、実際の国土面積をはるかに超える勢力へと躍進しました。当時プロイセンを統治していたフリードリヒ大王は、軍の訓練を絶え間なく行いました。彼の重要な革新の一つは、斜めの戦闘隊形です。これは、片方の側面を意図的に過密状態にし、もう片方の側面を弱体化させるというものです。弱体化した側面が持ちこたえれば、より強力な側が敵を突破し包囲することができました。このような機動には正確なタイミングと高度な技術が必要でしたが、彼の高度な技術を持つ軍隊はまさにそれらを十分に備えていました。[45] [46]
プロイセンの急速な台頭は、ヨーロッパの勢力バランスを大きく変化させた。イギリスとオーストリア帝国は長年にわたり対フランス同盟を育んできたが、オーストリアが関心の中心をフランスから、そして脆弱な西部植民地の防衛から、北部で台頭するプロイセンへと移したことで、同盟は突如崩壊した。一方、ロシアはフランスと幾度となく衝突を繰り返しており、外交的にますます攻撃的になるフランスと、ますます強大化するプロイセンに対抗する同盟国を探していた。そこでアレクセイ・ベストゥージェフ=リューミンは、ロシアの「天敵」であるフランスとプロイセンに対抗するため、ロシアの「天友」であるイギリスとオーストリアとの同盟構築を試みた。オーストリアとロシアは1725年に防衛同盟を締結したが、イギリスはそのような同盟に慎重だった。好機を察したフリードリヒ1世は、フランスの同盟国を迂回し、1756年にイギリスとウェストミンスター条約を締結した。フランスはすぐにプロイセンに反撃し、オーストリアとの同盟を結んだ。ロシアもポーランド不可侵を条件にこの同盟に加わった。このいわゆる外交革命は、後の七年戦争の引き金となり、ヨーロッパは不安定な平和に沈んでいった。[45] [47] [48] [49]
ミュンニヒの解任に伴い、エリザベートはロシア軍の指揮権をピョートル・イワノヴィチ・シュヴァロフに委ねた。シュヴァロフはミュンニヒの下で導入されていたドイツ軍の制服を速やかに廃止した。1750年代に戦争が迫ることを予見したシュヴァロフは、プロイセン軍をモデルにロシア軍の改良に取り組んだ。彼はフリードリヒ大王が用いたのと同じ戦術を軍に訓練させたが、ロシアにはプロイセン軍の戦術を完全に習得できる士官の専門知識が不足していたため、彼の成功は歩兵よりも騎兵に大きく寄与した。彼はまた、竜騎兵をより重装甲騎兵と騎乗擲弾兵に改造し、軽装竜騎兵では不可能な突撃を可能にした。彼はまた、ロシアの砲兵の改良にも取り組み、独自の設計による革新もいくつか導入したが、技術的な仕掛けに溺れる傾向があった。[45]
1756年から1757年、グロス・イェーガースドルフの戦い
ヨーロッパにもたらされた武力平和は長くは続かなかった。フリードリヒ1世は自身への攻撃を予期し、 1756年夏にザクセンを占領することで先手を打った。これにより、オーストリア=ロシアによる首都ベルリンへの直接攻撃の脅威は排除された。戦争は1757年に本格的に始まり、すぐに二つの戦域に分かれた。大陸ヨーロッパにおけるプロイセン、オーストリア、ロシアの勢力争いと、北アメリカにおけるフランスとイギリスの植民地戦争(アメリカ史ではフレンチ・インディアン戦争として知られる)である。イギリスは優勢な海軍力と比較的小規模な陸軍を植民地戦争に投入し、フランスもこれに倣った。こうして大陸における戦闘の大半は、プロイセンに対するオーストリア=ロシア同盟によって担われた。[44] [50] [51]
国土面積の差は甚大であったものの、プロイセンの立場は見た目ほど絶望的ではなかった。ロシアとオーストリアの戦略目標は異なり、ロシアは主に東プロイセンとオーストリア・シュレージエンに注力していた。両国はしばしば戦闘の負担を互いに転嫁しようとした。そのため、フリードリヒ1世は軍を頻繁に移動させる戦略をとったが、兵士たちにとっては煩わしかったものの、両国を寄せ付けないことに成功した。イギリスの財政支援とプロイセン軍の総合的な優位性は、オーストリアとロシアの規模の優位性をさらに弱めた。[44] [50] [51]

1757年、オーストリアのプロイセン侵攻により戦争は激化した。フリードリヒ2世はこれに対抗するため、10万人の軍勢を組織し、オーストリア領ボヘミアに4縦隊で侵攻した。オーストリア軍は侵攻計画を放棄して防御に転じ、国境沿いに長く脆い縦隊を編成した。オーストリア軍は比較的容易に突破口を開いた後、無秩序な撤退に陥り、フリードリヒ2世はオーストリアの首都プラハへの進撃を開始すると同時に、フランス軍への妨害にも転用した。フリードリヒ2世はプラハ郊外でオーストリア軍主力を血なまぐさい接戦の末に破り、首都を包囲した。しかし、6月、コリンで同様に血なまぐさい戦闘が勃発し、フリードリヒ2世は北方への撤退を余儀なくされた。南方での作戦が失敗に終わる中、フランス軍は西からドイツに侵攻し、その途中でプロイセンのイギリス軍とハノーファー軍を撃破した。[50] [52]
ヨーロッパで戦況が激化する中、ロシア軍は停滞したまま、目標である軍事的に孤立した東プロイセンへとゆっくりと進軍を続けていた。東プロイセンの守備兵は少なく、ステパン・フョードロヴィチ・アプラクシン率いる10万人のロシア軍にとって、大きな脅威とはならなかったはずである。アプラクシンは皇后の宮廷で人脈の広い外交官であったが、本格的な軍事経験は乏しかった。彼は軍を慎重に進軍させたが、その速度は破滅に近かった。1757年8月19日から30日にかけて、プロイセン軍はグロース=イェーガースドルフという小さな村で、不意を突いて進軍するロシア軍を捉えた。続く戦闘で、プロイセン軍は2対1という劣勢に立たされ、騎兵隊でロシア軍縦隊(3.2キロメートル以上)の両側面を包囲し、プロイセン歩兵は森の中を進軍して中央のロシア軍を攻撃した。プロイセン軍は、ナルヴァの戦いでスウェーデン軍が行ったように、慌てて再配置するロシア軍を圧倒し、個々の部隊を壊滅させると脅した。[50] [52]
事態を収拾できたのは、後にエカテリーナ2世の首席将軍となるピョートル・ルミャンツェフの活躍のみであった。彼は中央でロシア軍を結集させ、プロイセン軍を押し戻し、決定的な突破と敗北の危機を終わらせた。ロシア軍の縦隊、特に砲兵隊が攻撃軍に反撃を開始したため、プロイセン軍は撤退を余儀なくされた。損害はほぼ互角だったが、小規模なプロイセン軍にとって、損害を許容できる状況ではなかった。損失に戦慄したアプラクシンは勝利を活かす勇気を失い、冬営地へと撤退した。この戦いはロシア史上最も楽な勝利の一つとなった。彼は後に指揮官の職を解かれ、その悪質な行動力の欠如を理由に裁判にかけられ、翌年獄死した。[48] [50] [52]
1757年はフリードリヒ2世にとって総じて厳しい年であった。他国が動員される間にオーストリアを戦争から脱落させようとしたプロイセンのオーストリアへの電撃攻撃は失敗に終わった。彼は今や、国庫が空っぽで、人口の少ないプロイセンでは到底払えないほどの巨額の賠償金を背負った3つの列強との対決に直面していた。オーストリア軍は急速にシュレージエンの要塞を奪還し、この地域はオーストリアの手に落ちた。オーストリアの襲撃はフリードリヒ2世の首都ベルリンにまで及んだ。 [50]
1758年、ツォルンドルフの戦い

1758年はヨーロッパで新たな戦役を繰り広げ、プロイセンに新たな希望をもたらした。フリードリヒ大王はロスバッハでフランス軍に華々しい勝利を収め、続いてロイテンでオーストリア軍に、より犠牲は大きかったものの、同様に決定的な勝利を収めた。西側と南側の両翼の陣地は一時的に安泰となり、プロイセンの勝利に感銘を受けたイギリスからの資金が再び流入し始めた。[44] [53] [54]
アプラクシンの解任後、ロシア野戦軍の指揮権はウィリアム・ファーモアに移った。レーシーとミュンニッヒに師事した、端正で知的なバルト系ドイツ人であるファーモアは、兵士の福祉を最優先事項の一つとした。ファーモアの軍勢は、アプラクシンが苦戦していた東プロイセン諸州をあっさりと制圧した。東プロイセン奪還の見込みがないと悟ったフリードリヒは、オーストリア軍に目を向け、モラビア地方に侵攻した。しかし、オーストリア軍は戦闘を拒否し、これまでの戦略上の悪夢を救ってきた華々しい勝利は一つも挙げられなかった。更なる進撃は無駄だと悟ったフリードリヒは、夏の終わりまでに再びロシア軍に目を向けた。[52] [53] [54]
フリードリヒ大王はオーデル川東のツォルンドルフ村落郊外の沼地でフェルマー軍と遭遇した。フリードリヒ大王は夜陰に乗じてロシア軍の背後を南に回り込み奇襲を仕掛ける計画だった。しかし翌朝、ロシア軍は方向転換し、今度は南にいた敵と再び対峙した。プロイセン軍は奇襲の機会を失ったものの、ロシア軍は川と沼地に背を向けたため脆弱な位置に立たされた。1758年8月25日、2時間に及ぶ砲撃の後、プロイセン軍左翼はロシア軍と交戦し、たちまち激しい一斉射撃の応酬となった。しかし、ロシア軍右翼への攻撃支援を企図していたフリードリヒ大王の左翼縦隊は中央へと流れ、交戦は膠着状態に陥った。ファーモールは素早くこの隙を突いて騎兵隊を左翼の弱体化に突き落とし、混乱を招いて後退させたが、その優位はプロイセン騎兵隊の迅速な反撃によって打ち消された。戦闘は混乱した消耗戦へと発展し、血塗られた両軍は夜になるまで決着がつかなかった。こうしてツォルンドルフの戦いは総勢8万人のうち3万人の死傷者を出して終結し、両軍は翌朝までに撤退した。[53]
フェルモールは東へ撤退し(実際にはツォルンドルフからの撤退よりずっと前に逃亡していた)、プロイセン軍は南下してオーストリア軍の攻勢に再び直面する機会を得た。フリードリヒ大王はホッホキルヒに陣取っていた軍がオーストリア軍に制圧されそうになり、再び窮地に陥った。大軍の大半は無傷で脱出したものの、年末までにプロイセン軍の戦況は改善していないことが明らかになった。むしろ、フリードリヒ大王は精鋭部隊の多くを失い、ロシアとオーストリアは彼の戦術を無効化する新たな能力を発揮していた。[53]
その後のキャンペーン
ロシアはオーストリアとの同盟を継続したが、オーストリアはプロイセンに対抗するためフランスとの同盟へと転換した。1759年、ロシアとオーストリアの連合軍はクーネルスドルフでフリードリヒ大王を決定的に破り、1760年にはベルリンを占領した。プロイセン王国にとって幸運だったのは、エリザヴェータが1762年に亡くなり、後継者のピョートル3世はプロイセン王フリードリヒ大王への忠誠心から、ロシアとプロイセンの同盟を結んだことである。
余波
七年戦争は、ピョートル大帝以来、近隣諸国との紛争に巻き込まれていたロシアが、ヨーロッパの一流軍と戦った最初の戦争であり、結果は百戦錬磨であった。ロシア軍は、容赦ない一斉射撃にもひるむことなく立ち向かい、並外れた勇気と勇敢さを示した。しかし、指揮系統はそれほどうまく機能しなかった。全体的な調整はベストゥージェフ=リューミンと宮廷会議に委ねられたが、これはすぐに非効率であることが証明され、軍の細かな管理に多くの時間を費やした。ロシアの将校団はピョートル大帝の治世中にエリート部隊へと強化されたが、彼の政策は廃止され、指揮系統は荒廃していた。その結果、ロシアはプロイセンに対していくつかの重要な勝利を収めたものの、その成功を十分に活かすことはできなかった。この問題は、ロシア軍の補給線が不十分だったことでさらに悪化し、ロシア軍は毎年冬に撤退を余儀なくされた。[48] [50]
ピョートル3世
ピョートル3世の治世は短く、不人気だった。ピョートル大帝の孫であったが、父はホルシュタイン=ゴットルプ公爵であったため、ピョートル3世はドイツのルター派の環境で育った。そのため、ロシア人は彼を外国人とみなしていた。ロシアのあらゆるものに対する軽蔑を隠そうとしなかったピョートルは、ロシア軍にプロイセンの軍事演習を強制し、ロシア正教会を攻撃し、プロイセンとの突然の同盟を結んでロシアの軍事的勝利を奪うなどして、ロシア人の深い反感を買った。不満を利用し、自身の立場を恐れたピョートル3世の妻エカテリーナはクーデターで夫を廃位させ、その後、愛人のアレクセイ・オルロフが夫を殺害したため、1762年6月にエカテリーナはロシア皇后 エカテリーナ2世となった。
ロシア帝国の拡大と成熟
.jpg/440px-Catherine_II_by_D.Levitskiy_(1794,_Novgorod_museum).jpg)
エカチェリーナ2世の治世は帝国の拡張と国内の統合が特徴的だった。 1768年にオスマン帝国との露土戦争が勃発した後、両国は1774年にクチュク・カイナルジー条約に合意した。この条約により、ロシアは黒海への出口を獲得し、クリミア・タタール人はオスマン帝国から独立した。この戦争でロシアはロシア軍史上最も痛烈な海戦敗北、チェスマの海戦をもたらした。1783年、エカチェリーナ2世はクリミアを併合し、これが1787年に始まったオスマン帝国との次の露土戦争の引き金となった。 1792年のヤッシ条約により、ロシアは南方のドニエストル川まで拡張した。この条約の条項は、エカチェリーナ2世が掲げた「ギリシャ計画」の目標、すなわちオスマン帝国をヨーロッパから追放し、ロシアの支配下でビザンツ帝国を再建するという目標には程遠いものでした。しかしながら、オスマン帝国はもはやロシアにとって深刻な脅威ではなくなり、バルカン半島におけるロシアの影響力の増大を容認せざるを得なくなりました。[55]
ポーランド分割
エカチェリーナ2世統治下におけるロシアの西方への拡大は、ポーランド分割の結果であった。18世紀、ポーランドがますます弱体化すると、隣国であるロシア、プロイセン、オーストリアはそれぞれ自国の候補者をポーランドの王位に就かせようとした。1772年、3国はポーランド領土の最初の分割に合意し、これによりロシアはベラルーシとリヴォニアの一部を獲得した。分割後、ポーランドは広範な改革プログラムを開始し、その中にはポーランドとロシアの反動派を警戒させる民主的な憲法が含まれていた。過激主義の危険性を口実に、同じ3国は憲法を廃止し、1793年に再びポーランドの領土を剥奪した。今度はロシアはドニエプル川西側のベラルーシとウクライナの大半を獲得した。 1793年のポーランド分割は、反ロシア・反プロイセンの蜂起をポーランドで引き起こし、1795年の第三次分割で終結した。ロシア軍は激しい戦闘の末、ワルシャワ郊外のプラガを占領した。第三次分割の結果、ポーランドは国際政治の地図から姿を消した。
ポーランド分割はロシアの領土と威信を大きく高めたが、同時に新たな困難も生み出した。緩衝地帯としてのポーランドを失ったロシアは、プロイセンとオーストリアの両国と国境を接しなければならなくなった。さらに、多数のポーランド人、ウクライナ人、ベラルーシ人、そしてユダヤ人を吸収したため、帝国は民族的に多様化した。主に農奴として働かされていたウクライナ人とベラルーシ人の運命は、ロシア統治下においても当初はほとんど変化がなかった。しかし、ローマ・カトリック教徒のポーランド人は独立の喪失に憤慨し、統合は困難を極めた。
プガチョフの反乱とアレクサンダー・スヴォーロフ

1768年から1774年にかけてオスマン帝国と戦争を繰り広げたロシアでは、プガチョフの反乱という大きな社会的激変が起きた。1773年、ドン・コサックのエメリヤン・プガチョフが復活した皇帝ピョートル3世を自称した。他のコサック、ロシアの中央集権化の圧力を感じていた様々なトルコ系部族、ウラル山脈の工業労働者、そして農奴制からの脱却を願う農民たちが反乱に加わった。ロシアが戦争に没頭していたため、プガチョフはヴォルガ川流域の一部を掌握したが、1774年に正規軍によって反乱は鎮圧された。[56]
この時代のロシア軍の歴史は、アレクサンドル・スヴォーロフというロシアの将軍の名と結びついている。彼は歴史上、一度も戦闘に負けたことのない数少ない偉大な将軍の一人とされている。1777年から1783年までスヴォーロフはクリミアとコーカサスで従軍し、1780年に中将、1783年にそこでの任務を終えると歩兵将軍になった(クバン・ノガイの蜂起も参照)。1787年から1791年まで、彼は露土戦争(1787- 1792年)で再びトルコと戦い、イズマイールやリムニクなど多くの勝利を収めた。スヴォーロフのリーダーシップはまた、コシチュシュコ蜂起、特にプラガの戦いでロシアがポーランドに勝利する際に重要な役割を果たした。[57]
キャサリンの後

エカチェリーナ2世は1796年に亡くなり、息子のパウル(在位1796~1801年)が後を継ぎました。彼がロシアの外交を独自に指揮したため、ロシアはまず1798年に対仏大同盟に、次いで1801年には対イギリス武装中立に陥りました。新皇帝はロシア軍にプロイセンの戦術を叩き込みましたが、これがスヴォーロフとの対立を招き、スヴォーロフは解任され、自ら亡命することになりました。しかし、1798年から1799年にかけてスヴォーロフは軍に召還されました。スヴォーロフ率いるロシア軍は、イタリアとスイス、特にトレッビアの戦いで輝かしい戦果を挙げました。
19世紀初頭、ロシアは人口、資源、国際外交力、そして軍事力によって、世界で最も強大な国家の一つとなりました。その力によって、ロシアはヨーロッパ情勢においてますます積極的な役割を果たすようになりました。この役割は、ロシア帝国をナポレオンとの一連の戦争に巻き込み、ロシアとヨーロッパの他の国々に広範な影響を及ぼしました。啓蒙時代を経て、ロシアは中央ヨーロッパと西ヨーロッパにおける自由化の潮流に積極的に反対するようになりました。
ナポレオン戦争
ヨーロッパの大国であったロシアも、革命期およびナポレオン期のフランスとの戦争から逃れることはできなかった。ポール1世はフランスの強硬な反対者となり、ロシアはイギリス、オーストリアとともにフランスとの戦争に加わった。ポール1世が聖ヨハネ騎士団の理念を支持し(また、騎士団長の地位を受け入れたため)、宮廷の多くのメンバーから疎外された。下層階級に対する自由主義的な政策や国庫の腐敗の発覚、そして改革への熱意が彼の運命を決定づけた。1801年3月、ポール1世は少数の貴族と不満を抱いた将校らに暗殺された。父の暗殺に関与したとの噂があり、その結果、新しい皇帝アレクサンドル1世(在位1801年~1825年)が即位した。
アレクサンダーの主な関心は国内政策ではなく外交、特にナポレオンにあった。ナポレオンの拡張主義的野心とフランスの勢力拡大を恐れたアレクサンダーは、イギリスとオーストリアと連携してナポレオンに対抗した。ナポレオンは1805年にアウステルリッツでロシアとオーストリアを破り、1807年にはフリートラントでロシアを圧倒した。アレクサンダーは講和を申し入れざるを得なくなり、1807年に調印されたティルジット条約によってナポレオンの同盟国となった。この条約でロシアはほとんど領土を失うことはなく、アレクサンダーはナポレオンとの同盟を利用してさらなる拡張を図った。フィンランド戦争では、1809年にスウェーデンからフィンランドを奪い取り、1812年にはトルコからベッサラビアを獲得した。[58]
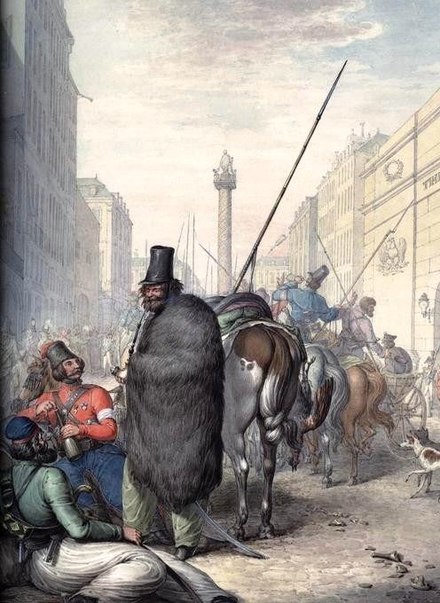
露仏同盟は徐々に緊張を深めていった。ナポレオンは戦略的に重要なボスポラス海峡とダーダネルス海峡におけるロシアの思惑を懸念していた。同時に、アレクサンドル1世は、フランス統治下で再建されたポーランド国家、ワルシャワ大公国に疑念を抱いていた。イギリスに対するフランスの大陸封鎖への参加はロシアの通商にとって深刻な障害となり、1810年にアレクサンドル1世はこの義務を放棄した。
1812年、ナポレオンはロシアに侵攻し、皇帝アレクサンドル1世を大陸封鎖にとどまらせ、差し迫ったロシアによるポーランド侵攻の脅威を排除しようとした。65万人の大陸軍(フランス軍27万人と同盟国や従属国の兵士多数)は、 1812年6月23日にニエメン川を渡った。ロシアは祖国戦争を宣言し、ナポレオンは第二次ポーランド戦争を宣言したが、侵攻軍に約10万人の兵士を供給したポーランド人の期待に反して、ナポレオンはロシアとの更なる交渉を念頭に置き、ポーランドに対するいかなる譲歩も避けた。ロシアは焦土退却政策を維持し、ボロジノの戦い(9月7日)でのみロシア軍が踏ん張って戦った。この戦いは血なまぐさい戦いとなり、ロシア軍は最終的に撤退を余儀なくされ、モスクワへの道が開かれた。 9月14日までにモスクワは陥落したが、この時点でロシア軍はほぼ放棄しており、フランス軍の妨害をするためモスクワの牢獄から囚人が釈放されていた。アレクサンドル1世は降伏を拒否し、明確な勝利の兆しも見えない中、ナポレオンはモスクワが焼け落ちた後、撤退を余儀なくされた。対立する両陣営は互いに火災の責任をなすりつけた。こうして悲惨な大撤退が始まり、飢餓と極寒の気候により37万人が犠牲となり、20万人が捕虜となった。11月までにベレジナ川を渡った兵士のうち、健全な兵士はわずか2万7千人だった。ナポレオンは軍をパリに戻し、進軍してくるロシア軍からポーランドを守る準備をさせた。[59]
フランス軍が撤退するにつれ、ロシア軍は中央ヨーロッパと西ヨーロッパ、そしてパリの門まで追撃した。同盟軍がナポレオンを破った後、アレクサンドル1世はヨーロッパの救世主として知られるようになり、 1815年のウィーン会議でヨーロッパの地図の書き換えに重要な役割を果たした。同年、アレクサンドル1世は神聖同盟の結成を主導した。これは、ヨーロッパの大半を含む関係国の統治者がキリスト教の原則に従って行動することを誓約する緩やかな協定であった。より実際的な観点から、1814年にはロシア、イギリス、オーストリア、プロイセンが四国同盟を結成した。同盟国は領土の現状を維持し、拡張主義的なフランスの復活を防ぐための国際体制を構築した。数々の国際会議で承認された四国同盟は、ヨーロッパにおけるロシアの影響力を確保した。[60]
参照

1815–1856
デカブリストの反乱
同時に、ロシアは領土拡大を続けた。ウィーン会議でポーランド王国(ロシア領ポーランド)が建国され、アレクサンドル1世は憲法を制定した。こうしてアレクサンドル1世は、ロシアの専制君主でありながら、ポーランドの立憲君主となった。また、1809年に併合され自治権を与えられたフィンランドの制限君主でもあった。1813年、ロシアはペルシャを犠牲にしてコーカサス山脈のバク地方の領土を獲得した。19世紀初頭までに、ロシア帝国はアラスカにも確固たる基盤を築いた。
歴史家たちは、アレクサンドル1世の治世中に革命運動が起こったということで概ね一致している。ナポレオンを追って西ヨーロッパまで行った若い将校たちは、革命的な思想を持ってロシアに戻った。18世紀に父権主義的で独裁的なロシア国家によって促進された知的近代化には、独裁政治への反対、代議制政府の要求、農奴制廃止の呼びかけ、そして場合によっては革命による政府打倒の提唱が含まれるようになった。将校たちは、アレクサンドルがポーランドに憲法を与えたのにロシアには憲法がなかったことに特に憤慨していた。1825年にアレクサンドルが予期せず死去したとき、いくつかの秘密組織が蜂起の準備を進めていた。彼の死後、次位であった弟のコンスタンティノスが王位継承権を放棄したため、誰が後継者になるかで混乱が生じた。約3,000人の兵士を率いる将校の一団が、新皇帝アレクサンドル1世の弟ニコライ1世への忠誠の誓いを拒否し、ロシア憲法制定の理念への忠誠を表明した。これらの出来事が1825年12月に起こったため、反乱者たちはデカブリストと呼ばれた。ニコライは反乱を容易に鎮圧し、生き残ったデカブリストたちは逮捕された。多くはシベリアに流刑された。デカブリストは、ある程度、自らの候補者を皇帝に据えようとした宮廷革命家の長い系譜を受け継いでいた。しかし、デカブリストたちは自由主義的な政治綱領の実施も望んでいたため、彼らの反乱は革命運動の始まりとみなされている。デカブリストの反乱は、政府と自由主義派の間に生じた最初の明白な亀裂であり、その後、亀裂は拡大していった。[61] [62]
軍隊の弱さ
ニコライ1世(在位1825~1855年)は、人口6000万~7000万人のうち、100万人の兵士を擁する大規模な軍隊に力を注いだ。装備と戦術は時代遅れだったが、兵士のような服装をし、周囲に将校を配置した皇帝は、1812年のナポレオンに対する勝利を大いに誇り、パレードでの派手さを誇示した。例えば、騎兵隊の馬はパレード隊形のみの訓練しか受けておらず、実戦では力不足だった。きらびやかな飾りや三つ編みは、皇帝が気づいていなかった深刻な弱点を隠していた。皇帝は、資格に関わらず、民間機関のほとんどを将軍に任じた。騎兵突撃で名声を博した不可知論者は、教会問題監督官に任命された。軍隊は、ポーランド、バルト海諸国、フィンランド、グルジアなど、ロシア以外の地域の貴族の若者にとって、社会的地位向上の手段となった。一方、多くの悪党、軽犯罪者、そして望ましくない者たちは、地方当局によって終身軍隊に徴兵されるという罰を受けた。徴兵制度は民衆に非常に不評で、農民に年間6ヶ月間兵士の住居を強制する慣行も同様であった。カーティスは、「戦闘訓練よりも無意識の服従と練兵場での訓練を重視したニコライの軍事制度の衒学的偏執は、戦時において無能な指揮官を生み出した」と述べている。クリミア戦争における彼の指揮官たちは老齢で無能であり、大佐たちが最高の装備と最高の食料を売っていたため、彼のマスケット銃も同様に無能であった。[63]
ついに、彼の治世末期に勃発したクリミア戦争は、それまで誰も気づいていなかった事実を世界に明らかにした。ロシアは軍事的に弱く、技術的に後進的で、行政能力も欠如していたのだ。南北とトルコへの壮大な野望を抱いたにもかかわらず、ロシアはその方面に鉄道網を敷設しておらず、通信手段も貧弱だった。官僚機構は汚職、腐敗、非効率に満ち、戦争への備えも不十分だった。海軍は弱体で、技術的にも後進的だった。陸軍は規模は大きかったものの、パレード程度しかできず、部下の給与を私腹を肥やす大佐の存在や低い士気、そしてイギリスとフランスが開発した最新技術との関連性も薄かった。フラーが指摘するように、「ロシアはクリミア半島で敗北を喫しており、軍事的弱点を克服する措置を講じない限り、再び敗北は避けられないと軍は恐れていた」[64] [65] [66] 。
歴史とサービス
クリミア戦争
クリミア戦争に関するメイン記事を参照
露土戦争、1877~1878年
露土戦争(1877-1878)に関するメイン記事を参照
日露戦争
日露戦争に関するメイン記事を参照
1904年2月8日、旅順港に駐屯していたロシア極東艦隊が日本軍の攻撃を受けたことで、ロシアと日本の戦争が勃発した。兵站問題、旧式化した軍事装備、そして無能なロシア将校に悩まされたロシア軍は、戦争の過程で幾度となく敗北を喫し、1905年9月の対馬沖海戦におけるロシア艦隊の壊滅を契機に終結した。[67] 1905年のロシア革命を含む国内問題の深刻化に直面したロシアは、ポーツマス条約で戦争が終結する中、講和を求めた。
第一次世界大戦
第一次世界大戦に関するメイン記事を参照。また、東部戦線(第一次世界大戦)とコーカサス戦役も参照。
1917年のロシア革命
1917年のロシア革命に関するメイン記事を参照
参照
引用
参考文献
- ^ リアサノフスキーおよびスタインバーグ、211~212ページ
- ^ クラークソン、187~188ページ
- ^ リ アサノフスキーおよびスタインバーグ、pp. 212–215
- ^ ヒューズ、9~17ページ
- ^ ab ストーン、44~46ページ
- ^ ヒューズ、22~23ページ
- ^ ヒューズ、24~26ページ
- ^ リアサノフスキーおよびスタインバーグ、215~217ページ
- ^ リアサノフスキーおよびスタインバーグ、217~218ページ
- ^ ヒューズ、34~37ページ
- ^ リ アサノフスキーおよびスタインバーグ、pp. 226–227
- ^ abc ストーン、46~48ページ
- ^ abcd Stone、48~50ページ
- ^ ヒューズ著、37~39ページ
- ^ リ アサノフスキーおよびスタインバーグ、218–220
- ^ ヒューズ、40~50ページ
- ^ ヒューズ著、50~57ページ
- ^ abcdefghijklmno リアサノフスキーおよびスタインバーグ、pp. 220–224
- ^ abcdefghijkl ストーン、50–54 ページ
- ^ abc ヒューズ、58~65ページ
- ^ アンガス・コンスタム『ピョートル大帝の軍隊(1):歩兵』(オスプレイ、1993年)。
- ^ フロスト、230、263ページ
- ^ ヒューズ、67~68ページ
- ^ ヒューズ、71~73ページ
- ^ ヒューズ著、79~82ページ
- ^ abcd ストーン、54~56ページ
- ^ abc Konstam、62~74ページ
- ^ コンスタム、74~88ページ
- ^ abcd ストーン、56~57ページ
- ^ グラント、154~155ページ
- ^ リアサノフスキーおよびスタインバーグ、228~231ページ
- ^ abc ストーン、57~60ページ
- ^ トゥルーマン、クリス. 「大北方戦争」. 2013年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月23日閲覧。
- ^ リアサノフスキーおよびスタインバーグ、231~233ページ
- ^ ヒューズ、165~169ページ
- ^ abcdefghi リアサノフスキーとスタインバーグ、239–243 ページ
- ^ abcdefgh ストーン、61~63ページ
- ^ ab ストーン、63~64ページ
- ^ ab プロテロとベニアン、303–304 ページ
- ^ abcde Stone、64~67ページ
- ^ abcde プロセロとベニアンズ、304~308ページ
- ^ abc ストーン、67~68ページ
- ^ ab プロテロとベニアン、309–312 ページ
- ^ abcd カウリーとパーカー、422~423ページ
- ^ abc ストーン、68~70ページ
- ^ マーストン、16~17ページ
- ^ リアサノフスキーおよびスタインバーグ、248~250ページ
- ^ abc プロセロとベニアンズ、314~320ページ
- ^ マートソン、15ページ
- ^ abcdefg ストーン、70~72ページ
- ^ マーソン著、26~28ページ
- ^ abcd マーソン、29~42ページ
- ^ abcd Stone、72~74ページ
- ^ ab プロテロとベニアン、322–324 ページ
- ^ ジョン・T・アレクサンダー『エカチェリーナ2世:生涯と伝説』(オックスフォード大学出版局、1988年)
- ^ ジョン・T・アレクサンダー著『国家危機における独裁政治:帝政ロシア政府とプガチョフの反乱、1773-1775』(インディアナ大学出版、1969年)
- ^ K. オシポフ『アレクサンダー・スヴォーロフ伝』(ハッチンソン、1944年)
- ^ カーティス・ケイト『二皇帝の戦争:ナポレオンとアレクサンダーの決闘:ロシア、1812年』(1985年)。
- ^ アダム・ザモイスキー、『1812年:ナポレオンのモスクワへの致命的な行進』(2012年)。
- ^ マーク・ジャレット『ウィーン会議とその遺産:ナポレオン以後の戦争と大国外交』(IBタウリス、2013年)
- ^ マーク・レイフ『デカブリスト運動』(1966年)
- ^ アナトール・G・マズール『 1825年最初のロシア革命:デカブリスト運動の起源、発展、そして意義』(スタンフォード大学出版、1961年)
- ^ ジョン・シェルトン・カーティス、「ニコラス1世の軍隊:その役割と性格」、アメリカ歴史評論(1958年)63巻4号、880~889頁、886頁を引用。JSTORより
- ^ フラー (1998年10月1日). 『ロシアにおける戦略と権力 1600–1914』サイモン&シュスター. 273ページ. ISBN 978-1-4391-0577-1。
- ^ バーバラ・イェラヴィッチ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアとソ連の外交政策、1814-1974』(1974年)119ページ
- ^ ウィリアム・C・フラー『ロシアにおける戦略と権力 1600–1914』(1998年)252-59ページ
- ^ フィゲス『民衆の悲劇』168-170頁。
参考文献
- ニコラス・V・リアサノフスキー、マーク・D・スタインバーグ(2011年)『ロシアの歴史』(第8版)オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-534197-3。
- デイヴィッド・R・ストーン(2006年)『ロシアの軍事史:イヴァン4世からチェチェン戦争まで』Praeger Security International . ISBN 0-275-98502-4。
- GWプロセロとアーネスト・アルフレッド・ベニアンズ(1909年)『ケンブリッジ近代史』第6巻、ケンブリッジ大学出版局。
- ジェシー・D・クラークソン(1961年)『ロシアの歴史』ランダムハウス
- RGグラント(2008年)『海戦:3000年の海軍戦争』ドーリング・キンダースリー社、ISBN 978-0-7566-3973-0。
- ロバート・カウリー、ジェフリー・パーカー編(2001年)『軍事史入門』ホートン・ミフリン社、ISBN 0-395-66969-3。
- リンジー・ヒューズ(2004年)『ピョートル大帝伝』イェール大学出版局、ISBN 978-0-300-10300-7。
- ロバート・I・フロスト(2000年)『北方戦争:北東ヨーロッパにおける戦争、国家、社会 1558-1721』ロングマン社ISBN 0-582-06429-5。
- アンガス・コンスタム(1994年)『ポルタヴァ1709:ロシアの成熟』エッセンシャル・ヒストリーズ、オスプレイ出版、ISBN 978-1-85532-416-9。
- ダニエル・マーストン(2001年)『七年戦争』エッセンシャル・ヒストリーズ、オスプレイ出版、ISBN 978-1-84176-191-6。
さらに読む
- ケイト・カーティス著『二皇帝の戦争:ナポレオンとアレクサンドルの決闘:1812年のロシア』(1985年)。
- フラー、ウィリアム・C.『ロシアにおける戦略と権力 1600-1914』(1998年)
- ヘイソーンスウェイト、フィリップ・J. 『ナポレオン戦争におけるロシア軍』(1987年)第1巻:歩兵(1799~1814年)、第2巻:騎兵(1799~1814年)
- Lieven, D.C.「ロシアとナポレオンの敗北(1812–14)」、Kritika: ロシアとユーラシアの歴史の探究(2006年)7巻2号、283–308頁。
- ウィリアム・レーガー、デイヴィッド・ジョーンズ(編)『ロシアとユーラシアの軍事百科事典』、アカデミック・インターナショナル・プレス。
- ジョン・L・キープ(1985年)『ツァーリの兵士たち ― ロシアの軍隊と社会 1462-1874』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-822575-1。
- ツァーリ軍の改革:ピョートル大帝から革命までの帝政ロシアにおける軍事革新。ケンブリッジ大学出版局。2004年。ISBN 978-0-521-81988-6。
- クリストファー・ダフィー(1982年)『ロシアの西方への軍事的道:1700~1800年のロシア軍事力の起源と本質』ラウトレッジ社、ISBN 978-0-7100-0797-1。
- ロバート・K・マッシー(1986年)『ピョートル大帝:その生涯と世界』ボールタイン・ブックス、ISBN 978-0-345-33619-4。
- ピーター・イングランド(2002年)『ヨーロッパを揺るがした戦い:ポルタヴァとロシア帝国の誕生』 IBタウリス社、ISBN 978-1-86064-847-2。
- W・E・D・アレンとポール・ムラトフ(1953年)『コーカサスの戦場』ケンブリッジ大学出版局
- ポール・ブリテン・オースティン(1993年)『1812年:モスクワ行進』グリーンウッド・プレス、ISBN 978-1-85367-154-8。
外部リンク
- マーク・コンラッドのホームページ – ロシアの軍事史
- ナポレオン戦争におけるロシア軍、ナポレオン、その軍隊と敵。
