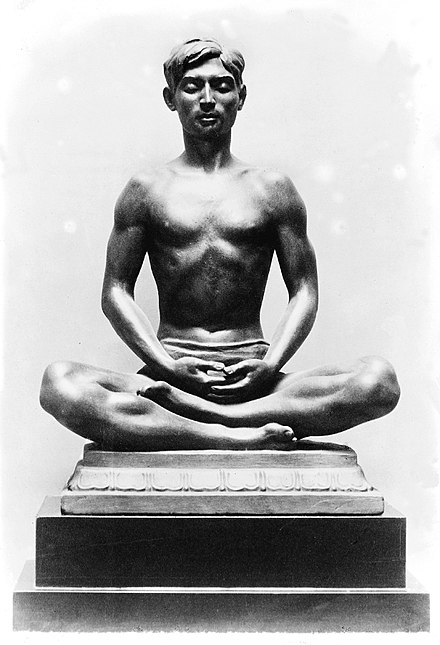サムサラ

サムサーラ(デーヴァナーガリー語:संसार)はサンスクリット語で「放浪」 [ 1 ] [ 2 ]と「世界」を意味し、「周期的な変化」 [ 3 ] 、あるいはより非公式には「ぐるぐると回り続ける」といった意味合いを持つ。インドの宗教や哲学において、サムサーラとは、すべての存在が生と死と再生の継続的なサイクルを経験するという概念である。 [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]そのため、輪廻転生、カルマのサイクル、あまり使われない用語であるプナルジャンマン、あるいは「目的のない漂流、放浪、あるいは俗世間の存在のサイクル」と広く同一視されることもある。 [ 1 ] [ 4 ] [ 6 ]
「すべての生命、物質、存在の循環性」は、ほとんどのインドの宗教の基本的な信念です。[ 4 ] [ 7 ] [ 8 ]サンサーラの概念は、ヴェーダ以降の文献に起源を持ちますが、その理論はヴェーダ自体では議論されていません。[ 9 ] [ 10 ]初期のウパニシャッドでは、機械論の詳細は述べられていませんが、発展した形で登場します。[ 4 ] [ 11 ] [ 12 ]サンサーラの教義の完全な解説は、初期の仏教やジャイナ教、ヒンドゥー教のさまざまな学派に見られます。[ 4 ] [ 12 ] [ 13 ]輪廻の教義はヒンズー教のカルマ理論と結びついており、輪廻からの解放はインドの伝統における精神的探求の中核であり、内部の不一致でもあった。[ 4 ] [ 14 ] [ 15 ]輪廻からの解放は、モクシャ、ニルヴァーナ、ムクティ、またはカイヴァルヤと呼ばれている。[ 4 ] [ 6 ] [ 16 ] [ 17 ]
語源と定義
サンサーラ(デーヴァナーガリー語:संसार)は「放浪」[ 1 ] [ 2 ]を意味すると同時に「世界」を意味し、「周期的な変化」を暗示する。[ 3 ]インドのあらゆる宗教における基本概念であるサンサーラは、カルマ論と結びついており、すべての生き物が周期的に生と死を繰り返すという信仰を指す。この用語は、「輪廻転生」「輪廻」「カルマの輪」「生命の輪」「すべての生命、物質、存在の周期性」といった語句と関連している。[ 1 ] [ 5 ] [ 18 ]多くの学術文献では、サンサーラをサンサーラと綴っている。[ 5 ] [ 19 ]
モニエ=ウィリアムズによれば、saṃsāraは動詞の語根sṛに接頭辞saṃ、Saṃsṛ (संसृ)がついたものから派生しており、「回る、回転する、一連の状態を通過する、向かうまたは得る、回路を移動する」という意味である。[ 20 ]接頭辞samはsamyakまたは井戸を意味し、 sarは動くことを意味する。[ 21 ]この語根から形成された名詞派生語は古代の文献にsaṃsaraṇaとして現れ、これは「一連の状態、誕生、生物と世界の再生を、妨げられることなく回る」という意味である。[ 20 ]同じ語源から派生した別の名詞的派生語はsaṃsāraであり、同じ概念を指している。それは「世俗的な存在の連続的な状態を通過すること」、輪廻、輪廻転生、以前の状態を繰り返す生活の循環、ある体から別の体へと変化する現世の生活、再生、成長、衰退、そして再死である。[ 6 ] [ 20 ] [ 22 ] Saṃsāraは、 mukti、nirvāṇa、nibbāna、kaivalyaとしても知られるmokshaの反対語として理解されており、生と死の輪廻からの解放を指す。[ 6 ] [ 20 ]
saṃsāraという言葉はSaṃsṛtiに関連しており、Saṃsṛtiは「現世の存在の過程、輪廻、流れ、回路、流れ」を指します。[ 20 ]
スティーブン・J・ラウマキスによれば、この言葉は文字通り「さまよう、流れ続ける」という意味で、「目的もなく方向もなくさまよう」という意味である。[ 23 ]輪廻の概念は、人が様々な領域や形で生まれ変わり続けるという信仰と密接に関連している。[ 24 ]
ヴェーダ文献の最初期には、人生の概念が組み込まれており、徳(功徳)または悪(過失)の蓄積に基づいて天国と地獄での来世が定められている。[ 25 ]しかし、古代ヴェーダの聖賢たちは、人々が等しく道徳的または不道徳な人生を送るわけではないとして、この来世の考え方は単純すぎると異議を唱えた。一般的に徳の高い人生の中には、より徳の高い人生もあれば、悪にも程度があり、文献は、ヤマ神が様々な程度の徳や悪徳を持つ人々を「どちらか一方」で、不均衡な方法で裁き、報いるのは不公平であると主張している。[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]彼らは、功徳に応じて天国または地獄での来世があり、それが尽きると人は戻って生まれ変わるという考え方を導入した。[ 26 ] [ 13 ] [ 29 ]この考えは、マハーバーラタの第6章31節やデヴィ・バガヴァタ・プラーナの第6章10節など、古代および中世の文献に生、死、再生、そして再死のサイクルとして現れています。[ 26 ] [ 18 ] [ 30 ]
歴史
サンサーラの概念はヴェーダ時代以降に発展し、リグ・ヴェーダの1.164、4.55、6.70、10.14節などのサンヒター層にその起源を辿ることができる。[ 11 ] [ 30 ] [ 31 ]この概念はヴェーダのサンヒター層にも記載されているが、明確な説明が不足しており、初期のウパニシャッドで完全に発展している。[ 32 ] [ 33 ]ダミアン・キーオンは、「周期的な生と死」の概念は紀元前800年頃に現れたと述べている。[ 34 ] saṃsāraという言葉は、 Mokshaと共に、Katha Upanishadの詩節1.3.7 、[ 35 ] Shvetashvatara Upanishadの詩節6.16 、[ 36 ] Maitri Upanishadの詩節1.4と6.34など、いくつかの主要なウパニシャッドに登場します。[ 37 ] [ 38 ]
輪廻転生、すなわちプナルジャンマンの概念の歴史的起源は不明瞭であるが、この考えは紀元前1千年紀のインドと古代ギリシャの文献に登場している。[ 39 ] [ 40 ]サンサーラの概念はリグ・ヴェーダなどの後期ヴェーダ文献に暗示されているが、理論は存在しない。[ 11 ] [ 41 ]セイヤーズによると、ヴェーダ文献の最も初期の層には祖先崇拝や、シュラッダ(祖先に食物を供える)などの儀式が示されている。アーラニヤカやウパニシャッドなどの後期ヴェーダ文献は、輪廻転生に基づく異なる救済論を示しており、祖先儀式とはほとんど関係がなく、初期の儀式を哲学的に解釈し始めているが、この考えはまだ完全には発展していない。[ 32 ]これらのアイデアは初期のウパニシャッドでより完全に展開されていますが、そこでも議論は特定のメカニズムの詳細は提供していません。[ 32 ]詳細な教義は、紀元前1千年紀中頃、仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー哲学の様々な学派などの多様な伝統の中で、独自の特徴を持って開花しました。[ 12 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]古代に誰が誰に影響を与えたかの証拠はわずかで推測の域を出ず、サンサーラ理論の歴史的発展は相互影響と並行して起こった可能性が高いです。[ 45 ]
Punarmrityu: 再死
輪廻転生は、通常、生物(ジーヴァ)の再生と輪廻(プナルジャンマン)として説明されるが、その思想の歴史における年代順の発展は、人間存在の本質とは何か、人は一度しか死なないのかという疑問から始まった。この疑問から、まずプナルムリティ(再死)とプナラッティ(帰還)の概念が生まれた。[ 22 ] [ 46 ] [ 47 ]これらの初期の理論では、人間の存在の本質には2つの現実が含まれると主張された。1つは不変の絶対的アートマン(自己)であり、これはブラフマンと呼ばれる究極の不変の不滅の現実と至福に何らかの形で関連している。[ 48 ] [ 49 ]残りは現象世界(マーヤ)における常に変化する主体(身体)である。[ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]ヴェーダの神智学的思索において、死は「スヴァルガまたは天国で過ごした至福の年月」の終わりを反映しており、その後に現象界への再生が続く。[ 53 ]サンサーラは存在の本質に関する基礎理論へと発展し、すべてのインドの宗教に共有されている。[ 54 ]
ジョン・ボウカーは、人間としての再生は「再生の連鎖を断ち切り、解脱、つまりモクシャを得る稀有な機会」として提示されたと述べています。[ 49 ]インドの精神的伝統はそれぞれ、この精神的解放のために独自の仮定と道(マールガまたはヨガ)を発展させ、 [ 49 ]ジヴァンムクティ(現世での解放と自由)の考えを発展させたものもあれば、 [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]ヴィデハムクティ(来世での解放と自由)に満足するものもありました。 [ 58 ] [ 59 ]
最初の真実
最初の真理である苦しみ(パーリ語:dukkha、サンスクリット語:duhkha)は、 輪廻(文字通り「放浪」)と呼ばれる 輪廻の領域における存在の特徴です。
シュラマナ教の伝統(仏教とジャイナ教)は、紀元前6世紀頃から新しい考えを加えました。[ 62 ]彼らは、より大きな文脈で人間の苦しみを強調し、再生、再死、痛みの真実を宗教生活の中心に置き、それを開始点としました。[ 63 ]シュラマナ教は、アンサーラを開始のない循環的なプロセスと見なし、生と死をそのプロセスの句読点と見なし、[ 63 ]精神的な解放を再生と再生からの自由と見なします。[ 64 ]サンサーラの再生と再生の考えは、これらの宗教でさまざまな用語で議論されており、仏教の多くの初期のパーリ語のスートラでは、アーガティガティと呼ばれています。[ 65 ]
アイデアの進化
異なる宗教では、それぞれのインドの伝統において輪廻理論が発展するにつれて、異なる救済論が強調されました。 [ 15 ]これらの伝統では、輪廻からの脱出は行為を止めること(ジャイナ教、アージーヴィカ教)または存在の本質を悟ること(ウパニシャッド、仏教)によってなされると提唱されました。[ 66 ]
ヒンドゥー教の伝統では、サンサーラ理論においてアートマンまたは自己の存在を認め、それが各生物の不変の本質であると主張したのに対し、仏教の伝統ではそのような魂の存在を否定し、アナッター(無我)の概念を展開した。[ 54 ] [ 15 ] [ 67 ]ヒンドゥー教の伝統における救済(モクシャ、ムクティ)はアートマン(自己)とブラフマン(普遍的実体)の概念を用いて説明され、[ 68 ]仏教では(ニルヴァーナ、ニッバーナ)はアナッター(無我)とシュニャター(空)の概念を通して説明された。[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]
アージーヴィカの伝統は、輪廻転生と自由意志がないという前提を結びつけたが、ジャイナ教の伝統は、魂(これを「ジーヴァ」と呼ぶ)の概念を自由意志とともに受け入れたが、輪廻転生からの解放手段として、禁欲主義と行為の停止を強調した。これは束縛と呼ばれている。[ 72 ] [ 73 ]
ヒンドゥー教では
ヒンズー教では、サンサーラはアートマンの旅です。[ 74 ]肉体は死にますが、アートマンは死なず、アートマンは永遠の現実であり、破壊できず、至福です。[ 74 ]あらゆるもの、すべての存在はつながっており、循環しており、自己、つまりアートマンと肉体、つまり物質の2つで構成されています。[ 19 ]アートマンと呼ばれるこの永遠の自己は決して生まれ変わることがなく、ヒンズー教の信仰では変化せず、変化することができません。[ 19 ]対照的に、肉体と人格は変化することができ、常に変化し、生まれては死んでいきます。[ 19 ]現在のカルマは、今生での将来の状況だけでなく、将来の生命の形態と領域にも影響を与えます。[ 75 ] [ 76 ]ヒンズー教の人生観では、良い意図と行為は良い未来につながり、悪い意図と行為は悪い未来につながります。[ 77 ]輪廻の旅路は、アートマンに、生死のたびに善悪のカルマを実行し、解脱を得るために精神的な努力をする機会を与える。[ 78 ]
ヒンズー教徒は、徳の高い生活、つまりダルマに即した行いは、今生であれ来世であれ、より良い未来に貢献すると信じています。[ 79 ]バクティ(帰依)、カルマ(仕事)、ジニャーナ(知識)、ラージャ(瞑想)の道を問わず、精神的な追求の目的は、サムサーラからの自己解放(モクシャ)です。[ 79 ] [ 80 ]
ヒンドゥー教の聖典の一部であるウパニシャッドは、主に輪廻からの自己解放に焦点を当てています。[ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]バガヴァッド・ギーターは、解放への様々な道を論じています。[ 74 ]ハロルド・カワードは、ウパニシャッドは「人間の本質が完成する可能性に関して非常に楽観的な見解」を示しており、これらの聖典における人間の努力の目標は、輪廻を終わらせるための自己完成と自己認識への継続的な旅であると述べています。[ 84 ]ウパニシャッドの伝統における精神的探求の目的は、内なる真の自己を見つけ、自己を知ることであり、この状態が至福の自由、モクシャにつながると信じられています。[ 85 ]
ヒンドゥー教の伝統における違い
すべてのヒンドゥー教の伝統はサンサーラの概念を共有していますが、詳細やサンサーラからの解放の状態をどのように説明するかは異なります。[ 86 ]サンサーラは常に変化する現実またはマーヤ(外観、幻想)の時間世界における再生のサイクルと見なされ、ブラフマンは決して変わらないものまたはサット(永遠の真実、現実)として定義され、モクシャはブラフマンの実現とサンサーラからの解放です。[ 68 ] [ 87 ] [ 88 ]
ヒンズー教のマドヴァチャリヤのドヴァイタ・ヴェーダーンタ伝統などの二元論的信仰の伝統は有神論的前提を支持し、個々の人間の自己とブラフマン(ヴィシュヌ、クリシュナ)は2つの異なる現実であり、ヴィシュヌへの愛情深い信仰がサンサーラ(輪廻転生)から解放される手段であり、ヴィシュヌの恩寵がモクシャ(解脱)につながり、精神的な解放は来世(ヴィデーハムクティ)でのみ達成できると主張している。[ 89 ]ヒンズー教のアディ・シャンカラのアドヴァイタ・ヴェーダーンタ伝統などの非二元論的伝統は一元論的前提を支持し、個々のアートマンとブラフマンは同一であり、無知、衝動性、惰性のみがサンスサーラによる苦しみにつながると主張している。実際には二元性はなく、瞑想と自己認識が解放への道であり、自分のアートマンがブラフマンと同一であることの認識がモクシャであり、精神的な解放は今生で達成可能です(ジヴァンムクティ)。[ 71 ] [ 90 ]
ジャイナ教では

ジャイナ教では、サンサーラとカルマの教義がその神学的基礎の中心であり、ジャイナ教の主要宗派におけるこの教義に関する広範な文献や、ジャイナ教の伝統の最初期からのカルマとサンサーラに関する先駆的な考えによって証明されている。 [ 91 ] [ 92 ]ジャイナ教におけるサンサーラは、様々な存在の領域での絶え間ない再生と苦しみを特徴とする現世の生活を表している。[ 93 ] [ 92 ] [ 94 ]
輪廻転生の教義の概念的枠組みは、ジャイナ教の伝統と他のインド諸宗教とで異なっています。例えば、ジャイナ教の伝統では、魂(ジーヴァ)はヒンドゥー教の伝統と同様に真理として受け入れられていますが、仏教の伝統ではそうではありません。しかし、輪廻転生、すなわち輪廻は、ジャイナ教において明確な始まりと終わりを持っています。[ 95 ]
魂は原始の状態から旅を始め、サンサーラを通して絶えず進化している意識連続体の状態で存在します。[ 96 ]より高い状態に進化するものもあれば、退行するものもあります。この動きはカルマによって駆動されます。[ 97 ]さらに、ジャイナ教の伝統では、アーバーヴィヤ(無能)またはモクシャ(解脱)に達することのできない魂のクラスが存在すると信じられています。[ 95 ] [ 98 ]魂のアーバーヴィヤ状態は、意図的で衝撃的な邪悪な行為の後に入ります。[ 99 ]ジャイナ教では、魂はカルマとサンサーラのサイクルの中でそれぞれが多元的であると考えられており、ヒンズー教のアドヴァイタスタイルの非二元論や仏教のアドヴァイタスタイルの非二元論には賛同していません。[ 98 ]
ジャイナ教の神智学は、古代アジーヴィカと同様だが、ヒンドゥー教や仏教の神智学とは異なり、それぞれの魂は輪廻転生しながら840万回の誕生状況を通過すると主張する。[ 100 ] [ 101 ]パドマナーブ・ジャイニーによれば、魂の循環において、ジャイナ教の伝統では魂は土の体、水の体、火の体、風の体、植物の体の5種類の体を経ると考えられている。[ 102 ]降雨、農業、食事、呼吸など、人間と非人間のすべての活動によって、微小な生物が誕生したり死にかけたりしており、その魂は常に変化する体をしていると信じられている。ジャイナ教では、人間を含むあらゆる生命体を乱したり、傷つけたり、殺したりすることは罪であり、悪しきカルマの影響を及ぼすと考えられている。[ 103 ] [ 94 ]
ジャイナ教において解放された魂とは、輪廻を超え、頂点に達し、全知であり、永遠にそこに留まり、シッダとして知られる者のことである。[ 104 ]男性は、特に苦行を通して、解脱を達成する可能性を秘めた頂点に最も近い存在であると考えられている。ジャイナ教、特にディガンバラ派では、女性はカルマの功徳を積んで男性に生まれ変わり、そうして初めて精神的な解脱を達成できるとされている。 [ 105 ] [ 106 ]しかし、この見解は歴史的にジャイナ教内で議論されており、様々なジャイナ教派、特にシュヴェータンバラ派は、女性も輪廻からの解脱を達成できると信じている。[ 106 ] [ 107 ]
仏教経典は植物や小さな生命体を傷つけたり殺したりすることを明確に、あるいは明確に非難していないのに対し、ジャイナ教経典はそうしています。ジャイナ教では、植物や小さな生命体を傷つけることは、魂の輪廻に悪影響を及ぼす悪い業とみなされています。[ 108 ]しかし、仏教やヒンドゥー教の経典の中には、植物や種子を含むすべての生命体を傷つけることについて警告しているものもあります。[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
仏教では

ジェフ・ウィルソンによれば、仏教における輪廻とは「始まりも終わりもない、苦しみに満ちた生と死と再生の輪廻」である。 [ 112 ]輪廻は存在の輪(バーヴァチャクラ)とも呼ばれ、仏教の文献ではしばしばプナルバヴァ(再生、再生)という言葉とともに言及される。この存在の輪廻からの解放、涅槃は仏教の基盤であり、最も重要な目的である。[ 112 ] [ 113 ] [ 114 ]
仏教では、他のインドの宗教と同様に、輪廻は永続的なものと考えられています。ポール・ウィリアムズは、仏教思想においてこの永続的な輪廻はカルマによって駆動されると述べ、「悟りを得ない限り、人は生まれ変わり、死に、自らのカルマの完全に非個人的な因果性に従って、別の場所に生まれ変わる。この生、再生、そして再死の終わりのない輪廻こそが輪廻である」と述べています。[ 115 ]すべての仏教の伝統に受け入れられている四諦は、この輪廻に関連する再生(輪廻転生)とそれに伴う苦しみの輪廻を終わらせることを目的としているのです。[ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]
ジャイナ教と同様に、仏教も独自の輪廻転生理論を発展させ、それは、世俗的な存在の輪が再生と死を無限に繰り返す仕組みに関する機械論の詳細を、時間の経過とともに発展させた。[ 119 ] [ 120 ]初期の仏教の伝統では、輪廻転生の宇宙観は、存在の輪が循環する 5 つの領域で構成されていた。[ 112 ]これには、地獄 (ニラヤ)、餓鬼 (プレタ)、畜生 (ティリヤク)、人間 (マヌシャ)、神 (ディーヴァ、天界) が含まれていた。[ 112 ] [ 119 ] [ 121 ]後の伝統では、このリストは、初期の伝統で神の領域に含まれていた半神 (アスラ) を加えて、6 つの再生の領域のリストにまで拡大した。[ 112 ] [ 122 ]「餓鬼道、天国道、地獄道」はそれぞれ、現代の多くの仏教の伝統における儀式、文学、道徳の領域を形作っています。[ 112 ] [ 119 ]
仏教における輪廻の概念は、これら6つの世界は相互に関連しており、誰もが無知、欲望、そして目的のある業、つまり倫理的および非倫理的な行為の組み合わせにより、これらの世界を通過する来世の状態に過ぎないというものである。[ 112 ] [ 119 ] 仏教では、涅槃は一般的に再生からの解放であり、輪廻の苦しみに代わる唯一の選択肢であると説明されている。 [ 123 ] [ 124 ]しかし、スティーブン・コリンズによると、仏典は再生への恐怖から、より包括的な再生の理論を展開し、アマタ(死のない状態)と呼ばれ、涅槃と同義であると考えられている。[ 123 ] [ 125 ]
シク教では
シク教には、サンサーラ(シク教のテキストではSaṅsāraと綴られることもある)、カルマ、時間と存在の循環的な性質という概念が組み込まれている。 [ 126 ] [ 127 ] 15世紀に創設されたシク教の開祖グル・ナーナクは、古代インドの宗教の循環的な概念と時間の循環的な概念を取り入れたと、コールとサンビは述べている。[ 127 ] [ 128 ]しかし、アルヴィンド・パル・シン・マンダイルは、シク教のサンサーラ概念とヒンズー教内の多くの伝統におけるサンサーラ概念との間には重要な違いがあると述べています。[ 126 ]その違いは、シク教では救済への手段として神の恩寵を固く信じており、その戒律ではムクティ(救済)のために唯一の主へのバクティを奨励している点である。[ 126 ] [ 129 ]
シク教は、インドの三つの古代の伝統と同様に、肉体は滅びるもので、輪廻転生があり、輪廻転生ごとに苦しみがあると信じている。[ 126 ] [ 130 ]シク教のこれらの特徴は、サンサーラ(輪廻転生)と神の恩寵に対する信仰とともに、ヒンドゥー教内のバクティ(帰依)志向のいくつかの分派伝統、例えばヴァイシュナヴィズムに見られるものと類似している。[ 131 ] [ 132 ]シク教は、ジャイナ教で推奨されているような禁欲生活が解放への道であるとは考えていない。むしろ、グルとしての唯一の神への信仰と組み合わされた社会活動と世帯生活こそが、サンサーラからの解放への道であると信じている。[ 133 ]
参照
参考文献
引用
- ^ a b c d eマーク・ユルゲンスマイヤー&ウェイド・クラーク・ルーフ 2011年、271~272頁。
- ^ a bロクテフェルド 2002、589ページ。
- ^ a bクラウス・クロスターマイヤー、2010 年、p. 604.
- ^ a b c d e f g Bodewitz, Henk (2019). 「第1章 ヒンドゥー教における輪廻転生の教義:その起源と背景」. Heilijgers, Dory H.; Houben, Jan EM; van Kooij, Karel (編). 『ヴェーダの宇宙論と倫理:選集』 . Gonda Indological Studies. 第19巻.ライデンおよびボストン:ブリル出版社. pp. 3– 19. doi : 10.1163/9789004400139_002 . ISBN 978-90-04-40013-9. ISSN 1382-3442 .
- ^ a b cリタ・M・グロス(1993年)『家父長制後の仏教:フェミニストによる仏教の歴史、分析、再構築』ニューヨーク州立大学出版局、 148頁、ISBN 978-1-4384-0513-1。
- ^ a b c dシャーリー・ファース (1997). 『英国のヒンドゥー教徒コミュニティにおける死と死別』ピーターズ出版社. pp. 106, 29– 43. ISBN 978-90-6831-976-7。
- ^ Yadav, Garima (2018)、「中絶(ヒンドゥー教)」、ヒンドゥー教と部族宗教、インド宗教百科事典、Springer Netherlands、pp. 1– 3、doi : 10.1007/978-94-024-1036-5_484-1、ISBN 978-9402410365
- ^フラッド、ギャビン・D.(1996年)、ヒンドゥー教入門、ケンブリッジ大学出版局
- ^ AM Boyer:サムサラ教義の起源の練習曲。 Journal Asiatique、(1901)、第 9 巻、第 18 号、S. 451–53、459–68
- ^ユブラージ・クリシャン: 。バーラティヤ ヴィディヤ バワン、1997、 ISBN 978-81-208-1233-8
- ^ a b c午前Boyer (1901)、「サムサラ教義の原点の練習」、Journal Asiatique、第 9 巻、第 18 号、451 ~ 53、459 ~ 68 ページ
- ^ a b cスティーブン・J・ラウマキス 2008年、90~99頁。
- ^ a bユブラジ・クリシュナン (1997). 『カルマの教義:ブラフマニカル、仏教、ジャイナ教における起源と発展』 バラティヤ・ヴィディヤ・バヴァン. pp. 17– 27. ISBN 978-81-208-1233-8。
- ^ Obeyesekere 2005、pp. 1–2、108、126–28。
- ^ a b cマーク・ユルゲンスマイヤー&ウェイド・クラーク・ルーフ 2011年、272~273頁。
- ^マイケル・マイヤーズ 2013年、36ページ。
- ^ハロルド・カワード 2008年、103ページ。
- ^ a bユブラジ・クリシャン(1988年)「カルマは進化論か?」インド哲学研究評議会ジャーナル、第6巻、24~26頁
- ^ a b c dジーニーン・D・ファウラー 1997年、10ページ。
- ^ a b c d eモニエ・モニエ=ウィリアムズ (1923). 『サンスクリット語-英語辞典』 オックスフォード大学出版局. pp. 1040–41 .
- ^「Samsara」ヒンドゥー教百科事典、Mandala Publishing、2013年、147ページ。
- ^ a bウェンディ・ドニガー (1980). 『インド古典伝統におけるカルマと再生』カリフォルニア大学出版局. pp. 268–69 . ISBN 978-0-520-03923-0。
- ^スティーブン・J・ラウマキス 2008年、97ページ。
- ^ Goa, David J.; Coward, Harold G. (2014年8月21日). 「ヒンドゥー教」 .カナダ百科事典. 2014年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月31日閲覧。
- ^ジェームズ・ヘイスティングス、ジョン・アレクサンダー・セルビー、ルイス・ハーバート・グレイ (1922). 『宗教と倫理百科事典』 T. & T. クラーク. pp. 616–18 . ISBN 9780567065124。
{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ a b cジェシカ・フレイザー&ギャビン・フラッド 2011年、84~86頁。
- ^クスム・P・メル(1996年)『あの世の栄光の主、ヤマ』ペンギン社、 213~ 15頁。ISBN 978-81-246-0066-5。
- ^アニタ・ライナ・タパン (2006). 『ペンギン・スワミ・チンミヤナンダ読本』 ペンギンブックス. pp. 84– 90. ISBN 978-0-14-400062-3。
- ^パトゥル・リンポチェ、ダライ・ラマ(1998年)『我が完璧な師の言葉:チベット仏教入門の古典の完全翻訳』ロウマン・アルタミラ、 95~ 96頁。ISBN 978-0-7619-9027-7。
- ^ a bルイ・ド・ラ・ヴァレー=プッサン(1917). 『涅槃への道:救済の修行としての古代仏教に関する6つの講義』 ケンブリッジ大学出版局. pp. 24– 29.
- ^ユブラジ・クリシュナン (1997). 『カルマの教義:ブラフマニカル、仏教、ジャイナ教における起源と発展』 Bharatiya Vidya Bhavan. pp. 11– 15. ISBN 978-81-208-1233-8。
- ^ a b cスティーブン・J・ラウマキス 2008年、90ページ。
- ^ダラル 2010、344、356–57 ページ。
- ^ダミアン・キーオン 2004年、248ページ。
- ^カタ・ウパニシャッド प्रथमोध्यायः/तृतीयवल्ली 2020 年 8 月 8 日、ウェイバック マシンにアーカイブウィキソース
- ^ Shvetashvatara Upanishad षष्ठः अध्यायः 2020 年 10 月 26 日にウェイバック マシンにアーカイブウィキソース
- ^マイトリ・ウパニシャッド、2020年 11 月 21 日にウェイバック マシンウィキソースにアーカイブ、引用:तत्प्रयत्नेन शोधयेत्
- ^ GA Jacob (1963)、『主要ウパニシャッドとバガヴァッド ギーターへの一致』、Motilal Banarsidass、947–48 ページ
- ^ノーマン・C・マクレランド (2010). 『輪廻とカルマ百科事典』マクファーランド. pp. 102–03 . ISBN 978-0-7864-5675-8。
- ^クリフトン・D・ブライアント、デニス・L・ペック(2009年)『死と人間の経験百科事典』SAGE出版、 pp.841-46、ISBN 978-1-4522-6616-9。
- ^ヴァレー・プッサン(1917年)『涅槃への道:救済の修行としての古代仏教に関する6つの講義』ケンブリッジ大学出版局、 24~ 25頁。
- ^ギャビン・D・フラッド(1996年)『ヒンドゥー教入門』ケンブリッジ大学出版局、 ISBN 978-0521438780、86ページ、引用:「カルマと輪廻の起源と教義は不明瞭である。これらの概念は確かに修行僧の間で広まっており、ジャイナ教と仏教は輪廻の過程について具体的かつ洗練された考えを展開した。カルマと輪廻転生が、修行僧あるいは出家者の伝統から主流のバラモン教思想に入り込んだ可能性は高い。しかし一方で、ヴェーダの賛歌には輪廻転生の明確な教義は存在しないものの、この世で死んだ人が来世で再び死ぬ可能性があるという再死の考えが存在する。」
- ^パドマナブ・S・ジャイニ、2001年「仏教研究に関する論文集」Motilal Banarsidass、 ISBN 81-208-1776-1、51ページ、引用:「ヤジュニャヴァルキヤがカルマの教義を公の場で議論することを躊躇したのは、おそらく、カルマがアートマンの輪廻と同様に、非バラモン教的な起源を持つという仮定によって説明できるだろう。この教義がシュラマナ経典のほぼすべてのページに記されているという事実を考慮すると、カルマがそこから派生したものである可能性は非常に高い。」
- ^ Govind Chandra Pande、(1994) Sankaracarya の生涯と思想、Motilal Banarsidass ISBN 81-208-1104-6、135ページ、引用:(…)これらのシュラマナは、それ自体が謎めいたハラッパー文明と関連していた可能性がある。ヤジュニャヴァルキヤのようなウパニシャッドの思想家の中には、この種の(シュラマナ的な)思考に精通していた者もいたようで、(…)カルマ、輪廻、解脱といったこれらの考えを伝統的なヴェーダ思想に取り入れようとした者もいた。
- ^ウェンディ・ドニガー (1980). 『インド古典伝統におけるカルマと再生』カリフォルニア大学出版局. pp. xvii– xviii. ISBN 978-0-520-03923-0。引用: 「ヴェーダ教と仏教は初期に非常に頻繁に交流していたため、多くの教義の初期の源泉を整理しようとするのは無駄である。両者はピカソとブラックのように、互いの懐に潜んでいたのだ(二人は後年、同じ初期の時代にどちらが特定の絵画を描いたのかを言えなくなった)。」
- ^ブイテネン 1957、34–35 ページ。
- ^ミルチャ・エリアーデ、1987 年、56–57 ページ。
- ^ジェシカ・フレイザー&ギャビン・フラッド 2011年、18ページ。
- ^ a b cジョン・ボウカー 2014年、84~85頁。
- ^ジェシカ・フレイザー&ギャビン・フラッド 2011年、18~19頁、24~25頁。
- ^ハロルド・カワード 2012年、29~31頁。
- ^ John Geeverghese Arapura 1986、85–88 ページ。
- ^ロバート・S・エルウッド、グレゴリー・D・アレス (2007). 『世界宗教百科事典』 Infobase Publishing. pp. 406–07 . ISBN 978-1-4381-1038-7。
- ^ a b Obeyesekere 1980、pp.139–40。
- ^クラウス・クロスターマイヤー「モクシャと批判理論」『東西哲学』第35巻第1号(1985年1月)、61-71頁
- ^ノーマン・E・トーマス(1988年4月)「生命のための解放:ヒンドゥー教の解放哲学」『宣教学』第16巻第2号、149~160ページ
- ^ Gerhard Oberhammer (1994)、La Délivrance dès cette vie: Jivanmukti、Collège de France、Publications de l'Institut de Civilization Indienne。セリエ in-8°、Fasc. 61、Edition–Diffusion de Boccard (パリ)、 ISBN 978-2868030610、1~9ページ
- ^ M. von Brück (1986)「模倣か同一化か?」インド神学研究第23巻第2号、95~105頁
- ^ポール・デューセン『ウパニシャッドの哲学』 356ページ、 Googleブックス、356~357ページ
- ^四諦、仏教哲学、Wayback Machineで2016年4月22日にアーカイブ、ドナルド・ロペス、ブリタニカ百科事典
- ^ロバート・E・バスウェル・ジュニア;ドナルド S. ロペス ジュニア (2013)。プリンストン仏教辞典。プリンストン大学出版局。ページ 304–05。ISBN 978-1-4008-4805-8。
- ^マイケル・マイヤーズ 2013年、79ページ。
- ^ a bマイケル・マイヤーズ 2013年、79~80頁。
- ^ポール・ウィリアムズ、アンソニー・トライブ(2000年)『仏教思想:インドの伝統への完全入門』ラウトレッジ、 18~ 19ページ、第1章。ISBN 0-415207002。
- ^ Thomas William Rhys Davids; William Stede (1921). Pali-English Dictionary . Motilal Banarsidass. pp. 94– 95, Āgatiの項目. ISBN 978-81-208-1144-7。
{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ George L Jart III (1980). Wendy Doniger (編). Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions . University of California Press. pp. 131–33 . ISBN 978-0-520-03923-0。
- ^ [a]無我Archived 10 December 2015 at the Wayback Machine、Encyclopædia Britannica (2013)、引用:「仏教における無我とは、人間には永続的な根底にある魂は存在しないという教義である。無我、あるいは無我の概念は、ヒンドゥー教のアートマン(「自己」)信仰とは異なる。」; [b] Steven Collins (1994)、『宗教と実践理性』(編集者:Frank Reynolds、David Tracy)、ニューヨーク州立大学出版局、 ISBN 978-0791422175、64ページ。「仏教の救済論の中心となるのは無我の教義(パーリ語:アナッター、サンスクリット語:アートマン、これと対立するアートマンの教義はバラモン教の思想の中心である)である。簡単に言えば、これは、人間には魂も自我も不変の本質もないという[仏教の]教義である。」;[c]エドワード・ローア(翻訳者)、シャンカラ序文、2ページ、Googleブックスのブリハド・アーラニヤカ・ウパニシャッド、2~4ページ;[d]ケイティ・ジャバノード(2013年)、仏教の「無我」教義は涅槃の追求と両立するか? 2015年2月6日にウェイバックマシンにアーカイブ、Philosophy Now;[e]デイヴィッド・ロイ(1982)『仏教における悟りとアドヴァイタ・ヴェーダーンタ:涅槃と解脱は同じか?』国際哲学季刊誌、第23巻第1号、65~74頁;[f] KNジャヤティレケ(2010)『初期仏教の知識理論』ISBN 978-8120806191、pp. 246–49、注385以降。
- ^ a b Moksha Archived 25 October 2020 at the Wayback Machine , Georgetown University
- ^スティーブン・J・ラウマキス 2008年、68~70頁、125~128頁、149~153頁、168~176頁。
- ^阿部正夫;スティーブン・ハイネ (1995)。仏教と諸宗教の対話。ハワイ大学出版局。ページ 7 – 8、73 – 78。ISBN 978-0-8248-1752-7。
- ^ a bロイ、デイヴィッド (1982). 「仏教における悟りとアドヴァイタ・ヴェーダーンタ:涅槃と解脱は同じか?」国際哲学季刊誌22 ( 1): 65– 74. doi : 10.5840/ipq19822217 .
- ^ Padmanabh S Jaini, George L Jart III (1980). Wendy Doniger (編). Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions . University of California Press. pp. 131–33 , 228–29 . ISBN 978-0-520-03923-0。
- ^クリストファー・パートリッジ (2013). 『世界宗教入門』 フォートレス・プレス. pp. 245–46 . ISBN 978-0-8006-9970-3。
- ^ a b cマーク・ユルゲンスマイヤー&ウェイド・クラーク・ルーフ 2011年、272ページ。
- ^ムクル・ゴエル (2008). 『Devotional Hinduism: Creating Impressions for God』 iUniverse. p. 6. ISBN 978-0-595-50524-1。
- ^クリストファー・チャップル(1986年)『カルマと創造性』ニューヨーク州立大学出版局、 ISBN 0-88706-251-2、60~64ページ
- ^ジーニーン・D・ファウラー 1997年、11ページ。
- ^ミシュラ、RC(2013)「モクシャとヒンドゥー教の世界観」SAGE出版、 22~ 24頁 。
- ^ a b Flood, Gavin (2009年8月24日). 「ヒンドゥー教の概念」 . BBCオンライン. BBC . 2014年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月31日閲覧。
- ^ジョージ・D・クリシデス、ベンジャミン・E・ゼラー(2014). 『ブルームズベリー新宗教運動コンパニオン』ブルームズベリー・アカデミック、333ページ。ISBN 978-1-4411-9829-7。
- ^ジーニーン・D・ファウラー 1997年、111~112ページ。
- ^ヨン・チュン・キム、デイヴィッド・H・フリーマン (1981). 『東洋思想:アジアの哲学・宗教思想入門』ロウマン&リトルフィールド. pp. 15– 17. ISBN 978-0-8226-0365-8。
- ^ジャック・シコラ (2002). 『インドの宗教:ヒンドゥー教、仏教、シク教、ジャイナ教へのユーザーフレンドリーで簡潔な入門』 iUniverse. pp. 17– 19. ISBN 978-1-4697-1731-9。
- ^ハロルド・カワード 2008年、129ページ。
- ^ハロルド・カワード 2008年、129、130–55頁。
- ^ジーニーン・D・ファウラー 1997年、10~12頁、132~137頁。
- ^ H・チャウドゥリ(1954)「ヒンドゥー哲学におけるブラフマンの概念」『東西哲学』4(1)、47-66頁
- ^ M. ヒリヤナ (1995)。インド哲学の要点。モティラル・バナルシダス。24–25、160–66ページ 。ISBN 978-81-208-1330-4。
- ^ジーニーン・D・ファウラー 2002年、340~347頁、373~375頁。
- ^ジーニーン・D・ファウラー 2002年、238〜240頁、243〜245頁、249〜250頁、261〜263頁、279〜284頁。
- ^ Jaini 1980、217–36ページ。
- ^ a bポール・ダンダス (2003). 『ジャイナ教』 ラウトレッジ. pp. 14– 16, 102– 05. ISBN 978-0415266055。
- ^ Jaini 1980、226~228頁。
- ^ a bタラ・セシア (2004)。アヒムサー、アネカンタ、ジャイナ教。モティラル・バナルシダス。ページ 30–31。ISBN 978-81-208-2036-4。
- ^ a b Jaini 1980、226ページ。
- ^ Jaini 1980、227ページ。
- ^ Jaini 1980、227~228頁。
- ^ a bポール・ダンダス (2003). 『ジャイナ教』 ラウトレッジ. pp. 104–05 . ISBN 978-0415266055。
- ^ Jaini 1980、225ページ。
- ^ Jaini 1980、228ページ。
- ^パドマナブ S. ジャイニ (2000)。ジャイナ教研究に関する論文を集めました。モティラル・バナルシダス。130 ~ 31ページ 。ISBN 978-81-208-1691-6。
- ^ Jaini 1980、223~224頁。
- ^ Jaini 1980、224~225頁。
- ^ Jaini 1980、222~223頁。
- ^ジェフリー・D・ロング(2013年)『ジャイナ教入門』 IBタウリス、 pp.36-37、ISBN 978-0-85773-656-7。
- ^ a bグラハム・ハーヴェイ (2016). 『宗教に焦点を当てる:伝統と現代の実践への新たなアプローチ』ラウトレッジ. pp. 182–83 . ISBN 978-1-134-93690-8。
- ^ポール・ダンダス (2003). 『ジャイナ教』 ラウトレッジ pp. 55– 59. ISBN 978-0415266055。
- ^ a bランバート・シュミットハウゼン(1991)『仏教と自然』、仏教哲学研究、国際仏教研究所、東京、pp. 6–7
- ^ロッド・プリース(1999年)、動物と自然:文化的神話、文化的現実、 ISBN 978-0-7748-0725-8ブリティッシュコロンビア大学出版局、pp. 212–17
- ^クリストファー・チャップル(1990)「エコロジカル非暴力とヒンドゥー教の伝統」『非暴力の視点』シュプリンガー、 ISBN 978-1-4612-4458-5、168–77ページ。L. Alsdorf (1962)、Beiträge zur Geschichte von Vegetableismus und Rinderverehrung in Indien、Akademie der Wissenschaften und der Literatur、F. Steiner Wiesbaden、592–93 ページ
- ^パトゥル・リンポチェ、ダライ・ラマ(1998年)『我が完璧な師の言葉:チベット仏教入門の古典の完全翻訳』ロウマン・アルタミラ、 61~ 99頁。ISBN 978-0-7619-9027-7。
- ^ a b c d e f gジェフ・ウィルソン (2010). 『仏教における輪廻と再生』オックスフォード大学出版局. doi : 10.1093/obo/9780195393521-0141 . ISBN 978-0195393521。
- ^エドワード・コンゼ(2013年)『インドにおける仏教思想:仏教哲学の三相』ラウトレッジ、p.71、ISBN 978-1-134-54231-4。引用:「涅槃は仏教の存在理由であり、その究極の正当化である。」
- ^ゲシン 1998、119ページ。
- ^ウィリアムズ 2002、74~75ページ。
- ^ポール・ウィリアムズ、アンソニー・トライブ、アレクサンダー・ウィン 2012年、30~42ページ。
- ^ロバート・バスウェル・ジュニア & ドナルド・ロペス・ジュニア 2013、304–05 ページ。
- ^ピーター・ハーヴェイ (2015). スティーブン・M・エマニュエル編. 『仏教哲学入門』 . ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. pp. 26– 44. ISBN 978-1-119-14466-3。引用:「上記のDCPS(律蔵経)のダンマ・チャッカ・パヴァターナ・スータ(法華経)で苦痛(ドゥッカ)として最初に述べられている特徴は、生きる上での基本的な生物学的側面であり、それぞれがトラウマとなり得る。これらのドゥッカは、仏教の輪廻転生の観点によってさらに複雑化している。輪廻転生には、繰り返しの生、老い、病、そして死が含まれるからである。」
- ^ a b c dケビン・トレイナー (2004). 『仏教:図解ガイド』 オックスフォード大学出版局. pp. 62– 63. ISBN 978-0-19-517398-7。引用:「仏教の教義では、衆生は涅槃に達するまで、無知と欲望に基づいて行動したために輪廻転生を繰り返し、その結果、業の種を生み出すとされています。」
- ^ダライ・ラマ 1992、pp. xi–xii、5–16。
- ^ロバート・デカロリ(2004年)『ブッダを悩ます:インドの民衆宗教と仏教の形成』オックスフォード大学出版局、 94~ 103頁。ISBN 978-0-19-803765-1。
- ^定方昭 (1997).仏教宇宙論: 哲学と起源。佼成出版社佼成出版社、東京。68 ~ 70ページ 。ISBN 978-4-333-01682-2。
- ^ a bスティーブン・コリンズ (2010).ニルヴァーナ:概念、イメージ、物語. ケンブリッジ大学出版局. p. 38. ISBN 978-0-521-88198-2。
- ^カール・B・ベッカー(1993年)『円環を破る:仏教における死と来世』南イリノイ大学出版局、pp. viii, 57– 59. ISBN 978-0-8093-1932-9。
- ^フランク・J・ホフマン(2002年)『初期仏教における合理性と心』モティラル・バナルシダス、pp. 103– 06. ISBN 978-81-208-1927-6。
- ^ a b c dアルヴィンド・パル・シン・マンダイル(2013年)『シク教:迷える人々のためのガイド』ブルームズベリー・アカデミック、pp. 145– 46, 181, 220. ISBN 978-1-4411-5366-1。
- ^ a b W.O. Cole; Piara Singh Sambhi (2016). Sikhism and Christianity: A Comparative Study . Springer. pp. 13– 14. ISBN 978-1-349-23049-5。
- ^アルヴィンド・パル・シン・マンダイル(2013年)『シク教:迷える人々のためのガイド』ブルームズベリー・アカデミック、176頁。ISBN 978-1-4411-5366-1。
- ^ HS Singha (2000). 『シク教百科事典』 ヘムクント出版社. pp. 68, 80. ISBN 978-81-7010-301-1。
- ^パシャウラ・シン、ルイス・E・フェネク(2014年)『オックスフォード・ハンドブック・オブ・シク教研究』オックスフォード大学出版局、231~607頁。ISBN 978-0-19-100411-7。
- ^ジェームズ・スローワー (1999). 『宗教:古典理論』 ジョージタウン大学出版局. p. 40. ISBN 978-0-87840-751-4。
- ^ JS Grewal (2006). 『中世インドにおける宗教運動と制度』オックスフォード大学出版局. pp. 394–95 . ISBN 978-0-19-567703-4。
- ^パシャウラ・シン、ルイス・E・フェネク(2014年)『オックスフォード・ハンドブック・オブ・シク教研究』オックスフォード大学出版局、pp. 230–31 . ISBN 978-0-19-100411-7。
出典
- ジョン・ギーヴァーゲーズ・アラプラ(1986年)『ヴェーダーンティック論に関する解釈学的エッセイ』モティラル・バナルシダス、ISBN 978-81-208-0183-7。
- ブイテネン、JAB ヴァン (1957)。 「ダルマとモクサ」。東洋と西洋の哲学。7 (1/2): 33–40 .土井: 10.2307/1396832。JSTOR 1396832。
- ジョン・ボウカー(2014年)『神:ごく短い入門』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-870895-7。
- ロバート・バスウェル・ジュニア、ドナルド・ロペス・ジュニア (2013). 『プリンストン仏教辞典』 プリンストン大学出版局. ISBN 978-1-4008-4805-8。
- ハロルド・カワード(2008年)『東洋と西洋の思想における人間性の完成可能性:中心的物語』ニューヨーク州立大学出版局、ISBN 978-0-7914-7336-8。
- ハロルド・カワード(2012年)『ホスピス緩和ケアにおける良き死の宗教的理解』ニューヨーク州立大学出版局、ISBN 978-1-4384-4275-4。
- ダラル、ロシェン(2010年)『ヒンドゥー教:アルファベット順ガイド』ペンギンブックス、ISBN 978-0-14-341421-6。
- ミルチャ・エリアーデ(1987年)『宗教百科事典』マクミラン社、ISBN 978-0-02-909480-8。
- ジーニーン・D・ファウラー(1997年)『ヒンドゥー教:信仰と実践』サセックス・アカデミック・プレス、ISBN 978-1-898723-60-8。
- ジーニーン・D・ファウラー(2002年)『現実の視点:ヒンドゥー教哲学入門』サセックス・アカデミック・プレス、ISBN 978-1-898723-93-6。
- ジェシカ・フレイザー、ギャビン・フラッド(2011年)『ヒンドゥー研究のためのコンティニュアム・コンパニオン』ブルームズベリー・アカデミック、ISBN 978-0-8264-9966-0。
- ゲシン、ルパート(1998年)『仏教の基礎』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0192892232。
- ジャイニ、パドマナーブ(1980年)。ドニガー、ウェンディ(編)『インド古典伝統におけるカルマと再生』カリフォルニア大学出版局。ISBN 978-0-520-03923-0。
- マーク・ユルゲンスマイヤー、ウェイド・クラーク・ルーフ(2011年)『世界宗教百科事典』 SAGE出版。ISBN 978-1-4522-6656-5。
- ダミアン・キーオン(2004年)『仏教辞典』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-157917-2。
- クラウス・クロスターマイヤー(2010年)『ヒンドゥー教概論:第3版』ニューヨーク州立大学出版局、ISBN 978-0-7914-8011-3。
- ダライ・ラマ(1992年)『人生の意味』、ジェフリー・ホプキンス訳・編、ウィズダム社、ISBN 978-1459614505。
- スティーブン・J・ラウマキス(2008年)『仏教哲学入門』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-1-139-46966-1。
- ロクテフェルド、ジェームズ(2002年)『図解ヒンドゥー教百科事典 第2巻:ニュージーランド』ローゼン出版ISBN 978-0-8239-2287-1。
- マイケル・マイヤーズ(2013年)『ブラフマン:比較神学』ラウトレッジ、ISBN 978-1-136-83565-0。
- オベイセケレ、ガナナス(1980年)。ウェンディ・ドニガー編『インド古典伝統におけるカルマと再生』カリフォルニア大学出版局。ISBN 978-0-520-03923-0。
- オベイセケレ、ガナナス(2005年)。ウェンディ・ドニガー編。『カルマと再生:異文化研究』。モティラル・バナルシダス。ISBN 978-8120826090。
- Sangave、Vilas Adinath (1980)、Jain Community: A Social Survey (第 2 版)、ボンベイ: Popular Prakashan、ISBN 978-0-317-12346-3
- ウィリアムズ、ポール(2002年)『仏教思想』ラウトレッジ、ISBN 0-415207010。
- ポール・ウィリアムズ、アンソニー・トライブ、アレクサンダー・ウィン(2012年)『仏教思想』ラウトレッジ、ISBN 978-1-136-52088-4。
さらに読む
- ダンダス、ポール(2002) [1992]. 『ジャイナ教』(第2版). ロンドンおよびニューヨーク: ラウトレッジ. ISBN 978-0-415-26605-5。
- ジャイニ、パドマナブ S. 編(2000年)。ジャイナ教研究に関する論文集(初版)。デリー:モティラル・バナルシダス。ISBN 978-81-208-1691-6。
- セシア、タラ (2004)。アヒンサー、アネカンタ、ジャイナ教。モティラル・バナルシダス。ISBN 978-81-208-2036-4。
外部リンク
- 輪廻転生:簡単な説明
- 生命の輪、C. ジョージ・ボーリー、シッペンズバーグ大学
- 輪廻と再生、仏教、オックスフォード書誌
.jpg/440px-Meerabai_(crop).jpg)