エージェンシー(社会学)
| シリーズの一部 |
| 社会学 |
|---|
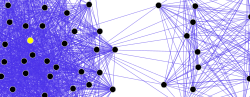 |
社会科学において、エージェンシーとは、個人が潜在能力を発揮するための力と資源を有する能力のことである。社会構造は、主体とその意思決定を決定または制限する影響要因(社会階級、宗教、性別、民族、能力、慣習など)から構成される。[ 1 ]構造とエージェンシーの影響については議論があり、個人の行動が社会システムによってどの程度制約されるかは明確ではない。
主体性とは、自らの意志に基づいて行動する独立した能力、あるいは能力のことです。この能力は、経験を通して形成された認知的信念構造、そして社会や個人が、自分が置かれている環境の構造や状況、そして自分が生まれた立場について抱いている認識によって影響を受けます。主体性の程度に関する意見の相違は、親と子など、当事者間の対立を引き起こすことがよくあります。
歴史
行為主体性という概念は啓蒙時代から存在し、人間の自由は道具的合理性によって表現されるのか、それとも道徳的・規範に基づいた行為によって表現されるのかという議論があった。ジョン・ロックは自由は利己心に基づくべきだと主張した。彼は伝統の束縛と社会契約の概念を否定し、行為主体性を人間が自らの生きる環境を形作る能力と捉えるようになった。[ 2 ]ジャン=ジャック・ルソーは自由を道徳的意志として捉え、別の概念を探求した。イマヌエル・カントが論じた合理的功利主義的側面と非合理的規範的側面の間には分岐があった。カントは自由を定言命法によって支配される規範に根ざした個人の意志とみなした。これらの考えは、合理的道具的行為に関する見解とは対照的に、古典社会学理論における非合理的で規範志向的な行為に関する懸念の出発点となった。[ 3 ]
これらの行為主体性の定義は、19世紀に哲学者たちが人間の選択は制御不能な力によって決定されると主張し始めるまで、ほとんど疑問視されることはなかった。[ 3 ]例えば、カール・マルクスは近代社会において人々はブルジョワジーのイデオロギーに支配されていると主張し、フリードリヒ・ニーチェは人間が自らの利己的な欲望、すなわち「権力への意志」に基づいて選択を行うと主張した。そして有名なポール・リクールは、人間の行動の無意識的な決定要因を説明した「疑念学派」の3人目の人物としてフロイトを加えた。 [ 4 ]ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが『哲学探究』の中で述べた規則遵守と私的言語の議論も、チャールズ・テイラーの著作などにおいて行為主体性の議論に取り入れられている。[ 5 ]
定義とプロセス
エージェンシーは、アメリカ社会学誌において、反復、投影、実践的評価という3つの異なる構成要素を包含する、時間的に埋め込まれたプロセスとして定義されています。 [ 3 ]これらの要素はそれぞれ、エージェンシー全体の構成要素です。これらは、エージェンシーの様々な側面を独立して研究し、より大きな概念についての結論を導き出すために使用されます。エージェンシーにおける反復要素は、過去の思考パターンと行動パターンの選択的な再活性化を指します。このように、行為者は典型的な状況に応じて日常的な行動をとり、それが時間の経過とともにアイデンティティ、相互作用、そして制度を維持するのに役立ちます。投影要素は、行為者の将来への希望、恐れ、そして願望と結びついた、将来の行動の可能性のある軌道を想像するプロセスを包含します。[ 3 ]最後の要素である実践的評価要素は、文脈、要求、あるいは現在進行している状況に応じて、人々が複数の可能な行動の中から実践的かつ規範的な判断を下す能力を意味します。[ 3 ]
ヒューソンの分類
ヨーク大学ヨーク国際安全保障研究センター准教授のマーティン・ヒューソン氏[ 6 ]は、エージェンシーを個人、代理、集団の3種類に分けていると説明しています。個人エージェンシーとは、個人が自分自身のために行動する場合で、代理エージェンシーとは、個人が他の人(雇用主など)のために行動する場合です。集団エージェンシーは、社会運動など、人々が一緒に行動する場合に発生します。ヒューソン氏はまた、エージェンシーを生み出す人間の3つの特性として、意図性、力、合理性を挙げています。人間は意図を持って行動し、目標志向です。また、能力や資源の量は人によって異なり、その結果、ある人は他の人よりも大きなエージェンシー(力)を持っています。最後に、人間は知性を使って自分の行動を導き、行動の結果を予測します。
会話の中で
会話的エージェンシーに関する研究において、デイヴィッド・R・ギブソンは、エージェンシーを「行為者の特異な目的を促進する行動であるが、同時にその行為自体を抑制する可能性も秘めている局所的な制約に直面している」と定義している。[ 7 ]誰が話しているか、参加者間でどのように参加が移行するか、話題性や関連性といった制約は、エージェンシーの表現可能性に影響を与える可能性がある。こうした制約の「緩さ」が許す瞬間を捉えることで、ユーザーはギブソンが「口語的エージェンシー」と呼ぶものを表現できるようになる。[ 8 ]
感情
社会心理学者ダニエル・ウェグナーは、「コントロール錯覚」が、人々が自分が引き起こしていない出来事を自分の功績だと思い込む原因となる可能性について論じています。[ 9 ]このような誤った行為主体性判断は、特にストレス下、あるいは出来事の結果が個人が望んだものであった場合に生じます(自己奉仕バイアスも参照)。ジャネット・メトカーフとその同僚は、行為主体性判断に用いられる他のヒューリスティック、つまり経験則を特定しました。[ 10 ]これらには、「順方向モデル」が含まれます。これは、心が行為主体性を判断するために、実際に2つの信号を比較するものです。1つは動作からのフィードバックですが、もう1つは「遠心性コピー」、つまり動作からのフィードバックがどのように感じられるかを精神的に予測するものです。トップダウン処理(状況の理解やその他の考えられる説明)も行為主体性判断に影響を与える可能性があります。さらに、あるヒューリスティックが他のヒューリスティックよりも相対的に重要度が高いかどうかは、年齢とともに変化するようです。[ 11 ]
進化論的な観点から見ると、行為主体性の錯覚は、社会的な動物が最終的に他者の行動を予測することを可能にする上で有益であると考えられる。[ 12 ]自分が意識のある主体であると考えるならば、行為主体性の性質は自然に他者に直観されるであろう。他者の意図 を推測することは可能であるため、行為主体性の仮定は、それらの意図から他者がどのような行動をとる可能性があるかを推測することを可能にする。
ヘンドリックス・カレッジの哲学准教授、ジェームズ・M・ダウは、他の状況下において相互にコントロール感を持つ二人の主体間の協力を「共同エージェンシー」と定義しています。[ 13 ]協力に関する楽観的な見解に関する様々な研究によると、「共に物事を行っているという意識は、協力する主体の経験が、活動が共同コントロール下にあるという肯定的な「今ここ」の経験を伴うことを示唆している」とのことです。[ 14 ]共有エージェンシーは、あらゆる状況において協力する者間のコントロール量を増加させますが、その代償として、コントロールするパートナーが関わる個人に悪影響を及ぼす可能性があります。既に権力のある二人が共同エージェンシーを持つ場合、パートナーの高められたエージェンシー感は、自分より下位の者に直接影響を及ぼします。下位の者のエージェンシー感は、上位の者が共同コントロールを行うと、威圧感や孤独感といった要因によって低下する可能性が高くなります。共通の目標に向かって共に働くことはエージェンシー感を高める傾向がありますが、コントロールの膨張は多くの予期せぬ結果をもたらす可能性があります。
子供たち
子どもの主体性は、大人の指導なしには自分で合理的な判断を下すことができないという一般的な考えのために、考慮されないことが多い。[ 15 ]
参照
参考文献
- ^バーカー、クリス. 2005.『カルチュラル・スタディーズ:理論と実践』 ロンドン:セージ. ISBN 0-7619-4156-8 p448
- ^リトルジョン, スティーブン・W. & フォス, カレン・A. (2009). エージェンシー. S. リトルジョン & K. フォス (編)『コミュニケーション理論百科事典』(pp. 28–32). サウザンドオークス, カリフォルニア州: SAGE Publications, Inc.
- ^ a b c d eエミールバイヤー, ムスタファ; ミシェ, アン (1998年1月). 「エージェンシーとは何か?」American Journal of Sociology . 103 (4): 962– 1023. doi : 10.1086/231294 . ISSN 0002-9602 . S2CID 39562300 .
- ^リトルジョン, スティーブン・W. & フォス, カレン・A. (2009). エージェンシー. S. リトルジョン & K. フォス (編)『コミュニケーション理論百科事典』(pp. 28–32). サウザンドオークス, カリフォルニア州: SAGE Publications, Inc.
- ^テイラー、チャールズ(1985年)『哲学論文集:第1巻、人間の行為と言語』ケンブリッジ大学出版局、イギリス、ISBN 9780521267526。
- ^ Hewson, M. (2010). Agency. A. Mills, G. Durepos, E. Wiebe (編)『 Encyclopedia of case study research』(pp. 13-17) . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- ^ギブソン、デイヴィッド・R.(2000年11月)「瞬間をつかむ:会話の主体性の問題」社会学理論. 18 (3): 368– 382. doi : 10.1111/0735-2751.00106 . ISSN 0735-2751 . S2CID 145158872 .
- ^ギブソン、デイヴィッド・R.(2000年11月)「瞬間をつかむ:会話の主体性の問題」社会学理論. 18 (3): 368– 382. doi : 10.1111/0735-2751.00106 . ISSN 0735-2751 . S2CID 145158872 .
- ^ Pronin E; Wegner DM; McCarthy K; Rodriguez S (2006). 「日常の魔法の力:個人の影響力の過大評価における見かけ上の精神的因果関係の役割」. Journal of Personality and Social Psychology . 91 (2): 218– 231. doi : 10.1037/0022-3514.91.2.218 . PMID 16881760 .
- ^ Metcalfe, J., Eich, TS, & Castel, AD (2010). 「生涯にわたる主体性のメタ認知」 『認知』267–282ページ。
- ^ Metcalfe, J., Eich, TS, & Castel, AD (2010). 「生涯にわたる主体性のメタ認知」 『認知』267–282ページ。
- ^リタ・カーター (2009). 『人間の脳』 p. 189.
- ^ Larkins, C. (2019). 「企業エージェントとしての遠出:子どもの主体性に関する批判的実在論的考察」 .子ども時代. 26 (4): 26(4), 414–429 . doi : 10.1177/0907568219847266 .
- ^ Dow, JM (2018). 「共同行為の意識について:共同行為の感情に関する悲観的説明」 J Soc Philos . 49 : 161–182 . doi : 10.1111/josp.12222 .
- ^ Larkins, C. (2019). 「企業エージェントとしての遠出:子どもの主体性に関する批判的実在論的考察」 .子ども時代. 26 (4): 26(4), 414–429 . doi : 10.1177/0907568219847266 .
