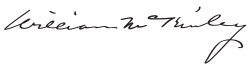マッキンリー関税
 | |
| 長いタイトル | 輸入税の歳入削減および関税の均等化、ならびにその他の目的のための法律。 |
|---|---|
| 制定者 | 第51回アメリカ合衆国議会 |
| 効果的 | 1890年10月6日 |
| 引用 | |
| 法令全般 | 26 法令 567 |
| 立法史 | |
| |
1890年関税法(通称マッキンリー関税法)は、当時のウィリアム・マッキンリー下院議員が起草した米国議会の法律で、1890年10月1日に成立した。[ 1 ]この関税法は輸入品の平均関税をほぼ50%に引き上げ、共和党の綱領で約束された通り、国内産業と労働者を外国との競争から保護することを目的とした引き上げとなった。[ 2 ]これは保護主義を象徴するものであり、共和党が支持し民主党が非難した政策であった。 1890年の議会選挙では激しい論争の的となり、民主党が圧勝した。1894年、民主党はマッキンリー関税法をウィルソン・ゴーマン関税法に置き換え、関税率を引き下げた。[ 3 ]
説明
| ||
|---|---|---|
オハイオ州選出の米国下院議員 第39代オハイオ州知事  | ||
450回の修正を経て、1890年関税法が可決され、全輸入品の平均関税が38%から49.5%に引き上げられた。[ 4 ]マッキンリーは「保護主義のナポレオン」として知られ、[ 5 ]一部の品目の関税は引き上げられ、他の品目の関税は引き下げられたが、これは常にアメリカの製造業の利益を守るための試みであった。ブリキや羊毛といった特定品目の関税の変更は最も物議を醸し、1890年関税法の精神を象徴するものであった。[ 6 ]この法律は特定の品目の関税を完全に撤廃し、他国に米国からの輸入品に対する関税を引き下げるよう促すため、関税の復活をちらつかせた。
関税撤廃
この法律は、砂糖、糖蜜、茶、コーヒー、皮革への関税を撤廃したが、これらの品目が米国の輸出品を「相互に不平等かつ不合理」な方法で扱う国から輸出された場合、大統領に関税を復活させる権限を与えた。その目的は、行政府が関税再導入の脅威を用いて他国に米国輸出品に対する関税を引き下げさせることで「相互貿易を確保する」ことだった。この権限委譲は、非委譲原則に違反する違憲のように見えたが、1892年のフィールド対クラーク事件において最高裁判所は、行政府が立法者としてではなく、議会の「代理人」としてのみ行動することを認めるものとしてこれを支持した。[ 7 ]大統領は、5種類の輸入品に関税を再度課す委任権限を行使しなかったが、そうするという脅しを利用して、他国が米国製品に対する関税を削減する10の条約を可決した。[ 8 ] [ 9 ]
ブリキ板
ブリキ板はアメリカ合衆国にとって主要な輸入品であった。毎年、数千万ドル相当のこれらの製品が国内に入ってきた。[ 6 ] 過去20年間、ブリキ板に対する関税率は何度も引き上げられたり引き下げられたりしたが、輸入量には変化がなく、国内生産は取るに足らないものであった。そこで、まだ幼少期にあった国内ブリキ板産業を刺激する最後の試みとして、この法律は関税率を30%から70%に引き上げた。[ 10 ]また、この法律には、1897年以降、ある年の国内生産量がその年の輸入量の3分の1に達しない限り、ブリキ板は無税で輸入されるという独自の規定も含まれていた。[ 11 ]関税を保護関税にするか、全く関税を課さないことが目標であった。
ウール
羊毛および羊毛製品に対する新たな関税規定は、極めて保護主義的なものでした。羊毛は従来、表に基づいて課税されており、価値の高い羊毛には高い税率が課されていました。複雑な関税表の改訂を何度も繰り返した結果、この法律はほぼすべての羊毛製品に最高税率を適用しました。[ 12 ]この法律は、米国産ではない非常に低品質の羊毛であるカーペットウールの関税も引き上げました。政府は、輸入業者が関税逃れのために高品質の羊毛をカーペットウールと偽装することのないよう、徹底的な対策を講じました。[ 13 ]
反応
この関税は、物価の高騰に苦しんだアメリカ人にはあまり受け入れられなかった。1890年の選挙では、共和党は下院で過半数を失い、獲得議席も171議席から88議席へとほぼ半減した。[ 14 ] 1892年の大統領選挙では、ハリソンはグロバー・クリーブランドに大敗し、上院、下院、大統領府の全てが民主党の支配下に入った。議員たちは直ちに新たな関税法案の起草に着手し、1894年にウィルソン・ゴーマン関税法が可決され、アメリカの関税平均は引き下げられた。[ 15 ] 1890年の関税法は海外でも不評だった。大英帝国の保護主義者たちは、この関税法を関税報復と帝国貿易特恵を主張する根拠とした。[ 16 ]
背景
19世紀後半のアメリカ合衆国にとって、関税(外国製品が輸入される際に消費者が支払う税金)は二つの目的を果たしていた。一つは連邦政府の歳入を増やすこと、もう一つは国内の製造業者と労働者を外国との競争から守ること、いわゆる保護主義である。[ 17 ] 1887年12月、民主党のグロバー・クリーブランド大統領は一般教書演説のすべてを関税問題に費やし、関税の引き下げと原材料に対する関税の撤廃を強く求めた。この演説により、関税と保護主義の考えが真に政党の重要事項となった。1888年の選挙では、共和党がベンジャミン・ハリソンの当選により上院と下院の両方で多数派を獲得し勝利した。党の路線を堅持するために、共和党はより強力な関税法案を可決する義務を感じた。[ 18 ]
1888年の選挙後、オハイオ州のウィリアム・マッキンリーはトーマス・ブラケット・リードに敗れ下院議長の座を逃した。[ 4 ] マッキンリーは下院歳入委員会の委員長となり、新たな関税法案の立案に取り組んだ。彼は、保護貿易主義は選挙を通じて国民に義務付けられたものであり、アメリカの富と繁栄に必要であると信じていた。[ 4 ]保護貿易主義論争に加えて、政治家たちは関税から生じる高額の歳入を懸念していた。[ 19 ]アメリカ南北戦争後、歳入を増やし、高額な戦争費用を賄うために関税は高いままだった。1880年代初めまでに、連邦政府は多額の黒字を計上していた。両党とも黒字を減らす必要があることには同意したが、同じ目的を達成するために関税を上げるべきか下げるべきかでは意見が分かれた。民主党の仮説は、関税率を引き下げることで関税収入を削減できるというものでした。一方、共和党は関税を引き上げることで輸入が減少し、関税収入全体が減少すると考えました。この議論は1888年の関税大論争として知られるようになりました。[ 19 ]
効果
ダグラス・アーウィンの1998年の論文は、1890年に共和党と民主党が提唱した対立する関税仮説の妥当性を検証している。民主党は輸入関税の引き下げを提案した。彼らは、これにより政府歳入が減少し、消費者と農家の税負担が軽減され、特別利益保護に伴う不公平が解消されると信じていた。一方、共和党は、関税引き下げは輸入を刺激し、さらなる歳入増加につながると主張した。共和党は、政府歳入の削減と輸入競争からのアメリカ産業の保護という二重の目的を達成するために、関税引き上げを提案した。[ 20 ]
アーウィンは歴史的データを分析して、1888年以前のアメリカ合衆国における輸入需要弾力性と輸出供給弾力性を推定した。彼は関税がまだ最大歳入率に達していないと計算し、関税の引き上げではなく引き下げが歳入と連邦黒字の両方を減少させたであろうことを示唆した。この結果は民主党の仮説(関税引き下げは政府歳入の減少につながる)を支持し、共和党の仮説(関税の引き上げは政府歳入の減少につながる)を反証した。[ 20 ]
アーウィンはさらに関税収入データを分析し、1890年の関税引き上げ後、総収入が2億2500万ドルから2億1500万ドルへと約4%減少したことを観察した。彼はこの減少は主に粗糖を免税品目に加えた規定によるものだと考えた。当時、砂糖は最大の収入源であったため、無税化は大幅な収入減少を招いた。アーウィンはまた、砂糖を輸入計算から除外した場合、関税収入は実際には1億7000万ドルから1億8300万ドルへと7.8%増加すると計算した。彼は、関税によって国内のブリキ生産の発展が約10年早まったと結論付けたが、この産業への利益は消費者への総コストを上回ったと主張した。[ 20 ]
参照
- 1893 年恐慌、高関税が実施されていた時期。
参考文献
- ^フランク・W・タウシグ、「マッキンリー関税法」、エコノミック・ジャーナル、2(1891):326–350、オンライン。
- ^レイタノ、ジョアン(1994年)『金ぴか時代の関税問題:1888年の大論争』ペンシルベニア州立大学ユニバーシティパーク、 129頁。ISBN 0-271-01035-5。
- ^タウシグ, FW (1892). 『アメリカ合衆国の関税史』(第8版). ニューヨーク: GP Putnam's Sons. p. 291 .
- ^ a b cレイタノ 1994, p. 129
- ^ Rove, K.、「ウィリアム・マッキンリーの勝利:1896年の選挙が依然として重要な理由」(ニューヨーク:サイモン&シュスター、2015年)、 67ページ。
- ^ a bタウシグ 1892, p. 273
- ^ FindLaw.comフィールド対クラーク判決文
- ^条約はオーストリア・ハンガリー帝国(1892年5月20日)、ブラジル(1891年4月1日)、ドミニカ共和国(1891年9月1日)、エルサルバドル(1892年2月1日)、ドイツ(1892年2月1日)、グアテマラ(1892年5月30日)、ホンジュラス(1892年5月25日)、ニカラグア(1892年3月12日)、スペイン(キューバおよびプエルトリコに対して、1891年9月1日)、およびイギリス(イギリス領西インド諸島およびイギリス領ギアナに対して、1892年2月1日)との間で締結された。
- ^ 「他国との相互条約」『ニューヨーク・タイムズ』 1901年11月24日。
- ^タウシグ 1892, 274ページ
- ^オルコット、CS、「ウィリアム・マッキンリーの生涯」、第1巻(ボストン:ホートン・ミフリン、1916年)、 172ページ。
- ^タウシグ 1892, 262ページ
- ^タウシグ 1892, 258ページ
- ^レイタノ 1994, p. 130
- ^タウシグ 1892, 291ページ
- ^パレン、マーク=ウィリアム (2010). 「保護、連邦、そして連合:マッキンリー関税が大英帝国に与えた世界的影響、1890~1894年」.帝国・連邦史ジャーナル. 38 (3): 395– 418. doi : 10.1080/03086534.2010.503395 . S2CID 159638185 .
- ^アーウィン、ダグラス・A. (1998). 「関税の上昇は歳入の減少?『1888年の関税大論争』の財政的側面の分析」(PDF) .経済史ジャーナル. 58(1): 59– 72. doi:10.1017/S0022050700019884 . S2CID 154971301 .
- ^タウシグ 1892, 256ページ
- ^ a bアーウィン 1998, p. 59
- ^ a b cアーウィン、ダグラス・A. (1998). 「関税の上昇は歳入の減少?1888年の関税大論争の財政的側面の分析」.経済史ジャーナル. 58 (1): 59– 72. ISSN 0022-0507 . JSTOR 2566253 .
さらに読む
- エッケス、アルフレッド・E. 『アメリカ市場開拓:1776年以降の米国の対外貿易政策』(ノースカロライナ大学出版、1995年)[『アメリカ市場開拓』オンライン版]
- ハウエルズ、ギャレス。「『星条旗のドラゴン』:マッキンリー関税が南ウェールズのブリキ産業に及ぼした直接的な影響:1880~1895年?ウェールズの生産と外国保護主義の再評価」(博士論文、オープン大学、2018年)。オンライン
- アーウィン、ダグラス・A.「アメリカ経済史における貿易政策」『Annual Review of Economics』 12(2020年):23-44ページ、オンライン
- アーウィン、ダグラス・A.「19世紀後半のアメリカの関税は幼稚産業を促進させたか?ブリキ産業の事例から」経済史ジャーナル60.2(2000年):335-360ページ、オンライン
- アーウィン、ダグラス・A.「関税の上昇は歳入の減少?『1888年関税大論争』の財政的側面の分析」 経済史ジャーナル58.1(1998年):59-72ページ、オンライン
- アーウィン、ダグラス A.「19世紀後半のアメリカにおける関税と成長」(NBER、2000年)[アーウィン、ダグラス A.「19世紀後半のアメリカにおける関税と成長」(2000年)。オンライン]
- モーガン、H. ウェイン著『ウィリアム・マッキンリーとそのアメリカ』(シラキュース大学出版、1963年)。オンライン
- パレン・マーク=ウィリアム。マーク・ウィリアム・ペイレン『帝国および連邦史ジャーナル』 38#3 2010 年、395 ~ 418 ページ。 オンライン
- レイタノ、ジョアンヌ著『金ぴか時代の関税問題:1888年の大論争』(ペンシルベニア州立大学出版、2010年)。オンライン
- タウシグ、フランク・W.「マッキンリー関税法」経済ジャーナル1.2(1891年):326-350。オンライン
- タウシグ、FW『アメリカ合衆国の関税史』(1931年)オンライン
- タウシグ、FW関税問題のいくつかの側面:保護下のアメリカ産業の発展の検討(1931年)、すべての主要産業をオンラインでカバー
国際的な影響
- グレイ伯爵著『イギリス植民地の商業政策とマッキンリー関税』(ロンドン:マクミラン社、1892年)オンライン
- ローダー、ロバート・H.『米国とカナダの通商、相互主義とマッキンリー関税に関する考察』(トロント:マネタリー・タイムズ・プリンティング、1892年)。オンライン
- パレン、マーク=ウィリアム。「保護、連邦、そして統合:マッキンリー関税が大英帝国に与えた世界的影響、1890~1894年」帝国・連邦史ジャーナル38.3(2010年):395~418ページ、オンライン。
- リウ、ヒューバート。「カナダ第一主義 vs. アメリカ第一主義:経済ナショナリズムとカナダ・米国貿易関係の進化」European Review of International Studies 6.3 (2019): 30–56。オンラインアーカイブ。 2022年12月25日、 Wayback Machineにて。
.jpg/440px-William_McKinley-head&shoulders_(3x4_close_cropped).jpg)