魔女の一族
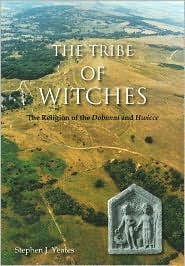 | |
| 著者 | スティーブン・J・イェイツ |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 主題 | イギリス鉄器時代考古学、アングロサクソン考古学 |
| 出版社 | オックスボウブックス |
発行日 | 2008 |
| 出版場所 | イングランド |
| メディアタイプ | 印刷(ペーパーバック) |
| ページ | 195 |
| ISBN | 978-1842173190 |
| に続く | 魔女の夢(2009) |
『魔女の部族:ドブニ族とフウィッチェ族の宗教』は、イングランド中部に居住していた鉄器時代のドブニ族と中世初期フウィッチェ族におけるキリスト教以前の宗教に関する歴史的・考古学的研究である。考古学者スティーブン・J・イェイツによって執筆され、 2008年にオックスボー・ブックスから出版された。イェイツは以前、英国考古学報告書から出版された3巻からなるモノグラフ『宗教、共同体、そして領土:鉄器時代から中世初期までのセヴァーン渓谷と周辺丘陵における宗教の定義』(2006年)で自身の理論を発表していた。 [ 1 ]
本書を通して、イェイツはドブニとフウィッチェ地域に位置する様々な考古学的・地理的特徴を探求し、鉄器時代、ローマ・ブリテン時代、そして中世初期を通して、この地域の景観がどのように変化してきたかを考察しています。これらの特徴には、この地域に建てられた寺院、聖なる川、鉱山、防御施設などが含まれます。
『魔女の部族』は、査読付き学術誌と多くの実践的異教徒の両方から批評を受けた。前者では主に否定的な意見が寄せられ、イェイツの議論は無理があり、十分な証拠を欠き、固有名詞学の理解が乏しいとされた。一方で、彼の文体や、参照やイメージの多用を称賛する意見も多くあった。イェイツは『魔女の部族』で提唱された理論を、後の著書『魔女たちの夢:ドブニ原始神話の再現』(2009年)でさらに発展させた。
背景
![[アイコン]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | このセクションは拡張が必要です。不足している情報を追加していただければ幸いです。 (2012年7月) |
この本は、イェイツが2001年から2005年にかけてオックスフォード大学で博士課程の一環として行った研究の成果です。研究の指導者はマーティン・ヘニグ教授とバリー・カンリフ教授、評価者はレイ・ハウエル博士とクリス・ゴスデン教授でした。しかし、CUDAに関するアイデアなど、この時期以前から既に構想されていたアイデアもありました。
イェイツの主張や理論のいくつかは、『魔女の部族』の出版前にすでに出版されていた。彼のクダ女神に関する理論は、査読付きの学術誌に国内外で発表されていた。[ 2 ] [ 3 ] 2006年に出版された『宗教、コミュニティ、領土』に対する言語学者ベイカーの書評では、クダ女神を今や認識すべきであり、クダ女神は *Cod を使った地名の語源である、と述べられている。[ 4 ]コッツウォルズの川の名前のいくつかは、『英国地名協会誌』の記事で議論されている。[ 5 ]この地域における文化的連続性に関する彼の主張は、ルイスとセンプル(2010年)の『景観考古学の展望:オックスフォードで2003~05年に発表された論文』に査読付きの論文として掲載された。[ 6 ]
概要
![[アイコン]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | このセクションは拡張が必要です。不足している情報を追加していただければ幸いです。 (2012年7月) |
第一章「ドブニ族、フウィッチェ族、そして宗教」は、イェイツの議論の序論であり、彼の研究が歴史学、考古学、そして固有名詞学を駆使した学際的な性質を持つと指摘している。ドブニ族とフウィッチェ族の背景を簡潔に説明した上で、イェイツは、英国におけるキリスト教以前の宗教研究における学者たちのこれまでのアプローチについて簡潔に論じている。[ 7 ]第二章「神と風景」では、ドブニ地域において考古学的に確認されている、ローマ時代以前およびローマ時代鉄器時代の様々な神社や寺院を考察する。語源学的証拠を用いて、彼はこれまで知られていなかった先史時代の神々がこの地域に定住していたという仮説を提示している。具体的には、コッツウォルズの鉄器時代の女神クダである。イェイツは、この地域の風景と、そこに住む人々がそれを「精神的で神聖なもの」と見なしていた様子を描写しようと試みている。[ 8 ]
第3章「聖なる川」では、イギリス鉄器時代における川の神格化と、そこで奉納された供物の考古学的証拠について考察する。イェイツは、セヴァーン川やワイ川など、論じられている地域内の複数の川を考察し、川沿いの儀式活動の証拠にも言及している。[ 9 ]第4章「部族と民族集団の神々」では、この地域のコミュニティの長期的な発展と、鉄器時代と初期中世の集落の間に存在しうる繋がりについて考察する。中世の史料には、地元の鉄器時代の神であるウェオゴネラとサレンセスの存在が記録されていると主張し、これを根拠として、先史時代から中世にかけて文化的連続性があり、したがってフウィッチェ族はドブニ族の子孫であると主張している。[ 10 ]第5章「鉱業と鉱物」では、この地域での鉱業の証拠を探り、この活動と先史社会における宗教的信仰との関連を強調しています。[ 11 ]第6章では戦争の側面を扱っています。
第7章では、地元の狩猟神と聖なる森、あるいはネメトンについて論じている。[ 12 ]地元の「ドブニク」宗教における狩猟神に関する議論は新しいものではなく、ブーン[ 13 ] 、ヘニグ[ 14 ]、メリフィールド[ 15 ]による一連の出版物に端を発している。第8章では、樹木の神殿について考察する。第9章では、風景における埋葬の重要性について考察する。第10章では、聖なる馬について考察する。第11章では、部族の神々について考察する。第12章では、キリスト教の影響について考察する。
レビューと受容
学術レビュー
イェイツはこの議論に、考古学、碑文学、地名学、図像学、民俗伝承、宗教、景観研究、そしてローマ時代および中世初期の歴史など、様々な証拠を盛り込んでいる。彼の主な焦点は宗教と景観であり、この二つのテーマを徹底的に調査することで、初期の集団から後期の集団への連続性という問いに取り組んでいる。彼が説明するように、イギリスにおけるキリスト教以前の宗教の信仰と実践は解明が困難だが、多様な証拠をまとめることで、著者は先史時代後期鉄器時代、ローマ時代、そして中世初期における宗教思想の関連性を明らかにしようとしている。
ミズーリ大学のピーター・S・ウェルズは、 2009年にケンブリッジ考古学ジャーナルで『魔女の部族』の書評を行った。ウェルズは、イェイツがドブニ族とフウィッチェ族の両方を指して「部族」という言葉を使ったことを批判し、別の用語の方が適切だったのではないかと考えた。また、地図の使用についても批判し、特に地域の景観に馴染みのない人にとっては役に立たないと述べた。ウェルズは、テキストが「非常に魅力的」であるとし、参考文献が「広範かつ貴重」で、図版も豊富に使われていると指摘した。しかしながら、ウェルズはイェイツの主張は説得力に欠けるとし、女性が容器を持った描写はローマ世界全体に広く見られ、ドブニ族の地域に限ったものではないという事実を指摘した。[ 16 ]
『Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture』誌は、民俗学者ジェレミー・ハートによる書評を掲載した。ハートは『魔女の部族』に対して概ね否定的な態度を取り、この作品は19世紀の古物研究家が期待するようなアプローチに非常に似ていると述べた。イェイツの広範な参照の使用を称賛しつつも、ハートの基本的な議論の多くは誤りであり、いくつかの記述は誤解を招くものだと述べた。「章全体が可能性の繰り返しに過ぎない」と指摘し、ハートの聖地の多くは「存在しない遺跡」で構成されており、「存在しない他の遺跡との類推によって作られた」と述べて、本書の主張の多くを非難した。最終的にハートは、『魔女の部族』は「色彩豊かな本」ではあるものの、歴史学というよりは「歴史ロマンス」に近いことを認めた。 [ 17 ]
アベリストウィス大学のケルト学者サイモン・ロッドウェイが執筆した、主に否定的な書評が、『ブリタニア:ローマ・ブリテンおよび親族研究ジャーナル』に掲載された。ロッドウェイは裏表紙から『魔女の部族』には「突飛な主張」が満載だろうと予想していたことを認めつつも、それらの主張がほとんど「ほのめかされているだけ」であることに驚いた。広範な資料を扱っているにもかかわらず、その多くが表面的な考察にとどまっているため、本書を「野心的な作品」と評することは難しく、イェイツは「自分の研究テーマへの関心を完全に失ってしまった」という印象をロッドウェイに与えた。ロッドウェイは、イェイツの仮説が「疑似ネンニアン理論の山」の中に埋もれていると述べ、鉄器時代と中世の文化的連続性に関する主張を裏付ける十分な証拠を提示していないこと、そしてそのような連続性がどのように維持されてきたのかを提示していないことを著者に厳しく非難した。彼は、イェイツのここでの議論が、ニコラス・ハイアムの「問題のある」ケルト語からゲルマン語への言語変遷は概ね平和的であったという理論に類似していることを指摘している。イェイツの考古学的資料の利用を判断する資格はないとしながらも、ハイアムの史料利用は「せいぜい適切」である一方、固有名詞学の活用は「ひどい」と指摘した。イェイツは明らかに「『少し似ている』語源学派」に属していたと述べつつ、イェイツは自身が引用している多くの固有名詞学者の議論も理解できておらず、「どんな初心者の歴史言語学者でも」イェイツの「魔女の一族」は「幻影」だと言い切れるだろうと述べている。さらに、「基本的な誤りがないページはほとんどない」と強調し、イェイツの考えを「混乱している」と表現し、最終的に『魔女の部族』は「浅はかで混乱しており、まったく期待外れの本」であり、ドブニ族やフウィッチェ族の学術研究にはまったく役に立たないと考えました。[ 18 ]
レビューを掲載した他の査読付きジャーナルには、OxoniensiaやTransactions of the Birmingham & Warwickshire Archaeological Societyなどがあります。
英国考古学評議会の雑誌『ブリティッシュ・アーキオロジー』に掲載された短い書評の中で、バーミンガム大学の景観考古学者デラ・フックは、イェイツの著書を批判し、「大胆な試み」と評しつつも、結論の多くには十分な証拠が欠けていると指摘した。フックは、イェイツの主張は「興味深いが証明されていない」と述べ、その結論を「一般向けに簡潔にまとめた形」で出版し、より多くの非学術的読者に届けるのは「賢明ではない」と考えた。さらに、フックは、フウィッチェ族が聖なる大釜をかき混ぜる鉄器時代の魔女にちなんで名付けられたというイェイツの説を批判し、「空想に陥りすぎている」と主張した。[ 19 ]
より広い受容
ドルイド・グローブのウェブサイトに寄稿したケストレルというペンネームの書評家は、イェイツの著作を「非常に興味深い本」と評したが、浴槽を持つ母なる女神が谷の象徴であるという彼の理論には疑問を呈した。[ 20 ]もう一人の現代ペイガンであるD・ジェームズは、ツイステッド・ツリー・ブックシェルフのウェブサイトでこの本をレビューした。ジェームズは、この本は現代のペイガンに読まれるべきだとし、「古代の祖先の社会構造と宗教構造への理解を大きく深め、どんな本棚にも置く価値のある一冊だ」と述べた。[ 21 ]言語学者スティーブン・ポッシュは、魔術が宗教になったのは20世紀になってからであり、1000年以上前の部族宗教から魔術を派生させようとする試みは結局のところ偏向していると述べ、イェイツは現代のウィッカから逆算して「狩猟の神と対になる三女神を探そうと躍起になった。角があればなお良い」と示唆している。ポッシュは、この本は現代の異教徒にとって歴史的というよりも神話的な意味で重要であり、イェイツの地域的な風景に根ざした異教のビジョンは、現代の異教の実践のテンプレートを提供すると主張している。[ 22 ]
参考文献
脚注
- ^イェイツ 2006 .
- ^イェイツ 2004
- ^イェイツ 2007
- ^ベイカー 2008
- ^イェイツ 2006 . 63–81頁。
- ^イェイツ 2010 . 78–93頁。
- ^イェイツ 2008年. 1~8頁.
- ^イェイツ 2008年9~29頁。
- ^イェイツ 2008年.30~58頁.
- ^イェイツ 2008年59~89頁。
- ^イェイツ 2008 . 90–101頁。
- ^イェイツ 2008 . pp. 107–116.
- ^ブーン 1989 . pp. 201–217.
- ^ヘニグ 1996 . 97–103ページ。
- ^メリフィールド 1996 . pp. 105–113.
- ^ a bウェルズ 2009 .
- ^ハート 2011 .
- ^ロッドウェイ 2009 .
- ^フック 2009 .
- ^ケストレル(日付なし)
- ^ジェームズ 2008。
- ^ポッシュ 2011 .
参考文献
- 学術情報源
- ベイカー、ジョン (2008). 「宗教、コミュニティ、そして領土に関するレビュー」.英国地名協会誌. 第40巻.
- ブーン、ジョージ・C. (1989). 「修復されたローマ彫刻:ペイガンズ・ヒルの犬」ブリタニア誌第20巻、 201~ 217頁。
- ハート、ジェレミー (2011). 「 『魔女の部族』レビュー」『時間と心:考古学、意識、文化ジャーナル』第4巻第1号、 123~ 126頁。
- ヘニグ、マーティン(1996)「ロンドンにおける西洋の彫刻家たち」第38巻、オックスフォード:オックスボー社、 97~ 103頁。
- ヘニグ、マーティン (2008). 「『魔女の部族』のレビュー」オクソニエンシア誌第73巻.
- フック、デラ(2009年1~2月)「魔女の部族のレビュー」『ブリティッシュ・アーキオロジー』第104巻、ヨーク:ブリティッシュ・アーキオロジー評議会、53頁。
- メリフィールド、R. (1996). 「ロンドンの狩猟神とロンドニウムの歴史におけるその意義」『ローマ時代のロンドンを解釈する:ヒュー・チャップマン追悼論文集』オックスフォード:オックスボー社、pp. 105– 113.
- ロッドウェイ、サイモン (2009). 「 『魔女の部族』レビュー」 .ブリタニア:ローマ・ブリテンおよび親族研究ジャーナル. 第40巻. 397–398頁.
- ウェルズ、ピーター・S. (2009). 「魔女の部族のレビュー」ケンブリッジ考古学ジャーナル第19巻、 283~ 284頁。
- イェイツ、スティーブン・J. (2004). 「コッツウォルズ、コードスウェラン、そして女神クーダ」『グレベンシス』第37巻、 2~ 8頁。
- イェイツ、スティーブン・J. (2006a). 『宗教、共同体、そして領土:鉄器時代から中世初期までのセヴァーン渓谷と周辺丘陵における宗教の定義 第1巻』オックスフォード:ブリティッシュ・アーキオロジカル・リポート.
- イェイツ、スティーブン・J. (2006b). 「川の名前、ケルト語と古英語:中世と後中世の二重の性格」イギリス地名協会誌、第38巻、 61~ 81頁。
- イェイツ、スティーブン・J. (2007). 「北西州における宗教と部族:ドブニ族の女神」ハウスラー、R.、キング、A.(編)『ローマ帝国西部における宗教の継続と革新』ローマ考古学ジャーナル補足シリーズ第67巻、 55~ 69頁。ISBN 978-1-887829-67-0。
- イェイツ、スティーブン・J. (2008). 『魔女の部族:ドブニ族とフウィッチェ族の宗教』オックスフォード:オックスボー・ブックス. ISBN 978-1842173190。
- イェイツ、スティーブン・J. (2009). 『魔女の夢:ドブニ原始神話の再現』オックスフォード:オックスボウ・ブックス. ISBN 978-1-84217-358-9。
- イェイツ、スティーブン・J. (2010). 「今もドブニと共に生きる」オックスフォード: 英国考古学報告書国際シリーズ2103. pp. 78– 93.
- イェイツ、スティーブン・J.(2012年)『神話と歴史:ブリテン諸島最初の千年紀における民族と政治』オックスフォード:オックスボー・ブックス、ISBN 978-1-84217-478-4。
- 「魔女の部族のレビュー」バーミンガム・ウォリックシャー考古学協会紀要第112巻、2008年。
- 人気の情報源
- ポッシュ、スティーブン (2011). 「考える魔女(あるいはホブマン)の2009年のベストブック」.クルックド・パス・ジャーナル第7巻. 26–27ページ .