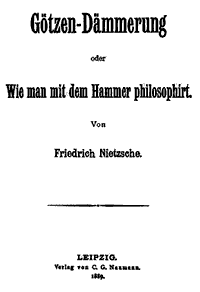 | |
| 著者 | フリードリヒ・ニーチェ |
|---|---|
| 原題 | ゲッツェン・デメルング |
| 翻訳者 | RJ ホリングデール |
| 言語 | ドイツ語 |
発行日 | 1889 |
| 出版場所 | ドイツ |
| メディアタイプ | 印刷版(ハードカバーとペーパーバック) |
| ページ | 208(1990年ペンギンクラシックス版) |
| ISBN | 978-0140445145 |
| OCLC | 22578979 |
| 先行 | ワーグナー事件(1888年) |
| に続く | 反キリスト(1888年) |
『偶像の黄昏、あるいはハンマーで哲学する方法』(ドイツ語: Götzen-Dämmerung, oder, Wie man mit dem Hammer philosophiert )は、1888 年に書かれ、1889 年に出版された フリードリヒ ニーチェの本です
創世記
『偶像の黄昏』は、ニーチェがシルス・マリアで休暇を過ごしていた1888年8月26日から9月3日までの1週間余りで執筆された。[1]ニーチェは『偶像の黄昏』について 手紙の中でこう書いている。「このスタイルは私の哲学を一言で表すと、犯罪的なまでに過激である…」[2]
後者のタイトル、ドイツ語では「Götzen-Dämmerung(神々の黄昏) 」は、リヒャルト・ワーグナーのオペラ「 Götterdämmerung 」(神々の黄昏)のタイトルをもじったものです。 「Götze」はドイツ語で「偶像」または「偽りの神」を意味します。ヴァルター・カウフマンは、ニーチェが「Götzen-Dämmerung」という言葉を用いるにあたり、偶像という概念を哲学に用いたフランシス・ベーコンの影響を受けているのではないかと示唆しています。 [3]
概要
ニーチェは当時のドイツ文化を洗練されておらず、退廃的で虚無主義的だと批判し、同様の傾向を示すフランス、イギリス、イタリアの主要な文化人たちにも非難の矢を放っている。文化的退廃の代表者とされるこれらの人々とは対照的に、ニーチェはカエサル、ナポレオン、ゲーテ、トゥキュディデス、そしてソフィストたちをより健全で力強いタイプとして称賛している。本書は、あらゆる価値の転換をニーチェの最終的かつ最も重要な課題と位置づけ、文学の分野においてではあるが、ローマ人が古代ギリシャ人よりも優位に立つという古代観を提示している。
この本は12のセクションに分かれています。
序文
ニーチェは序文で、この本は心理学者の暇つぶしの冒険であると述べています。そして、この小さな本は「偉大な宣戦布告」であると続けます。そして、この小さなハンマーで偶像を壊すことを楽しみにしていると述べ、1888年9月30日の日付を記して署名しています。
格言と矢
このセクションは、作品の主なテーマを紹介する 44 の短い格言で構成されています。
格言8
人生の戦争学校から抜け出す—私を殺さないものは私を強くする。(ドイツ語Was mich nicht umbringt, macht mich stärker )
ニーチェは『偶像の黄昏』の直後に出版された『エッケ・ホモ』の中で、このテーマについて詳しく説明している。「…本質的に健全な人間にとって、病気は生命、ひいては生命の余剰への強力な刺激となることさえある。…彼は怪我の治療法を予言し、重大な事故を自らの利益に転じる術を知っている。彼を死なせないものは彼を強くする。」[4]この原則を実践的に例証するものとして、ニーチェは自身の悲観主義克服が健康状態の劇的な悪化期に起こったと説明し、「私の活力が最低点に達した時期に、私は悲観主義者であることをやめました。自己回復の本能が、貧困と絶望の哲学に固執することを禁じたのです。」[5]
格言12
人間が自分の存在の目的を知れば、生き方は自ずと定まる。人間は幸福を希求するのではない。幸福を求めるのはイギリス人だけだ。
『偶像の黄昏』の中で、ニーチェはイギリス人について 22 の皮肉や嘲笑的な言葉を述べ、女性については 41 の言葉を述べ、ドイツ人については 100 以上の言葉を述べている。
格言31
踏まれると、ミミズは体を二つ折りにする。賢い。そうすることで、再び踏まれる可能性を減らすのだ。道徳的に言えば、謙虚さだ。
ニーチェは『道徳の系譜学』の中で謙虚さについての自身の見解を詳しく述べています。彼は謙虚さ、忍耐、慈悲といった美徳を弱者にとって有用な資質と捉えています。したがって、弱者は自らの苦しみを和らげる資質を称賛するのです。アフォリズム31は、謙虚さが苦しみの可能性を減らすのに役立つという考えを反映しています。[6]
ソクラテスの問題
ニーチェは、歴史を通して最も博識な人々は、人生は無価値であるという共通の信念を共有していたようだと主張する。ニーチェは、この考えは健全な社会の兆候ではなく、衰退する社会の兆候であると主張する。ニーチェは、ソクラテスやプラトンといった哲学者たちは、人生に対して否定的な感情を抱くという共通の生理的性質を持っていたと説明する。これは、彼らに先立つ優れたギリシャ文化の衰退を反映していた。
ニーチェはソクラテスを特に軽蔑していた。ニーチェはソクラテスを醜悪(内面の弱さと堕落の兆候、あるいは特徴)であり、社会の「下層階級」の産物だと考えていた。ニーチェはソクラテスの二つの思想を特に攻撃の対象としている。一つ目は、理性、美徳、幸福の相互関連性である。二つ目は、ソクラテスが哲学に弁証法(異なる視点を持つ二人以上の人々が、談話、論理、理性の過程を通して結論に到達する過程。ソクラテス的方法とも呼ばれる)を導入したことである。ニーチェは、弁証法によって、より弱い哲学的立場や洗練されていない思想家が社会において過度に大きな足場を築くことを許してしまうと考えた。ニーチェの思想は理性よりも本能を重視していたが、ソクラテスと弁証法のおかげで、ギリシャ文化は「途方もなく合理的」なものとなった。[7]ニーチェのテーゼの重要な部分は「幸福と本能は一つである」ということだが、理性は本能と真っ向から対立している。
ニーチェは、最終的に生命の価値は推定できず、生命に関するいかなる判断も、その人の生命を否定するか肯定するかの傾向を明らかにするだけだと主張した。[8]
哲学における理性
ニーチェはプラトンの思想の多く、特に存在と生成、形相の世界、そして感覚の誤りやすさを否定している。より正確に言えば、彼はプラトンのように感覚を否定すべきではないと考えている。[9]これはニーチェの人間的卓越性の理想に反し、個人的な退廃の兆候である。[10]ニーチェは退廃という言葉で、生命と活力の衰え、そして弱さを受け入れることを指している。ニーチェの見解では、もし人が感覚的でなく不変の世界を優れたものとし、我々の感覚世界を劣ったものと受け入れるならば、それは自然への憎悪、ひいては感覚世界、すなわち生ける者の世界を憎むことになる。ニーチェは、そのような信念に賛同するのは弱者、病弱者、あるいは卑しい者だけだと仮定している。
ニーチェは、この非物質的領域への執着をキリスト教と天国の概念に関連付けています。ニーチェは、キリスト教の神への信仰は、生命の退廃と憎悪に似ていると指摘しています。[10]キリスト教徒が天国を信じていること、そしてその概念がプラトンの形相の世界(不変で永遠の世界)の考えに似ていること、そしてキリスト教徒が世界を「現実」(天国)と見かけ(生きている)世界に分けていることを考えると、彼らもまた自然を憎んでいると言えるでしょう。
「真実の世界」が最終的にフィクションになった経緯
このセクションでは、ニーチェは、過去の哲学者たちがいかにして見かけ上の世界を虚構化し、感覚の産物を疑念に陥れ、それによって現実世界の概念を消し去ってきたかを示す。このセクションは6つの部分に分かれている。
- 賢明で敬虔な人は、自らの知恵を通じて得た現実世界に住んでいます(知覚のスキルは、現実世界のより正確な見方を保証します)。
- 賢明で敬虔な人は現実世界に住むのではなく、むしろ生きる目的が約束されているのです。(例:悔い改める罪人)
- 現実世界は到達不可能であり、約束もできないが、見かけ上の世界の不公平さに直面したときの慰めにはなり得る。
- 真実の世界に到達しなければ、それは未知のものである。したがって、真実の世界に対する義務はなく、そこから得られる慰めもない。
- 現実世界という概念はもはや無用なものとなった。それは何の慰めも動機も与えない。それゆえ、無用な抽象概念として捨て去られるのだ。
- 一体どんな世界が残されているのだろうか?現実世界という概念は廃絶され、それとともに仮象世界という概念が生まれた。最後の言葉はこうだ。「正午。最も短い影の瞬間。最も長い誤りの終わり。人類の最高点。ツァラトゥストラを心に刻め。」
反自然としての道徳
ニーチェは快楽主義者ではなく、いかなる情熱も過剰なものは「その愚かさの重みで犠牲者を引きずり降ろす」と主張している。しかし、彼は情熱が最終的に「精神化」される可能性を主張している。キリスト教は、節度を欠いた情熱に対処する際に、その情熱を完全に除去しようとすると批判している。ニーチェは、キリスト教の道徳観は、技術の低い歯科医が歯の痛みを治療する際に、他のより攻撃的でない、同等の効果のある治療法ではなく、歯を完全に抜くことと大差ないと主張する。キリスト教は「欲望を精神化、美化、神格化」しようとはしない。そのため、ニーチェはキリスト教会は「生命に敵対的」であると結論づけている。心理学的な視点から見ると、ニーチェは、特定の情熱を完全に根絶しようとする人々がそうするのは、主に「意志が弱く、堕落しすぎて、自分自身に節度を課すことができない」からだと述べている。[11]
ニーチェは、愛と敵意という概念を考察することで、情熱を霊化するという自らの思想を展開した。愛とは実際には「官能の霊化」であると彼は主張する。一方、敵意は敵を持つという状態を霊化する。なぜなら、敵を持つことは、私たちが自らの立場を明確にし、強化するのに役立つからである。ニーチェの思考には反キリスト教的な感情が浸透しているにもかかわらず、彼はキリスト教会を排除することに全く関心がないことを明確に示している。むしろ、彼はキリスト教会がなければ、自身の哲学的計画はそれほど効果的でも必要でもないことを認識していた。もし彼の敵である教会が「生命の本能」を否定するならば、それはニーチェがそれらを肯定する立場を展開する助けとなる。神学的な言葉を用いて、ニーチェは真の「冒涜」とはキリスト教的な「生命に対する反逆」であると主張する。キリスト教道徳は、究極的には「衰退し、衰弱し、疲弊し、断罪された生」の症状である。
ニーチェは、人々はこうあるべきだ、あああるべきだと主張することは、人間の多様性、つまり「魅惑的な種類の豊かさ」の良さを軽視する一種の偏見につながると結論づけています。また、人間が真に自分の本質を変えることができるという考えは、どんな人間も「運命の一部」であるという事実を無視しています。人は、自分が今の自分である原因となった過去の出来事や現在の状況から、自分自身を切り離すことはできません。ニーチェは最終的に、自分自身のような「不道徳主義者」こそが、ある人の人生観を他の誰かよりも高く評価しないため、個人の固有の価値を最も尊重していると結論づけています。[12]
4つの大きな誤り
「四つの大きな誤謬」の章で、ニーチェは人々、特にキリスト教徒が結果と原因を混同し、人間の自我と主観性を他の事物に投影することで、存在という幻想的な概念、ひいては物自体や神という幻想的な概念を生み出していると指摘する。実際には、動機や意図は行為の原因ではなく、「行為の付随物」[13]である。自由で意識的な意志に基づく因果関係を排除することで、ニーチェは説明責任の倫理を批判し、あらゆるものは全体の中に必要であり、その外には何も存在しないため、判断も非難もできないと示唆する。[14]人々が典型的に「悪徳」とみなすものは、実際には単に「刺激に反応せずにはいられないこと」に過ぎない。 [15]この観点から見ると、道徳の概念は純粋に制御の手段となる。「意志の教義は、本質的に処罰、すなわち有罪判決を目的として発明されたのである。」[16]
人間は自由であるがゆえに罪を犯すことができたと考えられていた。したがって、あらゆる行為は意志に基づくものと考えられ、あらゆる行為の起源は意識の中にあると考えられなければならなかった。……今日、私たちが逆の方向へ進み始め、特に私たち不道徳主義者が、罪悪感と罰の概念を世界から排除し、心理学、歴史、自然、そしてそれらの社会制度と制裁を一掃しようと全力を尽くしているとき、私たちの目には、神学者たちの反対以上に過激なものは映らない。彼らは「道徳的世界秩序」という概念を用いて、生成の無垢に「罰」と「罪悪感」を染み込ませ続けている。キリスト教は絞首刑執行人の形而上学である。四つの大きな誤謬
人類の「改善者」たち
この一節でニーチェは、客観的な道徳を信じていないことを宣言し、道徳的事実など存在しないと述べています。この情報に基づき、彼は完全な道徳的真実が存在しないにもかかわらず、人類の道徳化が試みられた二つの例を挙げています。ニーチェはこの道徳を推進する人々を「改良者」と呼んでおり、引用符はこれらの人々が人間を改良するという目標を達成できなかったという事実を表しています。
最初の例は宗教です。ニーチェはこの例で、ある司祭が男の道徳心を保つためにキリスト教に改宗させるという架空の物語を語ります。しかし、その男はやがて情欲といった人間の基本的な本能に陥り、罪人として烙印を押されます。その後、男は憎しみに満ち、他者から疎外されます。この物語の司祭は「改善者」の象徴であり、誰かを道徳的に導こうとしますが、結局は男の人生を惨めなものにしてしまうのです。
二つ目の例は、インドにおいてマヌスムリティによって認可されたカースト制度である。この制度は、4人種以上の交配を禁じることで人間を道徳化しようと試み、結果として追放されたチャンダラ族を非人間化した。このシナリオにおける「改善者」はマヌスムリティであり、アーリア人の価値観を強制するために、人々に対する道徳的偏見を助長している。[17]
ドイツ人に欠けているもの
ニーチェは当時のドイツ社会を考察し、ドイツ人が他のヨーロッパ諸国に対して持つ優位性は、文化的な洗練度ではなく、基本的な倫理的美徳によるものだと指摘した。ニーチェは、ドイツ思想の洗練度の低下は、知性よりも政治を優先したことに起因すると指摘した。国家と文化は、一方が他方を犠牲にして繁栄しているため、緊張関係にある。
文化と国家――この点で誤解してはならない――は敵対関係にある。「文化国家」とは単なる近代的な概念に過ぎない。一方が他方に依存し、一方が他方を犠牲にして繁栄する。すべての偉大な文化時代は政治的衰退の時代である。文化的な意味で偉大なものは、非政治的、いや、反政治的でさえあったのだ。[18]
ニーチェはまた、ドイツの知性の衰退を、当時の高等教育に見られた問題に起因するものとしている。まず、ニーチェは大学教員の資質に疑問を投げかけ、「自らも教育を受けた教育者」の必要性を主張する。教育者は、三つの重要な技能、すなわち「見る力」(衝動的に行動する前に考える能力)、思考力(「思考力はダンスを学ぶように学ばなければならない」)、そして「話す力と書く力」(「人はペンで踊ることができなければならない」)を教えるために不可欠であると彼は主張する。第二に、彼は大学を社会のあらゆる階層に開放することに対して強い批判的態度を示す。なぜなら、その「特権」が剥奪されると、高等教育の質が低下するからである。「高等教育はすべて例外的なものである。これほど高い特権を得るには、特権を与えられる必要がある。偉大で優れたものは決して共有財産にはなり得ない。」[19]
若くしてこの世を去った男の小競り合い
本書で最も長い章で、ニーチェは当時の様々な文化人を考察しています。また、人生に対する異なる態度を抱くきっかけとなるものについて、数々の心理学的考察も行っています。
古代人に負うもの
ニーチェはプラトンを批判し、「過剰な道徳」と「崇高な詐欺師」と呼んだ。さらに、その有害な道徳観において「キリスト教は民衆のためのプラトン主義である」と主張する。ニーチェはプラトンの生命への憎悪と見なすものに反論し、人間は苦しみを抱えながらも生命を大切にすべきだと主張する。ニーチェはディオニュソス秘儀を引用し、私たちは生命に勝利の「はい」と答える必要があり、苦痛でさえも神聖なものだと主張する。また、ニーチェは永劫回帰、つまり、もし自分が知らないうちに細部に至るまで同じ人生を何度も何度も生きなければならないと知ったら幸せだろうかという思考実験にも言及し(ニーチェは答えは「はい」であるべきだと考えている)、人々に生命を受け入れ、祝福するよう促した。ニーチェは、自分自身であることは「永遠の生成の喜び」であると信じていた。
ハンマーが語る
ニーチェは『ツァラトゥストラはこう語った』の第3部「古い法の板と新しい法の板について」について語っている。[20]
注記
- ^ ラージ・ダンカン(訳)『偶像の黄昏』(オックスフォード大学出版局)p. ix
- ^ トリノ、1888年10月20日。ゲオルク・ブランデス宛。当初の題名は『心理学者の怠惰』であったが、『偶像の黄昏、あるいはハンマーで哲学する方法』と改題された。
- ^ カウフマン、W.、「ポータブル・ニーチェ」、ニューヨーク:ヴァイキング、1954年、463ページ。
- ^ ニーチェ、フリードリヒ (1911)。エッチ ホモ。ポートランド、私。12~ 13ページ 。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^ ニーチェ、フリードリヒ (1911)。エッチ ホモ。ポートランド、私。 p. 12.
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^ ニーチェ、フリードリヒ、アンセル=ピアソン、キャロル・ディーテ(2008年)『道徳の系譜について』ケンブリッジ政治思想史テキスト(第3刷)ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-69163-5。
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 2003年43ページ。
- ^ ニーチェ、フリードリヒ著『偶像の黄昏と反キリスト』 RJホリングデール訳、ハーモンズワース:ペンギン社、1977年、40、55ページ。
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 45ページ。
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 49ページより。
- ^ ニーチェ、フリードリヒ著『偶像と反キリストの黄昏』 RJホリングデール訳、ペンギンブックス、ニューヨーク、2003年、52頁
- ^ ニーチェ、フリードリヒ著『偶像と反キリストの黄昏』 RJホリングデール訳、ペンギンブックス、ニューヨーク、2003年、56-57頁
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 60ページ。
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 65ページ。
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 54ページ。
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 64ページ。
- ^ 「フリードリヒ・ニーチェ ― 偶像の黄昏(第6章)」Genius . 2023年5月23日閲覧。
- ^ ニーチェ、フリードリヒ著『偶像と反キリストの黄昏』RJホリングデール訳、ペンギンブックス、ニューヨーク、2003年、74頁
- ^ ニーチェ、フリードリヒ著『偶像と反キリストの黄昏』RJホリングデール訳、ペンギンブックス、ニューヨーク、2003年、75頁
- ^ ニーチェ『偶像の黄昏』 122ページ
参考文献
- ベルント・マグヌス『平凡なものの神格化:偶像の黄昏』、ソロモン、ロバート・C. / ヒギンズ、キャスリーン・M.(編)『ニーチェを読む』、ニューヨーク / オックスフォード、1988年、152~181頁。
- ダンカン・ラージ:翻訳研究の観点から見たゲッツェン・ダメルング、ニーチェフォルシュング。 Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft 16: Nietzsche im Film、Projektionen und Götzen-Dämmerungen、ベルリン、2009 年、151 ~ 160 ページ。
- アンドレアス・ウルス・ゾンマー:ワーグナーのニーチェの解説。 Götzendämmerung (= Heidelberger Akademie der Wissenschaften (ed.): Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken、vol. 6/1)。 XVII + 698 ページ。ベルリン / ボストン: Walter de Gruyter 2012 ( ISBN) 978-3-11-028683-0)。
外部リンク
- NietzscheSource.org オリジナル版
- プロジェクト・グーテンベルクの「偶像の黄昏」(英語、ルドヴィチ訳)
- プロジェクト・グーテンベルクのゲッツェン・ダムメルング(ドイツ語)
- 英語翻訳:ウォルター・カウフマン、RJ・ホリングデール
 LibriVoxのパブリック ドメイン オーディオブック『Twilight of the Idols』(英語、ルドヴィチ訳)
LibriVoxのパブリック ドメイン オーディオブック『Twilight of the Idols』(英語、ルドヴィチ訳) Götzen-Dämmerung LibriVoxのパブリック ドメイン オーディオブック(ドイツ語)
Götzen-Dämmerung LibriVoxのパブリック ドメイン オーディオブック(ドイツ語)- 偶像の黄昏(英語、フェラー訳、2013年)

