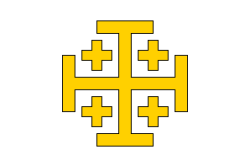エルサレム王国
 |
エルサレム王国
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099–1187 1192–1291 | |||||||||||||
 | |||||||||||||
| 資本 | |||||||||||||
| 公用語 | ラテン | ||||||||||||
| 共通言語 | 古フランス語、イタリア語、中世ギリシャ語、アラビア語、アラム語 | ||||||||||||
| 宗教 | ラテン教会東方キリスト教イスラム教(少数派)ユダヤ教 | ||||||||||||
| 政府 | 封建君主制 | ||||||||||||
| エルサレムの王 | |||||||||||||
• 1099–1100年(初代) | ゴドフロワ・ド・ブイヨン | ||||||||||||
• 1285–1291 (最後) | ヘンリー2世 | ||||||||||||
| 立法府 | オートクール | ||||||||||||
| 歴史的時代 | 中世盛期 | ||||||||||||
• 第1回十字軍 | 1096–1099 | ||||||||||||
• エルサレムの占領 | 1099年7月15日 | ||||||||||||
| 1187年10月2日 | |||||||||||||
• 第三回十字軍 | 1189–1192 | ||||||||||||
• 第六回十字軍 | 1228–1229 | ||||||||||||
• 男爵の十字軍 | 1239–1241 | ||||||||||||
| 1244年7月15日 | |||||||||||||
• エーカーの陥落 | 1291年5月18日 | ||||||||||||
| 人口 | |||||||||||||
• 1131 [ 2 ] | 25万 | ||||||||||||
| 48万~65万 | |||||||||||||
| 通貨 | ベザン、デニエ | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 今日の一部 | |||||||||||||
| シリーズの一部 |
| エルサレム |
|---|
 |
エルサレム王国は、十字軍王国としても知られ、第1回十字軍直後にレヴァント地方に建国された十字軍国家の一つです。1099年にゴドフロワ・ド・ブイヨンが即位してから1291年にアッコが陥落するまで、ほぼ200年間存続しました。その歴史は、1187年のエルサレム包囲後の崩壊と、1192年の第3回十字軍後の復興という短い中断期間を挟んで、2つの時期に分けられます。
元々の王国は1099年から1187年まで存続しましたが、サラディン率いるアイユーブ朝によってほぼ完全に滅ぼされました。第三回十字軍の後、1192年にアッコで再建されました。再建されたこの国家は、一般的に「第二エルサレム王国」、あるいは新たな首都にちなんで「アッコ王国」として知られています。アッコは、第六回十字軍においてフリードリヒ2世皇帝の外交を通じて十字軍がエルサレムを部分的に支配した後の20年間も、存続期間中ずっと首都であり続けました。
エルサレム王国に定住した十字軍の大部分はフランス王国出身であり、200年の歴史を通じて継続的に増援を送った騎士や兵士もフランス王国出身であったため、その統治者やエリート層は主にフランス人であった。[ 4 ]エルサレム王国は、その歴史を通じて、特に王国の首都が港湾都市アッコに移ってからは、イタリアの海洋共和国であるヴェネツィアとジェノヴァへの依存と影響をますます強めていった。[ 5 ] [ 6 ]
地理的境界
当初、この王国は第1回十字軍で征服した町や都市の緩やかな集合体に過ぎなかったが、12世紀半ばの最盛期には、現在のイスラエル、パレスチナ、ベイルートを含むレバノン南部の領域をほぼ網羅していた。地中海からは、北はベイルートから南はシナイ砂漠、東は現在のヨルダンとシリア、西はエジプトまで、細長く広がっていた。第1回十字軍中および後に建国された他の3つの十字軍国家は、さらに北に位置していた。エデッサ伯国(1097年 - 1144年)、アンティオキア公国(1098年 - 1268年)、トリポリ伯国(1109年 - 1289年)である。これらはすべて独立していたが、エルサレムと密接な結びつきがあった。これらの北と西には、アルメニア・キリキアとビザンチン帝国が位置し、エルサレムは12世紀にこれらと密接な関係を持っていました。さらに東では、様々なイスラム首長国が最終的にバグダッドのアッバース朝と同盟を結びました。王国は、イタリアの都市国家であるヴェネツィアとジェノヴァの支配が強まっていきました。彼らの海軍力は、兵士、食料、物資の輸送に不可欠であり、彼らの財源は、王国の軍事作戦を継続する上でしばしば決定的な役割を果たしました。王国の海上支援への依存が高まるにつれて、イタリア共和国の地方政治、外交、経済生活への影響力も高まりました。ヴェネツィアとジェノヴァは王国を直接統治することはありませんでしたが、王国の政策と優先事項を効果的に形作り、十字軍国家はますます彼らの力に依存するようになりました。[ 5 ] [ 6 ]
神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世(在位1220~1250年)は十字軍国家に野望を抱き、婚姻によって王国を主張したが、彼の存在は王国の貴族たちの間で内戦(1228~1243年)を引き起こした。王国は、エジプトのアイユーブ朝とマムルーク朝、そしてホラズム朝とモンゴル帝国の侵略者たちの政治と戦争において、ほとんど駒として扱われるに過ぎなかった。比較的小さな王国であったため、ヨーロッパからの財政的・軍事的支援はほとんど受けなかった。数々の小規模な遠征があったにもかかわらず、ヨーロッパ人は明らかに勝ち目のない大義のために、費用のかかる東方への旅に出ることを一般的に望まなかった。マムルーク朝のスルタンであるバイバルス(統治期間1260~1277年)とアシュラフ・ハリール(統治期間1290~1293年)は、最終的に残っていた十字軍の拠点をすべて再征服し、 1291年にはアッコを破壊した。
人々
王国は民族的、宗教的、言語的に多様であったが、十字軍は自身とその子孫をエリートカトリック少数派として確立した。彼らはヨーロッパの故郷から多くの慣習や制度を導入し、王国存続を通じて西洋との密接な家族的、政治的つながりを維持していた。王国はまた、既存の慣習や人口の影響を受けた「東洋的」な特質も受け継いでいた。王国の住民の大部分は、ギリシャ正教徒とシリア正教徒を中心とした土着のキリスト教徒、そしてスンニ派とシーア派のイスラム教徒であった。疎外された下層階級であった土着のキリスト教徒とイスラム教徒はギリシャ語とアラビア語を話す傾向があったが、主にフランス王国から来た十字軍はフランス語を話した。また、少数のユダヤ人とサマリア人も存在した。[ 7 ]
1170年頃に王国を旅したトゥデラのベンジャミンによると、ナブルスには1,000人、カイサリアには200人、アスカロンには300人のサマリア人がいたという。同時代のサマリア人年代記『トリダ』にはガザとアッコのコミュニティについても言及されているため、サマリア人の人口の下限は1,500人となる。トゥデラのベンジャミンは、王国内の14都市のユダヤ人人口を合計1,200人と推定しており、当時のサマリア人の人口がユダヤ人の人口を上回ったのは、おそらく歴史上唯一のことであった。[ 8 ]
歴史
第一次十字軍と王国の建国
第1回十字軍は、 1095年のクレルモン公会議において教皇ウルバヌス2世によって布告され、その目的は「トルコ人とアラブ人」の侵略からビザンチン帝国を支援し、「この卑劣な民族を友の土地から滅ぼす」ことであった。[ 9 ]しかし、すぐに主目的は聖地の支配へと移った。ビザンチン帝国はアナトリアとシリアの支配権をめぐって、セルジューク朝をはじめとするトルコ系王朝と頻繁に戦争を繰り広げていた。セルジューク帝国はかつてスンニ派のセルジューク人が支配していたが、1092年にマリク・シャー1世が死去した後、この帝国はいくつかの小国に分裂した。マリク・シャーの後継者としてアナトリアのルーム・スルタン国はキリジ・アルスラーン1世が、シリアでは弟のトゥトゥシュ1世が1095年に死去した。トゥトゥシュの息子であるファフル・アル・ムルク・ラドワンとドゥカクはそれぞれアレッポとダマスカスを継承し、シリアは互いに敵対するエミールたちとモスルのアタベグであるケルボガの間でさらに分割された。アナトリアとシリアのエミールの不統一により、十字軍はエルサレムへの道中で直面した軍事的抵抗を克服することができた。[ 10 ]
エジプトとパレスチナの大部分はファーティマ朝の支配下にあり、セルジューク朝到来以前にはシリアにまで勢力を拡大していました。ファーティマ朝とセルジューク朝の間の戦争は、地元のキリスト教徒と西方からの巡礼者に大きな混乱をもたらしました。ファーティマ朝は名目上はカリフのアル=ムスタリの統治下にありましたが、実際には宰相のアル=アフダル・シャーハンシャーによって統治されていました。1073年にセルジューク朝にエルサレムを奪われました。[ 11 ]ファーティマ朝は1098年、十字軍到来直前に、セルジューク朝と関係のあるトルコ系の小部族であるアルトゥク朝からエルサレムを奪還しました。 [ 12 ]

十字軍は1099年6月にエルサレムに到着し、近隣の町のいくつか(ラムラ、リダ、ベツレヘムなど)を最初に占領し、エルサレムは7月15日に占領されました。[ 13 ] 7月22日、聖墳墓教会で会議が開かれ、新しく建国されたエルサレム王国の国王を選出しました。トゥールーズ伯レーモン4世とゴドフロワ・ド・ブイヨンが十字軍とエルサレム包囲の指導者として認められました。レーモンは2人の中ではより裕福で権力もありましたが、最初は国王になることを拒否しました。おそらく自分の信心を示そうとしたためであり、他の貴族がいずれにせよ自分の選出を主張するだろうと期待していたのでしょう。[ 14 ]より人気のあったゴドフロワはレーモンのようにためらうことなく指導者の地位を受け入れました。現代の歴史家の多くは、彼が聖墳墓の「弁護者」または「擁護者」という称号を名乗ったと記録している。他の歴史家は、ゴドフロワはより曖昧な「プリンケプス」という用語を用いたようだ、あるいは単に下ロレーヌ地方の「ドゥクス」という称号を保持していたと報告している。12世紀半ば、ゴドフロワが伝説の英雄となった頃の著作に、ティルスのウィリアムが記しているように、彼はキリストが「茨の冠」を被ったのに対し、「金の冠」を被ることを拒否したという。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]レーモンドは激怒し、軍隊を率いて街から食料を探しに出て行った。新しい王国とゴドフロワの名声は、 8月12日のアスカロンの戦いでアフダル・シャーンシャー率いるエジプト軍に勝利したことで確固たるものとなったが、レーモンドとゴドフロワの継続的な敵対関係により、十字軍はアスカロンを占領することができなかった。[ 18 ]
新しい王国をどう扱うかについては、依然として不確実性があった。教皇特使ピサのダインベルトは、教皇の直接支配下にある神権国家を樹立する意図で、ラテン総主教としてゴドフリーにエルサレムを譲るよう説得した。ティルスのウィリアムによると、ゴドフリーはダインベルトの努力を支持した可能性があり、ダインベルトがエルサレムを統治することを許されるなら「さらに1つか2つの都市を占領し、それによって王国を拡大する」ことに同意した。[ 19 ]ゴドフリーは確かにヤッファ、ハイファ、ティベリアなどの都市を占領し、他の多くの都市を貢納国にすることで王国の境界を拡大した。彼は王国における封臣制度の基礎を築き、ガリラヤ公国とヤッファ伯国を設立したが、その治世は短く、1100年に病死した。弟のブローニュ伯ボードゥアンはダンベルトを出し抜き、「エルサレムのラテン人の王」としてエルサレムを主張した。ダンベルトは妥協し、ボードゥアンにエルサレムではなくベツレヘムで戴冠式を行ったが、エルサレムにおける君主制への道はすでに開かれていた。[ 20 ]この枠組みの中で、東方正教会とシリア正教会の権威者たちの上にカトリックの聖職者階級が確立された。両教会はそれぞれ独自の聖職者階級を維持していた(カトリックは彼らを分離主義者であり非合法とみなし、逆もまた同様であった)。ラテン総主教の下には4つの属司教区と多数の教区が存在した。[ 21 ]
拡大
ボードゥアンの治世下、王国はさらに拡大しました。 1101年の小規模な十字軍によって王国に援軍がもたらされ、ヨーロッパからの居住者数も増加しました。ボールドウィンは1115年にヨルダン川を渡って遠征した後、エルサレムにフランク人と土着のキリスト教徒を再び住まわせた。[ 22 ]イタリアの都市国家や他の冒険家、特にノルウェー王シグルズ1世の支援を受けて、ボールドウィンは港湾都市アッコ(1104年)、ベイルート(1110年)、シドン(1111年)を占領し、同時に北方の他の十字軍国家、エデッサ(1097年の十字軍中に彼が建国)、アンティオキア、トリポリ(1109年の占領に貢献)に対する宗主権を行使した。彼はラムラや王国南西部のその他の場所でのファーティマ朝からのイスラム教徒の侵略を何度も防ぎ、 1113年には北東部のアル・サンナブラの戦いでダマスカスとモスルからのイスラム教徒の侵略を防いだ。 [ 23 ]歴史家トーマス・マッデンが言うように、ボールドウィンは「真の創始者」であった。 「エルサレム王国の君主」として知られる彼は、「不安定な体制を強固な封建国家へと変貌させた。才気と勤勉さで強力な君主制を確立し、パレスチナ沿岸を征服し、十字軍の貴族たちを和解させ、王国のイスラム教徒隣国に対する強固な国境を築いた。」[ 24 ]

ボールドウィンは、エデッサのアルメニア人住民からの政治的支持を得るためにアルダという名のアルメニア人を妻として連れてきたが、エルサレムでアルメニア人の支持が不要になるとすぐに彼女を離縁した。1113年、彼はシチリアの摂政アデライデ・デル・ヴァストと重婚したが、1117年には彼女も離婚させられた。アデライデの最初の妻との間に生まれた息子、シチリア王ルッジェーロ2世はエルサレムを決して許さず、数十年にわたりシチリア海軍からの支援を差し控えた。[ 25 ]
1118年、エジプト遠征中にボードゥアンは跡継ぎを残さずに死去し、王国はボードゥアンとゴドフロワに同行して十字軍に参加していた弟のブローニュ公エウスタシュ3世に与えられた。エウスタシュは興味を示さず、代わりに王位はボードゥアンの親戚でおそらく従兄弟で、エデッサでボードゥアンの後を継いでいたル・ブール公ボードゥアンに渡された。ボードゥアン2世は有能な統治者であり、ファーティマ朝とセルジューク朝の侵略に対する防衛にも成功した。 1119年のアゲル・サングイニスの戦いの後、アンティオキアは著しく弱体化し、ボードゥアンは1123年から1124年までアレッポのエミールに捕らえられたが、ボードゥアンは1125年のアザーズの戦いで十字軍諸国を勝利に導いた。彼の治世中には、最初の軍事組織である聖ヨハネ騎士団とテンプル騎士団が設立された。 1120年にナブルス公会議で編纂された王国最古の成文法、および1124年にヴェネツィア共和国との最初の通商条約であるワルムンディ協定を締結した。ヴェネツィアからの海軍および陸軍の支援が増大したことで、その年にティルスは占領された。エルサレムの影響力はさらにエデッサとアンティオキアにも拡大し、これらの地域では自国の指導者が戦闘で戦死した際にボードゥアンが摂政を務めたが、ボードゥアンが捕囚されている間もエルサレムにも摂政政府が存在した。[ 26 ]ボードゥアンはアルメニアの貴族女性、メリテネのモルフィアと結婚し、4人の娘がいた。ホディエルナとアリスはトリポリ伯爵とアンティオキア公爵の家族と結婚した。イオヴェタは有力な女子修道院長となった。長女メリザンドは彼の後継者となり、1131年に彼が死去すると、夫のアンジュー伯フルク5世を王妃として王位を継承した。彼らの息子、後のボードゥアン3世は、祖父によって共同相続人に指名された。[ 27 ]
エデッサ、ダマスカス、そして第2回十字軍

フルクは経験豊富な十字軍戦士であり、 1120年の巡礼の際には王国に軍事支援をもたらしていた。彼はアンジュー公ジョフロワ5世の父であり、後のイングランド王ヘンリー2世の祖父として、エルサレムをアンジュー帝国の支配下に置いた。外国人を王に据えることを誰もが歓迎したわけではない。1132年、アンティオキア、トリポリ、エデッサはいずれも独立を主張し、フルクがエルサレムの宗主権を行使するのを阻止しようと陰謀を企てた。彼は戦いでトリポリを破り、伯爵夫人メリザンドの姪コンスタンスと自身の親戚レーモンド・ド・ポワティエとの結婚を取り決めてアンティオキアに摂政を置いた。[ 28 ]一方エルサレムでは、現地の十字軍貴族がフルクがアンジュー家の従者を優先することに反対した。 1134年、ヤッファのユーグ2世はフルクに反乱を起こし、アスカロンのイスラム教徒守備隊と同盟を結びました。このため、ユーグ2世は欠席裁判で反逆罪で有罪判決を受けました。ラテン総主教ウィリアム・オブ・マリーヌが紛争の解決にあたりましたが、ユーグ暗殺未遂事件が発生し、フルクが責任を問われました。このスキャンダルにより、メリザンドとその支持者たちは、父の思惑通り、政権を掌握することができました。[ 29 ]そのため、フルクは「非常に寵愛するようになり、…些細な事柄でさえ、彼女の承認と支援なしにはいかなる措置も取らなかった」[ 30 ] 。
フルクは新たな、そしてより危険な敵に直面した。アレッポを支配し、ダマスカスにも狙いを定めていたモスルのアタベグ、ゼンギーであった。これら3国の統合は、勢力を拡大していたエルサレムに深刻な打撃を与えたであろう。十字軍諸国すべてに帝国の宗主権を主張したかったビザンツ皇帝ヨハネス2世コムネノスは、1137年から1138年にかけて短期間介入したが、ゼンギーの脅威を止めることはできなかった。1139年、ダマスカスとエルサレムは両国に対する脅威の深刻さを認識し、ゼンギーの進軍を阻止する同盟が締結された。フルクはこの期間を利用してイベリンやケラクを含む多くの城を建設した。[ 31 ] 1143年にフルクとヨハネ皇帝が別々の狩猟事故で亡くなった後、ゼンギは1144年にエデッサに侵攻して征服しました。長男ボードゥアン3世の摂政となったメリザンド女王は、フルクの死後、軍の指揮官としてイエルゲスのマナセスを任命しましたが、エデッサは奪還できませんでした。 [ 32 ]エデッサの陥落はヨーロッパに衝撃を与え、 1148年に第二次十字軍が到着しました。
6月にアッコで会談した後、十字軍の王であるフランス国王ルイ7世とドイツ国王コンラート3世は、メリザンド、ボードゥアンおよび王国の主要貴族らとダマスカス攻撃に同意した。ゼンギーの領土は1145年の死後息子たちに分割されており、ダマスカスはもはや脅威を感じていなかったため、ゼンギーの息子でアレッポの首長ヌールッディーンと同盟を結んでいた。おそらく過去数十年にわたりダマスカスからエルサレムへの攻撃が開始されたことを思い出し、アレッポやエデッサの奪還が可能になる北方の都市よりも、ダマスカスが十字軍にとって最良の攻撃目標と思われた。続くダマスカス包囲戦は完全な失敗に終わった。市が崩壊寸前と思われたとき、十字軍は突如として城壁の別の区画に進軍し、撃退された。十字軍は3日以内に撤退した。裏切りと賄賂の噂が流れ、コンラッドはエルサレムの貴族たちに裏切られたと感じた。失敗の理由が何であれ、フランス軍とドイツ軍は帰国し、数年後にはダマスカスはヌールッディーンの支配下に置かれました。[ 33 ]
内戦
第二次十字軍の失敗は、王国にとって長期にわたる悲惨な結果をもたらした。西洋諸国は大規模な遠征を躊躇し、その後数十年間は、巡礼を希望するヨーロッパの小貴族を先頭とした小規模な軍隊のみが派遣された。一方、シリアのイスラム諸国はヌールッディーンによって徐々に統一され、ヌールッディーンが1149年のイナブの戦いでアンティオキア公国を破り、1154年にはダマスカスを制圧した。ヌールッディーンは非常に敬虔で、彼の統治下ではジハードの概念は王国に対する一種の反十字軍と解釈されるようになり、これは政治的にも精神的にもイスラム教徒の統一を阻害するものであった。[ 34 ]

エルサレムでは、十字軍はメリザンドとボードゥアンの争いに気をとられていた。ボードゥアンが成人した後も、メリザンドは摂政として長く統治を続けた。彼女を支えたのは、実質的に彼女のために執政を務めたイエルゲスのマナセス、彼女がヤッファ伯に据えたその息子のアマルリック、ミリーのフィリップ、そしてイベリン家であった。ボードゥアンはアンティオキアとトリポリの紛争の調停を行うことで独立を主張し、イベリン兄弟がマナセスの勢力拡大に反対し始めた時には、彼らの未亡人となった母ラムラのヘルヴィスと結婚していたおかげで彼らの支持を得た。1153年、ボードゥアンは自ら単独の支配者として戴冠し、妥協により王国は2つに分割され、ボードゥアンは北のアッコとティルスを手に入れ、メリザンドはエルサレムと南の諸都市の支配権を維持することとなった。ボードゥアンはマナセスを自身の支持者の一人、トロンのフムス2世に交代させた。ボードゥアンとメリザンドはこの状況が耐えられないことを知っていた。ボードゥアンは母の領地を侵略し、マナセスを破り、エルサレムのダビデの塔で母を包囲した。メリザンドは降伏してナブルスに退いたが、ボードゥアンは彼女を摂政兼首席顧問に任命し、特に教会の役人の任命においていくらかの影響力を保持した。[ 35 ] 1153年、ボードゥアンはアスカロンへの攻撃を開始した。アスカロンは王国の建国以来、ファーティマ朝エジプト軍がエルサレムを攻撃し続けて来た南部の要塞であった。要塞は占領され、ヤッファ伯領に編入された。[ 36 ]
ビザンツ同盟とエジプト侵攻

アスカロンの占領により王国の南の国境は安全になり、かつては王国にとって大きな脅威であったが、数人の未成年のカリフの統治下で不安定化していたエジプトは朝貢国に転落した。ヌールッディーンは東方で依然として脅威であり、ボードゥアンはアンティオキア公国の宗主権を主張するビザンツ帝国皇帝マヌエル1世コムネノスの侵攻に対処しなければならなかった。イスラム教徒の勢力拡大に対する王国の防衛を強化するため、ボードゥアンはマヌエルの姪テオドラ・コムネナと結婚することでビザンツ帝国と初めて直接同盟を結んだ。マヌエルはボードゥアンの従妹マリアと結婚した。[ 37 ]ウィリアム・オブ・ティルスが述べたように、マヌエルが「自身の豊かさによって我々の王国が苦しんでいる苦難を軽減し、我々の貧困を過剰に変える」ことができると期待されていた。[ 38 ]ビザンツ帝国とエルサレムの関係は歴史家の間で意見が分かれており、アマルリックがマヌエルを領主として認めたというビザンツ帝国の解釈を支持する歴史家もいるが、アンドリュー・ヨティシュキーなどの他の学者は、この関係はビザンツ帝国がエルサレムの正教徒を保護した関係の一つであると見ている。[ 39 ]
1162年、ボードゥアンが母メリザンドの死から1年後に子を残さずに亡くなると、王国はアマルリックの手に渡り、アマルリックはボードゥアンが交渉した同盟を更新した。1163年、エジプトの混乱した状況からエルサレムへの貢物の支払いが拒否され、エジプトの宰相シャーワルはヌールッディーンに援助を要請した。アマルリックはこれに応えてエジプトに侵攻したが、エジプト軍がビルベイスでナイル川を氾濫させたため撃退された。シャーワルは再びヌールッディーンに援助を要請し、ヌールッディーンからは将軍シール・クーフが派遣されたが、シャーワルはすぐに背を向け、アマルリックと同盟を結んだ。1164年、アマルリックとシール・クーフはともにビルベイスを包囲したが、ヌールッディーンのアンティオキアに対する作戦により撤退した。アンティオキアでは、ハリムの戦いでアンティオキアのボエモン3世とトリポリのレイモンド3世が敗れた。アンティオキアはヌールッディーンに陥落すると思われたが、マヌエル帝がビザンチン帝国の大軍をこの地域に派遣したため、ヌールッディーンも撤退した。ヌールッディーンは1166年にシール・クーフをエジプトに送り返し、シャーワールは再びアマルリックと同盟を結んだが、アマルリックはアル・ババインの戦いで敗北した。敗北にもかかわらず両軍は撤退したが、シャーワールはカイロに十字軍を駐屯させ、支配権を維持した。[ 40 ] [ 41 ]
アマルリックは1167年にマヌエルの姪マリア・コムネネと結婚してマヌエルとの同盟を強固なものにし、ウィリアム1世率いる使節団が軍事遠征の交渉のためコンスタンティノープルに派遣されたが、1168年にアマルリックはマヌエルが約束した海軍の支援を待たずにビルベイスを略奪した。アマルリックはそれ以上のことは成し遂げなかったが、彼の行動がきっかけでシャワールは再び寝返り、シール・クーフに助けを求めた。シャワールは速やかにシール・クーフによって処刑され、1169年にシール・クーフが死去すると、サラディンとして知られる甥のユースフが後を継いだ。同年、マヌエルはアマルリックの支援のため約300隻からなる大ビザンツ艦隊を派遣し、ダミエッタの町は包囲された。しかし、ビザンツ艦隊が航海できたのはわずか3か月分の食料だけだった。十字軍の準備が整った頃には、既に物資は底を尽きており、艦隊は撤退した。両陣営は失敗の責任を互いに押し付け合おうとしたが、互いの支援なしにエジプトを占領することはできないと認識していた。同盟は維持され、エジプトへの新たな遠征計画が立てられたが、最終的には失敗に終わった。[ 42 ]
最終的にヌールッディーンが勝利し、サラディンはエジプトのスルタンの地位を確立した。サラディンはヌールッディーンからの独立を主張し始め、1174年にアマルリックとヌールッディーンが共に死去したことで、ヌールッディーンのシリア領土も支配する立場に立った。[ 43 ]
ボードゥアン4世とサラディン

その後の出来事は、しばしば二つの対立する派閥間の争いとして解釈されてきた。一つは、小王ボードゥアン4世の母、アモーリックの最初の妻アグネス・オブ・コートネイとその近しい家族、そして王国の事情に不慣れでサラディンとの戦争に賛成するヨーロッパからの最近の移住者からなる「宮廷派」、もう一つは、トリポリのレーモンドと王国の下級貴族が率いる「貴族派」であり、イスラム教徒との平和的共存を支持した。これは「貴族派」に確固たる地位を築いていたティルスのウィリアムによる解釈であり、彼の見解は後世の歴史家たちにも引き継がれた。20世紀には、マーシャル・W・ボードゥアン[ 44 ] 、スティーヴン・ランシマン[ 45 ] 、ハンス・E・マイヤー[ 46 ]がこの解釈を支持した。一方、ピーター・W・エドベリーは、ウィリアム自身も、ウィリアムの年代記を継承し、レイモンドの支持者であるイベリン家と同盟を結んだ13世紀の著述家たちも、公平な立場にあるとは考えられないと主張している。 [ 47 ]事件は明らかに王朝間の争いであったが、「分裂は、現地の男爵と西から来た新参者の間ではなく、王の母方の親族と父方の親族の間であった」[ 48 ] 。
プランシーのマイルスは、ボードゥアン4世が未成年の間、短期間、摂政を務めた。マイルスは1174年10月に暗殺され、アモーリックの従弟にあたるトリポリ伯レーモン3世が摂政となった。レーモンかその支持者が暗殺を企てた可能性が高い。[ 49 ]ボードゥアンは1176年に成人し、ハンセン病を患っていたにも関わらず、摂政を必要とする法的根拠はなくなった。レーモンは男系ではボードゥアンに最も近い血縁者であり、王位継承権が強く、直系の後継者はいなかったものの、その野望の程度については懸念があった。この懸念を補うため、ボードゥアンは時折、 1176年に執事に任命された叔父のエデッサのジョスラン3世に頼った。ジョスランはレーモンよりもボードゥアンと血縁が近かったが、王位継承権はなかった。[ 50 ]
ハンセン病患者であったボードゥアンには子供がおらず、長く統治できるとは思えなかったため、継承権の中心は姉のシビーラと異母妹のイザベラに渡された。ボードゥアンと顧問たちは、軍事的危機の際にヨーロッパ諸国からの支援を得るためにはシビーラが西方の貴族と結婚することが不可欠であることを認識していた。レーモンがまだ摂政だった間に、シビーラと、フランス国王ルイ7世と神聖ローマ皇帝フリードリヒ・バルバロッサの従兄弟であるモンフェッラートのウィリアムとの結婚が取り決められた。西方皇帝の親族と同盟を結ぶことで、フリードリヒが王国の援助に来ることが期待された。[ 51 ]エルサレムは再びビザンツ帝国に助けを求め、マヌエル帝は1176年のミュリオケファロンの戦いでの敗北後、帝国の威信を回復する方法を模索していた。この任務はレーノー・ド・シャティヨンが引き受けた。[ 52 ] 1176年にモンフェッラートのウィリアムが到着した後、彼は病に倒れ、1177年6月に亡くなり、シビラは未亡人となり、将来のボードゥアン5世を身ごもった。レーノルドが摂政に任命された。[ 53 ]

その後まもなく、フランドルのフィリップが巡礼のためエルサレムに到着した。彼はボードゥアン4世の従弟であり、国王は彼に摂政と軍の指揮権を与えたが、フィリップはどちらも拒否した。特にレーナールの摂政任命には反対した。フィリップはシビラの2番目の夫をめぐる交渉に介入しようとし、自身の従者の一人を推薦したが、現地の男爵たちは彼の提案を拒否した。さらにフィリップはエジプトに独自の領土を確保できると考えていたようだったが、計画されていたビザンツ・エルサレム遠征への参加を拒否した。遠征は延期され、最終的に中止され、フィリップは軍を北へと撤退させた。[ 54 ]
エルサレム軍の大半は、フィリップ、レーモン3世、ボエモン3世と共にハマを攻撃するために北進し、サラディンはこの機会を捉えて王国に侵攻した。ボードゥアンは有能で精力的な王であると同時に、優れた軍事指揮官でもあった。1177年9月のモンジザールの戦いでは、圧倒的な兵力差と軍団による叛乱にもかかわらずサラディンを破った。病気にも関わらずボードゥアンがそこにいたことは人々に勇気を与えたが、軍事面での直接的な決定はレーモン3世によって下された。[ 55 ]
ブルゴーニュ公ユーグ3世はエルサレムに来てシビーヤと結婚すると思われていたが、ルイ7世の死後1179年から1180年にかけてフランスで政情不安が続いていたため、ユーグはフランスを離れることができなかった。一方、ボードゥアン4世の継母マリア(イザベルの母でシビーヤの継母)はイザベルの母でシビーヤの継母でもあるバリアン・ド・イブランと結婚した。1180年の復活祭に、レーモンと従弟のアンティオキア公ボエモン3世は、シビーヤをバリアンの弟であるバリアン・ド・イブランと結婚させようとした。レーモンとボエモンはボードゥアン王の父系の最も近い男性親族であり、王が後継者や適切な後任者を残さずに亡くなった場合には王位を主張できた。レーモンとボエモンが到着する前に、アニエスとボードゥアン王はシビーヤをポワトゥー出身の新参者ギー・ド・リュジニャンと結婚させようとした。ギーの兄アマルリックは既に宮廷で地位を確立していた。[ 56 ]国際的には、リュジニャン家はボードゥアンとシビラの従兄弟であるイングランド王ヘンリー2世の家臣として重宝された。ボードゥアンは8歳のイザベラを、権力者レーノルド・ド・シャティヨンの継子であるトロン公アンフリー4世と婚約させ、イブラン家と母の影響から彼女を遠ざけた。 [ 57 ]
王国内の2つの派閥間の争いは、1180年の新総主教選出に影響を与えた。アマルリック総主教が1180年10月6日に死去すると、後継者として最も有力視されたのはティルスのウィリアムとカイサリアのヘラクレイオスだった。2人は経歴や教育において互角だったが、ヘラクレイオスはアグネス・オブ・コートネイの支持者の1人であったため、政治的には反対の政党と同盟を結んでいた。聖墳墓教会の参事会員たちが国王に助言を求め、アグネスの影響でヘラクレイオスが選ばれた。アグネスとヘラクレイオスは恋人同士だったという噂もあったが、この情報は13世紀のティルスのウィリアムの歴史に関する党派的な続編から得たもので、そのような主張を立証する他の証拠はない。[ 58 ]
1181年末、レーノー・ド・シャティヨンはメディナ方面へ南下してアラビアを襲撃したが、そこまでは到達できなかった。レーノーがイスラム教徒の隊商を襲ったのもおそらくこの頃である。当時王国はサラディンと休戦しており、レーノーの行動は独自の山賊行為とみなされている。サラディンが軍を北進させてアレッポを占領し、サラディンの立場を強化するのを阻止しようとした可能性がある。[ 59 ]これに対しサラディンは1182年に王国を攻撃したが、ベルヴォア城で敗れた。ボードゥアン王は重病であったものの、まだ自ら軍を指揮することができた。サラディンは陸と海からベイルートを包囲しようとし、ボードゥアンはダマスカスの領土を襲撃したが、どちらの側も大きな損害を与えることはできなかった。 1182年12月、レーナルドは紅海に海軍遠征隊を派遣し、南はラービグまで到達した。遠征隊は敗北し、レーナルドの部下2人はメッカに連行され、公開処刑された。以前の襲撃と同様に、レーナルドの遠征は利己的でエルサレムにとって致命的なものと一般的に見なされているが、バーナード・ハミルトンによれば、実際にはサラディンの威信と評判を傷つけることを目的とした抜け目のない戦略であったという。[ 60 ]
1180年に親西派の皇帝マヌエルが崩御すると、エルサレム王国は最も強力な同盟国を失った。その息子アレクシオス2世は未成年であり、その母マリアの摂政は外国出身であること、プロトセバストス・アレクシオスとのスキャンダラスな恋愛関係、ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサなどのイタリア海洋共和国の商人に対する党派的態度のためにギリシャ人から反対されていた。3年後、アレクシオスはアンドロニコス・コムネノスによって暗殺された。コムネノスはコンスタンティノープルの城壁内に住むイタリア商人の大虐殺を扇動し、この虐殺によって西ヨーロッパとビザンチン帝国の関係が永久に悪化し、大分裂が悪化した。
1183年、王国全土に一般税が課されたが、これはエルサレムのみならず、当時の中世ヨーロッパのほぼ全域において前例のないことであった。この税はその後数年間、より大規模な軍隊の維持費に充てられた。サラディンはついにアレッポを制圧し、北部領土に平和がもたらされたことで南部のエルサレムに注力できるようになり、より多くの軍隊が必要になったのは明らかだった。ボードゥアン王はハンセン病で身体が不自由になり、摂政を任命する必要が生じた。そこでギー・ド・リュジニャンが選ばれた。彼はボードゥアン王の法定後継者であり、王の生存も危ぶまれていたからである。経験の浅いギーはフランク軍を率いてサラディンの王国侵攻に対抗したが、どちらの側も実質的な利益は得られず、ギーは機会があったにもかかわらずサラディンに攻撃を仕掛けなかったとして敵対者から批判された。[ 61 ]
1183年10月、イザベラはサラディンの包囲の最中、ケラクでトロンのフムスフリーと結婚した。サラディンはおそらく貴重な捕虜を得ることを期待していたのだろう。ボードゥアン王は、失明し身体が不自由になっていたものの、統治と軍の指揮を再開できるほど回復していたため、ギーは摂政の職を解かれ、ギーの5歳の継子でボードゥアン王の甥で同名のボードゥアンが11月に共同王として戴冠された。ボードゥアン王自らは輿を担ぎ、母に付き添われて城の救出に向かった。彼はトリポリのレーモンドと和解し、レーモンドを軍司令官に任命した。12月に包囲は解かれ、サラディンはダマスカスに撤退した。[ 62 ]サラディンは1184年にも再び包囲を試みたが、ボードゥアンはこの攻撃も撃退し、サラディンは帰路につく途中でナブルスなどの町を襲撃した。[ 63 ]
1184年10月、ギー・ド・リュジニャンはアスカロンの拠点からベドウィン遊牧民への攻撃を指揮した。レーナールが隊商を襲撃したのには軍事的な目的があったのかもしれないが、ギーが襲ったのはエルサレムに忠誠を誓い、サラディン軍の動向に関する情報を提供していた集団だった。時を同じくして、ボードゥアン王は病に倒れ、ギーではなくトリポリのレーモンが摂政に任命された。甥のボードゥアンはボードゥアン5世として王冠をかぶり、公の場で行進させられた。ボードゥアン4世は1185年5月、ハンセン病でついにこの世を去った。[ 64 ]
一方、王位継承危機は、西方への支援を求める使節団の派遣を促した。1184年、ヘラクレイオス総主教はヨーロッパ各地の宮廷を巡ったが、援助は得られなかった。ヘラクレイオスはフランス王フィリップ2世とイングランド王ヘンリー2世の双方に「聖墳墓の鍵、ダビデの塔の鍵、そしてエルサレム王国の旗」を差し出したが、王冠そのものは差し出さなかった。ヘンリー2世はフルクの孫でエルサレム王家の従兄弟であり、トマス・ベケット暗殺後に十字軍遠征に参加することを約束していた。両王はエルサレムの子供の摂政を務めるよりも、自国に留まって領土を守ることを望んだ。エルサレムへ赴いた数少ないヨーロッパの騎士たちは、サラディンとの休戦協定が再締結されていたため、戦闘さえ経験しなかった。モンフェッラート公ウィリアム5世は、孫ボードゥアン5世を助けに来た数少ない騎士の一人であった。[ 65 ]

ボードゥアン5世は、トリポリのレーモンドを摂政、大叔父のエデッサのジョスランを後見人としたが、統治は短かった。レーモンドは幼少期に病弱で、1186年の夏に亡くなった。レーモンドとその支持者たちはナブルスに行き、おそらくはシビラの王位継承を阻止しようとしたが、シビラとその支持者たちはエルサレムに行き、そこでギーとの結婚を無効にすれば王国はシビラに渡されることが決定された。シビラは同意したが、それは自分で夫と国王を選べるという条件付きだった。そして戴冠後、彼女は直ちに自らの手でギーを戴冠させた。レーモンドは戴冠式への出席を拒否しており、ナブルスで代わりにイザベラとハンフリーを戴冠させるよう提案したが、ハンフリーはこの案への同意を拒否した。この案は確実に内戦の引き金となるはずだった。ハンフリーはエルサレムに行き、ギーとシビラに忠誠を誓った。レーモンドの他の支持者の多くも同様であった。レーモンド自身はこれを拒否し、トリポリへ去った。イベリンのボードゥアンもこれを拒否し、領地を放棄してアンティオキアへ去った。[ 66 ]
エルサレムの喪失と第3回十字軍


トリポリのレーモンはギーに対抗するためにサラディンと同盟を結び、ティベリアにある自らの領地をイスラム教徒の守備隊に占領させた。おそらくサラディンがギー打倒の手助けをしてくれることを期待していたのだろう。一方、サラディンはメソポタミアの領土を平定し、十字軍王国への攻撃に躍起になっていた。1187年に休戦協定が失効した際、サラディンは休戦協定を更新するつもりはなかった。休戦協定失効前に、ウルトレジュールダンとケラクの領主でありギーの主要な支持者の一人であったレーノルド・ド・シャティヨンは、サラディンが軍勢を集結させていることに気づき、これを阻止しようとイスラム教徒の隊商を攻撃した。ギーはレーモンを攻撃する寸前だったが、サラディンの脅威に直面するには王国が統一される必要があると悟り、 1187年の復活祭の間にイブランのバリアンが両者の和解を成立させた。サラディンは4月に再びケラクを攻撃し、5月にはイスラム教徒の襲撃隊がレーモンと交渉に向かう途中のはるかに小規模な使節団に遭遇し、ナザレ近郊のクレソンの戦いでこれを破った。レーモンとギーは最終的にティベリアでサラディンを攻撃することで合意したが、作戦については意見が合わなかった。レーモンは会戦は避けるべきだと考えていたが、ギーは1183年に戦闘を避けたことで受けた批判を思い出したためか、サラディンに対して直接出撃することが決定された。1187年7月4日、王国の軍隊はハッティーンの戦いで完全に壊滅した。トリポリのレイモンド、イベリンのバリアン、シドンのレギナルドは逃亡したが、レイナルドはサラディンによって処刑され、ギーはダマスカスで投獄された。[ 67 ]
その後数か月で、サラディンは王国全体をいとも簡単に制圧した。フランク人の手中に残されたのはティルスの港だけであり、偶然にもコンスタンティノープルからちょうど間に合うよう到着していたモンフェッラートのコンラートが守っていた。エルサレムの陥落により、第一エルサレム王国は事実上終焉を迎えた。サラディンによる周辺地域の征服から逃れてきた難民で膨れ上がった住民の多くは、ティルス、トリポリ、あるいはエジプト(そこからヨーロッパに送還された)への逃亡を許されたが、自由の身となる代金を払えない者は奴隷として売られ、払える者は亡命の途中でキリスト教徒やイスラム教徒に同様に強盗に遭うことが多かった。エルサレムの占領をきっかけに、1189年にリチャード獅子心王、フィリップ・アウグストゥス、フリードリヒ・バルバロッサが率いる第三回十字軍が発足したが、最後の一人は途中で溺死した。[ 68 ]
コンラッドによってティルスへの入城を拒否されていたギー・ド・リュジニャンは、1189年にアッコの包囲を開始した。1191年まで続いたこの長期の包囲戦で、ヘラクレイオス総主教、シビーラ王妃とその娘たち、その他多くの人々が病死した。1190年にシビーラが亡くなったことでギーは王位継承権を失い、王位継承権はシビーラの異母妹イザベラに渡った。イザベラの母マリアとイブラン家(当時コンラッドと緊密な同盟を結んでいた)は、イザベラが当時未成年であったためアンフリーとの結婚は違法であると主張した。その根底には、アンフリーが1186年に妻の主義を裏切ったという事実があった。この結婚は論争の末に無効とされた。コンラッドは男系ではボードゥアン5世に最も近い親族となり、すでに有能な軍事指導者であることを証明していたため、イザベラと結婚したが、ギーは王位を譲ることを拒否した。[ 69 ]
1191年にリチャードが到着すると、彼とフィリップは継承権争いで異なる側についた。リチャードはポワトゥー出身の家臣ギーを支持し、フィリップは亡き父ルイ7世の従弟コンラッドを支持した。多くの悪感情と健康の悪化の後、フィリップはアッコ陥落直後の1191年に帰国した。リチャードは1191年のアルスフの戦い、1192年のヤッファの戦いでサラディンを破り、海岸線の大半を奪還したが、エルサレムや王国の内陸部は奪還できなかった。これはリチャードの失敗というよりもむしろ戦略的な判断だったのではないかという説もある。十字軍が防衛する義務がある限り、エルサレムは西方軍の援軍が到着できる海から隔絶されており、戦略的に負担になることを認識していた可能性があるからである。[ 70 ]コンラッドは1192年4月に満場一致で国王に選出されたが、わずか数日後にハシュシャシンによって殺害された。その8日後、妊娠中のイザベラは、リチャードとフィリップの甥でありながら政治的にはリチャードと同盟を結んでいたシャンパーニュ伯アンリ2世と結婚した。リチャードは補償として、リチャードがアッコへ向かう途中で奪取したキプロス島をギーに売却したが、ギーは1194年に死去するまでエルサレムの王位を主張し続けた。[ 71 ]
十字軍は1192年にラムラ条約が締結され、平和的に終結した。サラディンはエルサレムへの巡礼を許可し、十字軍兵士たちは誓いを果たした後に故郷へ帰還した。現地の十字軍男爵たちは、アッコをはじめとする沿岸都市から王国の再建に着手した。
エーカー王国
その後の100年間、エルサレム王国はシリア海岸沿いに広がる小さな王国のままであった。首都はアッコに移され、現在のイスラエルとレバノン南部および中部の海岸線の大半を支配下に置き、ヤッファ、アルスフ、カイサリア、ティルス、シドン、ベイルートといった要塞や町々を含んでいた。せいぜい、アスカロンやいくつかの内陸要塞といった他のいくつかの重要な都市と、トリポリとアンティオキアの宗主権を有した程度であった。新国王のアンリ・ド・シャンパーニュは1197年に事故死し、イザベルはギーの弟のエメリー・ド・リュジニャンと4度目の結婚をした。エメリーは既にギーからキプロスを相続しており、フリードリヒ・バルバロッサの息子である皇帝ハインリヒ6世によって国王に即位していた。ハインリヒは1197年に十字軍を率いたが、その途中で亡くなった。それにもかかわらず、彼の軍隊は1198年に帰国する前にベイルートとシドンを王国のために奪還した。[ 72 ] [ 73 ]その後、1198年にシリアのアイユーブ朝と5年間の休戦協定が締結された。[ 74 ]
アイユーブ朝は1193年のサラディンの死後、内戦に陥った。サラディンの息子たちは帝国の様々な地域の領有権を主張した。ザーヒルはアレッポを、アズィーズ・ウスマーンはカイロを、長男のアフダルはダマスカスを保持した。サラディンの弟であるアーディル・サイフ・アッディーン(十字軍からはしばしば「サファディン」と呼ばれた)はジャジーラ(メソポタミア北部)を獲得し、アーディルの息子であるムアザムはカラクとトランスヨルダンを占領した。1196年、アフダルはウスマーンと同盟を組んだアーディルによってダマスカスから追放された。1198年にウスマーンが亡くなると、アフダルはウスマーンの幼い息子のためにエジプトの摂政として権力を回復した。その後、ザヒルと同盟を結び、ダマスカスの叔父を攻撃した。同盟は崩壊し、アル=アーディルはエジプトでアル=アフダルを破り、エジプトを併合した。1200年、アル=アーディルはエジプトとシリアのスルタンを宣言し、ダマスカスをアル=ムアザムに、アル=ジャジーラをもう一人の息子アル=カミルに託した。兄弟によるダマスカス包囲戦が二度目に失敗に終わった後、アル=アフダルはサモサタをはじめとするいくつかの町からなる領地を受け入れた。1202年、アレッポのザヒルは叔父に服従し、アイユーブ朝の領土は再び統一された。[ 75 ]
一方、エジプトを経由してエルサレムを再征服する計画が練られた。第3回十字軍の失敗後、第4回十字軍が計画されたが、1204年にコンスタンティノープルが略奪され、参加した十字軍の大半は王国に到着しなかった。しかし、コンスタンティノープルへの迂回を知らなかったエメリーは、予想される侵攻に先立ちエジプトを襲撃した。[ 76 ]イザベラとエメリーは1205年に亡くなり、再び未成年の少女、イザベラとコンラッドの娘マリア・オブ・モンフェッラートがエルサレムの女王となった。イザベラの異母兄弟でベイルートの老領主ジャン・オブ・イベリンが摂政として統治し、1210年にマリアは経験豊富なフランス人騎士ジャン・オブ・ブリエンヌと結婚した。[ 77 ]マリアは1212年に出産で亡くなり、ジャン・オブ・ブリエンヌは娘イザベラ2世のために摂政として統治を続けた。[ 78 ]
第5回および第6回十字軍とフリードリヒ2世

1215年の第4回ラテラノ公会議は、エジプトに対する新たな、より組織化された十字軍の派遣を要請した。1217年後半、ハンガリー王アンドラーシュ2世とオーストリア公レオポルド6世はアッコに到着し、ブリエンヌのヨハンと共にタボル山を含む内陸部への侵攻を試みたが、成果はなかった。[ 79 ]ハンガリー軍の撤退後、残っていた十字軍は1217年の冬から1218年の春にかけて、カイサリアとテンプル騎士団の要塞であるシャトー・ペルランの要塞強化に着手した。 [ 80 ]
1218年の春、ドイツの十字軍艦隊がアッコに上陸し、第五回十字軍が本格的に始まった。十字軍のリーダーに選ばれたジョン王と共に艦隊はエジプトへ航海し、 5月にナイル川河口のダミエッタを包囲した。包囲はゆっくりと進み、エジプトのスルタン、アル・アーディルは1218年8月に亡くなった。十字軍がダミエッタの塔の一つを占領したことを受けてのショックによるものと考えられている。彼の後を息子のアル・カーミルが継いだ。1218年の秋には、教皇特使のアルバーノのペラギウスを含む援軍がヨーロッパから到着した。冬には十字軍は洪水と疫病に見舞われ、包囲は1219年中続いたが、アッシジのフランチェスコが休戦交渉のために到着した。アイユーブ朝が30年間の休戦とエルサレムおよび旧王国の残りの大部分の回復を提案したにもかかわらず、どちらの側も条件に同意できなかった。十字軍は最終的にこの都市を飢えさせ、11月に占領した。アル・カーミルは近くのアル・マンスーラ要塞に撤退したが、十字軍は1219年から1220年を通してダミエッタに留まり、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の到着を待った。一方ヨハネ王は、ヨハネ不在中にダマスカスから王国を襲撃していたアル・ムアザムから王国を守るため、短期間アッコに戻った。皇帝の差し迫った到着を依然として予想していた十字軍は、1221年7月にカイロに向けて出発したが、アル・カーミルがナイル川沿いのダムを破壊して氾濫させたため、ナイル川の水位上昇で進軍は阻まれた。フリードリヒ皇帝は実際にはヨーロッパを一度も離れたことがなかった。[ 81 ]
十字軍の失敗後、ヨハネはヨーロッパ各地を巡って支援を求めたが、支援を得られたのはフリードリヒ大王のみだった。フリードリヒ大王は1225年、ヨハネとマリアの娘イザベラ2世と結婚した。翌年、イザベラは息子コンラート4世を出産中に崩御した。コンラート4世は母の跡を継ぎ、東方では姿を現さなかった。フリードリヒ大王は第5回十字軍を指揮するという約束を破っていたが、コンラートを通して自らの王位継承権を固めようと躍起になっていた。また、アル=カーミルとダマスカスのアル=ムアッザムを攻撃する計画もあり、この同盟はイタリアに駐在するエジプト大使と協議されていた。しかし、聖地への出発が何度も遅れ、艦隊に疫病が蔓延したため、 1227年に教皇グレゴリウス9世によって破門された。フリードリヒ1世ではなく、その代理人であるリチャード・フィランジェリ、リンブルク公ハインリヒ4世、ドイツ騎士団長ヘルマン・フォン・ザルツァに率いられた十字軍は、1227年後半に東方に到着し、皇帝を待つ間にシドンの要塞化に着手して海の城塞と、後にドイツ騎士団の本部となるモンフォールを建設した。ダマスカスのアイユーブ朝は、アル・ムアザムが直前に急死したため、攻撃を敢えてしなかった。フリードリヒ1世は、1228年9月にようやく第6回十字軍に参加して到着し、幼い息子の名において王国の摂政を主張した。[ 82 ]
フリードリヒ大王は直ちにウトルメールの土着貴族たちと衝突した。彼らの中には、フリードリヒ大王がキプロスとエルサレムの両方に皇帝の権威を押し付けようとする試みに憤慨する者もいた。キプロス貴族たちは、まだ幼かったキプロス王ヘンリー1世の摂政をめぐって既に争っていた。キプロスの高等法院はジャン・ド・イブランを摂政に選出したが、ヘンリー1世の母アリス・ド・シャンパーニュは自身の支持者を任命したいと考えた。アリスとその一派、リュジニャン朝の支持者たちは、1197年にエメリー・ド・リュジニャンを国王に即位させていたフリードリヒ大王に味方した。リマソールでフリードリヒ大王は、ジャンに対し、キプロスの摂政権だけでなく、本土にあるジャン自身のベイルート領主としての地位も放棄するよう要求した。ジャンは、フリードリヒ大王にはそのような要求をする法的権限はないと主張し、どちらの称号も放棄しなかった。フリードリヒはその後、ジョンの十字軍への支持を保証するためにジョンの息子たちを人質として投獄した。[ 83 ]
ジョンはフリードリヒ2世に同行して本土へ向かったが、フリードリヒ2世はそこで歓迎されなかった。数少ない支持者の一人がシドンの領主バリアンであり、彼は前年に十字軍を歓迎し、このときアイユーブ朝の大使を務めていた。アル・ムアザムの死により、アル・カーミルとの同盟案は否決された。アル・カーミルは兄のアル・アシュラフと共に、甥であるアル・ムアザムの息子、アン・ナーシル・ダーウードからダマスカス(およびエルサレム)を奪取していた。しかし、アル・カーミルはフリードリヒ2世の軍隊の規模が小さいことや、彼の破門によって軍隊内に分裂が生じていることを知らなかったようで、新たな十字軍から自国の領土を防衛することを避けたかった。フリードリヒ1世の存在だけで、エルサレム、ベツレヘム、ナザレ、そして周辺の多くの城を戦闘なしに奪還することができ、これらは1229年2月にアイユーブ朝との10年間の休戦とエルサレムのイスラム教徒住民の礼拝の自由と引き換えに回復された。しかし、この条約の条項はエルサレム総主教ジェラルド・フォン・ローザンヌには受け入れられず、彼はエルサレムを禁教令下に置いた。3月、フリードリヒ1世は聖墳墓教会で戴冠式を行ったが、破門と禁教令のため、エルサレムは王国に真に復帰することはなく、アッコからの統治が続いた。[ 84 ]
一方、イタリアでは、教皇はフリードリヒ大王の破門を口実にイタリア領土に侵攻した。教皇軍はフリードリヒ大王の義父であるブリエンヌのジャンが率いていた。フリードリヒ大王は1229年に帰国を余儀なくされ、聖地はアッコの住民によって「勝利ではなく、内臓の雨を浴びせられた」状態となった。[ 85 ]
ロンゴバルド戦争と男爵十字軍

しかし、フリードリヒ2世は1231年にリチャード・フィランジェリ率いる帝国軍を派遣し、ベイルートとティルスを占領したが、アッコを制圧することはできなかった。ヨハンの支持者たちはアッコにコミューンを形成し、ヨハン自身は1232年に市長に選出された。ジェノバ商人の支援を受けて、コミューンはベイルートを奪還した。ヨハンはティルスにも攻撃を仕掛けたが、 1232年5月のカサル・インベルトの戦いでフィランジェリに敗れた。[ 83 ]
キプロスでは、1232年にアンリ1世が成人し、ジョンの摂政は不要になった。ジョンとフィランジェリは共に自らの権威を主張するためキプロスへ急ぎ戻り、帝国軍は6月15日のアグリディの戦いで敗れた。アンリは誰もが認めるキプロス王となったが、リュジニャン家と帝国軍よりもイブラン家を支持し続けた。本土では、フィランジェリはアンティオキアのボエモン4世、ドイツ騎士団、聖ヨハネ騎士団、ピサの商人らの支援を受けていた。ジョンはキプロスの貴族や、ベイルート、カイサリア、アルスフといった大陸の領地、テンプル騎士団、ジェノバ人らの支援を受けていた。どちらの側も進展させることができず、1234年にグレゴリウス9世はジョンとその支持者を破門した。この条約は1235年に部分的に撤回されたが、それでも和平は成立しなかった。ヨハンは1236年に死去し、戦争は息子のベイルートのバリアンと甥のモンフォールのフィリップによって引き継がれた。[ 86 ]
一方、アイユーブ朝との条約は1239年に失効することになっていた。フリードリヒ1世率いる新たな十字軍の計画は頓挫し、フリードリヒ1世自身も1239年にグレゴリウス9世から再び破門された。しかし、シャンパーニュ伯兼ナバラ王テオバルド4世、ドルー伯ピーター、 1239年9月にアッコに到着したアモーリー・ド・モンフォールなど他のヨーロッパの貴族たちがこの運動に加わった。アッコで開かれた会議でテオバルドは十字軍のリーダーに選出された。この会議にはワルテル・ド・ブリエンヌ、ジョン・オブ・アルスフ、バリアン・オブ・シドンなど王国の有力貴族のほとんどが出席した。十字軍の到着はロンバルディア戦争からの束の間の休息であり、フィランジェリはティルスに留まり参加しなかった。評議会は南のアスカロンを再強化し、北のダマスカスを攻撃することを決定した。
十字軍はアイユーブ朝内の新たな分裂を認識していた可能性がある。アル=カーミルは1238年にダマスカスを占領したが、その後まもなく死去し、その領土は一族に継承された。息子のアル=アーディル・アブ・バクルとアッサリーフ・アイユーブがエジプトとダマスカスを継承した。アイユーブはアル=アーディルを追い出そうとカイロへ進軍したが、彼の不在中にアル=カーミルの弟アッサリーフ・イスマイルがダマスカスを占領し、アイユーブはナーシル・ダーウードに捕虜にされた。一方、十字軍はアスカロンへ進軍した。その道中、ブリエンヌのウォルターはダマスカスへの補給物資として家畜を捕獲した。アイユーブ朝は十字軍のダマスカス攻撃計画を知っていたとみられる。しかし、この勝利は長くは続かず、1239年11月、十字軍はガザでエジプト軍に敗れました。バール伯アンリ2世は殺害され、モンフォール伯アモーリーは捕らえられました。十字軍はアッコに戻りましたが、これはおそらく、王国の現地貴族たちがティルスのフィランジェリに疑念を抱いていたためでしょう。ダウードはアイユーブ朝の勝利に乗じて、10年間の休戦が満了していた12月にエルサレムを奪還しました。
アイユーブはダーウードの捕虜であったが、二人はエジプトのアル・アーディルに対抗するために同盟を組み、1240年にアイユーブがこれを占領した。ダマスカスでは、イスマーイール1世はダーウードとアイユーブが自らの領土を脅かすことを認識し、十字軍に支援を求めた。テオバルドはイスマーイール1世と条約を締結し、領土譲歩と引き換えにエルサレムと旧王国の残りの大部分をキリスト教徒の支配下に回復させた。これはフリードリヒ2世が1229年に回復した領土よりもさらに広かった。しかし、テオバルドはロンバルド戦争で挫折し、1240年9月に帰国した。テオバルドの出発直後に、コーンウォールのリチャードが到着した。彼はアスカロンの再建を完成させ、エジプトのアイユーブとも和平を結んだ。1241年、アイユーブはイスマーイール1世の譲歩を確認し、ガザで捕らえた捕虜は両者で交換された。リチャードは1241年にヨーロッパに戻った。[ 87 ]
王国は実質的に復興したものの、ロンバルディア戦争は依然として王国の貴族たちを悩ませていた。テンプル騎士団とホスピタル騎士団は互いに敵対する側を支持していたため、互いに攻撃し合い、テンプル騎士団は1241年にアイユーブ朝との条約を破棄してナブルスを攻撃した。コンラッドは1242年に成人したと宣言し、フリードリヒ1世の摂政権と、彼に代わって統治を行う皇帝の後見人の必要性がなくなった。ただし、コンラッドはまだエルサレムの慣習では成人年齢である15歳に達していなかった。フリードリヒ1世はコンラッドを通して皇帝の摂政を派遣しようとしたが、アッコの反帝派はエルサレムの法律では独自の摂政を任命できると主張した。6月、オート・クールは摂政をイサベル1世の娘でコンラッドの大叔母であり、王国に住む最も近い親戚であるアリス・ド・シャンパーニュに与えた。アリスはフィランジェリの逮捕を命じ、イブラン家とヴェネツィア家と共にティルスを包囲し、1243年7月に陥落させた。ロンバルディア戦争は終結したが、コンラッドが東方に到着しなかったため、国王は依然として不在であった。アリスはティルスを掌握したモンフォール公フィリップとアッコを保持し続けたベイルート公バリアンによって、摂政としての実権を行使することができなかった。[ 86 ]
ルイ9世の十字軍
アイユーブ朝は依然としてエジプトのアイユーブ、ダマスカスのイスマーイール、ケラクのダーウードに分裂していた。イスマーイール、ダーウード、そしてホムスのマンスール・イブラーヒームはアイユーブと戦争を起こし、アイユーブはホラズム人を雇って自分のために戦わせた。ホラズム人は中央アジア出身の遊牧民トルコ人で、東方でモンゴル軍に追われてメソポタミアに居住していた。アイユーブの支援を受けて、彼らは1244年の夏にエルサレムを略奪し、エルサレムを廃墟と化し、キリスト教徒とイスラム教徒の双方にとって無用の都市とした。 10月、ホラズム軍はバイバルス率いるエジプト軍と共に、モンフォール公フィリップ、ブリエンヌ公ワルテル、テンプル騎士団、ホスピタル騎士団、ドイツ騎士団の長、そしてアル=マンスールとダーウード率いるフランク軍と対峙した。10月17日、エジプト・ホラズム軍はフランク・シリア連合軍を壊滅させ、ブリエンヌ公ワルテルは捕虜となり、後に処刑された。1247年までにアイユーブは1239年に割譲した領土の大部分を奪還し、ダマスカスも制圧した。[ 88 ]
1245年のリヨン公会議で、教皇インノケンティウス4世は新たな十字軍について議論した。公会議でフリードリヒ2世が廃位されたため、帝国からの援助は期待できなかったが、フランス国王ルイ9世は既に十字軍遠征に出ることを誓っていた。ルイは1248年にキプロスに到着し、自身の弟であるロベール・ド・アルトワ、シャルル・ド・アンジュー、アルフォンス・ド・ポワティエを含む部下と、イブラン家のジャン・ド・ヤッファ、ギー・ド・イブラン、バリアン・ド・ベイルートが率いるキプロスとエルサレムの部下から軍隊を集めた。再び目標はエジプトであった。1249年6月に十字軍が上陸したとき、ダミエッタは抵抗を受けることなく占領されたが、十字軍は11月までそこで停止した。その頃にはエジプトのスルタン、アイユーブが亡くなり、息子のトゥランシャーが後を継いでいた。 2月、十字軍はマンスーラの戦いで敗北し、アルトワ公ロベールが戦死した。十字軍はナイル川を渡ることができず、病気と物資不足に苦しみ、4月にダミエッタへ撤退した。その途中、ファリスクルの戦いで敗北し、ルイ14世はトゥランシャーの捕虜となった。ルイ14世が捕虜になっている間に、トゥランシャーは将軍アイバク率いるマムルーク軍によって打倒された。アイバクは5月、ダミエッタと多額の身代金と引き換えにルイ14世を解放した。その後4年間、ルイ14世はアッコに居住し、カイサリア、ヤッファ、シドンと共にアッコの要塞化に貢献した。彼はまた、シリアのアイユーブ朝と休戦協定を結び、イスラム世界を脅かし始めていたモンゴル人との交渉のために使節を派遣した後、1254年に帰国した。彼はアッコにジョフロワ・ド・セルジヌの指揮下にある大規模なフランス軍守備隊を残した。[ 89 ]
こうした出来事のさなか、1246年にアリス・ド・シャンパーニュが亡くなり、息子のキプロス王アンリ1世が摂政に代わった。ヤッファのジャンはアンリ1世のためにアッコのバイリを務めていた。ルイ9世がアッコに滞在中、1253年にアンリ1世が亡くなり、幼い息子のユーグ2世がキプロスでは跡を継いだ。ユーグは、コンラッドとその息子コンラッドが1254年に亡くなった後のコンラッドのバイリとして、技術的にはエルサレムの摂政でもあった。キプロスとエルサレムはどちらもユーグの母であるアンティオキアのプレザンスによって統治されていたが、アッコではジャンがユーグのバイリとして留まった。ジャンはダマスカスと和平を結び、アスカロンの奪還を試みた。マムルーク朝が支配するようになったエジプトは、これに応じて1256年にヤッファを包囲した。ジョンは彼らを打ち破り、その後、領地を従兄弟のアルスフのジョンに譲った。[ 90 ]
聖サバス戦争
1256年、ヴェネツィア商人植民地とジェノバ商人植民地の間の商業上の対立が勃発し、開戦となった。アッコでは、両植民地が聖サバス修道院の領有権を争った。ピサ商人の支援を受けたジェノバ人がヴェネツィア人居住区を攻撃し、彼らの船を焼き払ったが、ヴェネツィア人は彼らを追い出した。その後、ヴェネツィア人はモンフォール公フィリップによってティルスから追放された。アルスフのヨハネス、ヤッファのヨハネス、ベイルートのヨハネス2世、テンプル騎士団、ドイツ騎士団はヴェネツィア人を支援し、ヴェネツィア人はピサ人も説得して自分たちに加わらせたが、ホスピタル騎士団はジェノバ人を支援した。1257年、ヴェネツィア人は修道院を征服し、要塞を破壊したが、ジェノバ人を完全に追い出すことはできなかった。彼らはジェノヴァ人居住区を封鎖したが、ジェノヴァ人は近くに施設があったホスピタル騎士団と、ティルスから食料を送ってくれたモンフォールのフィリップから食料を補給されていた。1257年8月、アルスフのジャンはジェノヴァのイタリアの同盟国であるアンコーナ共和国にアッコの商業権を与えることで戦争を終わらせようとしたが、モンフォールのフィリップとホスピタル騎士団を除いて、残りの貴族たちはヴェネツィアを支持し続けた。1258年6月、ジェノヴァ艦隊が海から街を攻撃しているときに、フィリップとホスピタル騎士団はアッコに行進した。海戦はヴェネツィアが勝利し、ジェノヴァ人は居住区を放棄してフィリップと共にティルスに逃げることを余儀なくされた。戦争はトリポリとアンティオキアにも広がり、そこではジェノヴァ十字軍の子孫であるエンブリアコ家がヴェネツィアを支持するアンティオキアのボエモン6世と対立した。 1261年、総主教ジャック・パンタレオンが王国の秩序を回復するための会議を組織したが、ジェノバ人はアッコに戻らなかった。[ 91 ]
モンゴル人
モンゴル人が近東に到達したのはこの時期であった。東方ではモンゴル人の存在により既にホラズム人は駆逐されており、ルイ9世をはじめ様々な教皇がホラズム人と同盟を結んだり交渉したりするために使者を派遣していたが、ホラズム人は同盟には関心がなかった。1258年にバグダード、1260年にはアレッポとダマスカスを略奪し、アッバース朝とアイユーブ朝の最後の痕跡を破壊した。アルメニアのヘトゥム1世とアンティオキアのボエモン6世は既にモンゴル人に臣従していた。バグダードとダマスカス包囲戦の将軍の一人であるキトブカなどモンゴル人の中にはネストリウス派キリスト教徒もいたが、それにもかかわらずアッコの貴族たちは服従を拒否した。この王国は当時すでに比較的重要性の低い国であったため、モンゴル軍はこれにほとんど注意を払わなかったが、1260年にはいくつかの小競り合いがあった。シドンのユリアヌスの軍勢はキトブカの甥を殺害し、キトブカはシドンを略奪して応じ、ベイルートのヨハネス2世も別の襲撃でモンゴル軍に捕らえられた。モンゴルによる征服は避けられないと思われたが、シリアのモンゴル軍司令官フレグが兄モンケ・ハーンの死後帰国し、キトブカに少数の守備隊を残したことで頓挫した。その後、エジプトのマムルーク朝はフランク領土への進軍許可を求め、許可を得て、1260年9月のアイン・ジャールートの戦いでモンゴル軍を破った。キトブカは殺害され、シリア全土はマムルーク朝の支配下に入った。エジプトへの帰還途中、マムルーク朝のスルタン、クトゥズはバイバルス将軍に暗殺された。バイバルスは前任者よりもフランク人との同盟に非常に否定的だった。[ 92 ]
エーカーの陥落
ジャン・ド・アルスフは1258年に死去し、アッコにおけるルイ9世の副官ジョフロワ・ド・セルジーヌがバイリの地位に就いた。プレザンスは1261年に死去したが、その息子ユーグ2世が未成年であったため、キプロスは従弟のユーグ・ド・アンティオキア=リュジニャンに渡り、その母イザベラ・ド・キプロスは、ユーグ1世とキプロスの娘でユーグ2世の叔母にあたる。イザベラは夫のアンティオキアのアンリ(プレザンスの叔父でもある)をバイリに任命したが、1264年に死去。その後、アッコの摂政はユーグ・ド・アンティオキア=リュジニャンと従弟のユーグ・ド・ブリエンヌが主張し、ユーグ2世は成人前の1267年に死去した。ユーグ・ド・アンティオキア=リュジニャンが紛争に勝利し、ユーグ2世の跡を継いでユーグ3世としてキプロス王国を継承した。1268年にシチリアでコンラディンが処刑されたとき、ホーエンシュタウフェン家の後継者は他におらず、ユーグ3世は1269年にエルサレム王国も継承した。これはリュジニャン家の別分家によって争われた。アンティオキアのマリアがイサベル1世に最も近い存命の子孫として王位を主張したが、当面彼女の主張は無視された。この頃には、バイバルス率いるマムルーク朝が王国の絶え間ない紛争に乗じて、海岸沿いに残っていた十字軍都市を征服し始めた。1265年、バイバルスはカイサリア、ハイファ、アルスフを、1266年にはサファドとトロンを占領した。1268年にはヤッファとボーフォールを占領し、続いてアンティオキアを包囲して破壊した。[ 93 ]

これらの征服の後、ユーグ3世とバイバルスは1年間の休戦を結んだ。バイバルスはルイ9世がヨーロッパから再び十字軍を派遣する計画を立てていることを知っており、今回も目標はエジプトであると想定していた。しかし、十字軍はチュニスへと方向転換し、ルイはそこで死去した。バイバルスは自由に遠征を続けることができた。1270年にはアサシン教団にモンフォール公フィリップを殺害させ、1271年にはホスピタル騎士団とドイツ騎士団の拠点であるクラック・デ・シュヴァリエとモンフォール城を占領した。またトリポリも包囲したが、ルイ9世の十字軍のうち東方に到着したのは唯一の部隊であるイングランド王エドワード王子の到着に伴い、 5月に放棄した。エドワード王子はバイバルスと10年間の休戦を結ぶことしかできなかったが、それでもバイバルスはエドワードをも暗殺しようとした。エドワードは1272年に去り、 1274年の第2回リヨン公会議で新たな十字軍の計画があったにもかかわらず、その後の大規模な遠征隊は到着しなかった。ユーグ3世は人気のない王となり、本土における権威は崩れ始め、アッコとティルスの外に残された唯一の領土であるベイルートは独自に行動し始めた。その相続人であるイザベル・ド・イベリン(ユーグ2世の未亡人)は、実際にベイルートをバイバルスの保護下に置いた。本土が統治不可能であると悟ったユーグ3世は、アルスフのバリアンをバイリに残し、キプロスへ去った。その後、1277年にアンティオキアのマリアは王国に対する請求権をアンジューのシャルルに売却し、シャルルはサン・セヴェリーノのロジャーを代理人として派遣した。ヴェネツィア人とテンプル騎士団がこの請求を支持し、バリアンは抵抗する力がなかった。バイバルスは1277年に死去し、カラーウーンが後を継いだ。 1281年に10年間の休戦が期限切れとなり、ルッジェーロによって更新された。ルッジェーロは1282年のシチリアの晩祷の後ヨーロッパに戻り、オド・ポワレシャンに交代した。ユーグ3世は1283年にベイルートに上陸して本土での権威を回復しようとしたが、これは効果がなく、1284年にティルスで亡くなった。彼の後を息子のジャン2世が短期間継いだが、ジャン2世は1285年に間もなく亡くなり、その兄弟でユーグ3世のもう一人の息子であるヘンリー2世が跡を継いだ。その年、カラウーンはマルカブのホスピタル騎士団の要塞を占領した。アンジューのシャルルも1285年に亡くなり、軍の命令とアッコのコミューンはヘンリー2世を国王として受け入れた。オド・ポワレシャンは彼を認めなかったが、ヘンリーに直接ではなくテンプル騎士団にアッコを引き渡すことを許可され、テンプル騎士団はそれを国王に引き渡した。 1287年にヴェネツィア人とジェノバ人の間で再び戦争が勃発し、トリポリは陥落した。1289年にアンリ2世はカラーウーンに攻め込んだ。アッコも陥落するのは時間の問題であったが、十字軍王国の終焉は実際には1290年に新たに到着した十字軍によって扇動され、彼らはアッコで暴動を起こし、市内のイスラム教徒商人を攻撃した。カラーウーン自身は報復する前に亡くなったが、その息子のアシュラフ・カリルが1291年4月にアッコを包囲するために到着した。アッコはヘンリー2世の弟ティルスのアマルリック、ホスピタル騎士団、テンプル騎士団、ドイツ騎士団、ヴェネツィア人とピサ人、ジャン1世・ド・グライリー率いるフランス守備隊、オットン・ド・グランソン率いるイングランド守備隊によって守られていたが、数の上で圧倒的に劣勢だった。アンリ2世自身は包囲中の5月に到着したが、都市は5月18日に陥落した。アンリ、アマルリック、オットン、ジャンは、若いテンプル騎士ロジェ・ド・フロールと共に脱出したが、テンプル騎士団長ギヨーム・ド・ボージュを含む他の防衛隊員のほとんどは逃亡した。翌日ティルスは戦闘なく陥落し、シドンは6月に、ベイルートは7月に陥落した。[ 94 ]
十字軍はトルトサなどの北の都市に本部を移しましたが、そこも失い、キプロス沖合の司令部を移転せざるを得なくなりました。その後10年間、何度か海軍による襲撃や領土奪還の試みが行われましたが、 1302年から1303年にかけてアルワド島を失ったことで、エルサレム王国は本土から消滅しました。
初期の王国での生活
王国におけるラテン系住民の人口は常に少なかった。入植者や新たな十字軍兵士が絶えず到着していたものの、第1回十字軍に参加した初期の十字軍兵士のほとんどは帰国した。ティルスのウィリアムによると、1100年、ゴドフリーによるアルスフ包囲戦の際、王国には「わずか300人の騎士と2000人の歩兵しかいなかった」という。[ 95 ]当初から、ラテン系住民は、先住のユダヤ人、サマリア人、イスラム教徒、ギリシャ正教徒、シリア人を支配する植民地の辺境に過ぎなかった。
王国で新しい世代が成長するにつれ、彼らは自らを原住民と考えるようになりました。西ヨーロッパ人、あるいはフランク人という核となるアイデンティティを決して手放すことはありませんでしたが、彼らの衣服、食生活、そして商業主義は、東洋、特にビザンチンの影響を強く受けていました。年代記作者のシャルトルのフルチャーは1124年頃にこう記しています。
かつて西洋人であった我々は、今や東洋人となった。ローマ人やフランク人であった者は、この地でガリラヤ人、あるいはパレスチナの住民となった。ランスやシャルトル出身であった者は、今やティルスやアンティオキアの市民となった。我々は既に出生地を忘れ、多くの人々にとって未知のものとなり、少なくとも、語られることもなくなった。[ 96 ]
十字軍とその子孫はギリシャ語、アラビア語、その他の東洋の言語を学ぶことが多く、現地のキリスト教徒(ギリシャ語、シリア語、アルメニア語)と結婚したり、時には改宗したイスラム教徒と結婚したりした。[ 97 ]それにもかかわらず、フランク王国はイスラム教の中心地にある独特の西洋植民地であり続けた。
第1回十字軍に参加し、ボードゥアン1世の従軍牧師でもあったフルチャーは、1127年まで年代記を書き続けた。フルチャーの年代記は非常に人気があり、オルデリック・ヴィタリスやウィリアム・オブ・マームズベリーといった西洋の他の歴史家たちも史料として用いた。エルサレムが占領されるとほぼ同時に、そして12世紀を通して、多くの巡礼者が到着し、新王国に関する記録を残した。その中には、イギリスのザウルフ、キエフの修道院長ダニエル、フランクのフレテッルス、ビザンチンのヨハネス・フォカス、そしてドイツのヴュルツブルクのイオアンとテオドリヒなどがいる。[ 98 ]これらのほか、その後はティルスの大司教でエルサレムの法務官であったティルスのウィリアムまでエルサレムの出来事の目撃証言はない。ウィリアムは1167年頃に執筆を開始し、1184年頃に亡くなったが、第1回十字軍とフルチャーの死から自身の時代までの多くの情報を、主にエクスのアルベールとフルチャー自身の著作から引用して収録している。
イスラム教徒の観点から見ると、主要な情報源はウサマ・イブン・ムンキズである。彼は軍人で、ダマスカスからエルサレムやエジプトへ頻繁に大使として赴任した。彼の回想録『キタブ・アル・イティバル』には、東方における十字軍社会の生き生きとした記述が含まれている。さらに詳しい情報は、トゥデラのベンヤミンやイブン・ジュバイルといった旅行者からも得られる。
十字軍社会


当初、王国は忠実な臣民をほとんど失い、国の法と秩序を執行する騎士もほとんどいませんでした。イタリアの貿易商の到来、軍事騎士団の設立、そしてヨーロッパからの騎士、職人、農民の移民によって、王国の情勢は改善し、十字軍がヨーロッパで知っていた社会に似てはいるものの、それとは異なる封建社会が形成されました。この社会の性質は、十字軍の歴史家の間で長らく議論の的となってきました。
19世紀から20世紀初頭にかけて、E.G.レイ、ガストン・ドデュ、ルネ・グルーセといったフランスの学者たちは、十字軍兵士、イスラム教徒、キリスト教徒は完全に統合された社会に住んでいたと推測した。ロニー・エレンブラムは、この見方はフランス帝国主義と植民地主義に影響されたと主張している。中世フランスの十字軍兵士が現地社会に溶け込むことができたのであれば、レヴァント地方の近代フランス植民地が繁栄できたのは間違いない、と。[ 99 ] 20世紀半ばには、ジョシュア・プラワー、RCスマイル、メロン・ベンヴェニスティ、クロード・カーンといった学者たちが、十字軍兵士は現地住民から完全に隔離された生活を送っており、現地住民は徹底的にアラブ化および/またはイスラム化されており、外国の十字軍兵士にとって常に脅威であった、と主張した。プラワーはさらに、この王国は植民地化の初期の試みであり、十字軍は少数の支配階級であり、生存のために現地住民に依存していたものの、現地住民と統合しようとはしなかったと主張した。[ 100 ]このため、十字軍が慣れ親しんでいたヨーロッパの農村社会は、レバント地方に既に存在していた都市の、より安全な都市社会に取って代わられた。[ 101 ]
エレンブラムの解釈によれば、王国の住民(ギリシャ系およびシリア系キリスト教徒と共存するラテン系キリスト教徒、シーア派およびスンニ派のアラブ人、スーフィー派、ベドウィン、ドゥルーズ派、ユダヤ教徒、サマリア人)は、十字軍兵士との間だけでなく、互いにも大きな違いがあった。東方キリスト教徒とラテン系十字軍兵士の関係は「複雑で曖昧」であり、単純に友好的か敵対的かという単純な関係ではなかった。エレンブラムは、東方キリスト教徒はイスラム教徒のアラブ人よりも、同胞のキリスト教徒十字軍兵士との結びつきが強かった可能性が高いと主張している。[ 102 ]十字軍兵士は現地住民と完全に融合していたわけでも、都市部で農村部の現地住民から隔離されていたわけでもなく、むしろ都市部と農村部の両方に定住し、具体的には、伝統的に東方キリスト教徒が居住していた地域に定住した。伝統的にイスラム教徒が居住していた地域には、十字軍兵士の居住地はほとんどなく、同様に、現地のキリスト教徒の住民もほとんどいなかった。[ 103 ]
十字軍は、この混交社会に既存の制度を適応させ、ヨーロッパから馴染みのある慣習を導入した。ヨーロッパと同様に、貴族は家臣を持ち、彼ら自身も王の家臣であった。農業生産はイクタ(イスラムの土地所有と支払いの制度)によって規制されていた。これはヨーロッパの封建制度とほぼ(しかし完全には一致しない)同等であり、この制度は十字軍によって大きく混乱することはなかった。[ 104 ]
ハンス・マイヤーが述べているように、「ラテン王国のイスラム教徒の住民はラテン年代記にほとんど登場しない」ため、彼らの社会における役割に関する情報を見つけることは困難です。十字軍は「これらの事柄を単に興味のない、ましてや記録に値しないものとして無視する自然な傾向を持っていました」[ 105 ] 。イスラム教徒は、ユダヤ教徒や東方キリスト教徒と同様に、田舎では実質的に何の権利も持たず、土地を所有する十字軍領主の所有物でした。[ b ]他宗教に対する寛容さは、一般的に中東の他の地域と比べて高くも低くもありませんでした。ギリシャ人、シリア人、ユダヤ人は、かつてのイスラム教徒の領主が十字軍に取って代わられただけで、以前と同じように生活を続け、それぞれの法律と裁判所に従っていました。イスラム教徒は今や社会の最下層に彼らと共に身を置いていました。イスラム教徒やシリア人のコミュニティの指導者であるライは、土地を所有する貴族の一種の家臣であったが、十字軍の貴族は不在地主であったため、ライとそのコミュニティは高度な自治権を持っていた。[ 107 ]
フランク人に敵対していたアラブ・アンダルシアの地理学者で旅行家のイブン・ジュバイルは、12世紀後半にキリスト教十字軍のエルサレム王国の支配下で暮らしていたイスラム教徒について次のように記述している。
私たちはティブニンを出発し、フランク人の支配下で裕福な暮らしを送っているムスリムたちが暮らす農場を通り過ぎました。アッラーが私たちをこのような誘惑から守ってくださいますように! 彼らに課せられた規則は、収穫時に穀物の収穫量の半分を納めること、1ディナールと7キラートの人頭税を支払うこと、そして果樹に軽い税金を課すことです。ムスリムたちは自らの家を所有し、独自の方法で統治しています。これがフランク人の領土における農場や大きな村落の組織化の仕組みです。多くのムスリムは、ムスリムの支配下にある地域で同胞が暮らす生活環境が決して快適とは言えないのを見て、ここに定住したいという強い誘惑に駆られます。ムスリムにとって残念なことに、彼らは同胞が支配する土地における指導者たちの不正には常に不満を抱く理由がある一方で、常に信頼できるフランク人の行動には賞賛の念を抱くしかありません。[ 108 ]
都市ではイスラム教徒と東方キリスト教徒は自由であったが、エルサレム自体にはイスラム教徒の居住は認められていなかった。彼らは二級市民であり、政治や法律に関与せず、国王への兵役義務もなかった。ただし、一部の都市では人口の大多数を占めていた可能性もある。同様に、イタリアの都市国家の市民は港湾都市の自治区に居住していたため、何の義務も負っていなかった。[ 109 ]
21 世紀においても、文化統合や文化アパルトヘイトの問題に関する立場は依然として分かれている。フランク人と現地のイスラム教徒やキリスト教徒との交流は、混乱していたものの、実質的には共存していたことがわかる。ウサマ・イブン・ムンキズによるシャイザールのアンティオキアとエルサレムへの旅の記録は、民族的偏見を超えた貴族的交流のレベルを描いているが、誇張されている可能性が高い。[ 110 ]イスラム教徒とキリスト教徒の接触は行政上または個人的レベル (税金や翻訳に基づく) で行われ、共同体レベルや文化的なものではなく、階層的な領主対被支配の関係を象徴するものであった。[ 111 ]異文化統合の証拠は依然として乏しいが、異文化協力や複雑な社会的交流の証拠はより一般的であることがわかっている。シリア語の行政官やアラビア語の首長との間で、文字通り翻訳者を意味する「dragoman」という言葉が頻繁に使用されていたことは、双方の利益について交渉を行う必要が直接あったことを示している。[ 112 ]アラビア語を話すキリスト教徒と少数のアラブ化したユダヤ人やイスラム教徒がいる家庭についての記述は、20世紀半ばの歴史家が描いたほど二分的な関係ではない。[ 113 ]むしろ、フランク人キリスト教徒が非フランク人の司祭、医師、その他の役割を家庭内や異文化コミュニティ内で担っているという共通点は、標準化された差別がなかったことを示している。[ 113 ]エルサレム出身のティルスのウィリアムは、ラテン語やフランク語の医師よりもユダヤ人やイスラム教徒の医師を雇う傾向について不満を述べた。証拠は、衛生に関するフランク人の文化的・社会的慣習(アラブ人の間では洗濯の習慣がなく、浴場文化を知らないことで悪名高かった)が変化したことを示唆しており、灌漑に加えて家庭用の水の供給を確保することさえ行われている。[ 114 ]
人口
王国の人口を正確に推定することは不可能である。ジョサイア・ラッセルは、十字軍の時代、シリア全土の人口は約230万人で、村はおそらく1万1000あったと計算している。もちろん、これらのほとんどは、4つの十字軍国家の中で最も広大な地域であっても、十字軍の支配下にはなかった。[ 115 ]ジョシュア・プラワーやメロン・ベンヴェニスティなどの学者は、最大で12万人のフランク人と10万人のイスラム教徒が都市に住み、他に25万人のイスラム教徒と東方キリスト教徒の農民が田舎に住んでいたと推定している。十字軍兵士は全人口の15~25%を占めていた。[ 116 ]ベンジャミン・Z・ケダールは、王国には30万人から36万人の非フランク人がおり、そのうち25万人は田舎の村人で、「エルサレム王国の一部、おそらくほとんどの地域ではイスラム教徒が多数派を占めていたと推測できる」としている。[ 116 ]ロニー・エレンブラムが指摘するように、人口を正確に数えるには現存する証拠が不十分であり、いかなる推定も本質的に信頼できない。[ 117 ]同時代の年代記作者であるティルスのウィリアムは1183年の国勢調査を記録している。これは、侵略から守るために利用可能な兵士の数を把握し、住民(イスラム教徒またはキリスト教徒)から徴収できる税額を決定することを目的としていた。人口が実際に数えられたとしても、ウィリアムはその数を記録していない。[ 118 ] 13世紀にジャン・ド・イベリンは領地とそれぞれの領地に割り当てられた騎士の数のリストを作成しましたが、これには非貴族や非ラテン系の人口に関する情報は含まれていませんでした。
バイバルス率いるマムルーク朝は、最終的に中東全域からフランク人を排除するという誓約を果たした。アンティオキア(1268年)、トリポリ(1289年)、アッコ(1291年)の陥落に伴い、都市から脱出できなかったキリスト教徒は虐殺または奴隷化され、レヴァント地方におけるキリスト教支配の最後の痕跡は消滅した。[ 119 ] [ 120 ]
奴隷制
王国には、数え切れないほど多くのイスラム教徒の奴隷が暮らしていた。アッコには12世紀から13世紀にかけて大規模な奴隷市場が存在した。イタリア商人は、イスラム教徒の奴隷とともに、東南ヨーロッパのキリスト教徒を奴隷として売ったとして非難されることもあった。 [ 121 ]奴隷制は身代金よりも一般的ではなく、特に戦争捕虜に関しては顕著だった。毎年の襲撃や戦闘で大量の捕虜が捕らえられたため、キリスト教国とイスラム教国の間で身代金が自由に流れていた。[ 122 ]捕虜や奴隷の逃亡はおそらく困難ではなかっただろう。なぜなら、地方の住民の大半はイスラム教徒であり、逃亡奴隷は常に問題となっていたからだ。解放の唯一の合法的な手段は、(カトリック)キリスト教への改宗であった。西方キリスト教徒であれ東方キリスト教徒であれ、いかなるキリスト教徒も奴隷として売られることは法律で禁じられていた。[ 123 ]
エルサレム巡回裁判所は、王国における奴隷制の法的枠組みを確立した。この文書は、「農奴、動物、またはその他の動産」が売買可能であると規定していた。「農奴」とは、農奴に近い農村の半自由労働者であった。動産奴隷になる方法は複数あった。生まれながらに奴隷となる場合もあれば、襲撃で捕らえられた場合、借金の罰として、あるいは逃亡奴隷を助けたことによる罰として奴隷となる場合もあった。[ 124 ]
遊牧民ベドウィン族は王の財産とみなされ、王の保護下にあった。彼らは他の財産と同様に売却または譲渡される可能性があり、12世紀後半には下級貴族や軍事組織のいずれかの保護下に置かれることが多かった。[ 125 ]
経済

この地域の都市構成とイタリア商人の存在が相まって、農業よりも商業色が強い経済が発展しました。パレスチナは常に貿易の交差点でしたが、今やこの貿易はヨーロッパにも広がりました。北欧の毛織物などのヨーロッパの品物は中東やアジアへ、アジアの品物はヨーロッパへ輸送されました。エルサレムは特に絹、綿、香辛料の貿易に深く関わっていました。十字軍のエルサレムとの貿易を通じてヨーロッパに初めてもたらされた品物には、オレンジや砂糖などがあり、年代記作者のティルスのウィリアムは砂糖を「人類の生活と健康に非常に必要」と評しています。農村部では、小麦、大麦、豆類、オリーブ、ブドウ、ナツメヤシが栽培されていました。イタリアの都市国家は、ヴァルムンディ協定などの通商条約のおかげでこの貿易から莫大な利益を上げ、それは後の世紀のルネサンスに影響を与えました。
パレスチナにおけるジェノヴァとヴェネツィアの植民地もまた、その租借地で農業事業に着手した。彼らは特にヨーロッパへの輸出用に砂糖を栽培した。サトウキビはアラブ人によってパレスチナに持ち込まれていた。砂糖畑で働くために、イタリア人入植者はアラブ人やシリア出身の奴隷や農奴、あるいは地元の農奴を利用した。砂糖製造はティルスで始まった。13世紀にはパレスチナでの砂糖生産が増加し続け、商人は1291年にアッコが征服されるまで、その港を通じて無税で砂糖を輸出することができた。エルサレム王国で開拓された砂糖搾取システムは、アメリカ大陸における砂糖プランテーションの先駆けと見なされている。[ 126 ]
エルサレムは貢物の支払いを通じて収入を得ていたが、最初はまだ占領されていなかった沿岸都市から、後には十字軍が直接征服できなかったダマスカスやエジプトなどの近隣諸国からも貢物を徴収した。ボードゥアン1世が支配をオルトレヨルダンにまで拡大した後は、エルサレムはシリアからエジプトやアラビアへ向かうイスラム教徒の隊商への課税から収入を得た。エルサレムの貨幣経済は、傭兵を雇うことで人員問題を部分的に解決できることを意味していたが、これは中世ヨーロッパでは珍しいことであった。傭兵には同じヨーロッパの十字軍兵士が選ばれたり、あるいは有名なトルコ兵を含むイスラム教徒の兵士が選ばれることが多かった。
教育

エルサレムは王国の教育の中心地であった。聖墳墓教会には学校があり、そこでラテン語の読み書きの基礎が教えられた。[ 127 ]商人階級は比較的裕福であったため、その子女も貴族の子女と共にそこで教育を受けることができた。ティルスのウィリアムは後のボードゥアン3世の同級生であった可能性が高い。高等教育はヨーロッパの大学で受けなければならなかった。[ 128 ]戦争が哲学や神学よりもはるかに重要だった十字軍時代のエルサレムの文化では、大学の発展は不可能だった。とはいえ、貴族やフランク人の一般市民は高い識字率で知られており、弁護士や書記官は豊富で、法律や歴史その他の学問の研究は王族や貴族の大好きな娯楽であった。[ 129 ]エルサレムには、古代および中世のラテン語作品だけでなく、アラビア文学も収蔵する膨大な図書館がありました。その多くは、1154年の難破後、ウサマ・イブン・ムンキズとその一行から略奪されたものと思われます。 [ 130 ]聖墳墓には王国の写字室があり、市には勅許状やその他の文書が作成された官庁がありました。中世ヨーロッパの標準言語であったラテン語に加え、十字軍時代のエルサレムの住民はフランス語とイタリア語といった方言でコミュニケーションをとっていました。フランク人入植者たちはギリシャ語、アルメニア語、さらにはアラビア語も使用していました。
芸術と建築

エルサレム自体における最大の建築的試みは、聖墳墓教会の西方ゴシック様式による拡張でした。この拡張により、敷地内の個々の聖堂はすべて一つの建物に統合され、1149年に完成しました。エルサレム以外では、城や要塞の建設が主要な焦点となりました。ウルトレジョルダンのケラクとモントリオール、ヤッファ近郊のイブランなど、十字軍の城の数多くの例が挙げられます。
十字軍の芸術は、西洋、ビザンチン、イスラム様式が融合したものでした。主要都市には浴場、屋内配管、その他の先進的な衛生設備が備えられていましたが、これらは世界中の他のほとんどの都市や町には見られませんでした。十字軍の芸術の最も代表的な例は、おそらく1135年から1143年の間に制作され、現在は大英図書館に所蔵されている彩飾写本「メリザンド詩篇」と、彫刻による「ナザレの柱頭」でしょう。絵画とモザイクは王国で人気の芸術でしたが、その多くは13世紀のマムルーク朝によって破壊され、再征服を生き延びたのは最も耐久性の高い要塞だけでした。
政府と法制度
第一次十字軍の直後、ゴドフロワの忠実な家臣たちに土地が分配され、王国内に数多くの封建領主が形成された。これはゴドフロワの後継者たちにも引き継がれた。領主の数と重要性は12世紀から13世紀を通して変化し、多くの都市が王領の一部となった。国王は多くの官吏に補佐された。国王と王宮は通常エルサレムにあったが、イスラム教徒の居住が禁じられていたため、首都は小さく、人口も少なかった。国王はアッコ、ナブルス、ティルスなど、たまたま居合わせた場所で宮廷を開いた。エルサレムでは、王家はテンプル騎士団設立以前は神殿の丘に住み、後にダビデの塔を囲む宮殿群に住んだ。アッコにはもう一つ宮殿群があった。
貴族たちは田舎の領地よりもエルサレムに住む傾向があったため、ヨーロッパにいた頃よりも国王に対する影響力が大きかった。貴族たちは司教たちとともにオート・クール(フランス語で「高等法院」の意)を構成し、新国王(または必要に応じて摂政)の選出の確認、税金の徴収、貨幣の鋳造、国王への資金配分、軍隊の招集を担当した。オート・クールは王国の貴族たちにとって唯一の司法機関であり、殺人、強姦、反逆といった刑事事件や、奴隷の取り戻し、領地の売買、役務の不履行といったより単純な封建的紛争を審理した。処罰には領地の没収や追放、極端な場合には死刑も含まれた。伝承によれば、王国の最初の法律はゴドフロワ・ド・ブイヨンの短い治世中に制定されたが、 1120年のナブルス公会議でボードゥアン2世によって制定された可能性が高い。ベンジャミン・Z・ケダールは、ナブルス公会議の法典は12世紀には施行されていたが、13世紀には使われなくなっていたと主張した。マルワン・ナーダールはこれに疑問を呈し、法典が常に王国全体に適用されていたわけではない可能性があると示唆している。[ 131 ]最も広範な法典集であるエルサレム巡回法典は13世紀半ばに書かれたが、その多くは12世紀に起源を持つとされている。[ 132 ]
非貴族および非ラテン系住民のための下級裁判所も存在した。ブルジョワ裁判所は、非貴族系ラテン系住民のために、暴行や窃盗といった軽犯罪を扱う司法機関であり、法的権利が限られていた非ラテン系住民間の紛争に関する規則も定めていた。沿岸都市には、市場における商事紛争を扱うクール・ド・ラ・フォン裁判所や海事裁判所といった特別裁判所が存在した。現地のイスラム教徒や東方キリスト教系の裁判所がどの程度機能していたかは不明であるが、ライ(シリア人)は地方レベルで何らかの法的権限を行使していたと考えられる。シリア裁判所は、現地のキリスト教徒(「シリア人」)間の非刑事事件を裁いた。刑事事件については、非ラテン系住民はブルジョワ裁判所(犯罪が重大であればオート・クール)で裁かれることになっていた。 [ 133 ]
イタリアのコミューンは、第1回十字軍後の軍事・海軍の支援により、王国成立初期からほぼ完全な自治権を付与されていた。この自治権には独自の司法権も含まれていたが、管轄権の範囲は時代によって異なっていた。[ 134 ]
国王は法的には同輩の中の第一位であったが、高等法院の長として認められていた。
遺産
1291年にレヴァント地方の全領土を失った後、名目上はエルサレムの奪還を提案する十字軍遠征が後年試みられたが、オスマン帝国の台頭とともに、 その性格はますます必死の防衛戦争へと変化し、その範囲はバルカン半島の外に出ることは稀となった(アレクサンドリア十字軍、スミュルニオテ十字軍)。 イングランド王ヘンリー4世は1393年から1394年にかけてエルサレムに巡礼し、後に十字軍を率いてエルサレムを奪還することを誓ったが、1413年に死去するまでそのような作戦は実行に移さなかった。[ 135 ]レヴァント地方は1517年 から1918年のオスマン帝国分割までオスマン帝国の支配下にあった。
1302年のルアド陥落により、エルサレム王国はレヴァント海岸の最後の拠点を失い、聖地に最も近い領有地はキプロスとなった。 エルサレム王ヘンリー2世は1324年に死去するまでエルサレム王の称号を保持し、その後継者であるキプロス王もこの称号を主張し続けた。「エルサレム王」の称号は、ナポリのアンジュー朝王たちによっても継続的に用いられた。アンジュー朝の創始者であるアンジュー伯シャルルは、1277年にアンティオキアのマリアから王位継承権を買収していた。その後、エルサレム王国へのこの領有権はナポリ王位への貢物として扱われ、ナポリ王位は直接相続ではなく遺言や征服によってしばしば継承された。ナポリは教皇領であったため、教皇はナポリ王位だけでなくエルサレム王位もしばしば承認した。これらの領有権の歴史は、ナポリ王国の歴史である。 1441年、ナポリ王国の支配権はアラゴン王アルフォンソ5世に奪われ、スペイン王がナポリ王国の称号を主張しました。スペイン継承戦争後は、ブルボン家とハプスブルク家の両家がナポリ王国の称号を主張しました。この称号は現在もスペイン王室によって事実上使用されており、現在はスペイン王フェリペ6世が保持しています。また、1958年までハプスブルク家の僭称者オットー・フォン・ハプスブルクが、 1946年までイタリア王もナポリ王国の称号を主張していました。
参照
注記
参考文献
引用
- ^タイアーマン 2019、267頁。
- ^フランク・マクリーン『リチャードとジョン:戦争中の王たち』第5章、118ページ。
- ^ウィリアム・ハリス「レバノン:600年から2011年の歴史」オックスフォード大学出版局、51ページ
- ^ Arteaga, Deborah L. (2012年11月2日). 『古フランス語の研究:最先端技術』 Springer Science & Business Media. p. 206. ISBN 9789400747685。
- ^ a b「ヴェネツィアとエルサレムのラテン王国の征服」『軍事史』 。 2026年2月4日閲覧。
- ^ a b "テラサンタのジェノベージ" .ライム(イタリア語で)。 2024 年 7 月 3 日。2026 年2 月 4 日に取得。
- ^ジョシュア・プラワー「十字軍国家の社会階級:『少数派』」、ケネス・M・セットン編『十字軍の歴史 第5巻:十字軍が近東に与えた影響』ノーマン・P・ザクール、ハリー・W・ハザード編(マディソン:ウィスコンシン大学出版、1985年)、65-70頁。
- ^ベンジャミン・Z・ケダー、「サマリア人の歴史:フランク王国時代」、アラン・デイヴィッド・クラウン編『サマリア人』 (テュービンゲン:JCBモア、1989年)、82-94頁。
- ^教皇ウルバヌス2世の演説からの引用、「教皇ウルバヌス2世の第1回十字軍を呼びかける演説」。2013年9月25日。
- ^ホルト 1989、11、14–15ページ。
- ^ Gil 1997、410、411ページ注61。
- ^ホルト 1989、11~14頁。
- ^第1回十字軍については、一次資料および二次資料で広範囲に記録されています。例えば、トーマス・アズブリッジ著『第1回十字軍:新たな歴史』(オックスフォード、2004年)、(タイアマン、2006年)、ジョナサン・ライリー=スミス著『第1回十字軍と十字軍の理念』(ペンシルバニア、1991年)、そして、活気に満ちているものの時代遅れとなっているスティーブン・ランシマン著『十字軍の歴史:第1巻、第1回十字軍とエルサレム王国の建国』(ケンブリッジ、1953年)などを参照。
- ^タイアーマン 2006、159~160頁。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、『海の彼方で行われた行為の歴史』、EAバブコックとACクレイ訳、コロンビア大学出版局、1943年、第1巻、第9巻、第9章。
- ^ライリー・スミス(1979年)「ゴドフロワ・ド・ブイヨンの称号」歴史研究所紀要52、83-86頁。
- ^マレー、アラン・V.(1990)「エルサレムの統治者としてのゴドフロワ・ド・ブイヨンの称号」、コレッギウム・メディエヴァレ3、163-178頁。
- ^ Asbridge、326ページ。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、第1巻、第9巻、第16章、404ページ。
- ^タイアーマン 2006、201~202頁。
- ^マイヤー 1988、171–76ページ。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、第1巻、第11巻、第27章、507–508ページ。
- ^トーマス・マッデン『十字軍の新簡潔史』(ローマン・アンド・リトルフィールド、2005年)、40~43ページ。
- ^マッデン、43ページ。
- ^マイヤー 1988、71~72ページ。
- ^マイヤー 1988、72–77ページ。
- ^タイアーマン 2006、207~208頁。
- ^マイヤー 1988、83–85ページ。
- ^マイヤー 1988、83~84頁。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、第2巻、第14巻、第18章、76ページ。
- ^マイヤー 1988、86–88ページ。
- ^マイヤー 1988、92ページ。
- ^ジョナサン・フィリップス『第2回十字軍:キリスト教世界の境界の拡張』(イェール大学出版局、2007年)、216~227ページ。
- ^タイアーマン 2006、344~345頁。
- ^マイヤー 1988、108–111ページ。
- ^マイヤー 1988年、112ページ。
- ^マッデン、64~65ページ。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、第2巻、第18巻第16章、265ページ。
- ^アンドリュー・ジョティシュキー (2014). 『十字軍と十字軍国家』 テイラー・アンド・フランシス p. 94. ISBN 9781317876021。
- ^タイアーマン 2006、347–348頁。
- ^マイヤー 1988、118~119ページ。
- ^マイヤー 1988、119~120頁。
- ^タイアーマン 2006、350ページ。
- ^マーシャル・W・ボールドウィン「エルサレムの衰退と陥落、1174-1189」『十字軍の歴史』(ケネス・M・セットン編集)第1巻『最初の100年』(マーシャル・W・ボールドウィン編、ウィスコンシン大学出版、1969年)592ページ以降。
- ^スティーブン・ランシマン『十字軍の歴史』第2巻:エルサレム王国とフランク王国東部(ケンブリッジ大学出版局、1952年)、404ページ。
- ^マイヤー 1988、127–128ページ。
- ^ピーター・W・エドベリー「エルサレム王国におけるプロパガンダと派閥:ハッティンの背景」『 12世紀シリアの十字軍とイスラム教徒』 (マヤ・シャッツミラー編、ライデン:ブリル社、1993年)、174ページ。
- ^ハミルトン 2000、158ページ。
- ^ハミルトン 2000、93ページ。
- ^ハミルトン 2000、105~106ページ。
- ^ハミルトン 2000、101ページ。
- ^ハミルトン 2000、115ページ。
- ^ハミルトン 2000、118ページ。
- ^ハミルトン 2000、122–130ページ。
- ^ハミルトン 2000、132–136ページ。
- ^ハミルトン 2000、150–158ページ。
- ^ハミルトン 2000、161ページ。
- ^ハミルトン、pp. 162–163; エドベリーとロウ、「ウィリアム・オブ・ティルスと1180年の家長選挙」、 The English Historical Review 93 (1978)、再版。『十字軍の王国:エルサレムからキプロスへ』(アルダーショット:アッシュゲート、Variorum Collected Series Studies、1999)、pp. 23–25。
- ^ハミルトン 2000、170~171頁。
- ^ハミルトン 2000、174–183ページ。
- ^ハミルトン 2000、186–192ページ。
- ^ハミルトン 2000、192–196ページ。
- ^ハミルトン 2000、202~203頁。
- ^ハミルトン 2000、204–210頁。
- ^ハミルトン 2000、212–216頁。
- ^ハミルトン 2000、216–223頁。
- ^ハミルトン 2000、223–231頁。
- ^エドベリー 1991、4~5頁。
- ^エドベリー 1991、25~26ページ。
- ^スターク『神の大隊』
- ^エドベリー 1991、26~29頁。
- ^エドベリー 1991、31~33頁。
- ^ライリー・スミス『十字軍の歴史』(第2版、イェール大学出版局、2005年)、146-147頁。
- ^ライリー・スミス『十字軍の歴史』150ページ。
- ^ハンフリーズ、111~122ページ
- ^ライリー・スミス『十字軍の歴史』 153~160ページ。
- ^エドベリー 1991、40~41頁。
- ^エドベリー 1991、48ページ。
- ^ジェームズ・M・パウエル『十字軍の解剖学:1213–1221』(ペンシルバニア大学出版、1986年)、128–135頁。
- ^ Thomas C. Van Cleve、「第五回十字軍」、 A History of the Crusades(gen. ed. Kenneth M. Setton)、第2巻:The Later Crusades, 1189–1311(ed. RL Wolff and HW Hazard、University of Wisconsin Press、1969年)、394-395ページ。
- ^パウエル、137–195ページ。
- ^エドベリー 1991、55~56ページ。
- ^ a bエドベリー 1991、pp.57–64。
- ^ライリー・スミス『十字軍の歴史』第2版、180~182ページ。
- ^ライリー・スミス『十字軍の歴史』第2版、182ページ。
- ^ a bタイアーマン 2006、725–726頁。
- ^マイケル・ローワー『男爵たちの十字軍:武器への呼びかけとその結末』(ペンシルバニア大学出版、2005年)、159~177ページ。
- ^タイアーマン 2006、770–771頁。
- ^タイアーマン 2006、784–803頁。
- ^エドベリー 1991、81–85ページ。
- ^スティーブン・ランシマン「十字軍国家 1243–1291」『十字軍の歴史』第2巻、568–570ページ。
- ^ランシマン「十字軍国家 1243-1291」570-575ページ。
- ^エドベリー 1991、85~90頁。
- ^エドベリー 1991、92–99ページ。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、第1巻、第9巻、第19章、408ページ。
- ^フルチャー・オブ・シャルトル『エルサレム遠征の歴史』フランセス・リタ・ライアン訳、テネシー大学出版局、1969年、第3巻第3章第37節、271ページ( Wayback Machineで2008年4月15日アーカイブ )。
- ^フルチャー、第3巻、第37章第4節、271ページ。
- ^個々の巡礼者の多くの記録がパレスチナ巡礼者文書協会(ロンドン、1884 年–)にまとめられている「Recueil de voyages et mémoires」、Société de Géographie 発行(パリ、1824 ~ 1866 年)。 「航海と地理資料の記録」(パリ、1890 年 –)。
- ^ロニー・エレンブラム『エルサレムのラテン王国におけるフランク人の農村集落』(ケンブリッジ大学出版局、1998年)、3~4頁、10~11頁。
- ^ジョシュア・プラワー『十字軍の王国:中世ヨーロッパの植民地主義』(プラガー、1972年)60ページ、469~470ページ、および全文。
- ^エレンブラム、5~9ページ。
- ^エレンブラム、26~28ページ。
- ^エレンブラム、36~37ページ。
- ^ Prawer, Crusader Institutions、197、205ページ。
- ^マイヤー 1978、175ページ。
- ^マイヤー 1978、177ページ。
- ^ Prawer, Crusader Institutions, pg. 207; Jonathan Riley-Smith, "Some lesser officials in Latin Syria" ( English Historical Review , vol. 87, no. 342 (Jan., 1972)), pp. 1–15.
- ^ペルヌー『十字軍』172ページ。
- ^ Prawer, Crusader Institutions、202ページ。
- ^タイアーマン 2006、230ページ。
- ^タイアーマン 2006、231ページ。
- ^タイアーマン 2006、234ページ。
- ^ a bタイアーマン 2006、235ページ。
- ^タイアーマン 2006、237–238頁。
- ^ジョサイア・C・ラッセル「十字軍諸国の人口」、セットン編『十字軍』第5巻、108ページ。
- ^ a bベンジャミン・Z・ケダール、「フランク王国の被支配ムスリム」『ラテン支配下のムスリム 1100–1300』、ジェームズ・M・パウエル編、プリンストン大学出版、1990年、148ページ。トーマス・F・マッデン編『十字軍:必読書』 、ブラックウェル、2002年、244ページに再録。ケダールはジョシュア・プラワー著『エルサレムのラテン王朝史』、 G・ナホン訳、パリ、1969年、第1巻、498ページ、568–72ページから数字を引用している。
- ^エレンブラム、31ページ。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、第2巻、第22巻、第23章、486–488ページ。
- ^スーヘムのルドルフによれば(誇張されているように思われるが)、次のように記されている。「アッコやその他の場所では、10万6千人近くが殺害または捕らえられ、20万人以上がそこから逃亡した。サラセン人については、30万人以上が殺害されたことは今日でもよく知られている。」(スーヘムのルドルフ、268-272ページ)
- ^ミショー『十字軍の歴史』第3巻、18ページ。インターネットアーカイブで全文閲覧可能。脚注で、ミショーはムスリムに関する情報の多くを「イブン・フェラートの年代記」(ミショー第3巻、22ページ)に依拠していると主張している。
- ^ジョナサン・ライリー=スミス『封建貴族』62~63ページ。
- ^イヴォンヌ・フリードマン『敵との遭遇:エルサレムのラテン王国における捕虜と身代金』ブリル社、2002年、全文。
- ^ Prawer, Crusader Institutions、209ページ。
- ^ヴァーリンデン、1970 年、81–82 ページ
- ^ Prawer, Crusader Institutions、214ページ。
- ^ヴァーリンデン 1970、19–21 ページ
- ^マイヤー 1994、p. V.264。
- ^ウィリアム・オブ・ティルスの有名な例である『ウィレム・ティレンシス・アルキエピスコピ・クロニコン』(RBCホイヘンス編『キリストの記録集成、中世の継続』第38巻(ターンハウト:ブレポルス、1986年)、第19巻、第12章、879~881ページを参照。この章はバブコックとクレイの翻訳が出版された後に発見され、英語版には収録されていない。
- ^例えば、ボードゥアン3世は「かなり教養があり」、「特に歴史の朗読を聞くのが好きだった」と記されている(『ウィリアム・オブ・ティール』第2巻第16巻第2章138ページ)。アマルリック1世は「兄のボードゥアン3世ほどではないものの、かなり教養があり」、王国を統治する慣習法に精通しており、「歴史を熱心に聞き、他のあらゆる読み物よりも歴史を好んだ」と記されている(『ウィリアム・オブ・ティール』第2巻第19巻第2章296ページ)。
- ^ウィリアム・オブ・タイア、バブコックとクレイによる序文、16ページ。
- ^ベンジャミン・Z・ケダール『フランク王国エルサレム最古の法律の起源について:1120年ナブルス公会議の規範』(スペキュラム74、1999年)、330~331頁;マルワン・ナダール『エルサレムとキプロスのラテン王国における市民と市民法(1099~1325年)』(アッシュゲート、2006年)、45頁。
- ^ネイダー、28~30ページ。
- ^ネイダー、158~170ページ
- ^ネイダー、170~177ページ。
- ^ブライアン・ベヴァン(1994年)『ヘンリー4世』ロンドン:マクミラン社、32ページ。ISBN 0-948695-35-8。
引用文献
- フルチャー・オブ・シャルトル著『エルサレム遠征の歴史 1095-1127』フランシス・リタ・ライアン訳、テネシー大学出版局、1969年。
- ウィリアム・オブ・タイア著『海の彼方でなされた行為の歴史』、EAバブコック、ACクレイ訳。コロンビア大学出版局、1943年。
- フィリップ・K・ヒッティ訳『十字軍時代のアラブ系シリア紳士・戦士 ウサマ・イブン・ムンキドの回想録』 (キタブ・アル・イティバル)ニューヨーク、1929年
- ギル、モシェ(1997)[1983]. 『パレスチナの歴史 634-1099』 .エセル・ブライド訳.ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局.ISBN 0-521-59984-9。
- ハミルトン、バーナード(2000年)『ライ王とその相続人』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-1-316-34763-8。
- キャロル・ヒレンブランド『十字軍:イスラムの視点』ラウトレッジ、2000年。
- ホルト, PM (1989). 『十字軍の時代:11世紀から1517年までの近東』ロンドン: ロングマン. ISBN 9780582493025。
- エドベリー、ピーター・W. (1991). 『キプロス王国と十字軍、1191-1374』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局.
- ハンフリーズ、RS(1997)『サラディンからモンゴルへ:ダマスカスのアイユーブ朝、1193-1260』SUNYプレス
- ベンジャミン・Z・ケダール、ハンス・エーバーハルト・マイヤー、RC・スマイル編『Outremer: Studies in the history of the Crusading Kingdom of Jerusalem presented to Joshua Prawer』ヤド・イジャク・ベン・ズヴィ研究所、1982年。
- ジョン・L・ラ・モンテ『エルサレムのラテン王国における封建君主制、1100-1291年』マサチューセッツ州ケンブリッジ、1932年。
- マイヤー、ハンス・エーバーハルト(1988)[1965] 『十字軍』、ジョン・ギリンガム訳(第2版)、オックスフォード大学出版局。
- マイヤー、ハンス・エーバーハルト(1978). 「エルサレムのラテン王国におけるラテン人、イスラム教徒、そしてギリシャ人」.歴史. 63 (208). Wiley: 175–192 . doi : 10.1111/j.1468-229X.1978.tb02360.x . JSTOR i24408666 .
- 『エルサレム問題』(ドイツ語)に転載。バリオラム。 1983年。
- マイヤー、ハンス・エーバーハルト(1994年)「ギヨーム・ド・ティルの学校」エルサレムのラテン王国における王と領主(フランス語)。Variorum、p. V.264。
- 元は『Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et belles-lettres de Dijon』に掲載されました。 (全号 No 117 ) 1985 ~ 1986 年。
- ペルヌー、レジーヌ、『十字軍:聖地への闘争』イグナティウス・プレス、2003年。
- ジョシュア・プラワー著『エルサレムのラテン王国:中世ヨーロッパの植民地主義』ロンドン、1972年。
- ジョシュア・プラワー著『クルセイダー制度』オックスフォード大学出版局、1980年。
- ジョナサン・ライリー=スミス著『封建貴族とエルサレム王国、1174-1277年』マクミラン出版社、1973年。
- ジョナサン・ライリー=スミス『第一次十字軍と十字軍運動の理念』ペンシルバニア大学、1991年。
- ジョナサン・ライリー=スミス編『オックスフォード十字軍史』オックスフォード、2002年。
- スティーブン・ティブル『エルサレムのラテン王国における君主制と領主権、1099-1291年』クラレンドン・プレス、1989年。
- タイアーマン、クリストファー(2006年)『神の戦争:十字軍の新たな歴史』ペンギン社。
- タイアーマン、クリストファー(2019年)『十字軍の世界』イェール大学出版局、267頁。ISBN 978-0-300-21739-1。
- ヴァーリンデン、チャールズ(1970)『近代植民地化の始まり』イサカ:コーネル大学出版局。
- エルサレム、ラテン王国(1099–1291) – カトリック百科事典の記事
さらに読む
- フェルディナンディ、セルジオ (2017)。ラ・コンテア・フランカ・ディ・エデッサ。 Fondazione e Profilo Storico del Primo Principato Crociato nel Levante (1098–1150) (イタリア語)。イタリア、ローマ: ポンティフィシア大学アントニアヌム。ISBN 978-88-7257-103-3。
- ランシマン、スティーブン(1951–1954)『十字軍の歴史』(全3巻)ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。
- セットン、ケネス・M.編(1955–1989)『十字軍の歴史』(全6巻)マディソンおよびロンドン:ウィスコンシン大学出版局。
外部リンク
 ウィキメディア・コモンズにおけるエルサレム王国関連メディア
ウィキメディア・コモンズにおけるエルサレム王国関連メディア