心身の問題
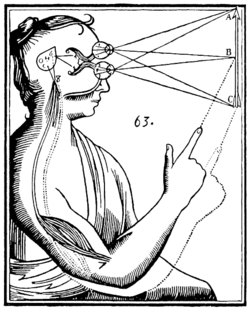
心身問題とは、人間の心身における思考と意識の関係に関する哲学的問題である。[ 1 ] [ 2 ]意識、精神状態、そしてそれらが物理的な脳や神経系とどのように関係しているかという本質を問う。この問題は、非物質的な思考や感情が物質世界とどのように相互作用するのか、あるいはそれらが究極的には物理現象であるのかどうかを理解することに焦点を合わせている。
この問題は17世紀以来、特にルネ・デカルトが心と身体は根本的に異なる実体であると提唱した二元論の定式化以降、心の哲学における中心的な課題となってきました。他の主要な哲学的立場としては、物理主義(すべてのものは究極的には物理的である)と観念論(すべてのものは究極的には精神的である)を包含する一元論があります。より最近のアプローチとしては、機能主義、属性二元論、そして様々な非還元主義理論があります。
心身問題は、精神的出来事と物理的出来事の因果関係、意識の本質、個人のアイデンティティ、そして自由意志といった根本的な問いを提起する。哲学と科学の両面において依然として重要な問題であり、認知科学、神経科学、心理学、人工知能といった分野に影響を与えている。
一般的に、こうした心身のつながりの存在は問題にならないように思われます。しかし、これらの関係を形而上学的あるいは科学的な観点から解釈しようとすると、問題が生じます。こうした考察は、以下のような多くの疑問を提起します。
- 心と体は2つの異なる実体ですか、それとも1つの実体ですか?
- 心と体が2つの異なる実体である場合、その2つは因果的に相互作用するのでしょうか?
- これら 2 つの異なるエンティティが因果的に相互作用することは可能ですか?
- この相互作用の性質は何ですか?
- この相互作用は経験的研究の対象となるでしょうか?
- 心と体が一つの実体であるならば、精神的な出来事は物理的な出来事によって説明できるのでしょうか、あるいはその逆でしょうか?
- 精神的出来事と身体的出来事の関係は、発達の特定の時点で新たに生じるものなのでしょうか?
心と体の関係を論じるこれらの質問やその他の質問はすべて、「心身問題」の範疇に入ります。
心身相互作用と精神的因果関係
哲学者のデイヴィッド・L・ロブとジョン・F・ハイルは、心身相互作用問題の観点から精神的因果関係を提唱している。
心身相互作用は、行為主体性という私たちの理論以前の概念において中心的な位置を占めています。実際、心身問題の定式化においては、精神的因果関係がしばしば明示的に取り上げられています。一部の哲学者は、心理学的説明という概念自体が精神的因果関係の理解可能性にかかっていると主張しています。もしあなたの心とその状態、例えば信念や欲求が、あなたの身体的行動から因果的に切り離されていたとしたら、あなたの心の中で起こっていることは、あなたの行動を説明できないでしょう。心理学的説明が成り立たなければ、行為主体性や道徳的責任といった密接に関連する概念も成り立たなくなります。明らかに、精神的因果関係の問題に対する満足のいく解決には多くのことがかかっており、行動(そしてより一般的には物理世界)に対する心の「因果的関連性」に関する謎が生じる方法は一つではありません。
[ルネ・デカルト]は、その後の心身関係に関する議論の議題を定めました。デカルトによれば、心と身体は異なる種類の「実体」です。彼は、身体は空間的に拡張された実体であり、感情や思考を持たないと考えました。一方、心は拡張されず、思考し、感情を持つ実体です。しかし、心と身体が根本的に異なる種類の実体であるならば、両者がどのようにして因果的に相互作用「できる」のかを理解することは容易ではありません。ボヘミアのエリザベート王女は1643年の手紙の中で、この点を力強く述べています。
人間の魂が、単なる意識ある実体であるにもかかわらず、どのようにして体内の動物的霊魂の動きを決定し、自発的な行為を行わせることができるのか。なぜなら、動きの決定は常に、運動する物体が推進されることから生じるように思われるからだ。つまり、運動のきっかけとなるものから得られる衝動の種類、あるいは後者の表面の性質と形状に依存する。さて、最初の二つの条件は接触を伴うものであり、三つ目は推進するものが拡張性を持つことを伴う。しかし、あなたは魂の概念から拡張性を完全に排除しており、接触は物体が非物質的であることと両立しないように思われる。
エリザベスは、物体の因果関係がどのように機能するかについて、一般的な機械論的見解を述べている。現代物理学が支持する因果関係は様々な形を取り得るが、その全てが押し引き関係に限るわけではない。[ 3 ]
— デイヴィッド・ロブとジョン・ハイル、「精神的因果関係」『スタンフォード哲学百科事典』
現代の神経哲学者ゲオルク・ノルトフは、精神的因果関係は古典的な形式的因果関係および最終的因果関係と両立すると示唆している。[ 4 ]
生物学者、理論神経科学者、哲学者であるウォルター・J・フリーマンは、心と体の相互作用を線形因果関係よりも「循環的因果関係」で説明する方が適切であると示唆している。[ 5 ]
神経科学においては、脳活動と主観的・意識的な経験との相関関係について多くの知見が得られています。多くの人が、神経科学が最終的に意識を説明するだろうと示唆しています。「…意識は生物学的プロセスであり、最終的には相互作用する神経細胞集団が利用する分子シグナル伝達経路によって説明されるだろう…」[ 6 ]しかし、この見解は、意識がプロセスであることが未だ証明されていないこと、[ 7 ]、そして意識と脳活動を直接関連付けるという「難問」が依然として解明されていないことから批判されています。[ 8 ]
今日の認知科学は、人間の知覚、思考、そして行動の具体化にますます関心を寄せています。抽象的な情報処理モデルはもはや人間の心の納得のいく説明としては受け入れられていません。関心は、物質的な人間の身体とその周囲環境との相互作用、そしてそのような相互作用が心をどのように形作るかへと移っています。このアプローチの支持者たちは、このアプローチが最終的に、非物質的な心と人間の物質的存在との間のデカルト的な分裂を解消するであろうという希望を表明しています(Damasio, 1994; Gallagher, 2005)。心身の分裂を橋渡しする上で特に有望と思われるテーマは、身体行為の研究です。身体行為は、外部刺激に対する反射的な反応でもなければ、心的状態の兆候でもなく、行為の運動特性(例えば、選択的な反応をするためにボタンを押すこと)と恣意的な関係しか持ちません。こうした行為の形、タイミング、そして効果は、その意味と切り離せないものです。それらは、物質的な特徴を研究することによってのみ理解できる、精神的内容に満ちていると言えるかもしれません。模倣、コミュニケーションのための身振り、道具の使用などがこうした行動の例である。[ 9 ]
— ゲオルク・ゴールデンバーグ、「心は身体をどのように動かすのか:失行症からの教訓」『オックスフォード人間行動ハンドブック』
1927年、オーストリアで開催されたソルベー会議以来、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのヨーロッパの物理学者たちは、光と電気に関する実験の解釈には、光が波と粒子の両方の振る舞いを示す理由を説明する別の理論が必要であることを認識しました。その意味合いは深遠でした。自然現象を説明する従来の経験的モデルでは、この物質と非物質の二重性を説明できませんでした。この会議は、心身二重性に関する議論を再び呼び起こす重要な契機となりました。[ 10 ]
神経相関

意識の神経学的相関とは、「赤色のように基本的なものから、ジャングルの風景を見たときに呼び起こされる官能的で神秘的で原始的な感覚のように複雑なものまで、特定の意識的な感情を表現するのに十分な脳のメカニズムとイベントの最小の集合体である…」[ 12 ]神経科学者は経験的アプローチを用いて主観的現象の神経学的相関を発見する。[ 13 ]
神経生物学と神経哲学
意識の科学は、主観的な意識状態と体内の電気化学的相互作用によって形成される脳の状態との間の正確な関係、いわゆる意識の難問を説明しなければならない。[ 14 ]神経生物学は、神経心理学や神経精神医学と同様に、この関係を科学的に研究する。神経哲学は、神経科学と心の哲学の学際的な研究である。この研究において、パトリシア・チャーチランド[ 15 ] [ 16 ] 、ポール・チャーチランド[ 17 ]、ダニエル・デネット[ 18 ] [ 19 ]などの神経哲学者は、心よりも身体に主に焦点を当ててきた。この文脈では、ニューロン相関が意識を引き起こすと見なすことができ、意識はこの複雑で適応性のある高度に相互接続された生物学的システムに依存する未定義の特性と考えることができる。[ 20 ]しかし、神経相関の発見と特徴づけが、最終的にこれらの「システム」の一人称体験を説明できる意識の理論を提供し、同等の複雑さを持つ他のシステムにそのような特徴が欠けているかどうかを判断できるかどうかは不明です。
ニューラルネットワークの超並列性により、冗長なニューロン集団が同一または類似の知覚を媒介することが可能になります。しかしながら、あらゆる主観的状態には関連する神経相関があり、それらを操作することで、被験者のその意識状態の経験が人為的に抑制または誘発される可能性があると想定されています。分子生物学の手法と光学的ツールを組み合わせてニューロンを操作する神経科学者の能力向上は、大規模なゲノム解析と操作に適した行動モデルと有機モデルの開発によって達成されました[ 21 ]。このような非ヒト解析は、ヒト脳の画像化と相まって、堅牢で予測力の高い理論的枠組みの構築に貢献してきました。
興奮と満足

意識という用語には、共通しているが異なる2つの次元があります[ 23 ]。1つは覚醒と意識の状態に関するもので、もう1つは意識の内容と意識状態に関するものです。何かを意識するためには、脳は起きているときでもレム睡眠中であっても、比較的高い覚醒状態(警戒状態と呼ばれることもあります)でなければなりません。脳の覚醒レベルは概日リズムで変動しますが、これらの自然なサイクルは睡眠不足、アルコールやその他の薬物、身体的運動などの影響を受ける可能性があります。覚醒は、特定の反応を引き起こすために必要な信号の振幅(たとえば、被験者が振り向いて音源の方を見るような音量)によって行動的に測定できます。高い覚醒状態には、特定の知覚内容、計画と回想、さらには空想を特徴とする意識状態が含まれます。臨床医は、グラスゴー・コーマ・スケールなどのスコアリングシステムを用いて、昏睡状態、持続性植物状態、最小意識状態などの意識障害状態にある患者の覚醒レベルを評価します。ここで「状態」とは、外部化された身体的意識の程度を指し、昏睡、持続性植物状態、全身麻酔による完全な意識消失から、夢遊病やてんかん発作のような変動する最小意識状態まで、多岐にわたります。[ 24 ]
被験者が何らかの経験をするのに十分な脳覚醒状態に達するためには、視床、中脳、橋に存在する、それぞれ異なる化学的特徴を持つ多くの核が機能している必要がある。したがって、これらの核は意識を可能にする因子に属する。逆に、特定の意識的感覚の具体的な内容は、大脳皮質の特定のニューロンと、それらに関連する衛星構造(扁桃体、視床、前障、基底核など)によって媒介されている可能性が高い。
理論的枠組み

様々なアプローチが提案されてきました。その多くは二元論か一元論のいずれかです。二元論は精神と物質の領域を厳密に区別します。一元論は、中立性、実体、本質といった唯一の統一的な実在が存在し、それによって全てを説明できると主張します。
これらのカテゴリーにはそれぞれ多数のバリエーションがある。二元論には主に2つの形態があり、実体二元論では心は物理法則に支配されない独自の種類の実体でできている、とされ、性質二元論では意識経験に関わる精神的性質は完成された物理学によって特定される基本的性質と並んで基本的性質である、とされる。一元論には主に3つの形態があり、物理主義では心は特定の方法で組織化された物質でできている、観念論では思考だけが真に存在し物質は単に精神的プロセスの表現に過ぎない、とされ、中立一元論では心と物質はどちらもそれ自体はどちらとも同一ではない独自の本質の側面である、とされる。精神物理学的平行主義は心と身体の関係、相互作用(二元論)と一方的な作用(一元論)の関係に関する3番目の可能な選択肢である。[ 25 ]
心身二分法を否定することでこの問題から逃れようとする哲学的視点がいくつか展開されてきた。カール・マルクスとその後の著述家たちの史的唯物論は、それ自体が物理主義の一形態であり、意識は環境の物質的偶然性によって生み出されると主張した。[ 26 ]二分法を明確に否定する立場はフランス構造主義に見られ、これは戦後大陸哲学の一般的な特徴であった。[ 27 ]
仏教の教えに説かれている五蘊モデルとして知られる古代の心のモデルは、心を絶えず変化する感覚印象と心的現象として説明しています。[ 28 ]このモデルを考察すると、絶えず変化する感覚印象と心的現象(すなわち心)が、世界のあらゆる外的現象、そして人体構造、神経系、そして脳器官を含むあらゆる内的現象を経験・分析していることがわかります。この概念化は、(i) 脳の働きに関する第三者の視点からの分析と、(ii) 個人の心の流れの瞬間瞬間の顕現を分析する(一人称視点からの分析)という2つのレベルの分析につながります。後者を考察すると、心の流れの顕現は、世界の様々な現象を分析し、脳器官の分析や仮説を立てる科学者でさえも、常にすべての人間に起こっていると説明されます。[ 28 ]
クリスチャン・リストは、ベンジ・ヘリーのめまいがするほどの問い、すなわち、なぜ個人は自分自身として存在し、他者として存在しないのか、そして一人称事実の存在は、物理主義に反する証拠であると主張する。しかし、リストによれば、これは標準的な二元論を含む他の三人称形而上学的見解に反する証拠でもある。[ 29 ]リストはまた、このめまいがするほどの問いは意識理論にとって「四つの難題」を暗示していると主張する。彼は、「一人称実在論」、「非独我論」、「非断片化」、「一つの世界」という形而上学的主張のうち、真となり得るのはせいぜい三つであり、したがって、これら四つのうち一つは拒絶されなければならないと主張する。[ 30 ]リストは、独我論に陥ることなく意識の主観的性質を調和させるために、「意識の多世界理論」と呼ぶモデルを提唱している。[ 31 ]
二元論
以下は、心身問題へのいくつかの貢献についての非常に簡単な説明です。
相互作用主義
相互作用主義の観点では、心と体は2つの別々の実体であるが、互いに影響を与え合うことができると示唆している。[ 32 ]この心と体の相互作用は、哲学者ルネ・デカルトによって最初に提唱された。デカルトは、心は非物質的で体全体に浸透しているが、心と体は松果体を介して相互作用すると信じていた。[ 33 ] [ 34 ]この理論は長年にわたって変化し、20世紀には科学哲学者のカール・ポパーと神経生理学者のジョン・カリュー・エクルズが主な支持者であった。[ 35 ] [ 36 ]相互作用主義のより最近の人気のあるバージョンは創発主義の観点である。[ 32 ]この観点では、精神状態は脳の状態の結果であり、精神的出来事が脳に影響を与え、その結果、心と体の間に双方向のコミュニケーションが生じるとされている。[ 32 ]
非物理的な心(もしそのようなものが存在するならば)とその物理的な延長(もしそのようなものが存在するならば)との間に、経験的に特定可能な接点が存在しないという主張は、相互作用主義二元論に対する批判として提起されてきた。この批判を受けて、多くの現代の心の哲学者は、心は身体から分離したものではないと主張するようになった。[ 37 ]これらのアプローチは、特に社会生物学、コンピュータサイエンス、進化心理学、神経科学といった分野において、科学に大きな影響を与えてきた。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
アブシャロム・エリツァルは相互作用論を擁護し、自身を「消極的二元論者」と称している。エリツァルが二元論を支持する論拠の一つに、困惑に基づく議論がある。エリツァルによれば、意識のある存在はPゾンビ版の自分を思い描くことができる。しかし、Pゾンビは対応するクオリアを欠いた自分の姿を思い描くことはできない。[ 42 ]
上乗せ現象主義
随伴現象主義の見解は、物理的な脳は心の中で精神的な出来事を引き起こすことはできるが、心は脳と全く相互作用できないと示唆し、精神的な出来事は単に脳のプロセスの副作用であると主張します。[ 32 ]この見解は、喜び、恐怖、悲しみなどの感情に体が反応するとしても、感情が身体的な反応を引き起こすわけではないと説明しています。むしろ、喜び、恐怖、悲しみ、そしてすべての身体反応は、化学物質とそれらの身体との相互作用によって引き起こされるのだと説明しています。[ 43 ]
心理物理学的平行性
心理物理学的並行主義の観点は、心と体は完全に独立していると示唆しています。さらに、この観点では、精神的刺激と身体的刺激、そして反応は心と体の両方で同時に経験されますが、両者の間に相互作用やコミュニケーションは存在しないとされています。[ 32 ] [ 44 ]
二重相主義
二重相論は、心と体が相互作用することも、分離することもできないことを示唆する心理物理学的平行論の延長である。[ 32 ]バルーフ・スピノザとグスタフ・フェヒナーは二重相論の著名な使用者であったが、フェヒナーは後にそれを拡張し、心と体の関係を証明しようとして心理物理学の分野を形成した。[ 45 ]
予定調和
予定調和の観点は、精神的出来事と身体的出来事は別個かつ明確に区別されるが、両者は外部のエージェントによって調整されているという、心理物理学的平行論のもう一つの派生である。そのようなエージェントの例としては、神が挙げられる。[ 32 ]予定調和の考えを支持した著名な人物としては、モナドロジー理論を唱えたゴットフリート・ヴィルヘルム・フォン・ライプニッツが挙げられる。 [ 46 ]彼の予定調和の説明は、初めに万物の精神的および身体的出来事を調整した外部のエージェントとしての神に大きく依存していた。[ 47 ]
ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツの予定調和論(フランス語:harmonie préétablie)は、因果関係に関する哲学理論である。この理論によれば、あらゆる「実体」は自身にのみ影響を及ぼすが、それでもなお、世界のあらゆる実体(肉体と精神の両方)は、神によって互いに「調和」するようにあらかじめプログラムされているため、因果的に相互作用しているように見える。ライプニッツはこれらの実体を「モナド」と呼び、著名な著作(『モナドロジー』第7章)の中でこれを「窓のない」ものと表現した。
予定調和の概念は、一見すると精神的側面と物理的側面の両方を持つ出来事を考えることで理解できます。例えば、つま先をぶつけた後に「痛い」と言うことを考えてみましょう。この出来事を記述する方法は大きく分けて2つあります。精神的出来事(痛みの意識的な感覚が「痛い」と言わせる)と物理的出来事(つま先の神経発火が脳に伝わり、「痛い」と言わせる)です。心身問題の主な課題は、これらの精神的出来事(痛みの感覚)と物理的出来事(神経発火)がどのように関連しているかを解明することです。ライプニッツの予定調和は、精神的出来事と物理的出来事は因果関係において真に関連しているのではなく、心理物理学的な微調整によって相互作用しているように見えるだけである、と述べることで、このパズルに答えようとしています。
ライプニッツの理論は、心がどのように身体と相互作用するかという心身問題への解決策として最もよく知られています。ライプニッツは、物理的な身体が互いに影響し合うという考えを否定し、あらゆる物理的な因果関係をこのように説明しました。
予定調和の下では、それぞれの心の事前プログラミングは極めて複雑でなければならない。なぜなら、それが存在する限り、その心だけが自身の思考や行動を引き起こすからである。相互作用しているように見せるためには、それぞれの物質の「プログラム」には、宇宙全体、あるいは、発生しているように見えるあらゆる相互作用において、その物体が常にどのように振る舞うか、のいずれかの記述が含まれている必要がある。
例:
- リンゴがアリスの頭に落ち、彼女の心に痛みを感じさせたように見えます。しかし実際には、リンゴが痛みを引き起こしているのではなく、痛みはアリスの心の以前の状態によって引き起こされているのです。アリスが怒って手を振っているように見える場合、実際には彼女の心ではなく、彼女の手の以前の状態が原因なのです。
心が窓のないモナドとして振舞う場合、その心の感覚知覚を生み出すために他のいかなる物体も存在する必要はなく、その結果、その心のみからなる独我論的宇宙が生まれることに注意すべきである。ライプニッツは『形而上学序説』第14節でこれを認めているように思われる。しかし彼は、神が可能な限り最善かつ最も調和のとれた世界を創造するという彼の調和原理は、各モナドの知覚(内部状態)が世界全体を「表現」し、モナドによって表現される世界が実際に存在することを規定していると主張している。ライプニッツは各モナドが「窓のない」と述べているものの、モナドは創造された宇宙全体の「鏡」として機能するとも主張している。
ライプニッツは時折、自らを「予定調和の体系の創始者」と称した。[ 48 ]
イマヌエル・カントの教授マルティン・クヌッツェンは、予定調和を「怠惰な心のための枕」とみなした。[ 49 ]
デカルトは『形而上学的省察』第六章において、「自然一般」を神自身と同一視した直後に、「神によって設置された被造物の調和的配置」について論じた。神と、現存する世界において実現される神の規範的本性との関係に関する彼の概念は、ライプニッツの予定調和論と、バルーク・スピノザの「神の本性」論の両方を想起させる。[ 50 ]
偶発主義
偶然主義の観点は、精神物理学的平行論のもう一つの派生であるが、大きな違いは心と体が間接的に相互作用するという点である。偶然主義は、心と体は別個かつ明確に区別されるが、神の介入によって相互作用すると示唆する。[ 32 ]ニコラ・マルブランシュはこの考えの主要な貢献者の一人であり、デカルトの心身問題に関する見解への異議を唱える手段としてこの考えを用いた。[ 51 ]マルブランシュの偶然主義において、彼は思考を身体が動くことへの願望と捉え、神が身体を動かすことでその願望が満たされるとした。[ 51 ]
歴史的背景
この問題は17世紀にルネ・デカルトによって普及され、デカルトの二元論に発展した。また、アリストテレス以前の哲学者[ 52 ] [ 53 ]、アヴィセンナ哲学[ 54 ]、そして初期のアジアの伝統でもこの問題は取り上げられた。
仏陀
仏教の開祖である釈迦牟尼(紀元前 480-400 年)は、心と身体は互いに依存し合っており、まるで二つの葦の束が互いに寄りかかっているかのようになっていると説明しました[ 55 ]。そして世界は心と物質で成り立ち、それらが相互依存的に作用していると教えました。仏教の教えでは、心は流れの速い小川のように、瞬間瞬間、一度に一つの思考の瞬間ごとに現れると説明されています。[ 28 ]心を構成する要素は、五蘊 (すなわち、物質的色彩、感覚、知覚、意志、および感覚的意識) として知られており、これらは絶えず生じては消滅しています。現在の瞬間におけるこれらの五蘊の発生と消滅は、生物的法則、心理的法則、物理的法則、意志的法則、および宇宙的法則という 5 つの因果法則に影響されていると説明されています。[ 28 ]仏教のマインドフルネスの実践には、この常に変化する心の流れに注意を払うことが含まれます。
最終的に、ブッダの哲学は、心と色は常に変化する宇宙の条件付きで生じる性質であり、涅槃に達するとすべての現象的経験が存在しなくなるというものです。[ 56 ]ブッダの無我の教義によると、概念的な自己は個々の実体の単なる精神的構築物であり、基本的には色、感覚、知覚、思考、意識によって維持される、永続しない幻想です。[ 57 ]ブッダは、精神的に何らかの見解に執着すると妄想とストレスにつながると主張しました。[ 58 ]ブッダによると、心が明晰であるときには本当の自己(観点と見解の基礎である概念的な自己)を見つけることができないためです。
プラトン
プラトン(紀元前429-347年)は、物質世界は彼がイデアと呼んだ概念から成る高次の現実の影であると信じていました。プラトンによれば、私たちの日常世界の事物はこれらのイデアに「参加」し、物質的な事物にアイデンティティと意味を与えます。例えば、砂に描かれた円は、イデアの世界のどこかに存在する理想的な円の概念に参加しているからこそ円となるのです。彼は、肉体が物質世界から来ているように、魂はイデアの世界から来ており、したがって不滅であると主張しました。彼は、魂は一時的に肉体と結合しており、死の時にのみ分離されると信じていました。魂が純粋であれば、死の時にイデアの世界に戻ります。そうでなければ、輪廻転生が起こります。魂は肉体のように時間と空間に存在しないため、普遍的な真理にアクセスできます。プラトンにとって、イデア(イデア)は真の現実であり、魂によって経験されます。プラトンにとって、肉体は世界の抽象的な現実にアクセスできないという点で空虚です。影しか経験できない。これはプラトンの本質的に合理主義的な認識論によって決定される。[ 59 ]
アリストテレス
アリストテレス(紀元前384-322年)にとって、心は魂の能力である。[ 60 ] [ 61 ]魂に関して、彼はこう言った。
魂と体が一つであるかどうかを問う必要はない。それは、蝋とその形が一つであるかどうかを問う必要がないのと同様である。また、一般的に、それぞれの物の物質とその物質となっているものが一つであるかどうかを問う必要はない。なぜなら、一と存在が様々な形で語られるとしても、正しく語られるのは現実性だからである。
— 『デ・アニマ』 ii 1, 412b6–9
結局、アリストテレスは魂と肉体の関係を単純なものと捉えた。それは、立方体という形が玩具の積み木の特性であるのが単純なのと同様である。魂は肉体が示す特性の一つであり、それは数ある特性の一つに過ぎない。さらにアリストテレスは、積み木が壊れるとその形が消え去るように、肉体が滅びれば魂も滅びると主張した。[ 62 ]
中世のアリストテレス主義
アリストテレスの影響を受けたトマス主義の伝統の中で活動したトマス・アクィナス(1225–1274)は、アリストテレスと同様に、心と体は印章と蝋のように一体であり、したがって一体であるかどうかを問うことは無意味であると信じていました。しかし、彼は(「心」を「魂」と呼び)、魂は肉体の死後も一体であるにもかかわらず存続すると主張し、魂を「この特別なもの」と呼びました。彼の見解は哲学的というよりはむしろ神学的なものであったため、物理主義や二元論のいずれの範疇にも明確に当てはめることはできません。[ 63 ]
東洋の一神教の影響
東洋の一神教の宗教哲学において、二元論とは、二つの本質的な部分を含む思想の二項対立を指す。「心と体」の分離という最初の正式な概念は、紀元前5世紀半ば頃の古代ペルシャのゾロアスター教における神性と世俗性の二元論に見られる。グノーシス主義とは、紀元1世紀から2世紀にかけて広まったユダヤ教に触発された様々な古代二元論の現代的名称である。これらの思想は後にガレノスの「魂の三分性」[ 64 ]に取り入れられ、後のアウグスティヌスの神義論[65]とアヴィセンナの「イスラム哲学におけるプラトン主義」に表れたキリスト教的感情[ 66 ]の両方につながったようである。
デカルト
| シリーズの一部 |
| ルネ・デカルト |
|---|
 |
ルネ・デカルト(1596-1650)は、心が松果体を介して脳を制御すると信じていました。
私の見解では、この腺は魂の主要な座であり、私たちのすべての思考が形成される場所です。[ 66 ]
— ルネ・デカルト『人間論』
私たちの体の仕組みは、この腺が魂やその他の原因によって何らかの形で動かされるだけで、周囲の霊魂を脳の毛穴へと導き、神経を通して筋肉へと導くようにできています。このようにして、腺は霊魂に手足を動かします。[ 67 ]
— ルネ・デカルト『情念論』
彼が提唱した心と身体の関係は、デカルト二元論あるいは実体二元論と呼ばれています。彼は、心は物質とは異なるが、物質に影響を与えることができるとしました。このような相互作用がどのように発揮されるかは、依然として議論の的となっています。
カント
イマヌエル・カント(1724–1804)にとって、精神と物質を超えたところに、理解の必要条件とみなされる先験的形式の世界が存在する。これらの形式の一部、例えば空間と時間は、今日では脳内に予めプログラムされているように思われる。
…心から独立した世界から私たちに影響を与えるものは何でも、空間的または時間的なマトリックスに位置するものではありません…心には、この「生の直感の多様性」を組織化できるようにするために、2つの純粋な直感が組み込まれています。[ 68 ]
— アンドリュー・ブルック、カントの心と自己意識についての見解:超越論的美学
カントは、心と体の相互作用は、心と体で異なる種類の力を通じて起こると考えている。[ 69 ]
ハクスリー
トーマス・ヘンリー・ハクスリー(1825-1895)にとって、意識は脳に影響を与えない脳の副産物、いわゆる付帯現象でした。
随伴現象主義の見解では、心的出来事は因果関係を持たない。この見解を唱えたハクスリーは、心的出来事を機関車の運転に何の貢献もしない蒸気汽笛に例えた。[ 70 ]
— ウィリアム・ロビンソン『エピフェノメナリズム』
ホワイトヘッド
アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドは、デイヴィッド・レイ・グリフィンが汎経験主義と呼んだ洗練された汎心論を提唱した。[ 71 ]
ポッパー
カール・ポパー(1902–1994)にとって、心身問題には三つの側面がある。物質の世界、心の世界、そして数学のような心の創造物の世界である。彼の見解では、心の第三世界の創造物は第二世界の心によって解釈され、第一世界の物質世界に影響を及ぼすために用いられる。例えばラジオは、第二世界の心が第三世界(マクスウェルの電磁気学理論)を解釈し、外部の第一世界の修正を示唆する例である。
心身問題とは、私たちの思考プロセスが第2世界と第1世界における脳の出来事とどのように結びついているのかという問題である。…これらの試みられた解決策の中で、最初にして最も古いものだけが真剣に受け止められるに値すると私は主張したい。つまり、第2世界と第1世界は相互作用し、誰かが本を読んだり講義を聞いたりすると、読者や聞き手の思考の第2世界に作用する脳の出来事が起こる。逆に、数学者が証明に従うと、彼の第2世界が彼の脳に作用し、ひいては第1世界に作用する。これが心身相互作用のテーゼである。[ 72 ]
— カール・ポパー『心身問題に関する実在論者の覚書』
ライル
ギルバート・ライルは1949年の著書『心の概念』で「デカルトの二元論の棺に最後の釘を打ち込んだ」とみなされた。[ 73 ]
「デカルトの神話」の章で、ライルは「機械の中の幽霊 の教義」を紹介し、心が身体とは別の存在であるという哲学的概念を説明しています。
私はそれが完全に誤りであることを証明したい。それも細部ではなく、原理的に誤りである。それは単なる個々の誤りの寄せ集めではない。一つの大きな誤りであり、特別な種類の誤りである。つまり、カテゴリーミスである。
サール
ジョン・サール(1932-2025)にとって、心身問題は誤った二分法である。つまり、心は脳のごく普通の側面である。サールは1980年に生物学的自然主義を提唱した。
サールによれば、マクロ経済学とミクロ経済学の問題が存在しないのと同様に、心身問題も存在しない。これらは同一の現象群を異なるレベルで記述しているに過ぎない。[...] しかしサールは、精神的なもの――質的な経験と理解の領域――は自律的であり、ミクロレベルには対応するものが存在しないと注意深く主張している。こうしたマクロ的な特徴の再記述は、一種の骨抜きに等しいのだ。[ 74 ]
— ジョシュア・ラスト、ジョン・サール
参照
参考文献
- ^ 「二元論」スタンフォード哲学百科事典スタンフォード大学形而上学研究室、2020年。
- ^ Georgiev, Danko D. (2020). 「心脳問題への量子情報理論的アプローチ」. Progress in Biophysics and Molecular Biology . 158 : 16– 32. arXiv : 2012.07836 . doi : 10.1016/j.pbiomolbio.2020.08.002 . PMID 32822698. S2CID 221237249.心脳問題とは、観測不可能な意識と観測可能な脳がどのように相互に関係しているかを説明することです。両者は相互作用するのか、それとも一方が
他方を一方的に生成するのか?
- ^ロブ、デイビッド、ハイル、ジョン (2009). 「精神的因果関係」エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』 (2009年夏版)所収。
- ^ジョージ・ノースフ (2004). 『脳の哲学:脳の問題』(意識研究の進歩編第52巻)ジョン・ベンジャミンズ出版. pp. 137– 139. ISBN 978-1588114174
因果関係を「効率的な因果関係」に限定することは、「目標志向」の軽視につながる。なぜなら、[その]枠組みではもはや必要ではなくなったからである。「目標志向」を考慮しないことは、「埋め込み」の軽視につながり、結果として脳、身体、環境の分離を伴う「孤立」が前提とされることになった。「埋め込み」の軽視は、知覚/行為と感覚的印象/運動を同一視することにつながるが、これは「効率的な因果関係」によって十分に説明できる。したがって、「効率的な因果関係」に支配されているため、
感覚的印象/運動ではなく知覚/行為に関連するクオリア
と志向性は科学から排除され、純粋に哲学的な問題とみなされるようになった。「目的因」と同様に、「形式的原因」も排除された。 「効率的な因果関係」は「埋め込まれたコーディング」とは両立しない。[これは必然的に「形式的因果関係」および「最終的因果関係」と結びついている。…最後に、精神的因果関係の可能性は「効率的な因果関係」とは両立しない。しかしながら、「形式的かつ最終的因果関係」によって適切に記述することは可能である。
- ^ Walter J Freeman (2009). 「意識、意図性、そして因果関係」 . Susan Pockett、W. P. Banks、Shaun Gallagher (編). 『意識は行動を引き起こすのか?』 . MIT Press. pp. 4– 5, 88– 90. ISBN 978-0262512572。
- ^エリック・R・カンデル(2007年)『記憶の探求:新たな心の科学の出現』WWノートン、9ページ。ISBN 978-0393329377。
- ^オズワルド・ハンフリング (2002). 『ウィトゲンシュタインと人間的生命形態』 心理学出版. pp. 108– 109. ISBN 978-0415256452。
- ^ユージン・O・ミルズ(1999年)がデイヴィッド・チャーマーズに帰した用語。 「意識という難問を諦める」。ジョナサン・シアー編『意識の説明:難問』MIT出版、109ページ。ISBN 978-0262692212。
- ^ゴールデンバーグ、ゲオルグ (2008). 「第7章 心は身体を動かす:失行症からの教訓」モーセラ、E.、バーグ、JA、ゴルウィッツァー、PM (編) 『オックスフォード・ハンドブック・オブ・ヒューマン・アクション』 社会認知と社会神経科学 オックスフォード大学出版局、米国. 136ページ. ISBN 9780195309980。LCCN 2008004997。
- ^ギルダー、L. (2009). 『エンタングルメントの時代:量子物理学が復活したとき』ヴィンテージブックス. ISBN 978-1-4000-9526-1. 2021年11月11日閲覧。
- ^ Christof Koch (2004). 「図1.1: 意識の神経相関」 . 『意識の探求:神経生物学的アプローチ』. コロラド州エングルウッド: Roberts & Company Publishers. p. 16. ISBN 978-0974707709。
- ^クリストフ・コッホ (2004). 「第5章:意識の神経相関とは?」『意識の探求:神経生物学的アプローチ』コロラド州エングルウッド:ロバーツ・アンド・カンパニー・パブリッシャーズ. pp. xvi, 97, 104. ISBN 978-0974707709。
- ^関連用語の用語集については、 Wayback MachineのArchived 2013-03-13 を参照してください。
- ^カンデル、エリック・R. (2007). 『記憶の探求:心の新しい科学の出現』 WWノートン社. p. 382. ISBN 978-0393329377。
- ^チャーチランド、パトリシア・スミス (2002). 『ブレイン・ワイズ:神経哲学研究』 ブラッドフォード・ブックス. MITプレス. ISBN 9780262532006。LCCN 2002066024。
- ^チャーチランド、パトリシア・スミス (1989).神経哲学:心と脳の統合科学に向けて. 認知と知覚の計算モデル. MITプレス. ISBN 9780262530859。LCCN 85023706。
- ^チャーチランド、ポール (2007). 『神経哲学の実践』 ケンブリッジ大学出版局. pp. viii– ix. ISBN 9780521864725。LCCN 2006014487。
- ^デネット、ダニエル・C. (1986). 『内容と意識』 国際哲学図書館. テイラー・アンド・フランシス. ISBN 9780415104319。LCCN 72436737。
- ^デネット、ダニエル・C. (1997). 『心の種類:意識の理解に向けて』 サイエンスマスターズシリーズ. ベーシックブックス. ISBN 9780465073511。LCCN 96164655。
- ^スクワイア、ラリー・R. (2008). 『基礎神経科学(第3版)』アカデミック・プレス. p. 1223 . ISBN 978-0-12-374019-9。
- ^ Adamantidis AR; Zhang F.; Aravanis AM; Deisseroth K.; de Lecea L. (2007). 「ヒポクレチンニューロンの光遺伝学的制御による覚醒の神経基質の解明」 . Nature . 450 ( 7168): 420–4 . Bibcode : 2007Natur.450..420A . doi : 10.1038/nature06310 . PMC 6744371. PMID 17943086 .
- ^ Christof Koch (2004). 「図5.1 コリン作動性活性化システム」 . 『意識の探求:神経生物学的アプローチ』. コロラド州エングルウッド:Roberts & Company Publishers. p. 91. ISBN 978-0974707709。オンラインで入手可能な第 5 章も参照してください。
- ^ Zeman, A. (2001). 「意識」 . Brain . 124 (7): 1263–1289 . doi : 10.1093/brain/124.7.1263 . PMID 11408323 .
- ^シフ、ニコラス・D.(2004年11月)「意識障害の神経学:認知神経科学の課題」ガッザニガ、マイケル・S.(編)『認知神経科学』(第3版)、MITプレス、ISBN 978-0-262-07254-0
- ^ヒュー・チザム編 (1911). .ブリタニカ百科事典. 第20巻 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. p. 762.
- ^ K. マルクス『経済学批判への貢献』、プログレス出版社、モスクワ、1977年、R. ロハスの注釈付き。
- ^ブライアン・S・ターナー(2008年)『身体と社会:社会理論の探究』(第3版)セージ出版、78頁。ISBN 978-1412929875...
心と体の二元論を否定し、その結果、体は決して単なる物理的な物体ではなく、常に意識の具現化であるという主張を主張します。
- ^ a b c d Karunamuni ND (2015年5月). 「心の5つの集合体モデル」 . SAGE Open . 5 (2): 215824401558386. doi : 10.1177/2158244015583860 .
- ^リスト、クリスチャン (2023). 「物理主義に対する第一人称論証」2025年2月7日閲覧。
- ^リスト、クリスチャン (2023). 「意識理論のためのクアドリレンマ」 . 『フィロソフィカル・クォータリー』 . 2025年2月7日閲覧。
- ^リスト、クリスチャン (2023). 「意識の多世界理論」 . 『哲学季刊』 . 2025年2月7日閲覧。
- ^ a b c d e f g hヘルゲンハーン、ボールドウィン・R. (2009). 『心理学史入門 第6版』 ベルモント、カリフォルニア州: センゲージ・ラーニング. p. 18. ISBN 978-0-495-50621-8。
- ^ヘルゲンハーン、ボールドウィン・R. (2009). 『心理学史入門 第6版』 ベルモント、カリフォルニア州: Cengage Learning. pp. 121– 122. ISBN 978-0-495-50621-8。
- ^ 「相互作用主義哲学」ブリタニカ百科事典オンライン。 2020年7月17日閲覧。
- ^ポッパー、カール・R.(1977年)『自己と脳:相互作用論の論拠』シュプリンガー・インターナショナル、ISBN 0-415-05898-8. OCLC 180195035 .
- ^エクルズ、ジョン・C.(1994)、「自己とその脳:究極の統合」、自己が脳を制御する方法、ベルリン、ハイデルベルク:シュプリンガー・ベルリン・ハイデルベルク、pp. 167– 183、doi:10.1007/978-3-642-49224-2_10、ISBN 978-3-642-49226-6
{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク) - ^キム・ジェグワン (1995). 「創発的性質」テッド・ホンデリッチ編.オックスフォード哲学コンパニオン. オックスフォード: オックスフォード大学出版局. p. 240. ISBN 9780198661320。
- ^ Pinel, J. (2009). Psychobiology (第7版). Pearson/Allyn and Bacon. ISBN 978-0205548927。
- ^ LeDoux, J. (2002). 『シナプスによる自己:脳はいかにして私たち自身を形成するのか』Viking Penguin. ISBN 978-88-7078-795-5。
- ^ラッセル, S. & ノーヴィグ, P. (2010). 『人工知能:現代的アプローチ』(第3版). プレンティス・ホール. ISBN 978-0136042594。
- ^ドーキンス, R. (2006). 『利己的な遺伝子』(第3版). オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0199291144。
- ^エリツァル、アブシャロム (2009). 「意識は違いを生む:消極的な二元論者の告白」 .還元不可能な意識. 意識に関する選集. 2025年1月24日閲覧。
- ^ Walter, Sven. 「Epiphenomenalism」 .インターネット哲学百科事典. ビーレフェルト大学. 2020年7月17日閲覧。
- ^ Broad, CD (2014-06-03).自然における心とその位置. doi : 10.4324/9781315824147 . ISBN 9781315824147。
- ^ヘルゲンハーン、ボールドウィン・R. (2013). 『心理学史入門 第7版』 センゲージラーニング. pp. 240– 241. ISBN 978-1-133-95809-3。
- ^ライプニッツ、ゴットフリート・ヴィルヘルム。 (2016年)。ラ モナドロジー。 BnF-P. ISBN 978-2-346-03192-4. OCLC 1041048644 .
- ^ヘルゲンハーン、ボールドウィン・R. (2009). 『心理学史入門 第6版』 ベルモント、カリフォルニア州: センゲージ・ラーニング. pp. 186– 188. ISBN 978-0-495-50621-8。
- ^ Leibniz Philosophischen Schriften hrsg. C. ゲルハルト、Bd VI 539, 546;そして新しいエッセイも
- ^ポーター、バートン(2010年)『カメが教えてくれたこと:哲学の物語』ロウマン&リトルフィールド出版社、133ページ。
- ^カッティンガム、ジョン(2013年6月1日)「II—ジョン・コッティンガム:デカルトとダーウィン:第六瞑想に関する考察」(pdf) .アリストテレス協会補遺巻. 87 (1). オックスフォード大学出版局: 268. doi : 10.1111/j.1467-8349.2013.00229.x . ISSN 0309-7013 . OCLC 5884450451. 2021年4月30日閲覧。
- ^ a bヘルゲンハーン、ボールドウィン・R. (2009). 『心理学史入門 第6版』 ベルモント、カリフォルニア州: センゲージ・ラーニング. p. 185. ISBN 978-0-495-50621-8。
- ^ロバート・M・ヤング (1996). 「心身問題」 RCオルビー、G・N・カンター、J・R・クリスティー、M・J・S・ホッジス編. 『近代科学史コンパニオン』(ラウトレッジ社1990年版のペーパーバック復刻版). テイラー・アンド・フランシス. pp. 702–11 . ISBN 978-04151457872007年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ロビンソン、ハワード(2011年11月3日)「二元論」エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』(2011年冬版)所収。
- ^ヘンリック・ラーゲルルンド (2010). 「序論」ヘンリック・ラーゲルルンド編著『心の形成:アヴィセンナから医学啓蒙時代までの内的感覚と心身問題に関するエッセイ』(2007年版ペーパーバック復刻版)Springer Science+Business Media . p. 3. ISBN 978-9048175307。
- ^ナラカラピヨ・スータ:葦の束アーカイブ済み2016年5月3日 at the Wayback Machine
- ^ Rohitassa Sutta: Rohitassa へ2011 年 5 月 12 日にウェイバック マシンにアーカイブ
- ^五蘊:学習ガイド 2002年9月17日アーカイブウェイバックマシン
- ^サバサヴァ・スータ:すべての発酵2006年6月25日アーカイブat the Wayback Machine
- ^ネルソン、アラン編 (2005). 『合理主義への手引き』オックスフォード、英国: Blackwell Publishing Ltd. pp. xiv– xvi. doi : 10.1111/b.9781405109093.2005.00003.x (2025年7月1日現在休止). ISBN 978-1-4051-0909-3。
{{cite book}}:欠落または空|title=(ヘルプ)CS1メンテナンス:DOIは2025年7月時点で非アクティブです(リンク) - ^ジェンドリン 2012b、121~122ページ432a1-2したがって、魂は手と同じです。なぜなら、手は道具の中の道具であり、ヌースは形の一種だからです( ὥστε ἡ ψυχὴ ὥσπερ ἡ χείρ ἐστιν· καὶ γὰρ η χεὶρ ὄργανόν ἐστιν ὀργάνων )アリストテレスは、ヌースと手のこの側面を、私の知る限り他のどこにも用いない新たな用語で定義しています。手は「道具の中の道具」であり、ヌースは「形相の中の形相」です。この点において、手と魂は特異です。これが何を意味するのか、さらに詳しく見ていきましょう。
アリストテレスは、ヌースは形態であると言っているようだが、よく調べてみるとそうではない、あるいは少なくとも通常の種類のものではないことがわかる。ヌースは形態を作る者である。「形態の形態」は道具の道具、道具を作る生体の器官のようなものである。ヌース自体は、確かにそれが作る種類の形態ではない。手は作られた道具ではない(それはまた別の手で作られなければならない)。ギリシア語では「道具」と「器官」は同じ語である。つまり、「道具の道具」という語句の最初の用法は生体の器官を表し、2番目は人工的に作られた道具を表す。II -4で彼は「すべての自然体は魂の道具(器官)である」(食料としても、道具を作る材料としても)と言っている。英語では、手は道具の器官であると言うだろう。
- ^ Hicks 1907 , p. 542 431b230–432a14.要約すると、魂はある意味で事物の宇宙であり、それは感覚できるものと知性的なものから成り立っています。そして知識はある意味でその対象である知性的なものと同一であり、感覚はその対象である感覚的なものと同一です。この記述にはさらなる説明が必要です。感覚と知識は、潜在的であろうと現実的であろうと、状況に応じて潜在的または現実的事物に分配されます。また、魂においては、感覚的能力と認識的能力が潜在的にそれぞれの対象です。したがって、これらの対象は魂の中に存在しなければなりませんが、具体的な全体、つまり形態と物質が結合したものとしてではなく(これは不可能です)、魂の中に存在するのは事物の形態でなければなりません。したがって、魂においては、知性は形態の形態、すなわち知性的なものの形態であり、感覚は感覚的なものの形態であり、それはまさに身体において手が道具の道具、すなわち他の道具を獲得するための道具であるのと同じです。
- ^ Shields, Christopher (2011). 「アリストテレスの心理学」 . Edward N. Zalta (編). 『スタンフォード哲学百科事典』(2011年春版) .
- ^マキナニー、ラルフ、オキャラハン、ジョン(2018年夏)。「聖トマス・アクィナス」スタンフォード哲学百科事典。2018年11月7日閲覧。
- ^ Researchgate:ガレノスと三者魂アーカイブ2017-05-31 at the Wayback Machine
- ^初期キリスト教の著作:ガレノスArchived 2017-05-31 at the Wayback Machine
- ^ロクホルスト、ゲルト=ヤン(2008年11月5日)「デカルトと松果体」エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』(2011年夏版)所収。ロクホルストは『人間論』の中でデカルトの言葉を引用している。
- ^ロクホルスト、ゲルト=ヤン(2008年11月5日)「デカルトと松果体」エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』(2011年夏版)所収。ロクホルストは『魂の受難』の中でデカルトの言葉を引用している。
- ^ブルック、アンドリュー(2008年10月20日)「カントの心と自己意識に関する見解」エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』(2011年冬版)所収。
- ^エリック・ワトキンス (2004). 「文脈における因果律」 .カントと因果律の形而上学. ケンブリッジ大学出版局. p. 108. ISBN 978-0521543613。
- ^ロビンソン、ウィリアム(2011年1月27日)「エピフェノメナリズム」。エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』(2012年夏版)第1巻、pp . 539– 547。doi : 10.1002 / wcs.19。PMID 26271501。S2CID 239938469。
- ^例えば、ロニー・デスメットとミシェル・ウェーバー編著『ホワイトヘッド『形而上学の代数』応用プロセス形而上学夏期研究所覚書』、2017年7月27日アーカイブ、ルーヴァン・ラ・ヌーヴ、Éditions Chromatika、2010年( ISBN 978-2-930517-08-7)。
- ^カール・ライムント・ポパー (1999). 「心身問題に関する実在論者の覚書」 .人生はすべて問題解決である(1972年5月8日マンハイムでの講演より). Psychology Press. 29頁以降. ISBN 978-0415174862
心身の関係は…人間の物理的世界における位置づけの問題を包含する…「世界1」。人間の意識的なプロセスの世界を「世界2」、人間の心の客観的創造物の世界を「世界3」と呼ぶことにする
。 - ^ Tanney, Julia (2007年12月18日). 「ギルバート・ライル」 .スタンフォード哲学百科事典. 2021年5月2日閲覧。
- ^ジョシュア・ラスト (2009).ジョン・サール. コンティニュアム・インターナショナル・パブリッシング・グループ. pp. 27– 28. ISBN 978-0826497529。
参考文献
- ブンゲ、マリオ(2014)『心身問題:心理生物学的アプローチ』エルゼビア、ISBN 978-1-4831-5012-3。
- フェイグル、ハーバート(1958)「『精神的』と『身体的』ハーバート・フェイグル、マイケル・スクリヴン、グローバー・マクスウェル(編)『概念、理論、そして心身問題』ミネソタ科学哲学研究第2巻、ミネアポリス:ミネソタ大学出版局、 370~ 457頁。
- ジェンドリン, ET (2012a). 「アリストテレス『デ・アニマ』第1巻と第2巻の逐語訳」(PDF) .
- ジェンドリン, ET (2012b). 「アリストテレス『デ・アニマ』第3巻の逐語訳」(PDF) .
- ヒックス、RD(1907年)アリストテレス『デ・アニマ』ケンブリッジ大学出版局
- Kim, J. (1995). 「心身問題」, Oxford Companion to Philosophy . テッド・ホンデリッチ編. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
- ジェグウォン・キム(2010年)『心の形而上学に関するエッセイ』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-162506-0。
- マッシミニ、M.; トノーニ、G. (2018). 『意識の大きさを測る:経験能力の客観的測定に向けて』オックスフォード大学出版局.
- ターナー、ブライアン・S.(1996)『身体と社会:社会理論の探究』
外部リンク
 ウィキブックスの意識研究
ウィキブックスの意識研究- プラトン中期形而上学と認識論 - スタンフォード哲学百科事典
- ロバート・M・ヤング (1996). 「心身問題」. R.C. オルビー、G.N. カンター、J.R. クリスティー、M.J.S. ホッジス編. 『近代科学史コンパニオン』(ラウトレッジ社1990年版のペーパーバック復刻版). テイラー・アンド・フランシス. pp. 702–11 . ISBN 978-0415145787。
- 心身の問題、BBCラジオ4のアンソニー・グレイリング、ジュリアン・バギーニ、スー・ジェームズとの討論(In Our Time、2005年1月13日)

