ジャングルの獣
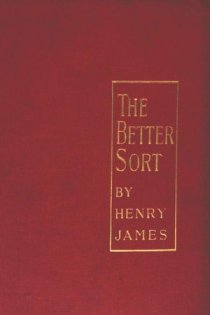 初版(英国) | |
| 著者 | ヘンリー・ジェイムズ |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 出版社 | メシューエン、ロンドンチャールズ・スクリブナー・サンズ、ニューヨーク市 |
発行日 | メシューエン:1903年2月26日スクリブナーズ:1903年2月26日 |
| 出版場所 | イギリス、アメリカ合衆国 |
| メディアタイプ | 印刷物(ハードカバーとペーパーバック)短編集『The Better Sort』の一部として出版 |
| OCLC | 24050323 |
『密林の獣』はヘンリー・ジェイムズによる1903年の中編小説で、初版は短編集『良き類人』に収録されています。ジェイムズの傑作短編の一つとして広く認められているこの物語は、孤独、運命、愛、そして死といった普遍的なテーマを巧みに扱っています。ジョン・マーチャーとその数奇な運命を描いた寓話は、多くの読者の心に響き、人生の価値と意味について考察してきました。
あらすじ
ジョン・マーチャーは、10年前に南イタリアに住んでいた頃に知り合ったメイ・バートラムと再会する。彼女はマーチャーの奇妙な秘密を思い出す。マーチャーは、自分の人生は「ジャングルの獣」のように待ち構えている、ある破滅的あるいは壮大な出来事によって定義づけられるという思いにとらわれていた。メイは大叔母から相続したお金でロンドンに家を買い、マーチャーと日々を過ごし、どんな運命が待ち受けているのかを好奇心を持って待つことにする。マーチャーは絶望的な宿命論者で、妻を自分の「壮大な運命」に巻き込ませたくないため、結婚はできないと信じている。
彼はメイを劇場に連れて行き、時折夕食に誘うものの、彼女に近づくことは許さない。ただ傍観し、人生の最良の時期を過ごす中で、メイもまた打ちのめされる。そして物語の結末で、彼は自分の人生における最大の不幸は、途方もない予感に基づいてそれを捨て、善良な女性の愛を無視したことだったと悟る。
主要テーマ
マーチャーの執着はあまりにも奇抜で非現実的であるため、彼の運命は的外れで説得力に欠けるように思えるかもしれない。しかし、多くの批評家や一般読者は、彼の悲劇は、平凡な人生を救い出す高揚感に満ちた体験への共通の憧れを、劇的に、そして効果的に描き出しているだけだと感じている。もっとも、ほとんどの人は、メイの墓前でマーチャーが明かすような最後の啓示のようなものに耐えることはできないだろうが。
この物語は、ジェームズ自身の人生についての告白、あるいは寓話として解釈されてきた。彼は結婚せず、おそらくは性的な関係を経験したこともなかった。美的創造性を深く味わったにもかかわらず、彼が「本質的な孤独」と呼ぶものを依然として悔いていた可能性もある。こうした伝記的な関連性が、『密林の獣』に新たな意味を与えている。
批判的評価
ジェイムズは、ニューヨーク版(1907~1909年)第17巻の冒頭に「密林の獣」を、生と死を洞察力豊かに描いたもう一つの作品「死者の祭壇」と共に掲載した。批評家たちはほぼ全員一致で、作者自身のこの物語に対する高い評価に同意しており、中にはこの物語をあらゆる文学作品の中でも最高の短編小説の一つに挙げる者もいる。
批評家たちは、ジェイムズが「この世に何も起こらなかったはずの男」を構想した際の洞察力の鋭さを高く評価している。また、物語の技法も称賛している。中立的で控えめな語り口で始まる物語は、力強いクライマックスへと盛り上がっていく。多くの批評家は、その強烈さと修辞的なインパクトから、最後の段落を特に高く評価している。特に最後の一文は、ジェイムズにしては短いながらも、物語を力強く締めくくるフレーズの連続で締めくくられている。
逃げ道は彼女を愛することだった。そうすれば、彼は生きられただろう。彼女は――今となってはどれほどの情熱を持って生きていたのか、誰が知ることができるだろうか――彼を自分自身のために愛していたから。一方彼は、彼女のことを(ああ、どれほど彼を睨みつけたことか!)決して自分のエゴイズムの冷たさと、彼女を利用することの光の中でしか考えていなかった。彼女の言葉が彼の心に蘇り、鎖はどんどん伸びていった。獣は確かに潜んでいた。そして、獣は、その時が来ると、飛び出したのだ。寒い四月の黄昏時に、青白く、病弱で、衰弱し、それでいて美しく、そしておそらくは回復の見込みさえあった彼女が椅子から立ち上がり、彼の前に立ち、想像を巡らせて推測させた時、飛び出したのだ。彼が推測しなかった時に、飛び出したのだ。彼女が絶望的に彼から背を向けた時に、飛び出したのだ。そして、彼が彼女のもとを去る頃には、標的は落ちるべき場所に落ちていた。彼は自分の恐怖を正当化し、運命を成し遂げたのだ。彼は、最後の正確さをもって、失敗するであろうすべてのことに失敗した。そして今、彼女が、彼が知らないようにと祈ったことを思い出し、うめき声が彼の唇からこみ上げてきた。目覚めることの恐怖――これは知識だった。息を呑むと、彼の目の涙さえも凍りつくように凍りつくような知識だった。それでも、彼はその知識を通して、それをしっかりと掴もうとした。痛みを感じることができるように、目の前にそれを保とうとした。少なくとも、遅ればせながら、苦い経験には、人生の味わいのようなものがあった。しかし、その苦さが突然彼を吐き気にさせた。そしてまるで、恐ろしいことに、彼は真実の中に、自分の姿の残酷さの中に、定められたこと、そしてなされたことを、見たかのようだった。彼は自分の人生のジャングルと、潜む獣を見た。そして、じっと見つめていると、空気のざわめきのように、それが巨大で醜悪な姿で、彼を落ち着かせようとする跳躍のために立ち上がるのを感じた。彼の目は暗くなった――それはすぐそこにあった。そして、彼は幻覚の中で本能的にそれを避けようと向きを変え、墓に顔から身を投げ出した。[ 1 ]
適応
膜
- この中編小説は2017年にブラジルの監督パウロ・ベッティ、エリアーネ・ジャルディーニ、ラウロ・エスコレルによって同名の映画化された。[ 2 ]
- この中編小説は2018年にオランダ人監督クララ・ファン・グールによって同名の映画化された。[ 3 ]
- この中編小説は2023年にオーストリアのパトリック・チハ監督によって同名の映画化された。[ 4 ]
- 2023年にフランスの監督ベルトラン・ボネロが制作した映画『ビースト』は、この小説から自由にインスピレーションを得たものである。[ 5 ]
音楽
- この小説に基づきアルノー・プティが作曲したオペラ『ジャングルの獣』が、2023年4月14日にケルン歌劇場(ドイツのケルン歌劇場)で初演された。
参考文献
- ^ジェイムズ、ヘンリー (1903). 「ジャングルの獣」. 『ザ・ベター・ソート』 . ニューヨーク: チャールズ・スクリブナー・サンズ.
- ^ “A Fera na Selva :: Entrevista exclusiva com Paulo Betti” .パポ・デ・シネマ(ポルトガル語)。 2017 年 10 月 4 日。
- ^オッジャーノ、ロベルト(2019年1月31日) 「クララ・ヴァン・グール • 『ビースト・イン・ザ・ジャングル』監督」Cineuropa .
- ^グッドフェロー、メラニー(2023年1月18日)。「『ジャングルの野獣』クリップ:ベルリン国際映画祭ヘンリー・ジェイムズ原作映画にアナイス・デモスティエ、トム・メルシエ、ベアトリス・ダルが出演」。Deadline。2023年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月22日閲覧。
- ^ Roos, Gautier (2021年12月25日). 「[ベルトラン・ボネロ インタビュー] Le grand entretien chaos」 [[ベルトラン・ボネロ インタビュー] The Great Chaos Interview]. Chaos Reign (フランス語).
- ヘンリー・ジェイムズ物語集:物語のテキスト、作者の技巧、批評クリストフ・ウェゲリンとヘンリー・ウォナム編(ニューヨーク:WWノートン社、2003年)ISBN 0-393-97710-2
- エドワード・ワーゲンクネヒト著『ヘンリー・ジェイムズ物語』(ニューヨーク:フレデリック・ウンガー出版社、1984年)ISBN 0-8044-2957-X
- マイク・ニコルズがダスティン・ホフマンを型破りな役柄で起用した決定に影響を与えたとされる「ニコルズさん、卒業制作展」 。ヴァニティ・フェア誌、2008年3月号。http ://www.vanityfair.com/news/2008/03/graduate200803
外部リンク
- ニューヨーク版『密林の獣』(1909年)
 LibriVoxのパブリックドメインオーディオブック「The Beast in the Jungle」
LibriVoxのパブリックドメインオーディオブック「The Beast in the Jungle」- 『密林の獣』(1909年)ニューヨーク版本文への著者の序文
- アメリカ図書館ウェブサイトの「ジャングルの獣」のテキストに関する注釈
- ジェームズ、H. 『The Better Sort』、メシューエン・アンド・カンパニー、ロンドン、1903年、インターネットアーカイブのデジタルコピー
- [1]文学と芸術のオンラインジャーナル「ブラックバード」より
