『城』(小説)
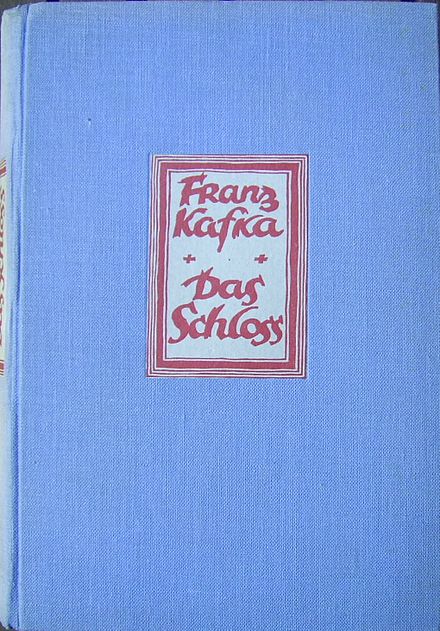 初版(1926年) | |
| 著者 | フランツ・カフカ |
|---|---|
| 原題 | Das Schloss |
| 翻訳者 | 出版履歴を参照 |
| 言語 | ドイツ語 |
| ジャンル | 政治小説、不条理小説、パラノイア小説 |
| 舞台 | 中央ヨーロッパの村 |
| 出版社 | クルト・ウォルフ |
出版日 | 1926年 |
| 833.912 | |
| LCクラス | PT2621.A26 S33 |
原文 | ドイツ語ウィキソースのDas Schloss |
| ウェブサイト | www.franzkafka.de / werk /das-schloss |
『城』(ドイツ語: Das Schloss、 Das Schloß [das ˈʃlɔs]とも綴られる)は、フランツ・カフカの最後の小説であり、1926年に初めて出版されました。この小説では、 「K」としてのみ知られている主人公が村に到着し、西西伯爵が所有していると思われる城から村を統治している謎の当局に近づくために奮闘します。
カフカはこの作品を完成する前に亡くなり、彼の意に反して死後に出版されました。暗く、時にシュールな『城』は、疎外感、反応のない官僚主義、不透明で一見恣意的な支配体制の中で事業を運営しようとするフラストレーション、そして達成不可能な目標への無駄な追求を描いた作品と解釈されることが多いです。
歴史

カフカは1922年1月27日の夜、山岳リゾート地シュピンドレルミューレ(現在のチェコ共和国)に到着したその日に、この小説の執筆を始めました。到着時に撮影された写真には、『城』を彷彿とさせる風景の中で、雪の中を馬そりに乗っているカフカの姿が写っています。[ 1 ]そのため、原稿の最初の数章は一人称で書かれ、後にカフカによって三人称の語り手「K」に変更されたことには重要な意味があります。[ 2 ]
マックス・ブロッド
カフカは小説を書き上げる前に亡くなったが、結核から生還していたとしても、完成させるつもりだったかどうかは疑問である。ある時、彼は友人マックス・ブロッドに、小説の結末は主人公Kが死ぬまで村に住み続けることで、城は彼の死の床で「村に住むという彼の法的権利は無効だが、いくつかの付随的な状況を考慮すれば、彼はそこで生活し、働くことが許される」と通知するだろうと語った。[ 2 ]しかし、1922年9月11日、ブロッドに宛てた手紙の中で、彼はこの小説の執筆を諦め、二度と取り掛からないと記している。[ 3 ]実際には、この小説は文の途中で終わっている。
カフカはブロッドに未発表作品をすべて死後に破棄するよう指示していたが、彼はその多くを出版した。『城』は1926年にミュンヘンの出版社ジョエラ・グッドマンによってドイツ語で初版が出版された。この版は当初印刷された1,500部をはるかに下回る販売数にとどまった。[ 4 ] 1935年にベルリンのショッケン出版社から、1946年にはニューヨークのショッケン・ブックスから再版された。[ 5 ]
ブロッドは出版に向けて作品に大幅な編集を施した。彼の目的は、カフカの文章の構造を維持することではなく、作品と作者の受容を得ることだった。この構造は翻訳の将来に大きな影響を与え、現在もなお本文に関する議論の中心となっている。[ 6 ]ブロッドは原稿をオックスフォード大学に寄贈した。[ 7 ]
ブロッドは城の象徴性に強い宗教的意味を見出しました。[ 1 ] [ 8 ]これは、アーノルド・エドシックを含む多くの人々が指摘した数多くのユダヤ・キリスト教の参照に基づいた作品の解釈の一つです。[ 9 ]
マルコム・パスリー
出版社はすぐに翻訳が「ひどい」ことに気づき、1940年に「全く異なるアプローチ」を望んだ。[ 6 ] 1961年、マルコム・パスリーは『審判』を除くカフカの全作品を入手し、オックスフォード大学ボドリアン図書館に寄贈した。パスリーと研究者チーム(ゲルハルト・ノイマン、ヨスト・シレマイト、ユルゲン・ボルン)は、1982年にS.フィッシャー出版社を通じて作品の出版を開始した。『城』はその年に二巻本として出版された。第一巻は小説、第二巻は断片、削除、編集者の注釈を収録した。このチームは、カフカ独特の句読点(作風に決定的な要素とみなされていた)を含め、原文のドイツ語テキストを完全かつ不完全な状態に復元した。[ 10 ]
ストロームフェルト/ローター・シュテルン
カフカの原稿の意図の解釈は現在も進行中です。かつてストロームフェルト/ローター・シュテルン出版社は、原稿と転写を並べて掲載した批評版の出版権を求めて活動していました。しかし、カフカの相続人とパスリーからの抵抗に遭いました。[ 11 ]
主な版

- 1930年 翻訳者:ウィラ・ミュアとエドウィン・ミュア。[ 12 ]マックス・ブロッドによる最初のドイツ語版に基づく。イギリスではSecker & Warburg社、アメリカではAlfred A. Knopf社から出版
- 1941年版翻訳者:ウィラ・ミュアとエドウィン・ミュア。この版にはトーマス・マンによるオマージュが収録されている。
- 1954年の翻訳者:ウィラ・ミュアとエドウィン・ミュア、追加部分はエイトネ・ウィルキンスとエルンスト・カイザーが翻訳。おそらく決定版。ショッケンの1951年版(おそらく決定版)に基づく。[ 13 ]
- 1994翻訳者: Muir 他、Irving Howeによる序文。
- 1997年翻訳:JAアンダーウッド、序文:イドリス・パリー。パスリー批判ドイツ語テキスト(1982年、1990年改訂)に基づく。
- 1998年翻訳者:マーク・ハーマン(序文も執筆)。パスリー批判ドイツ語テキスト(1982年、1990年改訂)に基づく。
- 2009年 翻訳者:アンシア・ベル、序文:リッチー・ロバートソン。パスリー批判ドイツ語テキスト(1982年、1990年改訂)に基づく。
タイトル
タイトルの「Das Schloss」は「城」あるいは「宮殿」と訳されることもあるが、ドイツ語の「Das Schloss」は多義語であり、「錠前」の意味も持ち合わせている。また、音韻的には「 der Schluss」(結論、終結)に近い。[ 1 ]城は鍵がかけられ、Kと町民は立ち入ることができない。
城は城らしくない。アンシア・ベルの翻訳では、「広大な建物群で、2階建ての建物もいくつかあるが、多くは低層で密集している。城だと知らなければ、小さな町だと思ったかもしれない」(11ページ)とされている。
あらすじ

主人公Kは、近くの城を拠点とする謎めいた官僚組織によって統治されている村に到着する。宿屋に身を寄せたKは、城当局から召喚された測量士だと名乗る。するとすぐに、城の連絡係がクラムという役人であることが知らされ、クラムはKに村長に報告するよう、紹介状を渡す。
村長はKに、城と村の間の連絡に手違いがあり、誤って依頼されたと告げる。しかし村長は、Kに学校教師の世話役の職を与える。一方、村の慣習、官僚制度、手続きに不慣れなKは、村人にとって強いタブーとされているクラムへの訪問を試み続ける。
村人たちは役人たちと城を高く評価しているが、役人たちの行動を実際に理解しているようには見えない。役人たちの行動は一度も説明されていない。村人たちは長々とした独白を通して、役人たちの行動に対する憶測と正当化を提示する。誰もが役人たちの行動について何らかの説明をしているように見えるが、しばしば矛盾しており、その曖昧さを隠そうとする様子もない。むしろ、村人たちは役人たちの行動を、役人のもう一つの行動、あるいは特徴として称賛する。
「公式声明」と村の認識との間の最も明白な矛盾の一つは、秘書官エルランガーがフリーダに酒場の女中として復帰するよう要求したという論文である。Kは、この要求が城によって強制されていることを知っている唯一の村人である(フリーダがその発端である可能性はあるものの)。[ 14 ] [ 15 ]村の住民は全く考慮されていない。
城は究極の官僚機構だ。膨大な書類を抱え、完璧だと主張している。しかし、その完璧さは嘘だ。書類に欠陥があり、それがKをこの村に導いたのだ。この制度には他にも欠陥がある。Kは、受取人が誰なのか分からず、書類を破り捨てる使用人を目撃する。
城の住人は皆成人男性のようで、城の官僚機構以外についてはほとんど触れられていない。注目すべき例外は、消防隊の存在と、オットー・ブラウンシュヴァイクの妻が城の出身だと宣言していることである。後者の宣言は、Kにとってオットーの息子ハンスの重要性を浮き彫りにし、城の役人に近づくための手段として利用されている。
役人には村で仕事をする秘書が1人、あるいは複数人いる。秘書は村を訪れることもあるが、性的な意味合いを持つ女性との交際を必要としない限り、村人と交流することはない。
登場人物
注:ミュア訳では「ヘレンホフ・イン」と表記されていますが、ハーマン訳では「ガストホフ・ヘレンホフ」を「紳士の宿屋」、ベル訳では「城の宿屋」と訳しています。以下、村の役人が宿泊する宿屋はすべて「ヘレンホフ・イン」です
| キャラクター | 説明 |
|---|---|
| 土地測量士 K | 物語の主人公であるKは、土地測量士として認められ、学校の用務員として雇われているものの、町の人々からはよそ者とされている。小説の大部分において、彼は村の官僚主義を乗り越え、城の役人であるクラムに連絡を取ろうと粘り強く努力するが、度々妨害され、挫折する。Kは酒場の女主人フリーダと性的関係を持つが、彼女は最終的にKを捨て、彼の助手の一人であるジェレミアと結ばれる。 |
| フリーダ | ヘレンホーフの元バーメイド。小説の大部分でKの婚約者となる。彼女はKへの義務と、彼の熱心すぎる態度への不安の間でしばしば葛藤する。最終的に彼女はKを捨て、彼の元アシスタントであるジェレミア(現在はヘレンホーフのウェイターになっている)の腕の中に引き寄せられる |
| ハンス、宿屋の主人(ブリッジ・イン) | 宿屋の元の所有者の甥。妻のガーデナによると、彼は怠け者で、K に優しすぎるという。K によると、ハンスには初恋の相手として別の妻がいたら、もっと自立して勤勉で男らしい男になっていただろうとのこと。 |
| ガーデナ、女将(ブリッジイン) | 長年一人で経営してきたブリッジ・インの経営の立役者だが、その仕事は彼女の健康を蝕んでいる。かつてクラムの短期間の愛人だった彼女は、Kの真意を深く疑っており、Kがクラムとの面会を強く求めたため、最終的にKを追い出す。彼女は依然としてクラムへの想いを募らせている。 |
| 使者 バルナバ | Kに任命された城の使者。彼は新人であり、Kは彼をクラム公との連絡係として使うよう指示されている。細身で機敏だが、非常に未熟で繊細な一面も持つ。 |
| K.の助手、アーサーとジェレミア(ハーマン版のアーサーとジェレミア) | 村に到着して間もなく、Kは様々な用事に対応するため、二人の助手を割り当てられる。しかし、彼らはKにとって常にフラストレーションと苛立ちの種であり、最終的にはKの残酷な仕打ちによって二人を解雇する。彼らは、当時クラムの代理を務めていた役人ガラターがKを喜ばせるために割り当てたものだ。 |
| 村長 (ハルマン版では村議会議長、ドイツ語:Dorfvorsteher) | クラムからKに任務を与えるよう任命された、親しみやすく太った、髭をきれいに剃った男。Kの上司でもある。しかし、ガーデナによれば、彼は全く取るに足らない存在で、妻のミッツィがいなければこの地位に一日もとどまることはなかっただろうという。一方、先生によれば、彼は立派な経験豊富で、尊敬に値する老人だという。痛風を患う市長はKをベッドで迎え、土地測量士としてKが必要とされていない理由を説明する。そして、先生を落胆させるかのように、Kに学校の用務員の職を提供する。 |
| 市長の妻 ミッツィ | ガーデナさんは市長の妻であり補佐官でもあるが、彼女のことを「仕事をする人」と呼んでいる。 |
| クラム | Kの城政官である、謎めいた城役人。作中に登場する他の城役人と同様に、彼の専門分野については具体的には触れられていない。Kは小説の大部分をクラムとの会談の確保に費やしている。Kは、クラムとの会談に問題の解決への多くの希望を託しているようだ。彼には少なくとも2人の秘書、エルランガー(第一秘書)とモムスがいる ドイツ語で「klamm」は「湿っぽい」または「湿った」という意味で、「峡谷」や「峡谷」を指すこともあります。形容詞としては、「狭い」や「お金に困っている」という意味もあります。チェコ語(カフカはチェコ語を話し、読み書きすることができました)では「klam」は「幻想」を意味します。 アンシア・ベルの翻訳に対するリッチー・ロバートソンの注釈によれば、クラムは「チェコ語の「幻想」を意味するklamを示唆している」とのことです (p. 277)。 プラハでは、クラム・ガラス宮殿は同じように発音され、カフカがクラム・クラムのこの複数の意味を使用することに影響を与えた可能性があります。 |
| クラムの秘書、 モムス | 非常にハンサムな若い紳士。顔色は青白く、赤みがかっている。クラムへのあらゆる文書作成と請願書の受付を担当する。また、ヴァラベーヌの秘書でもあるが、ヴァラベーヌは小説中では再登場しない。彼はKを尋問しようと試みるが、Kは従わない。 |
| クラムの秘書、 エルランガー | K. を「尋問」するために派遣されたクラムの第一秘書だが、彼に短いメッセージしか与えない。 |
| バルナバの妹 オルガ | アマリアとバルナバの姉。彼女はKの探求を手助けし、自分の家族がなぜ追放者とみなされているのかを話したり、村の習慣を教えたりした。 |
| バルナバの妹 アマリア | バーナバスとオルガの妹。城の役人ソルティーニからの性的行為の依頼を無礼に断ったため、村で不名誉な目に遭った。 彼女はほとんどの時間を病気の両親の世話に費やしている。 |
| バーナバスの父 | オルガ、アマリア、バーナバスの父。かつては村の靴屋で、著名な消防士でもあった。アマリアがソルティーニの使者と不名誉なやり取りをしたため、彼の事業は破綻し、消防士の資格を剥奪された。家族のために恩赦を得ようとしたが失敗し、彼は障害者となった |
| バルナバの母 | オルガ、アマリア、バルナバの母。 |
| オットー・ブランズウィック、ラーゼマンの義理の息子(ハーマン版ではラーゼマンの義理の兄弟) | ハンス・ブランズウィックの父。アマリアがソルティーニの使者を無礼に扱ったことでバーナバス家の評判が下がったため、ハンスは都合よくバーナバスの父の顧客を乗っ取る。村長によると、村で土地測量士の雇用を望んだのはブランズウィックだけだったという。理由は明かされていない。 |
| ブラウンシュヴァイク夫人 | ハンス・ブラウンシュヴァイクの母。彼女は自らを「城の出身」と称しており、城にいる唯一の女性である。Kは彼女が城への入り口を手伝ってくれるかもしれないと信じている |
| 思いやりのある学生 ハンス | Kが用務員をしている学校に通う少年。Kに協力を申し出るが、Kは彼を利用して、母親を通して城へ向かう方法を探そうとする。 |
| ヘレンホフの大家 | ヘレンホフ旅館の主人。 |
| ヘレンホフ女将 | ヘレンホフ・インの身なりの良い女将。この宿の女家長のような存在(ブリッジ・インのガーデナも同様)。Kを信用していない。 |
| ガラテル | 彼はKに助手を任命した城の役人です。また、ヘレンホーフ・インでの小さな火事の際、バーナバスの父親に「救助」されました |
| ブリューゲル (ハーマン版 ビュルゲル) | 城の役人フリードリヒの秘書。フリードリヒは作中では再び言及されていないが、削除された文章では、失脚しつつある役人として言及されている。[ 16 ]ブリューゲルは、Kがヘレンホーフの宿屋の彼の部屋に誤って入ってきた時、Kに城での尋問について思いを巡らせる、冗長な秘書である。彼はKに遠回しに助けを申し出るが、Kは疲れ果てていたため、申し出を受け入れない。 |
| ソルディーニ | イタリアの城の秘書官として素晴らしい能力を発揮し、最も低い地位に置かれているにもかかわらず、部署の城でのあらゆる取引を徹底的に管理し、潜在的なミスを疑います。 |
| ソルティーニ | 村の消防隊に所属する城の役人で、アマリアにヘレンホーフの自分の部屋に来るよう、性的に露骨で失礼な要求をして誘う |
| 教師 | 若く、肩身の狭い、横暴な小男。Kが学校の用務員になると、この教師はKの事実上の上司となる。彼はKが学校で働くことを認めていないが、Kの任命を解除する権限はないようだ |
| ミス・ギサ(フロイライン・ギサ)、学校の愛人 | 背が高く、金髪で美しいが、やや堅物な助教。シュワルツァーに求愛されているが、K を嫌っている。 |
| シュバルツァー | 城での暮らしを諦め、ギサ嬢に求愛し、彼女の教育実習生となった下級城主の息子。役人としての傲慢さを爆発させやすい |
| ペピ | 小柄で、血色の良い健康的な女性。フリーダがヘレンホフでの仕事を辞めてKと暮らすため、フリーダのバーメイドの地位に昇進したメイド。彼女はエミリーとアンリエットのメイドでもありました |
| 皮なめし職人のラーゼマン、オットー・ブランズウィックの義父(ハーマン版ではオットー・ブランズウィックの義兄弟) | ゆっくりと威厳のある村の皮なめし職人の家で、K は村に到着した最初の丸一日を数時間過ごしました。 |
| 御者ゲルスタッカー | 当初はKを疑っていたが、城への送迎を断られたため、ブリッジ・インまで無料でソリで送ってあげる。本の最後では、Kがエルランガーに影響力を持っていると信じ、Kと親しくなろうとする。 |
| 消防署長の シーマン | アマリアがソルティーニの使者を無礼に扱ったことでバーナバスの家族が恥をかいた後に、バーナバスの父親から消防士の資格を剥奪した消防署長。 |
| ウェストウェスト伯爵 | 地元の伯爵であり、城の所有者とされている。言及されるだけで、実際に登場することはありません |
主要テーマ
神学
ブロッドの原典は宗教的なテーマに基づいており、ミュアー兄弟の翻訳によってそれがさらに深められたことはよく知られています。しかし、批判版でそれが終わったわけではありません。様々な神学的な観点から、数多くの解釈がなされてきました
Kが城と連絡を取ろうと奮闘する様子に対する一つの解釈は、それが男の救いを求める行為を表しているというものである。[ 17 ] 1998年版の『城』の翻訳者であるマーク・ハーマンによると、これは1930年に最初の英語版を出版したオリジナルの翻訳者ウィラ・ミュア(エドウィンの助けを借りて)が好んだ解釈であった。 [ 12 ]ハーマンは翻訳におけるこの見解への偏りを取り除いたと感じているが、多くの人は依然としてこれがこの本の主題だと考えている。
この小説の聖書的解釈を支えているのは、様々な名前と状況です。例えば、公式のガラテル(ガラテヤ人への手紙のドイツ語)は、使徒パウロとその助手バルナバの活動によって強力なキリスト教信奉者を育成した初期の地域の一つです。使者バルナバの名前も同じ理由です。批評版では、冒頭の章を「到着」と名付けるなど、K.を旧約聖書の救世主になぞらえています。[ 9 ]
官僚主義
『城』全体に貫かれているのは官僚主義です。その極度は滑稽なほどで、村人たちのそれを正当化する言い訳は驚くべきものです。そのため、この作品が、反ユダヤ主義やハプスブルク家の残滓などが蔓延していた、執筆当時の政治状況の直接的な結果であると多くの人が感じるのも不思議ではありません。 [ 18 ] [ 19 ]
しかし、これらの分析の中にも、よりデリケートな問題への暗黙の言及が指摘されている。例えば、バーナバス家への扱い、つまり恩赦を求める前にまず罪を証明しなければならないという要求や、村人たちが彼らを見捨てる様子などは、当時の反ユダヤ主義的な風潮を直接的に示唆していると指摘されている。[ 20 ]
ウィリアム・バロウズはガーディアン紙のこの小説評論で、 『城』が官僚主義を扱っているという見解に異議を唱え、そのような見解はカフカの文学的・芸術的ビジョンを矮小化し、「還元主義的」だと主張している。彼はむしろ、この小説は孤独、苦痛、そして仲間への渇望について描いていると主張している。[ 21 ]
他の作品への言及
批評家はしばしば『城』と『審判』を併せて語り、主人公が官僚制度に抵抗し、法の扉の前に立ちはだかるが『審判』の司祭の寓話のように入ることができないという闘争を強調する。[ 18 ]
カフカの他の作品と共通のモチーフを持つにもかかわらず、 『城』は『審判』とは全く異なる。 『城』の主人公Kは、突如として襲い掛かる現実を捉えるのに苦労し、同じように不安に陥る。一方、 『審判』の主人公ヨゼフ・Kは、より経験豊富で、精神的に強いように見える。しかし、ヨゼフ・Kは奇妙な出来事に見舞われても周囲の環境が馴染み深いままであるのに対し、Kは、彼にとって馴染みのない法やルールを持つ新しい世界に身を置くことになる。
出版履歴

1926年、マックス・ブロッドはクルト・ヴォルフを説得し、 『城』のドイツ語初版を自身の出版社で出版しました。未完成であったことと、カフカの作品を出版したいという彼の願いから、マックス・ブロッドはある程度の編集の自由を取りました
2022年に『城』のドイツ語版は米国でパブリックドメインとなった。 [ 22 ]
ミュア訳
1930年、ウィラとエドウィン・ミュアは、マックス・ブロッドが編纂した『城』の初ドイツ語版を翻訳しました。イギリスではセッカー&ウォーバーグ社、アメリカではアルフレッド・A・クノップフ社から出版されました。トーマス・マンによるオマージュが加えられた1941年版は、戦後のカフカブームを盛り上げるものとなりました
1954年に「決定版」が出版され、ブロートがショッケンの決定版ドイツ語版に追加したセクションが含まれていました。新しいセクションは、アイトネ・ウィルキンスとエルンスト・カイザーによって翻訳されました。ミュアのテキストにはいくつかの編集が加えられ、具体的には「町議会」が「村議会」、「監督官」が「市長」、「依頼者」が「申請者」に変更されました。[ 13 ]
アルフレッド・A・クノップの『Everyman's Library』所蔵のミュアーズ訳の 1992 年版には、アーヴィング・ハウによる序文が掲載されている。
ミュアー夫妻の翻訳では、一部の人々が「霊的」と捉える言葉が使われている。例えば、ミュアー夫妻は、Kが城に喩えた故郷の教会の塔の描写を「揺るぎなくそびえ立つ」と訳している[ 23 ]。ハーマン(8ページ)は「断固として細くなる」、アンダーウッド(9ページ)は「まっすぐ上向きに細くなる」、ベル(11ページ)は「尖塔へと細くなる」としている。さらに、ミュアー夫妻は冒頭の段落以降で「幻想的な」という表現を用いている[ 24 ] 。一部の批評家は、これを彼らの神秘主義的解釈への偏向のさらなる証拠だと指摘している[ 1 ] 。
ハーマン訳
1961年、マルコム・パスリーは、カフカの他の著作の大部分( 『審判』を除く)とともに、この原稿を入手し、オックスフォード大学のボドリアン図書館に収蔵させました。そこでパスリーは学者チームを率いて、カフカの作品を批評版として再編しました。ドイツ語版の『キャッスル批評版』は2巻構成で、1巻は小説、2巻は断片、削除、編集者の注釈で構成されています。これらは1982年にS.フィッシャー出版社から出版されたため、「フィッシャー版」と呼ばれることもあります
マーク・ハーマンはこのセットの第1巻を用いて、1998年版『ザ・キャッスル』を出版しました。これはしばしば「復元本」または「英語批評版」に基づくと言われています。ミュア訳とは異なり、断片、削除、編集者注は含まれていません。出版社の注記によると:
パスリーの第二巻に収録されているカフカによる変奏や削除された箇所は、文学テクストの起源を明らかにする上で確かに役立つものの、私たちはそれらを省略することにしました。一般向けのこの新版の主な目的は、著者が原稿を残した状態に可能な限り近い形でテクストを提示することです。[ 25 ]
エリック・オームズビーは、ハーマンの翻訳はミュアー兄弟の翻訳よりも概ね正確であり、「カフカの散文に時折見られる荒々しくぎこちない質感」を感じさせると述べている。しかし、オームズビーは「ハーマンの翻訳は意味においては概ね正しかったものの、フレーズや文の正しい語調や韻律を捉える能力においては、時として間違っていたり、全く的外れだったりすることもあった」と付け加えている。[ 1 ]
ハーマンは、翻訳の哲学について11ページにわたる考察を記している。このセクションでは、彼が用いた手法と思考プロセスに関する重要な情報を提供している。読者が作品への理解を深められるよう、パスリー、ミュアー、そして自身の翻訳からの引用を多数掲載している。ハーマン(そして出版社)の作品への称賛とミュアー兄弟への「見下し」は、少々行き過ぎだと感じる人もいる。[ 1 ] JMクッツェーは、ハーマンが自身の翻訳はミュアー兄弟の翻訳よりも「奇妙で密度が高い」と述べていると記している。しかし、クッツェーは「奇妙さと密度を追求するハーマン自身の作品は、今日では歓迎されているものの、歴史が進み、人々の嗜好が変化するにつれて、陳腐化に向かっているかもしれない」と付け加えている。[ 26 ]
翻案
映画
この本は何度か映画化されました
- 『城』(Das Schloß)は、1968年のドイツ映画で、ルドルフ・ノエルテ監督、マクシミリアン・シェルがK役で
- 1986年にヤッコ・パッカスヴィルタ監督がフィンランドで映画化した『リンナ』。この映画の主人公の名前は、カフカの小説『審判』の主人公であるヨゼフ・Kである。
- 『城』 (Замок) は、アレクセイ・バラバノフ監督、ニコライ・ストツキーがK 役で
- 城( Das Schloß )は、ミヒャエル・ハネケ監督、ウルリッヒ・ミューエがK 役で
ラジオ
- この小説は2015年5月にエド・ハリスによってBBCラジオ4で二部構成でラジオ化されました。[ 27 ]キャストは、ドミニク・ローワン(K役)、サミー・T・ドブソン(フリーダ役) 、マーク・ベントン(イェレミア役)、ダニエル・ウェイマン(アルトゥール役)、スティーブン・グライフ(教師役)、レイチェル・バヴィッジ(ガーデナ/アマリア役)、ヴィクトリア・エリオット(オルガ役)、ニール・グレインジャー(バーナバス役) 、ジョナサン・カレン(警視正役)、ドミニク・ディーキン(ハンス役)です
その他
- 2012年、アメリカの作家(『Introducing Kafka』の著者でもある)デイヴィッド・ゼイン・マイロウィッツは、チェコのアーティスト兼ミュージシャンであるヤロミール99(ヤロミール・シュヴェイディーク)と共同で、 『 The Castle』のグラフィックノベル版をリリースしました。 [ 28 ] 2013年には、ドイツ語版(「Das Schloss」)とチェコ語版(「Zámek」)がリリースされました
- オフ・ブロードウェイ版(ジム・パーソンズとウィリアム・アサートン主演)は、デヴィッド・フィシェルソンが脚本・演出を担当し、2002年初頭に成功を収め、アウター・クリティックス・サークルの「最優秀オフ・ブロードウェイ演劇賞」とドラマ・リーグの「最優秀演劇賞」 (いずれもニューヨークの演劇賞)にノミネートされた。2002年にドラマティスト・プレイ・サービスから出版された。[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
- ドイツ語オペラ『城』は、1992年にアリベルト・ライマンによって作曲された。ライマンはカフカの小説とマックス・ブロッドによる脚色に基づき、独自の台本を書いた。初演は1992年9月2日にベルリン・ドイツ・オペラで行われ、ヴィリー・デッカーが演出、ミヒャエル・ボーダーが指揮を担当した。[ 33 ]
参照
参考文献
- ^ a b c d e fオームズビー。
- ^ a b The Castle 1968、p. vi、出版社注。
- ^『城』1968年、p. xv、訳者序文。
- ^ The Castle 1998、p. vii、出版社注。
- ^ The Castle 1968、p. iv、出版社注。
- ^ a b The Castle 1998、p. xi、出版社注。
- ^ 「イスラエルの博物館、ドイツからカフカの原稿を要求」 cbc.ca、2009年10月25日。 2012年8月22日閲覧。
- ^ The Castle 1998、p. xiv–xvii、出版社注。
- ^ a b Heidsieck、pp. 1–15。
- ^ Stepping into Kafka's head、ジェレミー・アドラー、 The Times Literary Supplement、1995年10月13日、textkritik.de経由
- ^学者たちがカフカ的ドラマで論争、デイヴィッド・ハリソン、オブザーバー、1998年5月17日、p. 23、textkritik.de経由(購読が必要)
- ^ a b “Willa Muir © Orlando Project” . orlando.cambridge.org . 2017年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月17日閲覧。
- ^ a b The Castle 1968、p. vii、出版社注。
- ^ The Castle 1968、p.428、断片。
- ^『キャッスル』1968年、395ページ。
- ^ The Castle 1968、p. 422、著者により削除された箇所。
- ^『ザ・キャッスル』1998年、p. xviii、訳者序文。
- ^ a b博士論文、Hartmut M. Rastalsky、1997
- ^ Heidsieck、1、10、13ページ。
- ^ Heidsieck、11ページ以降。
- ^ 「冬の読書:フランツ・カフカ著『城』」ガーディアン紙、2011年12月22日。2023年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^グロスマン、ダニエル (2021年12月28日). 「くまのプーさん、フランツ・カフカなど、2022年にパブリックドメインになる作品が続々登場」 . Polygon .
- ^ The Castle 1998、pp. xvii、訳者序文。
- ^冒頭の段落で、ミュア夫妻は「幻想的な空虚」と表現しているが、ハーマンとアンダーウッドは「見かけ上の空虚」と表現し、ベルは「空虚のように見えたもの」と書いている。
- ^ The Castle 1998、p. xii、出版社注。
- ^クッツェー、JM、「カフカ:裁判にかけられた翻訳者たち」、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、1998年5月14日
- ^ 「ドラマ、フランツ・カフカ『城』、エピソード1」。BBCラジオ4。
- ^発売:Jaromír 99とDavid Zane MairowitzによるThe Castle Self Made Hero
- ^ゲンツリンガー、ニール(2002年1月18日)「文字通りのカフカ的官僚主義、演劇評」ニューヨーク・タイムズ。2013年6月2日閲覧。
- ^ジェイコブス、レナード (2002年4月17日). 「アウター・クリティクス・サークル賞ノミネート発表」 .バックステージ. 2013年6月2日閲覧。
- ^ジョーンズ、ケネス (2003年4月28日). 「ドラマリーグのノミネート作品には『魔法にかけられて』、『アルベルティーン』、『アムール』、『サロメ』、『アベニューQ』など」 . Playbill . 2012年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月2日閲覧。
- ^ 「デイヴィッド・フィシェルソン劇作家ページ」 . The Playwrights Database . 2013年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月2日閲覧。
- ^ヘルボルト、ハインツ・ヨーゼフ (1992 年 9 月 11 日)。「フランツ・カフカス・ロマン『Das Schloß』als Musiktheater: Aribert Reimanns sechste Oper in Berlin uraufgeführt: Rundtanz um den Tabernakel der Bürokratie」。Die Zeit (ドイツ語)。 p. 23.2017 年8 月 4 日に取得。
出典
- アーノルド・エドシック「カフカの『城』における共同体、妄想、そして反ユダヤ主義」(PDF)。南カリフォルニア大学。 2009年9月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ
- カフカ、フランツ(1968年)『城』ニューヨーク:アルフレッド・A・クノップフ
- カフカ、フランツ(1998年)『城』マーク・ハーマン訳ニューヨーク:ショッケン・ブックスISBN 9780805241181。
- エリック・オームズビー(1998年11月) 「フランツ・カフカとスピンデルミューレへの旅」ニュー・クライテリオン誌Špindlerův Mlýnを参照

