アレクサンダー・ヘルツェン
アレクサンダー・ヘルツェン | |
|---|---|
 ニコライ・ゲーによる肖像画、1867年 | |
| 生まれる | アレクサンドル・イワノビッチ・ヘルツェン 1812年4月6日 (1812年4月6日)モスクワ、ロシア帝国 |
| 死亡 | 1870年1月21日(1870年1月21日)(57歳) パリ、フランス |
| 教育 | |
| 母校 | モスクワ大学 |
| 哲学的な作品 | |
| 時代 | 19世紀の哲学 |
| 地域 | ロシア哲学 |
| 学校 | 西洋化主義者農業ポピュリズム |
| 主な興味 | 政治、経済、階級闘争 |
| 注目すべきアイデア | 農業主義 |
| サイン | |
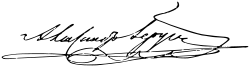 | |
アレクサンドル・イワノビッチ・ゲルツェン(ロシア語:Алекса́ндр Ива́нович Ге́рцен、ローマ字: Aleksándr Ivánovich Gértsen 、 1812年4月6日[旧暦3月25日] - 1870年1月21日[旧暦1月9日])は、ロシア社会主義の先駆者、農業ポピュリズムの主要先駆者の一人として知られるロシアの作家、思想家である(ナロードニキ、社会革命党、トルドヴィキ、農業アメリカ人民党の思想的祖先である)。ロンドンへの亡命中に多くが執筆された著作によって、彼はロシアの状況に影響を与えようとし、1861年の農奴解放につながる政治的風潮に貢献した。彼は重要な社会小説『誰の責任か?』を出版した。 (1845–46年)。彼の自伝『我が過去と思考』(1852–1870年執筆)[ 1 ]は、ロシア文学におけるこのジャンルの最高傑作の一つとしばしば考えられている。
人生
_(1830s,_GIM).jpg/440px-Alexandr_Herzen_in_youth_by_A.Zbruev_(7)_(1830s,_GIM).jpg)
ゲルツェン(ゲルツェンとも)は、裕福なロシア人地主イヴァン・ヤコブレフとシュトゥットガルト出身のヘンリエッテ・ヴィルヘルミナ・ルイサ・ハーグの私生子であった。ヤコブレフは息子が「心の子」(ドイツ語でHerz )であったことから、彼にヘルツェンという姓を与えた。[ 2 ]
彼は、ロシア写真界の父とされ、ヨーロッパにおける初期写真の最も重要な先駆者、発明家、革新者の一人とされるセルゲイ・リヴォヴィチ・レヴィツキー伯爵の従兄弟でした。1860年、レヴィツキーはゲルツェンを有名な写真で永遠に記憶に留めることになりました。
ゲルツェンは、ナポレオンによるロシア侵攻と短期間の占領の直前にモスクワで生まれた。彼の父はナポレオンとの直接会談後、フランス軍からの親書をサンクトペテルブルクのロシア皇帝に届けることに同意し、モスクワからの出国を許可された。彼の家族はロシア戦線まで同行した。[ 3 ]
1年後、家族はモスクワに戻り、ゲルツェンがモスクワ大学で学業を終えるまでそこに留まった。1834年、ゲルツェンと生涯の友人ニコライ・オガリョフは、ソコロフスキーの詩が皇帝に不名誉な歌として歌われる祭りに参加したとして逮捕され、裁判にかけられた。彼は有罪となり、1835年にロシア北東部のヴャトカ(現在のキーロフ)に流刑となった。1837年、皇帝の息子アレクサンドル大公(後の皇帝アレクサンドル2世)が詩人ジュコーフスキーを伴ってこの街を訪れ、ゲルツェンのために調停するまで、彼はそこに留まった。ゲルツェンはヴャトカからウラジーミルへ移ることを許され、そこで市の官報の編集者に任命された。[ 4 ] 1837年に彼は従妹のナタリア・ザハリナと駆け落ちし、[ 5 ]密かに彼女と結婚した。
1839年に釈放され、1840年にモスクワに戻った。そこで文芸評論家のヴィサリオン・ベリンスキーと出会い、強い影響を受けた。到着後、サンクトペテルブルクの内務省でアレクサンドル・ストロガノフ伯爵[ 6 ]の秘書官に任命されたが、警察官による死亡事件への抗議のためノヴゴロドに送られ、1842年まで国務院議員を務めた。1846年、父が亡くなり、莫大な遺産を残した[ 4 ] 。
1847年、アレクサンドルは妻と母、子供たちと共にイタリアへ亡命し、二度とロシアに戻ることはなかった。イタリアから1848年の革命の知らせを聞くと、彼は急いでパリへ、そしてスイスへと向かった。[ 4 ]彼は1848年の革命を支持したが、ヨーロッパの社会主義運動が失敗に終わった後、彼らにひどく幻滅した。ゲルツェンは政治評論家として名声を得た。亡命によりロシアにおける彼の資産は凍結されたが、彼の家族と商取引関係にあったロスチャイルド男爵が資産の解放を交渉し、名目上はロスチャイルドに譲渡された。
アレクサンドルと妻ナタリアの間には4人の子供が生まれた。1851年、母と息子の一人が船の難破で亡くなった。妻はドイツ人詩人ゲオルク・ヘルヴェクと不倫関係を続けていた。[ 1 ] 1852年、ナタリアは結核で亡くなり[ 7 ]、アレクサンドルはジュネーヴを離れ、ロンドンへ移り、そこで長年を過ごした。[ 4 ]彼は娘たちの教育のため、マルヴィダ・フォン・マイゼンブークを雇った。1853年にロンドンで設立した自由ロシア新聞社の出版物を通して、彼はロシアの情勢に影響を与え、彼が崇拝するロシア農民の状況を改善しようと努めた。
1856年、ロンドンで旧友のニコライ・オガリョフがゲルツェンに合流した。二人はロシア語の定期刊行物「コロコル」 (鐘)を共同で執筆した。間もなくアレクサンドルは、オガリョフの妻で戦争の英雄将軍トゥチコフの娘であるナタリア・トゥチコワと情事を始めた。トゥチコワとアレクサンドルには3人の子供が生まれた。オガリョフは新しい妻を見つけ、ゲルツェンとオガリョフの友情は続いた。[ 8 ]
ゲルツェンはロンドンで国際労働者協会の活動に携わり、バクーニンやマルクスといった革命家たちと親交を深めた。[ 9 ]ロンドン滞在中にゲルツェンは「スキャンダル屋」として名を馳せ始めた。シベリアの投獄から逃れて到着したばかりのバクーニンに対し、マルクスが彼をロシアのエージェントだと非難したと告げたのがきっかけだった。実際には二人は非常に良好な関係にあった。[ 10 ]
1864年、ヘルツェンはジュネーヴに戻り、しばらくしてパリへ移り、1870年に結核の合併症で亡くなった。遺体は当初パリに埋葬されたが、1ヶ月後にニースへ移された。[ 11 ]
政治的立場
ゲルツェンは1848年に西欧化を推進したヴィッサリオン・ベリンスキーの死後、その思想を広めた。彼はヴォルテール、シラー、サン=シモン、プルードン、そして特にヘーゲルとフォイエルバッハの影響を受けた。ゲルツェンは当初は自由主義者であったが、次第に社会主義を受け入れるようになった。彼は1847年にロシアを永久に去ったが、1857年から1867年までロンドンで発行していた機関誌『コロコル』は広く読まれた。ゲルツェンはフランス革命とドイツ観念論の主要な思想を融合させた。彼はブルジョア階級や中流階級の価値観を嫌い、農民階級の中に真実性を求めた。彼はロシアの農奴解放のために闘い、1861年に解放が実現すると、憲法上の権利、土地の共同所有、人民による政府に関する要求をエスカレートさせた。[ 12 ]
ゲルツェンは1848年の革命には幻滅していたが、革命思想には幻滅していなかった。彼は1848年の革命家たちを批判するようになった。彼らは「1848年以降の反動にひどく反発し、ヨーロッパのあらゆるものにひどく憤慨し、カンザスやカリフォルニアへと急いだ」のである。[ 13 ]ゲルツェンは常にフランス革命を称賛し、その価値観を広く受け入れていた。初期の著作の中で、彼はフランス革命を歴史の終わり、ヒューマニズムと調和に基づく社会の発展における最終段階と見なしていた。若い頃を通して、ゲルツェンは自らをロシア皇帝ニコライ1世の政治的抑圧と戦うよう召命された革命的急進主義者だと考えていた。本質的に、ゲルツェンはヨーロッパの支配層、キリスト教の偽善、そして個人の自由と自己表現のために戦った。
彼は社会主義と個人主義の両方を推進し、個人の完全な開花は社会主義秩序において最もよく実現されると主張した。しかしながら、社会が到達すべき運命的な地位といった壮大な物語を常に否定し、亡命中に著した著作は、非介入主義的な政府によって個人の自由が保護された小規模な共同生活を推進するものであった。
著作
彼の文学活動は1842年、洗礼名のトルコ語形であるイスカンデルというペンネームで、ロシア語で『科学におけるディレッタント主義』というエッセイを出版したことから始まった。2作目はやはりロシア語で書かれた『自然の研究に関する書簡』(1845-46年)である。1847年には小説『誰のせいか』を出版した。これは、鈍感で無知だが温厚な旧式のロシア人官能主義者の娘と結婚した若い家庭教師の幸せな家庭が、知的で教養があり冷酷な新式のロシア人官能主義者によってかき乱されるという物語であり、その悲劇的な結末の最大の責任が誰にあるかは誰も言えない。[ 14 ]
1847年にはロシアの定期刊行物に物語を発表し、それらは後に1854年にロンドンで『中断された物語』 ( Prervannye Rasskazy )という題名で収録・出版された。1850年にはロシア語原稿から翻訳された2冊の作品『向こう岸から』(From the Other Shore )と『フランスとイタリアの手紙』 (Lettres de France et d'Italie )が出版された。フランス語ではエッセイ『ロシアにおける革命思想の発展』(Du Developpement des idées revolutionnaires en Russie)と回想録(Memoirs )も出版された。回想録はロシア語で印刷された後、『ロシア世界と革命』(Le Monde russe et la Révolution) (全3巻、1860-1862)という題名で翻訳され、一部は『シベリアへの亡命』(My Exile to Siberia) (全2巻、1855)と『私の過去と思考』(My Past and Thoughts )として英語に翻訳された。[ 14 ]
作品
- 伝説(Легенда、1836) [ 15 ]
- エレナ(Елена、1838) [ 15 ]
- 若者の手記(1840年)[ 15 ]
- 科学におけるディレッタント主義[ 16 ] (1843) [ 15 ]
- 誰が責任を負うのか? (Кто виноват?, 1846) [ 15 ]
- ミモエズドム(Мимоездом、1846) [ 15 ]
- クルポフ博士(Доктор Крупов、1847) [ 15 ]
- 泥棒かささぎ (小説) (Сорока-воровка、1848) [ 15 ]
- ロシア国民と社会主義[ 16 ] (Русский народ и социализм、1848)
- 向こう岸から[ 17 ](1848–1850)
- フランスとイタリアからの手紙(1852年)
- 哲学選集[ 16 ] 1956
- 私の過去と思考:アレクサンダー・ヘルツェンの回想録
フリーロシアプレス

1853年、ロンドンで「自由ロシア新聞」を設立した彼は[ 18 ]、その成り行きを1863年に出版したロシア語の本で興味深い記述を残している。彼はその後、当時のロシアの統治体制に反対する多数のロシア語作品を出版した。その中には、農奴制を批判した『洗礼された財産』(1853年)のようなエッセイや、 『ポリャーナヤ・ズヴィエズダ』(北極星)、『コロコル』(鐘)、 『ロシアからの声』 (ロシアからの声)といった定期刊行物もあった[ 14 ]。
ロシア初の独立系政治出版者として、ゲルツェンは不定期に刊行された評論誌『ポーラー・スター』の刊行を開始し、後に1857年から1867年にかけてゲルツェンが私費で発行した雑誌『ベル』もこれに加わった。両誌はロシア領内での非合法な流通を通じて大きな影響力を獲得し、皇帝自身も読んでいたと言われている。両誌は、ロシア皇帝とロシア官僚機構の無能さについてリベラルな視点から報道することで、ゲルツェンにロシアにおける影響力を与えた。
創刊から3年間、『ロシア自由新聞』は一冊も売れず、ロシア国内にほとんど持ち込めなかった。しかし、ある書店主がついに10シリング相当の洗礼財産を買い取った時、驚いた編集者たちはその半金貨を特別な栄誉ある場所に置いた。 1855年のニコライ皇帝の崩御は、状況を一変させた。ゲルツェンの著作と彼が編集した雑誌はロシアに密輸され、その言葉は国中、そしてヨーロッパ全土に響き渡り、影響力は拡大していった。[ 14 ]
1855年はゲルツェンに楽観的な理由を与えた。アレクサンドル2世が帝位に就き、改革が可能であるように思われたからである。ゲルツェンは1856年の『北極星』の中で、改革に向けて「前進、前進」と帝政ロシアに訴えた。1857年の著作では、ゲルツェンはアレクサンドル2世による社会変革の可能性に興奮し、「ロシアでは間違いなく新しい生活が沸き立ちつつあり、政府さえもそれに引き込まれている」と記した。[ 19 ]ベル紙は1857年7月に政府が農奴解放を検討していると報じ、政府にはこの問題を解決する能力が欠けていると付け加えた。しかし1858年になっても完全な農奴解放は達成されておらず、ゲルツェンは改革に焦燥感を募らせていた。1858年5月にはベル紙は農奴の全面解放を求める運動を再開した。1861年のロシアにおける奴隷解放改革が達成されると、「ベル」の運動は「自由と土地」へと転換し、農奴の権利を支持しつつ更なる社会変革を目指す綱領となった。アレクサンドル2世は農奴に自由を与え、裁判所は改築され、陪審裁判が確立され、報道機関にもかなりの程度まで自由が認められた。[ 4 ]
現代の評判

ゲルツェンは、暴力に反対する自由主義者と、ゲルツェンが軟弱すぎると考える急進派の両方から批判を受けた。[ 20 ]ボリス・チチェリンとコンスタンチン・カヴェリンに率いられた自由主義者たちは、個人の自由は社会関係の合理化によって達成されると信じていた。彼らの国家主義的な自由主義は、ロシア社会がヘーゲル主義的な理性観に基づく理想国家へと進化していくと想定していたため、ゲルツェンはこれに反対した。彼らは革命家たちが理想国家の樹立を遅らせるだけだと考えていたが、ゲルツェンはむしろ彼らが歴史的現実に盲目だと考えていた。
ロシアの急進派はゲルツェンが穏健派すぎると嫌った。ニコライ・チェルヌイシェフスキーやニコライ・ドブロリュボフといった急進派は、暴力革命へのさらなる関与と改革派ツァーリへのいかなる希望も捨て去ることを求めた。急進派はゲルツェンに対し、 『鐘』を暴力的急進革命の代弁者として使うよう求めたが、ゲルツェンはこれらの要求を拒否した。彼はロシア急進派は政治的変革を成功させるほど団結し強力ではないと主張し、「君は幸福が欲しいのか?私はそう思う!幸福は征服しなければならない。強ければ手に入れ、弱ければ黙っていろ」と述べた。[ 21 ]ゲルツェンは新たな革命政府が独裁政権を別の独裁政権に置き換えるだけであろうことを恐れていた。
急進派は、ゲルツェンが即時の変化を望まないことからリベラル派だと非難するが、ゲルツェンは成功を確実にするペースでの変化を主張し、彼らの訴えを拒否した。ゲルツェンは、カヴェリンをはじめとする他のロシアのリベラル派と短期間協力し、ロシアにおける農民の「覚醒」を推進した。[ 22 ]ゲルツェンは引き続き『鐘』紙を媒体として、国民議会設立を求めるロシア社会のあらゆる階層との結束を促した。
しかし、1863年から1864年にかけての1月蜂起によって、ゲルツェンの結束力となる希望は打ち砕かれた。ポーランド人に対するツァーリの復讐を支持する自由主義派が、ゲルツェンとポーランド人の関係を断ち切ったのである。ゲルツェンは反乱軍の立場を擁護していた。この断絶により『鐘』の読者数は減少し、1867年に廃刊となった。1870年に亡くなるまでに、ゲルツェンはほとんど忘れ去られていた。
19世紀と20世紀への影響
「私がプロパガンダをしている作家が二人います。一人はゲルツェン、もう一人はシェストフです。二人とも本当に誠実で、心が広く、心の広い人間です。」
ゲルツェンは19世紀ロシアを支配した貴族制に反対し、農業集団主義的な社会構造モデルを支持した。[ 24 ] 1880年までにポピュリズムが台頭し、彼の著作は好意的に再評価されるようになった。ロシアでは、西洋特有の「進歩」の概念は、既存の体制に奉仕するために近代技術を取り入れることに基づく保守的な近代化の約束に取って代わられた。独裁政治に奉仕する近代化の約束はゲルツェンを怖れさせ、「電信を持ったチンギス・ハン」によって統治されるロシアを警告した。[ 25 ]
ポピュリズムと並んで、ゲルツェンはいかなる政治的信条の腐敗した政府も拒絶し、個人の権利を支持したことでも記憶されている。若い頃はヘーゲル主義者であったが、これは彼の思考を支配する特定の理論や単一の教義にはつながらなかった。 [ 26 ]ゲルツェンは、社会の複雑な問題には答えがなく、ロシア人は大義ではなく今を生きなければならないと信じるようになり、本質的に人生はそれ自体が目的である。ゲルツェンは極端に身を委ねず、むしろ競合するイデオロギーを平等に批判できるように公平に生きることで、より深い理解を見出しました。ゲルツェンは、壮大な教義は最終的に奴隷化、犠牲、専制につながると信じていました。
トルストイは、「これほど稀有な輝きと深みを兼ね備えた人物」に出会ったことがないと断言した。ゲルツェンは20世紀の哲学者イザヤ・バーリンの英雄であった。バーリンが最も執拗に繰り返したゲルツェンの言は、抽象概念の祭壇に人間を犠牲にすること、すなわち、現在の個人の幸福や不幸といった現実を未来の輝かしい夢に従属させることを非難する言葉であった。バーリンもゲルツェンと同様に、「人生の目的は人生そのもの」であり、それぞれの人生、それぞれの時代は、将来の目標のための手段ではなく、それ自体が目的であると考えるべきであると信じていた。バーリンはゲルツェンの自伝を「ロシアの文学的・心理的才能の偉大な記念碑の一つであり、ツルゲーネフやトルストイの偉大な小説に並ぶに値する」と評した[ 27 ] 。
ゲルツェンが登場するバーリンのエッセイ集『ロシアの思想家たち』(ホガース出版社、1978年)は、トム・ストッパードの戯曲三部作『ユートピアの海岸』のインスピレーションとなった。この戯曲は、2002年にロンドン国立劇場で、2006年から2007年にはニューヨークのリンカーンセンターで上演された。ロシア社会主義思想の初期の発展、1848年の革命、そしてその後の亡命生活を背景に、これらの戯曲は、無政府主義者のミハイル・バクーニン、文芸評論家のヴィサリオン・ベリンスキー、小説家のイワン・ツルゲーネフ、そして戯曲の主人公であるゲルツェンなど、 他のロシア人の人生と知的発展を描いている。
参照
注記
- ^ a bウィリアム・グライムズ (2007年2月25日). 「アレクサンダー・ヘルツェンの再発見」 .ニューヨーク・タイムズ.
- ^コンスタンス・ガーネット、アレクサンダー・ヘルツェン著『私の過去と思考』(バークレー:カリフォルニア大学出版局、1982年)、3、n1の注釈。
- ^シェッデン・ラルストン 1911年、402ページ。
- ^ a b c d eシェッデン・ラルストン 1911年、403ページ。
- ^フランスとイタリアからの手紙、1847–1851年
- ^ “ストロガノフ対ストロゴノフ論争” .
- ^ EH Carr, The Romantic Exiles (Harmondsworth, Penguin Books, 1949) p. 91.
- ^モス、ウォルター・G. (2002年3月1日). 『アレクサンドル2世、トルストイ、ドストエフスキーの時代のロシア』 . アンセム・プレス. 63ページ. ISBN 978-0-85728-763-2。
- ^ライアー、マーク(2006年)『バクーニン:創造の情熱』セブン・ストーリーズ・プレス、180頁。ISBN 978-1-58322-894-4。
- ^ “フランツ・メーリング: カール・マルクス (第 13 章 a)” . www.marxists.org。
- ^カー、1933年
- ^ウラジミール・K・カントル「ゲルツェンの悲劇、あるいは急進主義による誘惑」ロシア哲学研究51.3(2012年):40-57。
- ^ A. ヘルツェン、「終わりと始まり:I.S.ツルゲーネフへの手紙」(1862年)、アレクサンダー・ヘルツェンの回想録第4巻、チャットー・アンド・ウィンダス、ロンドン(1968年)、1683ページ。
- ^ a b c d上記の文の1つ以上には、現在パブリックドメインとなっている出版物からのテキストが含まれています: Shedden-Ralston, William Ralston (1911). " Hertzen, Alexander ". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica . Vol. 13 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 402– 403.
- ^ a b c d e f g h Alexander Herzen at Lib.ru
- ^ a b c「Selected Philosophical Works」外国語出版社. 1956年.
- ^ 「Selected Philosophical Works」外国語出版社. 1956年.
- ^パートリッジ、モニカ。「ヘルツェン、オガリョフとロンドンの自由ロシア報道機関」『アングロ・ソビエト・ジャーナル』1966年3月。
- ^ A. ヘルツェン「古い主題によるもう一つの変奏曲、Xへの手紙」(I.S. ツルゲーネフ、1857年)、アレクサンダー・ヘルツェンの回想録、第4巻、チャットーとウィンダス、ロンドン(1968年)、1561ページ。
- ^ケリー、「光り輝く足跡」:ヘルツェン、プルードン、そして知的革命家の役割、『近代知的歴史』(2005年)、2:179-205。
- ^ A. ヘルツェン「バザロフ、もう一度。手紙I」(1868年)、『アレクサンダー・ヘルツェンの回想録』第4巻、チャットーとウィンダス、ロンドン(1968年)、1753ページ。
- ^ D. オフォード『初期ロシア自由主義者の肖像』(1985年)ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ、p.200。
- ^ラミン・ジャハンベグルー『イザイア・バーリンとの対話』(ロンドン 2000年)、201~202ページ。
- ^ヴェンチュリ、F.『革命のルーツ:19世紀ロシアにおけるポピュリストと社会主義運動の歴史』(1960年)。ワイデンフェルド&ニコルソン。ロンドン。4頁。
- ^バートラム・D・ウルフ(2018年)『革命と現実』UNCプレスブックス、349ページ。ISBN 978-1-4696-5020-3。
- ^ I. バーリン『ロシアの思想家たち』(1979年)ホガース出版社ロンドンpp.191-192。
- ^ I. バーリン『ロシアの思想家たち』(1979年)ホガース出版社、ロンドン、209頁。
さらに読む
- アクトン、エドワード『アレクサンダー・ヘルツェンと知的革命家の役割』ケンブリッジ大学出版局、1979年。
- Carr, EH 『ロマンティックな亡命者たち: 19 世紀の肖像画ギャラリー』、Victor Gollancz、1933 年; Frederick A. Stokes Company、1933 年。
- コーツ、ルース。「バフチンとゲルツェンの初期の知的活動:行為の哲学に向けて」『東欧思想研究』第52巻第4号、2000年12月。
- エッカート、ユリウス『現代ロシア』スミス・エルダー社、1870年。
- ギャビン、WJ「ヘルツェンとジェームズ:急進派としての自由」ソビエト思想研究、第14巻、第3/4号、1974年9/12月。
- グレニエ、スヴェトラーナ。「ヘルツェンの『誰が責められるのか?新しい道徳のレトリック』」『スラヴ・東欧ジャーナル』第39巻第1号、1995年春。
- イスカンデル、ファシル。Alexandre Herzen (1812–1870): クールな生活、ヨーロッパのエスプリ、スイスの養子縁組。 『L'errance d'un temoin prophetique』、 Meandre Editions、フリブール、1997 年、ISBN 2-88359-017-6
- ケリー、アイリーン。「偶像の破壊:アレクサンダー・ヘルツェンとフランシス・ベーコン」『思想史ジャーナル』第41巻第4号、1980年10/12月号。
- ケリー、アイリーン・M. 『偶然の発見:アレクサンダー・ヘルツェンの生涯と思想』ハーバード大学出版局、2016年、ISBN 978-0-674-73711-2。
- マリア、マーティン・エドワード『アレクサンダー・ゲルツェンとロシア社会主義の誕生』グロスセット&ダンラップ、1965年。
- モーソン、ゲイリー・ソール。「ヘルツェン:懐疑的理想主義の英雄」(アイリーン・M・ケリー著『偶然の発見:アレクサンダー・ヘルツェンの生涯と思想』(ハーバード大学出版、592ページ、39.95ドル)の書評)、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、第63巻、第18号(2016年11月24日)、45~46ページ、48ページ。
- Orlova-Kopeleva、Raisa : Als die Glocke verstummte。 Alexander Herzens letztes Lebensjahr、 Karin Kramer Verlag、ベルリン、1988、ISBN 3-87956-190-7
- パルミエリ、F. アウレリオ。「ロシア革命の初期の理論家たち」『カトリック・ワールド』第53巻、1918年10月/1919年3月。
- パートリッジ、モニカ。「アレクサンダー・ヘルツェンとイギリスの報道機関」『スラヴと東ヨーロッパ評論』第36巻第87号、1958年6月。
- パートリッジ、モニカ (1984年1月1日).アレクサンダー・ヘルツェン: 1812-1870 (『アレクサンダー・ヘルツェン:研究集成』) . ユネスコ, 国際連合教育科学文化機関. ISBN 978-92-3-102255-5。
- ニコラス・ルジェフスキー「混沌の形:ゲルツェンと戦争と平和」『ロシア評論』第34巻第4号、1975年10月。
- スミス=ピーター、スーザン『ロシアの地域を想像する:19世紀ロシアにおけるサブナショナル・アイデンティティと市民社会』ブリル社、2018年。
- ワイデマイヤー、ウィリアム・キャノン。「ヘルツェンとニーチェ:近代ペシミズムの台頭における一環」『ロシアン・レビュー』第36巻第4号、1977年10月。
- A. アンドレーエフ、D. ツィガンコフ編 (2010). 『帝国モスクワ大学:1755–1917:百科事典』 モスクワ:ロシア政治百科事典(ROSSPEN). pp. 153– 155. ISBN 978-5-8243-1429-8。
