トールキンの伝説の宇宙論
J. R. R. トールキンの伝説における 架空の宇宙論は、キリスト教神学と形而上学の側面と、地球平面説の近代以前の宇宙論的概念、および太陽系の球体地球観を組み合わせたものである。
創造された世界エアには、地球に相当する惑星アルダが含まれる。それは平らに創造され、その中心に神のようなヴァラールの住居がある。これが邪悪なヴァラー・メルコールによって損なわれると、世界は完全な対称性を失い形を変え、ヴァラールはヴァリノールへと移動するが、エルフは依然として中つ国からそこへ航海することができる。人間が不死を願ってそこに行こうとすると、ヴァリノールとその大陸アマンはアルダから取り除かれ、アルダは丸い世界に形を変えられる。学者たちは、暗示される宇宙観をトールキンの宗教、カトリック、そしてパールやダンテの『天国篇』などの中世の詩の宇宙観と比較している。中世の詩では、地球、煉獄または地上の楽園、天国または天上の楽園の3つの部分がある。学者たちは中つ国における悪の本質について議論し、それが善の不在なのか(ボエティウス派の立場)それとも善と同等に強力なのか(マニ教の見解)を主張してきた。
オントロジー
創造と破壊
エルは『シルマリルの物語』において、宇宙の最高神であり、世界アルダとその中心大陸である中つ国を含む万物の創造主として登場する。トールキンが創作したエルフ語クウェンヤにおいて、エルは「唯一者」あるいは「孤独なる者」を意味し、イルーヴァタールは「全父」を意味する。[ T 1 ] エルはまず、強力なヴァラールとその助手であるマイアールからなる、神のような、あるいは天使のような存在であるアイヌルを創造した。彼らはアイヌリンダレ(「アイヌルの音楽」)と呼ばれる聖なる音楽と詠唱を通して、宇宙の創造を助けた。 [ T 2 ]
トールキンは、「不滅の炎」あるいは「秘密の火」はキリスト教神学における聖霊を表していると述べた。 [ 1 ]エルの創造活動は、エル自身とその創造物から切り離すことのできないものである。クリストファー・トールキンの解釈では、それは「作者の神秘」を表し、作者は作品の外に立つと同時に作品の中にも宿っている。[ 2 ]第一紀において、エルはエルフと人間、すなわち「イルーヴァタールの子ら」を創造した。[ T 4 ]ドワーフの種族は、強力なヴァラであるアウレによって創造され、エルによって知性を与えられた。[ T 5 ]動物と植物は、エルが定めた主題に従って、アイヌールの音楽の間にヤヴァンナによって形作られた。 [ T 4 ]
『アルダ』は終末的なダゴール・ダゴラスの戦いで終わるが、トールキンはこの戦いは北欧神話のラグナロクに負っていると述べた。[ T6 ]
エルの直接介入
第二紀、エルはヌーメノールの王アル=ファラゾーンとその軍勢がアマンに侵攻し、不死の地に到達しようとした際に、彼らを埋葬した。彼らは不死の地が彼らに不死をもたらすと誤解していた。エルは大地を球形にし、ヌーメノールを水没させ、不死の地を「大地の圏外」へと連れ去った。[ 3 ]『旅の仲間』でガンダルフがバルログとの戦いで死んだ とき、ヴァラールの力では彼を蘇らせることは不可能だった。エル自身が介入し、ガンダルフを送り返した。[ T 7 ]
トールキンは『王の帰還』でフロドが指輪を破壊できなかったことについて論じている手紙の中で、「唯一者」が世界に積極的に介入していることを示唆しており、ガンダルフがフロドに「指輪を見つけるのはビルボの運命であり、指輪の製作者によるものではない」と述べたこと、そしてフロドがその任務を遂行できなかったにもかかわらず指輪が最終的に破壊されたことを指摘している。[ T 8 ]
フェアとフロア
フェアとフロアは、エルフと人間の「魂」と「体」である。[ 2 ]フロアはアルダの物質から作られる。このためフロアは傷つけられ、トールキンが書いたように「メルコールの成分」を含む。[ T 9 ]エルフが死ぬと、フェアはフロアを離れ、フロアも死ぬ。フェアはヴァリノールにあるマンドスの館に召喚され、そこで裁かれる。しかし、死の場合と同様に、フェアの自由意志は奪われず、召喚を拒否することもできる。[ T 10 ]マンドスに許可された場合、フェアは以前のフロアと同一の新たな体に再具現化されることがある。人間の状況は異なる。人間のフェアはアルダへの訪問者に過ぎず、フロアが死ぬと、フェアはマンドスに短期間滞在した後、アルダを完全に去る。[ 2 ]
見えない世界
『指輪物語』において、トールキンは指輪の本質を正当化するために、中つ国のエルフやその他の不死の存在は「両世界」(物質界と精神界、すなわち見えざる世界)に同時に存在し、特に太陽や月が存在する以前にヴァリノールの二本の樹の光の中に住んでいた者たちは、両世界において強大な力を持っていると説明しています。「魔法」に関連する力は、本質的に霊的なものでした。[ T 11 ] [ T 12 ]
かつてメルコールが支配していた中つ国に留まったエルフたちは、肉体を持ち、メルコールの影響によって傷つき朽ちゆくものに囲まれていた。彼らは、物質世界を変わらぬままに保とうという願いから、エルフの指輪を創造した。まるでヴァラールの故郷である不死の地ヴァリノールにいるかのように。指輪がなければ、彼らはやがて「消え去り」、物質世界の影と化してしまう運命にある。これは、ヨーロッパの歴史的な神話において、エルフが別世界の、しばしば地下(あるいは海底)の次元に居住するという概念を予兆している。[ T 12 ]
力の指輪を身に着けた人間は、指輪が不自然なほど寿命を維持し、霊魂へと変貌するため、より急速に「衰退」する運命にある。この副作用として、着用者は一時的に霊界へと引き込まれ、透明人間になる。[ T 13 ] [ T 14 ]
人間、エルフ、そして楽園
人間は世界(アルダ)にのみ生き、そこで死ぬこともあり、魂を持ち、最終的には一種の天国に行くかもしれないが、この点は伝説の中では曖昧にされている。エルフの場合は異なる。彼らはヴァラールの故郷である「不死の地」ヴァリノールに住んでいるかもしれない。トールキン研究者トム・シッピーによれば、それは事実上、中英語(南英語)の伝説におけるエルフの「地上の楽園」である。他のエルフは中つ国に生息している。エルフの女王ガラドリエルは確かにヴァリノールから追放されているが、堕落したメルコールとよく似ている。しかし、彼女は明らかに善良で、天使のような存在である。シッピーはエルフに魂があるかどうかについて考察する。エルフは世界から離れることができないため、答えはノーであるに違いないと彼は考える。しかし、死後完全に消滅するわけではないことを考えると、答えはイエスであるに違いない。シッピーの見解では、『シルマリルの物語』はエルフを天国ではなくヴァリノールのマンドス館という中間地点に送ることで謎を解く。[ 4 ]オークのような、一見完全に邪悪な存在の場合、再び問題が生じる。悪は人を欺くことはできず、嘲笑することしかできないため、オークは人間と同等で正反対の道徳観を持つことはできない。しかし、オークは言葉を話し、道徳観念を持っている(ただし、それに従うことはできない)ため、完全に邪悪でもなければ知覚力も欠いているわけではない。[ 5 ] [ 6 ]様々な学者が指摘しているように、これらすべては中世の存在の大いなる連鎖に匹敵する種族の階層構造を暗示している。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
| トールキン | カトリック / 中世世界 |
|---|---|
| 創造主エル | 神 |
| ヴァラール、不死、創造に参加する | 天使(または北欧の神々 ) |
| 堕落したヴァラ、メルコール | 堕天使、サタン |
| エルフ(「機能的に不死」[ 7 ]) | |
| 男性(人間) | 男たち(魂を持つ) |
| オーク(悪)?[ 5 ] | |
| 獣たち | 動物(魂がない) |
多くの学者はトールキンの伝説に暗示されている宇宙観を、彼の宗教であるローマカトリックや中世の詩の宇宙観に例えています。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
| トールキン | カトリック | パール、ダンテの天国篇 |
|---|---|---|
| 「エルフの故郷を超えた、そして永遠に存在するもの」[ T 15 ] | 天国 | 天上の楽園、「その先」 |
| アマンの不死の地、ヴァリノールのエルフの故郷 | 煉獄 | 地上の楽園、エデンの園 |
| 中つ国 | 地球 | 地球 |
中つ国の悪
トールキンは『シルマリルの物語』の最初の部分であるアイヌリンダレ、すなわち創造物語を用いて、架空世界における悪の起源についての考えを述べた。彼は書簡の中で述べているように、この主題に関する自身の信念とこの考えを一致させるよう苦心した。アイヌリンダレ では、悪はエルーによって開始された創造過程に対する反逆を表している。悪はその最初の行為者であるメルコールによって定義されている。メルコールはルシファー的存在であり、エルーに対する積極的な反逆の中で、自分自身のものを創造し支配したいという欲望から堕落した。[ T 2 ]メルコールはエルフを嘲笑してオークを創造するか、中つ国の北部にあるウドゥンの要塞で捕らえたエルフを堕落させることによってオークを創造する。[ T 16 ]
シッピーは、トールキンの中つ国に関する著作は、悪の本質に関する古代キリスト教の議論を体現していると述べている。シッピーは、エルロンドのボエティウス的な発言「初めに悪というものは何もなかった。[闇の王]サウロンでさえそうではなかった」[ T 17 ]に注目している。言い換えれば、万物は善として創造されたのだが、これは善と悪は同等の力を持ち、世界で互いに戦うというマニ教的な見解と対比される。 [ 13 ]トールキンの個人的な戦争体験はマニ教的であった。悪は少なくとも善と同等の力を持ち、容易に勝利を収めることができたように見え、シッピーは、この傾向が中つ国にも見られると指摘している。[ 14 ]人文科学学者のブライアン・ローズベリーは、エルロンドの発言はアウグスティヌス的な宇宙、つまり善が創造されたことを示唆していると解釈している。[ 15 ]
物理宇宙
地球平面説
- トールキンが描いた虚空、クーマの中のアルダの概念の 1 つを描いたスケッチ。太陽と月が創造される前の、平らな地球、アンバール、大気、ヴィスタ、星空、イルメンの周囲を取り囲む海、エカイアが描かれています。
- ランプの年における平らな円盤としてのアルダ
エア(Eä)、「存在するもの」は、アイヌルのビジョンが実現した物質宇宙である。クウェンヤ語は、実存的な「 〜である」のアオリスト形に由来する。エアは、エル・イルーヴァタールが宇宙を現実化するために発した言葉である。[ T 2 ]
虚空(クーマ、外なる闇)はアルダの外にある虚無である。アルダからは夜の扉を通ってそこへ入ることができる。ヴァラールは怒りの戦争で敗北したメルコールを虚空へと追放した。伝説によれば、メルコールはダゴル・ダゴラスとの終末的な戦いの直前にアルダに帰還する。虚空は、エア創造以前の無の状態と混同してはならない。[ T 18 ]
アルダ(地球)が創造されたとき、すでに「無数の星」が存在していました。[ T 2 ]ヴァラールは後に、より豊かな光を提供するために中つ国に二つのランプを創造しました。そして、これらが破壊されると、ヴァリノールに二本の樹木を創造しました。これらはランプの時代と樹木の時代をもたらしましたが、星の時代は太陽と月が創造されるまで終結しませんでした。[ T 19 ]エルフの覚醒の直前、樹木の時代に、ヴァルダは「新しくより明るい」星々、そして星座である大いなる星々を創造しました。[ T 16 ]
イルヴァタールは地球平面説に基づいてアルダを創造した。この円盤状のアルダには大陸と海があり、月と星々が周囲を回っている。アルダはエルフと人間のための「住居」(アンバール)となるために創造された。[ 16 ]この世界はヴァラールによって創造された2つのランプ、イルイン(「空色」)とオルマル(「高貴な金色」)によって照らされていた。ランプを支えるため、アウレは2つの巨大な岩の柱を鍛えた。中つ国大陸の北にヘルカール、南にリンギルである。イルインはヘルカールの上に、オルマルはリンギルの上に置かれた。ランプの光が混ざり合う柱の間に、ヴァラールは大湖の真ん中にあるアルマレン島に住んでいた。 [ T 4 ]メルコールがランプを破壊したとき、2つの広大な内海(ヘルカールとリンギル)と2つの主要な海(ベレガエルと東の海)が形成されましたが、アルマレンとその湖は破壊されました。[ T 16 ]ヴァラールは中つ国を去り、西に新しく形成されたアマン大陸に行き、そこにヴァリノールと呼ばれる故郷を築きました。メルコールがアマンを攻撃するのを阻止するために、彼らは中つ国の大陸を東に押し出し、ベレガエルの中央部を広げ、中つ国に5つの主要な山脈、青、赤、灰色、黄の山脈と風の山脈を隆起させました。この行為により、大陸と海の対称的な形状が崩れました。[ T 20 ]
エカイアは、包み込む大海や取り囲む海とも呼ばれ、第二紀末の大変動以前、世界を囲んでいた暗い海である。この地球が平面であった時代には、エカイアはアルダの周囲を完全に流れ、アルダは海上の船のようにエカイアの上に浮かんでいた。エカイアの上には大気の層がある。水の王ウルモはアルダの下にあるエカイアに住んでいた。エカイアは非常に寒く、その水が中つ国の北西にあるベレガエルの海と出会うところに、ヘルカラクセと呼ばれる氷の裂け目ができた。エカイアはウルモの船以外の船を支えることができない。太陽は世界を一周する途中でエカイアを通過し、通過する際にエカイアを温める。[ T 4 ] [ T 21 ]
イルメニは、第二紀末の大変動以前、光に満ちた清浄な空気の領域であった。星々やその他の天体はこの地域に存在する。月は地球を一周する途中でイルメニを通過し、帰還時にイルメニの裂け目に落ち込む。[ T 21 ]
球状地球宇宙論
トールキンの伝説は、球体地球というパラダイムを、平面世界から球体世界への破滅的な移行を描くことで表現している。この移行において、ヴァリノール大陸が位置するアマン大陸は「世界の円から」排除された。[ 3 ]アマンへ到達するために残された唯一の道は、いわゆる「古き一直線の道」であった。これは中つ国の曲面から空と宇宙を抜ける隠された道であり、エルフだけが知る唯一の道であり、彼らは船で航行することができた。[ 3 ]
平面の地球から球体へと変容したこの現象は、トールキンの「アトランティス」伝説の中心を成す。ヌーメノール人は傲慢さを増し、ヴァリノール島に到達すれば不死が得られると信じて到達しようとしたが、エルフは彼らの島を破壊し、人間が到達できないように世界を作り変えた。トールキンの未完の『失われた道』は、第一紀のエルフ神話と古典アトランティス神話、ゲルマン民族の移動、アングロサクソン時代のイングランド、そして近代を繋ぐ歴史的連続性の概念を示唆し、プラトンのアトランティス伝説やその他の大洪水神話をヌーメノール物語の「混乱した」記述として提示している。この世界の大変動は、人類の文化的記憶と集合的無意識、そして個人の遺伝的記憶にさえも痕跡を残したであろう。伝説の「アトランティス」の部分は、西へと続く「一直線の道」の記憶というテーマを探求しているが、物理的な世界が変化したため、この記憶は今では記憶や神話の中にしか存在しない。[ T 22 ] [ 3 ]アカラベスによれば、大災害を生き延びたヌーメノール人は、古代の故郷を求めて可能な限り西へと航海したが、彼らの旅は世界を一周して出発点に戻るだけだった。[ T 23 ]
『指輪物語』出版の数年後、トールキンは「アトラベス・フィンロド、そしてアンドレ」という物語に関連した注釈の中で、アルダを太陽系と同一視した。なぜなら、この時点でアルダは複数の天体から構成されており、ヴァリノールも別の惑星にあり、太陽と月はそれぞれ独立した天体であったからである。[ 19 ]
惑星と星座
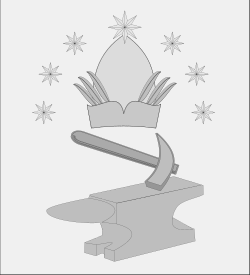
トールキンはクェンヤ語辞典と呼ばれる名前と意味のリストを作成した。クリストファー・トールキンは、特定の恒星、惑星、星座への言及とともに、この語の抜粋を『失われた物語の書』の付録に収録した。 [ 21 ] [ 22 ]太陽はアノールまたはウルと呼ばれていた。[ T 24 ] [ T 25 ]月はイシルまたはシルモと呼ばれていた。[ T 26 ] [ T 27 ]エアレンディルの星は、エアレンディルの船ヴィンギロットが空を飛ぶときにその船に搭載されていたシルマリルの光を表し、金星であると特定されている。古英語の詩『キリスト1世』で英語で使用されている「earendel」は、19世紀の文献学者によって何らかの明るい星であることが発見され、1914年からトールキンはこれを明けの明星を意味するものと解釈した。トールキンは晩年の1967年になっても、まだそう考えていた。[ T 28 ] 「エアレンデルよ、最も光り輝く天使たちよ」という一節がトールキンの着想の源であった。 [ 18 ]トールキンは、モルゴスの指輪に記録されているように、太陽系の他の惑星にシンダール語の名前を作ったが、他の場所では使用しなかった。木星はシリンド、火星はカルニル、水星はエレミール、天王星はルイニル、土星はルンバー、海王星はネナーであった。[ T 29 ]『失われた物語』には木星の名前としてモルウェンが記載されている。[ T 30 ]
いくつかの星は、トールキン、その息子クリストファー、あるいは学者によって、実在の星の名前として特定されている。トールキンは『指輪物語』の「三人寄れば文殊の知恵」の中で、ボルギルはレミラス(プレアデス)とメネルヴァゴール(オリオン)の間に現れる赤い星であると述べている。ラーセンらは、この説明に合致する主要な赤い星はアルデバランのみであると記している。 [ 23 ] [ 20 ]ヘルイン(ギル、ニールイン、ニールニンワとも呼ばれる)は犬の星シリウスであり、モルウィニヨンはアークトゥルスである。[ 20 ]
惑星と同様に、いくつかの主要な星座は伝説の中で名前が付けられており、北半球で見られる実際の星座と同一視することができます。エクシキルタ(エクタとも)はオリオン座のベルトです。[ T 26 ]メネルヴァゴール(ダイモルド、メネルマカール、モルド、天空の剣士、タイマヴァル、タイモンド、テリンベクター、テリメクター、テルメフタルとも)は狩人オリオンであり[ 20 ] 、トゥーリン・トゥランバーを表すことを意図していました。レミラト(イツェロクテまたはシサロスとも)、「網の目模様の星」はプレアデス星団または七姉妹です。[ 20 ]ヴァラキルカ(ヴァラールの鎌)[ T 31 ]は、大熊座(鋤または北斗七星)[ 20 ]であり、ヴァルダはこれをメルコールへの警告として北の空に立てた。ウィルワリン(蝶)はカシオペア座とされている。[ 20 ]
分析
神学的な根拠
英文学者のサム・マクブライドは、2020年に出版した著書『トールキンの宇宙論』の中で、トールキンの宇宙論の神学的基盤として、ヴァラール、マイアール、トム・ボンバディルのような存在を含む多神教のパンテオンと、一神エル・イルヴァタールによって創造された明らかに一神教的な宇宙を融合させた「一神教的多神教」という新たなカテゴリーを提唱している。 [ 24 ]マクブライドの見解では、ヴァラールは「霊的存在にも地の力にも還元できず、両方を同時に包含している」。[ 25 ]マクブライドは、エルの行動が世界(エア)と彼が行動するヴァラールの創造においてどのように見られるか、そして神の意志がせいぜいほのめかされるだけの第三紀においてより曖昧に見られるかを示している。[ 26 ]
神学者キャサリン・マドセンは、トールキンが『シルマリルの物語』の多くの草稿と改訂版を『指輪物語』と一致させることは不可能だと考え、死去時に未刊行のまま残したと書いている。その宇宙観は垣間見え、エアレンディルの物語が語られ、それがフロドとサムがエアレンディルの星の光の一部を宿すガラドリエルの小瓶を使う背景になっていると彼女は指摘している。対照的に、アイヌリンダレの創世神話は『指輪物語』では触れられていないが、彼女は触れられていた可能性もあると指摘している。『ベオウルフ』は、吟遊詩人が語る創世物語という形で、トールキンに馴染みのある適切なモデルを提供したのである。『指輪物語』がホビット族の視点で語られることで、宇宙観がさらに背景に押しやられるとマドセンは書いている。ホビット族はヴァラールについて人間よりもさらに知らず、エルー族については全く触れられていない。[ 27 ]
世界一周バージョン
学者たちは、トールキンが晩年、アルダの地球平面説から遠ざかり、球体説を支持したようだが、その説は伝説全体に深く根付いていたため、ディアドラ・ドーソンが『トールキン研究』で「より合理的で科学的に妥当な地球の形」と呼ぶものに作り直すことは不可能であることが判明したと指摘している。[ 27 ] [ 28 ]
トールキン学者のジャネット・ブレナン・クロフトは『神話』の中で、中つ国、ホビット族、人間、エルフ、ドワーフといった種族は皆、「善と悪の間に文字通りの宇宙的戦いがある」と信じており、「最終的な破滅的な戦い」を予期していると述べています。読者はアイヌリンダレを比喩的に解釈することも考えられます。例えば、メルコールがアルダを滅ぼそうとする試みは、「谷を隆起させ、山を崩し、海をこぼす」という地質学的力の象徴的な表現として解釈できるかもしれませんが、本文にはそのような示唆は一切ありません。[ 29 ]
参照
参考文献
主要な
- ^トールキン 1977、329、336、356、358 ページ
- ^ a b c dトールキン 1977、アイヌリンダレ
- ^トールキン 1954a第2巻第5章「カザド・ドゥームの橋」
- ^ a b c dトールキン 1977年、第1章「日々の始まり」
- ^トールキン 1977年、第2章「アウレとヤヴァンナについて」
- ^カーペンター2023、#131ミルトン・ウォルドマン宛、1951年後半
- ^カーペンター 2023、#156、 R. マレー SJ宛、1954年11月
- ^カーペンター2023、#192 エイミー・ロナルド宛、1956年12月
- ^トールキン 1993、400ページ
- ^トールキン 1993、339ページ
- ^トールキン 1954a第2巻、第1章「幾多の出会い」。「あなたは一瞬、彼が向こう側にいるのを見た。[...]聖なる領域に住んだ者たちは両方の世界に同時に生きており、見えるものと見えないものの両方に対して強大な力を持っている。」
- ^ a bトールキン 1954a第2巻 第7章「ガラドリエルの鏡」。「しかし、もし汝が成功すれば、我々の力は衰え、ロスリアンは衰退し、時の波に飲み込まれるだろう。我々は西へと去るか、谷や洞窟に住む田舎の民へと衰退し、ゆっくりと忘れ去られ、そして忘れ去られるかのどちらかだ。」
- ^トールキン 1954a第1巻第2章「過去の影」。「もし[人間が]指輪を使って姿を消すことを繰り返すと、彼は消え去ります。そして最終的には永久に姿を消し、指輪を支配する闇の力の監視下で薄明かりの中を歩くことになります。」
- ^トールキン 1954a第2巻 第1章「幾多の出会い」。「指輪をはめていた間、あなたは最も深刻な危機に瀕していました。なぜなら、あなた自身も半分は亡霊の世界にいたからです。」
- ^トールキン 1955年、第6巻第4章「コーマレンの野」
- ^ a b cトールキン 1977年、第3章「エルフの到来とメルコールの捕虜について」
- ^トールキン 1954a、第2巻第2章「エルロンドの評議会」
- ^トールキン 1993、「神話の変容」、第7章
- ^トールキン 1977年、第13章「ノルドールの帰還」
- ^トールキン 1977年、第11章「太陽と月とヴァリノールの隠れ家」
- ^ a bトールキン 1977年、第11章「太陽と月とヴァリノールの隠れ家」
- ^ a b「実際には、この物語の想像の中では、私たちは物理的に丸い地球に住んでいます。しかし、この『伝説』全体は、平らな世界から球体の世界への移行を含んでいます...」カーペンター2023、#154、ナオミ・ミッチソン宛、1954年9月25日
- ^トールキン 1977年、アカラベス
- ^トールキン 1984年、「ヴァラールの到来」
- ^トールキン 1955トールキンは索引 IV でアノールとドゥリンの王冠 (「星」の下) を定義し、付録 EI でメネルヴァゴールとイシルをそれぞれ「H」と「TH」の子音の項目で定義しています。
- ^ a b「Qenya Lexicon」。パルマ・エルダランベロン。12 。これには、『失われた物語の書』の付録の 35、43、63、82 ページから省略された星の名前が含まれます。
- ^トールキン 1955付録 E. I, TH
- ^トールキン 1984b、266ページ
- ^トールキン 1993、索引
- ^トールキン 1984、付録「モーニー」
- ^トールキン 1977年、『エルフの到来』(『ドゥリンの冠』『燃える茨』『エデギル』『オツェレン』『七つの星』『七つの蝶』『銀の鎌』『ティンブリジル』も)
二次
- ^キルビー、クライド・S・トールキンとシルマリルの物語。ハロルド・ショー、1976年、59ページ。「トールキンは1966年夏、クライド・キルビーに対し、これが聖霊であると認めた。三位一体の第二位格であるロゴスの性質は、『アトラベス・フィンロド・ア・アンドレト』という物語の中で抽象的にのみ現れ、受肉を予期している。『彼らは、その者がアルダに入り、人々とすべての傷を最初から最後まで癒すと言っている』」。ブラッドリー・J・バーザー、「エル」、マイケル・D・ドラウト編『JRRトールキン百科事典』、2007年、171ページ。
- ^ a b cディッカーソン、マシュー(2013). 「中つ国のホラとフェア:健康、生態、そして戦争」. クリストファー・ヴァッカロ編. 『トールキンの伝説における身体:中つ国の肉体に関するエッセイ』 .マクファーランド・アンド・カンパニー. pp. 64– 82.
- ^ a b c d eシッピー 2005年、324~328頁、「失われた直線道路」
- ^シッピー 2005、270–273頁。
- ^ a bタリー、ロバート・T・ジュニア(2010). 「Let Us Now Praise Famous Orcs: Simple Humanity in Tolkien's Inhuman Creatures」『ミスロア』29 (1). 記事3. 2022年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月17日閲覧。
- ^ Shippey 2005、362、438頁(第5章、注14)。
- ^ a b c Chandler, Wayne A.; Fry, Carrol L. (2017). 「トールキンの暗示的な背景:不死性とファンタジーの枠組みへの信仰」『ミスロア』35 (2). 記事7. 2022年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月16日閲覧。
- ^ a bスチュアート、ロバート (2022). 「トールキン、人種、そして批評家たち:中つ国における人種差別をめぐる議論」.トールキン、人種、そして中つ国における人種差別. シャム、スイス:パルグレイブ・マクミラン. p. 46. doi : 10.1007/978-3-030-97475-6 . ISBN 978-3-030-97475-6. OCLC 1312274691 . S2CID 248207455 . 2022年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月16日閲覧。
- ^タリー、RTジュニア(2022年)「より危険で、より賢くない:人種、階級、そして地政学的秩序」J・R・R・トールキン著『ホビットの冒険』. パルグレイブSF&ファンタジー:新たなる正典.パルグレイブ・マクミラン. pp. 65– 84. doi : 10.1007/978-3-031-11266-9_5 . ISBN 978-3031112669。
- ^ a b Drout, Michael DC (2007). 「エルダマー」. Drout, Michael DC (編). JRRトールキン百科事典. CRC Press . p. 145. ISBN 978-0-415-96942-0。
- ^ a bケリー、A. キース;リビングストン、マイケル(2009)。「遥かなる緑の国:トールキン、楽園、そして中世文学における万物の終焉」『ミスロア』27(3)。
- ^ a bディッカーソン, マシュー・T. (2007). 「楽園」.マイケル・D・ドラウト編. JRRトールキン百科事典. CRC Press . pp. 502– 503. ISBN 978-0-415-96942-0。
- ^シッピー 2005、160~161頁。
- ^シッピー 2005、169~170頁。
- ^ローズベリー、ブライアン(2003). 『トールキン:文化現象』パルグレイブpp. 35– 41. ISBN 978-1403-91263-3。
- ^ボリンティニアヌ、アレクサンドラ (2013)。 「アルダ」。ドラウト著、マイケル DC (編)。JRR トールキン百科事典。ラウトレッジ。24 ~ 25ページ 。ISBN 978-0-415-86511-1。
- ^コッチャー、ポール(1974) [1972]. 『中つ国の覇者:J・R・R・トールキンの功績』ペンギンブックスpp. 8– 11. ISBN 0140038779。
- ^ a bリー、スチュアート・D. ;ソロポヴァ、エリザベス(2005). 『中つ国の鍵:J・R・R・トールキンの小説を通して中世文学を発見する』パルグレイブpp . 256– 257. ISBN 978-1403946713。
- ^ラーセン、クリスティン (2008). サラ・ウェルズ編. 「彼自身の小さな地球:トールキンの月の創造神話」. 『指輪物語:トールキン2005年会議録』 . 2.トールキン協会: 394–403 .
- ^ a b c d e f gマニング、ジム; テイラー・プラネタリウム (2003). 「エルフの星の伝承」(PDF) . The Planetarian (14). 2016年12月20日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ラーセン、クリスティン (2011). 「海鳥と明けの明星:ケイクス、アルキュオネー、そしてエアレンディルとエルウィングの数々の変身」フィッシャー、ジェイソン編『トールキンとその資料研究:批評論文集』マクファーランド出版、 69~ 83頁 。インデックス エントリは、Gong、Ingil、Mornië、Morwinyon、Nieluin、Silindrin、および Telimektar です。
- ^ Larsen, Kristine (2014). Swank, Kris (ed.). Red Comets and Red Stars: Tolkien, Martin, and the Use of Astronomy in Fantasy Series (PDF) . Proceedings of the 2nd Mythgard Institute Mythmoot. Vol. 2. Mythgard Institute . 2015年3月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ラーセン、クリスティン (2005). 「トールキンの『ボルギル』の決定的な同定:天文学的・文学的アプローチ」トールキン研究. 2 : 161–170 . doi : 10.1353/tks.2005.0023 . S2CID 170378050 .
- ^マクブライド 2020、14頁。
- ^マクブライド 2020、35ページ。
- ^ Dickerson, Matthew (2020). 「[書評] サム・マクブライド著『トールキンの宇宙論:神々と中つ国』(2020年) . Journal of Tolkien Research . 11 (1). Article 5. 2021年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月23日閲覧。マクブライド2020のレビュー
- ^ a bマドセン、キャサリン (2010). 「エル・イレイスド:指輪物語のミニマリスト的宇宙論」ポール・E・ケリー編. 『指輪と十字架:キリスト教と指輪物語』フェアリー・ディキンソン大学出版局. pp. 152– 169. ISBN 978-1-61147-065-9. 2024年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月16日閲覧。
- ^ドーソン、デイドレ・A. (2008). 「トールキン神話の進化:中つ国の歴史研究(レビュー)」.トールキン研究. 5 (1): 205– 209. doi : 10.1353/tks.0.0028 . ISSN 1547-3163 . S2CID 170596445 .
- ^クロフト、ジャネット・ブレナン(2010). 「運命を握る糸:トールキンの中つ国における自由意志、不服従、そしてユーカタストロフィー」『ミスロア』29 ( 1 ). 第9条. 2021年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月23日閲覧。
出典
- カーペンター、ハンフリー編 (2023) [1981]. 『J・R・R・トールキン書簡集:改訂増補版』 ニューヨーク:ハーパーコリンズ. ISBN 978-0-35-865298-4。
- マクブライド、サム(2020年)『トールキンの宇宙論:神々と中つ国』ケント、オハイオ州:ケント州立大学出版局。ISBN 978-1-60635-396-7. OCLC 1121602421 .
- シッピー、トム(2005) [1982]. 『中つ国への道:J・R・R・トールキンはいかにして新たな神話を創造したか』(第3版).ハーパーコリンズ. ISBN 978-0-261-10275-0。
- トールキン, JRR (1954a). 『指輪物語』 .ボストン:ホートン・ミフリン. OCLC 9552942 .
- トールキン, JRR (1955). 『王の帰還』 . 『指輪物語』 . ボストン:ホートン・ミフリン. OCLC 519647821 .
- トールキン, JRR (1977).クリストファー・トールキン編. 『シルマリルの物語』 . ボストン:ホートン・ミフリン. ISBN 978-0-395-25730-2。
- トールキン, JRR (1993).クリストファー・トールキン編. 『モルゴスの指輪』 . ボストン:ホートン・ミフリン. ISBN 0-395-68092-1。
- トールキン, JRR (1984).クリストファー・トールキン編. 『失われた物語集』第1巻. ボストン:ホートン・ミフリン. ISBN 0-395-35439-0。
- トールキン, JRR (1984b).クリストファー・トールキン編. 『失われた物語集』第2巻. ボストン:ホートン・ミフリン. ISBN 0-395-36614-3。




