ロシア皇帝アレクサンドル1世
| アレクサンドル1世 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
-crop.jpg/440px-Alexander_I_of_Russia_by_G.Dawe_(1826,_Peterhof)-crop.jpg) ジョージ・ドーによる肖像画、 1825~29年頃 | |||||
| ロシア皇帝 | |||||
| 治世 | 1801年3月23日 – 1825年12月1日 | ||||
| 戴冠式 | 1801年9月15日 | ||||
| 前任者 | パウロ1世 | ||||
| 後継 | ニコライ1世 | ||||
| 生まれる | (1777年12月23日)1777年12月23日ロシア、サンクトペテルブルク、冬宮殿 | ||||
| 死亡 | 1825年12月1日(1825年12月1日)(47歳)[ 1 ]アレクサンドル1世宮殿、タガンログ、ロシア | ||||
| 埋葬 | 1826年3月13日 | ||||
| 配偶者 | |||||
| さらに問題... | マリア大公妃エリザベート・ニコライ・ルカシュ大公妃(非嫡出子) | ||||
| |||||
| 家 | ホルシュタイン=ゴットルプ=ロマノフ | ||||
| 父親 | ロシア皇帝パーヴェル1世 | ||||
| 母親 | ゾフィー・ドロテア・フォン・ヴュルテンベルク | ||||
| 宗教 | ロシア正教会 | ||||
| サイン | 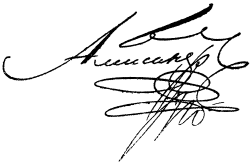 | ||||
| 兵役 | |||||
| 支店/サービス | ロシア帝国軍 | ||||
| 戦闘/戦争 | |||||
アレクサンドル1世(ロシア語:Александр I Павлович、ローマ字: Aleksandr I Pavlovich、IPA:[ɐlʲɪkˈsandr ˈpavləvʲɪtɕ]、1777年12月23日[旧暦12月12日] - 1825年12月1日[旧暦11月19日])[ a ] [ 2 ] 、 「祝福された」という愛称で呼ばれ、[ b ] 1801年からロシア皇帝、 1815年からポーランド議会の初代国王、1809年から1825年に死去するまでフィンランド大公であった。彼はナポレオン戦争の混乱期にロシアを統治した。
アレクサンドルは、パーヴェル1世とヴュルテンベルクのゾフィー・ドロテアの長男として、父の暗殺後に帝位を継承した。公子として、また治世の初期には、しばしば自由主義的なレトリックを用いたが、実際にはロシアの絶対主義政策を継続した。治世の最初の数年間、彼はいくつかの小規模な社会改革と(1803年から1804年)大学の増設といった大規模な自由主義教育改革を開始した。アレクサンドルは、村の司祭の息子であるミハイル・スペランスキーを側近のひとりに任命した。過度に中央集権化されたコレギウム省は廃止され、法制度を改善するために閣僚委員会、国家評議会、最高裁判所が設置された。議会を設立して憲法を署名する計画が立てられたが、実現することはなかった。ピョートル大帝のような西洋化を進めた前任者たちとは対照的に、アレクサンドルはロシアの民族主義者でありスラヴ主義者であり、ロシアがヨーロッパ文化ではなくロシア文化に基づいて発展することを望んでいた。
外交政策においては、1804年から1812年の間に、ロシアの対フランス政策を4度転換し、中立、反対、同盟の立場をとった。1805年にはナポレオンとの第三次対仏大同盟においてイギリスに加担したが、アウステルリッツの戦いとフリートラントの戦いで大敗を喫した後、寝返ってティルジット条約(1807年)でナポレオンと同盟を結び、ナポレオンの大陸封鎖に加わった。1807年から1812年にかけてはイギリスとの小規模な海戦を、またスウェーデンが大陸封鎖への参加を拒否したことを受けてスウェーデンとの短期戦争(1808年から1809年)にも従軍した。アレクサンドル1世とナポレオンは、特にポーランド問題に関してほとんど意見が合わず、同盟は1810年までに崩壊した。アレクサンドル1世にとって最大の勝利は、1812年にナポレオンのロシア侵攻がフランスにとって壊滅的な打撃となった時であった。ナポレオンに対する勝利を収めた同盟の一員として、彼はフィンランドとポーランドの領土を獲得した。彼はヨーロッパにおける革命運動を、正統なキリスト教君主に対する不道徳な脅威と見なし、鎮圧するために 神聖同盟を結成した。
アレクサンドルは治世の後半に、ますます独断的かつ反動的になり、自分に対する陰謀を恐れるようになった。その結果、治世初期に行った改革の多くを終わらせた。教育がより宗教的になり、政治的に保守的になったため、彼は学校から外国人教師を一掃した。[ 3 ]スペランスキーに代わった顧問には厳格な砲兵監察官のアレクセイ・アラクチェエフが就任し、アラクチェエフは軍事入植地の建設を監督した。アレクサンドルは1825年12月、南ロシアへの旅行中にチフスで亡くなった。彼には嫡子がおらず、2人の娘は幼少期に亡くなった。彼の兄弟はどちらも皇帝になる気はなかった。大混乱の時期(彼の死後数週間で自由主義派の軍将校によるデカブリストの反乱が失敗に終わる前兆となった)の後、弟のニコライ1世が彼の後を継いだ。
若いころ


アレクサンドルは1777年12月23日10時45分にサンクトペテルブルクで生まれ、[ 4 ]弟のコンスタンチンと共に祖母のエカテリーナに育てられた。[ 5 ] 12月31日[ 6 ]冬宮殿大教会[ 7 ]で、ミトラ首長司祭[ 8 ]ヨアン・イオアンノヴィチ・パンフィロフ[ 9 ](女帝エカテリーナ2世の聴罪司祭)により洗礼を受けた。 [ 10 ]名付け親はエカテリーナ2世、名付け親は神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世とフリードリヒ大王[ 11] である。[ 11 ]サンクトペテルブルクの守護聖人アレクサンドル・ネフスキーにちなんで名付けられた。[ 12 ]彼の生い立ちの相反する側面として、彼はエカテリーナ宮廷の自由な思想の雰囲気とスイス人の家庭教師フレデリック・セザール・ド・ラ・アルプからルソーの人道福音の原理を吸収した一方で、軍政長官ニコライ・サルトゥイコフからはロシアの専制政治の伝統を吸収した[ 13 ]。[ 13 ]彼の祖母が宗教指導者に選んだアンドレイ・アファナシエヴィチ・サンボルスキーは、典型的ではない髭のない正教会の司祭だった。サンボルスキーは長くイギリスに住み、アレクサンダーとその兄弟コンスタンチンに流暢な英語を教えたが、これは当時のロシアの専制君主候補にとっては非常に珍しい資質だった。
1793年10月9日、アレクサンドルがまだ15歳だった時、彼は14歳のバーデン公女ルイーゼと結婚し、エリザヴェータ・アレクセイエヴナという名を名乗った。[ 14 ]彼の祖母が、この若き公女との結婚を取り仕切った。[ 15 ]祖母が亡くなるまで、彼は常に祖母と父の間の忠誠の境界線を歩んでいた。彼の執事ニコライ・サルトゥイコフは、彼が政治的な舞台で活躍できるよう手助けしたが、そのことが彼に祖母への嫌悪感と父との付き合いへの恐怖感を植え付けた。
エカテリーナは夫妻のためにアレクサンドル宮殿を建てさせた。しかし、エカテリーナは夫妻をダンスやパーティーで楽しませようと躍起になり、妻を苛立たせたため、彼とエカテリーナの関係は悪化した。宮殿での生活は、夫としての役割を果たさなければならないというプレッシャーも彼に与えた。しかし、彼は大公妃に対しては兄のような愛情しか感じていなかった。[ 16 ]父の領地であるガッチナ宮殿を訪れることは、皇后の華やかな宮廷生活からの息抜きになると考えたため、父への共感を深めていった。そこでは、フランス宮廷で流行していた派手な衣装ではなく、簡素なプロイセン軍服を着用した。それでも、皇太子への訪問には少なからず苦労があった。パーヴェルは客人に軍事教練を行わせるのが好きで、息子のアレクサンドルとコンスタンチンにもそれを押し付けた。また、彼は癇癪持ちで、物事が思い通りにいかないとしばしば激怒した。[ 17 ]いくつかの情報源[ 18 ]によると、エカチェリーナ2世は息子のポールを(彼の不安定な気質と奇妙な性格を考慮して)継承権から完全に排除し、代わりにアレクサンダーを後継者にする計画を立てていたと言われています。
皇太子
1796年11月のエカテリーナの崩御により、アレクサンドルを後継者に指名する前に、息子のパーヴェルが帝位に就いた。アレクサンドルは、祖母以上に父を皇帝として嫌っていた。彼はロシアが「狂人の慰み物」となり、「絶対的な権力はすべてを混乱させる」と記している。歴代の皇帝2人がこのように独裁権力を乱用したのを目の当たりにしたことが、彼を19世紀のロマノフ朝における最も進歩的な皇帝の一人へと押し上げたと考えられる。国全体でパーヴェルは広く不人気だった。彼は妻が第二のエカテリーナとなり、母が父から権力を奪ったように、自分から権力を奪おうと陰謀を企てていると非難した。また、アレクサンドルが自分に対して陰謀を企てていると疑っていた。[ 19 ]
天皇
| シリーズの一部 |
| ロシアにおける保守主義 |
|---|
 |

上昇
アレクサンドルは、1801年3月23日に父が暗殺されたときにロシア皇帝になった。当時23歳だったアレクサンドルは暗殺の瞬間に聖ミカエル城にいて、彼の帝位継承は暗殺者の一人であるニコライ・ズーボフ将軍によって発表された。歴史家たちは、父の暗殺におけるアレクサンドルの役割について今も議論している。最も一般的な説は、彼は陰謀家の秘密を聞き出され、帝位に就く意思はあったが父を殺してはならないと主張したというものである。父の命を奪った罪で皇帝になったことは、アレクサンドルに強い自責の念と恥辱感を与えたであろう。[ 20 ]アレクサンドル1世はその日帝位を継承し[ 21 ] 、同年9月15日に クレムリンで戴冠した。
国内政策
.jpg/440px-Alexander_I_of_Russia_by_F.Kruger_(1837,_Hermitage).jpg)
正教会は当初、アレクサンドルの人生にほとんど影響を与えなかった。若き皇帝は、ロシアが依存していた非効率で高度に中央集権化された政治体制を改革することを決意した。しばらくの間、旧来の大臣たちを留任させつつも、彼の治世における最初の行動の一つは、ヴィクトル・コチュベイ、ニコライ・ノヴォシルツェフ、パーヴェル・ストロガノフ、アダム・イェジー・チャルトリスキといった若く熱心な友人たちからなる私設委員会を任命し、啓蒙時代の教えに基づいた立憲君主制の樹立を目指す国内改革計画を策定することだった。[ 22 ]
治世の数年後、自由主義者のミハイル・スペランスキーは皇帝の側近の一人となり、綿密な改革計画を立案した。政府改革では、旧来のコレッギア(閣僚機構)が廃止され、代わりに国王直属の大臣が率いる新しい省が設立された。皇帝を議長とする閣僚委員会が省庁間のあらゆる問題を扱った。立法技術の向上を目的に国家評議会が設立され、代議制議会の第二院となることが意図されていた。統治元老院は帝国最高裁判所として再編された。1801年に着手された法律の成文化は、彼の治世中には実施されなかった。[ 23 ]
アレクサンドルはロシアにおけるもう一つの重要な問題、すなわち農奴の地位の解決を望んでいたが、これは1861年(甥のアレクサンドル2世の治世下)まで実現しなかった。彼の顧問たちは、これらの選択肢について静かに長々と議論した。彼は慎重に、 1801年に国有農民を含むほとんどの階層の臣民に土地所有権を拡大し、1803年には主人によって自発的に解放された農民のために「自由農民」という新しい社会階層を創設した。大多数の農奴には影響がなかった。[ 24 ]
アレクサンドル1世の治世が始まった当時、ロシアにはモスクワ、ヴィリニュス(ヴィリニュス)、ドルパト(タルトゥ)の3つの大学がありました。これらの大学は強化され、さらにサンクトペテルブルク、ハリコフ、カザンに3つの大学が設立されました。文学・科学団体も設立または奨励され、アレクサンドル1世の治世は皇帝と裕福な貴族による科学と芸術への援助で知られるようになりました。アレクサンドル1世は後に外国人学者を追放しました。[ 25 ]
1815年以降、軍隊またはその一部を経済的に自立させ、新兵を補充する目的で、軍人入植地(軍の管理下で兵士とその家族が働く農場)が導入された。 [ 13 ]
同時代の人々の見解

独裁者でありジャコバン派[ 13 ]とも呼ばれ、世慣れした人物であり神秘主義者でもあったアレクサンダーは、同時代人にとっては、それぞれの気質に応じて解釈される謎かけのようだった。ナポレオン・ボナパルトは彼を「ずる賢いビザンチン人」[ 13 ]と考え、どんな目立つ役割でも喜んで演じる北のタルマと呼んだ。メッテルニヒにとっては、彼は機嫌を損ねるほどの狂人だった。キャッスルレーはリヴァプール卿に宛てた手紙の中で、アレクサンダーの「偉大な資質」を称賛しつつも、「疑い深く、優柔不断」であると付け加えた[ 13 ] 。ジェファーソンにとっては、彼は高潔な人格の持ち主で、善行をなす気質があり、ロシア国民大衆に「彼らの自然権意識」を浸透させると期待されていた。[ 26 ] 1803年、ベートーベンは作品30のヴァイオリンソナタをアレクサンダーに捧げ、アレクサンダーは1814年にウィーン会議でベートーベンにダイヤモンドを贈った。
ナポレオン戦争
他の勢力との同盟
アレクサンダーは即位後、父パウルの不人気な政策の多くを覆し、武装中立同盟を非難し、イギリスと和平を結んだ(1801年4月)。同時に神聖ローマ皇帝フランツ2世との交渉を開始した。その後まもなく、メーメルにおいてプロイセンとの緊密な同盟を締結したが、これは政策上の動機からではなく、真の騎士道精神に基づき、若きフリードリヒ・ヴィルヘルム3世とその美しい妻ルイーゼ・フォン・メクレンブルク=シュトレーリッツへの友情から生まれたものであった。[ 27 ]
この同盟の発展は1801年10月の短命な和平によって中断され、しばらくの間、フランスとロシアは和解に至ったように見えた。パリからロシアに帰国したフレデリック・セザール・ド・ラ・アルプの熱意に感化され、アレクサンドルはフランスの制度とナポレオン・ボナパルトという人物への称賛を公然と表明し始めた。しかし、すぐに変化が訪れる。パリを再訪したラ・アルプは、アレクサンドルに『終身領事の本質についての考察』を提出した。アレクサンドルの言によれば、この書は彼の目のベールを剥ぎ取り、ナポレオンが「真の愛国者」ではなく[ 27 ] 、 「世界が生んだ最も有名な暴君」であることを明らかにしたのである。[ 27 ]その後、ラ・アルプとその友人アンリ・モノはアレクサンドルに働きかけ、アレクサンドルはナポレオンに反対する他の連合国を説得し、ヴォードワとアルゴイの独立を認めさせた。ベルンはこれらの地域を従属地として返還しようとしたが、アレクサンドルはそれを拒否した。アンギャン公が捏造された容疑で処刑されたことで、アレクサンドルの幻滅は頂点に達した。ロシア宮廷はコンデ家最後の人物の死を悼み、フランスとの外交関係は断絶された。アレクサンドルは特に警戒し、ナポレオンの力を何とか抑制しなければならないと決意した。[ 28 ]
ナポレオンへの反対
アレクサンドル1世は、「ヨーロッパの抑圧者であり、世界の平和を乱す者」であるナポレオン1世に対抗することで、実は既に神聖な使命を果たしていると信じていた。ロンドン駐在の特使ニコライ・ノヴォシルツェフへの指示の中で、皇帝は自らの政策の動機を、首相ウィリアム・ピット(小ピット)にはあまり響かない言葉で詳述した。しかし、この文書は、革命期の終焉に際立った役割を果たすことになる国際政策の理想を公式文書で初めて定式化したものであり、非常に興味深い。[ c ]アレクサンドル1世は、戦争の成果はフランスの解放だけでなく、「人類の神聖な権利」の普遍的な勝利であると主張した。[ 27 ]これを達成するためには、「国民の最大利益のためだけに行動することができないような形で国民を政府に縛り付けた後、各州間の関係をより正確な規則に基づいて、そして国民が尊重すべき利益となるような規則に基づいて定めること」が必要である。[ 27 ]
一般条約は、「ヨーロッパ連合」を構成する諸国間の関係の主要な基盤となるはずだった。[ 27 ]彼は、この努力が普遍的な平和を達成するとは考えなかったものの、諸国家の権利に関する明確な原則を確立するならば、その努力は価値があると考えた。[ 27 ]この機関は「諸国家の積極的権利」と「中立の特権」を保証し、平和維持のためにあらゆる調停手段を尽くす義務を主張し、「新たな国際法典」を形成することになる。[ 29 ]
1807年フランス軍に敗北

一方、ナポレオンは同盟からの離脱を決して諦めなかった。ウィーンに凱旋するや否や、アレクサンドル1世との交渉を開始し、アウステルリッツの戦い(12月2日)後に交渉を再開した。ナポレオンはロシアとフランスは「地理的同盟国」[ 27 ]であり、両国の間に真の利害対立は存在せず、また存在し得ないと主張した。両国が力を合わせれば世界を支配できるかもしれないと。しかし、アレクサンドル1世は依然として「これまでヨーロッパ諸国に対して従ってきた無私無欲の体制を堅持する」[ 27 ]決意を固め、再びプロイセン王国と同盟を結んだ。イエナの戦いとアイラウの戦いが続いた。ナポレオンは依然としてロシアとの同盟に固執しつつも、ポーランド、トルコ、ペルシア人を扇動して皇帝の頑固さを打ち砕こうとした。ロシア国内でも、皇帝の弟コンスタンチン・パーヴロヴィチを筆頭とする勢力が和平を強く求めていた。しかしアレクサンドル1世は、新たな同盟を結成しようとして失敗した後、ロシア国民をナポレオンを正教の敵として聖戦へと招集した。その結果、フリートラントは敗走した(1807年6月13日/14日)。ナポレオンは好機を捉え、それを掴み取った。厳しい和平条件を要求する代わりに、懲りた独裁者に同盟を申し出、栄光の共同事業を申し出た。[ 27 ]
1807年6月25日、二人の皇帝はティルジットで会談した。ナポレオンは、新たに見つけた友人の豊かな想像力に訴えかける術を熟知していた。彼はアレクサンダーと世界帝国を分割し、まずはドナウ公国をアレクサンダーに残し、フィンランドへの対応を自由にさせる。その後、東西の皇帝は機が熟した暁にはトルコをヨーロッパから駆逐し、アジアを横断してインドを征服するだろうと考えた。しかし、ある考えがアレクサンダーの感受性の強い心に、これまで彼には縁のなかった野心を呼び覚ました。ヨーロッパ全体の利益は完全に忘れ去られていたのだ。[ 30 ]
プロイセン
しかし、こうした新たな構想の輝きは、アレクサンドルの友情の義務を曇らせることはなく、彼はプロイセンのさらなる分裂を覚悟してドナウ公国を保持することを拒否した。「我々は忠誠の戦争を行った。忠誠の和平を結ばなければならない」と彼は言った。[ 27 ]ティルジットの最初の熱意はすぐに冷め始めた。フランスはプロイセンに、ロシアはドナウ川沿いに留まり、互いに相手を不誠実だと非難した。しかし、アレクサンドルとナポレオンの個人的な関係は非常に友好的であり、新たな会談によって両者間のあらゆる相違点が調整されるだろうと期待されていた。会談は1808年10月にエアフルトで行われ、両皇帝の共通政策を定めた条約が締結された。しかし、アレクサンドルとナポレオンの関係は変化を余儀なくされた。彼は、ナポレオンにおいては感情が理性に勝ることは決してないこと、そして実際には彼が自らの「大事業」を真剣に考えたことは一度もなく、中央ヨーロッパにおける自身の権力を固める間、皇帝の心を掴ませるために利用したに過ぎないことに気づいた。この瞬間から、アレクサンドルにとってフランスとの同盟は、世界を支配するための兄弟的な協定ではなく、純粋な政策上の問題となった。彼はまず、フィンランドをスウェーデンから奪取(1809年)することでサンクトペテルブルクの門から「地理的な敵」を排除し、さらにドナウ川をロシアの南の国境にすることを望んだ。[ 27 ]
仏露同盟

事態は急速に露仏同盟の崩壊へと向かっていた。アレクサンドル1世は1809年の第五次対仏大同盟においてナポレオンを支援したが、オーストリア帝国が消滅させられることは決して許さないと明言した。その後、ナポレオンはロシア軍の軍事行動の停滞を痛烈に批判した。一方、皇帝はナポレオンがポーランド軍を奨励していることに抗議した。フランスとの同盟問題において、アレクサンドル1世はロシア国内で事実上孤立していることを認識しており、ナポレオンへの愛のために国民と帝国の利益を犠牲にすることはできないと断言した。「私は自分のために何も望んでいない」と彼はフランス大使に語った。「それゆえ、ポーランドの復興という問題に関して、世界はポーランド情勢について理解し合うほど広くはないのだ」[ 31 ] [ 32 ] 。
アレクサンダーは、ワルシャワ公国を大幅に拡大したシェーンブルン条約が「彼の忠誠心に反する」と不満を漏らしたが、ナポレオンがポーランドを回復する意図がないと公言したことと、1810年1月4日に署名されたものの批准されなかったポーランドの名前と騎士団を廃止する条約によって、当面は和らいだ。[ 33 ]
しかし、アレクサンドルがナポレオンの意図を疑っていたとすれば、ナポレオンはアレクサンドルに対しても同様に疑念を抱いていた。ナポレオンは彼の誠実さを試す意味もあって、皇帝の末妹である大公女アンナ・パヴロヴナに、ほとんど断りのこもった求婚状を送った。少し間を置いてアレクサンドルは、大公女の若さと皇太后が結婚に反対していることを理由に、丁重に断りの返事をした。ナポレオンの返答は、1月4日の条約の批准を拒否し、アレクサンドルに二つの婚姻条約が同時に交渉されたと思わせるような形で、マリー・ルイーズ大公女との婚約を発表することだった。このときから、二人の皇帝の関係は次第に緊張していった。[ 33 ]
アレクサンドル1世がナポレオンに対して抱いていたもう一つの個人的な不満は、1810年12月にフランスがオルデンブルクを併合したことであった。オルデンブルク公ヴィルヘルム(1754年1月3日 - 1823年7月2日)は皇帝の叔父であった。さらに、大陸封鎖がロシア貿易に壊滅的な影響を与えたため、皇帝はナポレオンが同盟を結んだ最大の動機であった政策を維持することができなかった。[ 33 ]
アレクサンドル1世は、進行中のフランスとイギリスの戦争(ロシアとイギリスの戦争は名目上のものに過ぎなかった)において、ロシアを可能な限り中立に保った。彼はイギリスとの貿易を秘密裏に継続することを許可し、大陸封鎖で義務付けられていた封鎖措置を強制しなかった。[ 34 ] 1810年、彼はロシアを大陸封鎖から脱退させ、イギリスとロシア間の貿易は拡大した。[ 35 ]

1810年以降、フランスとロシアの関係は徐々に悪化していった。1811年までに、ナポレオンがティルジット条約の条項を遵守していないことが明らかになった。彼はオスマン帝国との戦争においてロシアへの支援を約束していたが、戦役が進むにつれてフランスは全く支援を申し出なくなった。[ 34 ]
フランスとロシアの間で戦争が差し迫ると、アレクサンドルは外交的に準備を開始した。1812年4月、ロシアとスウェーデンは相互防衛条約を締結した。1ヶ月後、アレクサンドルはブカレスト条約(1812年)を通じて南方面を確保し、オスマン帝国との戦争は正式に終結した。[ 35 ]アレクサンドルの外交官たちは、ナポレオンがロシアに侵攻した場合、プロイセンはナポレオンを可能な限り支援せず、オーストリアは一切の援助を行わないという約束をプロイセンとオーストリアから引き出すことに成功した。
陸軍大臣のミハイル・アンドレアス・バルクラーイ・デ・トーリは、1812年の戦役開始前にロシア帝国軍の改革と強化を指揮していた。アレクサンドルは、主に妹であり伯爵でもあるアレクセイ・アラクチェエフの助言に基づき、1805年の戦役時のように自ら作戦指揮を執ることはせず、代わりに将軍のバルクラーイ・デ・トーリ、ピョートル・バグラチオン公爵、ミハイル・クトゥーゾフに指揮権を委譲した。[ 35 ]
ペルシャとの戦争

1796年のペルシャ遠征での短い敵対行為があったにもかかわらず、8年間の平和が過ぎた後、2つの帝国の間に新たな紛争が勃発した。1801年にロシアが何世紀にもわたってペルシャの属国であったグルジアのカルトリ・カヘティ王国を併合し、 [ 36 ]その後すぐにデルベント・ハン国も併合した後、アレクサンドルは戦略的に重要なコーカサス地方におけるロシアの影響力を拡大し維持することを決意した。 [ 37 ] 1801年、アレクサンドルはグルジア出身の筋金入りのロシア帝国主義者であるパベル・ツィツィアノフをロシアのコーカサス地方総司令官に任命した。1802年から1804年の間に、アレクサンドルは西グルジアとグルジア周辺のペルシャが支配するいくつかのハン国にロシアの支配を押し付け始めた。これらのハン国のいくつかは戦わずに服従したが、ギャンジャ・ハン国は抵抗し、攻撃を招いた。ギャンジャ包囲戦では、ギャンジャは容赦なく略奪され、ギャンジャの住民約3,000人[ 38 ] [ 39 ]から 7,000人[ 40 ]が処刑され、さらに数千人がペルシアへ追放された。チツィアノフによるこれらの攻撃は、新たな開戦理由となった。
1804年5月23日、ペルシャはロシアが占領していた地域(現在のジョージア、ダゲスタン、アゼルバイジャンの一部)からの撤退を要求した。ロシアはこれを拒否し、ギャンジャを襲撃して宣戦布告した。現在のダゲスタン、東ジョージア、アゼルバイジャン、北アルメニアを中心とする10年近くにわたる膠着状態の後、どちらの勢力も明確な優位に立つことができなかったが、ロシアはついに戦況を逆転させた。ピョートル・コトリャレフスキー将軍率いる一連の攻勢が成功し、ランカラン包囲戦での決定的な勝利も得られた後、ペルシャは和平を申し入れざるを得なくなった。 1813年10月、イギリスの仲介によりグリスタンで調印されたグリスタン条約により、ペルシャのシャー、ファト・アリー・シャーは北コーカサスにおけるペルシャ領土の全てと南コーカサスにおけるペルシャ領土の大部分をロシアに割譲した。これには現在のダゲスタン、ジョージア、そしてアゼルバイジャンの大部分が含まれていた。また、この条約によりコーカサス地方の人口構成が大きく変化し、多くのイスラム教徒の家族がペルシャに移住した[ 41 ] 。
フランスの侵攻
1812年の夏、ナポレオンはロシアに侵攻した。モスクワ占領と、聖なるロシアの聖地とされていたクレムリンの冒涜は、アレクサンドル1世のナポレオンに対する感情を激しい憎悪へと変えた。 [ 42 ] [ d ] 1812年の戦役はアレクサンドル1世の人生における転機となった。モスクワ焼失後、彼は自らの魂が啓示を受け、ヨーロッパの平和推進者としての使命という神の啓示を決定的に悟ったと宣言した。[ 33 ]
ロシア軍がロシアの奥深くまで3か月近く撤退している間、貴族たちはアレクサンドル1世にロシア軍司令官バルクレイ・ド・トーリ元帥を解任するよう圧力をかけた。アレクサンドル1世はこれに従い、ミハイル・クトゥーゾフ公を軍の指揮官に任命した。9月7日、大陸軍はモスクワの西110キロにあるボロジノという小さな村でロシア軍と対峙した。その後に起きた戦闘はナポレオン戦争中最大かつ最も血なまぐさい1日の戦闘となり、25万人以上の兵士が参加し7万人の死傷者が出た。戦闘の結果は決定的なものにならなかった。大きな損失があったにもかかわらず負け知らずだったロシア軍は翌日撤退することができ、フランス軍はナポレオンの求めていた決定的勝利を得ることができなかった。

1週間後、ナポレオンはモスクワに入ったが、皇帝に会う使節はいなかった。ロシア軍はモスクワから撤退しており、モスクワ知事のフョードル・ロストプチン伯爵はモスクワのいくつかの戦略拠点に火を放つよう命じた。モスクワを失ったことでもアレクサンドルは和平を申し入れることはなかった。1か月間市内に留まった後、ナポレオンは軍を南西のカルーガに向けて移動させた。カルーガにはクトゥーゾフがロシア軍と共に野営していた。カルーガへのフランス軍の進撃はロシア軍に食い止められ、ナポレオンは侵略によってすでに荒廃していた地域に撤退を余儀なくされた。その後数週間、大陸軍は飢えに苦しみ、ロシアの冬の到来に苦しんだ。食料と馬の飼料の不足、孤立した部隊へのロシア農民とコサックの執拗な攻撃が大きな損失につながった。11月にフランス軍の残党がベレジーナ川を渡河した時点で、残っていた兵士はわずか2万7千人だった。大陸軍は約38万人の戦死者と10万人の捕虜を出した。ベレジーナ川渡河後、ナポレオンは皇帝の地位を守り、進軍するロシア軍に抵抗するための軍勢を増強するため、軍を離脱してパリに戻った。この作戦は1812年12月14日に終結し、最後のフランス軍はついにロシア領から撤退した。
この戦役はナポレオン戦争の転換点となった。ナポレオンの評判は大きく揺るがされ、ヨーロッパにおけるフランスの覇権は弱体化した。フランスとその同盟軍からなる大陸軍は、当初の兵力のほんの一部にまで縮小した。これらの出来事はヨーロッパ政治に大きな変化をもたらした。フランスの同盟国であったプロイセン、そして間もなくオーストリアもナポレオンとの同盟を破棄して寝返り、第六次対仏大同盟の勃発につながった。
第六次対仏大同盟の戦争
.jpg/440px-Declaration_of_victory_after_the_Battle_of_Leipzig,_1813_(by_Johann_Peter_Krafft).jpg)
1812年、ロシア軍がナポレオンに勝利したことを受けて、ロシア、プロイセン、イギリス、スウェーデン、スペインなどの国々による第六次対仏大同盟が結成されました。ドイツ方面作戦の初期戦闘ではフランスが勝利したものの、オーストリアの参戦により、1813年秋のライプツィヒの戦いでフランスは決定的な敗北を喫し、対仏大同盟にとって大勝利となりました。この戦いの後、親仏派のライン同盟は崩壊し、ナポレオンのライン川東側の領土支配は永久に終わりました。対仏大同盟の最高司令官であり、三大君主の中でも最高権力者であるアレクサンダーは、ドイツに駐留するすべての対仏大同盟軍に対し、ライン川を渡りフランスに侵攻するよう命じました。
1814年1月、連合軍は3つのグループに分かれてフランス北東部に侵入した。戦場で彼らと対峙したのはわずか7万人ほどのフランス軍だった。ナポレオンは数で大きく劣勢であったにもかかわらず、ブリエンヌとラ・ロティエールの戦いで分裂した連合軍を破ったが、連合軍の進撃とナポレオンに対する大勝利を阻止することはできなかった。オーストリア皇帝フランツ1世とプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世は、戦役開始以来のナポレオンの勝利を聞いて士気が低下した。彼らは総退却を命じることさえ考えた。しかしアレクサンダーは、いかなる犠牲を払ってでもパリに勝利して入城すると、これまで以上に決意を固めており、シュヴァルツェンベルク公カール・フィリップと動揺する君主たちに自らの意志を押し付けた。[ 43 ] 3月28日、連合軍はパリに向けて進撃し、攻撃開始の準備を整えた。

3月29日に市の郊外に野営した連合軍は、翌3月30日の朝に市の北側と東側から攻撃することになっていた。戦闘は同日の朝、連合軍の陣地からの激しい砲撃で始まった。早朝、連合軍の攻撃はロシア軍が攻撃してベルヴィル付近でフランスの散兵を撃退したところから始まったが、市東郊外のフランス騎兵によってロシア軍自身も撃退された。午前7時までに、ロシア軍はフランス軍戦線中央のロマンヴィル付近でヤングガード隊を攻撃し、しばらくして激しい戦闘の末、これを撃退した。数時間後、ゲプハルト・レーベレヒト・フォン・ブリュッヒャー率いるプロイセン軍が市の北方から攻撃し、フランス軍の陣地をオーベルヴィリエ周辺に奪取したが、攻撃を強行することはなかった。ヴュルテンベルク軍はオーストリア軍の支援を受けて南東のサン=モールの陣地を占領した。その後、ロシア軍はパリ北東部のモンマルトルの丘陵を攻撃した。丘陵の制圧はフランス軍が降伏するまで激しい争いとなった。 [ 44 ] [ 45 ]
アレクサンドル1世はフランス軍の降伏を早めるため、特使を派遣した。彼はフランスに寛大な条件を提示し、モスクワへの復讐を企てながらも[ 46 ]、フランスを滅ぼすのではなく平和をもたらすと宣言した。3月31日[ 47 ] 、タレーランは皇帝にパリの鍵を託した。同日遅く、連合軍はアレクサンドル1世を先頭にプロイセン国王とシュヴァルツェンベルク公子を従え、凱旋入城を果たした。この戦いまで、百年戦争中に外国軍がパリに入城したのはほぼ400年ぶりのことであった。
4月2日、保守上院はナポレオンの退位を宣言する皇帝退位法案を可決した。パリ降伏の知らせを聞いたとき、ナポレオンはフォンテーヌブローにいた。激怒したナポレオンは首都への進軍を望んだが、元帥たちは彼のために戦うことを拒否し、繰り返し降伏を促した。4月4日、ナポレオンは息子に退位を申し出たが、連合国はこれを即座に拒否し、ナポレオンは4月6日に無条件退位を余儀なくされた。エルバ島への追放を含む退位の条件は、4月11日のフォンテーヌブロー条約で定められた。渋々ながらもナポレオンは2日後に条約を批准し、第六次対仏大同盟戦争は終結した。
南北戦争後
パリ条約とウィーン会議
_-_The_Allied_Sovereigns_at_Petworth,_24_June_1814_(George,_1751–1837,_3rd_Earl_of_Egremont,_with_His_C_-_486228_-_National_Trust.jpg/440px-thumbnail.jpg)

アレクサンドルは大陸の福音主義復興運動の指導者たちと文通することで良心の不安を鎮めようとし、聖句の中に兆しや超自然的な導きを求めた。しかし、彼自身の記述によれば、 1813年秋、バーゼルで、諸侯の改宗を特別な使命とする宗教的冒険家、クルーデナー男爵夫人に出会って初めて、彼の魂は平安を得たという。このときから、神秘主義的な敬虔主義は、彼の政治的活動だけでなく私的な活動においても、公然とした力となった。クルーデナー男爵夫人と、彼女の同僚である福音伝道師アンリ=ルイ・アンパイタズは、皇帝の最も秘密の考えを知る相談相手となり、パリ占領に至った軍事行動の間、皇帝の祈祷会は世界の運命を左右する啓示の神託であった。[ 33 ]
ナポレオンの失脚により、アレクサンドル1世がヨーロッパで最も強力な君主の一人となった時、彼の心境はまさにこれだった。ティルジット条約の記憶が人々の記憶にまだ生々しく残っていたため、クレメンス・ヴェンツェル・フォン・メッテルニヒのような皮肉屋の世間知らずの人々に、アレクサンドル1世は「福音主義的な自己犠牲の言葉の下に」、壮大で危険な野望を隠しているに過ぎないと思われたのも無理はなかった。[ 33 ]実際、困惑した列強は、皇帝の他の、一見矛盾しているように見える傾向を見て、ますます疑念を抱くようになった。しかし、それらの傾向はすべて、同じように不穏な結論を指し示しているように思われた。というのも、帝位の背後で影響力を持っていたのはクリューデナー夫人だけではなかったからだ。アレクサンドル1世は革命に宣戦布告したにもかかわらず、かつての家庭教師であるラ・アルプが再び彼の傍らにいて、人道の福音のスローガンは依然として彼の口から発せられていた。ナポレオンを「悪の天才」と非難したまさにその宣言は、「自由」と「啓蒙」の名において彼を非難した。[ 33 ]保守派は、東方の独裁者アレクサンドルが全ヨーロッパのジャコバン主義と同盟を結び、全能のフランスに代えて全能のロシアを狙うという、恐るべき陰謀を企てていると疑っていた。ウィーン会議におけるアレクサンドルの態度は、この不信感をさらに強めた。ヨーロッパにおける「公正な均衡」の回復を唯一の目標としていたキャッスルレー子爵ロバート・スチュワートは、条約上の義務に違反してポーランドを掌握し続けることで列強の協調を危うくした皇帝の「良心」を面と向かって非難した。[ 48 ]
リベラルな政治的見解
.jpg/440px-Alexander_I_by_Lawrence_(1814-18,_Royal_collection).jpg)
かつては限定的自由主義の支持者であり、イオニア諸島の代表制、フィンランド大公国、1815年のポーランド王国憲法を承認していたことなどがその例であるが[ 49 ] [ 50 ] 、 1818年末からアレクサンドルの考えは変わり始めた。ロシア帝国近衛兵の将校たちの間で革命的な陰謀が起こり、エクス・ラ・シャペル会議に向かう途中で彼を誘拐しようとした陰謀が、彼の自由主義的信念を揺るがしたと言われている。エクス・ラ・シャペル会議で彼は初めてメッテルニヒと親密な関係を持った。このときから、ロシア皇帝の心とヨーロッパ会議においてメッテルニヒが優位に立つようになったのである。
しかし、それは突然の転向ではなかった。ドイツにおける革命的煽動(代理人の劇作家アウグスト・フォン・コッツェビューの殺害(1819年3月23日)に危機感を抱きながらも、アレクサンダーは、1819年7月のカールスバッド布告で定式化された「諸政府が諸人民に対抗する同盟を結ぶ」というメッテルニヒの集団安全保障政策に対するキャッスルレーの抗議に加わった。アレクサンダーは、「『絶対権力』という不条理な主張」を支持するために、ヨーロッパ連盟が個々の国家の問題に介入することを非難した[ 51 ] 。彼は依然として、制限付きの自由制度を信じていると宣言した。「自由は正当な制限内に限定されるべきである。そして、自由の制限は秩序の原理である」と彼は主張した[ 52 ] 。

アレクサンドルの転向は、1820年にナポリとピエモンテで起きた革命と、フランス、ドイツ、そして自国民の間で高まった不満の高まりによって完了した。 1820年10月に列強が会議を開いたトロッパウという小さな町で、メッテルニヒはウィーンとエクスの混乱と陰謀の中で失われつつあったアレクサンドルへの影響力を強化した。午後の紅茶を飲みながらの親しい会話の中で、幻滅した独裁者は自らの過ちを認めた。「あなたには後悔することはないだろう」と彼は歓喜する首相に悲しげに言った。「しかし、私にはある!」[ 53 ]
この問題は極めて重大であった。1月時点では、アレクサンドルは依然として、列強独裁政策である四国条約に反対し、ヨーロッパ諸国の自由な連合体である神聖同盟の理想を掲げていた。11月19日、彼はトロッパウ議定書に署名することで屈服し、この議定書は、ヨーロッパ共同体の主張を主権国家の内政干渉に委ねることを認めた。[ 14 ]
ギリシャ人の反乱

1821年春に休会となったライバッハ会議において、アレクサンダーはギリシャがオスマン帝国に反乱を起こしたという知らせを受け取った。この時から死に至るまで、アレクサンダーの心は、ヨーロッパの安定した連邦という夢と、オスマン帝国に対する正教十字軍の指導者としての伝統的な使命との間で揺れ動いていた。当初、メッテルニヒの慎重な助言の下、アレクサンダーは前者を選択した。[ 27 ]
アレクサンドルは地域の安定のためにギリシャの反乱に反対し、その指導者であるアレクサンドル・イプシランティスをロシア帝国騎兵隊から追放し、ギリシャ人である外務大臣イオアニス・カポディストリアス(ジョヴァンニ・カポ・ディストリアス伯爵として知られる)にイプシランティスに対するロシアのいかなる同情も否定するよう指示した。そして1822年には、ヴェローナ会議に出席していたギリシャのモレア州からの代表団を引き返すよう命令を出した。[ 27 ]
彼は忠誠心を和解させようと努力した。オスマン帝国のスルタン、マフムト2世は、東方問題はヨーロッパ全体の問題ではなく「ロシアの国内問題」であるという原則に基づき、神聖同盟から除外されていた。しかしアレクサンドルは、この主張を放棄し、オーストリアがナポリで行ったように、東方において「ヨーロッパの委任国」として行動し、キリスト教の解放者としてオスマン帝国に進軍することを申し出た。[ 27 ]
メッテルニヒはこれに反対し、オーストリア主導の勢力均衡(オスマン帝国を含む)をキリスト教世界の利益よりも優先させた。これによりアレクサンドルは、オーストリアが彼の理想に対してどのような態度を取っているかを知ることになった。ロシアに帰国したアレクサンドルは、メッテルニヒの人柄に魅了されるどころか、再び国民の熱意に心を動かされ、ロシアの政策はギリシャ大義へと傾倒していった。[ 27 ]
1823年、1817年から1824年にかけてのコレラの大流行がアストラハンに到達し、皇帝はコレラ撲滅運動を命じ、それは他の国々でも模倣された。
私生活

.jpg/440px-Alexander_I_with_wife_by_anonym_after_Sant-Auben_(after_1807).jpg)
1793年10月9日、アレクサンドルはルイーゼ・フォン・バーデン(正教会に改宗後エリザヴェータ・アレクセイエヴナとして知られる)と結婚した。後に彼は友人フリードリヒ・ヴィルヘルム3世に、祖母エカチェリーナ2世が政略結婚させたこの結婚は、残念ながら彼と妻にとって不幸であったと語っている。 [ 14 ]二人の子どもは幼くして亡くなったが[ 54 ]、共通の悲しみが夫婦の絆を深めた。1799年から1818年まで愛妾マリア・ナルイシキナ[ 14 ]と関係を持った後、アレクサンドルは最愛の娘ゾフィア・ナルイシキナの死に見舞われる。皇后の惜しみない同情が夫婦の絆を強めた。
1809年、彼はフィンランドの貴族女性ウラ・メレルスヴァルドと不倫関係にあり、彼女との間に子供をもうけたという噂が広まったが、これは確認されていない。[ 55 ]
死
精神状態が悪化するにつれ、アレクサンドルはますます疑り深くなり、内向的になり、信仰心が薄れ、活動性も低下していった。一部の歴史家は、彼の性格は「まさに統合失調症の典型、すなわち内向的で孤立主義、どちらかといえば内気で、内向的で、非攻撃的で、いくぶん無関心な人物に一致する」と結論づけている。[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] 1825年秋、皇帝は妻の病状悪化のため、ロシア南部への航海に出た。航海中に自身もチフスに罹り、 1825年11月19日(旧暦)、南部の都市タガンログで亡くなった。しかし、彼の死の知らせは12月まで首都に届かなかった。 [ 59 ]二人の兄弟はどちらが皇帝になるかを争い、それぞれが相手を皇帝にしたいと考えていた。妻は数ヶ月後、皇帝の遺体が葬儀のためにサンクトペテルブルクへ運ばれる際に亡くなった。彼は1826年3月13日にサンクトペテルブルクのペトロパヴロフスク要塞の聖ペトロパヴロフスク大聖堂に埋葬された。[ 60 ]
- アレクサンドル1世のデスマスク
- タガンログにおけるアレクサンドル1世の死(19世紀の石版画)
- タガンログにあるアレクサンドル1世宮殿。1825年に皇帝が崩御した場所。
- タガンログからサンクトペテルブルクへの葬列
生存の伝説
アレクサンドル皇帝は死を偽装し、フョードル・クジミチという名で隠遁生活を送っていたという伝説があり、この説は人気作家によってしばしば取り上げられています。[ 61 ]この説は、アレクサンドルとクジミチの奇妙な類似性に関係しています。ロシア筆跡学協会会長のスヴェトラーナ・セミョーノワは、アレクサンドルとクジミチの筆跡が同一であると判定しました。フョードル・クジミチの臨終に付き添った司祭は、彼に本当にアレクサンドルなのかと尋ねたと伝えられています。クジミチは答えて、「主よ、あなたの御業は素晴らしいです…明かされない秘密はありません」と言いました。[ 62 ]
子供たち
| 名前 | 誕生 | 死 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 妻ルイーズ・オブ・バーデン | |||
| ロシア大公女マリア/マリヤ・アレクサンドロヴナ | 1799年5月18日/29日 | 1800年7月27日/8月8日[ 65 ] | アダム・チャルトリスキの子供であるという噂もあったが、1歳で死亡した。 |
| エリザベタ/エリザベタ・アレクサンドロヴナ、ロシア大公妃 | 1806年11月15日 | 1808年5月12日 | アレクセイ・オホトニコフの子供だという噂もあったが、感染症で1歳で亡くなった。 |
| マリア・ナルイシキナ | |||
| ジナイダ・ナリシキナ | 1807年12月19日頃 | 1810年6月18日 | 4歳で死亡。 |
| ソフィア・ナルイシキナ | 1805年10月1日 | 1824年6月18日 | 18歳で未婚のまま死去。 |
| エマニュエル・ナルイシュキン | 1813年7月30日 | 1901年12月31日/1902年1月13日 | キャサリン・ノヴォシルツェフと結婚、子供なし。*未確認、異論あり |
アーカイブ
アレクサンダーが祖父のヴュルテンベルク公フリードリヒ2世オイゲンに宛てた1795年から1797年にかけて書かれた手紙(および兄弟からの手紙)は、ドイツのシュトゥットガルトにあるシュトゥットガルト州立公文書館(Hauptstaatsarchiv Stuttgart)に保存されている。[ 66 ]
栄誉

彼は以下の勲章と勲章を受章した。[ 67 ]
 ロシア帝国:[ 68 ]
ロシア帝国:[ 68 ] スウェーデン:
スウェーデン:  プロイセン王国:
プロイセン王国:  両シチリア:聖ヤヌアリウス騎士団、1800年[ 72 ]
両シチリア:聖ヤヌアリウス騎士団、1800年[ 72 ]- フランス:
 デンマーク:象騎士、1808年7月2日[ 75 ]
デンマーク:象騎士、1808年7月2日[ 75 ] イギリス:ガーター勲章受章者、 1813年7月27日[ 76 ]
イギリス:ガーター勲章受章者、 1813年7月27日[ 76 ] バイエルン王国:聖フーベルト騎士、1813年[ 77 ]
バイエルン王国:聖フーベルト騎士、1813年[ 77 ] スペイン:金羊毛騎士団、1814年5月30日[ 78 ]
スペイン:金羊毛騎士団、1814年5月30日[ 78 ] オーストリア帝国:マリア・テレジア軍事勲章騎士、1815年[ 79 ]
オーストリア帝国:マリア・テレジア軍事勲章騎士、1815年[ 79 ] オランダ:ウィリアム軍事十字章、1818年11月19日[ 80 ]
オランダ:ウィリアム軍事十字章、1818年11月19日[ 80 ] サルデーニャ王国:受胎告知騎士、1822年11月5日[ 81 ]
サルデーニャ王国:受胎告知騎士、1822年11月5日[ 81 ] ポルトガル王国:三勲章サッシュ大十字章、1824年2月10日[ 82 ]
ポルトガル王国:三勲章サッシュ大十字章、1824年2月10日[ 82 ] ザクセン=ワイマール=アイゼナハ:白鷹の大十字[ 83 ]
ザクセン=ワイマール=アイゼナハ:白鷹の大十字[ 83 ]
祖先
参照
注記
- ^アレクサンドル1世の存命中、ロシアではユリウス暦(旧暦)が使用されていましたが、特に明記されていない限り、この記事の日付はグレゴリオ暦(新暦)を使用しています。詳細な説明については、 「旧暦と新暦の日付」の記事を参照してください。
- ^ロシア語: Благословенный、ローマ字表記: Blagoslovenny
- ^これは19世紀末のニコライ2世の勅令とハーグ会議で発布された(フィリップス1911、557ページ、ムラヴィエフ伯爵の回状、1898年8月24日を引用)。
- ^歴史学については、 Lieven 2006、283-308ページを参照。
- ^ブッシュコビッチ、ポール(2012年)『ロシアの簡潔な歴史』ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局、154頁。ISBN 978-0-521-54323-1。
- ^マイオロヴァ 2010、114ページ。
- ^ウォーカー 1992、343–360ページ。
- ^ "Читать" . Литмир – электронная библиотека 。2021 年7 月 27 日に取得。
- ^ “Alexander I” . 2011年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月1日閲覧。
- ^ "Vikent - Детство и юность императора Александра I" . vikent.ru 。2021 年7 月 27 日に取得。
- ^ “アレクサンドル1世(ロシア皇帝)” . history.wikireading.ru . 2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月27日閲覧。
- ^ 「HTC: Liturgical Ranks」 . www.holy-trinity.org . 2021年7月27日閲覧。
- ^ “Александро-Невская Лавра - Панфилов Иоанн Иоаннович” . lavraspb.ru 。2021 年7 月 28 日に取得。
- ^ "Читать" . Литмир – электронная библиотека 。2021 年7 月 28 日に取得。
- ^ "Александр I" . www.museum.ru 。2021 年7 月 27 日に取得。
- ^ "Александр I Павлович" . myhistorypark.ru (ロシア語) 。2021 年7 月 27 日に取得。
- ^ a b c d e fフィリップス 1911年、556ページ。
- ^ a b c dフィリップス 1911年、559ページ。
- ^セバグ・モンテフィオーレ 2016年、353ページ。
- ^セバグ・モンテフィオーレ 2016、354–356 ページ。
- ^セバグ・モンテフィオーレ 2016年、357頁。
- ^マクグルー 1992、184ページ
- ^セバグ・モンテフィオーレ 2016年、384ページ。
- ^パーマー 1974、第3章。
- ^オリヴィエ 2019 .
- ^パーマー 1974、52~55ページ。
- ^パーマー 1974、168–172ページ。
- ^マカフリー 2005年、1~21頁。
- ^フリン 1988、p. .
- ^リップスコム、バーグ&ジョンストン 1903、p. ;ジェファーソンからプリーストリーへの手紙、ワシントン、1802年11月29日
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o pフィリップス 1911、557ページ。
- ^ Esdaile 2009、192~193頁。
- ^ Phillips 1911、p. 557 は、 1804年9月11日付のM. Novosiltsovへの指示を引用している。Tatischeff、p. 82
- ^フィリップス、1911 年、p. 557 件引用: サヴァリーからナポレオンへ、1807 年 11 月 18 日。タティシェフ、p. 232.
- ^ Phillips 1911、pp. 557, 558 は、Coulaincourt から Napoleon への第 4 回目の報告、1809 年 8 月 3 日を引用しています。Tatischeff、p. 496。
- ^ Zawadzki 2009、110–124 ページ。
- ^ a b c d e f gフィリップス 1911年、558ページ。
- ^ a bノーラン2002、1666ページ。
- ^ a b cチャップマン 2001、29ページ。
- ^テッドネット.
- ^カゼムザデ 2013、5ページ。
- ^ Averyら1991年、332頁。
- ^ Baddeley 1908、p. 67は「ツィツィアノフの皇帝への報告書:Akti、ix(補足)、p. 920」を引用している。
- ^マンスーリ2008、245ページ。
- ^イェメリアノヴァ 2014 .
- ^ Phillips 1911、p. 558は、Alexander speaking to Colonel Michaud. Tatischeff、p. 612を引用している。
- ^セバグ・モンテフィオーレ 2016年、313ページ。
- ^ミカベリゼ 2013、255頁。
- ^ミハイロフスキー=ダニレフスキー 1839年、347–372頁。
- ^モンテフィオーレ 2016、313ページ。
- ^モード 1911、223ページ。
- ^ Phillips 1911、p. 558 は Castlereagh to Liverpool, 2 October 1814. FO Papers. Vienna VII を引用しています。
- ^リチャード・スタイツ(2014年)『ナポレオン以後のヨーロッパにおける自由への四騎士』オックスフォード大学出版局、ISBN 9780199981489。
- ^ジュリア・ベレスト(2011年)『ロシア自由主義の出現:アレクサンダー・クニーツィンの文脈』パルグレイブ・マクミラン、ISBN 9780230118928。
- ^ Phillips 1911、p. 558 は、 1819年11月30日(12月12日)のLievenの報告書と、 1820年1月27日のRussの回状を引用している。Martens IV、第270部。
- ^ Phillips 1911、pp. 558、559 引用: Aperçu des idées de l'Empereur、Martens IV.部品IP269。
- ^ Phillips 1911、p. 559 は Metternich Mem. を引用しています。
- ^パーマー 1974、154~155ページ。
- ^ Mäkelä-Alitalo 2006 .
- ^ニコルズ 1982年、41ページ。
- ^コックス 1987、121ページ。
- ^トラスコット 1997、26ページ。
- ^ブッシュコビッチ、ポール(2012年)『ロシアの簡潔な歴史』ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局、154頁。ISBN 978-0-521-54323-1。
- ^パーマー 1974、第22章。
- ^ Raleigh, Donald J.; Iskenderov, Akhmed Akhmedovich (1996). The Emperors and Empresses of Russia : Rediscovering the Romanovs . Internet Archive. Armonk, NY : ME Sharpe. ISBN 978-1-56324-759-0。
- ^ “Святой праведный старец Феодор Томский” . † Православие と Томске。2019年10月24日のオリジナルからアーカイブ。2023 年11 月 3 日に取得。
- ^パーマー 1974、p. .
- ^マクノートン 1973年、293–306頁。
- ^マニフェスト
- ^ “ヘルツォーク・フリードリヒ・オイゲン (1732-1797) - Briefwechsel des Herzogs mit dem kaiserlichen Hause von Russland, 1795-1797 - 3. Schreiben der jungen Großfürsten Alexander und Konstantin und Großfürstinnen Alexandrina、Anna、Katharina、Elisabeth、ヘレン、マリア」。シュトゥットガルト中央駅。2021 年11 月 22 日に取得。
- ^ロシア帝国軍 - ロシア皇帝アレクサンドル1世パーブロヴィチ2021年9月19日アーカイブat the Wayback Machine (ロシア語)
- ^ Almanach de la cour: pour l'année ... 1799。アカデミー インプ。科学。1799。45、52、61、85ページ 。
- ^ Nordenvall による (1998)。 「クングル。オーデン少佐」。Kungliga Serafimerorden: 1748–1998 (スウェーデン語)。ストックホルム。ISBN 91-630-6744-7。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^ Posttidningar、1814 年 4 月 30 日、p. 2
- ^ Liste der Ritter des Königlich Preußischen Hohen Ordens vom Schwarzen Adler (1851)、「Von Seiner Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm II. ernannte Ritter」 p. 10
- ^ Angelo Scordo、Vicende e personaggi dell'Insigne e reale Ordine di San Gennaro dalla sua Fondazione alla Fine del Regno delle Due Sicilie (PDF) (イタリア語)、p. 9、2016年 3 月 4 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ
- ^ M. & B. ワテル。 (2009年)。1805 年レジオン ドヌール勲章グランクロワ勲章。タイトルはフランセとエトランジェ。パリ:アーカイブと文化。 p. 513.ISBN 978-2-35077-135-9。
- ^アレクサンドル・トゥーレット (1863)。「Liste chronologique des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit depuis Son Origine jusqu'à Son Extinction (1578-1830)」 [聖霊騎士団の起源から消滅までの騎士の年表 (1578-1830)]。Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France (フランス語) (2): 113 。2020 年5 月 20 日に取得。
- ^ J ..... -H ..... -Fr ..... ベルリアン (1846)。デア・エレファンテン・オルデンとセーヌ・リッター。ベルリン。124 ~125ページ 。
- ^ショー、ウィリアム・A.(1906)『イングランド騎士団』I、ロンドン、 51ページ
- ^バイエルン (1824)。Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Bayern: 1824 年。ランデザムト。 p. 6.
- ^ Guerra、Francisco (1819)、「Caballeros Existentes en la Insignie Orden del Toison de Oro」、Caballeros Manual y guía de forasteros en Madroid (スペイン語): 42、2020年11 月 2 日取得
- ^ 「Ritter-Orden: Militärischer Maria-Theresien-Orden」、Hof- und Staatshandbuch des Kaiserthumes Österreich、1824、p. 17 、2020 年11 月 2 日に取得
- ^ “軍事ウィリアム騎士団: ロマノフ、アレクサンドル 1 世パブロヴィチ” [軍事ウィリアム騎士団: ロマノフ、アレクサンドル 1 世パブロヴィチ].ファン・デフェンシー大臣(オランダ語)。 1818 年 11 月 19 日。2020 年11 月 2 日に取得。
- ^ルイージ・シブラリオ (1869)。最高の聖なる年を告げる。 Sunto degli statuti、Catalogo dei cavalieri。エレディ・ボッタ。 p. 102.
- ^ブラガンサ、ホセ・ビセンテ・デ;エストレーラ、パウロ・ジョルヘ (2017)。「Troca de Decorações entre os Reis de Portugal e os Imperadores da Rússia」 [ポルトガル国王とロシア皇帝の間の勲章の交換]。プロ ファラリス(ポルトガル語)。16 :9. 2021年11月23日のオリジナルよりアーカイブ。2020 年11 月 2 日に取得。
- ^ Staatshandbuch für das Großherzogtum Sachsen / Sachsen-Weimar-Eisenach (1819)、『Großherzogliche Hausorden』 p. 8
- ^アレクサンドル・カメンスキー『 18世紀のロシア帝国:世界における地位の探求』(1997年)265~280ページ。
- ^ a b cベルリン 1768年、22ページ。
- ^ a b c dベルリン、1768 年、p. 21.
- ^ a bベルリン 1768年、110ページ。
参考文献
- エイブリー、ピーター、フィッシャー、ウィリアム・ベイン、ハンブリー、ギャビン、メルヴィル、チャールズ(1991年)『ケンブリッジ版イラン史:ナーディル・シャーからイスラム共和国まで』ケンブリッジ大学出版局、332ページ。ISBN 978-0-521-20095-0。
- バデリー、ジョン・F.(1908年)『ロシアによるコーカサス征服』ロンドン:ロングマンズ・グリーン・アンド・カンパニー、 67頁 。
- ベルリン、A. (1768)。 「表23」。Genealogie ascendante jusqu'au quatrieme degre inclusivement de tous les Rois et Princes de maisons souveraines de l'Europe actuellement vivans [現在居住しているヨーロッパの主権家のすべての国王と王子を含む 4 親等までの系図] (フランス語)。ブルドー:フレデリック・ギョーム・バーンスティール。 p. 23.
- チャップマン、ティム (2001). 『帝政ロシア 1801–1905』(図版入り、復刻版)ラウトレッジ、p. 29. ISBN 978-0-415-23110-7。
- コックス、ロバート・W.(1987年)『生産、権力、そして世界秩序:歴史形成における社会的力』コロンビア大学出版局、 121頁。
- エスデイル、チャールズ(2009年)『ナポレオンの戦争:国際史』ペンギン社、 192 ~193頁 。
- フリン、ジェームズ・T.(1988)『皇帝アレクサンドル1世の大学改革(1802-1835年)』
- 「ジェファーソンからワシントンのプリーストリーへ、1802年11月29日」。トーマス・ジェファーソン文書集第1巻。一般書簡。1651-1827年。アメリカ議会図書館。
- カゼムザデ、フィルズ (2013)。ペルシャにおけるロシアと英国: ガージャール・イランにおける帝国の野望。 IBタウリス。 p. 5.ISBN 978-0-85772-173-0。
- リップスコム、アンドリュー・アドゲイト、バーグ、アルバート・エラリー、ジョンストン、リチャード・ホランド編 (1903)。「ジェファーソンからワシントンのハリスへ、1806年4月18日」。トーマス・ジェファーソンの著作集。アメリカ合衆国トーマス・ジェファーソン記念協会の後援を受けて発行。
- リーヴェン、ドミニク (2006). 「レビュー記事:ロシアとナポレオンの敗北」.クリティカ:ロシア・ユーラシア史の探究. 7 (2): 283– 308. doi : 10.1353/kri.2006.0020 . S2CID 159982703 .
- マケラ・アリタロ、アンネリ (2006 年 5 月 5 日) [2005 年 11 月 10 日]。「メラースヴァルト、ウルリカ (1791–1878)」。kansallisbiografia (フィンランド国民伝記)。ISSN 1799-4349。
- モード、フレデリック・ナトゥシュ(1911年)ヒュー・チザム編『ブリタニカ百科事典』第19巻(第11版)ケンブリッジ大学出版局、223頁。
- マイオロヴァ、オルガ(2010年)『帝国の影から:文化神話を通してロシア国家を定義する 1855-1870』ウィスコンシン大学出版局、114頁。
- マンスーリ、フィルーズ(2008年)「17」アゼルバイジャンの歴史・言語・文化研究(ペルシア語)。テヘラン:ハザール・エ・ケルマーン。245頁。ISBN 978-600-90271-1-8。
- マッカフレー、スーザン・P. (2005). 「革命時代における農奴制への対峙:アレクサンドル1世時代の農奴改革プロジェクト」ロシア評論. 64 (1): 1– 21. doi : 10.1111/j.1467-9434.2005.00344.x . JSTOR 3664324 .
- マクグルー, RE (1992). 『ロシア皇帝パーヴェル1世:1754–1801』オックスフォード: オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19822-567-6。
- マクノートン、C. アーノルド (1973). 『列王記:王家の系譜』全3巻. 第1巻. ロンドン: ガーンストーン・プレス. pp. 293– 306.
- ミカベリゼ、アレクサンダー(2013年)『1814年戦役におけるロシアの目撃証言』フロントライン・ブックス、 225頁、ISBN 978-1-84832-707-8。
- ミハイロフスキー=ダニレフスキー、アレクサンダー(1839)『フランスにおける戦役史:1814年』スミス・エルダー社、 347~372頁。
- モンテフィオーレ、サイモン・セバグ(2016年)『ロマノフ家 1613–1918』オリオン出版グループISBN 978-0-297-85266-7。
- ニコルズ、アービー・C. (1982). 「皇帝アレクサンドル1世:平和主義者、侵略者、それとも優柔不断な人物か?」東ヨーロッパ季刊誌16 ( 1): 33–44 .
- ノーラン、キャサル・J. (2002). 『グリーンウッド国際関係百科事典:SZ』 . 『グリーンウッド国際関係百科事典』、キャサル. 第4巻(挿絵入り版). グリーンウッド出版グループ. p. 1666. ISBN 978-0-313-32383-6。
- オリヴィエ、ダリア(2019年12月19日)。「アレクサンドル1世|ロシア皇帝」ブリタニカ百科事典。
- パーマー、アラン(1974年)『アレクサンドル1世:戦争と平和の皇帝』ニューヨーク:ハーパー・アンド・ロウ社、ISBN 978-0060132644。
- ドナルド・J・ローリー編(1996年)『ロシアの皇帝と皇后:ロマノフ朝の再発見』MEシャープ、 252頁 。
- セバグ・モンテフィオーレ、サイモン(2016年)『ロマノフ家:1613-1918』クノップ・ダブルデイ出版グループ。
- 「ロシア帝国におけるジョージアの併合(1801–1878)」Tedsnet。2022年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月10日閲覧。
- トラスコット、ピーター(1997年)『ロシア第一:西側との決別』IBタウリス、 26頁 。
- ウォーカー、フランクリン・A (1992). 「皇帝アレクサンドル1世治世下のロシア教育における啓蒙と宗教」.教育史季刊誌. 32 (3): 343–360 . doi : 10.2307/368549 . JSTOR 368549. S2CID 147173682 .
- Yemelianova, Galina (2014年4月26日). 「イスラム教コーカサスにおけるイスラム教、ナショナリズム、国家」 . Caucasus Survey . 1 (2): 3– 23. doi : 10.1080/23761199.2014.11417291 . S2CID 128432463. 2014年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年4月28日閲覧。
- ザヴァツキ、ヒューバート (2009). 「ナポレオンと皇帝アレクサンドルの間:1807年ティルジットにおけるポーランド問題」.セントラルヨーロッパ. 7 (2): 110–124 . doi : 10.1179/147909609X12490448067244 . S2CID 145539723 .
帰属:
- この記事には、現在パブリックドメインとなっている出版物( Phillips, Walter Alison (1911). " Alexander I. ". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica . Vol. 1 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 556– 559.)からのテキストが含まれています。
さらに読む
- ハートリー、ジャネット・M.他編『ロシアとナポレオン戦争』(2015年)、新しい学術研究
- リーヴェン、ドミニク『ロシア対ナポレオン』(2011年)抜粋
- マコーネル、アレン著『皇帝アレクサンドル1世:父権主義的改革者』(1970年)オンライン無料貸出
- パーマー、アラン『アレクサンドル1世:戦争と平和の皇帝』(ワイデンフェルド&ニコルソン、1974年)
- レイ、マリー=ピエール『アレクサンドル1世:ナポレオンを倒した皇帝』(2012年)
- トロヤット、アンリ『ロシアのアレクサンダー』(ホッダー&スタウトン、1984年)
- ザヴァツキ、ヒューバート. 「ナポレオンと皇帝アレクサンドルの間:1807年ティルジットにおけるポーランド問題」『セントラル・ヨーロッパ』 7.2(2009年):110-124。
外部リンク
 ウィキメディア・コモンズにあるロシア皇帝アレクサンドル1世に関連するメディア
ウィキメディア・コモンズにあるロシア皇帝アレクサンドル1世に関連するメディア
- 1777年生まれ
- 1825人が死亡
- 19世紀のロシアの君主たち
- 19世紀のポーランドの君主たち
- ロシア皇帝
- フィンランドの国家元首
- ロシアの大公
- ロシアの皇太子
- ナポレオン戦争のロシアの指揮官
- ロシア皇帝アレクサンドル1世
- ホルシュタイン=ゴットルプ=ロマノフ家
- チフスによる死亡
- サンクトペテルブルクの聖ペトロ・パウロ大聖堂での埋葬
- ロシアにおける感染症による死亡者数
- 聖アンナ勲章一級受章者
- ガーター騎士団の仲間
- スペインの金羊毛騎士団
- レジオンドヌール勲章大十字章
- ウィリアム軍事勲章大十字勲章
- 剣騎士団大十字勲章
- キリスト騎士団大十字勲章(ポルトガル)
- アヴィス勲章大十字章
- 聖ヤコブ剣勲章グランドクロス
- マリア・テレジア軍事勲章騎士十字章
- ロシア皇帝パーヴェル1世の子供たち
- ロシア皇帝の息子たち
- ウィーン会議の参加者
- 伯爵の息子たち
- サンクトペテルブルク総督
- 露土戦争の人々(1806–1812)






















