ラテン教会
 ラテン教会 ラテン教会 | |
|---|---|
| エクレシア・ラティーナ | |
 | |
| タイプ | 特定の教会( sui iuris ) |
| 分類 | カトリック |
| オリエンテーション | 西洋キリスト教 |
| 聖書 | ノヴァ・ヴルガータ[ 1 ] |
| 神学 | カトリック神学 |
| 政治体制 | 聖公会[ 2 ] |
| ガバナンス | 聖座 |
| 法王 | レオ14世 |
| 完全な聖体拝領 | カトリック教会 |
| 地域 | 主に西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、アメリカ大陸、フィリピン、アフリカの一部、マダガスカル、オセアニア、そして世界中にいくつかの司教会議がある。 |
| 言語 | 教会ラテン語と現地語 |
| 典礼 | ラテン語の典礼 |
| 本部 | サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ大聖堂、ローマ、イタリア |
| 地域 | 全世界 |
| 起源 | 1世紀ローマ、ローマ帝国 |
| から分岐 | カトリック教会 |
| 分離 | |
| メンバー | 13億(2015年)[ 5 ] |
| その他の名前 |
|
| 公式サイト | バチカン |
 |
| シリーズの一部 |
| カトリック教会の管轄下にある特定教会 |
|---|
  |
| 特定の教会は典礼 によってグループ分けされている |
| アレクサンドリア典礼 |
| アルメニア典礼 |
| ビザンチン典礼 |
| 東シリア典礼 |
| ラテン語の典礼 |
| 西シリア典礼 |
東方カトリック教会東方カトリック典礼カトリックポータルキリスト教ポータル  |
 |
| シリーズの一部 |
| カトリック教会 |
|---|
 |
| 概要 |
 カトリック教会ポータル カトリック教会ポータル |
| シリーズの一部 |
| キリスト教 |
|---|
 |
ラテン教会(ラテン語:Ecclesia Latina )は、カトリック教会の中で最大の自治(sui iuris)分派教会であり、13億人のカトリック信者の大半を占めています。ラテン教会は、教皇と完全な交わりを持つ24の自治教会の一つです。他の23の教会は東方カトリック教会と総称され、合わせて約1,800万人の信者を有しています。[ 6 ]
ラテン教会はローマ司教である教皇が直接率いており、その司教座はイタリア、ローマのサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ大聖堂にある。ラテン教会は西洋文化の中で発展し、強い影響を与えた。そのため、西方教会(ラテン語:Ecclesia Occidentalis)と呼ばれることもあり、これは時代や文脈によって教皇に伝統的につけられる称号の一つである西方総主教に反映されている。[ 7 ]また、ローマ教会(ラテン語:Ecclesia Romana)、[ 8 ] [ 9 ]ラテンカトリック教会、[ 10 ] [ 11 ]、また文脈によってはローマカトリック教会(この名称はカトリック教会全体を指す場合もある)としても知られている。[ 12 ] [ b ]
ラテン教会は、1054年にローマとコンスタンティノープルで東西教会の分裂が起こるまで、いわゆる東方正教会と完全な交わりを保っていました。その時から、そしてそれ以前から、西方キリスト教徒をビザンチン人やギリシャ人と対比してラテン人と呼ぶことが一般的になりました。
ラテン教会はラテン典礼を採用しており、20世紀半ば以降、これらは非常に頻繁に現地語に翻訳されています。主要な典礼はローマ典礼であり、その要素は4世紀から実践されてきました。[ 13 ]古代から、現在スペインで限定的に使用されているモサラベ典礼、イタリアの一部で使用されているアンブロジオ典礼、そして個人教区における英国国教会の典礼など、ラテン典礼の追加の典礼や使用法が存在してきました。
近世初期およびその後、ラテン教会はアメリカ大陸、そして近世後期にはサハラ以南アフリカと東アジアに福音伝道活動を展開した。16世紀の宗教改革によりプロテスタントは分裂し、西方キリスト教は分裂した。これにはラテン教会から派生したプロテスタント諸派だけでなく、19世紀に分裂した独立カトリック諸宗派の小集団も含まれる。
用語
名前
西方カトリック教会の歴史的部分は、同じく教皇の首位権下にある東方カトリック教会と区別するために、ラテン教会と呼ばれています。歴史的文脈では、 1054年の東西教会分裂以前は、ラテン教会は西方教会と呼ばれることもありました。様々なプロテスタント教派に属する著述家は、暗黙の正統性を示すために「西方教会」という用語を使用することがあります。
ラテン・カトリックとは、ラテン典礼の信奉者を指し、その中でもローマ典礼が主流です。ラテン典礼は、東方カトリック教会の典礼とは対照的です。
「教会」と「儀式」
1990年の東方教会法典は、同法典における「教会」および「典礼」という語の使用を定義しています。[ 14 ] [ 15 ]東方カトリック教会を統治する法典におけるこれらの用法の定義によれば、ラテン教会は、位階制によって結ばれ、カトリック教会の最高権威によって「sui iuris 」と呼ばれる特定の教会として認められているキリスト教信者の集団の一つです。「ラテン典礼」とは、その特定の教会の遺産全体であり、それによって教会は、独自の典礼、神学、霊的実践と伝統、そして教会法を含む、信仰の生き方を表明します。カトリック教徒は、個人として、必然的に特定の教会の会員となります。また、人は特定の遺産または典礼を継承する、あるいは「属する」[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]とも言えます。儀式には典礼的、神学的、精神的、規律的な要素があるため、人は特定の儀式に従って崇拝し、教理教育を受け、祈り、規律を受けることも必要です。
特定の教会が特定の聖職を継承し、永続させる場合、「教会」または「典礼」という換喩表現によって識別されます。したがって、「典礼」は「独特の典礼を用いるキリスト教会の一派」 [ 21 ]、あるいは単に「キリスト教会」[ 22 ]と定義されています。この意味で、「典礼」と「教会」は同義語として扱われます。これは、米国カトリック司教会議が作成し、1999年に改訂された用語集で述べられているように、「東方典礼(オリエント典礼)教会は…教会内においてラテン典礼と同等とみなされる」というものです。[ 23 ]第二バチカン公会議も同様に、「カトリック教会の精神は、個々の教会または典礼がその伝統を完全に保持し、同様に、その生き方を時代と場所の様々な必要性に適応させることである」と述べ[ 24 ]、総主教と「個々の教会または典礼全体を統括する大司教」について言及した[ 25 ] 。したがって、「典礼」という言葉は「現在特定の教会と呼ばれるものの技術的な名称」として用いられた[ 26 ] 。「教会または典礼」は、米国議会図書館の著作分類においても単一の見出しとして用いられている[ 27 ] 。
歴史
歴史的に、ラテン教会の統治機関(すなわち聖座)は、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、アンティオキア、エルサレムの総主教区とともに、初期キリスト教の五大総主教区の一つとみなされてきました。地理的および文化的配慮から、これらの総主教区は、独自の東方キリスト教の伝統を持つ教会へと発展しました。この体系は、少なくともローマによって暗黙のうちに受け入れられていますが、ギリシャキリスト教の観点から構築されており、ローマ帝国の国境外で東方で発展した他の古代の教会を考慮に入れていません。東方キリスト教会の大多数は、451年のカルケドン公会議後の数世紀にわたる様々な神学上および管轄権上の論争の結果、ローマ司教およびラテン教会との完全な交わりを断った。これらには、ネストリウス派分裂(431-544年)(東方教会)、カルケドン派分裂(451年)(東方正教会)、および東西分裂(1054年)(東方正教会)が含まれる。[ 28 ] 16世紀のプロテスタント宗教改革では、同じ歴史的要因に基づいておらず、以前から存在していた歴史的キリスト教会全体の教えからのはるかに深刻な神学的な反対を伴ったため、類似しない分裂が見られた。2006年まで、教皇は「西方の総大主教」という称号を主張していたが、ベネディクト16世はこの称号を放棄した。 2024年、フランシスコ教皇は西方総主教を教皇の正式な称号の一つとして復活させた。[ 29 ]
イスラムの征服後、1095年から1291年にかけて、西洋諸国は聖地におけるキリスト教徒とその財産を迫害から守るために十字軍を派遣しました。十字軍は長期的にはパレスチナの政治的・軍事的支配を再確立することに成功せず、パレスチナはかつてのキリスト教国であった北アフリカやその他の中東地域と同様に、イスラムの支配下に置かれました。この広大な地域にあった多くのかつてのキリスト教教区の名称は、典礼家族の問題とは無関係に、カトリック教会によって今もなおカトリックの名目上の教区の名称として使用されています。
中世盛期には、ラテン教会においてスコラ哲学の発展が始まり、アリストテレスなどの古典ギリシャ文学の再発見とキリスト教の調和が図られました。その下、トマス・アクィナスやカンタベリーのアンセルムスといった新しい神学者が登場し、信仰と理性は矛盾なく存在し得ると信じました。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
大航海時代、ラテン教会はスペインとポルトガルの植民地支配下でアメリカ大陸とフィリピンに広がり、教皇アレクサンデル6世は教皇勅書「インター・カエテラ」で両国に植民地権を与えた。[ 33 ] 16世紀に始まった フランスによるアメリカ大陸の植民地化により、ケベックにフランス・ラテン教会が設立された。[ 34 ]
メンバーシップ
カトリック教会には、ラテン教会(ラテン総主教である教皇が直接率いており、西方キリスト教では聖なる伝統と7つの秘跡で有名)に加えて、独自の位階制を持つ自治権を持つ部分教会である東方カトリック教会が23ある。これらの教会のほとんどは、古代五大聖職者制の他の4つの総主教区に起源を遡れるが、歴史的に教皇との完全な交わりを断ったことはなく、ある時点で教皇との完全な交わりに戻った。これらは、典礼儀礼(儀式、祭服、聖歌、言語)、信心の伝統、神学、教会法、聖職者において互いに異なるが、すべて同じ信仰を維持し、ローマ司教である教皇との完全な交わりはカトリック教徒であるための必須事項であり、カトリック教会論における教会の4つの特徴によって定義される唯一の真の教会の一部であると考えている。
約1,800万人の東方カトリック教徒は、ローマ教皇と交わりを持つキリスト教徒の中では少数派である[ 6 ] 。一方、ラテンカトリック教徒は10億人を優に超える。さらに、世界中にはローマと合流していない東方正教会が約2億5,000万人、東方正教会が約8,600万人存在する。ラテン教会とは異なり、教皇は東方カトリック教会とその信者に対して直接的な家父長的役割を担うのではなく、むしろ内部の階層構造を奨励している。これらの階層構造はラテン教会の階層構造とは独立しているものの、ラテン教会と同様に機能し、東方正教会と東方正教会における東方キリスト教会と共通の伝統に従っている[ 28 ] 。
組織
典礼遺産
ジョセフ・ラッツィンガー枢機卿(後の教皇ベネディクト16世)は、1998年10月24日にラテン語の典礼について次のように述べた。 [ 35 ]
ラテン典礼にはいくつかの形態が常に存在し、ヨーロッパの様々な地域が統合された結果、徐々に廃れていった。公会議以前には、ローマ典礼と並んで、アンブロジオ典礼、トレドのモサラベ典礼、ブラガ典礼、カルトジオ典礼、カルメル会典礼、そして最もよく知られているドミニコ典礼が存在していた。おそらく他にも、私が知らない典礼があったかもしれない。
今日、最も一般的なラテン語典礼は、ローマ典礼(1969年に教皇パウロ6世によって公布され、 2002年に教皇ヨハネ・パウロ2世によって改訂された第2バチカン公会議後のミサ( 「通常形式」)、または1962年のトリエントミサ(「臨時形式」)、アンブロジオ典礼、モサラベ典礼、そしてローマ典礼の変種(英国国教会典礼など)である。23の東方カトリック教会は、 5つの異なる典礼様式を採用している。ラテン語典礼は、単一の「sui iuris」個別教会 でのみ用いられる。
その他の典礼系統のうち、現在も主に残っているのは、現在公式にイスパノ・モサラベ典礼と呼ばれ、スペインで限定的に使用されているもの、イタリアのミラノ大司教区を地理的に中心とし、形式はローマ典礼に近いが内容は特異ではないアンブロジオ典礼、そして厳格なカルトジオ会修道会内で実践されているカルトジオ典礼で、一般的にはローマ典礼に類似した形式を採用しているが、カルトジオ会独特の生活様式に適応させた重要な相違点がいくつかある。
かつてガリアやフランクの領土で用いられていたガリア典礼と呼ばれるものが存在しました。これは様々な形態の集合体であり、その一般的な構造は現在のイスパノ・モサラベ典礼と似てはいましたが、厳密に体系化されたことはなく、少なくとも7世紀以降はローマ教区に起源を持つ典礼文や典礼形式に徐々に浸透し、最終的には大部分が置き換えられました。過去に特定の修道会や主要都市で行われていた他の「典礼」は、実際にはローマ典礼の部分的な変種であることが多く、一部の復活に向けた限定的な懐古主義的な努力やローマ当局による一定の寛容にもかかわらず、現在ではほぼ完全に姿を消しています。
懲戒遺産
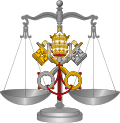 |
| シリーズの一部 |
| カトリック教会の教会法 |
|---|
 カトリックポータル カトリックポータル |
ラテン教会の教会法は教会法典に成文化されており、教会法典には2つの成文化があり、最初のものは1917年にベネディクト15世によって公布され、2番目のものは1983年にヨハネ・パウロ2世によって公布されました。 [ 36 ]
ラテン教会における堅信礼の執行基準は、死の危険にさらされている場合を除き、堅信を受ける者は「理性を持ち、適切な教育を受け、適切な心構えを持ち、洗礼の誓約を更新できる」こととされている[ 37 ]。また、「子供への聖体拝領の執行には、十分な知識と綿密な準備が求められ、能力に応じてキリストの神秘を理解し、信仰と献身をもってキリストの御体を受け入れることができることが必要である」とされている[ 38 ]。東方教会では、これらの秘跡は通常、幼児であっても洗礼直後に執行される[ 39 ] 。
完全な節制を守る義務の結果として、独身制はラテン教会の司祭に義務付けられている。 [ 40 ]他の教会からカトリック教会に入会した既婚の聖職者には例外が設けられ、彼らは既婚の司祭として続けることができる。[ 41 ]ラテン教会では、既婚男性は、司祭にならず助祭のままでいることが合法的に定められていない限り、助祭の職に就くことさえ認められない。[ 42 ]叙階後の結婚は不可能であり、それを試みることは教会法上の罰則につながる可能性がある。[ 43 ]ラテン教会とは異なり、東方カトリック教会には既婚の聖職者がいる。
現在、ラテン教会の司教は、一般的にローマ教皇庁の様々な部局、具体的には司教省、福音宣教省(管轄国の場合)、国務省対外関係部(行政機関の同意または事前通知を必要とする任命の場合)、東方教会省(管轄地域の場合、ラテン司教の任命も含む)の助言を聞いた後、教皇によって任命されます。省は通常、「テルナ」、つまり地方教会から提出された3人の候補者名簿に基づいて任命を行います。これは、教皇大使または司教座聖堂参事会(司教座聖堂参事会が司教を指名する権利を有する地域の場合)を通じて提出されることが多いです。
神学と哲学
アウグスティヌス主義

ヒッポのアウグスティヌスは、ローマ・アフリカ出身の哲学者であり、カトリック教会の司教でした。彼はラテン・キリスト教の形成に貢献し、教父時代の著作によりラテン教会において最も重要な教父の一人とされています。彼の著作には、 『神の国』、『キリスト教の教義について』、『告白』などがあります。
若い頃はマニ教に、後に新プラトン主義に傾倒した。386年に洗礼を受け改宗した後、アウグスティヌスは様々な方法論と視点を取り入れながら、独自の哲学と神学のアプローチを展開した。[ 44 ]キリストの恩寵が人間の自由に不可欠であると信じ、原罪の教理の定式化に貢献し、正戦論の発展に重要な貢献をした。彼の思想は中世の世界観に深く影響を与えた。ニカイア公会議とコンスタンティノープル公会議で定義された三位一体の概念を信奉した教会の一部[ 45 ]は、アウグスティヌスの『三位一体論』と密接に結びついていた。
西ローマ帝国が崩壊し始めると、アウグスティヌスは教会を物質的な地上の都市とは区別される、霊的な神の都市として構想した。 [ 46 ]著書『神の都市について』 (しばしば『神の都市』と呼ばれる)の中で、アウグスティヌスは教会のメッセージは政治的なものではなく、霊的なものであると宣言した。キリスト教は地上の政治ではなく、神秘的な天上の都市、新エルサレムに関心を持つべきだと彼は主張した。
『神の都』は、人類史をアウグスティヌスが「地上の都」(口語ではしばしば人間の都と呼ばれるが、アウグスティヌス自身は決してそう呼ばない)と「神の都」との間の闘争として描き、この闘争は最終的に後者の勝利に終わる運命にあるとしている。神の都は、地上の享楽を捨て、キリスト教信仰において完全に啓示された神の永遠の真理に身を捧げる人々によって特徴づけられる。一方、地上の都は、過ぎ去りゆく現世の煩悩と享楽に浸りきった人々によって構成されている。

アウグスティヌスにとって、ロゴスはキリストにおいて「肉体を帯び」、他の誰にも見られないロゴスがキリストに存在した。[ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]彼は中世初期のキリスト教哲学に強い影響を与えた。[ 50 ]
アテナゴラス[ 51 ] 、テルトゥリアヌス[ 52 ] 、アレクサンドリアのクレメンス、カイサリアのバシレイオス[ 53 ]などの他の教父と同様に、アウグスティヌスは「人工妊娠中絶の習慣を強く非難し」、妊娠のどの段階でも妊娠中絶を認めなかったものの、早期妊娠中絶と後期妊娠中絶を区別していました。[ 54 ]彼は、七十人訳の出エジプト記21章22-23節に記載されている「形成された」胎児と「形成されていない」胎児の区別を認めたが、これは元のヘブライ語テキストの「害」をギリシャ語七十人訳の「形」と誤訳したもので、アリストテレスの「胎児の『生命化』前と後」の区別に基づいていると考えられており、「形成されていない」胎児の堕胎は、胎児がすでに魂を与えられたとは確実に言えないと考えていたため、殺人とは分類しなかった。[ 54 ] [ 55 ]
アウグスティヌスもまた、 「真の」教会を異端のグループと 区別するために「カトリック」という用語を使用しました。
カトリック教会には、私をその懐に留めておく最も正当なものが他にも数多くあります。諸国民の同意が私を教会に留めています。奇跡によって始まり、希望によって養われ、愛によって拡大され、時代によって確立された教会の権威も同様です。司祭の継承も私を留めています。使徒ペトロの座に始まり、主が復活後、羊を養う責任を委ねられた(ヨハネ21:15-19)現在の司教職にまで至るのです。
そして最後に、カトリックという名称自体も、多くの異端が存在する中で、教会がこのように保持してきたのには理由があります。そのため、すべての異端者はカトリック教徒と呼ばれることを望んでいますが、見知らぬ人がカトリック教会がどこで集会を行っているか尋ねても、自分の礼拝堂や家を指差そうとする異端者はいません。
キリスト教徒の名に属する貴重な絆は、その数と重要性において、信者をカトリック教会に留めておくものであり、それは当然のことです。…あなたと共にいれば、私を惹きつけたり留めたりするものは何もないでしょう。…私の心をキリスト教という数多くの、そして強い絆で結ぶ信仰から、私を引き離すことは誰にもできません。…私自身としては、カトリック教会の権威に動かされない限り、福音を信じません。
- — 聖アウグスティヌス(354–430):「根本主義と呼ばれるマニカイオスの手紙に対する反論」第4章「カトリック信仰の証明」[ 56 ]
_-_The_Four_Doctors_of_the_Western_Church,_Saint_Augustine_of_Hippo_(354–430).jpg/440px-Gerard_Seghers_(attr)_-_The_Four_Doctors_of_the_Western_Church,_Saint_Augustine_of_Hippo_(354–430).jpg)
アウグスティヌスは哲学的・神学的思考の両面でストア哲学、プラトン主義、新プラトン主義、特に『エネアデス』の著者プロティノスの著作に多大な影響を受けており、これはおそらくポルピュリオスとウィクトリノスの仲介によるものと思われる(ピエール・アドットの主張による)。後に彼は新プラトン主義を放棄したが、初期の著作には依然としていくつかの考えが見られる。[ 57 ]倫理学の中心的なテーマである人間の意志に関する彼の初期の影響力のある著作は、ショーペンハウアー、キルケゴール、ニーチェといった後の哲学者たちの焦点となる。彼はまた、ウェルギリウス(言語に関する教えで知られる)やキケロ(議論に関する教えで知られる)の著作の影響も受けている。 [ 58 ]
東方では、彼の教えは論争の的となっており、特にヨハネス・ロマニデスによって攻撃された。[ 59 ]しかし、東方正教会の他の神学者や著名人、とりわけジョルジュ・フロロフスキーは、彼の著作を高く評価している。[ 60 ]彼に関連する最も議論を呼んだ教義であるフィリオクエ[ 61 ]は、正教会によって異端として拒絶された[ 62 ]。その他の論争を呼んだ教えには、原罪、恩寵の教理、予定説などがある。[ 61 ]しかし、いくつかの点で間違っていると考えられているにもかかわらず、彼は依然として聖人とみなされており、東方教会の教父、最も有名なのはギリシャの神学者グレゴリー・パラマス[ 63 ]に影響を与えた。正教会では、彼の祝日は6月15日である。[ 61 ] [ 64 ]歴史家ダイアミッド・マカロックは次のように書いている。「[アウグスティヌスの]西洋キリスト教思想への影響は計り知れない。彼の愛した模範であるタルソスのパウロだけがそれよりも影響力があり、西洋人は一般的にアウグスティヌスの目を通してパウロを見てきた。」[ 65 ]
教皇ベネディクト16世は、自伝的著書『マイルストーンズ』の中で、アウグスティヌスが自身の思想に最も深い影響を与えた人物の一人であると主張している。
スコラ哲学

スコラ哲学は、学者(「スコラ学者」または「スクールマン」)による教育を支配した批判的思考の方法である。1100年から1700年頃にかけてヨーロッパで中世の大学が設立されたことを考えると、13世紀から14世紀初頭はスコラ哲学の最盛期とみなされる。13世紀初頭はギリシャ哲学復興の頂点を極めた時期であった。イタリアやシチリア島で翻訳学校が発達し、やがてヨーロッパ全土に広がった。有力なノルマン王たちは、権威の証としてイタリアやその他の地域の知識人を宮廷に集めた。[ 66 ] 13世紀半ばのモルベケのウィリアムによるギリシャ哲学文献の翻訳と版は、それまで依拠していたアラビア語版よりも、ギリシャ哲学、特にアリストテレスの像をより鮮明に描くのに役立った。エドワード・グラントは次のように書いている。「アラビア語の構造はラテン語とは根本的に異なっているだけでなく、アラビア語版の中にはシリア語への翻訳に由来するものもあり、元のギリシャ語本文とは二重にかけ離れているものもあった。このようなアラビア語本文を逐語的に翻訳すると、難解な読み方になってしまう可能性があった。対照的に、ラテン語はギリシャ語と構造的に近似していたため、逐語的ではあるが理解しやすい逐語訳が可能だった。」[ 67 ]
この時期、ヨーロッパの大都市で大学が発達し、教会内で対立する聖職者会は、これらの教育の中心地に対する政治的、知的支配をめぐって争い始めた。この時期に設立された二つの主要な修道会は、フランシスコ会とドミニコ会である。フランシスコ会は、 1209年にアッシジのフランチェスコによって設立された。18世紀半ばの彼らの指導者は、アウグスティヌス神学とプラトン哲学を擁護し、アリストテレスを少しだけ新プラトン主義の要素に取り入れた伝統主義者のボナヴェントゥラであった。アンセルムスに倣い、ボナヴェントゥラは、哲学が宗教的信仰によって照らされたときにのみ、理性が真理を発見できると考えた。[ 68 ]他の重要なフランシスコ会のスコラ学者には、ドゥンス・スコトゥス、ピーター・オリオール、オッカムのウィリアムがいる。[ 69 ] [ 70 ]
トマス主義



聖トマス・アクィナス[ 71 ] [ 72 ]はイタリアのドミニコ会修道士、哲学者、司祭であり、スコラ哲学の伝統に多大な影響を与え、その中では「天使博士」や「コムニス博士」としても知られています。[ 73 ]
アキナスは「シンデレシスは人間の行動の第一原理である自然法の教訓を含む習慣であるため、私たちの心の法則であると言われています」と強調しました。[ 74 ] [ 75 ]
アキナスによれば、「…すべての徳行は自然法によって規定されている。なぜなら、各人の理性は自然に徳行を行うよう命じるからである。しかし、徳行をそれ自体、すなわちその本来の種において考察すると、すべての徳行が自然法によって規定されているわけではない。なぜなら、自然が当初は好まない徳行も多く行われているが、理性の探求を通して、人々が善い生活に役立つと見いだしたからである。」したがって、私たちは徳行を徳という側面から語っているのか、それともその種の行為として語っているのかを判断する必要がある。[ 76 ]
トマスは四つの枢要徳を、思慮分別、節制、正義、不屈の精神と定義した。枢要徳は自然で自然に現れるものであり、すべての人に適用される。しかし、神学上の徳として、信仰、希望、慈愛の三つがある。トマスはまた、これらの徳を不完全(不完全)な徳と完全(完全)な徳と呼んでいる。完全徳とは、慈愛を伴う徳であり、慈愛が枢要徳を完成させる。非キリスト教徒は勇気を示すことができるが、それは節制を伴う勇気であろう。キリスト教徒は慈愛を伴う勇気を示すであろう。これらはいくぶん超自然的であり、その対象、すなわち神において他の徳とは異なる。
さて、神学的徳性の対象は、すべてのものの究極目的である神ご自身であり、私たちの理性の認識を超越しています。一方、知的徳性および道徳的徳性の対象は、人間の理性によって理解できるものです。したがって、神学的徳性は、道徳的徳性および知的徳性から明確に区別されます。[ 77 ]
トマス・アクィナスはこう書いている。「[貪欲]は、人間が現世のもののために永遠のものを非難する限りにおいて、すべての大罪と同様に、神に対する罪である。」[ 78 ]
アキナスは倫理と正義の側面として経済思想にも貢献した。彼は「適正価格」という概念、つまり通常は市場価格、あるいは販売者の生産コストをカバーするのに十分な規制価格を論じた。彼は、単に買い手が商品を切実に必要としているという理由だけで販売者が価格を上げるのは不道徳であると主張した。[ 79 ] [ 80 ]
アクィナスは後に、黄金律を根拠として、貿易における不当な利益に反対する議論を展開した。キリスト教徒は「他人にしてもらいたいように他人にもしてやれ」、つまり価値と価値を交換するべきだと考えた。アクィナスは、特定の買い手が販売されている商品を緊急に必要としており、かつ現地の状況によってより高い価格を支払うよう説得される可能性があるという理由で価格を上げることは、特に不道徳であると信じた。
- もし誰かが他人の所有物によって大いに助けられ、そして売り手はそれを失っても同様に損害を受けないのであれば、売り手はより高い価格で売ってはならない。なぜなら、買い手にとっての有用性は売り手からではなく、買い手の困窮状態から来るからである。誰も自分の所有物でないものを売るべきではない。[ 81 ]
- — 『神学総論』、2-2、q. 77、芸術。 1
したがって、アキナスは自然災害の後に建築資材の価格を引き上げるといった行為を非難するだろう。既存の建物の破壊によって引き起こされる需要の増加は売り手のコストを増加させるものではないため、買い手の支払い意欲の高まりを利用することは、アキナスの見解では一種の詐欺行為を構成する。[ 82 ]
5つの方法
アキナスは『神学大全』と『反異邦人大全』の中で、神の存在を証明する5つの論拠、いわゆる「五つの道」を提示した。[ 83 ] [ 84 ]彼はまた、5つの神の性質を列挙したが、いずれも否定的な表現で示した。[ 85 ]
インパクト
アキナスはスコラ哲学を新プラトン主義からアリストテレスへと転換させました。この学派は、ラテンキリスト教とカトリック学派の倫理学に影響を与え、歴史上最も影響力のある哲学の一つであり、その教えを実践する人々の多さからも重要な意味を持っています。
神学においては、彼の『神学大全』は中世神学において最も影響力のある文書の一つであり、20世紀に至るまでラテンキリスト教の哲学と神学の中心的な参照点であり続けました。1914年の回勅『天使博士』[ 86 ] において、教皇ピウス10世は、トマス・アクィナスの主要テーゼの基本的な哲学的基盤なしにはカトリック教会の教えを理解することはできないと警告しました。
聖トマス哲学における大原則は、議論の余地のある意見の範疇に入るものではなく、自然と神に関するすべての学問の基礎となるものである。もし、このような原理が一旦無視されたり、何らかの形で損なわれたりすれば、必然的に、神学の研究者は、教会の権威によって提示された神の啓示の教義の言葉の意味さえも理解できなくなるであろう。[ 87 ]
第二バチカン公会議はアキナスの体系を「永遠の哲学」と表現した。[ 88 ]
アクトゥス・プルス
アクトゥス・プルス(行為)とは、神の絶対的な完全性である。スコラ哲学によれば、被造物は潜在性、すなわち現実性ではなく、完全性だけでなく不完全性も持つ。神だけが、無限に現実的であり、無限に完全であると同時に、その存在し得る全てである。「我は我なり」(出エジプト記3:14 )神の属性、あるいは神の働きは、神の本質と真に同一であり、神の本質は神の存在を必然的に必要とする。
本質とエネルギーの区別の欠如
その後、東方正教会の禁欲主義者でテッサロニキ大司教であった(聖)グレゴリウス・パラマスは、ヘシュカスト精神、変容の光の非創造的性質、そして神の本質とエネルギーの区別を擁護する論を展開した。彼の教えは、(1) 1336年から1341年にかけてのイタリア系ギリシャ人バルラムとの論争、(2)1341年から1347年にかけての修道士グレゴリウス・アキンディノスとの論争、そして(3)1348年から1355年にかけての哲学者グレゴラスとの論争という、3つの主要な論争を経て展開された。彼の神学的な貢献はパラミズム、そして彼の信奉者たちはパラミテスと呼ばれることがある。
歴史的にラテンキリスト教はパラマス主義、特に本質とエネルギーの区別を拒絶する傾向があり、時にはそれを三位一体に受け入れがたい分裂を持ち込む異端的なもの、多神教を示唆するものと特徴づけてきた。[ 89 ] [ 90 ]さらに、神化を達成するために用いられるヘシュカズム(神への帰依)という関連する実践は「魔術」と特徴づけられた。[ 91 ] [ 92 ]近年では、一部のローマ・カトリックの思想家が、本質とエネルギーの区別を含むパラマスの教えを肯定的に捉え、それがローマ・カトリックと東方正教会の間に克服できない神学的分裂を生じさせるものではないと主張している。[ 93 ]また、ローマと交わりを持つ一部のビザンチン・カトリック教会では、聖人としての彼の祝日が祝われている。[ 94 ] [ 95 ]
マーティン・ジュジーによれば、西側諸国と、西側諸国との統合を望んだ東側諸国(「ラテン語派」)によるパラミズムの拒絶は、実際には東側諸国におけるパラミズムの受容に貢献した。彼はさらに次のように付け加えている。「間もなく、多くの人々の心の中で、ラテン語主義と反パラミズムは同一のものとして見られるようになるだろう」[ 96 ]
フィリオクエ
フィリオクエは、ニカイア信条の原文に付け加えられたラテン語であり、東方キリスト教と西方キリスト教の間で大きな論争の的となってきました。この語は、コンスタンティノープル公会議(381年)に帰せられる原文には含まれていません。この信条は、聖霊は「父から」発せられると述べており、「そして子と共に」や「のみ」といったいかなる付加語も含まれていません。 [ 97 ]
フィリオクエという語句は、西ゴート王国スペインがアリウス派を放棄し、カトリックのキリスト教を受け入れた第三トレド公会議(589年)の信条に、反アリウス派[98] [99]として挿入されたものとして初めて登場する。この公会議で、西ゴート王国スペインはアリウス派を放棄し、カトリックのキリスト教を受け入れた。この追加はその後のトレド地方公会議で確認され、すぐに西方全域に広まり、スペインだけでなく、496年にカトリックの信仰を受け入れたフランク王国[ 100 ]や、 680年にハットフィールド公会議が単意論への対応としてイングランドにも広まった[ 101 ]。しかし、ローマでは採用されなかった。
6世紀後半、一部のラテン教会は聖霊降臨の描写に「そして御子から」(フィリオクェ)という言葉を加えたが、多くの東方正教会は後に、この言葉が第一ニカイア公会議にもコンスタンティノープル公会議にもテキストに含まれていなかったため、エフェソ公会議第7条に違反していると主張した。[ 102 ]これは1014年にローマの典礼慣行に組み込まれたが、[ 103 ]東方キリスト教では拒否された。
フィリオクエという用語が含まれるかどうか、そしてそれがどのように翻訳され理解されるかは、大多数のキリスト教会の中心となる三位一体の教義をどのように理解するかに重要な意味を持つ可能性があります。ある人々にとって、この用語は三位一体における父なる神の役割を著しく過小評価することを意味します。また、他の人々にとって、この用語が表す内容を否定することは、三位一体における子なる神の役割を著しく過小評価することを意味します。
フィリオクエというフレーズは、典礼でギリシャ語が使われている場合を除いて、すべてのラテン語典礼の信条に含まれていますが、[ 104 ] [ 105 ]、東方カトリック教会では採用されませんでした。[ 106 ]
煉獄

ラテンキリスト教のもう一つの教義は煉獄である。ラテンキリスト教はこれについて、「神の恵みと友愛の中で死にながらも、まだ完全に浄化されていない者」は、カトリック教会が煉獄と呼ぶ浄化の過程を経ると考えており、「天国の喜びに入るために必要な聖性を得る」としている。カトリック教会はこの教義を、浄化の火について語る聖書の節(コリントの信徒への手紙一 3:15、ペトロの手紙一 1:7)と、イエスが来世における赦しについて述べたこと(マタイによる福音書 12:32 )に基づいて定式化した。また、教会が始まって以来、教会内で行われてきた死者のための祈りの実践、そしてさらに以前、マカベア第二 12:46にも言及されている実践にもその教えの根拠を置いている。[ 107 ] [ 108 ]
煉獄の概念は古代にまで遡ります。プラトンやヘラクレイデス・ポンティコス、そして他の多くの異教の著述家たちの著作には、「天上のハデス」と呼ばれる一種の原始的な煉獄が登場します。この概念は、ホメロスやヘシオドスの著作に描かれた冥界のハデスとは区別されます。対照的に、天上のハデスは、魂が死後、より高次の存在レベルへと移行するか、地上に転生するまでの不確定な時間を過ごす中間地点として理解されていました。その正確な位置は著述家によって異なりました。ポントスのヘラクレイデスは天の川銀河にあると考えました。アカデメイア派、ストア派、キケロ、ウェルギリウス、プルタルコス、そしてヘルメス文書は、月と地球の間、あるいは月の周囲にあると考えました。一方、ヌメニウスとラテン新プラトン主義者たちは、恒星圏と地球の間にあると考えました。[ 109 ]
おそらくヘレニズム思想の影響を受けて、中間状態は紀元前最後の数世紀にユダヤ教の宗教思想に取り入れられました。マカバイ記には、死者の来世での浄化を願って死者のために祈るという慣習が見られ、[ 110 ]一部のキリスト教徒にも受け入れられていました。同様の慣習は他の伝統にも見られ、例えば中世中国仏教では、死者は数々の試練を受けるとされ、死者のために供物を捧げる慣習が見られます。[ 111 ]西方カトリックにおける煉獄の教えは、キリスト教以前(ユダヤ教)の死者のための祈りの慣習に基づいているという点も挙げられます。[ 112 ]

死後の浄化や、祈りを通じた生者と死者の交わりに対する信仰の具体例は、多くの教父の著作に見られる。[ 113 ]エイレネオス( c. 130–202 ) は、死者の魂が審判まで留まる場所について言及しており、この過程は「煉獄の概念を含む」とされている。[ 114 ]アレクサンドリアのクレメンス( c. 150–215 ) とその弟子のアレクサンドリアのオリゲネス( c. 185–254 )はともに、死後の浄化についての見解を展開した。[ 115 ]この見解は、火は神の道具であるという旧約聖書の観念に基づき、これを新約聖書の教え、例えば福音書の火による洗礼や聖パウロの死後の浄化の試練という文脈で理解した。[ 116 ]オリゲネスは魂の眠りに反対して、選ばれた者の魂は、まだ浄化されていない限り、直ちに楽園に入るが、浄化されていない場合は、罰の状態、すなわち浄化の場として考えられる刑罰の火に入ると述べた。[ 117 ]クレメンスとオリゲネスの両者にとって、火は物質的なものでも比喩でもなく、「霊的な火」であった。[ 118 ]初期のラテン語著者テルトゥリアヌス(c. 160–225)もまた、死後の浄化の見解を明確に述べた。[ 119 ]テルトゥリアヌスの死後の世界の理解では、殉教者の魂は永遠の祝福に直接入り、[ 120 ]残りの魂は死者の一般的な領域に入った。そこで悪人は永遠の罰を予感させられ、[ 120 ]善人は様々な段階と至福の場所を体験した。そこには「一種の煉獄という考え方が…非常に明確に見出される」が、これは古代に広く流布していた見解の代表である。[ 121 ]後世の例には、さらに詳しく説明されている聖キプリアヌス(258年没)[ 122 ] 、聖ヨハネ・クリュソストムス( 347年頃 -407年)[ 123 ] 、聖アウグスティヌスなどが挙げられる。(354–430)[ 124 ]など。
6 世紀後半に書かれた教皇グレゴリウス 1 世の対話は、ラテンキリスト教世界が辿る 方向性を特徴づける、来世に関する理解の発展を示しています。
軽微な過ちについては、最後の審判の前に浄化の火があることを信じなければなりません。真理なる方は、聖霊を冒涜する者はこの世でも来世でも赦されないと言っています。この言葉から、ある種の過ちはこの世で赦されますが、他のある種の過ちは来世で赦されないことがわかります。[ 125 ]
煉獄についての推測と想像

カトリックの聖人や神学者の中には、煉獄についてカトリック教会が採用している考え方を超えて、時に矛盾した考えを持つ者もいる。それは、特定の場所で、特定の期間、実際の火による浄化という概念を含む、一般的なイメージを反映し、あるいはそれに貢献している。ポール・J・グリフィスは次のように述べている。「近年のカトリックにおける煉獄に関する考えは、典型的には、基本的な教義の本質を保ちつつも、同時にそれらの要素について間接的な思弁的解釈を提供している。」[ 126 ]また、ヨゼフ・ラッツィンガーは次のように述べている。「煉獄は、テルトゥリアヌスが考えていたような、人間が多かれ少なかれ恣意的に罰を受けさせられる、超世俗的な強制収容所のようなものではない。むしろ、それは人がキリストと神とを共にすることができ、ひいては聖徒たちの全共同体と一体となることができるようになる、内面的に必要な変容の過程である。」[ 127 ]
ジョン・E・ティールは『神学研究』の中で、「煉獄は第2バチカン公会議以降、カトリックの信仰と実践から事実上姿を消した」と論じた。それは、煉獄が「中世後期の禁欲主義者の宗教的召命をめぐる競争的な霊性」に基づいていたためである。「煉獄の誕生は、一般信徒の終末論的な不安を解消した。[…] 禁欲主義者が殉教者との現世的な競争の場を生涯にわたって延長したのと同様に、煉獄への信仰は一般信徒と禁欲主義者との現世的な競争の場を延長した。」[ 128 ]
特に中世後期に西方教会やラテン教会で一般的だった思索や俗説は、教皇と完全な交わりを持つ23の東方カトリック教会では必ずしも受け入れられていません。煉獄の一般的なイメージに見られる、特定の場所での火刑という概念を明確に否定する者もいます。フィレンツェ公会議において、東方正教会の代表者たちはこれらの概念に反論しましたが、救われた者の魂は死後に浄化され、生きている者の祈りによって浄化されるという信念は支持すると宣言しました。「もし魂が信仰と愛をもってこの世を去るとしても、何らかの汚れを負っている場合、悔い改められていない軽微な汚れであれ、悔い改めたもののまだ悔い改めの実を結んでいない重度の汚れであれ、私たちは理にかなった範囲内でそれらの汚れから浄化されると信じますが、それはどこかの場所で浄化の火と特定の罰によって浄化されるのではありません。」[ 129 ]この公会議で採択された煉獄の定義は、正教会が反対する二つの概念を除外し、正教会が自らの信仰の一部であると主張する二つの点のみに言及した。したがって、ウクライナ・ギリシャ正教会をローマ・カトリック教会の完全な共同体として正式に承認したブレスト合同協定は、 「我々は煉獄について議論することはないが、聖なる教会の教えに身を委ねる」と述べている。[ 130 ]
ベタニアのマグダラのマリア

中世西洋の伝統では、ラザロの姉妹であるベタニアのマリアはマグダラのマリアと同一視されていました。これはおそらく、グレゴリウス1世が新約聖書に登場する複数の女性を同一人物であるかのように説いた説教が大きな要因だったと考えられます。このため、ベタニアのマリアはマグダラのマリアと、さらに別の女性(イエスに油を注いだベタニアのマリアとは別の女性)、姦淫の罪で捕らえられた女性と混同されました。東方キリスト教はこの同一視を採用しませんでした。1910年のカトリック百科事典に掲載された記事の中で、ヒュー・ポープは次のように述べています。「ギリシャ教父たちは全体として、ルカ7:36–50の『罪人』、ルカ10:38–42とヨハネ11章に登場するマルタとラザロの姉妹、そしてマグダラのマリアという3つの人物を区別しています。 」[ 131 ]
フランスの学者ヴィクトル・サクサーは、マグダラのマリアが娼婦であり、ベタニアのマリアであると特定されたのは、西暦591年9月21日のグレゴリウス1世教皇の説教によるものだとしている。この説教において、グレゴリウスは新約聖書に登場する3人の女性の行動を結びつけ、また名前のない女性をマグダラのマリアであると特定したようだ。別の説教では、グレゴリウスはマグダラのマリアをルカによる福音書10章に登場するマルタの妹であると明確に特定している。[ 132 ]しかし、神学者ジェーン・シャーバーグが最近示した見解によれば、グレゴリウスは既に存在していた伝説に最終的な仕上げを加えたに過ぎないという。[ 133 ]
ラテンキリスト教におけるマグダラのマリアとベタニアのマリアの同一視は、1969年に変更されるまでローマ暦の制定に反映されていましたが、 [ 134 ]これは、当時のカトリック教会ではベタニアのマリア、マグダラのマリア、そしてイエスの足に香油を注いだ罪深い女性は3人の別々の女性であるという解釈が一般的であったことを反映しています。[ 135 ]
原罪
カトリック教会のカテキズムにはこう記されています。
最初の人間である アダムは、罪を犯したことにより、自分自身だけでなく全人類のために神から受けていた本来の神聖さと正義を失いました。
アダムとイブは、自らの最初の罪によって傷つけられ、本来の神聖さと正義を奪われた人間性を子孫に伝えました。この喪失は「原罪」と呼ばれます。
原罪の結果、人間の本性は弱まり、無知、苦しみ、死の支配にさらされ、罪に傾くようになります(この傾向は「欲望」と呼ばれます)。[ 136 ]

原罪の概念は、2世紀にリヨンの司教聖イレネオが特定の二元論グノーシス主義者との論争の中で初めて言及されました。[ 137 ]アウグスティヌスなどの他の教父もこの教義を形成し発展させ、[ 138 ] [ 139 ]使徒パウロの新約聖書の教え(ローマ人への手紙5:12–21とコリントの信徒への手紙一15:21–22)と旧約聖書の詩篇51:5に基づいていると見ました。[ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ]テルトゥリアヌス、キプリアヌス、アンブロシウス、アンブロジアステルは、人類はアダムの罪を共有しており、それは人間の世代によって受け継がれていると考えました。 412年以降、アウグスティヌスによる原罪の定式化は、マルティン・ルターやジャン・カルヴァンといったプロテスタントの改革者たちの間で広く受け入れられました。彼らは原罪を情欲(または「有害な欲望」)と同一視し、洗礼後も持続し、善を行う自由を完全に破壊すると主張しました。412年以前、アウグスティヌスは原罪によって自由意志は弱まるものの破壊されることはないと述べていました。[ 139 ]しかし、412年以降、これは罪を犯す場合を除いて自由意志が失われるという考え方に変わりました。[ 145 ]現代のカルヴァン主義は、後期アウグスティヌス派の救済論を支持しています。カトリック教会が異端と断定したジャンセニスム運動もまた、原罪が自由意志を破壊したと主張しました。[ 146 ]一方、西方カトリック教会は次のように宣言しています。「洗礼は、キリストの恵みの命を与えることによって原罪を消し去り、人を神へと立ち返らせるが、弱体化し悪に傾倒した本性に対する結果は人の中に存続し、霊的な戦いへと招き入れる。」[ 147 ]「アダムの堕落によって弱体化し縮小したが、人類における自由意志はまだ破壊されていない。」[ 148 ]
聖アンセルムスはこう述べています。「アダムの罪と、出生時の子供たちの罪は全く別物である。前者は原因であり、後者は結果である。」[ 149 ]子供にとって、原罪はアダムの過ちとは別物であり、結果の一つである。カトリック百科事典によると、アダムの罪の結果は以下の通りである。
- 死と苦しみ:「一人の人間が、罪の罰である肉体の死だけでなく、魂の死である罪そのものさえも全人類に伝えた。」
- 情欲、つまり罪への傾向。洗礼によって原罪は消去されますが、罪への傾向は残ります。
- 新生児に聖化の恵みが与えられていないのも、最初の罪の結果です。アダムは神から聖性と正義を受けていましたが、それを自分自身だけでなく私たち自身も失ってしまったのです。洗礼は、アダムの罪によって失われた本来の聖化の恵みを与え、それによって原罪とあらゆる個人的な罪を消し去ります。[ 150 ]
東方カトリック教会と東方キリスト教は、一般的に、ラテンカトリック教会のような堕落と原罪に関する神学を持っていません。[ 151 ]しかし、第二バチカン公会議以降、カトリックの考え方は発展を遂げてきました。創世記3章をあまり文字通りに解釈することに対して警告する人もいます。彼らは、「神は世界の基が置かれる前から教会を念頭に置いておられた」(エフェソの信徒への手紙1章4節)ことを考慮に入れています。[ 152 ]また、テモテへの手紙二1章9節にも、「…神のご計画と恵みは、世界の基が置かれる前からキリスト・イエスにあって私たちに与えられていたのです。」とあります。 [ 153 ]また、ベネディクト16世教皇は著書『初めに…』の中で、「原罪」という言葉を「誤解を招きやすく、正確ではない」と述べています。[ 154 ]ベネディクトは創世記や悪の起源について文字通りの解釈を求めず、次のように書いている。「どうしてこのようなことが可能だったのか、どうしてこのようなことが起こったのか?これは依然として不明瞭である。…悪は依然として謎に包まれている。創世記第3章のように、二本の木、蛇、罪深い人間の幻影など、大きなイメージで表現されてきた。」[ 155 ] [ 156 ]
無原罪懐胎

無原罪懐胎とは、聖母マリアが御子イエスの功績によって原罪から解放された状態で受胎されたことを意味する。この信仰は後期古代から広く信じられていたが、カトリック教会においてこの教義が教義的に定義されたのは、1854年、教皇ピウス9世が教皇勅書『イネファビリス・デウス』において、教皇の不可謬性(ex cathedra)を用いて宣言した時である。[ 157 ]
ピウス9世によって定義された教義は、12世紀以前には明確に記されていなかったことは認められている。また、「聖書からこの教義を直接的、あるいは断定的かつ厳格に証明することはできない」とも認められている。[ 158 ]しかし、この教義は教父たちの教えに暗黙的に含まれていると主張されている。マリアの無罪性に関する教父たちの表現は、あまりにも広範かつ絶対的であるため、原罪だけでなく実際の罪も含むと解釈しなければならないと指摘されている。したがって、最初の5世紀においては、「あらゆる点で聖なる」「すべてにおいて汚れのない」「極めて無垢な」「唯一聖なる」といった称号がマリアに当てはめられ、彼女は贖われた民の祖先として堕落前のエバに例えられ、「呪われる前の大地」に喩えられている。聖アウグスティヌス(430年没)の有名な言葉を引用しよう。「神の母に関しては、罪についていかなる疑問も認めない」と彼は言う。確かに、ここで彼は実際の、あるいは個人的な罪について直接的に語っている。しかし、彼の主張は、すべての人間は罪人であり、それは原初的な堕落によるものであり、この原初的な堕落は神の恵みによって克服され得るというものである。そして、マリアが「あらゆる種類の」罪を克服するのに十分な恵みを持っていた可能性もある(omni ex parte)と付け加えている。[ 159 ]
12世紀、クレルヴォーのベルナルドは無原罪懐胎の問題を提起しました。聖母マリアの御宿りを祝う祭典は、すでに西方教会の一部で祝われ始めていました。聖ベルナルドは、リヨン大主教区の聖職者たちが聖座の許可なくこのような祭典を制定したことを非難しています。その際、彼はマリアの御宿りは罪のないものであるという見解を「新奇なもの」と呼び、全面的に否定しています。しかしながら、彼が「御宿り」という言葉を、教皇ピウス9世の定義で用いられているのと同じ意味で用いていたかどうかについては疑問視する声もあります。ベルナルドは、母親の協力という能動的な意味での御宿りについて語っていたように思われます。なぜなら、彼は「情欲(リビドー)があるところに、どうして罪がなくなろうか」と述べており、その後に続くより強い表現は、彼が子供ではなく母親について語っていたことを示唆していると解釈できるからです。しかし、ベルナルドは、この祭りを支持する人々が「マリアの栄光を増そうとしている」とも非難しており、これは彼が確かにマリアについて語っていたことを証明している。[ 159 ]
無原罪の御宿りの神学的根拠は中世を通じて論争の的となっており、ドミニコ会の聖トマス・アクィナスなどの人物が反対していた。しかし、フランシスコ会のウィリアム・オブ・ウェアやペルバルトゥス・ラディスラウス・オブ・テメスヴァールの支持論[ 160 ]とカトリック教徒の一般的な信仰によってこの教義はより受け入れられやすくなり、15世紀のバーゼル公会議はこれを支持し、トレント公会議はこの問題を回避した。フランシスコ会のシクストゥス4世は双方が他方を批判することを禁じることで事態の沈静化を図り、1477年に無原罪の御宿りの祝日をローマ暦に組み込んだが、ドミニコ会のピウス5世はこれを聖母マリアの御宿りの祝日に変更した。クレメンス11世は1708年にこの祝日を世界共通の祝日としたが、それでも無原罪の御宿りの祝日とは呼ばなかった。[ 161 ]この概念に対する一般大衆と神学的な支持は拡大し続け、18世紀までには芸術作品に広く描かれるようになりました。[ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ]
ドゥンス・スコトゥス

聖ボナヴェントゥラのような小さき修道士であった福者ヨハネ・ドゥンス・スコトゥス(1308年没)は、理性的な観点から、マリアがキリストによってあらゆる罪の汚れから守られたと主張することは、マリアが最初に罪に陥りその後解放されたと言うことと同じくらい、キリストの功績を貶めるものではないと主張した。[ 159 ]彼は、この教理とキリストにおける普遍的救済の教理を調和させるという神学的問題に対する解決策を提案し、マリアの無原罪懐胎はキリストによる救済から彼女を除外するものではなく、むしろ救済史における彼女の特別な役割ゆえに彼女に与えられたより完全な救済の結果であると主張した。[ 166 ]
スコトゥスの議論は、初期の教父たちの言語への深い理解と相まって、西方教会の諸学派で徐々に広まっていった。1387年、パリ大学は反対の見解を強く非難した。[ 159 ]
しかしながら、スコトゥスの議論は、特にドミニコ会の間では物議を醸したままであった。ドミニコ会は、マリアの聖化(罪からの解放)を祝うことには積極的であったが、ドミニコ会のトマス・アクィナスの議論に従い、マリアの聖化は彼女の受胎後まで起こり得なかったと主張し続けた。[ 158 ]
スコトゥスは、マリアの無原罪懐胎がイエスの救済の働きを強化すると指摘した。[ 167 ]
スコトゥスの主張は、 1854年に教皇ピウス9世が無原罪懐胎の教義を宣言した際にも見られる。「マリアは受胎の瞬間から、イエス・キリストの功績により原罪の汚れから守られていた。」[ 168 ]スコトゥスの立場は「使徒たちの信仰の正しい表現」として称賛された。[ 168 ]
独断的に定義される
無原罪懐胎の教義は完全に定義されており、次のように述べています。
我々は、最も聖なる聖母マリアが、その受胎の瞬間に、人類の救世主であるイエス・キリストの功績を鑑み、全能の神から与えられた特別な恩寵と特権によって、原罪のあらゆる汚れから守られたという教義は、神によって啓示された教義であり、それゆえ、すべての信者が堅くかつ絶えず信じるべきものであると宣言し、表明し、定義する。[ 169 ]宣言、発音と明確な教義、原則、ビートシマム ヴァージネム・マリアムは、最初の瞬間に完全な概念を実現し、全能性を備え、恩恵と特権を持ち、直感的な功績を持ち、クリスティ・レス・サルバトリス・ヒューマニ・ジェネリス、すべての独創性を発揮し、プラエセルバタムを実現します免疫は、すべての真実を明らかにし、オムニバス、フィデリバス、確固たる信条を求めます。 Quapropter si qui secus ac a Nobis。
教皇ピウス9世は、マリアがより崇高な方法で贖われたことを明確に断言しました。教皇は、マリアは罪の後に清められたのではなく、人類の救世主であるイエス・キリストの予見された功績によって、原罪を犯すことを完全に防がれたと述べました。ルカによる福音書1章47節で、マリアは「私の霊は私の救い主である神を喜びました」と宣言しています。これは、キリストによるマリアの先贖罪と呼ばれています。セミペラギウス主義を批判した第二オレンジ公会議以来、カトリック教会は、たとえ人間がエデンの園で罪を犯さず、罪のない者であったとしても、罪のない者であり続けるためには神の恵みが必要であると教えてきました。[ 170 ] [ 171 ]
この定義は原罪についてのみ言及しており、聖母マリアが実際の罪や個人的な罪から自由であるという意味で罪がなかったという教会の信仰については何も宣言していない。[ 159 ]この教義では、マリアは受胎の時から常に原罪から自由であり、通常は誕生後に洗礼によってもたらされる聖化の恩恵を受けたと教えている。
東方カトリック教会と東方キリスト教は、一般的にマリアは罪がなかったと信じているが、ラテンカトリック教会のような堕落と原罪の神学は持っていない。 [ 151 ]
聖母マリアの被昇天

聖母マリアの被昇天(しばしば聖母被昇天と略される)は、聖母マリアが地上での生涯を終える際に 肉体をもって天に上げられることです。
1950 年 11 月 1 日、教皇ピウス 12 世は使徒憲章「Munificentissimus Deus」の中で、聖母マリアの被昇天を教義として宣言しました。
我らの主イエズス・キリストの権威、聖使徒ペトロとパウロの権威、そして我々自身の権威によって、我々は、神の汚れなき母、永遠の処女マリアが地上の生涯を終え、肉体と霊魂を伴って天の栄光に引き上げられたことを、神によって啓示された教義として宣言し、宣言し、定義する。[ 172 ]
ピウス12世の教義的声明における「地上の生涯を終えて」という表現は、聖母マリアが被昇天前に亡くなっていたかどうかという疑問を残している。聖母マリアの被昇天は、「神の母」としてのマリアへの神の賜物であったとされている。ルートヴィヒ・オットの見解は、マリアが人類にとって輝かしい模範としてその生涯を終えたことで、被昇天という賜物の視点が全人類に与えられたというものである。[ 173 ]
ルートヴィヒ・オットは著書『カトリック教義の基礎』の中で、「マリアの死の事実は教父や神学者によってほぼ一般的に受け入れられており、教会の典礼においても明確に肯定されている」と述べ、さらにいくつかの有益な引用文献を付け加えている。彼は次のように結論づけている。「マリアにとって、原罪と個人的な罪からの自由の結果としての死は、罪の罰の結果ではなかった。しかしながら、本来死すべき体であったマリアの体が、神の子であるマリアの体と同様に、死の一般法に従うのは当然のことと思われる」[ 174 ] 。

マリアの肉体の死の時点については、どの教皇によっても明確に定義されていません。多くのカトリック教徒は、マリアは実際には死んでおらず、直接天に上げられたと信じています。ローマ・カトリック教会の教義によれば、聖母被昇天の教義を絶対的に宣言する使徒憲章『Munificentissimus Deus』における教義的な定義は、マリアの天に昇る際にマリアが肉体の死を遂げたかどうかという疑問を残しています。「地上の生涯を終えた」という言葉が示すように、その時点を教義的に定義しているわけではありません。[ 175 ]
『聖母マリアの誕生』における教義的定義の前に、教皇ピウス12世はカトリック司教たちの意見を求めた。多くの司教は、創世記(3章15節)を教義の聖書的根拠として挙げた。[ 176 ]ピウス12世は『神の御業』(39項)において、創世記3章15節の「地獄の敵との闘い」とパウロの手紙にある「罪と死に対する完全な勝利」を教義的定義の聖書的根拠として挙げ、コリントの信徒への手紙一15章54節にあるマリアの天への昇天を「その時、死は勝利に呑み込まれる」と書かれている言葉が実現するであろうと述べている。[ 176 ] [ 177 ]
聖母被昇天と生神女就寝
西方聖母被昇天祭は8月15日に祝われ、東方正教会とギリシャ正教会は同日に聖母マリアの死(または生神女就寝、聖母の眠り)を祝い、その前に14日間の断食期間を設けます。東方キリスト教徒は、マリアが自然死し、その魂は死後キリストに受け入れられ、死後3日目に肉体が復活し、その後の復活を待ち望んで肉体のまま天に召されたと信じている。彼女の墓は3日目に空っぽで発見された。

正教会の伝承は、(聖母マリアの生誕の)核心に関して明確かつ揺るぎない見解を示している。すなわち、聖母マリアは御子イエスと同様に肉体の死を遂げたが、その後、御子イエスと同様に復活し、肉体と霊魂の両方において天に召されたということである。聖母マリアは死と審判を超越し、来世に完全に生きる。聖母マリアの肉体の復活は…すでに予期され、既に実現された事実である。しかしながら、それは聖母マリアが人類全体から切り離され、全く異なるカテゴリーに位置づけられることを意味するものではない。なぜなら、私たちは皆、聖母マリアが今享受している肉体の復活の栄光に、いつの日か共にあずかることを望んでいるからである。[ 178 ]
多くのカトリック教徒も、マリアは聖母被昇天前にまず亡くなったと信じているが、聖母被昇天前に奇跡的に復活したと信じている。また、マリアは死ぬことなく肉体のまま天に昇ったと信じる者もいる。[ 179 ] [ 180 ]どちらの解釈もカトリック教徒には正当であり、東方カトリック教徒はこの祝日を聖母被昇天として祝う。
多くの神学者は、比較として、カトリック教会では聖母被昇天が教義的に定義されているのに対し、東方正教会では聖母被昇天が教義的というよりは典礼的、神秘主義的に定義されていることを指摘しています。こうした違いは、両教会のより大きなパターンに起因しています。カトリックの教えは、カトリック教会のより中央集権的な構造もあって、しばしば教義的かつ権威的に定義されるのに対し、東方正教会では多くの教義の権威性が低いのです。[ 181 ]
古代の日々
_British_Museum.jpg/440px-Europe_a_Prophecy,_copy_D,_object_1_(Bentley_1,_Erdman_i,_Keynes_i)_British_Museum.jpg)
ジョヴァンニ・ダレマーニャとアントニオ・ヴィヴァリーニによる 初期ヴェネツィア派の『聖母戴冠』 ( 1443年頃)では、父なる神は、後世の画家たちによって一貫して用いられた表現、すなわち、温厚でありながら力強い表情と長い白い髪とあごひげを持つ族長として描かれている。この描写は、旧約聖書の老いたる者の描写に大きく由来し、その描写によって正当化されており、旧約聖書における神の物理的な描写に最も近いものである。[ 182 ]
…老いたる者が座しておられた。その衣は雪のように白く、その頭髪は純粋な羊毛のようであった。その王座は燃える炎のようであり、その車輪は燃える火のようであった。(ダニエル書7:9)
聖トマス・アクィナスは、老いたる者が父なる神と一致するという反論を唱える者がいたが、必ずしもこの主張に自ら同意していたわけではないことを想起している。[ 183 ]
12世紀までに、ダニエル書の老いたる者を基本的に基にした父なる神の姿の描写が、フランスの写本やイギリスの教会のステンドグラスに現れ始めました。14世紀には、挿絵入りのナポリ聖書に燃える柴の中にいる父なる神が描かれました。15世紀までには、ローハンの時祷書に人間の姿や擬人化されたイメージで父なる神が描かれ、ルネサンス期までには西方教会で父なる神の芸術的表現が自由に使用されました。[ 184 ]

その後、カトリック美術において父なる神の描写は議論の余地がなかったが、三位一体の描写はそれほど一般的ではなかったため非難された。1745年、ベネディクトゥス14世は「太古の昔から」に言及し、慈悲の玉座の描写を明確に支持したが、1786年には、イタリア教会会議による三位一体の像を教会からすべて撤去するという決定を非難する教皇勅書をピウス6世が発布する必要があった。[ 185 ]
東方正教会の美術において、この描写は稀であり、しばしば議論の的となっている。東方正教会の賛美歌やイコンにおいて、老いたる者は父なる神ではなく、子なる神、あるいはイエスと同一視されるのが最も適切である。ダニエル書(7:9–10, 13–14)の箇所について解説する東方教会の教父の多くは、この老人の姿を、息子が肉体を得る前の預言的な啓示と解釈した。[ 186 ]そのため、東方キリスト教美術では、イエス・キリストを老人、すなわち老いたる者として描くことで、彼が永遠の昔から存在していたことを象徴的に示し、また、若者、あるいは賢い幼子として描くことで、彼が肉体を得た姿を表現している。このイコンは6世紀に東ローマ帝国で主に老人像と共に現れたが、通常は「老いたる者」として、あるいは具体的に特定されてはいない。[ 187 ]碑文でその名が付けられた「老いたる者」の最初の像は、図像学者によって様々な写本に描かれ、最も古いものは11世紀に遡ります。これらの写本に描かれた像には「老いたる者、イエス・キリスト」という碑文が含まれており、これはキリストを父なる神と共に永遠なる存在として特定する方法であったことを裏付けています。[ 188 ]実際、後にロシア正教会は1667年のモスクワ大シノドにおいて、「老いたる者」は父ではなく子であると宣言しました。 [ 189 ]
社会文化問題
性的虐待事件
1990年代以降、西方カトリック教会の聖職者やその他の教会員による未成年者への性的虐待問題は、世界各国で民事訴訟、刑事訴追、メディア報道、そして国民的議論の対象となってきました。一部の司教が告発された司祭を庇護し、他の司牧職に異動させ、そこでも性的犯罪を犯し続けた司祭がいたことが明らかになり、西方カトリック教会は虐待の訴えへの対応について批判を浴びました。
このスキャンダルを受けて、虐待を防止し、虐待が発生した場合の報告を奨励し、そのような報告を迅速に処理するための正式な手続きが確立されましたが、被害者を代表する団体はその有効性に異議を唱えています。[ 190 ] 2014年、フランシスコ教皇は未成年者を虐待から守るために教皇庁未成年者保護委員会を設立しました。 [ 191 ]
参照
注記
- ^ (16世紀にはルター派、カルヴァン派、英国国教会、アナバプテストが誕生した)
- ^「ローマ・カトリック教会」という用語は、特に非カトリックの文脈において、カトリック教会全体を指すために使用される一方で、東方カトリック教会と比較したラテン教会を指すために使用されることもあります。 「ローマ・カトリック教会とビザンチン・カトリック教会の違いを知っていますか?」 The Compass誌、2011年11月30日。2023年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年4月8日閲覧。
参考文献
- ^ Houghton, HAG (2016). 『ラテン語新約聖書:その初期の歴史、本文、写本へのガイド』オックスフォード大学出版局. p. 132. ISBN 9780198744733
1979年までローマカトリック教会の標準聖書は、1592年に教皇クレメンス8世のために作成されたクレメンス版ウルガタ聖書でした
。 - ^マーシャル、トーマス・ウィリアム(1844年)『聖カトリック教会の司教政体に関する覚書』ロンドン:リーヴィー、ロッセン、フランクリン。
- ^ハルナック、アドルフ(1921年)『マルキオン:異邦の神の福音』 スティーリー、ジョン・E、ビアマ、ライル・D訳 グランドラピッズ:ベイカー社ISBN 978-1-55635-703-9。
{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ 「キリスト教とドナティスト論争」 Encyclopædia Britannica, Inc.
- ^マッカリース、メアリー(2019年)『教会法における子どもの権利と義務:洗礼契約』ブリル出版社ISBN 978-90-04-41117-3。
- ^ a bアンダーソン、ジョン(2019年3月7日)「東方カトリック教会の美しい証人」カトリック・ヘラルド。2019年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月29日閲覧。
- ^マンチーニ、マルコ (2017 年 8 月 11 日)。「Patriarca d'Occidente? No grazie, disse Benedetto XVI」 [西洋総主教?いいえ、ベネディクト十六世は言いました。] ACI Stampa (イタリア語)。バチカン市国。2023 年11 月 28 日に取得。
- ^ターナー、ポール(2007年)『他のキリスト教徒がカトリック教徒になるとき』リトゥルジカル・プレス、141ページ。ISBN 978-0-8146-6216-8
他のキリスト教徒がカトリック教徒になった場合、その人はローマカトリック教徒ではなく東方カトリック教徒になる
。 - ^フォーテスキュー、エイドリアン(1910年)「ラテン教会」「カトリック百科事典」。
疑いなく、さらに拡張すれば、ローマ教会は総主教座のラテン教会と同等のものとして使われるかもしれない
。 - ^ファリス、ジョン D. (2002)。「ラテン教会スイ・イウリス」。法学者。62:280
- ^ Ashni, AL; Santhosh, R. (2019年12月). 「カトリック教会、漁師、そして開発交渉:ヴィジンジャム港プロジェクトに関する研究」 . 『開発と変化のレビュー』. 24 (2): 187– 204. doi : 10.1177/0972266119883165 . ISSN 0972-2661 . S2CID 213671195 .
- ^ターナー、ポール(2007年)『他のキリスト教徒がカトリック教徒になるとき』リトゥルジカル・プレス、141ページ。ISBN 978-0-8146-6216-8
他のキリスト教徒がカトリック教徒になった場合、その人はローマカトリック教徒ではなく東方カトリック教徒になる
。 - ^フォートスキュー、エイドリアン(1914年)、ワード、バーナード、サーストン、ハーバート(編)『ミサ:ローマ典礼の研究』ウェストミンスター図書館(新版)、ロンドン:ロングマンズ・グリーン社、p.167。
- ^ 「CCEO、教会法第27条」w2.vatican.va . 2019年4月1日閲覧。
- ^ CCEO、教会法第28条第1項
- ^ 「教会法典、第383条第2項」。ローマ教皇庁。 2019年4月1日閲覧。
- ^ 450 §1
- ^ 476
- ^ 479 §2
- ^ 1021
- ^ Rite、メリアム・ウェブスター辞典、2023年10月3日
- ^ Rite、コリンズ英語辞典
- ^ 「教会用語集」usccb.org。2013年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月1日閲覧。
- ^教皇パウロ6世(1964年11月21日)。「東方典礼オリエンタリウム・エクレシアラムに関する法令」。ローマ。
- ^オリエンタリウム・エクレシアラム、10
- ^バセット、ウィリアム・W. (1967). 『儀礼の決定:歴史的・法的研究』. アナレクタ・グレゴリアーナ. 第157巻. ローマ:グレゴリアン大学出版局. p. 73. ISBN 978-88-7652129-4。
- ^ 「Library of Congress Classification – KBS Table 2」(PDF) . loc.gov . 2019年4月1日閲覧。
- ^ a bフォートスキュー、エイドリアン(1910年)。「ラテン教会」。ハーバーマン、チャールズ(編)『カトリック百科事典』。ニューヨーク:ロバート・アップルトン社。

- ^ 「なぜフランシスコ教皇は(西洋の)家父長制を受け入れているのか?」ザ・ピラー誌、2024年4月10日。
- ^ギルソン、エティエンヌ (1991). 『中世哲学の精神』(ギフォード講義 1933–35) . ノートルダム大学出版局, インディアナ州. p. 490. ISBN 978-0-268-01740-8。
- ^グラント、エドワード『中世における神と理性』ケンブリッジ大学出版局、2004年、56ページ
- ^マキナニー、ラルフ、オキャラハン、ジョン(2018年2月5日)「聖トマス・アクィナス」。ザルタ、エドワード・N.(編)『スタンフォード哲学百科事典』所収。スタンフォード大学形而上学研究室 – スタンフォード哲学百科事典経由。
- ^コショルケ、K. 『アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおけるキリスト教の歴史』(2007年)、13、283ページ
- ^ライオンズ(2013)、17ページ
- ^ローランド、トレーシー(2008年)『ラッツィンガーの信仰:ベネディクト16世教皇の神学』オックスフォード大学出版局、ISBN 9780191623394. 2017年11月24日閲覧。
- ^ 「教会法典 – アーカイブ」ローマ教皇庁。2019年4月1日閲覧。
- ^ 「教会法典、第889条第2項」。ローマ教皇庁。 2019年4月1日閲覧。
- ^ 「教会法典、第913条第1項」。ローマ教皇庁。 2019年4月1日閲覧。
- ^ 「東方教会法典、第695条第1項および第710項」w2.vatican.va . 2019年4月1日閲覧。
- ^ 「教会法典、第277条第1項」。ローマ教皇庁。 2019年4月1日閲覧。
- ^ " Anglicanorum coetibus、 VI §§1–2"。w2.vatican.va 。2019 年4 月 1 日に取得。
- ^ 「教会法典、第1042条」ローマ教皇庁. 2019年4月1日閲覧。
- ^ 「教会法典、第1087条」ローマ教皇庁。2019年4月1日閲覧。
- ^テセル、ユージン (1970). 『神学者アウグスティヌス』 ロンドン. pp. 347–349 . ISBN 978-0-223-97728-0。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)2002年: ISBN 1-57910-918-7。 - ^ウィルケン、ロバート・L. (2003). 『初期キリスト教思想の精神』 ニューヘイブン:イェール大学出版局. p. 291. ISBN 978-0-300-10598-8。
- ^デュラント、ウィル(1992年)『シーザーとキリスト:ローマ文明とキリスト教の起源から紀元325年までの歴史』ニューヨーク:MJFブックス、ISBN 978-1-56731-014-6。
- ^アウグスティヌス『告白』第7巻第9章第13~14節
- ^アウグスティヌスの不滅の生命について:本文、翻訳、解説、聖アウグスティヌス(ヒッポの司教)、CWヴォルフスキール、序文
- ^ヨハネ第一 1:14
- ^ Handboek Geschiedenis van de Wijsbegeerte I、記事:Douwe Runia
- ^アテネ人、アテナゴラス。「キリスト教徒のための嘆願」。新臨臨。
- ^フリン、フランク・K、メルトン、J・ゴードン(2007年)『カトリック百科事典』『ファクト・オン・ファイル』『世界宗教百科事典』 ISBN 978-0-8160-5455-8)、4ページ
- ^クリスティン・ルーカー(1985)『中絶と母性の政治』カリフォルニア大学出版局、 ISBN 978-0-5209-0792-8)、12ページ
- ^ a bバウアーシュミット、ジョン・C (1999). 「中絶」フィッツジェラルド、アラン・D (編). 『アウグスティヌス百科事典』 Wm B Eerdmans. p. 1. ISBN 978-0-8028-3843-8。
- ^胎児の生命の尊重:教会の変わらぬ教え。米国カトリック司教会議
- ^ 「第5章 マニカイオスの手紙の題名に反して」 Christian Classics Ethereal Library . 2008年11月21日閲覧。
- ^ラッセル、第2巻、第4章
- ^メンデルソン、マイケル(2000年3月24日)「聖アウグスティヌス」スタンフォード哲学百科事典。2012年12月21日閲覧。
- ^ 「このウェブサイトの根底にある立場」romanity.org . 2015年9月30日閲覧。
- ^ 「教会の限界」 fatheralexander.org . 2015年9月30日閲覧。
- ^ a b cパパデメトリウ、ジョージ・C. 「ギリシャ正教の伝統における聖アウグスティヌス」 goarch.org 2010年11月5日アーカイブ、 Wayback Machine
- ^シエチェンスキー、アンソニー・エドワード(2010年)『フィリオクエ:教義論争の歴史』オックスフォード大学出版局、pp. 53– 67. ISBN 978-0195372045。
- ^ Kappes, Christiaan (2015年9月30日). 「グレゴリー・パラマスによるアウグスティヌスの『三位一体論』の原罪論への適用とその生神女への適用、およびスコラリウスによる無原罪懐胎のパラミティコス=アウグスティヌス主義 (ストックホルム 28.VI.15)」(文書). ストックホルム大学出版局.
- ^ Archimandrite . 「書評:聖アウグスティヌスの正教会における地位」 . Orthodox Tradition . II (3&4): 40– 43. 2007年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年6月28日閲覧。
- ^ダイアミッド・マカロック(2010年)『キリスト教の歴史:最初の3000年』ペンギンブックス、319ページ。ISBN 978-0-14-102189-8。
- ^リンドバーグ、デイヴィッド・C. (1978). 『中世の科学』 シカゴ:シカゴ大学出版局. pp. 70– 72. ISBN 978-0-226-48232-3。
- ^グラント、エドワード、および名誉エドワード・グラント著『中世における近代科学の基盤:その宗教的、制度的、知的文脈』ケンブリッジ大学出版局、1996年、23-28ページ
- ^ハモンド、ジェイ、ヘルマン、ジャレッド・ゴフ編 (2014). 『ボナヴェントゥラへの伴走』 ブリル著『キリスト教伝統への伴走』 第48巻. ブリル. p. 122. doi : 10.1163/9789004260733 . ISBN 978-90-04-26072-6。
- ^エヴァンス、ジリアン・ローズマリー (2002). 『中世の重要思想家50人』ラウトレッジ・キーガイド. ラウトレッジ. pp. 93, 147– 149, 164– 169. ISBN 9780415236638。
- ^グラシア, ホルヘ JE; ヌーン, ティモシー B. 編 (2005). 『中世哲学入門』 ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. pp. 353– 369, 494– 503, 696– 712. ISBN 978-0-631-21673-5。
- ^ヴォーン、ロジャー・ビード(1871年)『アキンの聖トマスの生涯と功績』第1巻、ロンドン。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^コンウェイ・プラシッド(1911年)『聖トマス・アクィナス 聖徒の会』第1巻、ロンドン:ロングマンズ・グリーン・アンド・カンパニー
- ^ Pius XI、 Studiorum Ducem 11 (1923 年 6 月 29 日)、AAS、XV (「non modo Angelicum, sed etiam Communem seu Universalem Ecclesiae Doctorem」) を参照。『ドクター・コミュニス』というタイトルは 14 世紀に遡ります。『ドクター・アンジェリカス』というタイトルは15 世紀に遡ります。Walz、 Xenia Thomistica、III、p. 4 を参照してください。 164n. 4.トロメオ・ダ・ルッカは、 『Historia Ecclesiastica』(1317 年)の中で次のように書いています。「この人は、哲学と神学の現代の教師の中で、実際、あらゆる分野において最高の人物です。そして、それが一般的な見解と意見なので、今日、パリ大学では、彼の教えの際立った明快さのために、彼をドクター・コミュニスと呼んでいます。」ヒストリア・エクルズ。xxiii、c. 9.
- ^ラングストン、ダグラス(2015年2月5日)「中世の良心理論」。エドワード・N・ザルタ編『スタンフォード哲学百科事典』 (2015年秋版)。スタンフォード大学形而上学研究室。
- ^神学大全、第二部第一部、質問94、回答意見2
- ^ Summa 問94、A.3
- ^ 「Summa , Q62a2」 . Ccel.org . 2012年2月2日閲覧。
- ^『神学大全』第2部第2問、質問118、第1条。2018年10月26日閲覧。
- ^トマス・アクィナス『神学大全』「売買における不正行為について」イギリス・ドミニコ会教父による翻訳[1] 2012年6月19日閲覧
- ^バリー・ゴードン (1987). 「トマス・アクィナス (1225–1274)」第1巻、100ページ
- ^アリキス・ムルトゥム・イウヴェトゥール・エクス・リ・アルテリウス・クァム・アクセプト、イレ・ヴェロ・キ・ベンディディット・ノン・ダムニフィカトゥー・カレンド・レ・ラ、ノン・デベット・イーム・スーパーベンダー。必要な条件を満たしていない場合でも、事前に条件を満たしていない場合でも、事前に変更を行う必要はありません。 。 。
- ^ Aquinas、 Summa Theologica、 2è-2ae q. 77 pr. : "ボランティア活動の定期交換については、優先的に検討してください。また、バスおよび販売の際の詐欺行為についても優先的に検討してください ... "
- ^ “Summa Theologiae: 神の存在 (Prima Pars、Q. 2)” .新しいアドベント。
- ^神学大全 I、第2問、哲学者が神の存在を証明した5つの方法
- ^クリーフト、74–112ページ。
- ^ “Doctoris Angelici” . 2009年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月4日閲覧。2012年10月25日にアクセス
- ^教皇ピウス10世、ドクトリス・アンジェリシ、1914年6月29日。
- ^第二バチカン公会議、オプタタム・トティウス(1965 年 10 月 28 日) 15.
- ^ジョン・メイエンドルフ (編集者)、グレゴリー・パラマス – トライアド、p. xi。パウリスト出版、1983、 ISBN 978-0809124473しかし、この態度はカトリック教会において普遍的に浸透していたわけではなく、むしろ過去1世紀のカトリック神学において広く批判されてきた(本稿第3節参照)。2014年9月12日閲覧。
- ^「党の指導者たちは、無知な修道士たちのこうした俗悪な慣習には無関心だったことは疑いようもないが、一方では危険な神学理論を広く流布していた。パラマスは、禁欲によって神性の肉体的、すなわち感覚的な見解、あるいは知覚を獲得できると説いた。また彼は、神においては神の本質とその属性の間に真の区別があると主張し、恩寵を神の固有性の一つとして捉え、それを創造されず無限のものとみなした。これらの甚だしい誤りは、カラブリアのバルラム、ニケフォロス・グレゴラス、そしてアクチュンディヌスによって非難された。この論争は1338年に始まり、パラマスの厳粛な列聖と彼の異端の公式認定によってようやく1368年に終結した。彼は「聖なる博士」であり「教会の父たちの中で最も偉大な人物の一人」と称され、彼の著作は「最も偉大な」と宣言された。 「キリスト教信仰の絶対的な導き手」。30年間にわたる絶え間ない論争と不一致な公会議は、多神教の復活で幕を閉じた。シモン・ヴァイエ(1909年)。「ギリシャ教会」。カトリック百科事典、ニューヨーク:ロバート・アップルトン社。
- ^ Fortescue, Adrian (1910), Hesychasm , vol. VII, New York: Robert Appleton Company , 2008年2月3日閲覧。
- ^「党の指導者たちは、無知な修道士たちのこうした俗悪な慣習には無関心だったことは疑いようもないが、一方では危険な神学理論を広く流布していた。パラマスは、禁欲によって神性の肉体的、すなわち感覚的な見解、あるいは知覚を獲得できると説いた。また彼は、神においては神の本質とその属性の間に真の区別があると主張し、恩寵を神の固有性の一つとして捉え、それを創造されず無限のものとみなした。これらの甚だしい誤りは、カラブリアのバルラム、ニケフォロス・グレゴラス、そしてアクチュンディヌスによって非難された。この論争は1338年に始まり、パラマスの厳粛な列聖と彼の異端の公式認定によってようやく1368年に終結した。彼は「聖なる博士」であり「教会の父たちの中で最も偉大な人物の一人」と称され、彼の著作は「最も偉大な」と宣言された。キリスト教信仰の絶対的な導き手である。30年間にわたる絶え間ない論争と不一致な公会議は、多神教の復活で幕を閉じた。(シモン・ヴァイエ「ギリシャ教会」、カトリック百科事典(ニューヨーク:ロバート・アップルトン社、1909年)
- ^マイケル・J・クリステンセン、ジェフリー・A・ウィトゥング(編)、神の性質の参加者(アソシエイテッド・ユニバーシティ・プレス、2007年ISBN 0-8386-4111-3)、243~244ページ
- ^神聖な静寂の探求 (melkite.org)
- ^大断食第2日曜日 グレゴリー・パラマス (sspp.ca)
- ^ 「マーティン・ジュジー『パラミテ論争』」 2009年6月13日。 2010年12月27日閲覧。
- ^アメリカ改革派教会。神学委員会(2002年)。「ニカイア信条と聖霊の進行」。ジェームズ・I・クック編『教会は語る:神学委員会文書、アメリカ改革派教会、1959-1984 』 。アメリカ改革派教会歴史シリーズ第40巻。グランドラピッズ、ミシガン州:アーダムズ。ISBN 978-0-80280980-3。
- ^デール・T・アーヴィン、スコット・サンクイスト著『世界キリスト教運動の歴史』(2001年)、第1巻、340ページ
- ^ディックス『典礼の形』(2005年)、487ページ
- ^クローヴィスの改宗
- ^ Plested, "Filioque" in John Anthony McGuckin, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity (Wiley, John & Sons 2011 ISBN 978-1-4051-8539-4)、第1巻、251ページ
- ^別の見方については、例:言葉のエクスカーサス πίστιν ἑτέραν を参照。
- ^ 「聖霊に関するギリシャ語とラテン語の伝統」Ewtn.com。
- ^キリスト教一致促進評議会:聖霊降臨に関するギリシャ語とラテン語の伝統および別のサイトにある同じ文書
- ^ Ρωμαϊκό Λειτουργικό (ローマミサ典礼典)、Συνοδική Επιτροπή για τη θεία Λατρεία 2005、I、p. 347
- ^ブレスト条約第1条
- ^カトリック教会のカテキズム「最後の浄化、あるいは煉獄」
- ^「ピウス4世トレント公会議-25」ewtn.com。
- ^エイドリアン・ミハイ、「L'Hadès céleste. Histoire du purgatoire dans l'Antiquité」(Garnier: 2015)、pp.185–188
- ^参照マカベア第二 12:42–44
- ^ブリタニカ百科事典の煉獄
- ^カトリック教会のカテキズム、 1032
- ^ジェラルド・オコリンズ、エドワード・G・ファルジア著『神学の簡潔な辞典』(エディンバラ:T&Tクラーク、2000年)27ページ。
- ^キリスト教教義学第2巻(フィラデルフィア:フォートレス・プレス、1984年)503ページ;イレナイオス『異端反駁』 5.31.2(アレクサンダー・ロバーツとジェームズ・ドナルドソン編『アンテ・ニケア教父』(グランドラピッズ:アーダムズ、1979年)1:560;5.36.2 / 1:567を参照;ジョージ・クロス「ローマ・カトリックとギリシャ・カトリックの来世観の差異」『聖書の世界』(1912年)107ページを
- ^ジェラルド・オコリンズ、エドワード・G・ファルジア共著『神学の簡潔辞典』(エディンバラ:T&Tクラーク、2000年)27頁;アドルフ・ハルナック共著『教義の歴史』第2巻、ニール・ブキャナン訳(ロンドン、ウィリアムズ&ノーゲート、1995年)337頁;アレクサンドリアのクレメンス『ストロマタ』6章14節
- ^ジャック・ル・ゴフ『煉獄の誕生』(シカゴ大学出版局、1984年)53ページ;レビ記10:1–2、申命記32:22、コリント人への第一の手紙3:10–15を参照
- ^アドルフ・ハルナック『ドグマの歴史』第2巻、ニール・ブキャナン訳(ロンドン:ウィリアムズ&ノーゲート、1905年)377ページ。オンラインで読む。
- ^ジャック・ル・ゴフ『煉獄の誕生』(シカゴ大学出版、1984年)55-57頁。アレクサンドリアのクレメンス『ストロマタ』 7:6および5:14
- ^ジェラルド・オコリンズ、エドワード・G・ファルジア共著『神学簡潔辞典』(エディンバラ:T&Tクラーク、2000年)27頁;アドルフ・ハルナック共著『教義の歴史』第2巻、ニール・ブキャナン訳(ロンドン、ウィリアムズ&ノーゲート、1995年)296頁注1;ジョージ・クロス「ローマカトリックとギリシャカトリックの来世観の差異」『聖書世界』(1912年);テルトゥリアヌス『デ・アニマ』
- ^ a b A. J. Visser、「古代キリスト教終末論の鳥瞰図」、Numen(1967年)13ページ
- ^アドルフ・ハルナック『ドグマの歴史』第2巻、ニール・ブキャナン訳(ロンドン:ウィリアムズ&ノーゲート、1905年)296頁注1。オンラインで読む。ジャック・ル・ゴフ『煉獄の誕生』(シカゴ大学出版、1984年)58~59頁も参照。
- ^キプリアン、書簡51:20;ジェラルド・オコリンズ、エドワード・G・ファルジア著『神学の簡潔な辞典』(エディンバラ:T&Tクラーク、2000年)27ページ
- ^ヨハネ・クリュソストム『第一コリント41:5の説教 』、 『ピリピ3:9–10の説教』、 ジェラルド・オコリンズとエドワード・G・ファルジア『簡潔な神学辞典』(エディンバラ:T&Tクラーク、2000年)27ページ
- ^アウグスティヌス『説教』 159:1, 172:2;『神の国』21:13;『信仰、希望、愛の手引き』 18:69, 29:109;『告白』 2.27;ジェラルド・オコリンズとマリオ・ファルージャ『カトリック:カトリックキリスト教の物語』(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、2003年)36ページ;ジェラルド・オコリンズとエドワード・G・ファルージャ『神学簡潔辞典』(エディンバラ:T&Tクラーク、2000年)27ページ
- ^グレゴリウス1世『対話』 4, 39: PL 77, 396;マタイによる福音書12:31参照
- ^ポール・J・グリフィス (2010). 「煉獄」ジェリー・L・ウォールズ編.オックスフォード終末論ハンドブック. オックスフォード大学出版局. 436ページ. ISBN 9780199742486。
- ^ジョセフ・ラッツィンガー(2007年)『終末論:死と永遠の生』CUA Press、230ページ。ISBN 9780813215167。
- ^ Thiel, John E. (2008). 「時間、裁き、そして競争的スピリチュアリティ:煉獄の教義の発展を読む」(PDF) .神学研究. 69 (4): 741– 785. doi : 10.1177/004056390806900401 . S2CID 170574571. 2020年11月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年7月5日閲覧。
- ^「エフェソス大司教マルコによる浄化の火に関する最初の演説」『パトロロギア・オリエンタリス』第15巻、40~41ページ
- ^ 「ブレスト条約第5条」。
- ^ポープ、H. (1910).聖マリア・マグダレン, 『カトリック百科事典』 , ニューヨーク: ロバート・アップルトン社.
- ^ヤンセン、キャサリン・ルートヴィヒ(2001年)『マグダレンの誕生:中世後期における説教と民衆の信仰』プリンストン大学出版局、ISBN 978-0-691-08987-4。
- ^リベラ、ジョン(2003年4月18日)。「ジョン・リベラ、「マグダラのマリアの復活」『ワールドワイド・レリジャス・ニュース』、ボルチモア・サン、2003年4月18日」。Wwrn.org 。 2018年4月5日閲覧。
- ^エルウィン・ファルブッシュ、ジェフリー・ウィリアム・ブロミリー(編)、キリスト教百科事典、第3巻(Eerdmans 2003 ISBN 978-90-0412654-1)、447ページ
- ^ジョン・フレーダー『クエスチョン・タイム:カトリック信仰に関する150の質問と回答』(テイラー・トレード・パブリケーションズ、2010年ISBN 978-1-58979594-5)、79~81ページ
- ^ 「カトリック教会のカテキズム – IntraText」 Vatican.va . 2017年1月24日閲覧。
- ^「最初のアダムの人格において、私たちは神の戒めに従わず、神を怒らせている」(Haeres., V, xvi, 3)。
- ^パット、ダニエル. 『ケンブリッジキリスト教辞典』. ダニエル・パット編. ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局, 2010, 892.
- ^ a bフランク・レスリー・クロス、エリザベス・A.・リビングストン編 (2005). 「原罪」.オックスフォード・キリスト教会辞典(第3改訂版). オックスフォード: オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-280290-3。
- ^ピーター・ネイサン. 「原罪の本来の見方」 . Vision.org . 2017年1月24日閲覧。
- ^ 「原罪の説明と擁護:アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教会の牧師への返答」Philvaz.com。2019年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年1月24日閲覧。
- ^序文と信仰箇条(Wayback Machineで2013年10月20日にアーカイブ) – V. Sin, Original and Personal – Church of the Nazarene. 2013年10月13日閲覧。
- ^赤ちゃんは罪を持って生まれるのか? 2013年10月21日アーカイブ、 Wayback Machine – Topical Bible Studies。2013年10月13日閲覧。
- ^原罪– 詩篇51:5 – カトリック通信社。2013年10月13日閲覧。
- ^ウィルソン、ケネス(2018年)『アウグスティヌスによる伝統的自由選択から「非自由的自由意志」への転換:包括的方法論』テュービンゲン:モーア・ジーベック。16 ~ 18頁、157~ 187頁。ISBN 9783161557538。
- ^ 「カトリック百科事典:ヤンセニウスとジャンセニズム」 Newadvent.org 、 1910年10月1日。 2017年1月24日閲覧。
- ^カトリック教会のカテキズム405。
- ^トレント公会議(第6会期、第1章と第5章)。
- ^ヴァージナリの概念、xxvi。
- ^ 「カトリック百科事典:原罪」。ニューアドベント。 2018年1月1日閲覧。
- ^ a b「原罪」、From East to West。
- ^ライトンボー、ジョン・W. (1998年5月31日). 「聖霊と三位一体(パート1)(説教)」 .聖書ツール. 2020年5月6日閲覧。
- ^モリス、ヘンリー・M. (2018年12月6日). 「世界が始まる前」 .創造研究所. 2020年5月6日閲覧。
- ^「枢機卿」ジョセフ・ラッツィンガー、『初めに』、1986年、72ページ。
- ^ 「2008年12月3日一般謁見演説:聖パウロ(15)。アダムとキリストの関係に関する使徒の教え|ベネディクト16世」ローマ教皇庁. 2020年5月6日閲覧。
- ^ 「教皇、原罪について考察し、現代の変化への欲求について語る」カトリック通信社、2008年12月3日。 2020年5月6日閲覧。
- ^ 「カトリック教会のカテキズム – 「聖霊の力によって宿り、聖母マリアから生まれた」「 。ローマ教皇庁。」
- ^ a bフレデリック・ホルウェック「無原罪懐胎」『カトリック百科事典』 1910年
- ^ a b c d e前述の文の1つ以上には、現在パブリックドメインとなっている出版物からのテキストが含まれています: Hedley, John (1911). " Immaculate Conception, The ". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica . Vol. 14 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 334– 335.
- ^ ZJ Kosztolnyik, Some Hungarian Theologians in the Late Renaissance , Church History. Volume: 57 . Issue: 1, 1988. ZJ Kosztolnyik, Pelbartus of Temesvar: a Franciscan Preacher and Writer of the Late Middle Ages in Hungary , Vivarium , 5/1967. Kenan B. Osborne, OFM, The History of Franciscan Theology , The Franciscan Institute St. Bonaventure, New York , 1994. Franklin H. Littell (ed.), Reformation Studies , John Knox Press, Richmond , Virginia , 1962.
- ^エドワード・ブーベリー・ピュージー著「J・H・ニューマン大司教への第一の手紙」(J・パーカー社、1869年)、379ページ
- ^キャスリーン・コイル著『キリスト教の伝統におけるマリア』 1996年ISBN 0-85244-380-338ページ
- ^中世百科事典第2巻、アンドレ・ヴォーシェ、リチャード・バリー・ドブソン著、2001年ISBN 1-57958-282-6348ページ
- ^バーク、レイモンド・L.他 (2008).『マリア論:司祭、助祭、神学生、奉献生活者のためのガイド』 ISBN 978-1-57918-355-4、642~644ページ
- ^カトリックの宗教改革マイケル・A・マレット著 1999年ISBN 0-415-18914-4、5ページ
- ^神学百科事典: 簡潔な世界の秘跡、カール・ラーナー著、2004 ISBN 0-86012-006-6、896~898ページ
- ^フォーリーOFM、レナード。「無原罪懐胎の祭儀」、今日の聖人(パット・マクロスキーOFMによる改訂)、AmericanCatholic.org
- ^ a b「福者ヨハネ・ドゥンス・スコトゥスの生涯」 EWTN。
- ^ “INEFFABILIS DEUS (無原罪の御宿り) 教皇ピウス9世” . ewtn.com。
- ^第2回オレンジ公会議、カノン19、Wayback Machineに2009年1月13日アーカイブ「神の慈悲によってのみ救われる。たとえ人間性がその形成時の完全性を保ったとしても、創造主の助けなしには自らを救うことはできない。したがって、神の恩寵なしには人間は受けた健康を守ることができないのだから、神の恩寵なしには、失ったものをどうやって取り戻すことができるだろうか?」
- ^初心者のための神学、フランシス・ジョセフ・シード著、1958 ISBN 0-7220-7425-5、134~138ページ
- ^バチカンのウェブサイトにある使徒憲章「Munificentissimus Deus」第44項、Wayback Machineで2013年9月4日にアーカイブ
- ^ルートヴィヒ・オットの『カトリック教義の基礎』 250ページ以降。
- ^カトリック教義の基礎、ルートヴィヒ・オット著、第3巻、第3部、第2章、§6、 ISBN 0-89555-009-1
- ^ 「使徒憲章 Munificentissimus Deus, no 44」 Vatican.va. 2013年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月3日閲覧。
- ^ a bマーク・ミラヴァル著『マリア入門』(1993年)クイーンシップ出版ISBN 978-1-882972-06-775~78ページ
- ^ポール・ハフナー著『マリア論:司祭、助祭、神学生、奉献生活者のためのガイド』(2008年) ISBN 9781579183554M.ミラヴァッレ編、328~350ページ
- ^ディオクレイアのカリストス(ウェア)司教、『フェスタル・メナイオン』[ロンドン:フェイバー・アンド・フェイバー、1969年]、64ページ。
- ^カトリックの答えの本:ジョン・トリジリオ、ケネス・ブリゲンティ著、2007年ISBN 1-4022-0806-564ページ
- ^シューメーカー 2006, p. 201
- ^中世資料集より、ダマスコのヨハネによる「聖母マリアの死後に関する三つの説教」
- ^ビッグハム第7章
- ^ Summa Theologica III.59.1 オブジェクト 2、広告 2
- ^ジョージ・ファーガソン、1996年『キリスト教美術における記号とシンボル』ISBN 019501432492ページ
- ^ビッグハム、73~76
- ^マッケイ、グレッチェン・K. (1999). 「ダニエル書『太古の日の幻』の東方キリスト教釈義の伝統」 .初期キリスト教研究ジャーナル. 7 : 139–161 . doi : 10.1353/earl.1999.0019 . S2CID 170245894 .
- ^カートリッジとエリオット、69~72
- ^古代の神の画像を含む写本については、グレッチェン・クレアリング・マッケイの未発表論文「神の画像化:ビザンチン写本における古代の神の表現の研究」(バージニア大学、1997年)で論じられている。
- ^モスクワ大公会議(1666-1667年)第2章43-45節、レフ・プハロ聖職者訳『カナダ正教会宣教ジャーナル』
- ^デイヴィッド・ウィリー (2010年7月15日). 「バチカン、虐待事件の処理を『迅速化』」 BBCニュース. 2010年10月28日閲覧。
- ^ “Comunicato della Sala Stampa: Istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Mineri” .教皇庁報道局。 2014 年 3 月 22 日。2014 年3 月 30 日に取得。






