ディラックのデルタ関数

| 微分方程式 |
|---|
| 範囲 |
| 分類 |
| 解決 |
| 人々 |
数学的解析において、ディラックのデルタ関数(または分布)は単位インパルスとも呼ばれ、[ 1 ]実数上の一般化された関数であり、その値はゼロ以外のすべての点でゼロであり、実数線全体にわたる積分は1に等しい。[ 2 ]したがって、それは 次のよう に 経験的に表すことができる。
この特性を持つ関数は存在しないため、デルタ「関数」を厳密にモデル化するには、極限、または数学で一般的な測度論と超関数の理論を使用する必要があります。
デルタ関数は物理学者ポール・ディラックにちなんで名付けられ、物理学と工学の分野で質点や集中荷重のモデル化に日常的に応用されてきました。デルタ関数と呼ばれるのは、クロネッカーのデルタ関数の連続的な類似物であるためです。デルタ関数の数学的厳密さは、ローラン・シュワルツが超関数論を展開するまで議論の的となっていました。シュワルツは超関数論において、デルタ関数を関数に作用する線型形式として定義しました。
動機と概要
ディラックのデルタのグラフは通常、全体の - 軸と正の - 軸に沿っていると考えられています。[ 3 ]ディラックのデルタは、高くて狭いスパイク関数(インパルス)や、点電荷や点質点などの他の同様の抽象化をモデル化するために使用されます。[ 4 ]たとえば、ビリヤードのボールが打たれるダイナミクスを計算するには、ディラックのデルタで衝撃の力を近似することができます。 [ 5 ]そうすることで、方程式を簡略化し、衝突の全インパルスのみを考慮してボールの動きを計算できます。 [ 6 ]
応用数学において、デルタ関数は、各要素が原点に高いスパイクを持つ関数の列の一種の極限(弱い極限)として扱われることが多い。例えば、分散がゼロに近づく原点を中心とするガウス分布の列などである。(ただし、一部の応用では、高度に振動する関数がデルタ関数の近似として使用されることもある。以下を参照)。
ディラックのデルタ関数は、上で概説した望ましい特性を前提とすると、定義域と値域が実数である関数にはなり得ない。[ 7 ]例えば、と はを除いてどこでも等しいが、積分は異なる。ルベーグ積分論によれば、と がほぼどこでも となるような関数であれば、が積分可能であることと、との積分が同一であることは同値である。[ 8 ]ディラックのデルタ関数をそれ自体で数学的対象とみなす厳密なアプローチでは、測度論または超関数の理論が用いられる。[ 9 ]
歴史
ポール・ディラックは、量子力学の発展の一環として、1927 年の論文で - 関数を導入し、これは後に 1930 年の著書『量子力学の原理』で普及しました。[ 10 ]彼はこれを離散的なクロネッカーのデルタの連続体アナログとして使用したため、「デルタ関数」と呼びました。[ 11 ]しかし、この関数は 19 世紀に複数の数学者によって使用されていました。[ 12 ]ディラックの伝記作家であるグラハム・ファーメロは、ディラックの工学のバックグラウンドを考慮して、オリバー・ヘヴィサイドがディラックに直接影響を与えた可能性が高いと推測しました。 [ 13 ]実際、ヘヴィサイドは電磁気学と電気工学の研究で - 関数を導入しました。[ 14 ] 1963 年のインタビューで、ディラックは、「すべての電気技術者はパルスの概念に精通しており、- 関数はパルスを数学的に表現する方法に過ぎません」と述べています。[ 15 ]数学者は同じ概念を通常の意味での関数ではなく、一般化された関数または分布と呼びます。 [ 16 ]
-関数の最も古い使用例は、ジャン=バティスト・ジョセフ・フーリエの著作に見られる。[ 13 ]フーリエは、1822年に発表した論文『運動の分析理論』の中で、現在フーリエ積分定理と呼ばれている定理を次の形式で提示した。[ 17 ]これは、-関数を次の形式で 導入したことと同義である。 [ 18 ]
その後、無限に高い単位インパルスデルタ関数(コーシー分布の無限小版)の無限小式が、1827年のオーギュスタン=ルイ・コーシーのテキストに明示的に登場した。[ 19 ]コーシーはこの定理を指数関数を用いて表現した。[ 20 ]
コーシーは、状況によっては積分の順序がこの結果に重要になることを指摘した(フビニの定理と比較のこと)。[ 21 ] [ 22 ]
超関数の理論を用いて正当化されるように、コーシー方程式はフーリエの元の定式化に似るように変形することができ、関数は次のように 表される 。ここで関数は次のように表される。
シメオン・ドニ・ポアソンとシャルル・エルミートはフーリエ積分の研究において-関数を導入した。 [ 23 ]グスタフ・キルヒホフはグリーンの定理を波動光学(ホイヘンスの原理)に応用した論文でこれを用いた。 [ 15 ]キルヒホフ、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ、ウィリアム・トムソン(ケルビン卿)はこれをガウス関数の列の極限とみなした。しかし、-関数を独立した実体として明示的に初めて提示したのはヘヴィサイドとディラックであった。[ 23 ]
指数関数の形式とその応用に必要な関数の様々な制限に対する厳密な解釈は、数世紀にわたって続けられてきた。古典的な解釈の問題点は、次のように説明される。古典的な関数の概念は、フーリエ積分が存在するためには無限大において十分急速にゼロに近づく必要があるため、狭すぎる。このため、古典的なフーリエ変換を分布に拡張すると、変換できるオブジェクトのクラスが大幅に拡大する。[ 24 ]フーリエ積分に関するさらなる研究には、ミシェル・プランシュレル(1910年)、ノーバート・ウィーナー、サロモン・ボクナー(1930年頃)、そして最後に厳密な分布理論を確立したローラン・シュワルツ(1945年)による貢献がある。[ 25 ]
定義
ディラックのデルタ関数は、実数直線上の関数として大まかに考えることができ、原点以外ではゼロで原点では無限大であり、 また恒等式を満たすように制約されている[ 26 ]。
これは単なる経験的な特徴づけである。実数上に定義された拡張実数値関数はこれらの性質を持たないため、ディラックのデルタは伝統的な意味での関数ではない。 [ 27 ]
対策として
ディラックのデルタ関数の概念を厳密に捉える 1 つの方法は、ディラック測度と呼ばれる測度を定義することです。これは、実数直線のサブセットを引数として受け入れ、の場合はを返し、それ以外の場合は を返します。[ 28 ]デルタ関数が 0 における理想化された質点をモデル化するものとして概念化される場合、 はセット に含まれる質量を表します。次に、に対する積分を、この質量分布に対する関数の積分として定義できます。正式には、ルベーグ積分が必要な解析デバイスを提供します。測度に関するルベーグ積分は、 すべての連続コンパクトにサポートされた関数 に対してを満たします 。測度はルベーグ測度に関して絶対的に連続ではありません。実際、それは特異測度です。したがって、デルタ測度にはラドン・ニコディム導関数(ルベーグ測度に関して) がなく、この特性が 成り立つ真の関数はありません。[ 29 ]結果として、後者の表記法は表記法の都合の良い乱用であり、標準的な(リーマン積分やルベーグ積分)積分ではない。[ 30 ]
デルタ測度は、上の確率測度として、その累積分布関数によって特徴付けられ、これは単位ステップ関数である。[ 31 ] これは、が累積指示関数の測度 に関する積分であることを意味する。すなわち、 後者はこの区間の測度である。したがって、特にデルタ関数の連続関数に対する積分は、リーマン・スティルチェス積分 として適切に理解することができる。[ 32 ]
の高次モーメントはすべてゼロである。特に、特性関数とモーメント生成関数はともに1である。[ 33 ]
配布として
超関数の理論では、一般化関数はそれ自体が関数ではなく、他の関数に対して「積分」されたときに他の関数にどのような影響を与えるかによってのみ関数であるとみなされる。[ 34 ]この考え方に従えば、デルタ関数を適切に定義するには、十分に「良い」テスト関数 に対するデルタ関数の「積分」が何であるかを述べれば十分である。[ 7 ]デルタ関数がすでに測度として理解されている場合、その測度に対するテスト関数のルベーグ積分は必要な積分を提供する。[ 35 ]
典型的なテスト関数の空間は、必要な数の導関数を持つ、コンパクトな台を持つ滑らかな関数の集合から構成される。超関数として、ディラックデルタはテスト関数の空間上の 線型関数であり、次のように定義される。
| 1 |
が適切に分布であるためには、検定関数の空間上の適切な位相において連続でなければならない。一般に、検定関数の空間上の線型関数が分布を定義するためには、任意の正の整数 に対して、任意の検定関数 に対して不等式 が成り立つよう な整数と定数 が存在することが必要かつ十分である。 ここで は上限 を表す。分布 では、すべての に対してとなる不等式 ( ) が成り立つ。したがって、は位数ゼロの分布である。さらに、これはコンパクトな台を持つ分布であり、台は である。[ 37 ]
デルタ分布は、いくつかの同値な方法で定義することもできます。例えば、デルタ分布はヘヴィサイドのステップ関数の分布微分です。これは、任意の検定関数φに対して、
直感的に、部分積分が許されるならば、後者の積分は次のように簡約されるはずであり 、実際、スティルチェス積分には部分積分の形式が許されており、その場合、
測度論の文脈では、ディラック測度は積分によって超関数を生じる。逆に、式( 1 )は、コンパクトに支えられた連続関数全体の成す空間上のダニエル積分を定義し、これはリースの表現定理により、あるラドン測度に関するルベーグ積分として表すことができる。[ 38 ]
一般的に、 「ディラックのデルタ関数」という用語は、測度ではなく超関数の意味で用いられます。ディラック測度は、測度論における対応する概念を表す複数の用語の一つです。一部の文献では、 「ディラックのデルタ分布」という用語も使用されています。
一般化
デルタ関数は、n次元ユークリッド空間R nにおいて、次の測度として 定義される。
コンパクトに支えられた連続関数fに対して、 n次元デルタ関数は、各変数における 1 次元デルタ関数の積の測度として定義される。したがって、形式的には、 x = ( x 1 , x 2 , ..., x n )とすると、[ 39 ]
| 2 |
デルタ関数は、1次元の場合と全く同じように、分布の意味で定義することもできます。[ 40 ]しかし、工学の文脈で広く使用されているにもかかわらず、分布の積は非常に狭い状況でのみ定義できるため、(2)は注意して扱う必要があります。[ 41 ] [ 42 ]
ディラック測度の概念は任意の集合上で意味を成す。[ 28 ]したがって、Xが集合、x 0 ∈ Xがマークされた点、ΣがXの部分集合の任意のシグマ代数であるとき、集合A ∈ Σ上 で定義される測度は
はx 0に集中するデルタ測度または単位質量です。
デルタ関数のもう一つの一般的な一般化は、微分可能多様体への一般化である。この多様体では、微分可能構造のため、デルタ関数の超関数としての性質のほとんどを活用できる。点x 0 ∈ Mを中心とする多様体M上のデルタ関数は、次の超関数として定義される。
| 3 |
M上のコンパクトに支えられた滑らかな実数値関数φすべてに対して成り立つ。[ 43 ]この構成の一般的な特殊ケースは、 M がユークリッド空間R n上の開集合である場合である。
局所コンパクトハウスドルフ空間X上で、点xに集中するディラックのデルタ測度は、コンパクトに支えられた連続関数φ上のダニエル積分 ( 3 ) に関連付けられたラドン測度である。[ 44 ]この一般性レベルでは、微積分そのものはもはや不可能であるが、抽象解析からの様々な手法が利用可能である。例えば、写像は、その漠然とした位相を備えた、 X上の有限ラドン測度の空間へのXの連続埋め込みである。さらに、この埋め込みによるXの像の凸包は、 X上の確率測度の空間で稠密である。[ 45 ]
プロパティ
スケーリングと対称性
デルタ関数は、非ゼロスカラーに対して次のスケーリング特性を満たす:[ 46 ]
など
| 4 |
スケーリング特性の証明: 変数x′ = αx の変化を用いる。α が負、すなわち α = −| a | の場合、となる。したがって、と なる 。
特に、デルタ関数は、
これは次数−1の同次である。
代数的性質
δとxの分布積はゼロに等しい。
より一般的には、すべての正の整数に対して。
逆に、xf ( x ) = xg ( x )(fとgは分布)の場合、
翻訳
任意の関数の積分に時間遅延ディラックデルタを乗じると、
これは、ふるい分け特性[ 48 ]またはサンプリング特性[ 49 ]と呼ばれることもあります。デルタ関数は、 t = Tにおけるf(t)の値を「ふるいにかける」と言われています。[ 50 ]
したがって、関数f ( t )を時間遅延ディラックデルタと畳み込むと、同じ量だけf ( t )が時間遅延することになる。 [ 51 ]
ふるい分け特性は、fが緩和分布であるという厳密な条件の下で成立する(フーリエ変換に関する以下の議論を参照)。例えば、特別な場合として、(分布の意味で理解される)恒等式が成り立つ。
機能を持つ構成
より一般的には、デルタ分布は滑らかな関数g ( x )とよく知られた変数変換の公式が成り立つように構成することができる(ただし、)
ただし、 gは連続的に微分可能な関数で、 g′ が零となる点がないものとする。[ 52 ]つまり、この恒等式がコンパクトに支えられたすべてのテスト関数fに対して成り立つように、分布に意味を割り当てる唯一の方法がある。したがって、定義域はg′ = 0点を除外するように分割する必要がある。この分布は、gが零となる点がないときδ ( g ( x )) = 0 を満たし、そうでない場合、g がx 0に実根を持つとき、
したがって、連続的に微分可能な関数gの合成δ ( g ( x ))を次のよう に定義するのが自然である。
ここで、和はg ( x )のすべての根に及び、それらは単純根であると仮定される。したがって、例えば
積分形式では、一般化されたスケーリング特性は次のように表される。
不定積分
定数と「行儀の良い」任意の実数値関数y ( x )の 場合、 H ( x )はヘビサイドのステップ関数、cは積分定数です。
n次元の特性
n次元空間のデルタ分布は、代わりに次のスケーリング特性を満たす ので、 δは次数−nの同次分布となる。
1変数の場合と同様に、δの合成を双リプシッツ関数[ 53 ] g : Rn → Rnで一意に定義することができ、すべてのコンパクトに サポートされた関数fに対して以下が成り立つ 。
幾何学的測度論の共面積公式を用いると、あるユークリッド空間から次元の異なる別のユークリッド空間へのデルタ関数の合成を定義することもできる。その結果は一種の電流となる。連続的に微分可能な関数g : Rn → Rでgの勾配がゼロにならない特殊なケースでは、次の恒等式が成り立つ[ 54 ]。 ここで右辺の積分はg −1 (0)、つまりミンコフスキー含有量測度に関してg ( x )=0で定義される( n −1)次元面上の積分である。これは単純層積分として知られている。
より一般的には、SがR nの滑らかな超曲面である場合、 S上の任意のコンパクトにサポートされた滑らかな関数gを積分する超関数をSに関連付けることができます。
ここで、σはSに付随する超曲面測度である。この一般化は、S上の単純層ポテンシャルのポテンシャル理論と関連している。DがR n内の滑らかな境界Sを持つ領域である場合、δ S はDの指示関数の正規分布的な意味で の導関数に等しい。
3 次元では、デルタ関数は球座標で次のように表されます。
デリバティブ
ディラックのデルタ分布の微分はδ′で表され、ディラックデルタプライムまたはディラックデルタ微分とも呼ばれ、コンパクトにサポートされた滑らかなテスト関数φ上で次のように定義される[ 57 ]。
ここでの最初の等式は部分積分の一種である。なぜならδが真の関数であれば、
数学的帰納法によれば、δのk次導関数は、次のようにテスト関数に与えられる分布と同様に定義される。
特に、δは無限に微分可能な分布です。
デルタ関数の1次導関数は、差分商の分布極限である。[ 58 ]
より正確には、 τ hは変換演算子であり、関数 τ h φ ( x ) = φ ( x + h )上で定義され、超関数S上 では
電磁気学の理論では、デルタ関数の一次微分は原点に位置する点磁気双極子を表す。したがって、これは双極子関数または二重項関数と呼ばれる。[ 59 ]
デルタ関数の微分は、 テスト関数を適用して部分積分を行うことで示せる [ 60 ]など、いくつかの基本的な性質を満たしている。
さらに、 δ′とコンパクトにサポートされた滑らかな関数fとの畳み込みは
これは畳み込みの分布微分の特性から導かれます。
高次元
より一般的には、n次元ユークリッド空間の開集合U上で、点a∈Uを中心とするディラックのデルタ分布は、 U上にコンパクト台を持つすべての滑らかな関数の空間で あるすべてのに対して[ 61 ]で定義される。が任意の多重添字で、が関連する混合偏微分演算子を表す場合、δ aのα次導関数∂αδ aは[ 61 ]で与えられる。
つまり、δaのα次導関数は、任意のテスト関数φ上の値がaにおけるφのα次導関数(適切な正または負の符号付き) となる分布です。
デルタ関数の一次偏微分は、座標平面に沿った二重層として考えられます。より一般的には、表面上に支持された単層の法線微分は、その表面上に支持された二重層であり、層流磁気単極子を表します。デルタ関数の高次微分は、物理学では多重極子として知られています。[ 62 ]
高次微分は、点支持を持つ超関数の完全な構造の構成要素として数学に自然に登場します。SがU上の任意の超関数で、 { a }という一点からなる集合に支持されている場合、整数mと係数cαが存在し、[ 61 ] [ 63 ]
表現
デルタ関数は関数列の極限として見ることができる。
この制限は弱い意味で意味されます。
| 5 |
コンパクト台を持つすべての連続関数fに対してこの極限が成り立つこと、あるいは、コンパクト台 を持つすべての滑らかな関数fに対してこの極限が成り立つこと。前者は測度のあいまい位相における収束であり、後者は超関数の意味での収束である。
恒等式の近似
近似デルタ関数ηεは次のように構成できる。ηをR上の絶対積分可能関数で全積分値が1であるとし、
n次元では、代わりにスケーリングを使用する。
すると、単純な変数変換により、η εも積分1を持つことが示される。( 5 )はすべての連続コンパクトに支えられた関数fに対して成り立ち、[ 64 ]、η ε は測度の意味で δに弱収束することが示される。
このように構成された η ε は恒等関数の近似として知られている。[ 65 ]この用語は、絶対積分可能関数の空間L 1 ( R )が関数の畳み込み操作に関して閉じているためである。すなわち、 fとg がL 1 ( R )に含まれるときはいつでも、 f ∗ g ∈ L 1 ( R )となる。しかし、 L 1 ( R )には畳み込み積の恒等関数は存在しない。すなわち、すべてのfに対してf ∗ h = fとなるような元hは存在しない。それでも、列η ε は次の意味でそのような恒等関数を近似する 。
この極限は平均収束( L 1における収束)の意味で成立する。η εに関する更なる条件、例えばそれがコンパクトに支えられた関数に付随する軟化因子であることなど[ 66 ]は、ほぼ全ての点における収束を保証するために必要である。
初期η = η 1がそれ自身滑らかでコンパクトにサポートされている場合、その列は軟化関数と呼ばれる。標準的な軟化関数は、例えば η を適切に正規化されたバンプ関数として選択することによって得られる。
(全積分が1になることを保証する)。
数値解析のような状況では、恒等式の区分線形近似が望ましい。これは、 η 1をハット関数とすることで得られる。η 1をこのように選ぶと、
これらはすべて連続しており、コンパクトにサポートされていますが、滑らかではないため、緩和作用はありません。
確率論的考察
確率論の文脈では、恒等関数への近似において初期η 1 は正でなければならないという追加条件を課すのは自然である。なぜなら、そのような関数は確率分布を表すからである。確率分布との畳み込みは、出力が入力値の凸結合であり、したがって入力関数の最大値と最小値の間になるため、オーバーシュートやアンダーシュートを生じないため、好ましい場合がある。 η 1を任意の確率分布とみなし、上記のようにη ε ( x ) = η 1 ( x / ε )/ εとすると、恒等関数への近似が生じる。一般に、さらにη の平均が0で高次モーメントが小さい場合、これはデルタ関数により急速に収束する。例えば、η 1が上の一様分布(長方形関数とも呼ばれる)である場合、次のようになる。[ 67 ]
もう一つの例はウィグナー半円分布である。
これは連続的かつコンパクトにサポートされていますが、滑らかではないため、緩和機能はありません。
半群
デルタ関数の近似は、しばしば畳み込み半群として現れる。[ 68 ]これは、 η εとη δの畳み込みが満たさなければならない というさらなる制約に等しい。
すべてのε、δ > 0について。デルタ関数を近似するL 1の畳み込み半群は常に上記の意味で恒等関数の近似となるが、半群条件は非常に強い制約である。
実際には、デルタ関数を近似する半群は、物理的に動機付けられた楕円型または放物型偏微分方程式の基本解またはグリーン関数として生じる。応用数学の文脈では、半群は線形時間不変システムの出力として生じる。抽象的には、Aがxの関数に作用する線形作用素である場合、初期値問題を解くことによって畳み込み半群が生じる。
ここで、極限は通常通り弱い意味で理解される。η ε ( x ) = η ( ε , x )と置くと、関連する近似デルタ関数が得られる。
このような基本解から生じる物理的に重要な畳み込み半群の例には次のものがあります。
熱核
[ 69 ]によって定義される熱核は、t = 0の時点 で無限長のワイヤの原点に単位熱エネルギーが蓄えられていると仮定した場合の、t > 0の時点でのワイヤ内の温度を表す。この半群は、1次元熱方程式に従って発展する。
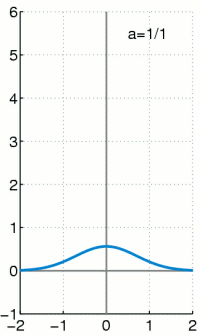
確率論において、η ε ( x )は分散ε、平均0の正規分布である。これは、標準的なブラウン運動に従って原点から出発した粒子の位置の、時刻t = εにおける確率密度を表す。この文脈において、半群条件はブラウン運動のマルコフ性を表す表現である。
高次元ユークリッド空間R nにおいて、熱核は であり 、必要な変更を加えた上 で、同様の物理的解釈を持つ。また、 ε → 0のとき、分布の意味でη ε → δとなるという意味で、デルタ関数の近似を表す。
ポアソン核
ポアソン核
は上半平面におけるラプラス方程式の基本解である。 [ 70 ]これは、エッジに沿った電位がデルタ関数で一定に保たれている半無限板の静電ポテンシャルを表す。ポアソン核は、コーシー分布やエパネチニコフ核関数、ガウス核関数とも密接に関連している。[ 71 ]この半群は次式に従って発展する。
ここで演算子は厳密にはフーリエ乗数として定義される。
振動積分
波動伝播や波動力学といった物理学の分野では、関係する方程式は双曲型であり、より特異な解を持つ可能性がある。その結果、関連するコーシー問題の基本解として生じる近似デルタ関数は、一般に振動積分となる。遷音速気体力学のオイラー・トリコミ方程式の解から得られる例として、[ 72 ]再スケールされたエアリー関数が挙げられる。
フーリエ変換を用いているにもかかわらず、これはある意味で半群を生成することが容易に分かる。これは絶対積分可能ではないため、上記の強い意味での半群を定義することはできない。振動積分として構成される多くの近似デルタ関数は、測度の意味で収束するのではなく、超関数の意味でのみ収束する(例として、以下のディリクレ核が挙げられる)。
もう一つの例はR 1+1の波動方程式のコーシー問題である: [ 73 ]
解u は、原点に初期擾乱がある無限弾性弦の平衡からの変位を表します。
この種の恒等式の他の近似値としては、シンク関数(電子工学や通信分野で広く使用されている) がある。
ベッセル関数
平面波分解
線形偏微分方程式の研究への一つのアプローチ
ここでLはR n上の微分作用素である。この方程式の解である基本解をまず求める。
Lが特に単純な場合、この問題はフーリエ変換を用いて直接解くことができることが多い(既に述べたポアソン核や熱核の場合のように)。より複雑な演算子の場合、まず次のような方程式を考える方が簡単な場合がある。
ここでhは平面波関数であり、次の形をとる。
あるベクトルξに対して、このような方程式は( Lの係数が解析関数であれば)コーシー・コバレフスカヤの定理によって、( Lの係数が定数であれば)求積法によって解くことができる。したがって、デルタ関数を平面波に分解できれば、原理的には線型偏微分方程式を解くことができる。
デルタ関数の平面波への分解は、ヨハン・ラドンによって本質的に最初に導入され、その後フリッツ・ジョン(1955)によってこの形で発展した一般的な手法の一部でした。[ 74 ] kをn + kが偶数になるように選び、実数sに対して、
そしてδは、単位球面S n −1におけるξについてg ( x · ξ )の単位球面測度dωに関する積分にラプラシアンのべき乗を適用することによって得られる。
ここでのラプラシアンは弱微分として解釈されるので、この式は任意のテスト関数φに対して、
この結果は、ニュートンポテンシャル(ポアソン方程式の基本解)の公式から導かれる。これは本質的にラドン変換の逆変換公式の一種であり、超平面上の積分からφ ( x )の値を復元する。[ 75 ]例えば、nが奇数でk = 1の場合、右辺の積分は
ここでRφ ( ξ , p )はφのラドン変換である。
平面波分解の別の等価表現は次の通りである: [ 76 ]
フーリエ変換
デルタ関数は緩和分布であるため、明確に定義されたフーリエ変換を持つ。正式には[ 77 ]
厳密に言えば、ある分布のフーリエ変換は、シュワルツ関数と緩和分布の双対関係においてフーリエ変換の自己随伴性を課すことによって定義される。したがって、は、次を満たす唯一の緩和分布として定義される 。
全てのシュワルツ関数φに対して、
この恒等式の結果として、デルタ関数と他の緩和分布Sとの畳み込みは単にSとなる。
つまり、δは緩和分布上の畳み込みの単位元であり、実際、畳み込みの下でコンパクトに支えられた分布の空間は、デルタ関数を単位とする結合代数である。この性質は信号処理において基本的なものであり、緩和分布との畳み込みは線形時不変システムであり、この線形時不変システムを適用することでそのインパルス応答を測定することができる。インパルス応答は、 δに適切な近似値を選択することで任意の精度で計算でき、一度それが分かれば、システムを完全に特徴づけることができる。LTIシステム理論の§インパルス応答と畳み込みを参照のこと。
緩和分布f ( ξ ) = 1の逆フーリエ変換はデルタ関数です。正式には、これは と表され 、より厳密には、 すべてのシュワルツ関数fに対して となるため、 が成り立ちます。
これらの用語で、デルタ関数はR上のフーリエ核の直交性に関する示唆的な記述を与える。正式には、
もちろん、これは緩和分布のフーリエ変換が、 フーリエ変換の自己随伴性を課すことによって再び従うという 主張の省略形 です 。
フーリエ変換の解析接続により、デルタ関数のラプラス変換は[ 78 ]となる。
フーリエカーネル
フーリエ級数の研究では、周期関数に関連付けられたフーリエ級数が関数に収束するかどうか、またどのような意味で収束するかを決定することが主要な問題です。周期2πの関数fのフーリエ級数のn番目の部分和は、区間[−π,π]上でのディリクレ核との畳み込みによって定義されます。 したがって、 ここで 基本フーリエ級数の基本結果は、区間 [−π,π]に制限されたディリクレ核は、 N → ∞としてデルタ関数の倍数に近づくことを示しています。これは、コンパクトにサポートされた滑らかな関数f に対して、超関数の意味で解釈されます 。したがって、 区間[−π,π]上では正式には次が成り立ちます 。
それにもかかわらず、この結果はすべてのコンパクトに支えられた連続関数に当てはまるわけではない。つまり、D N は測度の意味で弱収束しない。フーリエ級数の収束性の欠如は、収束をもたらすための様々な総和可能性法の導入につながった。チェザロ総和法はフェイェール核[ 79 ]につながる。
フェイエル核は、より強い意味でデルタ関数に近づく傾向がある。[ 80 ]
コンパクトに支えられた連続関数fに対して成り立つ。これは、任意の連続関数のフーリエ級数は、その関数のあらゆる点における値とチェザロ和可能であることを意味する。
ヒルベルト空間理論
ディラックのデルタ分布は、平方可積分関数の成すヒルベルト空間L 2上の稠密に定義された非有界線型関数である。[ 81 ]実際、滑らかでコンパクトに支えられた関数はL 2上で稠密であり、そのような関数に対するデルタ分布の作用は明確に定義されている。多くの応用において、 L 2の部分空間を識別し、デルタ関数が有界線型関数を定義するより強い位相を与えることが可能である。
ソボレフ空間
実数直線R上のソボレフ空間に対するソボレフ埋め込み定理は、任意の 平方積分可能な関数fが
は自動的に連続であり、特に
したがってδはソボレフ空間H 1上の有界線型汎関数である。[ 82 ]同様に、δはH 1の連続双対空間H −1の元である。より一般に、n次元では、δ ∈ H − s ( R n )が成り立つ。ただしs > n/2。
正則関数の空間
複素解析では、デルタ関数はコーシーの積分公式を介して登場する。コーシーの積分公式によれば、 Dが滑らかな境界を持つ 複素平面上の領域である場合、
Dの閉包上で連続なD内のすべての正則関数fに対して成り立つ。結果として、デルタ関数δ z は、この正則関数のクラスではコーシー積分で表される。
さらに、H 2 (∂ D )を、 Dの境界まで連続なDのすべての正則関数のL 2 (∂ D )における閉包からなるハーディ空間とする。すると、H 2 (∂ D )の関数はDの正則関数に一意に拡張され、コーシー積分公式は依然として成立する。特にz∈Dに対して、デルタ関数δzはH 2 (∂ D )上の連続線型関数である。これは、複素変数が複数ある状況の特殊なケースであり、滑らかな領域Dに対して、セゲー核がコーシー積分の役割を果たす。[ 83 ]
正則関数の空間におけるデルタ関数の別の表現は、開集合 における平方積分可能な正則関数の空間上である。これは の閉部分空間であるため、ヒルベルト空間となる。一方、の点での正則関数を評価する汎関数は連続汎関数であるため、リースの表現定理により、核 に対する積分、すなわちベルグマン核で表される。[ 84 ]この核は、このヒルベルト空間におけるデルタ関数の類似物である。このような核を持つヒルベルト空間は、再生核ヒルベルト空間と呼ばれる。単位円板の特別な場合では、
アイデンティティの解決
可分ヒルベルト空間における関数の完全な直交基底関数集合{ φ n }、例えばコンパクトな自己随伴作用素の正規化された固有ベクトルが与えられれば、任意のベクトルfは次のように表すことができる 。 係数{α n }は 次のように表される。これは ディラックのブラケット記法 の一種である。[ 85 ]この記法を用いると、 fの展開は2項形式となる。[ 86 ]
ヒルベルト空間上の恒等作用素を I とすると、この式は 恒等作用素の分解と 呼ばれる。ヒルベルト空間が領域D上の平方可積分関数の空間L 2 ( D )であるとき、以下の量:
は積分演算子であり、 fの式は次のように書き直すことができる。
右辺はL 2 の意味でfに収束する。fが連続関数であっても、点ごとの意味では必ずしも成立する必要はない。しかしながら、記法を乱用して デルタ関数の表現となる書き方をすることが多い 。 [ 87 ]
適切なリグドヒルベルト空間(Φ, L 2 ( D ), Φ*)(ただしΦ ⊂ L 2 ( D )はすべてのコンパクトに支えられた滑らかな関数を含む)を用いると、この和は基底φ nの性質に依存してΦ*に収束する可能性がある。実用上重要なほとんどの場合、直交基底は積分演算子または微分演算子(例えば熱核)から得られ、その場合級数は分布の意味で収束する。[ 88 ]
無限小デルタ関数
コーシーは1827年の多くの論文で、無限小αを用いて、無限に高く狭いディラック型デルタ関数δαを満たす単位インパルスを記述した。 [ 89 ]コーシーはCours d'Analyse (1827年)において、零に向かう列として無限小を定義した。つまり、そのような零列は、コーシーとラザール・カルノーの用語 では無限小となる。
非標準解析は、無限小を厳密に扱うことを可能にする。山下(2007)の論文には、超実数によって提供される無限小に富んだ連続体の文脈における現代のディラックのデルタ関数に関する参考文献が含まれている。ここで、ディラックのデルタは、任意の実関数Fに対してフーリエとコーシーが予想した性質を持つ実関数によって与えられる。[ 90 ]
ディラックコム

ディラックのデルタ測度のいわゆる均一な「パルス列」は、ディラック・コームあるいはSha分布として知られ、デジタル信号処理(DSP)や離散時間信号解析でよく用いられる標本化関数を生成する。ディラック・コームは無限和として与えられ、その極限は分布の意味で理解され、 各整数における質点の列となる。[ 91 ]
全体の正規化定数を除いて、ディラックコームはそれ自身のフーリエ変換に等しい。これは重要な意味を持つ。なぜなら、fが任意のシュワルツ関数である場合、fの周期化は畳み込みによって与えられるからである 。 特に、 はまさにポアソン総和公式である。[ 92 ] [ 93 ]より一般的には、 fが急降下する緩和分布、あるいはそれと同値で、緩和分布空間内で緩やかに増加する通常の関数である 場合も、この公式は成り立つ。
ソホーツキー・プレメリ定理
量子力学において重要なソホーツキー・プレメリ定理は、デルタ関数と分布pv を関連付けます。1/×、関数のコーシー主値1/×、定義
ソホーツキーの公式によれば[ 94 ]
ここでの極限は、すべてのコンパクトに支えられた滑らかな関数fに対して、
クロネッカーデルタとの関係
クロネッカーデルタδ ijは次のように定義される量である。
すべての整数i , jに対して、この関数は次のようなふるい分けの性質を満たす。つまり、 a i(iはすべての整数の集合に含まれる)が任意の二重無限列である場合、
同様に、 R上の任意の実数値または複素数値連続関数fに対して、ディラックのデルタはふるい分け特性を満たす。
これはクロネッカーのデルタ関数をディラックのデルタ関数の離散的な類似物として示している。[ 95 ]
アプリケーション
確率論
確率論と統計学において、ディラックのデルタ関数は、離散分布、または部分的に離散的で部分的に連続な分布を、確率密度関数(通常は絶対連続分布を表すために使用される)を用いて表すためによく用いられる。例えば、点x = { x 1 , ..., x n }から成り、対応する確率p 1 , ..., p nを持つ離散分布の確率密度関数f ( x )は、次のように表される[ 96 ]
別の例として、6/10の確率で標準正規分布 が、4/10の確率で正確に3.5 が返される分布(つまり、部分的に連続で部分的に離散的な混合分布)を考えてみましょう。この分布の密度関数は次のように表すことができます。
デルタ関数は、連続微分可能関数によって変換された確率変数の確率密度関数を表すためにも用いられる。Y = g(X) が連続微分可能関数である場合、 Yの確率密度は次のように表される 。
デルタ関数は、拡散過程(ブラウン運動など)の局所時間を表すために全く異なる方法でも用いられる。 [ 97 ]確率過程B ( t )の局所時間は次のように与えられ 、過程が過程の範囲内の点x に費やす時間を表す。より正確には、1次元においてこの積分は次のように書ける。 ここで、は区間の指示関数である。
量子力学
デルタ関数は量子力学において便宜的なものである。粒子の波動関数は、与えられた空間領域内で粒子が見つかる確率振幅を与える。波動関数は二乗積分可能な関数のヒルベルト空間L 2の元であると仮定され、与えられた区間内で粒子が見つかる確率全体は、波動関数の大きさの二乗を区間で積分したものである。波動関数の集合{ | φ n ⟩ }が直交するのは、
ここでδ nm はクロネッカーのデルタである。直交波動関数の集合が平方積分可能関数の空間において完備であるとは、任意の波動関数|ψ⟩ が複素係数を持つ{ | φ n ⟩ }の線形結合として表せる場合である。
ここでc n = ⟨ φ n | ψ ⟩である。波動関数の完全な直交系は、量子力学において、エネルギー準位(固有値と呼ばれる)を測定するハミルトニアン(束縛系)の固有関数として自然に現れる。この場合の固有値の集合は、ハミルトニアンのスペクトルとして知られている。括弧記法では、この等式は恒等式 の解決を意味する。
ここでは固有値は離散的であると仮定されているが、観測量の固有値の集合は連続的であることもある。一例として位置演算子Qψ ( x ) = x ψ( x )が挙げられる。位置のスペクトル(1次元)は実数直線全体であり、連続スペクトルと呼ばれる。しかし、ハミルトニアンとは異なり、位置演算子には適切な固有関数がない。この欠点を克服する従来の方法は、超関数も許容することで利用可能な関数のクラスを拡張すること、すなわち、ヒルベルト空間をリグドヒルベルト空間に置き換えることである。[ 98 ]この文脈では、位置演算子には、実数直線上の点yでラベル付けされた一般化固有関数の完全な集合[ 99 ]があり、これは次のように与えられる。
位置演算子の一般化固有関数は固有ケットと呼ばれ、φy = | y⟩と表記される。[ 100 ]
同様の考察は、運動量作用素Pのような、連続スペクトルを持ち、退化した固有値を持たない他の(有界でない)自己随伴作用素にも当てはまる。その場合、実数の集合Ω (スペクトル)と、 y ∈ Ω となるような 超関数φ yの集合が存在し、
つまり、φ yはPの一般化固有ベクトルである。これらが分布の意味で「直交基底」を形成する場合、次の式が成り立つ。
すると、任意のテスト関数ψに対して、
ここでc ( y ) = ⟨ ψ , φ y ⟩である。つまり、恒等式の解決が存在する。
ここで、作用素値積分は再び弱意味で理解される。Pのスペクトルが連続部分と離散部分の両方を持つ場合、恒等式の解は離散スペクトル上の和と連続スペクトル上の積分によって得られる。
デルタ関数は、単一および二重のポテンシャル井戸の デルタポテンシャルモデルなど、量子力学においてさらに多くの特殊な用途にも使用されています。
構造力学
デルタ関数は構造力学において、構造物に作用する過渡荷重や点荷重を記述するために用いられる。時刻t = 0において突発的な力インパルスIによって励起される単純な質量-バネ系の支配方程式は[ 101 ] [ 102 ]と表される。 ここで、mは質量、ξはたわみ、kはバネ定数である。
別の例として、細長い梁の静的たわみを支配する方程式は、オイラー・ベルヌーイの定理によれば、
ここで、EIは梁の曲げ剛性、 wはたわみ、xは空間座標、q ( x )は荷重分布である。梁がx = x 0において点力Fによって荷重を受けている場合、荷重分布は次のように表される。
デルタ関数の積分はヘヴィサイドの階段関数となるため、複数の点荷重を受ける細長い梁の静的たわみは区分多項式の集合によって記述されることになります。
また、梁に作用する点モーメントはデルタ関数で記述できます。距離d離れた2つの反対方向の点力Fを考えてみましょう。これらの力は、梁に作用するモーメントM = Fdを生み出します。ここで、距離dが限界ゼロに近づくと仮定し、Mは一定に保ちます。x = 0に時計回りのモーメントが作用すると仮定すると、荷重分布は次のように表されます 。
したがって、点モーメントはデルタ関数の微分で表すことができます。梁方程式を再び積分すると、区分多項式たわみが得られます。
参照
注記
- ^ジェフリー1993、639ページ。
- ^
- アルフケン&ウェーバー 2000、p.84
- ゲルファントとシロフ 1966–1968、第 1 巻、§1.1
- ディラック 1967、58ページ
- ^趙 2011、p. 174 .
- ^ |ブレイスウェル 2000、p. 74 |スニーダー 2004、p. 212 }}
- ^ Popescu & Jianu 2023、p. 352 .
- ^スミス、キャンベル、トゥーミー 2026 、 p.154–155 。
- ^ a bゲルファンド&シロフ 1966–1968、第1巻、§1.1。
- ^シュワルツ 1950、19ページ。
- ^シュワルツ 1950、5ページ。
- ^
- ^ディラック 1967、62ページ。
- ^
- ^ a bファーメロ 2009、113ページ。
- ^
- ^ a bジャマー 1966、301ページ。
- ^
- ジー 2013、33ページ
- ジル&ライト 2013、312~314ページ
- ^ Fourier 1822 , p. 408、p. 449およびpp. 546–551と比較。フランス語原文はこちら。
- ^小松 2002、p. 200。
- ^ Laugwitz 1989、230ページ。
- ^
- ミン・U. & デブナス 2007、p. 4
- デブナス&バッタ 2007 、 p.2
- ^ Grattan-Guinness, Ivor (2009). 『フランス数学における畳み込み 1800–1840: 微積分学と力学から数理解析と数理物理学まで』第2巻. Birkhäuser. p. 653. ISBN 978-3-7643-2238-0。
- ^ たとえば、 Cauchy, Augustin-Louis (1789-1857) Auteur du texte (1882-1974) を参照。"Des intégrales doubles qui se présentent sous une form indéterminèe"。オーギュスタン・コーシーの全作品。シリーズ 1、巻数 1 / 科学アカデミーおよび科学教育の方向性を示す出版物...
{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ a bジャクソン 2008 .
- ^ミトロヴィッチ & ジュブリニッチ 1998、p. 62.
- ^クラハト & クライスツィヒ 1989、p. 553 .
- ^
- ^ディラック 1967、58-59ページ。
- ^ a bルディン 1966、§1.20。
- ^ヒューイット&ストロンバーグ 1963、§19.61。
- ^ Gelfand & Shilov 1966–1968、第 1 巻、§1.3。
- ^ Driggers 2003 , p. 2321異なる解釈については、 Bracewell 1986 , Chapter 5も参照のこと。ヘヴィサイド関数のゼロにおける値を割り当てる方法は他にも存在し、その中には以下で述べる内容と矛盾するものもある。
- ^ Hewitt & Stromberg 1963、§9.19。
- ^ビリングスリー 1986年、356ページ。
- ^ Hazewinkel 2011、41ページ 。
- ^スタイン & シャカルチ 2007、p. 285. sfn error: no target: CITEREFSteinShakarchi2007 (help)
- ^ストリチャートス 1994、§2.2。
- ^ヘルマンダー、1983 年、p. 35、定理2.1.5。
- ^シュワルツ 1950 .
- ^ Bracewell 1986、第5章。
- ^ Hörmander 1983、§3.1。
- ^ストリチャートス 1994、§2.3。
- ^ Hörmander 1983、§8.2。
- ^ディウドネ 1972、§17.3.3。
- ^クランツ, スティーブン・G.; パークス, ハロルド・R. (2008年12月15日).幾何積分理論. シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア. ISBN 978-0-8176-4679-0。
- ^フェデラー 1969、§2.5.19。
- ^
- ディラック 1967、60ページ
- Strichartz 1994、問題 2.6.2
- ^ウラジミロフ、1971 年、第 2 章、例 3(d)。
- ^ Weisstein, Eric W.「Sifting Property」。MathWorld 。
- ^ Karris , Steven T. (2003). MATLABアプリケーションによる信号とシステム. Orchard Publications. p. 15. ISBN 978-0-9709511-6-8。
- ^ローデン、マーティン・S. (2014-05-17).コミュニケーション理論入門. エルゼビア. p. [1] . ISBN 978-1-4831-4556-3。
- ^ロットウィット, カーステン; ティデマンド・リヒテンベルク, ピーター (2014年12月11日).非線形光学:原理と応用. CRC Press. p. [2] 276. ISBN 978-1-4665-6583-8。
- ^ゲルファントとシロフ 1966–1968、Vol. 1、§II.2.5。
- ^さらに改良して、沈み込み式にすることも可能ですが、これにはより複雑な変数変換式が必要になります。
- ^ Hörmander 1983、§6.1。
- ^ランゲ 2012、29~30頁。
- ^ゲルファントとシロフ 1966–1968、p. 212.
- ^ゲルファントとシロフ 1966–1968、p. 26.
- ^ Gelfand & Shilov 1966–1968、§2.1。
- ^ Weisstein, Eric W. 「Doublet Function」 . MathWorld .
- ^ブレイスウェル 2000、86ページ。
- ^ a b c Hörmander 1983、56ページ。
- ^ナミアス、ビクター(1977年7月)「ディラックのデルタ関数の電荷分布と多重極分布への応用」アメリカ物理学会誌45 ( 7):624-630。Bibcode:1977AmJPh..45..624N。doi :10.1119/1.10779。
- ^ Rudin 1991、定理6.25。
- ^ Stein & Weiss 1971、定理1.18。
- ^ルディン 1991、§II.6.31。
- ^より一般的には、積分可能な放射対称減少再配置を得るには、 η = η 1のみが必要である
- ^ Saichev & Woyczyński 1997、§1.1 物理学者とエンジニアから見た「デルタ関数」、p. 3。
- ^ミロヴァノヴィッチ、グラディミール・V.; ラシアス、マイケル・Th (2014年7月8日). 『解析的数論、近似理論、特殊関数:ハリ・M・スリヴァスタヴァに捧ぐ』シュプリンガー. p. 748. ISBN 978-1-4939-0258-3。
- ^スタイン & シャカルチ 2005、p. 111. sfn error: no target: CITEREFSteinShakarchi2005 (help)
- ^スタイン&ワイス 1971、§I.1。
- ^ Mader , Heidy M. (2006).火山学の統計. ロンドン地質学会. p. 81. ISBN 978-1-86239-208-3。
- ^ Vallée & Soares 2004、§7.2。
- ^ Hörmander 1983、§7.8。
- ^クーラント&ヒルベルト 1962、§14。
- ^ジョン 1955。
- ^ Gelfand & Shilov 1966–1968、I、§3.10。
- ^数値係数はフーリエ変換の規則に依存します。
- ^ブレイスウェル 1986 .
- ^ラング 1997、312ページ。
- ^ Lang (1997)の用語では、フェイエル核はディラック列であるが、ディリクレ核はそうではない。
- ^リードとサイモン 1980、Ch. II~III、VIII。
- ^ Adams & Fournier 2003、71ページ。
- ^ Hazewinkel 1995、357ページ 。
- ^朱 2007、Ch. 4.
- ^レビン 2002、109ページ。
- ^デイビス&トムソン 2000、343ページ。
- ^デイビス&トムソン 2000、344ページ。
- ^デ・ラ・マドリッド、ベーム&ガデラ、2002 年。
- ^ラウグヴィッツ 1989 .
- ^山下 2007 .
- ^ジェームズ2002、17ページ 。
- ^コルドバ 1988年。
- ^ Hörmander 1983、 §7.2。
- ^ウラジミロフ 1971、§5.7。
- ^ハートマン 1997、154–155ページ。
- ^ Kanwal, Ram P. (1997). 「15.1. 確率過程とランダム過程への応用」一般化関数理論と技法ボストン, マサチューセッツ州: Birkhäuser Boston. doi : 10.1007/978-1-4684-0035-9 . ISBN 978-1-4684-0037-3。
- ^ Karatzas & Shreve 1998、p. 204.
- ^イシャム 1995、§6.2。
- ^ゲルファントとシロフ 1966–1968、Vol. 4、§I.4.1。
- ^デ・ラ・マドリッド・モディーノ、2001 年、96、106 ページ。
- ^アルフケン&ウェーバー 2005、975–976ページ。
- ^ボイス、ディプリマ、ミード 2017、270–273頁。
参考文献
- アダムス、ロバート・A.; フルニエ、ジョン・JF (2003)、『ソボレフ空間』(第2版)、アカデミック・プレス、ISBN 978-0-12-044143-3。
- アーフケン、ジョージ・ブラウン、ウェーバー、ハンス=ユルゲン(2005年)『物理学者のための数学的手法』ボストン:アカデミック・プレス、ISBN 0-12-088584-0。
- アラティン、ヘンリック、ラシナリウ、コンスタンティン(2006年)、Mapleを使った数学手法の短期コース、World Scientific、ISBN 978-981-256-461-0。
- Arfken, GB ; Weber, HJ (2000) 『物理学者のための数学的手法』(第5版)、ボストン、マサチューセッツ州:Academic Press、ISBN 978-0-12-059825-0。
- ビリングスリー(1986)『確率と測度』(第2版)
- ボイス, ウィリアム E.; ディプリマ, リチャード C.; ミード, ダグラス B. (2017). 『初等微分方程式と境界値問題』 ホーボーケン, ニュージャージー: Wiley. ISBN 978-1-119-37792-4。
- Bracewell, RN (1986)、「フーリエ変換とその応用(第2版)」、McGraw-Hill、Bibcode : 1986ftia.book.....B。
- Bracewell, RN (2000)、『フーリエ変換とその応用(第3版)』、McGraw-Hill。
- コルドバ、A. (1988)、「La formule sommatoire de Poisson」、Comptes Rendus de l'Académie des Sciences、Série I、306 : 373–376。
- クーラント、リチャード;ヒルベルト、デイヴィッド(1962年)、数理物理学の方法、第2巻、ワイリー・インターサイエンス。
- デイビス、ハワード・テッド、トムソン、ケンドール・T(2000)、工学における線形代数と線形演算子、Mathematicaでの応用、アカデミック・プレス、ISBN 978-0-12-206349-7。
- デブナス、ロケナス。 Bhatta、Dambaru (2007)、Integral Transforms and Their Applications (2nd ed.)、CRC Press、ISBN 978-1-58488-575-7。
- ディウドネ、ジャン(1976)『分析論』第2巻、ニューヨーク:アカデミック・プレス[ハーコート・ブレイス・ジョバノビッチ出版社]、ISBN 978-0-12-215502-4、MR 0530406。
- ディウドネ、ジャン(1972)「分析論」第3巻、ボストン、マサチューセッツ州:アカデミック・プレス、MR 0350769。
- ディラック、ポール(1927年1月)「量子力学の物理的解釈」、ロンドン王立協会紀要。シリーズA、数学的および物理学的性質の論文を含む、113(765):621-641、Bibcode:1927RSPSA.113..621D、doi:10.1098/rspa.1927.0012、ISSN: 0950-1207、S2CID :122855515。
- ディラック、ポール(1967年)『量子力学の原理』(第4版、改訂版)、オックスフォード大学出版局、ISBN 0-19-852011-5
- ドリガース、ロナルド G. (2003)、「光工学百科事典」、CRC プレス、Bibcode : 2003eoe..book.....D、ISBN 978-0-8247-0940-2。
- Duistermaat, ハンス州; Kolk (2010)、分布: 理論と応用、Springer。
- ファーメロ、グラハム(2009年)『最も奇妙な男:ポール・ディラックの隠された人生、原子の神秘』ベーシックブックス、ISBN 978-0-465-02210-6。
- フェデラー、ヘルベルト(1969)、幾何測度理論、Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften、vol. 153、ニューヨーク: Springer-Verlag、pp. xiv+676、ISBN 978-3-540-60656-7、MR 0257325。
- フーリエ、ジョセフ(1822)、『熱の解析理論』(アレクサンダー・フリーマン英訳、1878年版)、大学出版局。
- ギャノン、テリー(2008)、「頂点作用素代数」、プリンストン数学コンパニオン、プリンストン大学出版、ISBN 978-1400830398。
- ゲルファンド, IM ; シロフ, GE (1966–1968) 『一般化関数』第 1巻~第5巻、アカデミック・プレス、ISBN 9781483262246。
- ハルペリン、イスラエル; シュワルツ、ローラン (1952). 『分布理論入門』 トロント [オンタリオ]: トロント大学出版局. ISBN 978-1-4875-9132-8。
{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help)。 - ハートマン、ウィリアム・M.(1997)、信号、音、感覚、シュプリンガー、ISBN 978-1-56396-283-7。
- Hazewinkel、Michiel (1995)、Encyclopedia of Mathematics (set)、Springer Science & Business Media、ISBN 978-1-55608-010-4。
- ヘヴィサイド、オリバー(1893)「物理数学における演算子について。第1部」、ロンドン王立協会紀要、52(315–320):504–529、doi:10.1098/rspl.1892.0093。
- ヘヴィサイド、オリバー(1894)「物理数学における演算子について。第2部」、ロンドン王立協会紀要、54(326–330):105–143、doi:10.1098/rspl.1893.0059。
- ヘイズウィンケル、ミシェル(2011)。数学の百科事典。 Vol. 10.スプリンガー。ISBN 978-90-481-4896-7. OCLC 751862625 .
- Hewitt, E ; Stromberg, K (1963),実解析と抽象解析, Springer-Verlag。
- Hörmander、L. (1983)、線形偏微分演算子 I の分析、Grundl。数学。 Wissenschaft.、vol. 256、スプリンガー、土井: 10.1007/978-3-642-96750-4、ISBN 978-3-540-12104-6、MR 0717035。
- Isham, CJ (1995), Lectures on Quantum Theory: Mathematical and Structural Foundations、Imperial College Press、Bibcode : 1995lqtm.book.....I、ISBN 978-81-7764-190-5。
- ジェームズ、JF(2002)、フーリエ変換の学生ガイド:物理学と工学への応用(第2版)、ケンブリッジ大学出版局。
- ジェフリー、アラン(1993)、線形代数と常微分方程式、CRCプレス、p.639
- ジャクソン、ジョン・デイビッド(2008年8月1日)「科学史における零定理の例」アメリカ物理学会誌、76(8):704–719、arXiv:0708.4249、Bibcode:2008AmJPh..76..704J、doi:10.1119/1.2904468、ISSN : 0002-9505、OSTI 929336。
- ジャマー、マックス(1966)「量子力学の概念的展開」マグロウヒル、ISBN 978-0-88318-617-6。
- ジョン、フリッツ(1955)、偏微分方程式に適用される平面波と球面平均、ニューヨーク-ロンドン:インターサイエンス出版社、MR 0075429再版、ドーバー出版、2004年、ISBN 9780486438047。
- 小松彦三郎 (2002)、「フーリエの超関数とヘヴィサイドの擬微分作用素」、河合貴弘、藤田恵子(編)、微局所解析と複素フーリエ解析、ワールドサイエンティフィック、ISBN 978-981-238-161-3。
- カラツァス、イオアニス。 Shreve、Steven E. (1998)、Brownian Motion and Stochastic Calculus、vol. 113、ニューヨーク、ニューヨーク州: Springer New York、土井: 10.1007/978-1-4612-0949-2、ISBN 978-0-387-97655-6。
- Kracht, Manfred; Kreyszig, Erwin (1989) 「特異積分作用素と一般化について」、Rassias, Themistocles M. (ed.)、Topics in Mathematical Analysis: A Volume Dedicated to the Memory of AL Cauchy、World Scientific、ISBN 978-9971-5-0666-7。
- ラング、セルジュ(1997)、学部生分析、学部生向け数学テキスト(第2版)、ベルリン、ニューヨーク:シュプリンガー・フェアラーク、doi:10.1007 / 978-1-4757-2698-5、ISBN 978-0-387-94841-6、MR 1476913。
- ランゲ、ルトガー・ヤン (2012)、「ポテンシャル理論、経路積分、および指示薬のラプラシアン」、Journal of High Energy Physics、2012 (11) 32: 29– 30、arXiv : 1302.0864、Bibcode : 2012JHEP...11..032L、doi : 10.1007/JHEP11(2012)032、S2CID 56188533。
- Laugwitz, D. (1989)、「無限和の定数値:1820年頃の無限小解析の基礎に関する諸側面」、Arch. Hist. Exact Sci.、39 (3): 195– 245、doi : 10.1007/BF00329867、S2CID 120890300。
- レビン、フランク・S.(2002)「座標空間波動関数と完全性」量子論入門、ケンブリッジ大学出版局、109頁以降、ISBN 978-0-521-59841-5
- Li, YT; Wong, R. (2008)、「ディラックのデルタ関数の積分表現と級数表現」、Commun. Pure Appl. Anal.、7 (2): 229– 247、arXiv : 1303.1943、doi : 10.3934/cpaa.2008.7.229、MR 2373214、S2CID 119319140。
- デ・ラ・マドリッド・モディノ、R. (2001).リグド・ヒルベルト空間言語における量子力学(博士論文). バリャドリッド大学.
- de la Madrid, R.; Bohm, A.; Gadella, M. (2002), 「連続スペクトルのリグドヒルベルト空間処理」, Fortschr. Phys. , 50 (2): 185– 216, arXiv : quant-ph/0109154 , Bibcode : 2002ForPh..50..185D , doi : 10.1002/1521-3978(200203)50:2<185::AID-PROP185>3.0.CO;2-S , S2CID 9407651。
- ミトロヴィッチ、ドラギシャ。ジュブリニッチ、ダルコ (1998)、応用関数解析の基礎: 分布、ソボレフ空間、CRC Press、ISBN 978-0-582-24694-2。
- McMahon, D. (2005)、「状態空間入門」(PDF)、量子力学の謎を解き明かす、自習ガイド、Demystifiedシリーズ、ニューヨーク:McGraw-Hill、p. 108、ISBN 978-0-07-145546-6、 2008年3月17日閲覧。
- Myint-U., Tyn; Debnath, Lokenath (2007)、「科学者とエンジニアのための線形偏微分方程式(第4版)」、Springer、ISBN 978-0-8176-4393-5
- Popescu, Sevar Angel; Jianu, Marilena (2023)、『エンジニアと物理学者のための上級数学』、Springer、ISBN 978-3-031-21502-5。
- リード、マイケル、サイモン、バリー(1980年)、現代数理物理学の方法、第1巻:関数解析、アカデミックプレス、ISBN 9780125850506
- ルディン、ウォルター(1966)、ディヴァイン、ピーター・R(編)、実解析と複素解析(第3版)、ニューヨーク:マグロウヒル(1987年出版)、ISBN 0-07-100276-6
- スミス、カルロス A.; キャンベル、スコット W.; トゥーミー、ライアン G. (2026)、『微分方程式、モデリング、シミュレーション入門』、CRC プレス: テイラー & フランシス グループ、ISBN 978-1-040-39977-4
- ルディン、ウォルター(1991年)、関数解析(第2版)、マグロウヒル、ISBN 978-0-07-054236-5。
- ヴァレー、オリヴィエ、ソアレス、マヌエル(2004年)、エアリー関数と物理学への応用、ロンドン:インペリアル・カレッジ・プレス、ISBN 9781911299486。
- Saichev, AI; Woyczyński, Wojbor Andrzej (1997)、「第1章 基本定義と演算」、物理科学と工学科学における分布:分布計算とフラクタル計算、積分変換、ウェーブレット、Birkhäuser、ISBN 978-0-8176-3924-2
- Schwartz, L. (1950)、Théorie des distributions、vol. 1、ヘルマン。
- Schwartz, L. (1951)、Théorie des distributions、vol. 2、ヘルマン。
- スニーダー、ロエル(2004年)、数学的手法のガイドツアー:物理科学のために、ケンブリッジ大学出版局
- スタイン、エリアス、ワイス、グイド(1971年)、ユークリッド空間におけるフーリエ解析入門、プリンストン大学出版局、ISBN 978-0-691-08078-9。
- Strichartz, R. (1994)、「分布理論とフーリエ変換ガイド」、CRC Press、ISBN 978-0-8493-8273-4。
- ファン・デル・ポル、バルト州; Bremmer, H. (1987)、Operational Calculus (第 3 版)、ニューヨーク: Chelsea Publishing Co.、ISBN 978-0-8284-0327-6、MR 0904873。
- ウラジミロフ、VS(1971)、数理物理学の方程式、マルセル・デッカー、ISBN 978-0-8247-1713-1。
- ワイスタイン、エリック W. 「デルタ関数」。MathWorld 。
- 山下 秀次 (2006)、「スカラー場の点単位解析:非標準的アプローチ」、Journal of Mathematical Physics、47 (9) 092301、Bibcode:2006JMP....47i2301Y、doi:10.1063/1.2339017
- 山下 秀之 (2007)、「スカラー場の点単位解析:非標準的なアプローチ」[J. Math. Phys. 47, 092301 (2006)]へのコメント」、Journal of Mathematical Physics、48 (8) 084101、Bibcode:2007JMP....48h4101Y、doi:10.1063/1.2771422
- Zhao, Ji-Cheng (2011),相図決定法、Elsevier、ISBN 978-0-08-054996-5
- ジー、アンソニー(2013)、アインシュタイン重力イン・ア・ナッツシェル、イン・ア・ナッツシェル・シリーズ(第1版)、プリンストン:プリンストン大学出版局、ISBN 978-0-691-14558-7。
- Zhu, Kehe (2007).関数空間における作用素理論. 数学概説とモノグラフ. 第138巻. アメリカ数学会.。
- ジル、デニス G.; ライト、ライト (2013)、『境界値問題を伴う微分方程式』(第 8 版)、Cengage Learning、ISBN 978-1-111-82706-9。
外部リンク
 ウィキメディア・コモンズにおけるディラック分布に関連するメディア
ウィキメディア・コモンズにおけるディラック分布に関連するメディア- 「デルタ関数」、数学百科事典、EMSプレス、2001 [1994]
- KhanAcademy.orgのビデオレッスン
- ディラックのデルタ関数、ディラックのデルタ関数に関するチュートリアル。
- ビデオ講義 – 講義 23 、アーサー・マタックによる講義。
- ディラックのデルタ測度は超関数である
- 我々は、ソース項がディラックデルタ測度である場合の唯一の解の存在を示し、有限要素近似を解析する。
- R. ルベーグ=スティルチェス測度、ディラックデルタ測度上の非ルベーグ測度。 2008年3月7日、 Wayback Machineにアーカイブ。
















![{\displaystyle {\begin{aligned}f(x)&={\frac {1}{2\pi }}\int _{-\infty }^{\infty }e^{ipx}\left(\int _{-\infty }^{\infty }e^{-ip\alpha }f(\alpha )\,d\alpha \right)\,dp\\[4pt]&={\frac {1}{2\pi }}\int _{-\infty }^{\infty }\left(\int _{-\infty }^{\infty }e^{ipx}e^{-ip\alpha }\,dp\right)f(\alpha )\,d\alpha =\int _{-\infty }^{\infty }\delta (x-\alpha )f(\alpha )\,d\alpha 、\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/656c821d528199232d832d301bbec290a815fe63)














![{\displaystyle \mathbb {1} _{(-\infty ,x]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/75912059b7b568e536b8fcd64859718aa39b9e06)
![{\displaystyle H(x)=\int _{\mathbf {R} }\mathbf {1} _{(-\infty ,x]}(t)\,\delta (dt)=\delta \!\left((-\infty ,x]\right),}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9a67b29a323434685200c36791fa963803be0c31)


![{\displaystyle \delta [\varphi ]=\varphi (0)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/df9006764a21dbc1593891d76b94e4a6c13cdd06)




![{\displaystyle \left|S[\varphi ]\right|\leq C_{N}\sum _{k=0}^{M_{N}}\sup _{x\in [-N,N]}\left|\varphi ^{(k)}(x)\right|}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a8921d57621545fc5640742ebe3f0a611bfd5998)




![{\displaystyle \delta [\varphi ]=-\int _{-\infty }^{\infty }\varphi '(x)\,H(x)\,dx.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5d867f4262298fa1f65e8b5ddc95df0f4d509f4a)





![{\displaystyle \delta _{x_{0}}[\varphi ]=\varphi (x_{0})}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9219b75c2a59f85c4a495187a42b9f997c7547a9)





















![{\displaystyle \delta \left(x^{2}-\alpha ^{2}\right)={\frac {1}{2|\alpha |}}{\Big [}\delta \left(x+\alpha \right)+\delta \left(x-\alpha \right){\Big ]}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d6570a1d3ae92889f1cb92ad03121ad1ef10acd1)







![{\displaystyle \delta_{S}[g]=\int_{S}g({\boldsymbol{s}})\,d\sigma({\boldsymbol{s}})}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8d0759b7b4d698e108b006b83385cb19a2048002)


![{\displaystyle \delta '[\varphi ]=-\delta [\varphi ']=-\varphi '(0).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6dcbd7eb8726c02cb50a897f5d3ae2fdc88ad3d0)

![{\displaystyle \delta ^{(k)}[\varphi ]=(-1)^{k}\varphi ^{(k)}(0).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/92b8ca88b17041c8f71580ab9779320dfddadb28)


![{\displaystyle (\tau _{h}S)[\varphi ]=S[\tau _{-h}\varphi ].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/da7641428f61e4c1de41526c105208eccffd83eb)



![{\displaystyle \delta _{a}[\varphi ]=\varphi (a)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ae820065c43b667f4247c78672dcd2f83fa79316)














![{\textstyle \left[-{\frac {1}{2}},{\frac {1}{2}}\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/19b64dd6fad3e022e8b3d9f606a2a42292c6181e)



![{\displaystyle {\begin{cases}{\dfrac {\partial }{\partial t}}\eta (t,x)=A\eta (t,x),\quad t>0\\[5pt]\displaystyle \lim _{t\to 0^{+}}\eta (t,x)=\delta (x)\end{cases}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2dcd8145e7871cf48f317c1c4d935ac7eb468604)







=|2\pi \xi |{\mathcal {F}}f(\xi ).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a9dba5209bfdb79796ee7978fbc154e029212b62)




![{\displaystyle L[u]=f,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/074535ba6bdba1d73b1f0bdb8cde6be6f06d1d6c)
![{\displaystyle L[u]=\delta .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6306e66d605d9cde6ddf5b7f85302c2aa915dcd7)
![{\displaystyle L[u]=h}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d0a532cf7d2fd63a65144c98a7bbf8456eceaf91)

![{\displaystyle g(s)=\operatorname {Re} \left[{\frac {-s^{k}\log(-is)}{k!(2\pi i)^{n}}}\right]={\begin{cases}{\frac {|s|^{k}}{4k!(2\pi i)^{n-1}}}&n{\text{奇数}}\\[5pt]-{\frac {|s|^{k}\log |s|}{k!(2\pi i)^{n}}}&n{\text{偶数}}\end{cases}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3fb36840bedf496b8822ad586804f91ae10fcba1)


![{\displaystyle {\begin{aligned}&c_{n}\Delta _{x}^{\frac {n+1}{2}}\iint _{S^{n-1}}\varphi (y)|(yx)\cdot \xi |\,d\omega _{\xi }\,dy\\[5pt]&\qquad =c_{n}\Delta _{x}^{(n+1)/2}\int _{S^{n-1}}\,d\omega _{\xi }\int _{-\infty }^{\infty }|p|R\varphi (\xi ,p+x\cdot \xi )\,dp\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d7bb9fbfb3720307465949837a5c76ae4a649295)










![{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }e^{i2\pi \xi _{1}t}\left[e^{i2\pi \xi _{2}t}\right]^{*}\,dt=\int _{-\infty }^{\infty }e^{-i2\pi (\xi _{2}-\xi _{1})t}\,dt=\delta (\xi _{2}-\xi _{1}).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8007cb6fa52a213211396ce15fa16d836540ab0c)











![{\displaystyle \delta [f]=|f(0)|<C\|f\|_{H^{1}}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4d546155e53e1d2a324b2639790b8845db523fca)

![{\displaystyle \delta _{z}[f]=f(z)={\frac {1}{2\pi i}}\oint _{\partial D}{\frac {f(\zeta )\,d\zeta }{\zeta -z}}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/35176ad52679bd943137c4ab9d002ad92a8c4dea)






![{\displaystyle \delta _{w}[f]=f(w)={\frac {1}{\pi }}\iint _{|z|<1}{\frac {f(z)\,dx\,dy}{(1-{\bar {z}}w)^{2}}}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4107a6750747d8aad60c24262e3c1bc56d9f9e4b)
























![{\displaystyle \ell (x,t)=\lim _{\varepsilon \to 0^{+}}{\frac {1}{2\varepsilon }}\int _{0}^{t}\mathbf {1} _{[x-\varepsilon ,x+\varepsilon ]}(B(s))\,ds}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5559ee5dae6a003812081e6f4785fe97c5c7ce3e)
![{\displaystyle \mathbf {1} _{[x-\バレプシロン ,x+\バレプシロン ]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5d2638b50ca5e6ffd77a1e6e4747b7b98c5b786f)
![{\displaystyle [x-\varepsilon ,x+\varepsilon ].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ee3e4409bd7fe914f16bb104c11de59e5ee1a225)











![{\displaystyle {\begin{aligned}q(x)&=\lim _{d\to 0}{\Big (}F\delta (x)-F\delta (xd){\Big )}\\[4pt]&=\lim _{d\to 0}\left({\frac {M}{d}}\delta (x)-{\frac {M}{d}}\delta (xd)\right)\\[4pt]&=M\lim _{d\to 0}{\frac {\delta (x)-\delta (xd)}{d}}\\[4pt]&=M\delta '(x).\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bd72d95be9328aeeea207fd8a970c1bdd5304b56)
