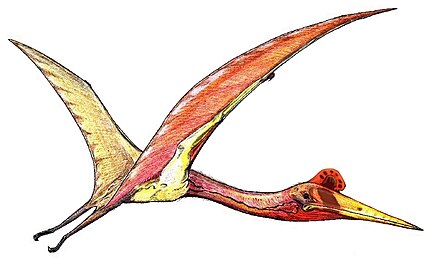翼竜
| 翼竜 | |
|---|---|
| 6 種の翼竜(左上から時計回り):プテラノドン、ディモルフォドン、プテロダクティルス、トゥパンダクティルス、アヌログナトゥス、ランフォリンクス | |
| 科学的分類 | |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 脊索動物 |
| クラス: | 爬虫類 |
| クレード: | アーキオサウルス類 |
| クレード: | アベメタタルサリア |
| クレード: | オルニトディラ |
| クレード: | †翼竜形類 |
| 注文: | †翼竜カウプ、1834/オーウェン、1842 |
| サブグループ[ 1 ] [ 2 ] | |
| |
 | |
| 翼竜の化石の分布。色分けされた種名または属名は、それぞれの分類群に対応しています。[ a ] | |
| 同義語 | |
オルニトサウルスシーリー、1870 | |
翼竜[ b ] [ c ]は、翼竜目に属する絶滅した飛行爬虫類の系統です。中生代の大部分、すなわち三畳紀後期から白亜紀末(2億2800万年前から6600万年前)に生息していました。[ 8 ]翼竜は、動力飛行を進化させたことが知られている最古の脊椎動物です。翼は、足首から劇的に長くなった第4指まで伸びる皮膚、筋肉、その他の組織からなる膜で形成されていました。 [ 9 ]
伝統的に、翼竜は2つの主要なタイプに分けられていました。基底翼竜(非プテロダクティロイド翼竜または「ランフォリンクス類」とも呼ばれる)は小型の動物で、翼開長は最大2メートル、歯が発達した顎と、典型的には長い尾を持っていました。幅の広い翼膜は、おそらく後肢を包んで繋いでいたのでしょう。地上では、中手骨が短いため不自然な寝た姿勢をとっていたと思われますが、関節の構造と強力な爪のおかげで木登りが得意で、中には木で生活していたものもいたかもしれません。基底翼竜は食虫動物、魚食動物、または小型陸生脊椎動物の捕食者でした。後の翼竜(プテロダクティロイド)は、様々なサイズ、形状、生活様式に進化しました。プテロダクティルス類は、自由な後肢を持つより狭い翼、大きく縮小した尾、大きな頭を持つ長い首を持っていた。地上では、長い中手骨のおかげで直立姿勢で四肢すべてでうまく歩行し、後肢で蹠行し、翼指を上に折り曲げて中手骨の上を歩き、手の3本の小さな指を後ろに向けた。彼らは地面から飛び立つことができ、化石の足跡は少なくともいくつかの種が走ったり、水の中を歩いたり、泳いだりできたことを示している。[ 10 ]彼らの顎には角質のくちばしがあり、いくつかのグループには歯がなかった。いくつかのグループは性的二形を伴う精巧な頭蓋骨を発達させた。2010年以降、多くの種、基底的なモノフェネストラタは中間的な体格で、高度な長い頭骨と長い尾を組み合わせたことが分かっている。
翼竜は、体と翼の一部を、毛のような繊維状の毛皮で覆っていました。毛皮繊維は、単純な繊維から枝分かれした羽毛まで、様々な形態をとっていました。これらは、鳥類恐竜と一部の非鳥類恐竜に見られる羽毛と相同性がある可能性があり、初期の羽毛は翼竜と恐竜の共通祖先において、おそらく断熱材として進化したことを示唆しています。[ 11 ]翼竜は温血動物(内温性)で活動的な動物でした。呼吸器系は、骨を極度に空洞化した気嚢を用いた効率的な一方向の「フロースルー」呼吸器系でした。翼竜は成体の大きさが幅広く、非常に小さなアヌログナトゥス科から、ケツァルコアトルスやハツェゴプテリクスといった既知の最大の飛行生物まで存在し、翼開長は少なくとも9メートルに達しました[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 。内温性、十分な酸素供給、そして強靭な筋肉の組み合わせにより、翼竜は力強く優れた飛行能力を有していました。
翼竜は、大衆メディアや一般大衆から「空飛ぶ恐竜」と呼ばれることが多いが、恐竜は竜盤類と鳥盤類の最後の共通祖先の子孫と定義されており、翼竜は含まれない。[ 15 ]翼竜は鳥類の祖先ではないものの、ワニや他の現生爬虫類よりも鳥類や他の恐竜に近い。翼竜は、特にフィクションやジャーナリズムでは、口語的にプテロダクティルスと呼ばれることもある。[ 16 ]しかし、厳密に言えば、プテロダクティルスはプテロダクティルス属、より広義には翼竜亜目プテロダクティロイド類を指すこともある。[ 17 ]
翼竜は多様な生活様式を持っていました。伝統的に魚食と考えられていましたが、現在では陸生動物を狩る動物、昆虫食、果実食、さらには他の翼竜を捕食する動物も含まれていたことが分かっています。彼らは卵によって繁殖し、その化石がいくつか発見されています。[ 18 ]
解剖学

翼竜の解剖学は、飛行への適応により爬虫類の祖先から大きく変化した。翼竜の骨は鳥類のように中空で空気で満たされていた。これにより、一定の骨格重量に対して、より大きな筋肉付着面が提供された。骨壁は紙のように薄いことが多かった。彼らは飛行筋を働かせるために大きく竜骨状の胸骨を持ち、複雑な飛行行動を調整できる巨大な脳を持っていた。 [ 19 ]翼竜の骨格には、しばしばかなりの癒合が見られる。頭骨では、要素間の縫合が消失した。後の翼竜の中には、肩の上の背骨がノタリウムと呼ばれる構造に癒合し、飛行中に胴体を強化し、肩甲骨を安定して支える役目を負ったものもあった。同様に、仙椎は単一の仙骨を形成することができ、骨盤骨も癒合した。
サイズ

翼竜は大きさが多種多様で、地球史上最大の飛行生物もいた。[ 20 ] [ 21 ]三畳紀とジュラ紀の初期の翼竜は典型的には小型の動物で、翼開長は最大2メートル(6.6フィート)であったが、白亜紀の翼竜のほとんどはより大型であった。[ 20 ] [ 22 ] [ 23 ]いくつかの孤立した標本はこの規則の例外を示しており、時代によるサイズの区分は不完全な化石記録の結果である可能性がある。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]アヌログナティッドは翼開長が0.4メートル(1.3フィート)と最も小さい翼竜だった可能性があるが、これらの個体の年代は不明である。[ 27 ] [ 28 ]最も大きな翼竜はハツェゴプテリクスやケツァルコアトルスなどのアズダルキダエ科のもので、翼開長は10~11メートル(33~36フィート)、体重は150~250キログラム(330~550ポンド)に達したと推定されています。[ 29 ] [ 30 ]
頭蓋骨

翼竜は、他の飛翔脊椎動物である鳥類やコウモリに比べて頭蓋骨が大きい。後の翼竜の頭蓋骨は非常に細長く、時には胴体全体よりも長かった。成体では多くの骨が癒合していた。[ 31 ]頭蓋骨には、骨性の鼻孔、眼窩、吻側の前眼窩窓、および各後側の2つの側頭窓など、複数の大きな穴が開いていた。モノフェネストラタン翼竜は、鼻と前眼窩窓が1つの大きな鼻眼窩窓に癒合していた。[ 32 ] [ 31 ]後頭部は最初は垂直方向であったが、進化の過程でいくつかのグループがほぼ水平に回転した。[ 33 ]一対の下顎は前部で癒合して、細長い下顎結合となった。初期の翼竜の下顎の後部には下顎窓があったが、後の種ではこれは失われた。[ 34 ]

吻部または頭蓋骨の後部には、しばしば上向きに突出した隆起部があり、その大きさは時に非常に大きいものもあった。下顎にも同様に下向きに突出した竜骨が見られることがあった。これらの隆起部は軟部組織によって大きさや形状が拡張された可能性がある。[ 35 ]隆起部の中には骨核を全く持たないものもあり、その存在は極めて保存状態の良い標本からのみ知られている。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
初期の翼竜は異歯類で、複数の種類の歯を持っていた。後期の翼竜は同歯類で、頭骨全体に単一の歯があり、多くの場合細長く円錐形だった。歯は生涯を通じて継続的に生え変わった。種によって歯列はかなり異なっていた。魚食性の動物は、顎の先端が拡張した部分に長い歯を持っていることが多かった。濾過摂食性の動物は、最大で1000本の歯を持つふるいを持っていた。後期の翼竜のグループの中には、完全に歯がなく、鳥類に似た角質の嘴を持つものもあった。[ 34 ] [ 32 ]ほとんどの種は嘴に角質化した組織を持っていたが、歯と同じ吻部には決してなかった。[ 37 ]
首と胴体

翼竜の脊柱は最大70個の椎骨を持っていた。後の翼竜は椎骨の側面に外棘突起と呼ばれる独特の構造を持ち、[ 39 ]また、凹状の前部には正中線の突起である下垂体突起があった。[ 40 ]翼竜の首は典型的には長く、深く、まっすぐで、プテロダクティルロイドでは胴体よりも長かった。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]首の椎骨の数は常に7個で、胴体の椎骨を2個含めると9個になる。[ 41 ]翼竜はすべての肋骨を失っている。[ 40 ]首は深く、筋肉が発達していた。[ 42 ] [ 43 ]

胴体は短くコンパクトで、最大7つの前後椎骨と肋骨が癒合してノタリウムと呼ばれる硬質構造を形成していた。[ 41 ] [ 44 ]
肩帯は強固で筋肉質であり、上部肩甲骨と下部烏口骨は後期種では単一の肩甲烏口骨に癒合した。この構造の上部はノタリウムに接合され、下部は胸骨に接合されて堅固な閉ループを形成し、羽ばたき飛行時の力に耐えやすくなっていた。[ 45 ] [ 46 ]肩関節は鞍型で、翼にかなりの可動性を与えていた。[ 46 ]肩関節は斜め横向きと上向きに伸びていた。[ 47 ]
胸骨は幅広く、浅い竜骨を有し、胸肋骨が背肋骨に付着していた。[ 48 ]その背後には、腹肋骨(gastralia)が腹部全体を覆っていた。[ 47 ]前方には、頸棘と呼ばれる長く尖った構造が斜め上方に突出していた。胸郭は胸骨の後部で最も深くなっていた。[ 49 ]鎖骨(鎖間)は存在しなかった。[ 47 ]
翼竜の骨盤は、体全体に比べて中程度の大きさでした。3つの骨盤骨は癒合していることがよくありました。[ 50 ]仙骨には最大10個の仙椎があり、仙骨と同様に棒でつながっていることもありました。[ 44 ]腸骨は長く低く、その前後の刃状部は下部の骨盤骨の縁を超えて水平に突出していました。この長さにもかかわらず、これらの突起が棒状であることから、これらに付着した後肢の筋肉の強度が限られていたことがわかります。[ 43 ]また、側面から見ると、狭い恥骨が幅広い坐骨と癒合して坐骨恥骨刃を形成していました。場合によっては、両側の刃状部も癒合し、骨盤を下から閉じて骨盤管を形成していました。股関節は穿孔されておらず、脚にかなりの可動性がありました。[ 51 ]斜め上方に向いているため、脚を完全に垂直にすることはできませんでした。[ 50 ]恥骨の前部は、一対の恥骨前骨という独特な構造で接合されていました。これらは骨盤と腹肋骨の間、後腹部を覆う尖頭を形成していました。この要素の垂直方向の可動性は、呼吸において胸腔の相対的な硬さを補う機能を示唆しています。[ 51 ]
翼
翼膜

主翼膜は非常に長い第4指に付着しており、おそらく足首まで伸びていた。後縁の形状は不明である。[ 52 ]膜は皮膚でできた革のようなひだではなく、能動的な飛行スタイルに適した非常に複雑な動的構造であった。[ 53 ]膜はアクチノフィブリルと呼ばれる密集した繊維によって強化されており、[ 54 ]翼には3つの異なる層があり、互いに交差したパターンで重なり合っていた。アクチノフィブリルは翼を硬化または強化する機能を持っていた。[ 55 ]また、薄い筋肉層、線維組織、そしてループ状の血管からなる独特で複雑な循環系が存在していた。[ 36 ]この組み合わせにより、動物は翼のたるみと反りを調整して揚力を制御できたのかもしれない。[ 53 ]

翼膜は3つの部分に分かれている。[ 56 ]前膜( propatagium、"fore membrane")は翼の最前部で、手首と肩の間に接続され、飛行中の"前縁"を形成する。腕膜( brachiopatagium、"arm membrane")は第4指から後肢まで伸びている。最後に、脚の間に伸びる膜は、おそらく尾を組み込んでおり、尾膜と呼ばれる。 [ 56 ]これは脚を繋いでいるだけだった可能性があり、cruropatagiumとなる。初期の翼竜は、おそらく長い第5趾の間に伸びるより幅広いuro/cruropatagium/cruropatagiumを持っていた。プテロダクティルス類にはそのような趾はなく、脚に沿って走る膜のみを持っていた。[ 57 ]ランフォリンクス類のソルデスの化石、[ 58 ]アヌログナトゥス類のジェホロプテルスの化石、[ 59 ]は、翼膜が後肢に付着していたことを示唆している。[ 60 ]しかし、翼竜の四肢の比率は、翼の平面にかなりのバリエーションがあったことを示している。[ 61 ]
翼の骨

腕の骨は翼を支え、伸ばしました。上腕骨は短いながらも力強い骨です。[ 62 ]上腕骨には大きな三角筋隆起があり、主要な飛翔筋が付着しています。[ 62 ]上腕骨は内部が中空または空気充填されており、骨の支柱によって補強されています。[ 49 ]下腕の長骨である尺骨と橈骨は、上腕骨よりもはるかに長いです。[ 63 ]翼竜特有の骨である翼状骨は、手首と肩の間の翼板を支えていました。[ 64 ]翼竜の手首は、2つの内側手根骨と4つの外側手根骨で構成されています。2つの内側手根骨と3つの外側手根骨は癒合して「合手骨」を形成します。ウィルキンソンによれば、残りの外側手根骨には深い凹状の窩があり、その中で翼状骨が関節を形成します。[ 65 ]
派生したプテロダクティロイド類では、第1中手骨から第3中手骨は小さく、手根骨に接せず、第4中手骨に接して垂れ下がっている。[ 51 ]この場合、第4中手骨は非常に長く、典型的には下腕長骨の長さと同等かそれ以上の長さになる。[ 50 ]第5中手骨は失われていた。[ 62 ]第1指から第3指は第4指(「翼指」)よりもはるかに小さく、それぞれ2、3、4つの指骨から構成されている。[ 51 ]小さな指には鉤爪がある。翼指は翼の全長の約半分以上を占める。[ 51 ]通常、翼指は4つの指骨から構成される。それぞれの相対的な長さは種によって異なり、近縁種を区別することができる。[ 51 ]第4指骨は通常最も短い。鉤爪がなく、ニクトサウルス類では完全に失われている。翼指は後方に湾曲しており、その結果、翼端は丸みを帯び、誘導抵抗が低減されます。翼指もまた、やや下向きに曲がっています。[ 50 ]翼竜は直立時、中手骨で支え、外側の翼は後方に折り畳まれていました。中手骨の「前側」は後方に回転し、これにより小さな指は斜め後方を向いていました。ベネットによれば、これは翼のどの要素よりも大きな弧(最大175°)を描くことができる翼指が、屈曲ではなく極度の伸展によって折り畳まれたことを示唆しています。肘を曲げると、翼は自動的に折り畳まれました。[ 43 ] [ 66 ]
後肢

翼竜の後肢は強靭な体格をしていたが、翼開長に比べると鳥類よりも小さく、胴体の長さに比べて長かった。[ 67 ]大腿骨は比較的まっすぐで、頭部は大腿骨の軸に対してわずかな角度しか作らなかった。[ 51 ]これは、脚が体の下に垂直に保持されておらず、やや広がった状態であったことを示唆している。[ 67 ]脛骨はしばしば足首の上部の骨と癒合して、大腿骨よりも長い脛足根骨を形成していた。[ 67 ]歩行時には垂直姿勢をとることができた。[ 67 ]ふくらはぎの骨は細くなる傾向があり、特に下端は進化した形態では足首に届かず、全長が3分の1になることもあった。典型的には、脛骨と癒合していた。[ 51 ]足首は単純な「中足根骨」の蝶番構造であった。[ 67 ]やや細長い[ 68 ]中足骨は常にある程度広がっていた。[ 69 ]足は底行性であり、歩行周期中に中足骨の裏が地面に押し付けられることを意味する。[ 68 ]
第一指から第四指は長かった。それぞれ2、3、4、5本の指骨があった。[ 67 ]第三指が最も長い場合が多く、第四指の場合もある。関節が平らなことから可動性が限られていたことがわかる。これらの指には鉤爪があったが、その鉤爪は手の鉤爪より小さかった。[ 69 ]第5指の形状に関して、初期の翼竜と進化した種との間には明らかな違いがあった。もともと、第5中足骨は頑丈で、あまり短縮していなかった。他の中足骨よりも高い位置で足首につながっていた。[ 68 ]第5中足骨には、2本の指骨からなる、長く、しばしば湾曲した、可動性のある鉤爪のない第5指があった。[ 69 ]これらの指は尾板(または足甲板)を支えていると考えられている。第5指は足の外側にあったため、このような配置は飛行中に指の前面を外側に回転させた場合にのみ可能であったこのような回転は大腿骨の外転によって引き起こされる可能性があり、脚が広がることを意味します。これにより、足は垂直な姿勢になります。[ 68 ]より進化した翼竜では、第5中足骨は大幅に縮小し、第5趾は(もし存在したとしても)ほとんど切断された状態でした。[ 70 ]
しっぽ
尾は脊柱の延長であるが細長く、後肢を動かす力はなかった。[ 43 ]初期の種は最大50個の椎骨からなる長い尾を持ち、細長い椎骨とV字形の突起で補強されていた。[ 48 ]これらは舵として機能し、後部で垂直の羽根となって終わっていた。[ 47 ]翼竜の尾は短く柔軟で、[ 47 ]椎骨は10個程度しかなかった。[ 44 ]
ピクノファイバー

すべての翼竜は頭部と胴体にピクノファイバーと呼ばれる毛のような繊維を持っていた。 [ 71 ]ピクノファイバーは哺乳類の毛に似た独特の構造で、収斂進化の例である。[ 58 ]翼竜の毛皮の密度は哺乳類のものと同等であった可能性がある。[ 71 ]皮膚の部分を見ると、手足の裏に小さな丸い重なり合わない鱗が見られるが、体の他の部分には見られなかった。[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]ピクノファイバーは翼竜が温血動物であり、熱の損失を防ぐ断熱材の役割を果たしていたことを示している。[ 71 ]
中国内モンゴル自治区で発見されたジュラ紀の小型翼竜の化石2体から、一部の翼竜がこれまで報告されていた均一な構造とは対照的に、多様な羽毛繊維の形状と構造をとっていたことが明らかになった。これらの中には、鳥類や他の恐竜で知られている特定の羽毛の種類と構造によく似た、ほつれた端部を持つものもあった。[ 75 ]トゥパンダクティルスの保存状態の良い化石には、現代の鳥類に見られるものと形状が似ており、他の翼竜でこれまで知られていたものよりも組織が複雑である色素細胞があることがわかった。この標本はステージIIIaの羽毛の存在も示唆しており、翼竜のより複雑な羽毛構造をさらに示唆している。鳥類の羽毛との共通祖先モデルを支持するため、著者らはこれらの構造を羽毛繊維ではなく翼竜の羽毛と名付けた。[ 76 ]この共通起源は以前にも示唆されていたが、依然として議論の的となっている。[ 38 ] [ 55 ] [ 71 ]
発見の歴史
最初の発見

翼竜の化石は骨の構造が軽いため、非常に稀少である。完全な骨格は通常、例外的な保存状態の地層、いわゆるラーガーシュテッテンでのみ発見される。そのようなラーガーシュテッテンの一つ、バイエルン州にある後期ジュラ紀のゾルンホーフェン石灰岩から採取された化石[ 77 ]は、裕福な収集家の間で非常に人気があった。[ 78 ] 1784年、イタリアの博物学者コジモ・アレッサンドロ・コリーニが翼竜の化石を記述した最初の科学者となった。[ 79 ]当時は進化と絶滅の概念が未発達だった。翼竜の奇妙な体格は、既存のどの動物グループにも明確に当てはめることができず、人々を驚かせた。[ 80 ]このように、翼竜の発見は現代の古生物学と地質学の進歩に重要な役割を果たすことになる。[ 81 ]当時の科学的見解では、もしそのような生物が生きているとしたら、信頼できる生息地は海だけだった。コリーニは、プテロダクティルスは長い前肢をパドルのように使って泳ぐ動物かもしれないと示唆した。 [ 82 ] 1830年、ドイツの動物学者ヨハン・ゲオルク・ヴァーグラーがプテロダクティルスは翼をヒレとして使い、魚竜類やプレシオサウルス類に属すると示唆するまで、少数の科学者は水生生物という解釈を支持し続けた。[ 83 ]

1800年、ヨハン・ヘルマンはジョルジュ・キュヴィエへの手紙の中で、これが飛翔生物を表していると初めて示唆した。キュヴィエは1801年、これが絶滅した飛翔爬虫類であると理解し、これに同意した。[ 84 ] 1809年、彼は「翼指」を意味するプテロダクティルス(Ptéro-Dactyle )という名称を考案した。 [ 85 ]これは1815年にラテン語化され、プテロダクティルス(Pterodactylus )となった。[ 86 ]当初はほとんどの種がこの属に分類され、最終的に「プテロダクティルス」は翼竜類全体に誤って適用された。[ 16 ]今日、古生物学者はこの用語をプテロダクティルス属、またはプテロダクティロイド上科の種に限定している。[ 17 ]
1812年と1817年、サミュエル・トーマス・フォン・ゾンメリングは、元の標本と追加の標本を再記載しました。[ 87 ]彼はそれらを鳥類やコウモリ類に属するものと見なしました。これは彼の誤りでしたが、彼の「コウモリモデル」は19世紀を通して影響力を持つことになります。[ 88 ] 1843年、エドワード・ニューマンは翼竜を飛行する有袋類と考えました。[ 89 ]皮肉なことに、「コウモリモデル」は翼竜を温血動物で毛皮を持つものとして描写していたため、最終的にはキュヴィエの「爬虫類モデル」よりもいくつかの点で正確であることが判明しました。1834年、ヨハン・ヤコブ・カウプは「プテロダクティルス」(プテロダクティルス)を含む「プテロサウルス亜目」を命名し、おそらく複数の属から構成されていると示唆しました。[ 90 ]カウプはしばしばプテロサウリア(Pterosauria)という名称の創始者として言及されている。実際にプテロサウリアという綴りを最初に使用したのは1841年か1842年のリチャード・オーウェンであり、彼はプテロダクティルス・キュヴィエリ(キモリオプテルス)、プテロダクティルス・ギガンテウス(ロンコドラコ)、プテロダクティルス・コンプレッシロストリス(ロンコデクテス)、プテロダクティルス・マイクロニクス(ディモルフォドン)をこの目に含めた。ブライアン・アンドレスとティモシー・マイヤーズは、オーウェンがプテロサウリアを「胸鰓肢の変形によって飛翔能力を獲得した爬虫類」と記述したことが、現代の類縁進化に基づく系統群の定義として有用であると指摘している。[ 91 ] [ 92 ]
研究の拡大

1828年、メアリー・アニングはイギリスでドイツ以外で最初の翼竜の属を発見し、[ 93 ]リチャード・オーウェンによりディモルフォドンと命名されたが、これはまた、知られた最初の非プテロダクティロイド翼竜でもあった。[ 94 ]世紀の後半には、前期白亜紀のケンブリッジグリーンサンドから何千もの翼竜の化石が産出されたが、それらは質が悪く、ほとんどが強く侵食された破片で構成されていた。[ 95 ]それでも、これらに基づいて、数多くの属と種が命名されることになる。[ 81 ]多くは、当時この分野のイギリスの主要な専門家であったハリー・ゴヴィア・シーリーによって記載され、彼はまた、最初の翼竜の本である『鳥類』[ 96 ]と、1901年に最初の一般向けの本である[ 81 ]『空のドラゴン』を執筆した。シーリーは、翼竜は温血で活動的な生き物であり、鳥類に近いと考えていた。[ 97 ]以前、進化論者のセント・ジョージ・ジャクソン・ミバートは、翼竜が鳥類の直接の祖先であると示唆していた。[ 98 ]オーウェンは両者の見解に反対し、翼竜は冷血の「真の」爬虫類であると見なした。[ 99 ]
アメリカ合衆国では、1870年にオスニエル・チャールズ・マーシュがニオブララ・チョーク層でプテラノドンを発見した。これは当時最大の翼竜であり、[ 99 ]歯のない最初の翼竜であり、アメリカ大陸で発見された最初の翼竜でもあった。[ 100 ]これらの地層からも数千の化石が発見され、[ 100 ]ゾルンホーフェンの標本のように強く圧縮されることなく、三次元的に保存された比較的完全な骨格も含まれていた。これにより、 [ 100 ]骨の中空構造など 、多くの解剖学的詳細についてより深い理解が得られた。

一方、ゾルンホーフェンからの発見は続き、発見された完全で高品質の標本の大半を占めました。[ 101 ]これにより、ランフォリンクス、スカフォグナトゥス、ドリグナトゥスなどのほとんどの新しい基底分類群を特定することができました。[ 101 ]この標本から、飛行爬虫類を温血で毛皮に覆われ活動的な中生代の現代のコウモリや鳥類に相当するものと見なしたドイツ翼竜研究の学派が生まれました。[ 102 ] 1882年、マーシュとカール・アルフレッド・ツィッテルは、ランフォリンクス の標本の翼膜に関する研究を発表しました。[ 103 ] [ 104 ]ドイツの研究は1930年代まで続き、アヌログナトゥスなどの新種が記載されました。 1927年、フェルディナンド・ブロイリは翼竜の皮膚に毛包を発見し[ 105 ]、古神経学者ティリー・エディンガーは翼竜の脳は現代の冷血爬虫類よりも鳥類の脳に似ていると判定しました[ 106 ] 。
対照的に、20世紀半ばまでに、イギリスとアメリカの古生物学者は翼竜への関心をほぼ失っていました。彼らは翼竜を進化の失敗例と見なし、冷血動物で鱗に覆われ、飛ぶことはほとんどできず、大型種は滑空しかできず、離陸するために木に登ったり崖から身を投げたりしなければならなかったと見なしていました。1914年、アーネスト・ハンバリー・ハンキンとデイヴィッド・メレディス・シアーズ・ワトソンによって、翼竜の空気力学が初めて定量的に分析されましたが、彼らはプテラノドンを純粋な滑空動物と解釈しました。[ 107 ] 1940年代と1950年代には、このグループに関する研究はほとんど行われませんでした。[ 81 ]
翼竜ルネッサンス

恐竜の状況も同様であった。1960年代以降、恐竜ルネサンスが起こり、デイノニクスの化石が新たに発見され、その驚くべき特徴がそれまで定着していた正統派の見解を覆したことで、研究や批判的な考えが急速に増加した。1970年には、同様に毛皮で覆われた翼竜ソルデスの記述により、ロバート・バッカーが翼竜ルネサンスと名付けた現象が始まった。 [ 108 ]特にケビン・パディアンはこの新しい見解を広め、翼竜を温血で活動的な走る動物として描いた一連の研究を発表した。[ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]これは、1970年代に現代の翼竜科学の基礎を築いたペーター・ヴェルンホファーの業績によるドイツ学派の復活と一致している。 [ 77 ] 1978年に彼は最初の翼竜の教科書[ 112 ] Handbuch der Paläoherptologie, Teil 19: Pterosauria、[ 113 ]を出版し、1991年には2冊目の科学的な翼竜の本[ 112 ] Encyclopedia of Pterosaursを出版した。[ 114 ]
この発展は、2つの新しいラーゲルシュテッテンの開発によって加速されました。[ 112 ] 1970年代、ブラジルの前期白亜紀サンタナ層でチョークノジュールが産出され始めました。これらのノジュールは、含まれる化石の大きさや完全性には限界があったものの、翼竜の骨格の立体的な部分が完璧に保存されていました。[ 112 ]ドイツとオランダの研究所は、このようなノジュールを化石密猟者から購入し、ヨーロッパで処理しました。これにより、自国の科学者は多くの新種を記載し、全く新しい動物相を明らかにすることができました。間もなく、アレクサンダー・ケルナーをはじめとするブラジルの研究者たちがこの取引を阻止し、さらに多くの種を命名しました。

さらに豊富な発見があったのは、遼寧省の前期白亜紀の熱河生物群で、1990年代以降、数百点もの非常に保存状態の良い二次元化石が発見され、その多くは軟組織の残骸も残っていました。呂俊昌をはじめとする中国の研究者たちは、再び多くの新分類群を命名しました。世界各地での発見も増加するにつれ、命名された属の総数は急増しました。2009年には約90属にまで増加し、この増加は鈍化する兆候を見せていません。[ 115 ] 2013年、MPウィットンは、発見された翼竜の種数が130種に達したと報告しました。[ 116 ]既知の分類群の90%以上は、「ルネサンス」期に命名されました。これらの多くは、存在が知られていなかったグループのものでした。[ 112 ]計算能力の進歩により、研究者は定量的な系統分類学の手法を用いて、それらの複雑な関係を明らかにすることができました。新旧の化石を現代の紫外線やレントゲン写真、CATスキャンにかけると、はるかに多くの情報が得られるようになった。[ 117 ]得られたデータには、他の生物学分野からの知見も応用された。[ 117 ]この結果、翼竜研究は大きく進歩し、一般向けの科学書に書かれた古い記述は完全に時代遅れのものとなった。
2017年、スコットランドのスカイ島で1億7000万年前の翼竜の化石が発見されました。この化石は後に2022年にDearc sgiathanachと命名されました。スコットランド国立博物館は、これはジュラ紀で発見された同種の化石としては最大であり、世界で最も保存状態の良い翼竜の骨格であると評されています。[ 118 ]
進化と絶滅
起源

翼竜の解剖学は飛行のために大きく改変されており、その直前の移行期の化石祖先がこれまで発見されていないため、翼竜の祖先は完全には解明されていない。[ 119 ]最古の翼竜はすでに飛行生活に完全に適応していた。シーリー以降、翼竜の起源は「主竜類」、つまり今日では主竜形質類と呼ばれる類に遡る可能性が高いことが認識されていた。1980年代の初期の分岐論的解析により、翼竜はアベメタタルサリア類(ワニ類よりも恐竜に近い主竜類)であることが判明した。これは翼竜が恐竜の近縁種でもあることを意味し、ケビン・パディアンはこの結果を、翼竜を二足歩行の温血動物とする自身の解釈を裏付けるものと捉えた。これらの初期の解析は限られた数の分類群と形質に基づいていたため、結果は本質的に不確実なものであった。[ 120 ]
パディアンの結論を否定した影響力のある研究者数名は、代わりの仮説を提示した。デイビッド・アンウィンは、基底的主竜形類、特にタニストロフェイド類のような首の長い形態(「プロトロサウルス」)に祖先がいるという説を提唱した。また、エウパルケリアのような基底的主竜形類の中に位置づけることも示唆された。[ 121 ]これらのような基底的主竜形類は、その長い四肢の解剖学的構造から、翼竜の近縁種として有力視されており、特にシャロヴィプテリクスは後肢に滑空に使用したと思われる皮膚膜を持っていた。[ 120 ]マイケル・ベントンによる1999年の研究では、翼竜がスクレロモクルスと近縁の獣脚類であることが再確認され、翼竜と恐竜を含むグループとしてオルニトディラと命名された。[ 122 ] 1996年、S・クリストファー・ベネットの研究者は、後肢の特徴を除いた分析結果から翼竜がプロトロサウルス類かそれに近縁であると結論付ける分析を発表し、翼竜と恐竜の移動に基づく収斂進化の可能性を検証した。[ 123 ] 2007年のデイブ・ホーンとマイケル・ベントンの反論ではこの結果を再現できず、後肢の特徴がなくても翼竜は恐竜に近縁であると結論付けた。彼らは、関係性を明確にするにはより基盤的な翼竜形態が必要であるものの、現在の証拠は翼竜がアベメタタタルサリア類であり、スクレロモクルスの姉妹群か、スクレロモクルスとラゴスクスの分岐のいずれかであると示唆していると結論付けた。[ 124 ]

2011年にスターリング・ネスビットが行った主竜類に焦点を当てた系統解析では、はるかに多くのデータから恩恵を受け、翼竜がアベメタタタール類であることを強く裏付ける結果が得られたが、スクレロモクルスは保存状態が悪いため含まれていなかった。[ 125 ] 2016年にマーティン・エズキュラが主竜形態に焦点を当てた研究では、様々な翼竜の近縁種が提案されたが、翼竜は恐竜に近く、より基盤的な分類群とは無関係であることも判明した。[ 126 ]ベネットは1996年の解析を基に、2020年にスクレロモクルスに関する研究を発表し、スクレロモクルスと翼竜はどちらも主竜類ではない主竜形態類であるが、互いに特に近縁ではないと主張した。[ 127 ]対照的に、2020年の後の研究では、ラゲルペティド主竜類が翼竜の姉妹系統であると提唱された。[ 128 ]これは、翼竜との様々な解剖学的類似性を示す新たに記載された頭蓋骨と前肢の化石と、翼竜との神経解剖学的類似性を示すCTスキャンに基づくラゲルペティドの脳と感覚系の再構築に基づいていた。[ 129 ] [ 130 ]後者の研究結果は、その後、初期の翼竜形類の相互関係に関する独立した分析によって裏付けられた。[ 131 ]
関連する問題は、翼竜の飛行の起源である。[ 132 ]鳥類と同様に、仮説は大きく分けて「地上飛行」と「樹上飛行」の2種類に分類できる。木登りは、高さと重力によって飛行開始に必要なエネルギーと強い淘汰圧の両方を生み出す。なぜなら、木登りをする動物は落下すると命を落とす可能性があるからだ。ルパート・ワイルドは1983年、仮説上の「プロプテロサウルス」を提唱した。これは、四肢の間に膜を発達させ、まず安全にパラシュートで降下し、その後、第4指を徐々に伸ばして滑空飛行を行う、トカゲのような樹上性動物である。[ 133 ]しかし、その後の分岐論的研究の結果はこのモデルにうまく適合しなかった。プロトロサウルス類もオルニトディラン類も、生物学的にはトカゲと同等ではない。さらに、滑空飛行と羽ばたき飛行の間の遷移は十分に解明されていない。基底的な翼竜の後肢の形態に関する最近の研究は、スクレロモクルスとの関連性を裏付けているように思われる。この主竜類のように、基底翼竜の系統は跳躍に適応した蹠行性の後肢を持っています。[ 134 ]
少なくとも1つの研究では、三畳紀初期の生痕化石プロロトダクティルスが解剖学的に初期の翼竜に類似していることが判明した。[ 128 ]
絶滅

かつては、初期の鳥類との競争が多くの翼竜の絶滅をもたらしたと考えられていました。 [ 135 ]白亜紀末までに、非常に大型の翼竜種のみが存在したと考えられていました。小型種は絶滅し、そのニッチは鳥類によって埋められたと推定されました。[ 136 ]しかし、翼竜の衰退は(実際に起こっているとしても)、2つのグループ間の生態学的重複が最小限であるため、鳥類の多様性とは無関係と思われます。[ 137 ]実際、白亜紀-古第三紀絶滅イベントの前に、少なくともいくつかの鳥類のニッチは翼竜によって奪還されました。[ 138 ]白亜紀末のこのK-Pg絶滅イベントは、すべての非鳥類型恐竜と他の多くの動物を一掃し、翼竜絶滅の直接的な原因であったと思われます。
小型翼竜種は明らかにチェバーニャ層に存在していたことが示されており、これまで考えられていたよりも後期白亜紀の翼竜の多様性が高かったことを示している。[ 139 ]近年発見されたネコ科の小型の成体アズダルコ科の化石は、幼少恐竜などの陸生小型脊椎動物に対する偏見が強いことから、後期白亜紀の小型翼竜は実際には化石記録にほとんど残っていなかっただけかもしれないこと、そしてその多様性はこれまで考えられていたよりもはるかに高かった可能性があることをさらに示唆している。[ 140 ]
2021年の研究では、かつて小型翼竜が占めていたニッチが、白亜紀後期には大型種の幼若期によって占められるようになったことが示されています。翼竜は鳥類との競争に敗れるのではなく、本質的に特殊化しており、これは中生代以前の時代にすでに起こっていた傾向です。[ 141 ]
分類と系統

系統分類学において、翼竜(プテロサウルス)は通常、ノードを基盤として定義され、広く研究されている複数の分類群と原始的と考えられる分類群に結び付けられてきました。2003年のある研究では、翼竜は「アヌログナトゥス科、プレオンダクティルス、ケツァルコアトルス、およびそれらのすべての子孫の最も最近の共通祖先」と定義されました。[ 142 ]しかし、このような定義では、やや原始的な近縁種が翼竜から除外されてしまうことになります。これを改善するために、特定の種ではなく、翼膜を支える拡大した第4指の存在という解剖学的特徴にその名称を結び付ける新しい定義が提案されました。[ 143 ]この親和形質に基づく定義は、 2020年にPhyloCodeによって「プテロダクティルス(元々はオルニトケファルス)アンティクウス(Sömmerring 1812)に受け継がれた、翼膜を支えるために肥大した第4指の親和形質を特徴とする系統群」として採用されました。[ 144 ]より広義の系統群であるプテロサウロモルファは、恐竜よりも翼竜に近いすべてのオルニトディラン類として定義されています。[ 145 ]
翼竜の内部分類は、化石記録に多くの空白があったため、歴史的に困難でした。21世紀以降、新たな発見によってこれらの空白が埋められ、翼竜の進化のより明確な全体像が明らかになりつつあります。伝統的に、翼竜は2つの亜目に分類されていました。長い尾を持つ「原始的」な翼竜であるランフォリンクイデア(Rhamphorhynchoidea )と、短い尾を持つ「進化的」な翼竜であるプテロダクティロイド(Pterodactyloidea )です。 [ 121 ]しかし、この伝統的な区分は大部分が放棄されています。ランフォリンクイデアは、プテロダクティロイド類が共通の祖先からではなく、ランフォリンクイデアから直接進化したため、側系統的(非自然的)なグループです。そのため、分岐論の使用が増えるにつれて、この分類は多くの科学者の間で支持されなくなりました。[ 116 ] [ 146 ]
翼竜には、いくつかのより小さな系統群が命名されている。ノビアロイデア系統群は、 2003年に古生物学者アレクサンダー・ヴィルヘルム・アーミン・ケルナーによって、カンピログナトイデスの最後の共通祖先であるケツァルコアトルスとそのすべての子孫からなるノードベースの分類群として命名された。この名称は、ラテン語の「新しい」を意味するnovusと「翼」を意味するalaに由来し、この系統群の個体が有する翼の共形質に由来している。 [ 147 ]
古生物学者デイビッド・アンウィンは2003年、ノビアロイド上科を掲載した雑誌(ロンドン地質学会、特別出版217)の同じ号でこのグループをロンコグナタと命名し、エウディモルフォドン・ランツィイ、ランフォリンクス・ミュンステリ、それらの最も最近の共通祖先、およびその全ての子孫(ノードベースの分類群として)と定義した。[ 148 ]アンウィンとケルナーの系統解析(エウディモルフォドンとカンピログナトイデスがランフォリンクスとケツァルコアトルスの両方の基底となるグループを形成する)によれば、ノビアロイド上科はロンコグナタと実質的に同一である。しかし、他の解析ではロンコグナタは別の概念(アンドレスら、 2010年)、[ 149 ]または翼竜と同義(アンドレス、2010年)であるとされている。[ 150 ]
翼竜間の正確な関係は未だ解明されていません。過去の翼竜の系統関係に関する研究の多くは、データが限られており、矛盾が顕著でした。しかし、より大規模なデータセットを用いた最近の研究では、状況が明らかになりつつあります。以下の系統樹(クラドグラム)は、2018年にLongrich、Martill、Andresが発表した系統解析に基づいており、系統名はAndres et al. (2014)に由来しています。 [ 1 ] [ 138 ]
アヌログナトゥス科(アヌログナトゥス、ジェホロプテルス、ヴェスペロプテリルス)の位置づけについては議論がある。[ 151 ]アヌログナトゥス科は高度に特殊化した小型の飛翔動物で、短い顎と広い口吻を有していた。中には夜行性または薄明薄暮性の習性を示唆する大きな眼、口毛、そしてしがみつくのに適した足を持つものもいた。同様の適応は、飛行中の昆虫を捕食する鳥類やコウモリにも見られる。
古生物学
フライト

翼竜の飛行の仕組みは現時点では完全には解明されておらず、モデル化もされていない。[ 152 ] [ 153 ]
日本の科学者佐藤勝文は、現代の鳥類を使って計算を行い、翼竜が空中に留まることは不可能であると結論付けました。[ 152 ]著書『翼竜の姿勢、移動、古生態学』では、後期白亜紀の酸素が豊富で濃い大気のおかげで翼竜は飛ぶことができたと理論づけられています。[ 154 ]しかし、佐藤も『翼竜の姿勢、移動、古生態学』の著者も、翼竜は海鳥に似ているという、今では時代遅れの理論に基づいて研究を行っており、そのサイズの制限はアズダルコ科やタペジャリド科のような陸生翼竜には当てはまりません。さらに、ダレン・ナイシュは、現在と中生代の間の大気の違いは、翼竜の巨大なサイズには必要なかったと結論付けました。[ 155 ]

理解が難しかったもう一つの問題は、彼らがどのように飛び立ったかである。初期の説では、翼竜は主に冷血の滑空動物で、カロリーを燃焼するのではなく、現代のトカゲのように周囲の熱を利用していたとされていた。この場合、非効率的な冷血代謝を持つ巨大で大型の動物が、後ろ足だけを使って推進力を生み出して空中に飛び上がるという鳥のような離陸戦略をどうやって管理できたのかは不明であった。その後の研究では、翼竜は温血動物で強力な飛翔筋を持ち、その飛翔筋を使って四足歩行していたことがわかっている。[ 156 ]ポーツマス大学のマーク・ウィットンとジョンズ・ホプキンス大学のマイク・ハビブは、翼竜が飛ぶために跳躍機構を使用したと示唆した。[ 157 ]翼の付いた前肢の途方もない力があれば、容易に離陸できたであろう。[ 156 ]翼竜は空中では時速120キロメートル(75マイル)の速度に達し、数千キロメートルを移動することができました。[ 157 ]
1985年、スミソニアン協会は航空技師ポール・マクレディにケツァルコアトルスの半分の実用模型の製作を依頼しました。この模型は地上設置型のウインチで打ち上げられました。1986年には数回飛行し、スミソニアン協会のIMAX映画『On the Wing』の一部として撮影されました。[ 158 ] [ 159 ]
頭の大きい種はバランスをとるために翼を前方に広げたと考えられている。 [ 160 ]
気嚢と呼吸
2009年の研究では、翼竜は肺と気嚢のシステムと精密に制御された骨格呼吸ポンプを持っていたことが示され、鳥類のそれに類似した翼竜の肺換気モデルを支えている。少なくとも一部のプテロダクティロイドに皮下の気嚢システムが存在していたことで、現生動物の密度がさらに低下したと考えられる。 [ 161 ]現代のワニ類と同様に、翼竜は肝臓ピストンを持っていたとみられる。これは、肩胸帯が鳥類のように胸骨を動かすには硬すぎたことと、強力な腹甲を持っていたことによる。[ 162 ]そのため、翼竜の呼吸器系は、現代の両方の主竜類系統に匹敵する特徴を持っていた。
神経系

翼竜の脳腔のX線研究により、これらの動物(ランフォリンクス・ミュンステリとアンハングエラ・サンタナエ)は巨大な小脳片を有していたことが明らかになりました。小脳片は、関節、筋肉、皮膚、平衡器官からの信号を統合する脳領域です。[ 19 ]翼竜の小脳片は、動物の脳全体の質量の7.5%を占めており、これは他のどの脊椎動物よりも大きい値です。鳥類は他の動物と比較して異常に大きな小脳片を有していますが、脳全体の質量の1~2%を占めるに過ぎません。[ 19 ]
片葉は神経信号を発し、眼筋に小さな自動運動を生じさせる。これにより、動物の網膜上の像が安定する。翼竜は翼が大きかったため、処理すべき感覚情報が非常に多かったと考えられるため、片葉が非常に大きかったと考えられる。[ 19 ]鳥類の片葉の相対質量が小さいのは、鳥類の脳全体がはるかに大きかったためでもある。これは、翼竜が鳥類に比べて構造的に単純な環境に生息していたか、行動がそれほど複雑ではなかったことを示していると考えられてきたが、[ 163 ]ワニ類やその他の爬虫類に関する最近の研究では、竜弓類は小さな脳で高い知能レベルを達成するのが一般的であることがわかっている。[ 164 ]アルカルエンのエンドキャストに関する研究では、プテロダクティロイドの脳の進化はモジュール型のプロセスであったことが示されている。 [ 165 ]
陸上移動

翼竜の股関節はわずかに上向きになっており、大腿骨頭はわずかに内側を向いている。これは、翼竜が直立姿勢をとっていたことを示唆している。滑空するトカゲのように、飛行中に大腿骨を水平に持ち上げることもできたと考えられる。
翼竜が四足歩行していたのか二足歩行していたのかについては、かなりの議論がありました。1980年代に古生物学者のケビン・パディアンは、ディモルフォドンのような後肢の長い小型翼竜は、ロードランナーのように飛ぶだけでなく、二足歩行や走行もしていた可能性があると示唆しました。[ 111 ]しかし、後に、特徴的な4本指の後足と3本指の前足を持つ翼竜の足跡が多数発見されました。これらは、翼竜が四足歩行していたことを示す紛れもない足跡です。[ 166 ] [ 167 ]

化石の足跡は、翼竜が人間やクマなどの多くの哺乳類と同様に、足全体を地面につけた状態で立っていたことを示している(蹠行性) 。アズダルコ科やいくつかの未確認種の足跡は、翼竜が四肢をほぼ垂直に体の真下に伸ばした直立姿勢で歩行していたことを示している。これは、現代の爬虫類のように四肢を広げるのではなく、ほとんどの現代の鳥類や哺乳類が採用しているエネルギー効率の高い姿勢である。[ 168 ] [ 156 ]実際、直立四肢は翼竜のどこにでも見られる可能性がある。[ 134 ]
伝統的に地上では不格好でぎこちない姿で描かれてきたが、一部の翼竜(特にプテロダクティロイド)の解剖学は、彼らが有能な歩行者および走行者であったことを示唆している。[ 169 ]初期の翼竜は、大きな肢体肢の存在のために特に扱いにくい運動動物であると長い間考えられてきたが、彼らも地上では概して効率的であったようである。[ 134 ]

アズダルコ科とオルニトケイリド科の前肢の骨は他の翼竜に比べて異常に長く、特にアズダルコ科では腕と手の骨(中手骨)が細長かった。さらに、アズダルコ科の前肢は全体として、速く走る有蹄類のプロポーションに似ていた。一方、後肢はスピードを重視して作られたわけではなかったが、ほとんどの翼竜と比較して長く、長い歩幅を可能にしていた。アズダルコ科の翼竜はおそらく走ることができなかっただろうが、比較的速く、エネルギー効率が高かったと考えられる。[ 168 ]
翼竜の手足の相対的な大きさは(鳥類などの現生動物との比較で)、翼竜が地上でどのような生活を送っていたかを示しているのかもしれない。アズダルコ科翼竜は、体の大きさや脚の長さに比べて足が比較的小さく、足の長さは下肢の長さの約25~30%に過ぎなかった。これは、アズダルコ科翼竜が乾燥した比較的固い地面を歩くことに適応していたことを示唆している。プテラノドンの足はわずかに大きく(脛骨の長さの47% )、クテノカスマトイド翼竜のような濾過摂食翼竜は非常に大きな足を持ち(プテロダクティルスでは脛骨の長さの69%、プテロダウストロでは84% )、現生の渉禽類と同様に、柔らかい泥土の中を歩くことに適応していた。[ 168 ]明らかに前肢を主肢とする発射体ではあるが、基底翼竜は跳躍に適した後肢を持っており、スクレロモクルスなどの主竜類との関連を示唆している。[ 134 ]
水泳
クテノカスマトイド類の足跡は、これらの翼竜が後肢を使って泳いでいたことを示している。一般的に、これらの翼竜は後足が大きく胴体が長いことから、他の翼竜よりも遊泳に適応していた可能性が高い。[ 170 ]逆に、プテラノドン類の上腕骨には、典型的な四足歩行の飛翔の水中バージョンを示唆すると解釈される種がいくつかあり、また、グンカンドリのような空中での鷹狩りはできないと思われるボレオプテリド類のように、遊泳しながら餌を探していたに違いないと考えられる。[ 170 ]これらの適応はアズダルコ科のような陸生翼竜にも見られ、おそらく水の中に落ちた場合に備えて、水から飛翔する必要があったと思われる。ニクトサウルス科のアルシオーネは、現代のカツオドリやネッタイチョウのように、翼で推進して潜水するための適応を示している可能性がある。[ 138 ]
食事と摂食習慣

伝統的に、ほぼすべての翼竜は表層で餌を食べる魚食動物、あるいは魚食動物と考えられており、この見解は今でも一般科学の主流となっています。今日では、多くの翼竜のグループは陸生の肉食動物、雑食動物、または昆虫食動物であったと考えられています。
小型のアヌログナ科は、夜行性の空中食虫動物であることが早くから認識されていました。翼指の関節が非常に柔軟で、翼は幅広く三角形をしており、大きな目と短い尾を持つこれらの翼竜は、比較的低速で高い機動性を発揮できたことから、ヨタカ類や現生の食虫コウモリに類似していたと考えられます。[ 171 ]

基底グループの習性に関する解釈は大きく変化した。 過去にはツノメドリの類似種と考えられていたディモルフォドンは、顎の構造、歩行、飛行能力の低さから、小型哺乳類、有鱗目動物、大型昆虫の陸生/半樹上性捕食者であったことが示されている。[ 172 ]カンピログナトイデスはその頑丈な歯列から小型脊椎動物のゼネラリストまたは陸生捕食者とみなされていたが、非常に頑丈な上腕骨と高アスペクト比の翼の形態から、翼で獲物を捕らえることができた可能性があることが示唆されている。[ 173 ]その後の研究では、腸管内からイカの発見に基づき、イカ食性であったことが示唆されている。 [ 174 ]小型の昆虫食動物であるカルニアダクティルスと、より大型のエウディモルフォドンは、高度に飛翔する動物で、長く頑丈な翼を持ち、素早く機敏に飛行していました。エウディモルフォドンは胃の中に魚の残骸が発見されていますが、その歯列は日和見食であったことを示唆しています。細長い翼を持つオーストリアダクティルスとカビラムスは、陸生または半樹上性の雑食動物であったと考えられます。カビラムスは強い咬合力を持っていたと思われ、歯の摩耗から、硬い食物を噛んでいた可能性が示唆されます。[ 175 ]

ランフォリンクス科の中には、ランフォリンクス自身やドリグナトゥスなど、細長い翼、針のような歯列、細長い顎を持つ魚食性の種もいた。一方、セリキプテルス、スカフォグナトゥス、ハルパクトグナトゥスはより頑丈な顎と歯(セリキプテルスでは短剣状のジフォドント)と、より短く幅広い翼を持っていた。これらは脊椎動物の陸生/空中捕食者[ 176 ]か、カラス科のような雑食性であった[ 177 ] 。ダーウィノプテルスのようなウコンゴプテルス科は、当初は空中捕食者と考えられていた。頑丈な顎構造や強力な飛翔筋を欠いているため、現在では樹上性または半陸生の食虫動物と見なされている。特に、ダーウィノプテルス・ロブスティデンスは甲虫類を専門としていたようである[ 178 ] 。
プテロダクティロイド類では、食性により多様性が見られる。プテラノドン亜科には、オルニトケイラ科、ボレオプテルス科、プテラノドン科、ニクトサウルス科など、多くの魚食性分類群が含まれていた。ニッチ分割により、オルニトケイラ類と後期のニクトサウルス科は、今日のグンカンドリ類(飛び込み型に適応したアルシオーネ・エライヌスを除く)のように空中でディップフィーダーとなった。一方、ボレオプテルス科はウミウ類に類似した淡水潜水動物であり、プテラノドン類はカツオドリやカツオドリ類に類似した外洋性の飛び込み型ダイバーであった。ロンコドラコの分析では、嘴の先端に有孔の塊が見られた。同様に多数の有孔を持つ鳥類は、餌を探すのに敏感な嘴を持っているため、ロンコドラコは浅瀬の魚や無脊椎動物を探すのに嘴を使っていた可能性がある。[ 179 ]イスティオダクティルス科は主に腐肉食だったと思われる。 [ 180 ]始祖鳥は沿岸または淡水域で餌を得ていた。ゲルマノダクティルスとプテロダクティルス科は魚食であり、クテノカスマ科は多数の微細な歯を使って浅瀬の小生物を濾過する懸濁物摂食者であった。プテロダウストロはフラミンゴのような濾過摂食に適応していた。 [ 181 ]

対照的に、アズダルコイデア科は主に陸生翼竜であった。タペジャリダエ科は樹上性の雑食性で、種子や果実を小型昆虫や脊椎動物で補っていたと考えられる。[ 170 ] [ 182 ]タペジャリダエ科のシノプテルス属の標本から、様々な植物由来の植物珪酸塩からなる腸内容物が発見され、翼竜が草食であったことを示す最初の証拠となった。[ 183 ] ズンガリプテルス科は軟体動物に特化した食性で、強力な顎を用いて軟体動物や甲殻類の殻を砕いていた。タラソドロミダエ科は陸生肉食性であった可能性が高い。タラソドロメウスという名前自体は、「スキムフィーディング」と呼ばれる漁法に由来するが、後に生体力学的に不可能であると理解された。強化された顎関節と比較的高い咬合力から判断すると、比較的大型の獲物を捕獲していた可能性がある。[ 184 ]アズダルキダエ科は現在では地上の捕食動物で、地上のサイチョウやコウノトリに類似しており、丸呑みできる獲物なら何でも食べていたと考えられています。[ 185 ]ハツェゴプテリクスは頑丈な体格の捕食動物で、中型恐竜を含む比較的大型の獲物を捕食していました。[ 186 ] [ 187 ]アランカは軟体動物に特化した動物だった可能性があります。[ 188 ]
2021年の研究では、プテロダクティロイドの頭蓋骨の内転筋を復元し、選ばれた9種の咬合力と潜在的な食性を推定した。[ 189 ]この研究は、プテラノドン科、ニクトサウルス科、アナヌエラ科が比較的弱いが素早く噛むことから魚食性であるという見解を裏付け、トロペオグナトゥス・メセンブリヌスはアナヌエラに比べて比較的大きな獲物を捕食することに特化していたことを示唆している。ドゥンガリプテルスはデュロファージであることが裏付けられ、タラソドロメウスも高い推定咬合力指数(BFQ)と絶対咬合力値に基づいてこの摂食習慣を共有していたと提案されている。[ 189 ] Tapejara wellnhoferiは、比較的高いBFQと高い機械的利点を持つ硬い植物質に特化した消費者であることが確認されており、Caupedactylus ybakaとTupuxuara leonardiiは、中程度の咬合力とそれほど特殊化していない顎を持つ地上摂食の汎用動物であると提案されている。[ 189 ]
天敵

翼竜は獣脚類に食べられていたことが知られている。2004年7月1日発行のネイチャー誌で、古生物学者エリック・ビュフェトーは、白亜紀前期の翼竜の頸椎3個の化石に、おそらくイリタトルと思われるスピノサウルスの折れた歯が埋め込まれていたと論じている。この椎骨は食べられて消化されたのではなく、関節がまだつながっていることがわかっている。[ 190 ]プテラノドンの化石にはスクアリコラックスなどのサメの歯型が付いて発見されており、[ 191 ]またトゥーレバック層で発見された歯型付きの化石は、魚竜(おそらくプラティプテリギウス)に襲われたか、あるいは腐食動物として食べられたと解釈されている。
生殖と生涯

翼竜の繁殖についてはほとんど分かっていないが、すべての恐竜と同様、すべての翼竜は産卵によって繁殖したと考えられているが、そのような発見は非常にまれである。最初に知られている翼竜の卵は、羽毛恐竜が産出されたのと同じ遼寧省の採石場と、ロマ・デル・プテロダウストロ(ラガルシト層、アルゼンチン)で発見されている。遼寧省の卵は平らに押しつぶされており、ひび割れの兆候が見られなかったため、現代のトカゲのように革のような殻を持っていたことは明らかである。[ 192 ]ラガルシト層で発見された卵はプテロダウストロ[ 193 ] [ 194 ]によって産まれたもので、豊富な化石で知られる翼竜である。[ 195 ]これは、2011年に記載されたDarwinopterus属に属する追加の翼竜の卵の記述によって裏付けられており、この卵も革のような殻を持ち、現代の爬虫類に似ているが鳥類とは異なり、母親のサイズと比較するとかなり小さかった。[ 196 ] 2014年には、 Hamipterus tianshanensis種の扁平でない卵5個が中国北西部の前期白亜紀の堆積物で発見された。走査型電子顕微鏡で殻を検査したところ、下に膜がある薄い石灰質の卵殻層の存在が示された。[ 197 ] 2007年に発表された翼竜の卵殻の構造と化学に関する研究は、翼竜が現代のワニやカメのように卵を埋めていた可能性が高いことを示した。卵を埋める方法は、重量を減らす適応を可能にするため、翼竜の初期の進化には有益であったと思われるが、この繁殖方法はまた、翼竜が生息できる環境の多様性を制限し、鳥類との生態学的競争に直面し始めたときに不利になった可能性がある。[ 198 ]
ダーウィノプテルスの標本は、少なくとも一部の翼竜が機能的な卵巣を1つしか持っていなかったことを示しており、鳥類の機能的な卵巣が1つしかないのとは対照的であり、動力飛行の要件として機能的な卵巣の縮小を否定している。[ 199 ]

翼竜の胚に保存されている翼膜はよく発達しており、翼竜は生後すぐに飛ぶ準備ができていたことを示唆している。[ 200 ]しかし、ハミプテルスの卵の化石の断層撮影スキャンは、若い翼竜は歩行のために大腿骨がよく発達していたが、飛行には胸骨が弱かったことを示唆している。[ 201 ]これが他の翼竜にも当てはまるかどうかは不明である。生後数日から1週間の翼竜の化石(「フラップリング」と呼ばれる)が発見されており、プテロダクティルス科、ランフォヒンクス科、クテノカスマ科、アズダルコ科など、いくつかの翼竜科を代表するものである。[ 121 ]保存されているすべての骨は、年齢の割に比較的高度に硬化(骨化)しており、翼の比率は成体と同様である。実際、過去には多くの翼竜の羽ばたきの幼体は成体とみなされ、別種に分類されてきました。さらに、羽ばたきの幼体は、ドイツのゾルンホーフェン石灰岩で発見されたプテロダクティルスとランフォリンクスの羽ばたきの幼体、アルゼンチンで発見されたプテロダウストロの羽ばたきの幼体のように、通常、同種の成体や幼体と同じ堆積物から発見されます。これらはすべて、海岸から遠く離れた深海環境で発見されています。[ 202 ]

翼竜の種の大多数については、何らかの形の親による育児を行っていたかどうかはわかっていないが、卵から出るとすぐに飛べる能力があることや、巣から遠く離れた環境で成鳥と一緒に多数の羽ばたきが見られることから、クリストファー・ベネットやデイビッド・アンウィンを含むほとんどの研究者は、幼鳥は飛べるほど長く翼が成長するまでの急速な成長期の比較的短い期間だけ親に依存し、その後おそらく孵化後数日以内に巣を離れて自力で生き延びたと結論付けている。[ 121 ] [ 203 ]あるいは、生後数日間は、現代の爬虫類と同様に、親に餌を頼るのではなく、貯蔵しておいた卵黄製品を栄養源としていた可能性がある。[ 202 ]ハミプテルスの巣の化石には、現代の海鳥のコロニーに似た方法で、多くのオスとメスの翼竜が卵と共に保存されていることがわかった。[ 197 ] [ 204 ]孵化したばかりの幼鳥の胸部が飛行するには未発達であったことから、ハミプテルスは何らかの形の親による世話をしていた可能性が示唆された。 [ 201 ]しかし、この研究はその後批判されている。[ 205 ]現在、ほとんどの証拠は、翼竜の孵化した幼鳥が超早成性であったことを示唆している。これは、孵化後すぐに親の世話を必要とせずに飛ぶメガポッド鳥類に似ている。さらなる研究では、超早成性と「後期飛行」の証拠を比較し、すべての翼竜ではないにしてもほとんどが孵化後すぐに飛行可能であったことを圧倒的に示唆している。[ 206 ]その後の研究では、成長過程における翼の縦横比の一定または減少から、小型翼竜は超早成または早成であった可能性が高いと示唆されたが、プテラノドンなどの大型翼竜の中には、孵化後、体に最も近い四肢の骨の成長速度が骨格の他のどの部分よりも速いことから、幼体が晩成であった可能性が示唆された。その他の要因としては、軟殻卵の限界と大型の雌翼竜の骨盤開口部の大きさが挙げられた。[ 207 ] [ 208 ]
翼竜の孵化後の成長率はグループによって異なっていた。ランフォリンクスなどの初期の長い尾を持つ翼竜(ランフォリンクス上科)では、生後1年目の平均成長率は130%から173%で、ワニの成長率よりもわずかに速かった。これらの種の成長は性成熟後に鈍化し、ランフォリンクスが最大サイズに達するまでには3年以上かかったとみられる[ 203 ] 。一方、プテラノドンなどの後期のプテロダクティルロイド翼竜は、生後1年以内に成体サイズに成長した。さらに、プテロダクティルロイドは決定的成長を示し、成体の最大サイズが一定に達すると成長を停止した[ 202 ]。
2021年の研究では、大型種の翼竜の幼体が、以前は成体の小型翼竜が担っていた役割を担うようになったことが示されています。[ 141 ]
日常の活動パターン
翼竜と現生の鳥類や爬虫類の強膜輪の比較は、翼竜の日常的な活動パターンを推測するために用いられてきた。プテロダクティルス、スカフォグナトゥス、トゥプクスアラといった翼竜属は昼行性、クテノカスマ、プテロダウストロ、ランフォリンクスは夜行性、タペジャラは短い間隔で日中活動するカテメラル性であると推測されている。その結果、おそらく魚食だったクテノカスマとランフォリンクスは現代の夜行性の海鳥と類似した活動パターンを持っていた可能性があり、濾過摂食のプテロダウストロは夜間に摂食する現代のカモ形の鳥類と類似した活動パターンを持っていた可能性がある。ゾルンホーフェンの翼竜であるクテノカスマ、ランフォリンクス、スカフォグナトゥス、プテロダクティルスの活動パターンの違いは、これらの属間のニッチ分割を示している可能性もある。 [ 209 ]
文化的意義

翼竜は、近縁種の恐竜と同じくらい長い間、大衆文化の定番となっていますが、映画、文学、その他の芸術作品において、それほど目立った描写は少ないのが現状です。古生物学の進歩に伴い、大衆メディアにおける恐竜の描写は劇的に変化してきましたが、20世紀半ば以降、主に時代遅れの翼竜のイメージが定着しています。[ 210 ]

これらの生物には、漠然とした総称である「プテロダクティルス」がしばしば用いられる。フィクションやポップカルチャーに描かれる動物は、プテラノドン、あるいは(非プテロダクティロイドである)ランフォリンクス、あるいは両者の架空の交雑種であることが多い。[ 210 ]多くの子供のおもちゃや漫画には、プテラノドンのような冠とランフォリンクスのような長い尾と歯を持つ「プテロダクティルス」が登場するが、自然界にはこのような組み合わせは存在しない。しかし、少なくとも1種の翼竜は、プテラノドンのような冠と歯の両方を持っていた。ルドダクティルスという種で、その名前は古くて不正確な子供のおもちゃに似ていることから「おもちゃの指」を意味する。[ 211 ]鳥類は獣脚類恐竜であり、翼竜の子孫ではないにもかかわらず、翼竜は鳥類(の祖先)と誤って特定されることがある。
翼竜は、アーサー・コナン・ドイルの1912年の小説『失われた世界』と、その1925年の映画化作品でフィクションとして使われました。その後も、1933年の映画『キングコング』や1966年の『百万年紀元前』など、数多くの映画やテレビ番組に登場しました。後者では、アニメーターのレイ・ハリーハウゼンは、膜が壊れないようにするために、ストップモーションモデルに不正確なコウモリのような翼の指を追加しなければなりませんでしたが、この特定のエラーは、映画が作られる前から美術では一般的でした。ラドンは、 1956年の映画『ラドン』で初めて登場した架空の巨大モンスター(または怪獣)で、プテラノドンの巨大な放射線を浴びた種として描かれています。[ 212 ] [ 213 ]ラドンは1960年代、1970年代、1990年代、2000年代に公開された複数の日本のゴジラ映画に登場しており、2019年のアメリカ製作映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』にも登場した。[ 213 ] [ 214 ] [ 215 ]

J・R・R・トールキンの『指輪物語』に登場する邪悪な獣は、しばしば「翼竜のような」ものとして理解されているが、トールキン自身はそれが実際の翼竜であることを否定している。
1960年代以降、翼竜は2001年の『ジュラシック・パーク3』まで、アメリカの著名な映画にはほとんど登場しませんでした。古生物学者のデイブ・ホーンは、この映画の翼竜は現代の研究を反映した大幅な更新がされていないと指摘しました。歯のないプテラノドンを描写するつもりだったのに歯が描かれていたこと、2001年までに不正確であることが判明した営巣行動、そして翼が翼竜の飛行に必要な緊張した筋繊維の膜ではなく革のような膜であったことなど、依然として誤りが残っていました。[ 210 ]アニメ映画『リトル・パンサー』(1988年)のペトリーは、その顕著な例です。[ 216 ]
翼竜はメディアに登場する多くの場合、魚食動物として描かれており、その食性の多様性を完全に反映していない。また、猛禽類に似た空中捕食者として描かれることも多く、足の爪で人間を捕らえる。しかし、掴むのに適した足と手を持つのは、小型のアヌログナトゥス科のヴェスペロプテリルスと小型のウコンゴプテリド科のクンペンゴプテルス[ 217 ]のみであることが知られている。他の既知の翼竜はすべて、対趾のない扁平な蹠行性の足を持ち、少なくともプテラノドン類では、足は一般的に体長に対して小さい。[ 16 ]
参照
説明ノート
参考文献
- ^ a b Andres, B.; Clark, J.; Xu, X. (2014). 「最古のプテロダクティロイドとそのグループの起源」 . Current Biology . 24 (9): 1011–16 . Bibcode : 2014CBio...24.1011A . doi : 10.1016/j.cub.2014.03.030 . PMID 24768054 .
- ^ Baron, Matthew G. (2020). 「avemetatarsalianの分類群と特徴のより広範なサンプリングと様々な系統解析手法による翼竜の集団内関係の検証」 . PeerJ . 8 e9604. doi : 10.7717/peerj.9604 . PMC 7512134. PMID 33005485 .
- ^ Mark P. Witton (2013)、「Pterosaurs: Natural History, Evolution, Anatomy」、Princeton University Press、Bibcode : 2013pnhe.book.....W、ISBN 978-0-691-15061-1
- ^ David M. Unwin (2010)、「ダーウィノプテルスと翼竜の系統発生への影響」、Acta Geoscientica Sinica、31 (1): 68– 69
- ^ジョーンズ、ダニエル(2003) [1917]、ピーター・ローチ、ジェームズ・ハートマン、ジェーン・セッター(編)、英語発音辞典、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-3-12-539683-8
- ^ 「翼竜」。Merriam -Webster.com辞書。Merriam-Webster。
- ^コルバート、エドウィン・H.(エドウィン・ハリス); ナイト、チャールズ・ロバート(1951年)『恐竜図鑑:支配的な爬虫類とその近縁種』ニューヨーク:マグロウヒル、153頁。
- ^ Barrett, PM; Butler, RJ; Edwards, NP; Milner, AR (2008). 「時間と空間における翼竜の分布:アトラス」(PDF) . Zitteliana . 28 : 61–107 . 2017年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2015年8月31日閲覧。
- ^ Elgin RA, Hone DW, Frey E (2011). 「翼竜の飛翔膜の範囲」 . Acta Palaeontologica Polonica . 56 (1): 99– 111. Bibcode : 2011AcPaP..56...99E . doi : 10.4202/app.2009.0145 .
- ^ “Pterosaur.net :: Terrestrial Locomotion” . pterosaur.net . 2009年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月1日閲覧。
- ^ Geggel, Laura (2018年12月17日). 「公式発表:翼竜と呼ばれる空飛ぶ爬虫類はふわふわの羽毛で覆われていた」livescience.com . 2020年2月1日閲覧。
- ^ Wang, X.; Kellner, AWA; Zhou, Z.; Campos, DA (2008). 「中国で発見された希少な樹上性森林生息性飛翔爬虫類(翼竜亜科、翼竜下科)について」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 105 (6 ) : 1983– 87. Bibcode : 2008PNAS..105.1983W . doi : 10.1073/pnas.0707728105 . PMC 2538868. PMID 18268340 .
- ^ Lawson DA (1975年3月). 「西テキサスの白亜紀後期の翼竜:最大の飛行生物の発見」. Science . 187 ( 4180): 947–948 . Bibcode : 1975Sci...187..947L . doi : 10.1126/science.187.4180.947 . PMID 17745279. S2CID 46396417 .
- ^ Buffetaut E, Grigorescu D, Csiki Z (2002年4月). 「ルーマニアの白亜紀後期に発見された、堅牢な頭蓋骨を持つ新たな巨大翼竜」 ( PDF) . Naturwissenschaften . 89 (4): 180–84 . Bibcode : 2002NW.....89..180B . doi : 10.1007/s00114-002-0307-1 . PMID 12061403. S2CID 15423666 .
- ^ベントン、マイケル・J. (2004). 「恐竜の起源と関係」. ワイシャンペル、デイビッド・B.、ドッドソン、ピーター・オスモルスカ、ハルシュカ編. 『恐竜』(第2版). バークレー:カリフォルニア大学出版局. pp. 7–19 . ISBN 978-0-520-24209-8。
- ^ a b c Naish, Darren. 「翼竜:神話と誤解」 . Pterosaur.net. 2009年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年6月18日閲覧。
- ^ a bアレクサンダー、デイビッド・E. & フォーゲル、スティーブン (2004). 『自然の飛翔者:鳥、昆虫、そして飛翔のバイオメカニクス』 JHU Press. p. 191. ISBN 978-0-8018-8059-9。
- ^セント・フルール、ニコラス(2017年11月30日)「中国で数百個の化石化した翼竜の卵が発見される」ニューヨーク・タイムズ。 2024年12月5日閲覧。
- ^ a b c d Witmer LM, Chatterjee S, Franzosa J, Rowe T (2003). 「飛翔性爬虫類の神経解剖学と飛翔、姿勢、行動への影響」 ( PDF) . Nature . 425 (6961): 950–53 . Bibcode : 2003Natur.425..950W . doi : 10.1038/nature02048 . PMID 14586467. S2CID 4431861 .
- ^ a b Hone, DWE; Benton, MJ (2007). 「翼竜におけるコープの法則、そして異なる分類レベルでのコープの法則に対する異なる認識」 . Journal of Evolutionary Biology . 20 (3): 1164– 1170. doi : 10.1111/j.1420-9101.2006.01284.x . PMID 17465925 .
- ^ Villalobos, Fabricio; Olalla-Tárraga, Miguel Á.; Vieira, Cleiber Marques; Mazzei, Nicholas Diniz; Bini, Luis Mauricio (2017). 「翼竜における体サイズ進化の空間的次元:ベルクマン則はコープ則を左右しない」『進化生態学研究』18 : 169–186 .
- ^ Benson, RBJ; Frigot, RA; Goswami, A.; Andres, B.; Bulter, RJ (2014). 「巨大飛翔爬虫類の進化におけるコープ則は競争と制約によって導かれた」 . Nature Communications . 5 (1): 3567. Bibcode : 2014NatCo...5.3567B . doi : 10.1038/ncomms4567 . PMC 3988819. PMID 24694584 .
- ^ Smith, RE; Chinsamy, A; Unwin, DM; Ibrahim, N; Zouhri, S; Martill, DM (2022). 「白亜紀アフリカの小型未成熟翼竜:飛翔性爬虫類における化石化バイアスと古生物群集構造への示唆」 .白亜紀研究. 130 105061. Bibcode : 2022CrRes.13005061S . doi : 10.1016/j.cretres.2021.105061 . S2CID 239257717 .
- ^ Etienne, JL; Smith, RE; Unwin, DM; Smyth, RSH; Martill, DM (2024). 「イギリスのジュラ紀に生息する『巨大な』プテロダクティロイド翼竜」地質学者協会紀要135 ( 3): 335– 348. Bibcode : 2024PrGA..135..335E . doi : 10.1016/j.pgeola.2024.05.002 .
- ^ Jagielska, N.; Challands, TJ; O'Sullivan, M.; Ross, DA; Fraser, NC; Wilkinson, M.; Brusatte, SL (2023). 「スコットランド、スカイ島のLealt Shale層から発見された新たな頭蓋骨後期の化石は、中期ジュラ紀の隠れた翼竜の多様性を示している」 . Scottish Journal of Geology . 59 ( 1– 2): 001. Bibcode : 2023ScJG...59....1J . doi : 10.1144/sjg2023-001 . hdl : 20.500.11820/8bc004a4-ab80-4f9f-965d-f211f18e9876 . S2CID 258232744。
- ^ Martin-Silverstone, Elizabeth; Witton, Mark P.; Arbour, Victoria M.; Currie, Philip J. (2016). 「白亜紀後期、空飛ぶ巨人の時代から発見された小型のアズダルコイド翼竜」 . Royal Society Open Science . 3 (8) 160333. Bibcode : 2016RSOS....360333M . doi : 10.1098/rsos.160333 . PMC 5108964. PMID 27853614 .
- ^ Hone, DWE (2020). 「アヌログナ科(爬虫綱、翼竜亜綱)の分類学と古生態学のレビュー」. Acta Geologica Sinica - 英語版. 94 (5): 1676– 1692. Bibcode : 2020AcGlS..94.1676H . doi : 10.1111/1755-6724.14585 .
- ^ウィットン 2013、107ページ。
- ^ Witton, MP; Habib, MB (2010). 「巨大翼竜のサイズと飛行の多様性、翼竜の類似体としての鳥類の利用、そして翼竜の飛べない状態に関する考察」 . PLOS ONE . 5 (11) e13982. Bibcode : 2010PLoSO...513982W . doi : 10.1371/journal.pone.0013982 . PMC 2981443. PMID 21085624 .
- ^ Andres, B.; Langston, W. Jr. (2021). 「ケツァルコアトルス・ローソン 1975(プテロダクティロイド上科:アズダルコイデア)の形態と分類」 . Journal of Vertebrate Paleontology . 41 (sup1): 46– 202. Bibcode : 2021JVPal..41S..46A . doi : 10.1080/02724634.2021.1907587 . ISSN 0272-4634 . S2CID 245125409 .
- ^ a bウィットン 2013、p. 23。
- ^ a bウェルンホファー 1991、47ページ。
- ^ウィットン 2013、26ページ。
- ^ a bウィットン 2013、p. 27。
- ^ウィットン 2013、24ページ。
- ^ a b Naish D, Martill DM (2003). 「翼竜 ― 先史時代の空への侵略の成功」生物学者50 ( 5): 213–16 .
- ^ a bフレイ E、マーティル DM (1998)。 「ドイツのジュラ紀後期のプテロダクティルス・コチ(ワグナー)標本における軟組織の保存」。 Neues Jahrbuch für Geology und Paläontologie、Abhandlungen。210 (3): 421–41 . Bibcode : 1998NJGPA.210..421F。土井:10.1127/njgpa/210/1998/421。
- ^ a b Czerkas, SA, Ji, Q. (2002). 頭冠と複雑な外皮構造を持つ新しいラムフォリンクス類. Czerkas, SJ (編).羽毛恐竜と飛行の起源. 恐竜博物館: ブランディング, ユタ州, 15–41. ISBN 1-932075-01-1。
- ^ S. Christopher Bennett (1994). 「後期白亜紀の翼竜プテラノドン(翼竜亜綱、翼竜類)の分類と系統学」 .カンザス大学自然史博物館臨時刊行物. 169 : 1– 70.
- ^ a bウィットン 2013、28ページ。
- ^ a b cウェルンホファー 1991、50ページ。
- ^ a bウィットン 2013、45ページ。
- ^ a b c d eウィットン 2013、46頁。
- ^ a b cウィットン 2013、30頁。
- ^ウィットン 2013、44ページ。
- ^ a bウィットン 2013、31ページ。
- ^ a b c d eウェルンホファー 1991、52ページ。
- ^ a bウェルンホファー 1991、51ページ。
- ^ a bウィットン 2013、32ページ。
- ^ a b c dウェルンホファー 1991、55ページ。
- ^ a b c d e f g hウィットン 2013、35ページ。
- ^ウィットン 2013、54ページ。
- ^ a bウィットン 2013、53ページ。
- ^ Bennett SC (2000). 「翼竜の飛行:翼機能におけるアクチノフィブリルの役割」. Historical Biology . 14 (4): 255–84 . Bibcode : 2000HBio...14..255B . doi : 10.1080/10292380009380572 . S2CID 85185457 .
- ^ a b Kellner, AWA; Wang, X.; Tischlinger, H.; Campos, D.; Hone, DWE; Meng, X. (2009). 「ジェホロプテルス(翼竜亜綱、アヌログナ科、バトラコグナチナ亜科)の軟部組織と翼膜の構造」 Proceedings of the Royal Society B . 277 (1679): 321–29 . doi : 10.1098/rspb.2009.0846 . PMC 2842671 . PMID 19656798 .
- ^ a bウィットン 2013、52ページ。
- ^ウィットン 2013、55ページ。
- ^ a b Unwin DM, Bakhurina NN (1994). 「Sordes pilosusと翼竜の飛行装置の性質」. Nature . 371 (6492): 62– 64. Bibcode : 1994Natur.371...62U . doi : 10.1038/371062a0 . S2CID 4314989 .
- ^ Wang X, Zhou Z, Zhang F, Xu X (2002). 「中国北東部、内モンゴルで発見された、ほぼ完全に関節化されたランフォリンクス類翼竜。非常に良好な保存状態にある翼膜と「毛」を持つ」. Chinese Science Bulletin . 47 (3): 3. Bibcode : 2002ChSBu..47..226W . doi : 10.1360/02tb9054 (2025年7月12日現在非アクティブ). S2CID 86641794 .
{{cite journal}}: CS1 maint: DOIは2025年7月時点で非アクティブです(リンク) - ^ Frey, E.; Tischlinger, H.; Buchy, M.-C.; Martill, DM (2003). 「軟部組織を持つ翼竜(爬虫類)の新標本:翼竜の解剖学と運動に関する示唆」.ロンドン地質学会特別出版. 217 (1): 233–66 . Bibcode : 2003GSLSP.217..233F . doi : 10.1144/GSL.SP.2003.217.01.14 . S2CID 130462931 .
- ^ Dyke GJ, Nudds RL, Rayner JM (2006年7月). 「翼竜の四肢の不均衡と翼の形状」 . J. Evol. Biol . 19 (4): 1339–42 . doi : 10.1111/ j.1420-9101.2006.01096.x . PMID 16780534. S2CID 30516133 .
- ^ a b cウェルンホファー 1991、53ページ。
- ^ウィットン 2013、33ページ。
- ^ウィットン 2013、34ページ。
- ^ Wilkinson MT; Unwin DM; Ellington CP (2006). 「翼竜の翼状骨と前翼の高揚力機能」. Proceedings of the Royal Society B. 273 ( 1582): 119–26 . doi : 10.1098/rspb.2005.3278 . PMC 1560000. PMID 16519243 .
- ^ウェルンホファー 1991、53~54頁。
- ^ a b c d e fウェルンホファー 1991、56ページ。
- ^ a b c dウェルンホファー 1991、57ページ。
- ^ a b cウィットン 2013、36ページ。
- ^ウィットン 2013、37ページ。
- ^ a b c dウィットン 2013、51頁。
- ^ウィットン 2013、47ページ。
- ^ウィットン 2013、48ページ。
- ^ Hone, D.; Lauer, R.; Lauer, B. (2025). 「翼竜の手足の軟部組織解剖学 ― ゾルンホーフェン地域のプテロダクティロイド標本からの新たな情報」 . Lethaia . 58 (3): 1– 12. Bibcode : 2025Letha..58..3.1H . doi : 10.18261/let.58.3.1 .
- ^ Yang, Zixiao; Jiang, Baoyu; McNamara, Maria E.; Kearns, Stuart L.; Pittman, Michael; Kaye, Thomas G.; Orr, Patrick J.; Xu, Xing; Benton, Michael J. (2019年1月). 「複雑な羽毛のような分岐を持つ翼竜の外皮構造」 . Nature Ecology & Evolution . 3 (1): 24– 30. doi : 10.1038/s41559-018-0728-7 . hdl : 1983/1f7893a1-924d-4cb3-a4bf- c4b1592356e9 . PMID 30568282. S2CID 56480710 .
- ^ Cincotta; et al. (2022). 「翼竜のメラノソームは初期の羽毛のシグナル伝達機能を支える」 . Nature . 604 (7907): 684– 688. Bibcode : 2022Natur.604..684C . doi : 10.1038/s41586-022-04622-3 . PMC 9046085. PMID 35444275 .
- ^ a bウィットン 2013、5ページ。
- ^ウェルンホファー 1991、22ページ。
- ^ウィットン 2013、6ページ。
- ^ウィットン 2013、6~7頁。
- ^ a b c dウィットン 2013、p.7。
- ^カリフォルニア州コッリーニ (1784)。 「Sur quelques Zoolithes du Cabinet d'Histoire Naturelle de SASE Palatine & de Bavière、à Mannheim」。 Acta Theodoro-Palatinae Mannheim 5 Pars Physica、58–103 ページ (1 枚のプレート)。
- ^ Wagler、J. (1830)。 Natürliches System der Amphibien Munich、1830: 1–354。
- ^キュヴィエ G (1801)。 「[爬虫類のボランティア]。In: Extrait d'un ouvrage sur les espèces de quadrupèdes dont on a trouvé les ossemens dans l'intérieur de la terre」。Journal de Physique、de Chimie et d'Histoire Naturelle。52 : 253-67 .
- ^ Cuvier, G.、1809、「Mémoire sur le squelette fossile d'un Reptil volant des environs d'Aichstedt, que quelques Naturalistes ont pris pour un oiseau, et donc nous formons un ジャンル de Sauriens, sous le nom de Ptero-Dactyle」、 Annales du Musée 『自然の歴史』、パリ、 13ページ、424–37
- ^ラフィネスク、CS、1815年、宇宙と軍団組織の自然分析、パレルモ
- ^ Von Soemmerring、ST、1812、「Über einen Ornithocepalus oder über das unbekannten Thier der Vorwelt, dessen Fossiles Gerippe Collini im 5. Bande der Actorum Academiae Theodoro-Palatinae nebst einer Abbildung in natürlicher Grosse im Jahre 1784 beschrieb, und welches Gerippe sich gegenwärtig in der Naturalien-Sammlung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München befindet"、 Denkschriften der königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften、ミュンヘン: 数学物理学クラス3 : 89–158
- ^ウェルンホファー 1991、27ページ。
- ^ニューマン、E (1843). 「有袋類コウモリと考えられるプテロダクティルス族に関する注記」.動物学者. 1 : 129–31 .
- ^カウプ、J. (1834)。「Ver such einer Einheilung der Säugethiere in 6 Stämme und der Amphibien in 6 Ordnungen」。イシス・フォン・オーケン。1834 : 311–315 .
- ^オーウェン、リチャード (1842). 「英国の化石爬虫類に関する報告書 第2部」英国科学振興協会報告書60–204 .
- ^アンドレス, ブライアン; マイヤーズ, ティモシー S. (2012年9月). 「ローンスター翼竜」 .エディンバラ王立協会地球環境科学論文集. 103 ( 3–4 ): 383– 398. doi : 10.1017/S1755691013000303 . ISSN 1755-6910 .
- ^ウェルンホファー 1991、28ページ。
- ^ウェルンホファー 1991、29ページ。
- ^ウェルンホファー 1991、33ページ。
- ^シーリー、HG、1870年、「オルニトサウルス類 - プテロダクティルスの骨の基礎研究」、ケンブリッジ大学出版局
- ^シーリー、HG、1901年、「空のドラゴン:絶滅した飛行爬虫類の記録」、ロンドン:メシューエン
- ^ Mivart, G (1881). 「カメレオンに関する一般的な説明」. Nature . 24 (615): 309–38 . Bibcode : 1881Natur..24..335. . doi : 10.1038/024335f0 . S2CID 30819954 .
- ^ a b Wellnhofer 1991、35ページ。
- ^ a b cウェルンホファー 1991、36ページ。
- ^ a b Wellnhofer 1991、31ページ。
- ^ウェルンホファー 1991、37~38頁。
- ^ Marsh, OC (1882). 「プテロダクティルスの羽」. American Journal of Science . 3 (16): 223.
- ^ツィッテル、KA (1882)。 「Über Flugsaurier aus dem lithografischen Schiefer Bayerns」。古地理学。29:47~ 80
- ^ Broili, F.、1927 年、「Ein Ramphorhynchus mit Spuren von Haarbedeckung」、 Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften p. 49-67
- ^エディンガー、T (1927)。「翼竜のゲヒルン」(PDF)。解剖学と知識の研究。83 (1/3): 105–12 .土井: 10.1007/bf02117933。S2CID 19084773。2020-07-28 のオリジナル(PDF)からアーカイブされました。2019年10月27日に取得。
- ^ハンキンEH & ワトソンDSM; 「プテロダクティルスの飛行について」航空ジャーナル、1914年10月、324–335ページ
- ^バッカー、ロバート、1986年、「恐竜異端」、ロンドン:ペンギンブックス、1988年、283ページ
- ^ Padian, K. (1979). 「翼竜の翼:新たな視点」. Discovery . 14 : 20–29 .
- ^ Padian, K., 1980,翼竜(爬虫類:翼竜亜科)の構造、進化、飛行に関する研究、イェール大学生物学部博士論文
- ^ a b Padian K (1983). 「翼竜の飛行と歩行の機能分析」.古生物学. 9 (3): 218–39 . Bibcode : 1983Pbio....9..218P . doi : 10.1017/S009483730000765X . JSTOR 2400656. S2CID 88434056 .
- ^ a b c d eウィットン 2013、9ページ。
- ^ Wellnhofer, P.、1978、 Handbuch der Paläoherpetologie XIX。翼竜、アーバン & フィッシャー、ミュンヘン
- ^ウェルンホファー 1991、pp.1-192。
- ^ Dyke, GJ McGowan; Nudds, RL; Smith, D. (2009). 「翼竜の進化の形状:化石記録からの証拠」 . Journal of Evolutionary Biology . 22 (4): 890–98 . doi : 10.1111/j.1420-9101.2008.01682.x . PMID 19210587. S2CID 32518380 .
- ^ a bウィットン 2013
- ^ a bウィットン 2013、p. 10。
- ^ "「スコットランドで『非常に保存状態の良い』翼竜の化石が発掘された」。AP通信。2022年2月22日。
- ^ウィットン 2013、13ページ。
- ^ a bウィットン 2013、14、17頁。
- ^ a b c dアンウィン、デイヴィッド・M. (2006). 『翼竜:深き時より』 ニューヨーク:パイ・プレス. p. 246. ISBN 978-0-13-146308-0。
- ^ Benton, MJ (1999). 「Scleromochlus tayloriと恐竜および翼竜の起源」 . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 354 (1388): 1423–46 . doi : 10.1098/rstb.1999.0489 . PMC 1692658 .
- ^ベネット、S. クリストファー (1996). 「主竜形類における翼竜の系統学的位置」 .リンネ協会動物学誌. 118 (3): 261– 308. doi : 10.1111/j.1096-3642.1996.tb01267.x .
- ^ Hone DWE; Benton MJ (2007). 「翼竜と主竜形類爬虫類の系統関係の評価」Journal of Systematic Palaeontology . 5 (4): 465–69 . doi : 10.1017/S1477201907002064 . S2CID 86145645 .
- ^ Nesbitt, SJ (2011). 「主竜類の初期進化:主要な系統群の関係と起源」 .アメリカ自然史博物館紀要. 352 : 1– 292. doi : 10.1206/352.1 . hdl : 2246/6112 . S2CID 83493714 .
- ^ Ezcurra, Martín D. (2016年4月28日). 「基底竜脚類の系統関係、特にプロテロスクス類竜脚類の系統分類学に着目して」 . PeerJ . 4 e1778. doi : 10.7717/peerj.1778 . PMC 4860341. PMID 27162705 .
- ^ Bennett, SC (2020). 「三畳紀の主竜類Scleromochlus tayloriの再評価:走者でも二足歩行者でもなく、跳躍者だった」 . PeerJ . 8 e8418. doi : 10.7717/peerj.8418 . PMC 7035874. PMID 32117608 .
- ^ a bエズクラ、マルティン D.;ネスビット、スターリング J.ブロンツァティ、マリオ。ダラ・ヴェッキア、ファビオ・マルコ。アグノリン、フェデリコ L.ベンソン、ロジャーBJ。ブリッソン・エグリ、フェデリコ。カブレイラ、セルジオ F.エバース、セルヨッシャ W.ジャンティ、アドリエル R.アーミス、ランダル B.マルティネリ、アグスティン G.ノバス、フェルナンド E.ロベルト・ダ・シルバ、ルシオ。スミス、ネイサン D.ストッカー、ミシェル R.ターナー、アラン H.マックス・C・ランガー(2020年12月17日)「謎の恐竜前駆体が翼竜の起源への橋渡しとなる」(PDF)。自然。588 (7838): 445– 449. Bibcode : 2020Natur.588..445E . doi : 10.1038/s41586-020-3011-4 . PMID 33299179 . S2CID 228077525 .
- ^ 「古生物学者、初期の進化史の空白を埋める翼竜の先駆体を発見」 phys.org . 2020年12月14日閲覧。
- ^ブラック、ライリー。「翼竜の起源が焦点に」サイエンティフィック・アメリカン。 2020年12月14日閲覧。
- ^バロン、マシュー・G. (2021年10月). 「翼竜の起源」.地球科学レビュー. 221 103777. Bibcode : 2021ESRv..22103777B . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103777 .
- ^ウィットン 2013、18ページ。
- ^ Rupert Wild、1983、「Über die Ursprung der Flugsaurier」、 Weltenberger Akademie、Erwin Rutte-Festschrift、pp. 231–38
- ^ a b c d Witton, Mark P. (2015). 「初期の翼竜は陸上移動が不得意だったのか?」 . PeerJ . 3 e1018 . doi : 10.7717/peerj.1018 . PMC 4476129. PMID 26157605 .
- ^ BBCドキュメンタリー:ウォーキング・ウィズ・ダイナソーズ(エピソード4) - ジャイアント・オブ・ザ・スカイズ22分、ティム・ヘインズ、1999年
- ^ Slack KE, Jones CM, Ando T, et al. (2006年6月). 「初期ペンギンの化石とミトコンドリアゲノムが鳥類の進化を検証する」 . Molecular Biology and Evolution . 23 (6): 1144–55 . doi : 10.1093/molbev/msj124 . PMID 16533822 .
- ^バトラー, リチャード J.; バレット, ポール M.; ナウバス, スティーブン & アップチャーチ, ポール (2009). 「サンプリングバイアスが翼竜の多様性パターンに与える影響の推定:鳥類/翼竜の競争的置換仮説への示唆」.古生物学. 35 (3): 432– 46. Bibcode : 2009Pbio...35..432B . doi : 10.1666/0094-8373-35.3.432 . S2CID 84324007 .
- ^ a b c Longrich, NR; Martill, DM; Andres, B. (2018). 「北アフリカ産後期マーストリヒチアン翼竜と白亜紀-古第三紀境界における翼竜類の大量絶滅」 . PLOS Biology . 16 (3) e2001663. doi : 10.1371/journal.pbio.2001663 . PMC 5849296. PMID 29534059 .
- ^ Prondvai, E.; Bodor, ER; Ösi, A. (2014). 「形態は骨組織学に基づく発生を反映するのか?ハンガリー産後期白亜紀の翼竜の顎結合の事例研究は、隠れた分類学的多様性を明らかにする」(PDF) . Paleobiology . 40 (2): 288– 321. Bibcode : 2014Pbio...40..288P . doi : 10.1666/13030 . hdl : 10831/75031 . S2CID 85673254 .
- ^ Martin-Silverstone, Elizabeth; Witton, Mark P.; Arbour, Victoria M.; Currie, Philip J. (2016). 「白亜紀後期、空飛ぶ巨人の時代から発見された小型のアズダルコイド翼竜」 . Royal Society Open Science . 3 (8) 160333. Bibcode : 2016RSOS....360333M . doi : 10.1098/rsos.160333 . PMC 5108964. PMID 27853614 .
- ^ a b Smith, Roy E.; Chinsamy, Anusuya; Unwin, David M.; Ibrahim, Nizar; Zouhri, Samir; Martill, David M. (2021年10月16日). 「白亜紀アフリカの小型未成熟翼竜:飛翔性爬虫類における化石化バイアスと古生物群集構造への示唆」 .白亜紀研究. 130 105061. Bibcode : 2022CrRes.13005061S . doi : 10.1016/j.cretres.2021.105061 . S2CID 239257717 .
- ^ Kellner, AW (2003). 「翼竜の系統発生と同グループの進化史に関する考察」.ロンドン地質学会特別出版. 217 (1): 105–37 . Bibcode : 2003GSLSP.217..105K . doi : 10.1144/gsl.sp.2003.217.01.10 . S2CID 128892642 .
- ^ Nesbitt, SJ, Desojo, JB, & Irmis, RB (2013).初期主竜類とその近縁種の解剖学、系統発生、古生物学. ロンドン地質学会. ISBN 1862393613
- ^ de Queiroz, K.; Cantino, PD; Gauthier, JA, 編 (2020). 『Phylonyms: A Companion to the PhyloCode』 CRC Press Boca Raton, FL. p. 2072. ISBN 978-0-429-82120-2。
- ^ Padian, K. (1997). 「翼竜類」, pp. 617–18, Currie, PJ and Padian, K. The Encyclopedia of Dinosaurs . Academic Press. ISBN 0122268105。
- ^ Lü J.; Unwin DM; Xu L.; Zhang X. (2008). 「中国下部白亜紀産の新たなアズダルコイド翼竜と翼竜の系統発生および進化への示唆」.自然科学誌. 95 (9): 891– 97. Bibcode : 2008NW.....95..891L . doi : 10.1007/s00114-008-0397-5 . PMID 18509616. S2CID 13458087 .
- ^ Kellner, AWA, (2003): 翼竜の系統発生と同グループの進化史に関する考察. pp. 105–137. — Buffetaut , E. & Mazin, J.-M. (編):翼竜の進化と古生物学. ロンドン地質学会特別出版217, ロンドン, 1-347
- ^アンウィン, DM, (2003): 翼竜の系統発生と進化史について. pp. 139–190. —ビュッフェトー, E. & マジン, J.-M. (編):翼竜の進化と古生物学. ロンドン地質学会特別出版217, ロンドン, 1-347
- ^ Brian Andres、James M. Clark、Xu Xing (2010) 中国新疆ウイグル自治区ジュラ紀後期から発見された新しいランフォリンクス科翼竜と基底翼竜の系統関係、Journal of Vertebrate Paleontology、30:1、163-187、DOI: 10.1080/02724630903409220
- ^アンドレス、ブライアン・ブレイク (2010).翼竜の系統分類学. イェール大学. p. 366.系統名なしで系統樹を表示するプレビュー
- ^ Andres, Brian; Clark, James M.; Xing, Xu (2010年1月29日). 「中国新疆ウイグル自治区ジュラ紀後期から発見された新種のランフォリンクス科翼竜と、基底翼竜の系統関係」(PDF) . Journal of Vertebrate Paleontology . 30 (1): 163– 187. Bibcode : 2010JVPal..30..163A . doi : 10.1080/02724630903409220 . S2CID 53688256 .
- ^ a b Alleyne, Richard (2008年10月1日). 「プテロダクティルスは飛ぶには重すぎた、と科学者は主張」 The Telegraph . 2009年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年3月2日閲覧。
- ^ Powell, Devin (2008年10月2日). 「翼竜は飛べないほど大きかったのか?」 . NewScientist . 2012年3月2日閲覧。
- ^ Templin, RJ; Chatterjee, Sankar (2004).翼竜の姿勢、移動、古生態. コロラド州ボルダー: アメリカ地質学会. p. 60. ISBN 978-0-8137-2376-1。
- ^ Naish, Darren (2009年2月18日). 「翼竜は鳥のように呼吸し、翼には膨張可能な気嚢を持っていた」 . ScienceBlogs . 2009年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年4月3日閲覧。
- ^ a b c「なぜ翼竜は結局それほど怖くなかったのか」『オブザーバー』紙、2013年8月11日。 2013年8月12日閲覧。
- ^ a bジェフ・ヘクト(2010年11月16日)「巨大翼竜は吸血コウモリのように高く跳躍したのか?」ニューサイエンティスト。 2012年3月2日閲覧。
- ^ MacCready, P. (1985). 「The Great Pterodactyl Project」(PDF) . Engineering & Science . 49 (2): 18– 24. 2020年7月28日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年11月23日閲覧。
- ^モロツキー、アーヴィン(1986年1月28日) 「翼を広げてプテロダクティルの模型が空を飛ぶ」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ 「翼竜の翼端:解剖学、航空機能、そして3つの生態学的影響」(PDF) . Qmro.qmul.ac.uk. 2022年6月25日閲覧。
- ^ Claessens LP, O'Connor PM, Unwin DM (2009). Sereno P (編). 「呼吸器の進化は翼竜の飛行と空中巨大化の起源を促進した」 . PLOS ONE . 4 (2) e4497. Bibcode : 2009PLoSO...4.4497C . doi : 10.1371/journal.pone.0004497 . PMC 2637988. PMID 19223979 .
- ^ Geist, N.; Hillenius, W.; Frey, E.; Jones, T.; Elgin, R. (2014). 「箱の中での呼吸:巨大翼竜の肺換気に関する制約」 . The Anatomical Record . 297 (12): 2233–53 . doi : 10.1002/ar.22839 . PMID 24357452. S2CID 27659270 .
- ^ Hopson JA (1977). 「アーキオサウルス類爬虫類の相対的な脳の大きさと行動」. Annual Review of Ecology and Systematics . 8 (1): 429–48 . Bibcode : 1977AnRES...8..429H . doi : 10.1146/annurev.es.08.110177.002241 .
- ^アンセス、エミリー(2013年11月18日)「冷血だからといって愚か者というわけではない」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ Codorniú, Laura; Paulina Carabajal, Ariana; Pol, Diego; Unwin, David; Rauhut, Oliver WM (2016). 「パタゴニア産のジュラ紀翼竜とプテロダクチロイド神経頭蓋の起源」 . PeerJ . 4 e2311. doi : 10.7717/peerj.2311 . PMC 5012331. PMID 27635315 .
- ^ Padian K (2003). 「翼竜の姿勢と歩行、そして足跡の解釈」(PDF) . Ichnos . 10 ( 2–4 ): 115–26 . Bibcode : 2003Ichno..10..115P . doi : 10.1080/10420940390255501 . S2CID 129113446 .
- ^ Hwang K, Huh M, Lockley MG, Unwin DM, Wright JL (2002). 「韓国南西部、後期白亜紀ウハンリ層から発見された新しい翼竜の足跡(プテライクニダエ科) 」地質学雑誌139 (4): 421–35 . Bibcode : 2002GeoM..139..421H . doi : 10.1017/S0016756802006647 . S2CID 54996027 .
- ^ a b c Witton MP, Naish D (2008). McClain CR (編). 「アズダルキド翼竜の機能形態学と古生態学の再評価」 . PLOS ONE . 3 (5) e2271. Bibcode : 2008PLoSO...3.2271W . doi : 10.1371/journal.pone.0002271 . PMC 2386974. PMID 18509539 .
- ^ Unwin DM (1997). 「翼竜の足跡と翼竜の陸上移動能力」(PDF) . Lethaia . 29 (4): 373–86 . doi : 10.1111/j.1502-3931.1996.tb01673.x .
- ^ a b cウィットン 2013、p. 51
- ^サウスカロライナ州ベネット (2007)。 「翼竜アヌログナトゥス・アンモニの 2 番目の標本」。古生物学時代。81 (4): 376–98。Bibcode : 2007PalZ...81..376B。土井:10.1007/bf02990250。S2CID 130685990。
- ^ウィットン 2013、103ページ。
- ^ウィットン 2013、121ページ。
- ^ Cooper, SLA; Smith, RE; Martill, DM (2024). 「ジュラ紀初期翼竜カンピログナトイデス・ストランド(1928年)とドリグナトゥス・ワグナー(1860年)の食性傾向、および翼竜類における鉄食のさらなる証拠」Journal of Vertebrate Paleontology. e2403577. doi:10.1080/02724634.2024.2403577.
- ^ウィットン 2013、122ページ。
- ^ Andres, B.; Clark, JM; Xing, X. (2010). 「中国新疆ウイグル自治区ジュラ紀後期から発見された新種のランフォリンクス科翼竜と、基底翼竜の系統関係」(PDF) . Journal of Vertebrate Paleontology . 30 (1): 163– 87. Bibcode : 2010JVPal..30..163A . doi : 10.1080/02724630903409220 . S2CID 53688256 .
- ^ウィットン 2013、134ページ。
- ^ Lü J.; Xu L.; Chang H.; Zhang X. (2011). 「中国北東部遼寧省西部の中期ジュラ紀から発見された新しいダルウィノプテリド翼竜とその生態学的示唆」. Acta Geologica Sinica - 英語版. 85 (3): 507–14 . Bibcode : 2011AcGlS..85..507L . doi : 10.1111/j.1755-6724.2011.00444.x . S2CID 128545851 .
- ^ Martill, David M.; Smith, Roy E.; Longrich, Nicholas; Brown, James (2021-01-01). 「翼竜における触覚採餌の証拠:イングランド南部の上部白亜紀に生息するLonchodraco giganteus(翼竜亜綱、ロンコデクチダエ科)のくちばしの敏感な先端」 . Cretaceous Research . 117 104637. Bibcode : 2021CrRes.11704637M . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104637 . ISSN 0195-6671 . S2CID 225130037 .
- ^ウィットン 2013、150~151頁。
- ^ウィットン 2013、199ページ。
- ^ Wu, Wen-Hao; Zhou, Chang-Fu; Andres, Brian (2017). 「白亜紀前期熱河生物群の歯のない翼竜Jidapterus edentus (翼竜下綱:アズダルコイデア)とその古生態学的示唆」 . PLOS ONE . 12 (9) e0185486. Bibcode : 2017PLoSO..1285486W . doi : 10.1371/ journal.pone.0185486 . PMC 5614613. PMID 28950013 .
- ^ Jiang, S.; Zhang, X.; Wu, Y.; Zheng, M.; Kellner, AWA; Wang, X. (2025). 「翼竜における植物珪酸体の最初の出現—草食性の証拠」. Science Bulletin . 70 (19): 3134– 3138. Bibcode : 2025SciBu..70.3134J . doi : 10.1016/j.scib.2025.06.040 . PMID 40683846 .
- ^ Pêgas, RV, & Kellner, AW (2015). Thalassodromeus sethi (Pterodactyloidea: Tapejaridae) の下顎筋の筋学的復元(予備的). Flugsaurier 2015 Portsmouth, abstracts, 47–48
- ^ Witton, MP; Naish, D. (2015). 「アズダルキド翼竜:水域を移動するペリカンの模倣者か、それとも「地上のストーカー」か?」 Acta Palaeontologica Polonica . 60 (3): 651. Bibcode : 2015AcPaP..60..651W . doi : 10.4202/app.00005.2013 .
- ^ Naish, D.; Witton, MP (2017). 「首のバイオメカニクスは、トランシルヴァニアの巨大なアズダルコ科翼竜が短い首を持つ弓状捕食者であったことを示している」 . PeerJ . 5 e2908. doi : 10.7717/peerj.2908 . PMC 5248582. PMID 28133577 .
- ^ Witton, M.; Brusatte, S.; Dyke, G.; Naish, D.; Norell, M.; Vremir, M. (2013).トランシルヴァニアの翼竜の覇者:後期白亜紀ルーマニアの短首巨大アズダルキド類. 脊椎動物古生物学・比較解剖学年次シンポジウム. エディンバラ. 2016年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Martill, David M.; Ibrahim, Nizar (2015年3月). 「モロッコのケムケム層から発見された白亜紀中期のアズダルコ科翼竜、cf. Alanqaの顎の異常な変化」 .白亜紀研究. 53 : 59– 67. Bibcode : 2015CrRes..53...59M . doi : 10.1016/j.cretres.2014.11.001 .
- ^ a b c Pêgas, Rodrigo V; Costa, Fabiana R; Kellner, Alexander WA (2021年9月24日). 「プテロダクチロイド(翼竜類)における内転筋腔の再構築と予測咬合力」.リンネ協会動物学誌. 193 (2): 602– 635. doi : 10.1093/zoolinnean/zlaa163 .
- ^ Buffetaut E, Martill D, Escuillié F (2004年7月). 「スピノサウルスの食生活における翼竜」 . Nature . 430 (6995): 33. Bibcode : 2004Natur.429...33B . doi : 10.1038/430033a . PMID 15229562. S2CID 4398855 .
- ^ 「化石が明らかにする、先史時代のサメは空飛ぶ爬虫類を好んで食べていた」サイエンス&イノベーション2018年10月3日。2018年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Ji Q, Ji SA, Cheng YN, et al. (2004年12月). 「古生物学:革のような殻を持つ翼竜の卵」(PDF) . Nature . 432 (7017): 572. Bibcode : 2004Natur.432..572J . doi : 10.1038/432572a . PMID 15577900. S2CID 4416203 .
- ^コドルニュ、L.;チアッペ、L.リヴァローラ、D. (2004)。「翼竜の胎児報告書(アルゼンチン、サンルイス、クレタシコ劣等地)」。アメギニアナ。41 (4 (補足、ラプラタ、2004 年 5 月 26 ~ 28 日の XX Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados からの要約)): 40R。
- ^ルイス・M・チアッペ;コドルニュ、ローラ。グレレット・ティナー、ジェラルド。デビッド・リヴァローラ(2004 年 12 月)。 「アルゼンチンの未孵化翼竜の化石」。自然。432 (7017): 571–572 .土井: 10.1038/432571a。hdl : 11336/156308。ISSN 1476-4687。PMID 15577899。
- ^ Codorniú, Laura; Chiappe, Luis M.; Cid, Fabricio D. (2013年5月). 「翼竜における胃石の初発見」. Journal of Vertebrate Paleontology . 33 (3): 647– 654. Bibcode : 2013JVPal..33..647C . doi : 10.1080/02724634.2013.731335 . hdl : 11336/4391 . ISSN 0272-4634 .
- ^ Lü J.; Unwin DM; Deeming DC; Jin X.; Liu Y.; Ji Q. (2011). 「翼竜における卵と成体の関連、性別、そして生殖」. Science . 331 (6015): 321–24 . Bibcode : 2011Sci...331..321L . doi : 10.1126/ science.11 97323. PMID 21252343. S2CID 206529739 .
- ^ a b王暁林 (2014). 「中国で発見された性的二形性を持つ三次元的に保存された翼竜とその卵」 . Current Biology . 24 (12): 1323–30 . Bibcode : 2014CBio...24.1323W . doi : 10.1016/j.cub.2014.04.054 . PMID 24909325 .
- ^ Grellet-Tinner G, Wroe S, Thompson MB, Ji Q (2007). 「翼竜の営巣行動に関するノート」. Historical Biology . 19 (4): 273–77 . Bibcode : 2007HBio...19..273G . doi : 10.1080/08912960701189800 . S2CID 85055204 .
- ^ Xiaolin Wang, Kellner Alexander WA; Cheng, Xin; Jiang, Shunxing; Wang, Qiang; Sayão Juliana, M.; Rordrigues Taissa, Costa Fabiana R.; Li, Ning; Meng, Xi; Zhou, Zhonghe (2015). 「卵殻と組織学は、2つの機能的な卵巣を持つ翼竜の生涯史に関する洞察を提供する」 . Anais da Academia Brasileira de Ciências . 87 (3): 1599– 1609. doi : 10.1590/0001-3765201520150364 . PMID 26153915 .
- ^ Wang X, Zhou Z (2004年6月). 「古生物学:白亜紀前期の翼竜の胚」 . Nature . 429 ( 6992): 621. Bibcode : 2004Natur.429..621W . doi : 10.1038/429621a . PMID 15190343. S2CID 4428545 .
- ^ a b「翼竜の孵化には親が必要だった、大量の卵が明らかに(更新)」phys.org . 2020年3月21日閲覧。
- ^ a b c Bennett SC (1995). 「ドイツのゾルンホーフェン石灰岩産ランフォリンクスの統計的研究:単一大型種の学年区分」Journal of Paleontology . 69 (3): 569–80 . Bibcode : 1995JPal...69..569B . doi : 10.1017 /S0022336000034946 . JSTOR 1306329. S2CID 88244184 .
- ^ a b Prondvai, E.; Stein, K.; Ősi, A.; Sander, MP (2012). Soares, Daphne (編). 「骨組織学から推定したランフォリンクスの生活史と翼竜の成長戦略の多様性」 . PLOS ONE . 7 (2) e31392. Bibcode : 2012PLoSO...731392P . doi : 10.1371/journal.pone.0031392 . PMC 3280310. PMID 22355361 .
- ^ 「親と一緒に見つかった初の3D翼竜の卵」phys.org . 2020年3月21日閲覧。
- ^アンウィン、デイビッド・マイケル;ディーミング、D・チャールズ(2019年)「翼竜の出生前発達と出生後の運動能力への影響」英国王立協会紀要B:生物科学. 286 (1904). doi : 10.1098/ rspb.2019.0409 . PMC 6571455. PMID 31185866 .
- ^ Naish, Darren; Witton, Mark P.; Martin-Silverstone, Elizabeth (2021). 「孵化したばかりの翼竜の動力飛行:翼の形状と骨の強度からの証拠」 . Scientific Reports . 11 (1): 13130. Bibcode : 2021NatSR..1113130N . doi : 10.1038/s41598-021-92499-z . PMC 8298463. PMID 34294737 .
- ^ Yang, Zixiao; Jiang, Baoyu; Benton, Michael J.; Xu, Xing; McNamara, Maria E.; Hone, David WE (2023-07-26). 「相対成長による翼の成長は親の育児と翼竜の巨大化を結びつける」 . Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 290 (2003) 20231102. doi : 10.1098 /rspb.2023.1102 . ISSN 0962-8452 . PMC 10354479. PMID 37464754 .
- ^ブリストル大学 (2023年7月19日). 「7月号:翼竜の親|ニュースと特集|ブリストル大学」www.bristol.ac.uk . 2023年8月22日閲覧。
- ^ Schmitz, L.; Motani, R. (2011). 「強膜輪と眼窩形態から推定される恐竜の夜行性」. Science . 332 ( 6030): 705–08 . Bibcode : 2011Sci...332..705S . doi : 10.1126/science.1200043 . PMID 21493820. S2CID 33253407 .
- ^ a b c Hone, D. (2010). 「大衆文化における翼竜」Wayback Machine Pterosaur.netに2021年5月2日アーカイブ、2010年8月27日アクセス。
- ^ Frey, E., Martill, D., Buchy, M. (2003). 「ブラジル北東部下部白亜紀産の新たな冠毛オルニトケイリッドと、特異な翼竜の異常な死」, Buffetaut, E., Mazin, J.-M. (編).『翼竜の進化と古生物学』 ,地質学会特別出版217 : 56–63. ISBN 1-86239-143-2。
- ^ベリー2005、452ページ。
- ^ a b Thomas, HN (2020). 「火より生まれたもの:ラドンの翼竜学的分析」 Journal of Geek Studies 7 : 53–59.
- ^ゴンザレス、デイブ(2016年10月12日)「モンスター級の『ゴジラ』映画の狂気」Thrillist.com . 2019年7月11日閲覧。
- ^シャーフ、ザック(2018年12月10日)。『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』予告編、モスラ、ラドンなどが登場し壮大なスペクタクルに』(動画)。IndieWire。2019年7月11日閲覧。
- ^マンスール、デイヴィッド(2005年)『アバからズームまで 20世紀後半のポップカルチャー百科事典』アンドリュース・マクミール出版、272頁。
- ^ Zhou, X.; Pêgas, RV; Ma, W.; Han, G.; Jin, X.; Leal, MEC; Bonde, N.; Kobayashi, Y.; Lautenschlager, S.; Wei, X.; Shen, C.; Ji, S. (2021). 「新たなダーウィン翅目翼竜が樹上生活と反対の親指を明らかにする」 Current Biology . 31 (11): 2429–2436.e7. Bibcode : 2021CBio...31E2429Z . doi : 10.1016/j.cub.2021.03.030 . PMID 33848460 .
出典
- ベリー、マーク・F. (2005). 『恐竜のフィルモグラフィー』 . マクファーランド・アンド・カンパニー. ISBN 978-0-7864-2453-5。
- ヴェルンホファー、ピーター(1991年)『翼竜図鑑:中生代飛翔爬虫類の図解自然史』クレセントブックス、ISBN 978-0-517-03701-0。
- マーク・ウィットン(2013年)『翼竜:自然史、進化、解剖学』プリンストン大学出版局、ISBN 978-0-691-15061-1。
外部リンク
- Pterosaur.net 2021年5月2日アーカイブWayback Machine、翼竜科学のあらゆる側面に関する複数の著者によるウェブサイト
- 翼竜データベース、ポール・パースグローブ著
- 「翼竜綱の系統発生に関するコメント」アレクサンダー・WA・ケルナー著(技術解説)